![]()
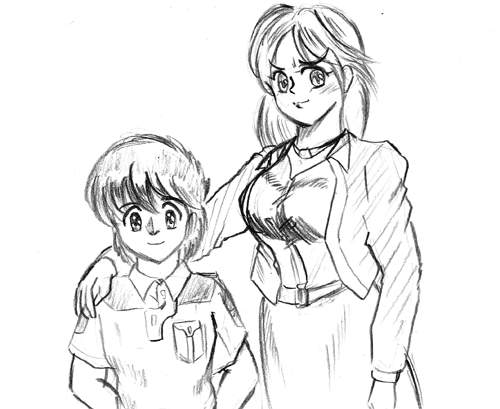
小学校6年生の崇は幼い頃生母を亡くしていた。まもなく父は再婚し、崇には美しい継母ができた。鞭打ち愛好者の継母は美少年の崇を気にいってはいたが、その可愛がり方は「厳しいしつけ」に名を借りたお仕置きの形で表現された。崇の方も厳しい継母を恐れつつも憧れを感じていくのであった。
そのころ崇には私立中学受験のために家庭教師がつけられていた。しかし、最近の崇は勉強に実が入らなかった。実は同じクラスの桐生文と言う女の子に恋をして勉強中もその子のことを考えていることが多かったのである。家庭教師に勉強を見てもらっている間も時々気持ちがあさってのほうにいってはなはだ能率が悪かったのである。
「崇君、最近どうしたの?勉強に身が入らないようだねまたお母さんに言い付けてお尻を叩いてもらおうか?」
と、家庭教師に脅かされると崇はあわてて謝り、真剣に
「お母さんにはだまってて、」
と頼むのであった。
しかし、崇のスランプは長引き、やがてその事は家庭教師から継母に伝えられた。
ある日学校から帰ってくると崇は継母の部屋に呼ぱれた。継母は厳しい表情でべッドに腰掛けていた。
「崇、そこに立ちなさい、なんで呼ばれたかわかっているの?.!
崇はいよいよきたかと思った、自分でも最近の勉強ぷりはひどいと思っていたしそろそろその事が継母にばれる頃だと覚悟していたのである。
「はっ、はい。最近あんまり勉強に身が入っていないので・・・・」
「その通りだよ。昨日家庭教師の先生からお聞きしたんだよ。勉強中何かほかのことを考えているんだってね,一体どんなことを考えて入るんだい?」
「実はクラスにすきなこができちゃって………」
「なんだって?女の子のことを考えているだって?おまえ今阿才なの?」
「はい、12才です.」
「12才だったら他にすることがあるでしょう。女の子のことを考えていて勉強がてにつかないなんてとんでもないわね。さあ久し振りに痛い思いをして勉強に身が入るようにしてあげようね。」
継母は立ち上がって壁に掛けてあった皮製の房鞭を手にとり鋭く一振りした、ヒュッという恐ろしい音がした。
崇は青くなり、ひざまずいて哀願した。
「お母さん、素直にお仕置をお受けします、ですから、皮鞭を使うのだけはご勘弁ください。」
崇はこの皮鞭の痛さを知り過ぎていた。つい1か月前も帰宅時闘を守れなかった罰としてお尻をこの皮鞭で50回も打ち据えられていたのだ、そのときの鞭の跡がお尻からきえたのはついこの1週閻くらいのことだ。
「なんだい、いくじがないねえ、勇敢にお尻を突き出せないのかい?そんなに鞭が怖いならまずはスパンキングでおまえのお尻を痛さに慣れさせてあげよう。さあ、お母さんの膝の上にうつぷせにおなり。」
崇は素直に継母の膝の上にうつぶせになった.これ以上継母を焦らすと事態は悪くなる一方だ。スバンキング程度なら素直に受けたほうが良いと判断したからだ。
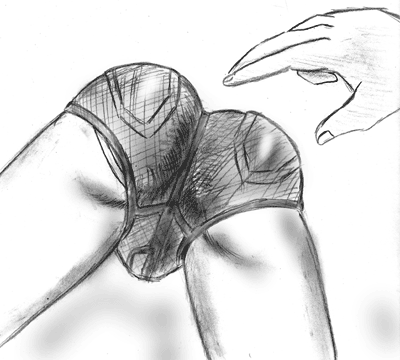
継母は崇のお尻を撫ぜたり、擦ったり、操んだり、尻溝に指を這わせたりしながらお説教した、これはいつもスパンキングの前に行われる儀式であったのだ。崇は1年を通じて極端に短い半ズボンをはかされている。これは崇のくりっとしたお尻やぴちぴちした太ももの魅力を十分に味わおうという継母の趣味である。このお尻や太ももむきだしの魅力を強調するために崇は一年中厚手のハイソックスをはくことも義務づけられていた。極端に短い半ズボンは、同時にスパンキングや鞭打ちの効果を高めようというねらいもあった。この儀式のために普段から尻たぶが少しはみでるぐらいに短い崇の半ズボンはさらにお尻の割れ目に食い込み、大袈裟にいうと尻たぶの3分の2がむきだしになるはめになった。
「崇、チャンスをあげよう、今から母さんはおまえのお尻を20回打ちます。このお仕置を悲鳴一つあげないで男らしく耐え抜いたらもうそれで罰は終り。鞭は使わないよ.約束しよう。」
「はい、お母さん。」
「ようし、さあ一発目がいくから覚悟するんだよ。ひと一つ。」
崇はお尻をきゅっと縮めて待った。一呼吸あってピシーリと平手が打ち降ろされる。崇はあやおくうめき声をあげそうになったが、歯を食いしばって耐えた。継母は崇が痛みを味わう時閻を十分にとる。そして、
「ふた一つ」
と次の平手打ちの数を数える。その間15秒ぐらいだろうか,崇は段々増してくる苦痛に繭えるのに必死だったが、継母は時々熱を帯びてきている崇の裏門辺りを指でまさぐったりしてスパンキングを楽しんでいた。
崇は本当によく残酷なスパンキングに耐えた。しかし、ついに19回目にして我慢の糸がほんのちょっぴりほころびた。ビシッという残酷な一打ちについに「ううっ」とかすかなうめき声を洩らしてしまったのである。継母は激怒して崇をベッドの上から床へ突き落とした。
「いくじなしっ、スパンキングさえ満足に受けられないのかい?今日という今日はもう許さないよ、皮の鞭で打ちのめしてやる。崇、さあとっとと半ズボンを脱いでベッドの上に四つん這いにおなりっ!

しかし、さんざんお尻を打たれたあげくにベッドの上から突き落とされた崇は床の上にうつぶせに倒れたまま起き上がれなかった。継母は残酷にもその崇の真っ赤に腫れ上がったお尻の上にピシリと皮鞭を振り降ろした、
「ぐずぐずするんじゃないよっ、おまえが起き上がって鞭打ちのときのおきまりの姿勢をとるまでおまえのお尻にぷち当たる鞭は数の申にいれないからね。」
ヒュッ・・…・…ピシーリ…・・・…ヒュッ………ピシーリ…・
皮鞭は次々と崇のお尻の上に振り降ろされる。崇は例えようのない激痛に床の上でのたうちまわったがやがて金切り声をあげて継母に哀願した。
「ひぃー、お母さん、堪忍してください。もう打たないでください。素直にお仕置をお受けしますから。」
崇はよろよろと立ち上がり、半ズボンを脱ぐとベッドの上にあがり手と膝をついてお尻を高く上げた。
「そう、それでいいんだよ、こんなに赤いお尻を鞭で打ったら、さぞかし痛いだろうね。勉強を怠けたとかそんなことじゃなくて、私はおまえを男らしく育てたいんだよ。あそこのうちは継母だから子供がだめだなんて、だれ一人いわせたくないんだよ。鞭で打たれたらそれはいたいだろう。だからといってぴいぴい悲鳴なんかあげてほしくないんだよ。さあ今日は途中で妥協しないからね。この痛い痛い、お前のお尻の匂いが染み付いている鞭でお尻を100回打つからね。さあ、覚悟するんだよ。始めるからね。」
「ひと一つ」
ヒュッと鞭がなって崇のお尻に叩き付けられる。切り裂くような悲鳴。
「ふた一つ、・・…・…みい一つ、…・・・…よお一っつ…・・・…」
延々と罰の鞭は続けられた。鞭の数が10を過ぎると崇は手と膝で這っていたのが腹這いになっていた。体を支えるだけの気力がなくなってしまったのだ。継母はそんな崇を叱り付けたがうつぷせの姿勢でも鞭打ちにそんなに支障はない。鞭はさらにうつぷせになった崇のお尻に叩き付けられた。
「15…・・一…16・……・・17・・・・・・…」
崇の意識は朦朧としてきて、鞭の数を数える継母の声が彼の耳から遠のいていった。
(おわり)