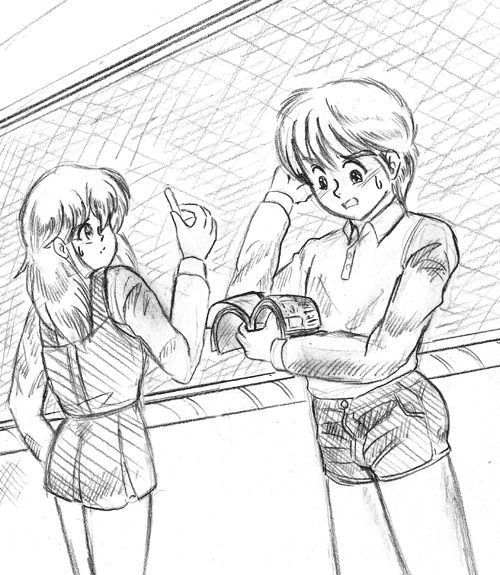
春の目覚め Part2
6年生になってクラスは変わらなかったが、担任の先生が変わった。東條幹男先生だ。東條先生はその前年も6年生の担任であり、あの、植野光一君にムチを振るった先生でもある。厳しいことでは有名であったが、保護者の評判は必ずしも悪くはなかった。ひいきもないし、厳しいが力もつけてくれる、しつけもびしっとしている、そんな評判の先生だった。
始業式の日、教室に入ってきた東條先生の話は簡潔だった。
「君達も聞いているとは思うが、君達が、誰でも納得のいく決まりを破ったり、誰もが当 然やらなくてはならない当番や宿題をサボったりした時は、このムチで打つからそのつもりで。このムチは『ケイン』といって、イギリスでは君達と同じ年齢の子ども達がこのケインでお尻を打たれて教育されている。イギリスの子ども達が耐えられて君達が耐 えられないはずがない。」
東條先生はケインを撓らせながら話した。去年、廊下から植野君が打たれているのを見た時にはよく撓る竹のムチだと思っていたのが、籐製のムチだったわけだ。
初めの1週間ぐらいは、皆緊張して過ごし、なかなかケインの洗礼を受ける第一号は出なかった。
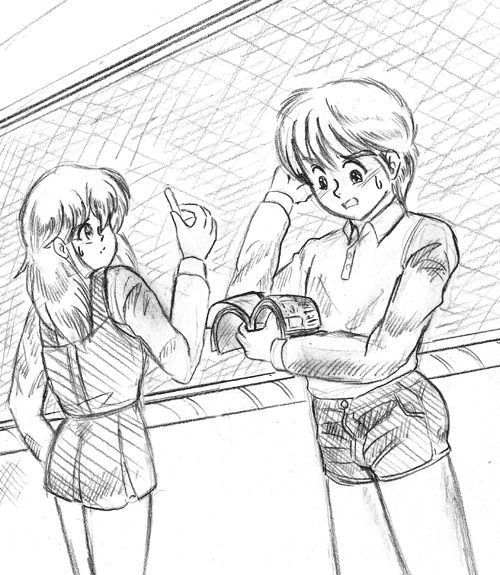
その頃、音楽の時間に「おぼろ月夜」を歌った。昔から歌われている歌だが、とても気に入った。あの、4月1日の衣替えの日の菜の花畑を思い出した。音楽の授業中に押井沙耶の方をチラッと見たが、彼女もにこっとして目で応えていた。彼女もあの日の菜の花畑を思い出しているのかもしれない。
音楽の次の時間は学級会だった。1学期の学級委員はぼくと押井沙耶だ。2人で司会をした。議題は6年1学期の係活動についてだった。うまくまとめられずに、次の時間に20分以上食い込んでしまった。東條先生は途中何も口をはさまなかった。ケインを撓らせて黙っていた。学級会が終わった時、
「樋口、押井、今日、放課後ちょっと残れ。」
と、言った。周りがちょっとざわざわした。みんなある予想をした。押井沙耶もぼくもいやな予感は一緒だった。ぼく達が「ケイン第一号」になるのではないかと・・・。
放課後、教室に二人だけ残りいつどのような状況でケインがお尻にとんでくるかとびくびくしているぼく達を前に、東條先生は、その日の学級会の司会のどこがいけなかったか、どうしたらよかったかを懇々と教えてくださった。その指導は、ぼくも押井沙耶も心から納得できるものだった。
「さて、お前達は今日、ムチを受けると思っているかね?それとも、打たれないと思っているかね?」
ぼく達はどちらとも答えられずに黙っていた。東條先生は話を続けた。
「学級会の次の時間は何だったかな?」
「はい、社会科です。」
押井沙耶が答えた。
「そう、社会科だったね。みんな、縄文時代のくらしの様子を調べるんだ、ってはりきっていたね。うちから重い学習辞典を持ってきた子もいたね。」
「樋口、内のクラスは何人だったかな?」
「は、はい。38人です。」
「お前ら二人は38人の学ぶ楽しみをうばってしまったんだぞ。」
「・・・・・・」
「よって、二人で38回、一人19回のムチ打ちを与える。ただし、お前らが納得できないんだったら先生は打たない。このまま帰りなさい。」
「いえ、先生、すごく納得できます。ムチを受けます。」
二人同時に答えていた。ぼくは、続けていった。
「先生、今日学級会が延びたのは、ぼく一人のせいです。 押井さんは打たないでください。ぼく一人で38回のムチを受けます。」
100%こういう気持ちだったかというとそうでもない。男の子だったらこう言わなくてはならないという空気が当時確かに存在した。100%うそかというとそうでもない。トム・ソーヤーよろしく、愛する美少女の身代わりでムチ打たれてみたいという気も確かにあった。4月1日菜の花畑で彼女が特別に見えたということは、彼女に恋をしているということだということに今さらのようにに気づいた。
押井沙耶はぼくをきっと睨むと言った。
「樋口君!そんなの古いわよ。男の子が強くて、女の子は男の子に守られる存在だなんて昔むかしの話よ。それに、自分の愛する人が自分の身代わりで38回もムチ打たれる音を聞いているなんてそんな辛いことできないわ!」
きっぱりとこう言い切った彼女はもう泣いていた。ぼくの全身に電流が走った。「自分の愛する人が・・・」彼女は確かにこう言ったぞ。ああ、今日は恍惚とした気分でムチを受けられそうだ。
「二人とも、立派な態度だ。こういう子どもこそムチを受ける資格があるんだ。いいか、お前達が言いふらさなくても、今日、学級委員の二人が計38回もムチ打たれたといううわさはさーっと伝わる。これでこのクラスはさらに引き締まる。もう、ムチ打たれるようなことをする子は出ないかもしれないんだ。さっ、押井はスカートを上げて、樋口は半ズボンを脱いで机の上にうつ伏せになれ。」
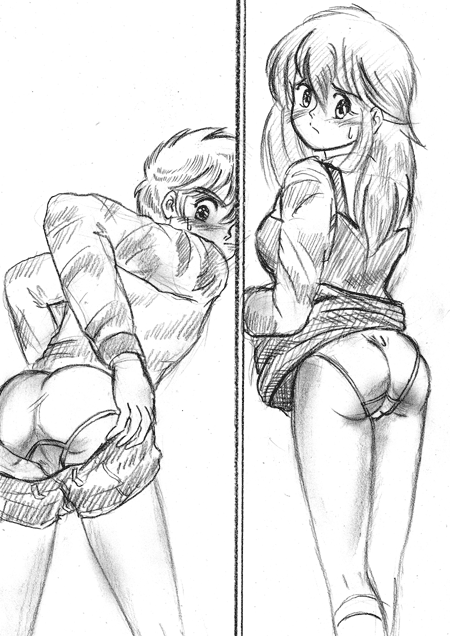
この時代は二人掛けの木机だった。この机がお仕置き台になった。
「ほう、押井の下着はずいぶんお尻に食い込んでいるな。これじゃ素肌を打つのとあまり変わらないな。痛いと思うが…樋口、お前もパンツの裾を自分でたくし上げろ。」
超短のデニム半ズボンの下で激しい動きにもまれているから、ぼくのブリーフもかなりお尻に食い込んでいたと思うが、押井さんのお尻よりもぼくのお尻の方がブリーフの布で保護されている面積が少しでも広かったら潔くないような気がして、ぼくは素直にパンツの裾を思い切りたくしあげ、ふんどし状態にした。
「さあて、どちらからムチ打つとするかな?」
一瞬二人とも沈黙した。誰しもいやなことは早く済ませたい。でも、ぼくは言った。
「先生、せめてこれだけは『レディ・ファースト』にしてください。」
「ありがとう、樋口君、その厚意はありがたく受けるわ。私、ムチ打たれてるその時よりもムチを待っている時の方がすごく怖いの。」
「よし、じゃあ、押井のほうから始めるぞ。歯を食いしばって。」
「ひとーつ」ヒュッ…ケインのうなる音…ピシーリ…「ああっ!」押井沙耶の叫び声…「ふたーつ」ヒュッ…ピシリッ…「い、いたーい!」…押切彩は一つ打たれるごとに叫び声をあげた。でも、決していやな感じはしなかった。お尻に食い込むケインの痛さに対する素直な反応だと思った。叫び声だって意に反して出てしまう悲鳴で「もうしません」とか「打たないでください」とかの哀願は一切なかったし、叫び声をあげることで打ち方を弱くしてもらおうなどという意図は全く感じられなかった。
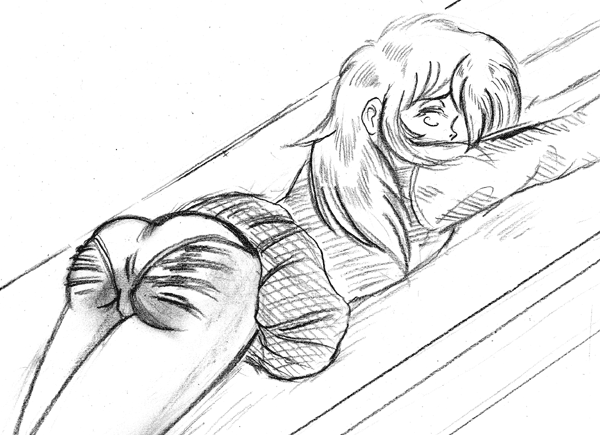
19回のムチ打ちを受け終わると押井沙耶は机の上にうつ伏せになったままで、左手の上に顔を乗せてしゃくりあげ、右手ではさっと超ミニのジャンパースカートの裾を降ろしてお尻を覆い、その上から腫れあがったお尻をさすっていた。
いよいよぼくの番だ。押井沙耶の自然な叫び声はよいとは思ったものの、自分は一言も声をあげないでムチを受けてみようと心に決めていた。去年見た植野光一君もこの同じ東條先生のケインを一言も声をあげないで受けていたではないか。
「さあ、次は樋口の番だ。いくぞ。ひとーつ」ヒュッ…ピシリッ…想像していた以上の痛さだった。お父さんからベルトで打たれ、お母さんから50cmの竹物差しで打たれているぼくのお尻はクラスの中でも痛さに慣れているほうではあると思うが、ベルトにしても物差しにしても幅が広いので、ケインのように細いムチが食い込む痛さはまた違ったものであった。でも、かろうじて悲鳴は押さえた。でも、涙は自分の意思とは関係なくあふれるように流れた。19回よく耐え抜いたと自分でも自分のがんばりに驚いている。初めに決めたように1回も声は上げなかった。しかし、あまりの痛さに気を失うのではないかとさえ思った。植野君のようにベントオーバーの姿勢で打たれていたらきっと途中で倒れていただろう。
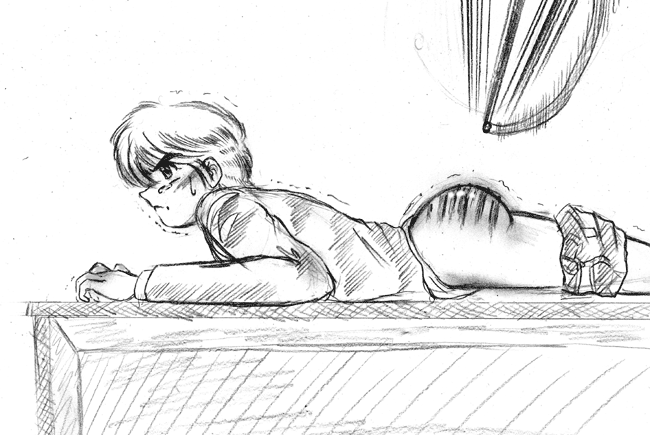
「よし、二人とも立派にムチに耐えた。偉いぞ。少し休んでから帰れ。」
東條先生はケインを黒板の横にかけると教室から出て行った。押井沙耶は相変わらずうつ伏せの姿勢で泣いている。それから、10分ぐらいぼくもうつ伏せの姿勢のまま、剥き出しの太ももが冷たい机の上に擦れる感触を味わいながらムチ打ちの余韻に浸っていたが、やがて元気が回復してきたので、机の上から降り、ムチの痕に触れないように気をつけながらデニムの半ズボンをはいた。お尻が腫れているので余計きつくなったように感じた。
「沙耶ちゃん、帰ろう。」
いつのまにか、ぼくは押井沙耶を名前で呼んでいた。押井沙耶は痛そうにお尻をさすりながら机から降りた。ぼくと目が合うと泣き笑いのような表情を浮かべた。
その日、ぼく達は並んで帰った。手まではつながない。お尻がひりひりするのでどちらも歩き方はぎこちなかった。ぼくの場合、歩くたびに短いデニム半ズボンの裾がお尻に食い込み、ケイン特有のぷくっと膨れた筋に触れてすごく痛い。
「男の子ってやっぱり強いわね。ワタル君は一回も声をあげないでムチを受けきったわね。」押井沙耶もいつかぼくのことを名前で呼んでいた。
「そんなことないさ。単なるやせ我慢さ。ぼくはかえって沙耶ちゃんの自然さがよかったと思うよ。…沙耶ちゃん、ちょっとうちに寄っていく?」
「いいの?だったらお言葉に甘えさせていただこうかしら。」
今日、ぼくのうちは誰もいない。今朝、かぎを渡されていた。うちに帰ると、ぼくはすぐに布団を2枚敷いた。今思い返すと、愛する美少女を大人が誰もいない家に連れてきて布団を敷くなんてなんと危険なことなのだろうと思うのだが、その頃は4月1日になんとも得体の知れない「春の目覚め」があったものの、その他の性に関する知識を体系的に身に付けていたわけではない。単に二人ともお尻が痛くて椅子にも座布団にも坐れない状態だから、布団を敷いてうつ伏せになって語ろうという意図だけだった。
「さ、沙耶ちゃんも遠慮なくうつ伏せに寝て。うちではね、お尻をムチで打たれるとき、まず、布団を敷いてそのうえで四つんばいの姿勢をとるんだよ。気を失ってもそのまま寝ていられるからね。あの日、4月1日、沙耶ちゃんと別れた後、うちに帰りのが遅くなってお母さんから50cmの竹物差しでお尻を20回も打たれちゃったんだよ。」
押井さんも布団の上にうつ伏せに寝て、剥き出しの太ももが布団に触れる感触を味わっているようだったが、だんだんリラックスしていくようだった。
「え、ワタル君も4月1日にムチ打たれたの?私もあの日、菜の花畑でワタル君に会う直前にムチ打たれていたのよ。」
そういえば、春風にめくり上げられたスカートの下のお尻には生々しいムチの痕がついていた。
「うちでも4月1日が衣替えなの。冬の間はいていた長ズボンを脱いで、5年生時代に着ていたねずみ色のジャンパースカートを身につけてみてびっくり。冬の間に身長が伸びて丈がすごく短くなっているの。ちょっと動いたら下着が見えてしまうくらい。『うわー、こんなの着れないわ!』って思わず叫んだら、お父さんに聞かれちゃって、『親が与える服が気に入らないなんてわがまま言うんじゃない、懲らしめてやる、庭からムチをとってこい!』って…うちではね、ムチ打たれる時はそのつど、罰を受ける子どもが庭からムチになる生木の枝をとってくるのよ。その日はよくしなる柳の枝を枝切バサミで切っていったわ。あんまり痛くなさそうな枝を選ぶと、やり直しの上打つ数をふやされちゃうからね。その枝をお父さんに渡した後、うちで『反省の椅子』と呼んでいる長椅子の肘掛の上に両手を重ねてその上に顔を乗せ両膝を立ててお尻を高く上げるのよ。小さい時からお尻をムチで打たれる時はこの姿勢をとらされるんだけど、4月1日はなんだがすごく恥ずかしく感じたわ。それで、お父さんは今日の東條先生のように『ひとーつ、ふたーつ』と数えながら、ムチを振るうのよ。私は今日と同じように、一つ打たれるごとに叫び声をあげてしまったわ。20回打たれ終わったときは、うつ伏せの姿勢で『反省の椅子』の上でつぶれていたわ。」
これで、4月1日に疑問に思ったことがすべてわかった。押井さんはどんな姿勢でどんなムチでお尻を打たれているか…。押井さんは話を続けた。
「ワタル君、あの日ね。菜の花畑であなたにあったでしょう?あなたも冬の間はずっと長ズボンだったわよね。久し振りに見たあなたの太もも、短い半ズボンの裾が食い込んだお尻、太ももを引き立てているハイソックス…あなたがすごく輝いて見えた。それから、学校でもはしたないようだけど、あなたの太ももやお尻ばっかり見ていたのよ。…ワタル君、私はあなたが大好きよ。」
「沙耶ちゃん、ぼくも全く同じだよ。あの日菜の花畑であって以来、君の小麦色の太ももや赤いハイソックスが頭から離れなくなった。そして、春風が見せてくれたお尻のムチ痕のことがすごく気になっていたんだ。…ぼくも沙耶ちゃんが大好き。」
この先、二人はどうしたか?今になって、あれもすればよかった、これもすればよかった、と後悔するけれど、そこは、二人とも昭和40年代の小学生だ。二人で布団の上にうつ伏せになって「おぼろ月夜」を歌っただけで、押井さんは帰っていった。