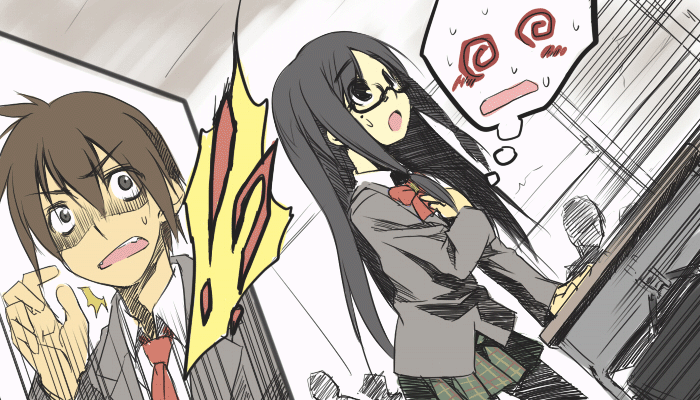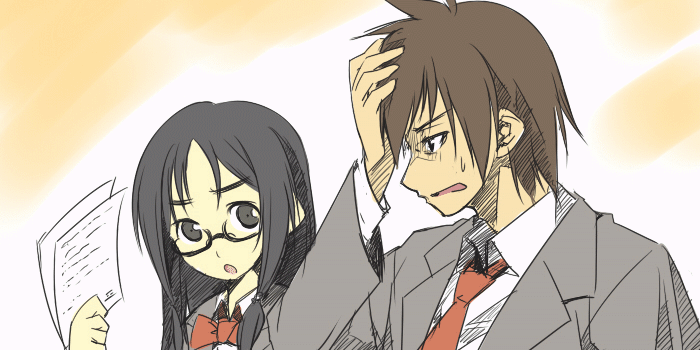思春期玉虫色
00
朝、体は自然に目覚める。
「ん…………」
身を起こす。
空気は爽やかだった。
体調は正常――いつも通りである。
葦原牧人の生活サイクルはこう見えて規則正しい。
早寝早起きというほどではないが、寝坊はあまりしたことがなかった。
起床に目覚まし時計の類は使わない。
両親が騒音を嫌うからだ。
登校準備を終え、階下に。
葦原家の居間は無人。
これもいつも通り、一人の朝食である。
台所に置かれた食パンを数枚手に取り、トースターへ。
焼け上がるまでの三分弱の間、冷蔵庫を開きバター、ジャムを取り出す。
その他、未開封のハムと昨日の残り物であるレタスを発見した。
音を立て、トーストが飛び出る。
包丁を使って切れ目を入れ、そこに先程用意した具材を挟み込む。
簡易なホットサンドの完成だ。
乾いた皿を一枚用意して、乗せた。
「…………」
黙々と食す。
立ったまま、台所での食事だ。
朝食は一日を生きる力だと言う。
どこか年寄り臭い発想と思ったが、牧人はそれを信条としている。事実だとも思えたからだ。
故に欠かさない。気分に応じてパンの中身が決まるため栄養バランスはまちまちだが、活動に支障はない程度である。
元より質素な内容だ。食事は素早く終わる。
テレビやラジオをつけることはない。少しでも雑音がすれば、神経質な牧人の両親は目を覚ましてしまうだろう。
二人は起床が遅い。いわゆる重役出勤だからであるが、帰宅が遅いこともその理由である。
牧人の両親は夜遅くに帰宅し、次の日の出勤直前まで眠っている。
息子と顔を合わさない日もある。最後に食卓を囲んだのもいつのことか定かではない。
「…………」
だが、牧人はひとりの食事が好きだった。
煩わしいことは何もなく、自立している感覚が心地よい。
朝は面倒だが、夜にはそれなりに凝った料理にも挑戦する。食にこだわる方ではないため、買い弁当やレトルトで済ますこともままある。
しかし、いずれにせよ解放感はあった。
食事は好きだ。安息の時間だからである。
「………………」
食器を片付け、冷蔵庫から小型のゼリー飲料を取り出した。
アルミパウチの上部についた飲み口を開き、咥える。
ホットサンドだけでは小腹が空くときもある。そんな時は、買い置きしてあるこの手の栄養食品に頼る。
値段は張るが、時間を取らないのがいい。
「ごっそさん」
げっそりと痩せたアルミパウチをくず入れに放り捨てて、牧人は動き出す。
トイレを済ませ、歯を磨く頃にはもう登校時間だ。
玄関を出て、キシリトールガムを一粒含む。
いつも通りくちゃくちゃと咀嚼しながら、歩き出した。
大体が、このような朝の風景だった。
高校に進学して学校までの距離が変わった分、少しだけ時間に余裕ができた。
だが、一週間もしないうちに差はわからなくなる。
しかし新学期の感覚はまだ強く残っている。
季節は、春であった。
■■■■■■■■■
学校は歩いて行ける距離にある。
何を隠そう、牧人にとって最大の志望理由はそこにある。それでいて偏差値もそこそこに高く、進学校としての評判も良い。言うことなしだった。
言ってしまえば、その程度の理由で合格できてしまうくらいには牧人の学力は高いのだった。
だが、つまらないことにはまるで努力をしないその性質が、彼の成績を普段は中の下程度に留まらせていた。
「おはよう、牧人」
「おう」
家を出てすぐ、彼の友人である武田明彦と会った。
二人の家は近所というほどでもないが、同じ地域にある。
どちらともなく隣に並んだ。
歩き出す。
「今日もいい天気だね」
「相変らずジジイみたいなことを言うな、お前」
自然と笑みが浮かぶ。
彼との会話は何も考えずに済んで気楽だった。
明彦は牧人にとって“幼馴染”であり“腐れ縁”だ。
小学校低学年に出会って以来、なんとなく一緒にいる機会が続いている。
一言で表してしまえば、二人は自然な友人といったところだろうか。
特別趣味が合うわけでもないが、なんとなくいつも近くにいたからお互い一番自然に話せる知人同士。
そしてつい先日、同じ高校に二人は進学し、その付き合いの記録がまたしても更新された。
「牧人の方が学校に家近くなったね」
「まぁな。あんまりそんな自覚ねぇけど」
二人の通っていた中学校は、高校とは正反対の方角に位置している。
中学時代は牧人の家の方が学校から遠かったのだ。
春の空気は弛んだように心地よい。
――サボりてぇな……。
このまま学校など忘れてどこかに行ってしまいたくなる。
「牧人、高校だと少し静かだよね」
不意に明彦がそう口にした。
「そうか?」
「んー、中学の時ほど、キャラが立ってないというか」
「……おい」
「どうかした?」
「いや、別に……」
牧人的に聞き流せない発言だったが、深く追求するのも躊躇われた。
葦原牧人は個性を愛する。
大衆に没することを嫌うのだ。
故に嗜好もやや独走に過ぎるきらいがある。今履いている虎縞模様のシューズなどその最たるものだ。
中学校の時は、その個性的な感性が周囲に面白がられ、彼はクラスの中心的な位置にいた。
クラスメイトは誰もが親しみを込めて彼を“マキ”と呼んだ。
「まぁ、このぐらいなのも気楽でいいさ」
「そう? ならいいけどね」
今、その名前で彼を呼ぶ人間は周囲にいない。
中学時代にそのあだ名が普及する以前からの付き合いである明彦は、普通に彼を名前で呼ぶ。
高校というものは中学校とは明らかに異なる集団である。
肉体的にはそれほどの差はない。高校生より大柄な中学生も最近では珍しくない。
しかし、両者の精神的な差は著しい。
高校は生徒数が多い。しかも彼等は皆同じようなレベルの学力であり、言わば同程度の能力を持っている。多少の差はあれど、ある程度均一化がなされている。
受験という制度が、子供たちをふるいにかけるのだ。学力や理解力に応じて、選別が行われ、その時点で妥当なランクが定められる。
同レベルの人員が集まった集団は結束力がある。他者の思考を自分のものと共通させて理解することが容易いからだ。硬い友情や結びつきが生まれやすい。
しかし、同様の理由で上に立つことは極端に難しくなる。実力の程が初期から割れているため、威力を見せることが困難なのだ。
……団結力のある集団における統率者の必要性。その是非はさておくとして、単に個性を出すだけで人気者になれるわけではないのだ。
むしろこの場合、極端な個性はかえって仇となる。
まだ警戒心が強い一年の新学期などで強い個性を発揮すれば話題にされる。
結果的にそれは、その気はなくともそれが欠点のように扱われかねない。
そんな空気を牧人は察している。だから派手な言動を慎んでいるつもりではある。
しかし、牧人が中学時代より地味に見えるのはもっと単純な理由がある。
――なんというか、濃い……どいつもこいつも。
中学時代に比べ、皆キャラクターが強い。
それは中学のクラスより学力水準が高めであることも理由だろうが、より大きいのは地方差である。
都会から来ている生徒はファッションセンスがある者が多い。
体育会系の部活が強い中学の出身者は多くが活動的で真剣だ。
今まで見たこともない個性を発揮する生徒もいる。言動を見て驚嘆させられることがある。
その雑多な個性は、一つ一つが強力だ。輝かしいまでに。
身なりに関しても、中学時代より男女問わず格段に気を使うようになる。
地味な制服を自分なりに着こなす生徒、装飾品などで個性を演出する生徒も目立つ。
牧人の個性的なセンスも、受験が終わって解放的な気分になっている他の生徒たちに埋没している感があった。
とてもセンスがあった少年は、ちょっとセンスがある程度の少年になってしまったのだ。
世界は広い、牧人は漠然とそう感じた。
それはなんというか、ままならない。悔しい。
しかし逆に、目立たないというのも案外楽なのだと感じた。
そう考えると、牧人は以前に比べ少しだけ余裕が生じたということにもなる。
「まぁ、ボチボチやっていくさ」
「そうだね。実際、変わったのは周りの環境で、牧人自身はそんなに変わってないんだと思うよ」
「だよな」
明彦が思いを代弁してくれた。
共感を得て、牧人は少し安堵する。
そんな感じで、牧人は今日もそれなりに生きていた。
01
そんなある日のこと。
「マキ、くん?」
牧人はそんな懐かしい名で呼びかけられた。
最後にそう呼ばれたのは中学校の卒業式の日。
一月程度の期間といえ、もう呼ばれることがないと思っていただけに妙な感覚だった。
「ん……?」
振り返る。
一人の少女と目が合った。
――……?
認識が追いつかない。
まだ新学期が始まって一週間程度。クラスメイト全員の顔は記憶できていない。
「あは、やっと話しかけられた。久しぶりだね」
親しげな様子で微笑みながら、手を振ってくる。
長い髪をした少女だった。
大振りの分厚い眼鏡をかけており、いかにも勤勉で大人しそうな雰囲気――
――……久しぶり?
マキ、というそのあだ名は、中学時代のものだ。
従って、その名前で彼を呼ぶからには、相手は中学時代の知り合いのはず――
――――なのだが……、
「…………?」
――誰だこいつ?
牧人は即座に認識ができなかった。
かつて、牧人は学年中にそのあだ名で呼ばれていた。
親交のあるクラスメイトは勿論のこと、特に会話をしたこともない生徒も牧人のことをそう呼んだ。
牧人は有名人だったのだ。
だから、この少女もそんな会話もしたこともない生徒の一人だったのだろうと牧人は考えた。
「……マキくん、だよね?」
押し黙る牧人に不安になったのか、確認するように尋ねてくる。
「あぁ……。そうだよ」
とりあえずそこだけは肯定した。
適切な反応がわからず、素っ気無い言い方になってしまったが。
――しかし、誰だ……?
牧人の疑問は募る。
「………………」
少女の姿をさりげなく見やる。
その顔には見覚え――よく目にしていた記憶はある。恐らく知り合いであったことが予想された。
しかし、喉元まで出かかった名前は曖昧な記憶と共に飲み込まれてしまう。
「……もしかしてマキくん、わたしのこと覚えてない……?」
「――っ」
鋭い少女だった。
そして牧人も図星だとすぐ表情に出てしまう。一瞬で察せられる。
「……やっぱり。確かにそんなに話したこともなかったけど…………」
落胆された。
「えぇと……」
――確か……。
必死に記憶を辿るも、思い出せない。
その工程の最中、牧人は自身がいかに無自覚な状態で中学時代を過ごしてきたのかを思い知らされつつあった。
「はぁ……」
眼前の少女は呆れたように嘆息する。
「藤宮薫、だよ。中学三年の時、同じクラスだったじゃない」
まるで不出来な子供を見守るように、優しげな微笑を浮かべてそう言う。
「…………藤宮、薫――?」
――あぁ、そういえば……。
名前を口にして、曖昧だった記憶が一気に輪郭を帯びた。
――いたっけ……、こんなヤツ。
結局その程度の認識である辺りは葦原牧人。
冷めた中学時代を送ってきただけのことはある。
しかし、彼女に関する情報は大体思い出した。
――藤宮薫。
本人が言う通り、彼女は牧人と中学三年時に同じクラスだった。
しかし、特に親交があったわけでもないのもまた事実。
牧人は目立つ方だったため、相手が一方的に認知していたというのも肯ける話である。
――それに……なんて言うか……、
「………………」
「――?」
再度、藤宮薫の姿を見る。
――地味だよな、こいつ。
聞かれたら憤慨されそうなことも平然と思考するのが牧人だ。
確かに、外見的な要素に限定するなら、藤宮薫は地味な少女である。
普遍的な美人ではないにせよ、瞳は大きく鼻は小振りで、愛敬のある見た目をしている。
だが、分厚い眼鏡も長い黒髪も洒落っ気に欠け、華やかさとは程遠い印象だ。
それだけに牧人の記憶は薄かった。話しかけられた記憶はない。話しかけた記憶もない。
「その様子だと、全然覚えてないみたいだね……」
「……すまん」
さすがにショックを受けたらしい。藤宮薫は眼鏡越しの視線を俯かせる。
実際、牧人は全然覚えていなかったが、思い出しはした。
……最も、思い出したところで特筆すべき思い出話もなかったが。
「合格発表の時、マキくんも来てるの見て、もしかしたら……って思ったのに」
「そうなのか」
牧人からすれば、薫がその場にいても認識すらできなかっただろう。
「でも、クラスまで同じなんて、すごい偶然だね」
「……そうだな」
またしてもつれない感じになってしまう。
――仕方ねぇだろ、自覚ないんだから……。
心中で言い訳などしてみたり。
「わたし、中学からの知り合いとか全然いなくて、ちょっと不安だったの」
目線を逸らしつつ、少し恥ずかしげな素振りを見せる薫。
「だからマキくんがいるって知って、すごく安心したんだよ?」
「そ、そうなのか……」
その直截な物言いに、牧人は少したじろぐ。
「でも、マキくんはわたしのこと覚えてなかった……」
直前とは対照的な低い声音。心に突き刺さる言い方だった。
彼女のような真面目そうな人間がこれをやると、より効果的だ。
「……悪かったよ」
だから牧人は素直に謝った。
悪気などこれっぽっちもなかったが、そんな気にさせられたのである。
「まあ……、いいけど。これからはよろしくね」
「……あぁ。まぁ、適当にな」
「もぉ……」
上手い言い方が見つからず、そのように濁したらため息をつかれた。
何やら反応が予想されていたような雰囲気だ。
どうも牧人の性質をかなり正確に把握しているようだった。
――なんか、嫌な感じだな。
苦手意識のようなものが生じた。見透かされている感がある。
もしかすると、覚えていないだけである程度親交があったのかもしれない。そう思った。
かくして、葦原牧人は藤宮薫と約一月ぶりの再会を果たした(無自覚に)。
02
前述の通り、新学期とは警戒心の強くなる時期である。
とりわけ一年生の一学期などは特にその傾向が強い。
周辺環境の一変。
昔からの知人の喪失。
そこには多くの不安要素が存在し、否応なしに個々の自衛意識を高めてしまう。
下手な個性の発揮は身を滅ぼす。
そうした空気が存在する。
誰も口外しないが、暗黙のルールとしてそれは認知されている。
……否、認知しなければならない。
例え無知であっても、逸脱すれば注目を集めてしまう。
警戒心の強い空間における注目は危険だ。安易な標的にされてしまう可能性がある。
標的にされる――それは軽度な物なら話題の中心になる程度だが、重度な物ならいじめを筆頭とする各種攻撃の対象になってしまう。
それに耐え抜くだけの図太さや、注目を集めても良い意味でそれを利用できるような狡猾な性質がないのであれば、極力目立たないよう努めなければならない。
客観的に見れば酷く卑屈な空気である。
大袈裟な物言いに聞こえるかもしれない。
実際、辺りの空気そのものは気怠げで、そこまで無理な力が働いているとも思えない。
だが同時に、今まで述べてきた事もある一面で真実だったはずだ。
誰もがこの瞬間無自覚に、新しい環境、新しい他者との軋轢を体験しているのに違いはないのだから。
だから、沈黙は、黙考は、自分の身を守る盾だった。
結果、どうにも居心地が悪い。
然るに、新学期で最初の試練とは、現在牧人のクラスで行われているこの時間ではなかろうか。
――――委員会決め。
入学式から約一週間が経過。
高校生活も本格的にスタートし、授業のみならずそうしたサブ的な活動も開始されるようになる。
牧人の通う平坂高等学校では、まず委員会が決定される。部活動の選択決定はその後に行われることになっていた。
そして今。
クラスには、微妙な空気が漂っている。
委員会の席が埋まらないのだ。
「…………」
担任教師がため息をつく。
この停滞感自体には慣れたものだが、好きになれるはずもない。
残された席は学級委員――いわゆる委員長と副委員長である。
その立場は言わばクラスの代表。わかりやすいリーダーだ。
責任の伴う立場だ。生半可な気持ちで成し遂げられるポジションではない。
確かに高校ともなれば、生徒たちの自立性は高まり、小中学校程の無秩序な集団にはなりにくいだろう。
しかし、そんな中でも代表の存在は重要だ。
それは統率者としてではなく、明確な方向性やわかりやすい看板としての意味合いが強い。
従って、学級委員の作業自体は何もそこまで面倒なものではない。
クラスとしての意見のまとめや、イベント時の司会進行程度の物だ。
しかし立場上、ある程度の信任が必要になる。
いい加減な性格の者や、弱腰の者が自分たちを代表する者とは思われたくないものだ。
故に、新学期の学級委員は埋まらない。
環境も違い、知り合いもいない状態で、クラスの顔を張れるほど自信のある者がこの年代で果たしてどれだけいるだろうか。
――面倒臭ぇなぁ……、早く終われよ。
牧人は肘を突きながらこのようなことを考えていたが、クラスメイトの多くが同じように思っていることだろう。
やる気のない者にとってこの時間は無意味なものでしかなく、やる気がある者も挙手のタイミングや自分に対する自信など終わらない葛藤を持て余す。
結果、停滞する。意味不明な沈黙が続く。
ちなみに牧人はどの委員会にも所属しない。
……葦原牧人は強制を嫌う。
面倒な雑務をこなすだけの委員会活動など、進んで行うはずもない。
そう言ってしまうと身も蓋もないが、そうした真面目な活動を通して何かを得ようとするような真剣さが牧人にはなかったのだから仕方ない。
幸い、決まらないのは学級委員だけだった。
この沈黙がしばらく続いた後に、色々と無茶な方法で適任の生徒が選ばれるのだろうと考えていた。
――もう俺には関係ねぇな。
退屈だが、気楽ではあった。
「誰か、学級委員に立候補する人はいないか?」
担任が言った。
軽い口調だ。これで決まるとも思っていないのだろう。
「新学期でみんなお互いのことなんか知らんだろうからなぁ……、いきなり推薦ってワケにもいかんし……」
悩ましげに言う。
「どこの委員会にも入っていない人、誰かやってみないか。確かに学級委員は大変な仕事だが――」
この後、担任は学級委員の活動を通して身につく実力や、その成長の素晴らしさなどを数分間にかけて語った。
いい話だった。話術に長けた優秀な教師である。
「………………」
しかし、牧人を始めとする生徒の多くは心を揺さぶられることはなかった。
相変らず立候補者はいない。
――うるせぇなぁ……、誰か早く立候補しろよ……。
意外に難航している状況に牧人は徐々に苛立ってきた。
気付けば終了時間間際である。この流れでは延長は必至だ。
「うーん……」
担任教師も困った様子だ。
今回の件に関して彼の教師としての能力に是非を問うても詮の無いことである。
これは生徒の精神的な問題であり、乱暴な言い方をすればシステム上の弊害ですらあるのだ。
一教師にどうこうできるレベルではない。彼等にできるのは上手い具合に場を持っていくことくらいだ。
「参考までに聞くが……、」
何気ない調子で切り出す。
場を持たせるためだけの発言であることが感じられた。
「この中で中学校の時委員長をやっていた人いるか? いたら手を挙げてくれ」
――ハッ……!?
牧人は心の中で失笑した。
そんな質問、冗句でも笑えない。
――馬鹿じゃねぇのか。そんなんで手ぇ挙げるヤツなんかいるかよ。
この状況での挙手など、委員長確定まっしぐらである。
例え実際にそうであったとしても、素直に挙手できる程に容易い空気ではない。
「……はい」
しかし、手は挙がった。
静かな教室内には、控えめなその声でもよく響く。
牧人はその声を記憶していた。
新学期、まだクラスメイト全員を覚えていない段階でも、たまたま知っていた。
――藤宮薫。
長い黒髪の少女は眼鏡越しにやや不安そうな目をしながら、真っ直ぐに手を挙げていた。
「…………ば――」
――馬鹿かあいつ……! 何、馬鹿正直に手なんか挙げてんだよ……!?
思わず声に出そうになったのを必死に押し留める。
「…………」
牧人からすればこのタイミングの挙手など理解不能だ。自殺行為に等しい。
――そういや、藤宮って委員長だったんだっけ……?
思い返してみれば彼女の姿は壇上でよく見かけた。行事の指揮をよく執っていたのも思い出した。その時に何度か会話を交わしたような記憶も……、
「………………」
見るからに真面目そうな少女である。単に嘘をつくことができないのだろう。
いずれにせよ、牧人の中で焦燥と手遅れ感が広がっていく。
牧人が焦っても何の意味がないのだが。
「お、藤宮は中学の時に委員長だったのか」
「は、はい……」
おずおずと肯く。
期せずして担任と一対一の会話が始まる。
クラスメイトの頭上を通過して行われる会話は、静謐としていながらもまるで銃撃戦のようだった。
他のクラスメイトは頭を屈めて身を隠すようにしている。自分に矛先が向くことのないように、目立たないように努める。
教師が目をつけた哀れな標的がこのまま撃たれることを切に願う。
客観的に見れば残酷なものである。これでは人柱を立てるのと変わりない。
……ちなみに牧人もその中に含まれるが、そのことを冷静に見直すほど彼の心中は穏やかではなかった。
「なら、またやってみないか?先生もできる限りの手助けはするぞ?」
「え、ええと……」
口調は柔らかいがそこには強制の臭いがひしひしと感じられる。
ここに来てようやく、当の薫も具合の悪そうな顔をしだした。
「他のみんなもフォローしてくれるはずだ」
「…………」
生徒側からすればそんなことを勝手に口約されても困るのだが、この静かな戦場においては誰もがそれも吝かではないと考えていた。
「わ……、わかりました……」
遂に断り切れなくなる薫。
それに対して担任は大義そうに肯いた。
「よく決心してくれた。みんなも藤宮を助けてやってくれ!」
ようやく席が一つ埋まって一安心。そんな顔をしていた。さりげなく拍手をし出し、生徒たちも戸惑い気味にそれに続く。
しかし、無言の喝采の中心――槍玉に挙げられた薫の表情は、苦笑いをする程度の余裕はあるものの、やはり暗い。
責任感はありそうだ。委員長としての仕事をこなすだけの能力もあるのだろう。
だが、仕切り屋というには程遠そうな少女である。できればやりたくはなさそうだった。
だというのに、上手い具合に引き合いに出されてそのまま押し付けられてしまっている。
牧人を含め、クラスメイトたちはそんな彼女を呆然と眺めていた。
――なんて言うか……、
可哀想だった。
俯く彼女の姿が哀愁を誘った。
誰もがそう思った。
そして、犠牲になってくれた彼女を助ける機会があれば助けよう、とも。
――まぁ……、困ったヤツだよな……。
牧人も心中では同情の念を禁じえない。
一応、中学時代からの付き合いでもあるし(今や多少は実感が湧いてきた)、そのうち声援でもかけてやろうとは思った。
「さて、残るは副委員長だけだな」
喪に服すような教室内で、担任の口調は場違いなまでに爽やかだ。
一部のクラスメイトでその態度に反発心が芽生えかけているのを彼は果たして理解しているのだろうか。
「誰か、藤宮と一緒に仕事をしてくれる人はいないか?クラスを代表して藤宮をサポートしてやって欲しい」
――卑怯な言い方をするな、こいつ……。
他人事ながら、牧人は腹立たしくて歯噛みした。
藤宮薫を同情させるポジションに据えておいて、その発言。彼女に対する罪悪感から、思わず挙手してしまいたくなる。
「………………」
しかし、皆、相応に狡猾だった。
相変わらず手は挙がらない。
「うーん、弱ったな……」
――もっと弱ってるのは藤宮だろうが。
無意味に心中で抗議する牧人。
同様の思考をもう何人かも抱いた様子だ。
担任に対する目に見えぬ敵愾心のようなものが教室を覆っていく。
あわや再び戦場と化す予感がしたその時――
「あ、あの……」
藤宮薫が、再度挙手をした。
「ん? どうした藤宮」
担任のそんな平和な口調とは裏腹に、生徒間には緊張が走る。
――このタイミングで今度は一体何を……!?
誰もが次なる薫の発言に傾注した。
「え、ええと……、副委員長の推薦を……してもいいですか?」
爆弾発言だった。
これは言わば爆撃の予告。もう一人の犠牲者を自ら指名して、巻き添えを喰らわせようというのだ。
犠牲者と思われた少女が実は自爆テロリストであったかのような衝撃である。
「おお、誰か推薦したい人がいるのか? いいぞ、言ってみるといい」
担任の安易な許容発言に、クラス中の緊張感はピークに達する。
同時に一部生徒内でこの担任へ信頼が地に堕ちた瞬間でもあった。
若く能力もある教師だったが、生徒からの信頼はそうした要素とは無関係に離れていく。
得難い物なのだ。難儀なことである。
閑話休題。
クラス一同は藤宮薫が一体誰を指名するのか、動揺に沸き立っていた。
落ち着きがなくなる。そわそわし出す。
言を発するものはいなかったが、それ故に無数の鼓動が聞こえてきそうだった。
「ええ……と――」
そんな中、少女はおもむろに口を開き――
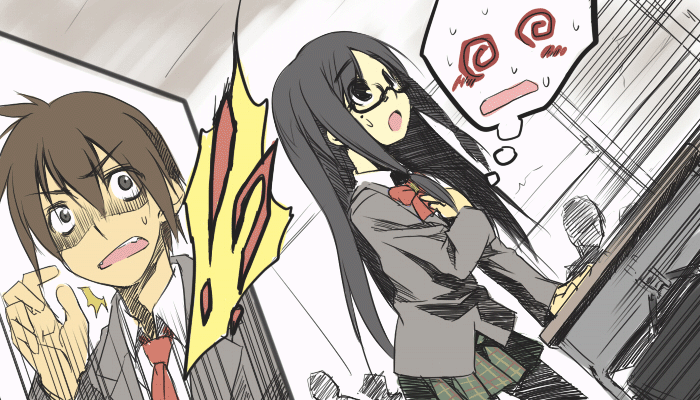
「葦原くんを、副委員長に推薦……したいです」
「な、え…………っ!?」
今度こそ声に出してしまっていた。
――な、何ぃぃいいぃい……ッ!?
心の中では絶叫していた。
全くの奇襲だった。自分が指名される可能性など考えもしなかった。
「…………っ! ……っ!」
何か言いたいが、顔面の筋肉が全てひきつって言葉にならない。
驚愕によってなんとも無様な顔をしていたが、今の牧人はそれどころではなかった。
――あいつ……俺を巻き添えに――何を考えて……!?
思考も言葉にならなかった。もう無茶苦茶である。
「…………?」
対する他のクラスメイトは、
――葦原って誰だっけ?
という新たな疑問に首を傾げていた。
ただ一人、彼を良く知る武田明彦だけが穏やかに苦笑している。
「葦原……か、一応理由を聞いてもいいかな?」
「は、はい。葦原くんとは中学校の時から同じクラスで……ええと、お互い顔見知りだし、やりやすいかと……思って」
「ほぅ、そうだったのか」
感心する担任。
薫も嘘はついていない。
「葦原、どうだ? 同じ中学のよしみでやってくれないか?」
「いや……俺は――」
――馬鹿が! やれるわけねぇだろ!
思っているままストレートにものが言えない牧人は曖昧に渋っていると……、
――キーンコーンカーンコーン。
時間終了のチャイムが鳴り響いた。
■■■■■■■■■
「……………………」
私立平坂高等学校一年B組の副委員長である葦原牧人は呆然としていた。
現在は下校時刻。
直前まで委員会決めのHRという重苦しい空間におかれていたクラスメイトたちは解放感のおもむくままに下校していく。
結局、牧人は副委員長になってしまった(されてしまった)。
あの瞬間、時間終了を告げるチャイムを聞きながら、肯くより他になかったのである。
自分以外に新たな副委員長を選出する作業を、最低限の時間延長で行うだけの手腕を、彼は持ち合わせていなかった。
というか、クラス中からの視線が痛かった。
――お前ここで余計なこと言って延長なんかさせんじゃねえぞ。
そんな空気をひしひしと感じたのである。
空気を読まなければならなかった。
ここで我を通せるほど強いのなら、始めから牧人が委員長もやっている。
薫には曲がりなりにも中学の時に委員長をやっていたという実績がある。彼女が学級委員の任を務めるというのは、まあ、わからない話ではない。
しかし、牧人は全然そんなことはない。
藤宮薫同じ中学出身だった、というだけの理由である。
それに牧人は初見でもそういった仕事に向いていなさそうだと感じられる容姿や態度をしている。要するに、どう見てもミスキャストなのだ。
その人選に対しての反対や疑問の声もクラスメイトたちの中にはあっただろう。
しかし、そのようなことを考え、議論するほどの余裕が彼等にはもうなかった。
……ぶっちゃけると、もうどうでもよかった。
よくよく考えると、薫の言った“同じ中学だから”という理由も選出の根拠としては甚だ曖昧だ。ものすごく強引に押し切っている感じがする。
そのような適当な理由付けで納得させられてしまうクラスメイトも担任も牧人は嫌いになりそうだった。
――くっそ……、なにがどうなって――
今の牧人は限りなく猜疑心の塊――人間不信一歩手前だ。
ちなみにあの後、薫は多くのクラスメイトから、
――がんばってね!
とか、
――何か手伝えることがあったら言ってくれよ!
などと言われて励まされていた。
やはり一人晒し者となった姿はそれなりに同情を集めたのだろう、やや後ろ向きとはいえ、彼女の学級委員生活は早くも安泰の兆しを見せている。
「…………」
しかし牧人の周りには、だーれも来ない。
声援も慰めも何もない。
牧人の席では牧人自身がカカシのように茫然自失としているだけだ。
客観的に見れば、意味不明な理由で副委員長に抜擢された牧人の方が同情できそうなものだ。
それに対して明確な拒絶ができなかったのだから仕方ないと言われればそこまでだが、そんなの薫も同じである。同情の余地はない。
日頃の行いの差だろうか。有り得た。いくら取り繕っても男子では女子に勝てないのか。
様々な疑念が生じては消えていく。
――くそっ、理不尽だ……、今の世の中はどうなってるんだ……!?
世の中にまで疑問の声を投げかけてしまう牧人。
依然として混乱中だった。
そんな中、
「あの、マキくん……」
現れた藤宮薫。
何か言いたそうな表情で、いつの間にか牧人の前に立っていた。
「――!」
放心状態だった牧人だが、彼女の出現に一気に意識が覚醒する。
平常に近い心理状態になって、色々な何かが心の中で渦巻き始めた。
様々な危険物質が化合して、今にも爆発を起こしそうである。
――こいつ、さっきはよくも……!
まさしく仇敵扱いだった。
理由を問い詰めるまでもなく激怒する直前だ。
「藤宮ァ……、お前――!!」
心に溜まった鬱憤から、思いのほか大声が出てしまった。
教室に残っていたクラスメイト数名が何事かと視線を向けてくる。
――……!?
何か危機感を覚えて声を潜める。
「お前……は、一体どういうつもり、で…………」
精一杯努力して声を抑え、尻すぼみになる。
同時にもう色々が嫌になって、よろよろと机に手を突くような体勢になってしまっていた。
――ああ……もう……、くそっ……。
これ以上感情を爆発させたらクラスにおける立場がますますややこしいことになる。
中学の時のように中心に立ちたい欲求はあまりないまでも、ヘンな方向に持ち上げられるのだけは御免だった。
だから、とりあえずキレない方向で。
わだかまる不燃感を抑えて、必死に自分を落ち着かせる。
「藤宮――」
「――マキくん、本当にごめんっ!」
そうして何か言おうとしたら、ものすごい勢いで頭を下げられた。
「……っ」
かなり必死だった。気圧されて言葉が止まる。
くすぶっていた火は今の謝罪で完全に消えてしまった。
「……………………」
わけもわからず巻き込まれたことについての怒りはあるが、もう吐き出す気分ではなくなってしまっている。
……結果的に、牧人はむっつりした。
「あの、あのね……」
それでも薫はきちんと事情を説明しようとする。
「な、なんか自分でもよくわかってない間に決められちゃってて……その、知り合いが誰もいなくて心細かったから……」
それは、あまり理路整然とした説明ではない。
「わ、わたしとマキくん、同じ中学出身だから、お互いヘンな遠慮もいらなくていいな、って思っちゃって、気付いたら……」
彼女はただひたすら心情を語っているだけだ。
「い、今思うと……自分でもなんであんなこと言ったのか……、わたし、緊張してて……その、迷惑……だよね……。ごめん、本当にごめんね!」
そこには正当な理由がまるでない。
ただ、彼女は素直で、必死だった。
「そ、その……」
言うべきことがもうなくなったのか、そこで言葉を詰まらせる。
顔を上げた薫は不安定に視線を彷徨わせながら、なんとか牧人と目を合わせる。
正面から、見つめてくる。
「…………」
そこで目を逸らすのもなんだか嫌だったので、牧人は正面から受け止めた。
自然、見詰め合う形になる。
怯えたような表情だった。若干涙ぐんでいる。
「う……!」
――なんでお前がそんな顔するんだよ……っ!
やり場のない気持ちが生じたが、飲み込む。
深呼吸をする。冷静になろうと試みた。
ちなみに葦原牧人にはわかりやすい弱点があった。
それは、女の涙である。
男で得意な者などそういないだろうが、基本的に口下手な牧人はものすごく苦手だった。
一瞬でも目にしてしまうと、まるで自分が泣かせてしまったかのような罪悪感で身が凍りつく。
何も言えなくなる。何をしたらいいのかわからなくなるのだ。
「ああ、もう……!」
舌打ちをした。
「いいよ、お前の気持ちもわからなくはねぇし……、あんな状況でうまく立ち回れって方が無茶だ」
ぶっきらぼうに言った。
「……マキくん」
「……………………」
最初に感じていた怒りなど、既にどこかに失せている。
確かに、薫の心情は理解できる。感覚としては先の自分と似たようなものだろう。理不尽な状況におけるやり場のない感情。
それに、あの孤軍奮闘はあまりに過酷な状況だった。そんな状況で知り合いがいたら、迷わず頼りたくもなるだろう。
「じ、じゃあ……一緒に学級委員、やってくれるの……?」
「今更断れるかよ。いいよ、別に」
不安げだった薫の表情が見る見る晴れやかになっていく。
「ありがとう、ホントにありがとう……!」
「っ……!」
いたいけな少女が自分に安堵の表情を向けてくる。
青少年的にはなかなか威力のあるシチュエーションだ。
――なんか……照れる……。
思わず赤面しそうになるのを、牧人は意思の力で誤魔化す。
「……い、言っとくけど、俺は全然役に立たねぇからな。あんまアテにすんじゃねぇぞ」
牧人はとりあえずツンケンした。
「ううん。一緒にやってくれるだけで嬉しいよ。がんばろうね、マキくん」
しかし薫は微笑んだ。
「…………」
無垢な笑顔を向けられて、また言葉に詰まる。
――こいつ、どうすりゃいいんだよ……。
反応に困った。どんな顔をすればいいのかわからない。
そんなことを言われると、自分の発言が酷く卑屈でいじけたものに聞こえてしまうのが牧人である。
なんだか面倒臭くなった。
しかし、同時に妙な気分だった。
……胸の奥が、もやもやする。
――くそぅ……やっぱ苦手だ、こいつ。
とりあえず、そういうことにしておいた。
こうして、葦原牧人と藤宮薫の関係性が生まれた。
03
――ばし!
そんな音と頭部に加わる衝撃で目が覚めた。
「ん……」
机に突っ伏していた体を起こす。
「おはよう、マキくん」
顔を上げると、恐い顔をした藤宮薫が見下ろしていた。
「ん、藤宮……あれ?」
眠い目を擦りながら、現状を把握。
ここは教室ではない。
四角形に並べられた長机とホワイトボード。
どこか会議場めいたその部屋は、学級委員の集会が行われる特別教室だ。
水曜日、放課後。
その時間には全委員会が特定の場所に集合し、報告会のようなものが行われる。
今日はその水曜日。そして壁の時計はそれが終了した時間を示している。
「もーっ、ようやく今日は顔出してくれたと思ったらまた居眠りしてた! 怒られるのはわたしなんだからね!」
「ん? あぁ……そうか」
「そうか、じゃないよ! しっかりしてよマキくん……」
がっくりとうなだれる薫を尻目に、牧人は伸びをした。
今日の委員会も熟睡だったらしい。
五月下旬。
ゴールデンウィークも過ぎ去り、一学期も中盤に差し掛かっている。
……牧人は五月病だった。
それも、かなり重度の。
――やる気しねぇ……。
そんな日々なのだった。
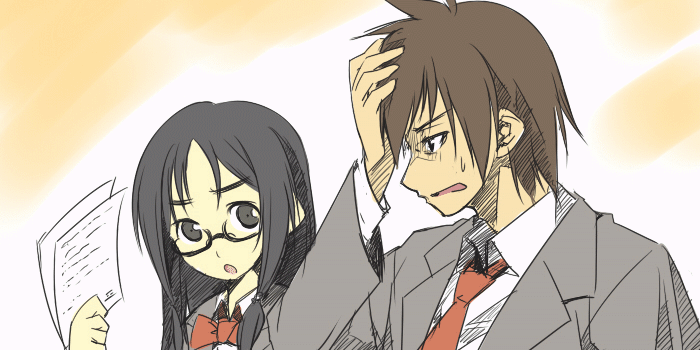
「はい。これ今日配られたプリント、ちゃんと見ておいてよ!」
「あぁ、うん」
「ホントにもぉ……大丈夫なの? 具合悪い?」
「……いや、平気」
まだ眠い頭でプリントを流し見た。
何も頭に入って来ない。
牧人はクラスの副委員長である。
この時期、学内は来たる六月の体育祭に向けて忙しげに動き回っている。
各クラスを取りまとめる学級委員も、特別種目の出場選手を体育委員会に報告するなどの各種事務作業に追われ、何かとせわしなかった。
しかし、そんな中で牧人は委員会をサボりがちだった。
理由は……、特にない。なんとなくやる気がしなかったのだ。
「ほら、行くよ」
「どこに?」
「体育教官室! クラス対抗リレーの出場選手表、提出しなきゃいけないんだから」
「かったりぃなぁ……、藤宮一人で行けばいいんじゃねぇの?」
「駄目に決まってるでしょーっ!」
吠えられては牧人も立ち上がるしかない。
薫に引き立てられるようにして、渋々後をついていく。
実を言うと、クラス対抗リレー出場選手表の存在すら今知ったほどだ。
完全にやる気が欠如していた。抜け殻のような牧人である。
「大体マキくん、先週だってふらっといなくなっちゃってたじゃない!」
「…………」
「それで太田先生に叱られたっていうのに……ちょっと、聞いてるの!?」
「あーもう、うっせぇなぁ! 聞いてるよ!!」
「聞いてるなら返事してよ!」
逆ギレ牧人にも薫は気丈に言い返す。
「はいはい、わかりました。悪かったよ! 来週は寝ねぇから、もういいだろ!?」
「もぉ……」
不満そうに頬を膨らませる。
気付けば、ここ最近そんな顔をさせてばかりだった。
毎度毎度サボタージュを決め込む牧人に対しても、薫はこのように話しかけてきた。
――藤宮って、意外に口うるさいヤツだよな……。
真面目な性格なのは初見で理解していたが、こうも鬱陶しいとは思わなかった。ため息をつきたくなる。
ならば牧人も怠けたりせず委員会に参加すればいいという話になるのだが、それはそれで面倒だった。
共に仕事をこなすようになって早二ヶ月弱。
牧人としては一方的に構ってくる薫に対して、もう特に思うこともなくなっていた。
――なんか、もっと大人しいヤツだと思ってたのに……。
かつて一緒に学級委員をやることになった時のあのいじらしい彼女は何かの間違いだったのだろうか。
――女って……意味わからんな……。
そんな都合のいい疑問を抱いたりもする。
「……最初の頃はまだやる気があったのに、最近のマキくんはどうしちゃったの?」
「そんなことねぇよ。俺は最初から副委員長なんてだるい仕事やりたくなかった」
「――またそうやって意地張って」
「張ってねぇし。俺がやる気ねぇの藤宮は知ってるだろ」
本音を言うと、学級委員の仕事はそこまで苦痛でもない。
ただ、真面目に仕事をするのが何だか納得がいかなかっただけで。
葦原牧人は強制を嫌う。抑圧されればとりあえず反発したくなる。
それが彼なりの個性の主張でもあったからだ。
……客観的に見れば、やや形骸化している感はあったが。
「そんな……こと――マキくんは……」
薫は不満そうだった。そうではないとでも言いたげだ。
一応二人は同じ中学校の出身だったが、大した交流もない。少なくとも牧人はそう認識している。
そんな相手に、訳知り顔で自分のことなど語られたくはなかった。
ただでさえ付き纏われるのも鬱陶しいというのに。
「……てゆうか、お前もなんで俺なんか推薦したんだ? 明彦でもいいじゃねぇか」
「明彦って……武田くん? どうして?」
「どうしてって……、明彦も同じ中学だっただろ」
「えっと……」
薫は気まずそうに目線を泳がせる。
――なんだよ、知らなかったのかよ……。
牧人はわけもなく明彦のことが恨めしくなった。
最初――牧人がまだ少しはやる気があった頃は、真剣で頑張り屋な彼女に感心したりもした。だが、慣れてくるとそんな気も起こらなくなる。
今では、薫があれこれ言ってくるのを牧人が文句を垂れつつ聞き流すのが日常になってきている。
生真面目で口やかましい彼女はらしいと言えばらしいが、それを一身に受ける牧人としては面倒でしかない。
「あ、委員長お疲れー」
「おい葦原、あんまり委員長に苦労かけんなよー」
通りすがりのクラスメイトがそんな言葉をかけてくる。
薫はそれに笑顔で対応していたが、
「うっせぇなぁ……」
牧人はだるそうにそっぽを向くだけだった。
実際問題として、牧人がいてもいなくても大して問題がないというのもやる気が出ない大きな理由だった。
クラスの議事運営や集会時の報告に関しても、薫一人でも全て上手にこなしてしまう。
牧人はそれを隣で眺めていることがほとんどだった。時々手伝ったりもしたが、正直いてもいなくても変わりない。
委員長・藤宮薫としての能力はクラスでも高く評価されている。
先程のように、クラスメイトからは“委員長”と呼ばれて信頼されている。
「マキくん、そんなこと言ったら駄目だよ。応援してくれてるんだから」
「そうだな。藤宮は……“委員長”は前向きだな」
露骨な皮肉を込めるように敢えてそのような呼び方をした。
「…………」
……信頼の厚い薫に対して、牧人は相変らず微妙なポジションを保っていた。
委員長・薫の仕事を流れで手伝っている、やる気のない男子生徒――そんなところだ。
その状況が気に入らないというほどではないが、なんとなく疎外感のようなものを感じてはいた。
やる気も出なくなる。
「マキくん」
不意に呼ばれる。
今や彼女専用となったその名前で。
「わたしは、マキくんのこと……頼りにしてるんだよ?」
「…………」
――なんで突然そんなこと……?
怪訝な顔をする牧人。
「…………そうかよ」
とりあえず、また曖昧に返事をした。
――そんなこと言われたって、困るんだよ……。
頼りにされたって、どうせ何もできない。
何もできないのなら、何もしなくてもいいじゃないか。
「………………」
そう思いつつも、薫の反応を想像すると口には出せない。
こんなにも気怠い、五月の午後だったからだ。
やる気が出ないのだ。
■■■■■■■■■
自宅。
「だりぃ……」
牧人はギターを外し、スタンドに置いた。
ジャックは最初から刺さっていない。アンプに繋がずに弾いていたのだ。
「………………」
床に寝転がる。
ここ最近、日課となっていたギターの練習はおざなりになりつつあった。
やる気がしないのである。
このところ、牧人が無気力になってしまっているのには理由があった。
五月病とは解り易い隠れ蓑でしかない。
実際のところ、彼は目標を見失っていたのである。
元々、牧人は高校に入学したらバンドを組むつもりでいた。
中学の頃から練習してきたギターもかなり上達した。これならば人前に出て恥をかくようなこともないだろうと思うことができた。
軽音楽部に入部し、そこで音楽的に趣味の合う友人を作って、ライブハウスなどでカッコよく演奏したいと考えていたのである。
大勢のオーディエンスが浴びせる嵐のような声援、ステージ上からの眺め。
かつて憧れたその場所へ、ようやく自分も踏み出すことができる。
入学してから、意味不明な理由で副委員長にされてしまったりしたものの、その気持ちは変わっていなかった。
だから、部活動が開始されたその日に軽音楽部の部室を見学に行った。
かねてから決めていた本格的なバンド活動である。
期待と不安が入り混じり、心地よい高揚をもたらしていた。
足取り軽くやって来た軽音楽部部室。
……廃部になっていた。
軽音楽部は、昨年で最後の部員だった生徒たちが卒業してしまい、活動を無期限で停止していたのである。
偶然その場を通りかかった吹奏楽部顧問の教師がそう教えてくれた。
室内を覗く。当然、楽器の類も撤去されて何も置かれていない。
掃除もされていない、埃を被った廃屋のような部屋。
隣は吹奏楽部の部室だ。薄い壁越しに、微かな音が聞こえてくる。
……いたたまれなくなって、すぐに出た。
場に拒絶されているような気分だった。
もうこの部屋で音楽を奏でることが不躾になるかのような、妙なよそよそしさを感じた。
錯覚だろう。
だが、事実ここには誰もいない。
廊下に佇んで、愕然としていた。
しばらく何をしたらいいのかわからなかった。
……強烈な肩透かしを喰らわせられた。
立てなくなるほどに。
それ以降も牧人はバンドを組む方法がないかを考えた。
音楽が好きそうなクラスメイトは何人かいたが、実際に演奏をする者はいなかった。
興味はあるようだった。興味はあるが、踏み込めない様子。
……それは、以前の自分を見るようだった。
誘う気になれなかった。
それ以前に、牧人はそのような突っ込んだ話ができるほど繋がりの深いクラスメイトがいない。
学期初めに副委員長にされて以来、なんとなく他のクラスメイトとの間に溝ができてしまった気がする。
嫌われているとまでは言わないが、仲良くなるタイミングを逸した感は否めなかった。
溶け込み損なった少年は、攻撃の対象にはならないまでも、少し浮いた存在に変わる。
だからクラスでは、牧人に自分の趣味を持ち出す余裕はなかった。
集団の空気を探るのに手一杯だったからだ。
そんなことをしているうちに、なんだかだんだんやる気が失せていった。
現状を作り出した一因に薫の存在がなかったとは言えないが、それをどうこう言うのももう面倒だった。
「………………」
そして、一ヶ月近くが経つ。
ギターの練習は続けている。しかし、前ほど熱心にはやらなくなった。
今日のように繋がずに弾くことも多い。中学の頃にはあり得ない。
息切れしていくのを感じた。
体が帯びていた熱が徐々に冷めていくような、嫌な感覚。
「――なに、やってんだろな……俺……」
天井を見上げながらぼやく。
ここ最近、どうもつまらなかった。
学校はあまり楽しくない。
クラスの居心地は悪くはないが、あまり居場所がないような感じがする。
明彦や薫など、話をするクラスメイトはいる。
そういう時は少し楽しい。しかし、どこか満たされない。
一人で弾くギターも面白くない。
……何から何まで、やる気がない。
――このまま、ぼんやりと世界に溶け込んでしまう……。
中学時代に恐れていた、集団に没する感覚がここ最近常にあった。
個性を殺し、クラスメイトに話を合わせる……虚構のような自分。
しかし、以前ほど気味悪く感じない。
無個性な青少年の一人になるのは確かに嫌だしつまらない。
だが、それを回避するために何か行動を起こす気にもなれない。
――てゆうか……何かするにしても、俺は何をすりゃいいんだろう……?
空気が水のように感じる。
……重く苦しく、沈んでいく。
寄る辺を失くした少年は、流木のようにただたゆたっていた。
大切な何かがあって、心地よい場所があって、なりたい自分があって。
そうした色々を全て満足のいく形で得ようとした。
無理に多角的に順応しようとすることがいけなかったのか。
牧人は思い悩む。
……どこかで間違えたのだろうか。
高校という新たな環境。
その高次に濃縮された空間の中で、若者は自己を喪失していくのか。
……アイデンティティの喪失。
以前から各メディアにて目にしてきた言葉だ。
まさか自分がそれを感じることになるとは。
最も、思春期とは、そんなものなのかもしれない。
明確な自己の獲得に憧れつつも、日々の生活に順応していく中でそれらは希釈され、曖昧になっていく。
そんな年代。
………………玉虫色の時期だった。
「あーぁ……」
その真っ只中の少年は、絶息する魚のように呻いた。
今はただ、空気が海水のように重い。
一週間後、牧人は委員会をサボった。
……その間、牧人がギターを弾く事はなかった。
【戻る】