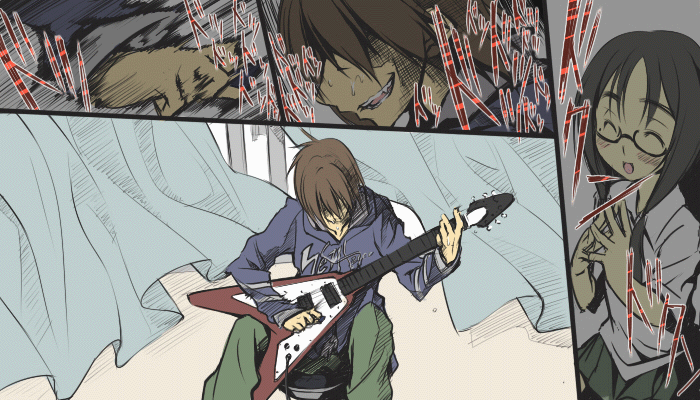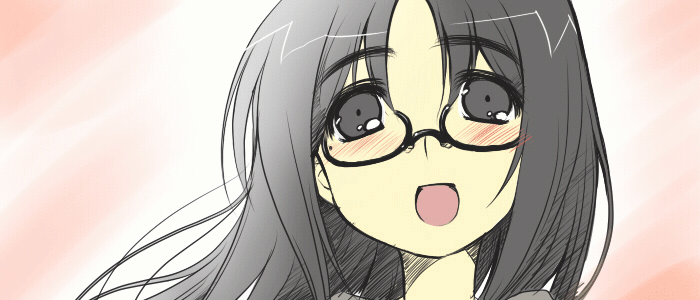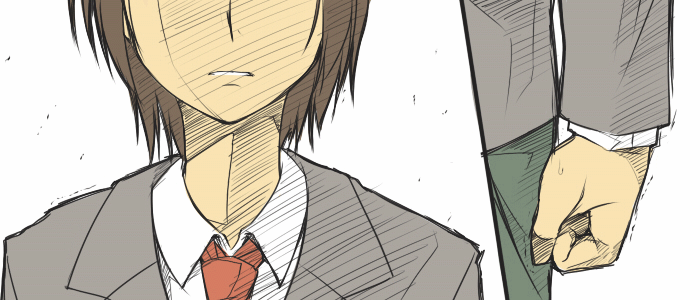幸福のエッセンス
00
葦原牧人は藤宮薫について思うところが色々あった。
一言で言ってしまうと苦手である。
苦手意識にもいろいろな種類がある。
感覚に根ざした性質の好き嫌い。性格上の不和。生理的な嫌悪感。
対人関係における悪感情は様々な原因から生じるものだ。
牧人が薫に抱くそれは、苛立ちを感じるレベルのものである。軽度なものだ。
苛立ち――それが生じる理由は実にシンプルだ。上手くいかないと生じるのである。
そして、それらは発散させることが難しい。やり場のない怒りと言える。
……上手くいかない。
日々の活動の随所に現れるその感覚。
多くの場合、それらは自分の意思と異なる行動を強いられる際に強く現出する。
葦原牧人は強制を嫌う。とにかく反発心が強い。
好きでもないことをやらされるのは嫌なもの。
世の人全てが抱くそうした感覚を、一際強く抱いているのが牧人だ。
彼がそうした類の束縛を嫌う理由は家庭環境による部分が大きい
優秀な両親の期待を受け、厳しい教育の下、育ってきた牧人。
幼少から様々な理由でさぞ口うるさく注意や指導を受けてきたことだろう。
幼子にとって親とは神にも等しい存在である。
抵抗の術など知らず、ただ愚直に従う以外の姿を子供たちは知らない。
しかし、自我意識の発達と共に子供は逆らう方法を覚え、それらを盛んに実行しようとする。
いわゆる、反抗期だ。青春期に現れるものは特に第二反抗期と呼ばれる。
牧人は反抗期と言えた。
両親の数々の要求に応ずることをしなくなったのだ。
小学校高学年辺りからそれが始まり、今なおそれが続いている。
それに伴い、彼は自分の行動に横からけちをつけられることを極端に嫌がるようになった。
然るに、同様の理由から藤宮薫の存在は牧人にとってとても面倒なのだった。
彼女は規律を重視する。
助言をする。忠告をする。注意をする。意見をする。
それら言辞は一般社会における正論であり、明確な基準線として常に妥当である。
しかし、牧人のように諸所の理由から規律を蔑視する人間にとって、それらは“口うるさい”ものでしかない。そうした層と議論を交わす際には、薫の述べる規律は効果が薄い。
……念のために付言すると、薫は何もそこまで潔癖な人間というわけでもない。
彼女は典型的な“良い子”なだけである。無意味なルール違反を好まないだけだ。
周囲から不快感を持たれるほど声を大にして公序良俗を振りかざすわけではない。
ドロップアウトを根拠無く忌避するのは人として健全な感覚であり、薫の規律は見ている分にはむしろ心地よい。
共感できる。牧人のような人間を除いては。
しかし、完全な規律は世界を明確にする。
簡単に言うと、規則があれば身の振り方がわかりやすくなる。
確かに過度なルール設定は面倒だ。牧人のように反発もしたくなる。
だが、横から色々と口出しをされるのは面倒であるが、それが何もない状況というのもまた不安定で落ち着かないものだ。
ルールは時に防壁としても機能する。
それを律儀に守れば、とりあえずある程度の結果が推察できる。
それが健全なものであればあるほど、それだけ性質の安全性を主張になる――要するに、いわゆる“良い子”は周囲から好感を持たれる。薫などそれのいい例だ。
そうして見れば、ルールの遵守は面倒なようで気楽なのだ。
社会のルールやモラルを念頭に行動すれば、その中で生きていくことが保障される。
時に厳し過ぎる方向性は“人生のレール”などと揶揄されるが、レールがあるから電車は走れるとも言えるだろう。
反抗少年の牧人にとってもそれは変わらない。
ここ最近でこそ抵抗の意を示しているものの、彼は人生の大半をルールに縛られて生きてきた。
牧人にとっては、ルールを設定してくれる存在というものは難儀なものでありながらも、わかりやすい基準を提示してくれるものでもある。
不確定なあるべき姿を示し、自分の行動がどの程度の位置にあるのか確認をさせてくれるありがたい存在なのだ。
……ありがたい。
それは、庇護者に対する親愛の念と同じだ。
守ってくれて、支えてくれて、嬉しい。
安心感を提供してくれて、ありがとう。
…………甘えたくなる。
牧人は安心するのは嫌いだった。
安心してしまうと、緊張感のない無様な自分が曝け出されてしまう。
それは、カッコ悪い。
そのような理由から、
葦原牧人は藤宮薫が苦手だった。
――あーぁ……、今日も藤宮と委員会か、面倒臭ぇ……。
ただ、彼は気付かない。
そうした解り易い束縛への嫌悪を表明することで、心中で抱く薫への親愛には。
01
葦原牧人、高校一年。
とりわけ何も起こらないまま、牧人は夏休みを終えた。
高校生の夏期休暇ともなれば、友人や恋人と解放感を分かち合い、より親睦を深める絶好の機会だろう。
しかし、牧人に恋人はいない。
休日遊びに出るような友人もほぼゼロだ。
よくつるむ武田明彦は、あまりアウトドアな人間ではない。誘えばついてくるのだろうが、旅行などに大して興味もなさそうだと牧人は思う。
……それ以前に、明彦と二人でどこかを旅するなど牧人の方から願い下げだっただろう。
したがって、牧人の夏はひたすら続く週末のような日々だった。
言わば毎日が日曜日。
朝は存分に惰眠を貪り、昼は自宅で漫画や雑誌を読み耽った。
飽きれば外出して服屋やCDショップを巡った。牧人はそうした店が好きだ。
牧人は自分の服装のセンスや好きな音楽を、人に説明できるレベルまで明確に定めている。
そうして確固たる趣味の方向性を持つことは、確固たる自我を持っているかのようで心地よいからだ。
音楽や本のジャンルに関して他者と語り合いたい欲求もないではなかった。
しかしそんな相手もいない。だからいつかそんな日が来てもいいように、彼は自分を磨いている。
そうして……、特別するべきこともなく、日々が無為に過ぎて行った。
山のような宿題は最後の一週間でやり終えた。能力的にはそれなりの牧人だ。追い詰められればやることはやる。
そして、ギターはしばらく触っていなかった。
■■■■■■■■■
「おい、そこのお前」
「……ん?」
そして新学期。
牧人は、相変らず気怠げに日々を過ごしていた。
「これとこれ、藤宮に渡しておいてくれよ」
「……?」
いきなり、廊下で見知らぬ男子生徒に話しかけられた。
不躾な態度で声をかけられ、そのまま何枚かプリントを手渡される。
「……てゆうか、お前誰だよ?」
馴れ馴れしい人間は嫌う牧人だ。口調にも警戒心が滲む。
「いつもサボってばっかだから人の顔と名前が覚えられねえのよ」
だが、相手の反応は悠然としたものだ。
その妙に落ち着いた態度が牧人は鼻に付いた。
「なんだと……?」
そうして詰め寄りかける牧人を、男子生徒は手で制す。
「オレは棗耕平。隣のクラスの委員長閣下様だ」
洒落たデザインの眼鏡をかけたその男子生徒は、豪放な口調でそう名乗った。
不敵ににやつく口元には明らかな余裕が見て取れる。
「棗、耕平……?」
その名前と顔には、そういえば覚えがあった。
彼は週に一度の学級委員の集まりで、自分のすぐ近くに座っている。
――隣のクラスの、委員長……?
錆付いた情報だった。すぐに思い出せないのは更新作業の不備――委員会への度重なる不参加が原因だ。
「それ、この間の委員会で藤宮が忘れていったんだよ。今日のホームルームでないと困るから、渡しておいてくれ」
「あ、あぁ……」
遊び人のような見た目とは対照的な、てきぱきとした棗耕平の口調に流されるように肯いてしまう牧人。
受け取ったプリントに何気なく目を落とすと、文化祭の運営要綱が書かれたものであることがわかる。
――そうか、もうすぐ文化祭なのか……。
すっかり忘れていた。
「しっかりしとくれよ少年。文化祭がちゃんとするかどうかはオレらみたいな各クラスの委員長様の仕事っぷりにかかってるんだからよ」
心中を読んだようなその苦言に、牧人は感情を刺激される。
「……お前に言われなくたってわかってるさ」
睨みつけるようにしてそう言った。
「なら藤宮にもあんま苦労かけさせんなや。いつも一人で作業してて大変そうだぜ、彼女」
しかし、耕平は薄笑いを浮かべるばかりだ。まるで効いていない。
「………………」
「んじゃ、また委員会で会おうぜ」
棗耕平は牧人の前から立ち去った。最後までにやついた表情を崩さないままに。
その人を食ったような態度が牧人は気に食わない。
――ヘラヘラしやがって、癪に障るヤツ……。
最後の言葉も、挑発の一種に聞こえた。
「ふん……」
見下すように鼻を鳴らす。
「………………」
見れば、掴んでいたプリントがくしゃくしゃになっていた。
――藤宮、一人で大変なのかな……。
とりあえずそれは少しだけ気がかりだった。
――そういえば……さっきのあいつ……、
しわくちゃになったプリントを直しながらふと思う。
自分のクラスの委員長のことを“藤宮”と呼んでいる人間を、自分以外に初めて見たな、と。
「………………………………」
葦原牧人は、棗耕平が嫌いになった。
02
そして一週間ほど経ったその日。
牧人はまたしても委員会をサボっていた。
「………………」
自室にて、牧人はごろごろしていた。
熟読するでもなく雑誌の文面を目で追っている。
このごろ、牧人は無趣味になってきていた。
何もしていない時間が増えてきている。
日常的な読書や音楽鑑賞につけても、いまいち没入し切れておらず、今日のようにただそうしているだけの有様だ。
以前あれだけ情熱を持っていたギターも今では久しく触れていない。
やる気が出ないという感覚すら懐かしい。
今や出す方法も忘れてしまったかのように、彼は空虚に酸素を吸っていた。
――ピンポーン。
「……ん…………?」
だからこの日、そうして来訪があった時、牧人は目が覚めるような気分だった。
実際に眠ってはいなかったが、混濁した意識を取り戻す感覚は似たようなものだ。
――宅配便か……?
多忙な牧人の両親は通信販売をよく利用する。
そうした商品は平日の昼に配達されてくるため、受け取るのは専ら牧人の仕事だった。
牧人は両親と仲が悪い。
うるさい両親のために何かする気にはなれないのだが、無視した理由を問い詰められるのはもっと面倒だった。
牧人はやむなく床から起き上がる。
しかし気が緩んでいた。
「あ、こんにちはマキくん」
「…………………………」
だから、来訪したのが藤宮薫だと理解した瞬間、牧人の頭脳は緊急停止した。
――…………え? え?
言葉にもならないテンパり具合。
「突然お邪魔してごめんね、どうしてもすぐに連絡しないといけないことがあったから」
フリーズ状態からの復帰に忙しい牧人の内情などまるで解さず、薫は話を始める。
「れ、連絡……?」
「今日、委員会で出た話。マキくんにも知っておいてもらわないといけなくて」
――ま、まあ、藤宮から俺に持ってくる話なんてそんなもんか……。
いつものことだ。
そう納得して、余裕を持とうとする牧人。
「そんなの……明日学校であった時でもいいじゃん」
「駄目だよ。今日のうちに知っておいて欲しいことなんだから」
真剣な口調で薫は言う。
それは牧人が苦手な瞬間だ。
「にしたって何も直接来なくたって……、ケータイとかに連絡してくれれば……」
「だってわたし、マキくんの番号とか知らないし……」
「あ……」
そういえば教えていなかった。
一緒に委員をやっているとは思えないほど疎通の悪い二人。
「まぁ……、とりあえず入れよ。せっかく来たんだし、茶の一杯でも出すよ」
「あ、うん、ごめんね。お邪魔しまーす」
さすがの牧人でもここまで来られて追い返すほど社会性のないことはしない。
どこか降伏めいてはいたが、とるべき態度は弁えている。
薫も慎ましい性格だが過度な遠慮はしないタイプだ。
こういうところでは素直に相手の厚意を受け取る。それが牧人のような社交辞令であっても。
「……そういえば藤宮って、なんで俺の家知ってんの?」
「武田くんに聞いたら教えてくれたの。結構近所なんだね、わたしたち」
「あの野郎……」
「え?」
――勝手なことしやがって……明日会ったら絶対なんか言ってやる。
馴染みの知り合いには強気な牧人だった。
■■■■■■■■■
「ここ、俺の部屋」
無愛想な人間というものは、名詞で会話を行おうとする。
「失礼しまーす……」
男の部屋に入ることなど初めてなのだろう。少し緊張した様子で部屋に入る薫。
「へえ……ここがマキくんの部屋なんだ……」
「あんまキョロキョロすんなよ」
「いいじゃない。ちょっと散らかってるね」
「…………」
なんとも居心地が悪い。自分の恥部でも見られているような気分だった。
「飲み物でも出すよ。麦茶でいいか?」
「あ、うん、ありがとう」
そそくさと自室から出た。
――なんで俺が追い出されてるんだよ……。
そこで逃げたとは思わないのが牧人だ。
戻ってくると、床に散らばっていた雑誌類がひとまとめにされていた。
「…………」
中学時代、自室に鍵を取り付けて両親の出入りを禁じてからというもの、牧人は部屋を勝手に整理されたことなどなかった。
だから、それはなんとなく懐かしい感覚だった。
……不思議と、あまり鬱陶しいとは思わなかった。
冷えた麦茶を飲みつつ一呼吸を置いてから、薫は鞄を開く。
「マキくんまた委員会サボるんだから……、もううるさく言っても意味ないから半分諦めてるけど」
ふて腐れるようにそう言って、鞄からプリントを何枚か取り出す。
「はい、これ。今日、文化祭の準備でそれぞれのクラスの委員が担当する仕事が決まったから連絡しないといけなくて。わたしたちは廊下の掲示の貼り替えが担当になったから」
「……あぁ」
――そういや文化祭近いんだっけ……。
また忘れていた。
どこか呆然とする牧人の手に、ばさばさとプリントが手渡される。
「もう明日から準備期間だから放課後はこの仕事だよ。いつもの委員会と違ってサボっちゃ駄目だからね」
「んー……」
「マキくん! わかったの!?」
「わかってるよ……」
そうやって強く言われれば、日頃だらけている牧人はもう肯くしかない。
最早年貢の納め時のようだった。
――藤宮にもあんま苦労かけさせんなや。
先日の棗耕平とのやり取りが思い出されてなんとなく腹立たしかった。
どの道、文化祭の準備が始まってしまえばクラスや部活動の出し物の手伝いなどで早く下校するのは不可能になる。ほぼ全ての生徒が学校に居残ることになるからだ。
牧人のクラスの出し物は手打ちそば屋だ。麺まで自分たちで作ってしまおうとする辺り、高校生の文化祭にありがちなどことなく無茶な空気が滲み出ている。
家庭科室で調理を行い、教室で配膳をする。
明日からは文化祭実行委員の指揮の下、カウンターや照明などの内装や飾り付けの製作が行われるようになる。
クラスでそば屋の内装作りをするのも、薫と掲示板のポスターを貼りかえるのも、どちらも大変さの具合では似たようなものだろう。
――どっちかって言うと……、
どちらかと言えば、割に気心が知れた薫が一緒の後者の方が楽ではある。
「………………」
自身の感覚に牧人はどことなく納得がいかないところがあったようだが、まあ、それはいいとしよう。
「…………」
「…………」
言うべき連絡事項を済ませてしまうと、急に会話が途切れた。
――そういや、藤宮と委員会以外の話なんてしたことねぇな……。
会話をしようにも糸口が掴めない。
「ねえ、マキくん」
「ん?」
薫から声がかけられ、応ずる。
「マキくんって、ギター弾くの?」
「え?」
彼女が部屋の隅を指差したのを見て、牧人は言葉に詰まった。
そこには長らくスタンドに立て掛けられたままのギターがある。
「ま、まぁな……趣味で、少し……」
「へえ、そうなんだ。マキくん、そういうの好きそうだよね」
「そ、そうか?」
「うん。似合ってる」
笑む薫。
「……っ」
焦る牧人。
最初はそのような言葉が欲しくて、牧人はギターをはじめたようなものだからだ。
「ね、それってエレキギター、だよね?」
「ああ……、そうだよ」
嬉しかったが、表情に出ないように頑張った。
「エレキギターって、やっぱりああいうすごく大きい音が出るんでしょ?」
「うん……まぁ」
薫の言う“ああいう”がどのようなものかはわからなかったが、いわゆるディストーションのことを示しているのだと思った。
「エフェクターに繋がなければ、別にうるさくしないこともできるけどな」
「あ、そうなんだ。エレキギターって最初からあんな音の楽器なのかと思ってた」
「そんなことはねぇよ。色々いじれば幅広い音色が出せるもんなんだ」
経験者だけにそこそこは語れる牧人だ。ここぞとばかりに流暢になる。
薫はそんな牧人の話に興味深そうに肯いている。聞き上手な少女である。
「ねえ、ちょっと聞かせてくれない?」
「聞く……って、何を?」
「そのギターの音色。実際にどんな音がするのか聞いてみたいな」
「なら鳴らしてみろよ、繋ぐから」
「違うよ、別に弾いてみたいんじゃなくて――」
薫は真っ直ぐな目を向けて、
「――マキくんが弾いてるところを見てみたいの」
そんなことを言う。
「え、俺……?」
面食らう。
「うん。弾けるんでしょ?」
「え、えっと……」
また閉口。
弾けるか弾けないかで言えば、弾けるということになるのだろう。
中学生の頃から練習してきただけあり、人に聞かせられる程度には上達している。
ここ最近は弾いていないから多少なまってはいるだろうが、聞くに耐えないほどではないはずだ。
「……で、でもヘタクソだぜ? 聞いたってあんま面白くねぇよ」
「そんなの聞いてみないとわかんないよ」
牧人は渋ってみるが、薫は気にしない様子だ。
「……それに、藤宮が好きそうな曲もわかんないし」
「気にしないでいいよ。マキくんの好きな曲でいいから」
「……っ、……」
内心、嬉しかった。
誰かに実力を期待されるというのは、何事においても嬉しいものだ。
牧人はおだてる言葉に弱い。とにかく弱い。
ええかっこしいの少年は、その効果が出ることがとりあえず喜ばしい。
しかもそれが薫のように裏表のない反応だと、もう小躍りすらしたくなる。
「どうしても嫌だって言うなら、別にいいけど……」
「仕方ねぇな」
果たして牧人はこの時口元に浮かぶ笑みを隠せていただろうか。
シールドを繋ぎ、アンプに電源を入れる。
エフェクターを挟もうか悩んで、先程の会話からなんとなく薫は歪んだ音を嫌いそうだと思ってやめた。
ギターを手に取り、弦に挟んだピックを抜く。
久方振りに手にしたギターはすっかり埃を被っていた。
「……ちょっと待っててくれ。チューニングするから」
「うん。なんか楽しみになってきたなぁ」
ギターを抱えて椅子に座る牧人の前に正座する薫。
――そ、そんな身構えるなよ……。
逆に緊張してしまいそうになる。
平静を装わなければ、と言い聞かせた。
――大丈夫だ。冷静に……。
「ねえ、なんでさっきから五弦ばっかり確認してるの?」
「あ、いや……なんでもねぇよ」
超緊張していた。
ピックを持つ手が震えている。
――なんだよ、俺……そんな、大したことじゃねぇだろ……。
薫に自分のギターを聞かせる。
それだけのことだというのに、失敗した時のことを考えると恐くてたまらない。
思えば、人に演奏を聞かせる事自体、今回が初だった。
その事実に、背筋を冷たい汗が流れ落ちる。
座っての演奏も慣れてきていたはずなのに、気づけば初めてギターに触った時のようなぎこちなさだ。
「じ、じゃあ……ディープ・パープルのハイウェイ・スターって曲をやるよ」
「うん」
律儀に曲名など宣言して、ネックを握った。
薫は拍手をしてくれるが、牧人は更に緊張してしまう。
「よし――」
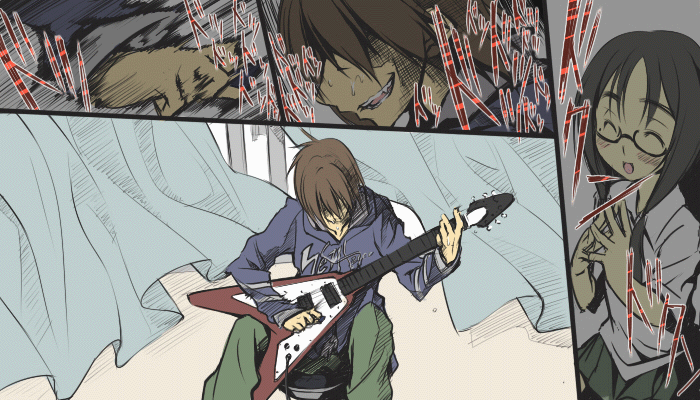
そして、演奏開始――――
曲の最後、
「……、あ……」
ビブラートをかけようとして失敗した。
変に間延びした音色が残響する。
「…………すまん」
何か言われる前に牧人は謝った。
そのぐらい、自分でも微妙な演奏だったからだ。
――マジかよ……、超下手になってるじゃねぇか、俺……。
凹んだ。
まさかここまで劣化しているとは思わなかった。
指が柔らかくなっていて、コードを押さえると痛んだ。
手が震えていて、ピックを何度も取り落としそうになった。
そんな状態のためストロークも酷く、和音も上手く鳴らなかった。
下手にエフェクトを切っていた所為で余計に和音の不出来が目立った。ディストーションをかけていれば、多少は誤魔化せていたものを。
――いや、そんなレベルじゃねぇ……。
一応、この曲は牧人が最初に覚えたものだった。従って、演奏した回数も多く、一番得意な曲でもあった。
難しいパートは簡略化することでスムーズに弾けるよう独自にアレンジを加えていた。テクニカルな部分も多く、見せ場も充分にある。
だというのにこの体たらく。
「…………」
穴を掘って入ってしまいたかった。
「……どう、だったよ?」
それでも評価を聞いてしまうのが牧人だ。
薫は優しいから、稚拙な演奏も笑って流してくれることを期待して――
しかし、
「なんか……、うーん……どうしよう……」
――な、悩まれた!?
牧人は珍しく心からダメージを受けた。
下手な希望を抱いていると、それが裏切られた時、痛手は更に甚大なものとなる。
「時々、鳴ってない弦があったりするよね。かき鳴らす時も微妙に手がぶれるし」
「う……!」
図星だった。自分でも一番気になっているところだった。
「指板の方ばっかり見てるから、なのかな……。でも時々運指も乱れるから、そっちでもたまに不協和音になるし……」
「く……!」
歯噛みした。
――この女……ギターのことなんか何もわかんないくせに……!
訳知り顔で辛辣な批評などして欲しくなかった。
……かといって安易な慰めの言葉など欲しくもなかったが。
牧人の中で実に格好悪い怒りが蓄積されていく。
「あ、あとコードの押さえ方も何箇所か不自然なところがあったよね……でも――」
「……ふじみ――」
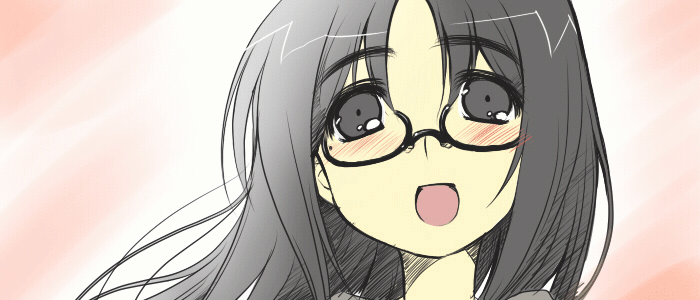
「――でもマキくん、かっこよかったよ」
「――――――」
名前も呼べなかった。
ただ、そう言った彼女の笑顔が眩しくて、喉元まで出ていた自分の言葉がいかに矮小で無様なものかを思い知らされたからだ。
だから飲み込んだ。必死に飲み込んだ。
そして、恥じ入るように目を伏せた。
地中より芽吹いた植物がまばゆい太陽の光に圧倒されるとしたら、果たしてこのような気分だろうか。
――かっこよかった。
その言葉が、今までずっと言われてみたかったその言葉が、無垢な笑顔と共に放たれる様は想像を絶する達成感と快さを牧人にもたらした。
「ふ、藤宮って、ギター詳しいのか?」
「そんなことないよ。お父さんがクラシックギターを持ってて、それを少し触ったことあるだけ。だから、あんまり偉そうなことは言えないね。ごめん、気に触った?」
「いや、いいよ……、その通りだったし。その……指摘ありがとよ」
完全に毒気を抜かれていた。実に牧人らしくない物言い。
「実は、ギター弾くの久しぶりなんだよ」
「え、そうだったの?」
気付けば臆面もなくそのようなことを口にしていた。
「また、練習すっかなぁ……」
「そうしなよ、せっかく弾けるんだから、もったいないよ!」
「……そ、そうか?」
何気なく言っただけなのに、妙に強い口調で肯定されてしまった。
――ホントに、またやろうかな……。
バンドを組む気はしなくなってしまった。だからもうギターを触っても意味がないと思っていた。
――けど、もし藤宮が……
藤宮薫がまたさっきのように笑ってくれるなら。
牧人は、それだけで生きていけるような気がした。
――ばっ、バカか俺……! 藤宮だぞっ、こんな地味な女に褒めてもらったって……!
何に対してか、心中で言い訳。
「練習して上手くなったら、また聞かせてくれる?」
「…………うん」
そう言って可憐に首を傾ける彼女に、向かい合う牧人は曖昧に下を向くだけだった。
――藤宮って、こうやって笑うと結構……、
押さえ込むようにギターを抱える。
Vシェイプのギターは直線的で抱き心地が悪かった。
「藤宮って、あんま眼鏡似合ってねぇよな」
「え……なんでいきなりそんなこと言うの?」
そっぽを向きつつそんなことを言った。
それは、下手すぎる照れ隠しだった。
03
それから数日間、牧人はどこか上の空だった。
「葦原……、おい葦原! 何ぼんやりしてるんだ!?」
「……はい?」
頭上からの怒鳴り声で、牧人は我に返る。
強面の体育教師がグラウンドに座る牧人を見下ろしていた。
「お前の番だぞ、早く準備をしろ」
「はぁ」
「何がはぁ、だ。話聞いてなかっただろうお前」
「いえ、大丈夫です」
牧人は立ち上がって、白線の前にしゃがみこんだ。
線に合わせて両手を地面につき、前後差をつけた両膝を曲げて力を込める――クラウチング・スタートの姿勢。
今は体育の授業中。種目は陸上競技だった。
百メートル走のタイムが計られる。
牧人の隣にホイッスルを手にした体育教師が立ち、コースの終わりに立った生徒がストップウォッチを構えた。
――だりぃな、サッサと走って終わらすか。
牧人は前方を向く。
砂漠のようなグラウンドの遠方で、同じクラスの女子の体育の授業が行われていた。
女子の授業も陸上競技、こちらはハードル競争のタイムを計っている。
この年代の男子ともなれば、女子の体操服姿に色々と愉快な反応をするもの。同じ空間での授業というだけあって、クラスの男子の注意はそちらに向きがちだ。
だが、牧人はそんな無様な姿は見せまいと心を強く保っていた。
「……!」
しかしこの時、偶然スタートラインに立つ彼女の姿を見つけてしまう。
否、実際は無意識の内に探していたのかも知れない。
――ピッ!
ホイッスルの音と共に駆け出す彼女。
妙にゆったりとした走り。どうやら第一ハードルを恐れて速度を控えめにしているようだ。
――バカか、あんなスピードじゃ跳べるものも跳べな――
「よーい……!」
牧人のすぐ隣で、強面の体育教員がホイッスルをくわえた。
しかし牧人の意識は今や第一ハードルに差し掛かろうとしている彼女にしか向いていない。
まるでなっちゃいない低速の助走の後、彼女――藤宮薫は跳躍し、
「きゃーっ!!?」
ハードルを乗り越えられず、頭から派手にズッ転んだ。
こちらまで聞こえて来るほどの悲鳴が上がり、クラスの女子が大変だとばかりに駆け寄っていた。状況を見ていた数名の男子の間にもざわめきが広がる。
保健委員と思しき生徒が薫の手を引いて、校舎の方へ連れていく。地面に顔をぶつけて鼻血を出したらしい。
……藤宮薫は、運動オンチのようだった。
「ったく、あの馬鹿、何やってんだか……」
その一部始終を見ていた牧人はぼんやりと呟いて――
――ごん!
「………………」
体育教師に頭を殴られた。
「お前が何やってんだ。俺がホイッスル吹いたの聞こえなかったのか?」
「…………」
――全然聞こえなかった。
気付けば牧人はクラウチング・スタートの姿勢のまま硬直していた。
背後のクラスメイトたちの間からくすくすと忍び笑いが聞こえる。
「……すんません。もう一回お願いします」
「ったく、女子の体育着に見惚れてンじゃねえぞ」
――うるせぇよハゲオヤジ。
からかう体育教師に心中で悪態を吐きながら、牧人は百メートルを十四秒で走った。
「牧人、さっき何見てたのー?」
授業後、明彦がそのように話しかけてきた。
普段どおりの呑気な口調に他意はない。
「なっ、なんでもねぇよ、学食行こうぜ!」
しかし牧人は、すたすたと歩き去る。
それは明らかに動揺している風だった。
牧人自身も、そのことに違和感を隠せずにいたのだ。
■■■■■■■■■
放課後。
ふと、黒板の日付を見た。
――そういや今日って……。
委員会の集まりがある日だ。
いつもサボっていたというのに、何故かこの日の牧人はそのことを覚えていた。
あと十分ほどで開始の時刻だ。
薫は既に牧人のことなど諦めているのか、一人で向かうつもりらしい。
「………………」
――もう来週には文化祭だもんな。
さすがにもう忘れていなかった。
無意味に周囲を気にしながら、牧人は薫の席に向かう。
「ふ、藤宮さ」
「……あ、マキくん。どうしたの?」
「今日、委員会だろ? 行こうぜ」
「え……?」
――って、これじゃなんか嫌味言ってるみたいじゃねぇか、俺?
言ってから心中で迷うのが牧人だ。
今までサボり続けていた牧人が、しれっと委員会に行こうなどという言葉をかける。
なんとも白々しい。怒られても仕方のないことを言ってしまったと少し後悔した。
「マキくん……、ちゃんと出てくれるの?」
しかし薫の反応は、見ている方が申し訳なくなるような晴れがましさである。
「いや、まぁ、うん……」
対する牧人は煮え切らない。
――藤宮って、何でこんな素直なんだろ……?
「あ、う……!」
その時、突然薫が顔を背けた。
口元を手で覆いながら、唾を飲むように呻く。
「ど、どうした藤宮!?」
焦った。
急に気分が悪くなったのかと心配する。
「……はなぢ」
「は?」
聞き取りが困難な声量で言う。
そしてふやけたような鼻声。
「ああ、さっきの体育でコケたヤツか……」
「ふぇ……、なんでマキくんが、それ知ってるの……」
牧人の方を向いた。涙目だった。
「あ、いや……、とりあえず、保健室……行く?」
気遣う牧人だが、薫は首を振る。
「へ、平気……。ちょっと遅れて行くから、マキくん先に行ってて」
「いや、でも……」
そしてデリカシーが足りない。
「いいから早く行ってよ! もう、わたし今すごく恥ずかしいんだよ……?」
「す、すまん! 先行ってる……」
薫からの恨みがましい視線を受けて、牧人はそそくさと教室を出た。
――鼻血出してるところなんか、見られたくねぇか……。
今更気付く。
少しむしゃくしゃした。
そして委員会が始まる。
開始数分前に薫は入室してきた。鼻血は止まったらしい。
牧人はあまり意識しないよう心がける。
「来週は文化祭です。皆さんも知っている通り、我々学級委員は生徒会役員の皆さんと協力して、全体の運営にあたります。今日は当日の流れについて説明します」
「………………」
久しぶりに参加した牧人は、話に全くついていけなかった。
顧問の教師や上級生があれこれと説明をする中、本日提出用の書類を書いている。
本来ならば既に書き終えているべきものだが、多忙なこの時期に一人で雑務をこなすには薫にも限界があったようだ。
彼女ばかりに仕事をやらせるのは悪いと引き受けた牧人だったが……、
「藤宮……ここの出展番号って、何書けばいいんだ?」
質問。小声で。
「この間渡したプリントに書いてあるから……それ見ればわかるよ」
解答。小声で。
「悪ぃ……俺、かえって足引っ張ってるよな」
「いいよ」
苦笑される。
しかし牧人はどこか心地よかった。
少し前の自分なら、そんなことは思わなかっただろうことに彼は気付かない。
今はただ、彼女との空気が面映い。
■■■■■■■■■
そして夜。
牧人は帰宅した。
委員会の後も文化祭の準備であちこち駆け回り、疲弊していた。
時計を見る。
両親が帰ってくるまで、恐らくあと一時間弱。
「…………」
牧人は決意するような面持ちで、自室のドアを開いた。
カバンを床に置き、制服のままギターの前に立つ。
――今日こそ、弾くか。
練習再開。
そのために必要なやる気のようなものが、本日ようやくフルチャージされた。
――もっと上手くなって、藤宮に聞かせてやるんだ。
そしてまた褒めてもらいたかった。
その思考はどこかカッコ悪いので、牧人は振り払うようにギターを手にする。
とりあえず弦を張り替え、布巾で埃を拭き取った。
改めてチューニングをし、ストラップを肩からかける。
「………………」
そして姿見の前に立つ。
久しぶりに見る、ギターを構えた自分だった。
「よし……」
なんだか、心が清らかだった。
初心――とでも言うべき心情か。長らく忘れていた感覚。
肩の重み。響く音色。
それまで澱んでいた部屋の空気が懐かしく心地良いものに塗りかえられていく。
そして、
「ぐあ……!」
前髪が目に入った時の痛み。
集中していると不意に訪れる、懐かしいその痛み。
「くっそぉ……」
傷ついた戦士のように必死に痛みに堪えながらも、牧人はよろよろと膝をつく。
コンタクト装着時に一度覚えた異物感は、それが除去されてからもしばらく続く。
ギターを抱えたまま、机の引き出しを漁る。
以前使っていたカチューシャがどこかにあったはずだ。
「あれ……? どこやっちまったのかな……」
しかし見つからない。
結局その日は、カチューシャを探している間に両親が帰ってきてしまった。
牧人がギターを弾くことに否定的な両親だ。
在宅中の練習はややこしいことになるのでやらない。
――くそぅ、明日こそは……!
変に規制されたことで、この日の牧人は逆に志向がそちらに向いた。
後日、牧人はカチューシャを改めて購入した。
「なんでまた買ってんだよ。馬鹿か俺……」
秋空を仰ぎつつぼやく。
だが、情熱は取り戻した。
牧人は再びギターを始めることにした。
04
多忙な日々は走るように過ぎ去る。
気付けば文化祭当日だった。
牧人は、学級委員として受付を担当していた。
来訪者はこの受付で、専用の用紙に名前や職業、来校の理由・目的などを記入することになっている。入校記録とアンケートを兼ねている手続きと言えた。
尤も、この受付というものも案内所のようなもので、来校者の中にも立ち寄らない人は多い。
記入してくれるのは多くは律儀な保護者たちで、卒業生たちや学校見学がてらにやって来た中学生たちは空気のように素通りしていく。
従って、暇な時間帯も多かった。
牧人はパイプ椅子にふんぞり返って、顧問の教師が差し入れてくれた飴を舐めていた。
――暇だなぁ……。
「マキくん、もっとちゃんとしてないと、先生来たら怒られるよ」
「あー、へいへい」
隣に座る薫に注意されて、居住まいを正す。
この受付は各学級の委員が交替で担当することになっている。
当然その時間帯は束縛されることになる。
そのため、前日に行われた学級委員全員の意見を汲んでのシフト製作は難航した。演劇やコンサートなど、時間が決まっている物を見たいと主張する生徒たちの熾烈なぶつかり合いだった。
特に見たいものもない牧人としては、そのような無意味な議論をただぼんやり聞いているだけだったが。
――この後、どうすっかなぁ……。
牧人と薫の担当時間はもうすぐ終了だった。
クラスの出し物である手打ちそば屋の仕事は、学級委員の仕事がない翌日にしてもらったため、今日これからは半日ほど暇になる。
文化祭開催中は毎日最後に報告会のようなものが行われ、その日の来校傾向やアンケートの暫定結果が発表される。学級委員はそれに参加しなければならないため、仕事が終わったからといって帰れない。
――面倒臭ぇなぁ……。
それを思うと、牧人の労働意欲は見る見る萎えていくのだった。
「マキくんは、この後どうするの?」
「ん?」
ぼんやり人波を眺めていたら薫が話し掛けてきた。
「演劇とか、見に行ったりするの?」
「別に。気が向いたら行くかもしんないけど、特に決めてねぇよ」
「そうなの? 見たい出し物とかないの?」
「ねぇよ。知り合いとかが出てるモンも別にないしな」
それ以前に牧人は知り合い自体が少ないのだが、それは言っても惨めなだけなので言わない。
「じゃあさ」
「うん?」
「この後、わたしと一緒に文化祭見て回らない?」
「……藤宮、と?」
「そう」
「…………」
一瞬、対応に困る。
これは言わば、薫からの突然の文化祭デートの誘いだ。
……尤も牧人はそうした浮ついた感覚が疎い方なので、明確なそうした感覚はない。
ただ、無意識のうちに少しだけ胸が高鳴った。
「わたしも特に見たいものないから、適当に回ろうと思ってたの。だから、マキくんさえよかったら一緒に回らない?」
「……俺と一緒でいいのか? 他に見て回るヤツとかいねぇの?」
「友達、みんな部活とか委員会の仕事が忙しいみたいで」
「藤宮ってなんか部活やってたっけ?」
「吹奏楽部。でもコンサートは午後からだから、それまで暇なの」
「クラスの仕事は……俺と同じだから明日か」
「……なんかマキくん、嫌そうだね」
声のトーンが低くなる。
牧人は焦った。薫のこの声音は特に苦手だ。
「べ、別にっ、嫌じゃねぇよ。いいよ、一緒に回ろうぜ」
「ホント? よかった」
「…………」
流れで了承してしまうも、明るさを取り戻す薫を見て牧人は安堵した。
――って、二人で文化祭見て回ったりして平気か? 誤解されたりしねぇよな……?
そして今更そんなことを意識し出した。
「……っ、っ」
何をどう誤解されるというのか。そもそも誤解されるような二人なのか。そして誤解されて困るようなことなのか。
自分の思考に、自分の中からそのような反論が上がる。
――うるせぇ! 何ヘンなこと考えてんだよ! 背負ってんじゃねぇぞ、カッコ悪ィ!
それら全ての意見に、そう喝を飛ばして黙らせる。
「葦原、藤宮、交替だぜ」
「あ、棗くん」
牧人が心中でそのような自分サミットを開催していると、受付のテントに隣のクラスの学級委員が入ってくる。
その片割れ――棗耕平は相変らずの軽佻な調子で牧人の傍までやって来た。
「よう、何マヌケな顔してるんだ葦原? 何かいいことでもあったのか?」
「うるせぇな、何もねぇよ!」
何故か怒鳴る牧人。耕平の発言が微妙に的を射ていたからだろうか。
「ふーん、そうかい」
対して涼しげな耕平だった。今日も随分と温度差のある二人である。
「とりあえず、引継ぎ作業だろ」
「うん。ええっと……ちょっと待ってね」
「この時間は人が来なくて楽そうだな、ラッキー」
「あ、とりあえず、この名簿と――」
薫の指示を受けて耕平が肯いている。
この少年は軽薄そうな見た目に反して、意外に仕事は真面目にやるのだということを牧人は最近になって知った。
最近――割と真面目に委員会に出席するようになって知った。
受付の引継ぎ作業を済ませ、牧人と薫の二人はテントを出る。
「じゃあ、いこっかマキくん」
「あぁ」
そんな二人のやり取りを見て、耕平は口笛を吹いた。
「……っ!?」
牧人は睨みつけてやった。
「わははははは!」
そしたら大声で笑われた。
葦原牧人は、棗耕平が嫌いになった。
■■■■■■■■■
「………………」
――やっぱ、ダチ同士で見てるヤツ多いな……。
基本的に自意識過剰な牧人は、こういう時にやたら衆目を気にしてしまう。
彼は現在、女子と二人で文化祭を回っている。
それは傍から見てどのような感じなのか。
意識し出したら、妙に気になった。
いざ歩き出したものの、取り立てて見たい物もない二人である。
とりあえず時刻は正午。
二人は適当な場所で昼食を取ることにした。
「どこに行こう?」
「別にどこでも」
牧人の意識は大して食欲には向いていない。
女子と二人きりで文化祭を回っているという状況を意識すまいという方に意識が向いている。
「せっかく聞いてあげてるのにー」
「藤宮が食いたいモンでいいよ」
だからどうにもつっけんどんな対応になってしまう。
二人が歩いているのは校門から校舎へと続くメインストリートだ。
左右には主に運動部の生徒たちによる急ごしらえの屋台が並んでいる。
たこ焼き、やきそば、フランクフルトにカキ氷。
雑多な品目の羅列はまさしく縁日や花火大会の露店を思わせる。
無論、学生の手によるものだけあって、味付けや店構えは縁日のそれらより更に雑なものばかりだったが。
「あっ、りんご飴があるよ!」
「そうか」
「こっちはベビーカステラだって、ホントのお祭りみたいだね!」
「そうだな」
文化祭のパンフレットと実際の露店を見比べつつ、楽しそうな薫。
対する牧人は祭にとても似つかわしくない仏頂面だ。
「……もぉ、なんでそんなつまんなそうなの?」
「別に。早いとこなんか見つけて食おうぜ。腹減った」
実際は少しも空腹ではなかった。
とりあえずそうした気怠い言葉を口にしたかった。
本音としては、明朗な薫の言動にどう反応したらいいのかよくわからなかったからだ。
――なんか……ぎこちねぇ。
生来それほど多弁な方ではなかったとはいえ、かつては問われれば答えることくらい苦労せずこなせたはずだ。
「………………」
だというのに、隣を歩く少女の言葉を受けて自分が取るべき態度に迷ってしまう。
本当はぶっきらぼうな言葉を返したいわけでもない。
かといって、過度に明るく振舞うのも何か違う。
結局、どうすればいいのかわからない。
――………………。
今の牧人は、思考においても無言だった。
ただ、晴れやかな秋の空の下、薫と共に校内を歩くだけだ。
そんな中、
「おぅい」
どこか間延びした調子の声がかけられる。
前方で、同じ制服の少年が手を振っている。
……しかし、今日の彼は普段とはいくらか趣が違った。
「明彦か……?」
存在の認識をするように、牧人はその名前を呟いた。
接近していく。
「やぁ牧人、学級委員の仕事は終わったの?」
「ん……、まぁな」
慣れ親しんだ明彦に対しても牧人の言葉が硬いのは、牧人の意識が明彦の現状認識に向けられていたからだ。
「ごはんは? よかったら食べてく?」
言いつつ、彼の両手に握られたヘラが規則的に動いた。
「お前……、なんでお好み焼き屋なんかやってるんだ?」
「うん? ラグビー部の友達の手伝い」
「……明彦って、なんか部活やってたっけ?」
「文化人類学研究会っていうのに入ってるけど、文化祭は研究発表の展示だけだから暇なんだ」
「ふーん……それでお好み焼き屋か」
「なかなか上手だろ?」
確かに自称するだけあって、明彦の手際は見事なものだ。
鉄板の上に引かれた小麦粉が、肉や野菜を飲み込んで見事に一つに纏められていく。
――いや、それ以前に……、

「ん? どうしたの?」
なんというか、似合い過ぎていた。
露店の中に立ち、捻り鉢巻にエプロン姿で、鉄板の前でヘラを振るうその有様が。
――どう見てもテキ屋のオッサンじゃねぇか……、いいのか、お前はそれで……。
牧人は柄にもなく友人の高校生としての立場を心配した。
「あ、武田くん。こんにちは」
薫がようやく牧人と会話をしているのが明彦だと認識し、近づいて来た。
「あれ。藤宮さんもいたんだ」
相変らず喋りながらも器用に調理を続ける明彦に、薫も多少戸惑う。
しかし大したもので、目だった反応はそれだけだった。
「武田くん、お好み焼き焼くの上手だね」
「たまに自分で作って食べるからね」
「え、一人でお好み焼き食べるの?」
「おやつにね」
薫は冗談と受け取って笑ったが、あり得ると牧人は思ったようだ。
ふくよかな体躯のこの少年は、見た目相応に食欲旺盛。
「それより、今日は二人一緒なんだ。楽しそうだねー」
「え……?」
――忘れてた、今は藤宮と一緒なんだっけ……!
明彦にそれを見られた。意識して、まごつく。
「そ、そんなんじゃねぇよ……」
牧人はそそと微妙に薫から距離を取る。
葦原牧人――焦ると愉快な反応をする男。
「?」
「そんなん?」
牧人の実に中途半端な反応に、薫も明彦も首を傾げた。
「………………」
そのまま、無言でそっぽを向いてしまう牧人。
――くそ……、見られた、どうする?
牧人としては薫と一緒にいるところを他のクラスメイトに見られたら困ると思っていた。
何がどのように困るのかは相変らず不明だが、とにかく困るのだった。
――委員会の仕事以外でもつるんでいると思われたら……、
だからどうだというのか。
「まあ、よくわかんないけど。お昼まだなら食べていきなよ」
「あ、う……?」
明彦は今出来上がったお好み焼きを、プラスチックのケースに入れて輪ゴムを巻いていた。
牧人の返事も待たない。既に持って行かせるつもりなのだ。
「せっかくだから、ご馳走するよ」
「え、いいの?」
「うん。二人くらいなら全然問題ないから」
「ありがとう武田くん」
嬉々として二人分のお好み焼きを受け取る薫。
「はい、マキくんの分だよ」
「あ……うん」
割り箸の添えられた、まだ熱いケースを手渡される。
「…………」
プラスチック越しにその熱を手に感じつつ、牧人は明彦を流し見る。
彼としては意外なことに、明彦から薫と一緒にいることについて何の追求もなかった。
――絶対何か言われると思ったのに……。
気を使ってくれているのだろうか。だとしたら余計に気恥ずかしい。
「………………」
対する明彦はそんな勘繰るような牧人の視線に気付きながらも、曖昧に笑うだけだ。
付き合いの長い明彦は、牧人がこういう時どのようなことを考えるか知っている。
「牧人、マヨネーズかける?」
「いや……いらねぇ」
だから、敢えてそのことは指摘しない。
この不器用な少年が慌てふためく姿に興味はあったが、まあそこは見守ってやるのが友人の務めだろう。
「じゃあな、明彦」
「うん。友達が帰ってきたら、そっちに合流するよ」
「ごちそうさま、武田くん」
「いえいえ。牧人をよろしくね、藤宮さん」
「……っ」
最後に少しだけ友人の反応を楽しんでから、武田明彦は作業に戻った。
■■■■■■■■■
適当なベンチに腰掛けて、食事を終えた。
「おいしかったねー」
「……ああ、うまかった。びっくりだ」
不味くないのではなく、普通に美味だった。
――明彦のヤツ、マジで料理上手かったんだな……。
見るからに得意そうではあるが、またなんとなく牧人は悔しくなった。
「さって、と……午後からは何をやってるのかな」
再び、文化祭のパンフレットを取り出す。
「……」
牧人はそんな薫の横顔を眺めながら、
――意外と、こんくらいフツーなのかな……。
まだそんなことを考えていた。
「な、なに、マキくん……もしかして、ソースついてる……!?」
「ついてるよ、口の回り」
「ええっ、どこどこ!?」
微笑ましく狼狽する。
「うそ。別になんにもついてねぇ」
「もーっ! なんでそんないじわるするのー!?」
がー、と威嚇された。
楽しかった。
「さて……、午後からは何がやってるんだ?」
「あ、やっとやる気出してくれた?」
基準が解れば急に割り切るのが牧人だ。
普通で良いということが解ったので、素っ気無い態度は自重するよう心がける。
「まぁな、せっかく暇なんだし、勿体ないだろ」
「よしよし。えーと、じゃあねえ……」
薫はパンフレットのタイムスケジュールを横に見ていきつつ、
「あっ、これにしない? マキくん、こういうの好きだよね」
ある一点を指差して、牧人にそのページを見せた。
――野外ステージ。音楽ライブ(有志バンド)。
「………………」
牧人は、複雑な気分になった。
嫌ではない。演奏を見るのは好きだ。
しかし、その光景を目にすれば、思い出されるだろう。
……ステージに立つプレイヤーというものの格好良さを。
結局、夢見るだけでそこに立つことの出来なかった自分を直視させられるだろう。
諦めた自分。無力な自分。
そうした自分の姿がありありと想起させられて――
「嫌だ、だりぃ」
「えーっ、なんでよ? マキくん、ギター好きなんでしょ?」
「見るのと弾くのは違ぇよ。俺は他人の音楽になんか興味ねぇんだ」
心にもないことをまた言った。
「うそだよ! マキくんの部屋、CDとかDVDがいっぱいあったもん!」
「う……」
――そっか……、こいつ俺の部屋来たことあるんだっけ……!
「で、でも、藤宮こそ興味ねぇだろ。なら無理しなくたって……」
「いいよ、わたしこれ見たい! だから一緒に行こう? ね?」
「く……!」
――こいつ、もしかして俺のことイジめてるつもりか?
追い詰められるとわけのわからないことまで考え出すのが牧人だ。
……結局、牧人は今回も根負けした。
グラウンドに設けられた野外ステージ。
その一番端に、牧人はだるそうに立っていた。
「わぁ……! すごいねマキくん! 音おっきいね!」
「…………」
初めての爆音に驚きつつも興奮気味の薫だったが、牧人は微妙な気分だった。
舞台上で叫ぶボーカル。応じるように手を挙げ、飛び跳ねるギャラリー。
熱狂的なファンなのか、単純に身内の晴れ舞台が嬉しいのか、学生服姿の男子たちでステージ前は意味もなくモッシュ状態だ。
そうした生徒たちは別枠として、そこから一歩引いた場所にいる観客たちも、楽しげに首を振ったりリズムを取ったりしている。
客席全体に温度がある。いいライブだった。
「………………」
しかし、牧人は冷めていた。
自分と他の観客との間に明確な線を感じた。
聞こえてくる音楽に乗ることもせず、ただ腕を組んで会場全体を眺めている。
演奏自体は悪くない。
曲は牧人くらいの年代がよく知っている流行歌やアニメソングを、パンクロック風にアレンジしたものだ。
所々ミスはあるが、演奏全体に影響が出る程ではないし、曲のアレンジも原曲の良さを残しながらも斬新で聞き易い。
どこか拙く簡易な奏法もパンク系のサウンドにはよく似合っている。
恐らくは初めて音楽に触れる者ばかりなのだろう。
ギターだけに限定すれば、全盛期の牧人の方が技術的には上なのではないだろうか。
「………………」
それでも、牧人は届かない。
ただ、彼等は楽しそうだ。
ステージ上で唄い踊り、時々つっかえながらも気にせず音を紡ぐ少年たち。
止まらない。
彼等は止まらない。迷わない。俯かない。
ひたすら前へ前へ。
余計なことは考えず、一心に前へと進むかのように。
そこには、どこまでも純粋で美しい情熱と速度と、そして勇気がある。
「あぁ……」
……それは、牧人自身には圧倒的に存在しないもの。
そうした自分にない何かを持つ他者に、素直に敬意を表することが彼には出来ない。
だから、見下されるのを恐れて、自分もそれを得ようとした。
しかし結果的には、それを得ようと一人努力することもまた出来なかった。
――俺、何やってたんだろ……。
折しも、あの時――中学二年の秋にライブを見てから、ちょうど二年。
年月を経て、軌道を周回して速度を増した流星か何かのように、その感情は牧人の心をより強く深く抉り抜いた。
胸に残るのは、悔恨の情と虚無感だけだ。
しかし、それを吐き出す資格は、
……逃げ出した自分にはない。
「……っ!」
だから、歯を食いしばって、拳を握り締めて……耐えるだけだ。
ステージ上で楽しげに唄う、彼等の姿を見るしかない。
……見ていることしか、出来ない。
「ねえ、マキくん」
演奏が終わり、拍手と歓声の中で隣に立つ少女が言った。
「来年か再来年には、マキくんもあそこに立ってるんじゃない?」
ステージを指差して、楽しそうにそう言った。
――この……っ!
それは、少年にとってなんて残酷な言葉だっただろう。
純真な言葉と笑顔を放つその少女は、少年の苦悩を何も知らない。
知らなければ許されることはないが、それを糾弾することも果たして彼には許されるのか。
「………………」
ただ、負けず嫌いで、見栄っ張りなだけの少年だ。
何も出来ないのなら、
「まぁ、そういうこともあるかもな」
眩しいばかりの少女の笑顔に、曖昧に肯くだけだ。
強がるのだ。
――それで未来がどうなろうと、知ったこっちゃない……。
未来は自分で引き寄せるもの。
磨きぬかれた、優れた自分がそこにあれば、光は自然と向けられる。
いつだってそうしてきた。そうできればいいと。
……だけど、今回ばかりは、できれば失敗したくねぇなぁ…………。
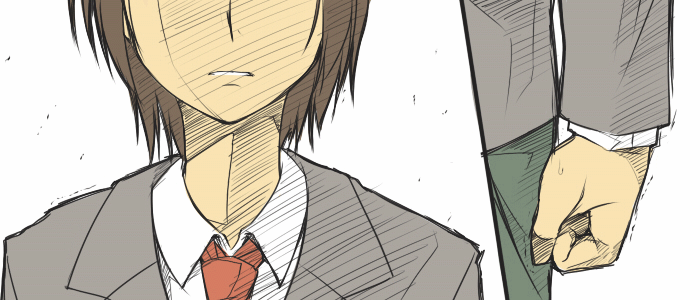
なぜならそれは、本当に本当に、
彼の人生を全て駄目にしてしまうくらい、
「あるかもじゃなくて、絶対いけるよマキくんなら! わたしは、そう信じてる!」
……カッコ悪いことだから。
■■■■■■■■■
ライブが終わる。
いくつかのバンドによる演奏を全て聞いて、牧人と薫は会場を後にした。
「あ、やっぱり牧人ここにいたー」
明彦に発見される。
しかし、牧人の意識はまたもそれどころではない。
――ギター、弾かねぇと……。
……自分も文化祭バンドに出るかどうか。
実現性の程度はさておいても、その可能性だけで頭がいっぱいな牧人だった。
その後、牧人は明彦の所属する文化人類学研究会なるマイナーな文化部の展示を見に行った。
アカデミックに過ぎて、まるで理解出来なかった。
更にその後、薫の所属する吹奏楽部の演奏を一人で聞いて、牧人の文化祭は終了した。
……それも、いい演奏だった。
05
休日の駅前。
楽器屋の店先に牧人はいた。
再びギターを始めたこともあって、何気なくぶらりとやって来たのだ。
「……………………」
そして、食い入るようにガラス越しのそれを見つめていた。
ショーケースには何本もギターが陳列されている。
そのうちひとつ、牧人の目前に燦然と掲げられているギター。
鋭く孤高なV字型のその楽器は牧人がかつて先輩から譲り受けたような安物とは訳が違う。
――――真正のギブソン社製・フライングV。
67年と記された漆黒のそれは、生産開始当時から現在に至るまで多くの音楽家に愛されてきた純正品である。
「………………」
憧れてきた、プレイヤーという立場。
自室にあるCD何枚かの向こう側にいる人々が使っているものと同じ楽器が、今目の前にある。
その事実を認知して、牧人は壮大な何かに捕らわれかけた。
――これを、俺が手に入れる……?
想像するだに心身が震える。
無論、名器のみが英雄を英雄足らしめるわけではない。
スターダムにのし上がるには、たゆまぬ努力や優れた人間性も同様に必要だ。
幾多の先人が手にした名品と同じ物を自分が持ったところで、劇的に何かが変わるはずもない。牧人もそのくらいは弁えている。
「………………」
しかし、これを手にすることが、越境か何かのように感じられる。
素晴らしい環境におかれることで自身も改革されていくのでは?
そんな期待を捨て切れない。
――藤宮は、どう思うかな……?
唐突に牧人はそのようなことを考える。
薫はギターの良し悪しなど知らない。疎い彼女にこの名器の素晴らしさを語り聞かせても喜ばれるかどうかは微妙なところだ。
しかし、優れた楽器は優れた演奏を可能にさせるだろう。
薫にはもっと自分の演奏を聴いて欲しい。
そのためなら練習をしていくつもりだし、いい機材も欲しい。
…………そうして向上していけば、彼女は喜んでくれるだろうか?
……上達した姿を、褒めてくれるだろうか?
――よし……!
牧人の中で色々な何かが決まる。
購入することにした。
――絶対、薫にすごいって言わせてやる。
この時の牧人はそのような決意を固めていた。
勿論、見栄っ張りな牧人がはっきりとそう思ったはずもない。
だが明言化はされないものの、そのような漠然とした意識に突き動かされていた。
そうしたかった。
これは自分を改革する第一歩。藤宮薫に認めてもらうための第一歩。
気分としてはもう自宅に持ち帰り、意気揚々と電話で薫にそのことを報告しているようなところまで先行している。
だから、興奮気味に値札を見た。
「……嘘だろ………………」
車も買えてしまいそうな額だった。
思わずがっくりとうなだれる。
――こんな薄っぺらな機械が……なんでこんな……、納得いかねぇ……。
仮にも音楽を嗜む者としてあるまじき思考を抱きかけて、牧人は首を振る。
――馬鹿が……っ、真面目にやるって決めたんだろ!
決めたからには貫き通す。彼にも彼なりの筋がある。
ならば情熱を萎えさせるそのような寒い思考や発言はタブーとせねばならない。
――もっと安いヤツはねぇのか……? 中古でもいい……!
今更、他の種類のギターを触る気にはなれなかった。
V型のギター――可能なら最高峰たるギブソン製のものがいい。
ギブソン自体に特別な思い入れはないが、やはり意識として重要である。
表にあったような特定年代のものなら付加価値としては尚いいのだろうが、冷静に考えて高校生風情にヴィンテージ・モデルなど荷が勝ち過ぎている。
店内に突入し、中古品のコーナーを物色した。
「あった……!」
中古品が一本だけ。
生産年は割と最近、当然量産品だ。
使用済みというだけあって、多少汚れが目についたが、見たところ保存状態は良好。牧人の目には新品とそう変わらないように見える。
――こいつだ……!
親の仇を見るように値札を睨み付ける。
値段は……高いものの、表の怪物ギターに比べれば半額以下だ。
高校生にも決して手の届かない額ではない。
「それにしても、高ぇ……」
金欠学生の身分で一括購入などできるはずもない。
楽器というものはどうしてこうどれもこれも高額なのだろう。
改めて音楽というものの困難具合に愕然としてしまう。
だが、例え目を見張るような額でも、自分も辿り着ける可能性があるのなら話は別だ。
現実性が増してくると、先程浮かべた様々な予想が蘇ってくる。
これを手にしている自分、それに対する薫の反応。
「……よし」
購入することに決めた。
すぐにではない。長い時間をかけて。
「バイト、すっか……」
どこか諦観めいたため息を漏らして、牧人は店を出ることにした。
最後に、吊り下げられたフライングVを一瞥してから店内を睥睨する。
自分が目をつけたのだから誰も手を出すな、とでも言いたげに。
コンビニで求人雑誌とキシリトールガムを購入して、牧人は帰宅した。
その求人雑誌のタイトルは、『NOVICE』という。
【戻る】