――オレも出るからマキも見に来いよ。
今では名前も覚えていない。どうして知り合いだったのかも覚えていない。
そんな中学時代のとある先輩のこの言葉が、全ての始まりだったのかもしれない。
今にして、そのように思う。
――オレも出るからマキも見に来いよ。
今では名前も覚えていない。どうして知り合いだったのかも覚えていない。
そんな中学時代のとある先輩のこの言葉が、全ての始まりだったのかもしれない。
今にして、そのように思う。
「………………」
季節は春。
桜並木の通学路を行く、不機嫌な面持ちの少年。
名前は葦原牧人。中学三年。
学ランの襟首をだらしなく緩めて、キシリトールガムをくちゃくちゃと噛みながら、彼は一人歩いている。
どこか気怠げなその歩みは、見た目も相まっていかにも不健全な様相を呈していた。
頭髪はどちらかと言えば派手な感じに纏まっている。
天を衝く怒髪というほどではないものの、整髪されたそれらは周囲を攻撃するように程好く伸びて尖っている。
長過ぎず短過ぎず、絶妙な長さで保たれた前髪と、その下に覗く鋭い目付き。
何も知らない人間が見れば、少々近寄り難い印象だ。
学校帰りのため服装は制服であるため、ここには攻撃的な要素は少ない。
しかし、足元の靴だけは対照的に派手だ。
丈のある高そうなシューズ。全面を覆う虎縞模様が目に痛い。
地味な制服という抑圧に抵抗するかの如く、どこまでもアヴァンギャルドなデザイン。
……だがそれは、一般的な感性からすると少々いただけない。
何より彼の学校の制服には似合っていない。
しかし、牧人は抵抗や反骨というものを大事にする。
幼少期から思春期にかけて彼の感性は暴走気味で、このトラ柄シューズを始め、服装から小物に至るまで全てが独自のルールに基づいて選出されて来た。
他人に合わせることを牧人は極端に嫌うのである。
ある種の特殊性こそ人間の大きな価値の一つであると、彼は信じて疑わない。
現代の若者に見られがちな傾向――
思春期特有のこの偏ったアイデンティティを牧人も主張してやまないのだった。
だから、牧人は学校でも際立った存在として一目置かれていた。
中学生の年代にしては、牧人の感覚はかなり早熟だ。
――中学生。
身体の成長は活発であっても、精神的にはまだ幼さが残る年代である。
大人から見れば笑ってしまうような背伸びやカッコ付けをしても、同年代からは“大人びている”と好意的に解釈してもらえるだろう。
故に、牧人のそんな個性的過ぎるセンスも、クラスや学年では愛すべきパーソナリティの一つとして認知され、彼は相応の立場を確立していた。
友人はそれなりに多い。教室でも割と多弁な方だ。
しかし、下校は大体一人だ。友達を家に呼ぶ事もほとんどない。
どこか冷めていたのだ。
そんな中、
「おぅい」
どこか間延びした調子の声がかけられる。
前方で、同じ制服の少年が手を振っている。
「明彦か……」
存在の認識をするように、牧人はその名前を呟いた。
接近していく。
「たまには一緒に帰ろうか」
少年――武田明彦は穏やかに笑う。
「そうだな」
対する牧人はぶっきらぼうな口調だが、機嫌はそれほど悪くない。
明彦も全体の雰囲気からそれを察し、うむと肯いた。
並んで歩き出す。
葦原牧人にとって、武田明彦はこうして会えば一緒に下校することもある程度の友達である。
一人の時間をそれなりに大事にする牧人だ。無意味に群れることは厭う傾向にある。
その彼が平常のまま応じるということは、そのつながりは薄弱なようでいて、実際は強固であることが伺えた。
「牧人、チゲムーチョたべる?」
明彦がカバンから取り出したのはピリッとした辛さが特徴的なスナック菓子だ。
ふくよかな体躯のこの少年は、見た目相応に食欲旺盛。
「食うよ」
今日も明彦は近所の駄菓子屋経由の帰宅コースだった。
牧人もよく一緒に買い食いをすることがある。
「ほら」
「サンキュ」
開かれた袋に手を入れてスナック菓子を一つつまむ。
一口に含んで咀嚼すれば、口内に広がる刺激的な辛味。
「もう僕らも三年だ。早いねえ」
「お前とは久々に別のクラスになっちまったな」
「そうだね。でもまあ、よくこうやって一緒に帰ったりしてるし」
言いながら、もりもりとスナック菓子を食べる明彦。
それをチラチラ見ながら、牧人は指先に付着したスナックの残滓を舐めたりした。
「…………」
もう一つ貰いたいが、なんとなくタイミングが掴めない。
「……お前って、帰宅部だっけ?」
場を繋ぐように無関係な話題。
「うん? そうだよ、牧人と同じ」
「帰宅部に同じもクソもあるかよ」
「牧人はどうして部活入らなかったの? 僕と違って運動得意じゃん」
「そんなことねぇよ。……てゆうか、そう言うお前はもうちょい運動しろ。また太ったんじゃねぇのか?」
「ん? そんなことないよ」
「目が泳いでんじゃねぇかよ」
自然と笑みが浮かぶ。
明彦との会話は何も考えずに済んで気楽だった。
楽しい時間はすぐに過ぎる。
気付けば、明彦の家の前。
「もうお前んちの前か、早いな」
「そだね」
言いつつ、牧人の視線はスナック菓子へ。
――結局一つしか食ってない……。
言い出さなかった自分が悪いのだが、なんとなく腹立たしい気分になる。
それを察してか、
「牧人、チゲムーチョ食べる?」
袋を差し出す。
武田明彦――彼は常々空気の読める男でありたいと思っている。
「……食うよ」
今度は二つ取って一つずつ食べた。
少し、負けた気分。
「やっぱこういう菓子は辛いのがうまいな」
負け惜しみのような言い方になってしまう。
「僕はもうちょい抑え目の方が好きだなあ」
「馬鹿だな。塩っ辛いだけの菓子なんかもう食い飽きただろ」
「大人だねえ、牧人は」
「ふん、まぁな」
大人と言われて少し機嫌を良くした。
まあ、そんな風に、
葦原牧人はませた少年だった。
……いわゆるマセガキである。
葦原牧人は、ギターを始めることに決めた。
それは年齢にして十三歳――中学二年の秋の時点のことである。
もう今から、半年ほど前の話だ。
彼は、音楽がやりたかった。
ロックである。バンドマンへの憧れだ。
きっかけは中学二年の時に見た、文化祭での有志バンドによるライブである。
知り合いだった先輩がステージに立つというから何の気なしに見に行き、その演奏に心底から打ちのめされたのだ。
――ちくしょう、カッコいいじゃねぇか……!
正直な感想を言ってしまえばそうだった。
反骨精神ばかり強い牧人は決して口にはしなかったが。
彼は普段からそれなりに音楽を聴いた。
あくまでそれなりだ。難しい理論や楽器については良く知らない。
しかし牧人は、音楽自体には多分に苦手意識がある。
それはコンプレックスに近い。
「音楽をやっているヤツはカッコいい」「音楽に詳しいヤツはいけている」
そうした認識が彼にあった。街中で楽器を持ち歩いている人間を見ただけで、なんだか負けた気分になる。
それが、先輩のライブを見て爆発した。
漠然と抱いていた感覚が確信に変わったのだ。
音楽をやる彼等は、やはりカッコよくていけていたのだ。少なくともこの時の牧人にとっては。
認めざるを得ないパワーがあった。もう完全に敗北だった。
演奏の良し悪しに興味はない。
所詮は中学生の有志参加によるバンドである。演奏技術も歳相応に粗く、拙い。
……ぶっちゃけると普段CDから聞こえてくるものなどに比べれば全然大したことなかった。しかしそんなことはどうでもいい。
ステージでがなるように唄うボーカルや、耳をつんざくバンドサウンドに、牧人は感動してしまったのだ。
……不覚にも感動してしまったのである。
音楽には間違いなく人を惹き付ける何かがあると、この時は直感した。
激しい曲には沸き立ち、静かな曲にはうっとりと聞き入っていた観衆の生徒たちがまさしくその証人だ。
牧人自身もその中に含まれている。
その点に関して、彼の心中は穏やかでない。
演奏者のいいように感動させられるばかりの、安易でいかにも流されている感のある一リスナーなどという立場は牧人としては真っ平御免だった。
ステージ上の彼等の、迸るカッコ良さと生命エネルギーのようなものは圧倒的だった。
言うならば、それは自分にない要素。
有名人の着ている服を羨むのと同じような心理である。欲しくなるのだ。
彼の友人――武田明彦ならばここでその相手に素直に敬意を表する。
だが、牧人は彼ほど大人ではなかった。
強さを見て感じるのは、それを素直に賞賛する気持ちではなく、それを超えようとする気概だけである。
好意的な見方をすればチャレンジ精神豊富とも言える。
――くそっ……俺だって……!
そしてヘンなところで負けず嫌いなのが牧人だ。
これはもう自分も音楽を始めるしかなかった。
――モテたいからロックをやろう。
そのような発想は青少年ならではのわかりやすいロマンスに至る王道である。
だが、牧人の動機はそれらと似ているようで、えらく後ろ向きだ。
使用楽器にはギターを選んだ。六本の弦に特別な愛着はない。ただライブで目立っていたからというだけの理由である。
……そのような理由で、
葦原牧人はギターを始めることに決めた。
しかし、そんなことを考えながらも、季節は巡って冬を通過してしまった。
だというのに彼はまだ、音楽をやりたいと悩んでいる。
――そんなやりたいんならさっさと始めればいいじゃん。
大昔に、別の何かをやろうと悩んでいる時、誰かがそう言った。
だが、そこは葦原牧人。
一筋縄ではいかないのである。
彼は大衆音楽に対してはそこそこ造詣が深い。
しかし演奏に関しては完全に素人だ。ギターの仕組みなどまるでわからない。
従って、音楽をやるのなら誰かに技術を教わらなければならない。
……だが、牧人は人に教えを請うのが嫌いだった。
なぜなら彼は見栄っ張りの負けず嫌いだからである。下に見られるのが嫌なのだ。
だから独学でやろうとも思った。教則本の類の存在は牧人も知っている。
道のりは困難だろうが、うるさく言われない分、気は楽だろう。
しかし今度はもっと単純に、ギターの入手法という問題に直面した。
決意した次の日、軽い気持ちで楽器屋に行った。
すぐに帰ってきた。
……居心地が悪すぎた。俗に言うアウェー感というヤツである。
店舗の様子も店員の雰囲気も専門色が強すぎてとても馴染めない。
あんな場所にいたのでは五秒でボロを出すのが必定だ。そう思ってすごすごと逃げてきた。
――八方塞だった。
一応、補足しておく。
ここで、経験者の知人や音楽スクールに頭を下げるのは簡単である。
ここで、初心者として店員に質問をするのは簡単である。
しかし、そういうわけにはいかない。
それは牧人のルールに反するからだ。
そうすることは、彼にとって“カッコ悪い”のである。
牧人は武士のような少年である。醜態を晒すくらいなら切腹である。
いかに優雅に素敵にスタイリッシュに、かつ自然に日々を送るかが、彼にとっては重要なのだ。
その理論に基づけば、素人面して安易に質問するなどできるわけがない。
……彼のちっぽけな自尊心がそんなことゆるさない。
――だから、八方塞。
音楽を習うことも、楽器を手に入れることもできない。
多分、そんなの葦原牧人本人か、それに似たような感性の持ち主にしか理解できないのだろう。
牧人もそれを理解している。共感など得られるはずもないと。
だから、誰にも相談できない。答えは一人で見つけなければならないのだ。
カッコつけるとは、そういうことだ。
格言のように纏めたところで、何の重みもないのであるが。
――どうすりゃいいんだ……。
だからきっと、意味不明な理由をつけてウロウロしている牧人の姿はどこか滑稽なのだろう。
そんなことを延々と悩んでいたある日、
「よう、マキじゃねーか」
「あ、先輩……」
牧人は、懊悩の根源たるその先輩に偶然出くわした。
元はと言えば、この先輩に誘われてライブを見に行ったのが始まりなのだ。
この日は、お互い学校帰りだった。
向こうは少し遠方に位置する高校の制服を着ていた。
肩にギターをかけている、相変らず音楽は続けているようだ。
「元気か? ま、卒業してからだからまだそんなに経ってねーけど」
先輩は爽やかに笑う。
確かにそれほど時間は経っていないが、久しぶりな感覚がするのも事実だった。
向こうは電車を数十分乗らなければならないような場所に通っている。当然、通学時間帯も異なってくる。
このように偶然出会う機会も、かなりのレアケースだろう。
――まあ……これから先も、もうこの人とはそんなに会わねぇんだろうな。
なんとなくそう思った。
「あ……!」
しかし、思い至る。
――もうこの人とはそんなに会わない。
それが決め手だったのか、
「ん? どした、マキ」
「先輩――」
敢えて妥協をすることにした。
もうそんなに会わないのなら、多少はカッコ悪くてもいいと思ったのだ。
そのようなことででいいのだろうか?
……牧人的にはいいのだろう。おそらくは。
「これがレスポールな、そんでこっちがストラトキャスター」
「………………」
その足で先輩宅に招かれて、牧人は憮然とした表情でギターについての講釈を受けていた。
まず結果から言ってしまうと、
――この人……、すげぇ人だったんだ……。
そういうことだった。
同年代とは思えないほどに音楽の知識も機材も豊富で、通された自室は楽器倉庫のような装いだった。
スタンドに立て掛けられた何本ものギター、ベース。奥にはドラムセットまである。
聞けば、父親が音楽を趣味にしていて、その影響を受けて育った彼は必然的に多くの楽器に触れてきたというのである。
――にしても、こりゃハンパねぇだろ……。
自然と体が強張ってしまう。
これでは楽器屋の店員を相手にするのと変わりない。
今にして思えば、あの有志バンドの中でもギターだけはかなりまともな演奏をしていたように牧人は思う。
それはそうだ、と今にして再認する。
きっと牧人がギターを弾こうと思った理由も、それが目立っていたからではなく上手だったからなのだろう。
カッコいいと思ったのだ。だから羨ましくなった。
――まぁいいか、どうせこの先輩とはもうそんな会わねぇし。
結局はそういうことだった。
心の中に生じたもやもやを纏めて飲み込む。
とりあえずギターを借りておいて、ある程度慣れたら自分用を買いに行こうと考えていた。
そこで借りたギターを返却すれば、もうこの先輩との繋がりもそこまでだ。
「んで、ギターなんだけどさ、どれがいい?」
「ん――」
話を振られて意識を戻す。
部屋中に何本も置かれたギターをざっと見渡した。
「オススメとかあります?」
良し悪しなどわからないので聞いてみた。
割り切ると意外に曝け出すのが牧人だ。
「これなんかどうだ?」
提示されたのは赤いギター。
ストラトキャスターというこれの名称もついさっき聞いて知った。
エレキギターといえば思いつく、見覚えのあるデザイン。角のように突き出したボディや、ヘッドに一列に連なったペグがどことなく現代的だ。
――見た目は、悪くねぇけど……。
「初心者には弾きやすいと思うぞ」
「…………」
先輩のその一言で牧人は微妙な気分になった。
――初心者には弾きやすい……?
そのような文言は牧人が一番嫌うものだった。
――そんなの、自分ビギナーですって言いふらしてるようなもんじゃねぇか……!
初心者――ノービスとは常に無様なものだ。自分は決してそうなりたくはない。
相変らず体裁大事な男、葦原牧人。多少割り切ってもその辺は変わらない。
「とりあえず、他のも――」
だからとりあえず渋った。
「ん? 気に入らなかったか?」
「いや、一通り見てから決めようかと……」
そして強く言い切れないのも牧人だ。
「じゃあこれはどうだ?」
その隣に置かれたギターを指差す。
二本目。黒いギターだった。
先程の講釈では、それをレスポールと言っていた。
牧人の認識ではエレキギターといえばまずこれが思い浮かぶ。ヒョウタン型の分厚い形状からは、あの重低音が発せられることが予想された。
「んー、……あんまり」
「まあレスポールはちょっとクセがあるからな」
同意してくれるが当然牧人はそんなことは知らない。
単純に、エレキギターと聞いて連想されるようなギターなど弾きたくなかっただけだ。
――もっと個性的なのがいいな。こういうのは……他に候補がなかったらだ。
個性派志向の牧人には普遍的なデザインなど退屈でしかない。
「ん……?」
そこでふと、部屋の隅に置かれた一本が目に留まる。
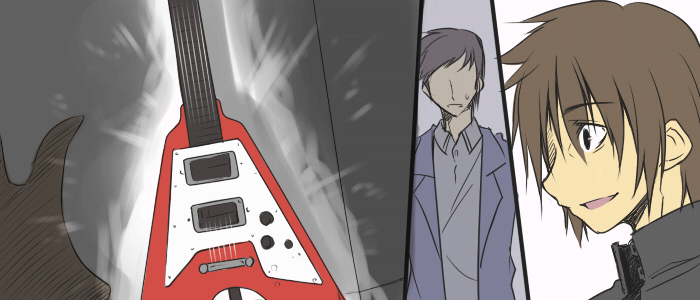
それは、変なギターだった。
ボディは妙に細く薄く、下部が二股に分かれているという非常に奇妙な形状をしている。
ちょうどアルファベットのVを逆様にした感じだろうか。
一見しても、それが今見てきた二本と同じ楽器だとは思えない。
「……先輩、こいつは?」
「え、それ?」
意外な顔をされる。
「それはフライングVっていうんだけど……」
「これ、いいですね。これにしよっかな」
説明を受けるより先に、牧人は嬉々としてそのギターを手に取った。
さして使われた形跡のない真新しいネックを、獲物を捕らえた狩人のように引っ掴む。
「え、まさか……、それにするのか?」
牧人の選択に、先輩は目を丸くする。
そんな奇異の視線に対して、牧人はここぞとばかりに不適な笑みを返す。
「何言ってんですか先輩。こいつの形が一番面白いですよ」
初見の時点で、彼の心は決まっていたのだ。
今の牧人は演奏上の特徴や弾きやすさなどにはあまり興味がない。
大事なのは形と色だ。気に入った形状でなければ弾く気にはなれない。
そして牧人はこのギターの詳細を聞いた。
本来はエレクトリックギター大手のギブソン社というメーカーが開発したものであること。
その特殊な形状から、発売当初は前衛的過ぎて受け入れられなかったこと。
後に徐々に注目されるようになり、今では変型ギターの先駆的存在となっていること。
それらの説明を受けるうち、牧人の興味はますますそそられた。
確かに、奇抜なデザインである。とても弾きやすい形状とは思えない。
だが、そこには絶妙なバランスが在るような気がした。
左右対称の形状がそう思わせるのか、特徴的でありながらシンプルなフォルムが美しいのか。
……とにかく、カッコいいと感じたのだ。
ギターと聞いて誰もが想像するような形状など、牧人にとってはつまらない要素でしかない。
正道に興味はない。標準的なスタートラインなど願い下げだ。
常人を躊躇させるような特殊性をありありと感じさせるような物を牧人は好む。
確かに特殊性を有するものは、多くが相応の取っ付き難さ、扱い難さはもちろんのこと、マイノリティとしての共感の得難さなど、数々の障害が歴然と存在する。
しかし、そうしたハードルの高さに、葦原牧人は強く惹かれるのだった。
牧人が即座に妄想するのは、それらを乗り越えて飼い慣らしている自身の姿だ。
その仮定、そしてそれが現実となった時の興奮を想像すれば、心は強く躍動させられる。
なればこそ、
今や変型ギターの代名詞的存在たるV型ギターを選択するのは、牧人にとってある意味当然の帰結であったのだろう。
手にかかる、予想以上の重量。
見てきた三本の中で最もボディが小振りで薄いこのギターですらこうなのだ。
他の二本の重量を想像して、牧人は苦笑した。
「はは、いいですねこれ。軽くて使いやすそうだ」
ここぞとばかりに強がった。
牧人のそんな心中など知る由もない先輩は怪訝な顔をする。
「なあマキ……、ホントにそれでいいのか?」
「いいんですよ、俺はこれが気に入ったんです」
もう心は決まっていた。今更変える気はない。
「てゆうか……それだったら、マキにやるよ」
「え?」
意外なことを言われる。
「それって元々貰い物なんだ。使いづらいからほとんど弾いてないし、マキにだったらやってもいい」
「……マジですか」
嬉しい誤算だった。思わず声が低くなる。
――なら、返す手間もいらないわけだ。
それこそ黒いことも考えていた。
「なら先輩、早く使い方教えてくださいよ!」
早速そのギターを抱えて、未だに困惑気味の先輩を煽る。
もういても立ってもいられなかった。
――このギターが俺を呼んでいる。
そんな、らしくもない夢のある思考すら抱いてしまう。
勢いと情熱ばかりが先行している。
ギターに限らず、何かを新しく始めるというのは、往々にしてそういうものかもしれない。
基本的な操作と仕組みを教わり、その他の機材も何点か譲ってもらって、牧人は先輩宅を後にした。
――後は、自分で練習しよう。
ギターを貰う段になっても、先輩に教えを請う気は毛頭なかった。
やはり技術の習得効率よりも、“独学”という言葉の響きの格好良さが牧人の心を捉えたのだ。
ギターを背負い、機材を手に持って町を歩く。
「〜♪」
ガラにもなく鼻歌混じり。
いつも噛んでいるキシリトールガムも美味く感じる。
なんというか、既に勝った気分だった。
「なー、高城よう。ギタリスト的によく使うテクニックってなんなん?」
「……そーだなァ、やっぱチョーキングじゃないか」
友人二人がギターの話をしているのを、牧人は横で聞いていた。
「なに? ナベやんギター始めたの?」
「そなんだよ。でも全然わからんから、経験者に相談を」
「やめとけ、高城なんて。こいつ一時期ハマってただけで全然経験者じゃないぜ」
「ちょ……! 甘く見ないで欲しいぜ、オレにはスバラシイ絶対音感がだなァ――!」
「ナベやんは努力家だからこいつよりは長続きしそうじゃね?」
「ミッチも一緒にやろうよ、オレとバンド組まない?」
「俺はいいや、音楽とか興味ねえし。……マキは?」
「……ん? 俺も別にいい」
会話に加わらないようにしていた牧人だったが、話を振られて曖昧に答える。
「マキくん音楽好きそうなのになあ。CDいっぱい持ってるっしょ?」
「聞くだけだよ。弾く方は、別に興味ないな」
心にもないことを言いつつ、絆創膏の巻かれた左手の指を隠す牧人。
先輩からギターを貰って数週間。
牧人は一人で練習を続けていた。
最初は意味不明だった仕組みも徐々に把握し始め、指も弦の硬さに馴染んできた。
しかし、牧人は友人間ではギターの話題を口にしない。
音楽の趣味を持った友人は何人かいて、彼等の会話からヒントを掴むことはあるが、牧人からその話題を振ることはなかった。
確かに、ギターを始めたという話題は普段よくつるむ友人ならば喜んで食いついてきそうなものである。
だが、まだ口外する時期ではない。少なくとも牧人はそう思っていた。
人に自慢できるような腕前ならば、喜んで語るだろう。
しかし、今の牧人は未熟だ。
実際に演奏をせがまれて、拙い演奏をしてしまった時の自分の居心地の悪さは容易に想像できてしまう。
その時、大言壮語の謗りを受ける可能性は否めない。
「……ところで、今度の小テストあるじゃん?」
「あー、そだったね」
「ヤッバ、勉強してねーよ! マキ、嫌なこと思い出させるなや」
だから音楽の話題はさりげなく回避する牧人だった。
したい気持ちはないではないが、それよりボロを出す恐怖の方が強い。
――そういや、あの先輩……何してんのかな?
ふと思い出す。
彼とはあれきり会っていない。
何かあれば連絡してくれと言われたが、牧人にそんな気はさらさらなかった。
おそらく今後もそんなことはないだろう。
あの先輩が、牧人と同じような境遇だったなら、まだ相談相手として成立したかもしれない。
しかし、彼は生粋の音楽家だった。少なくとも牧人にはそう感じられた。
技術や知識の面では勿論のこと、音楽に対する愛情や熱意の面でもとても敵わない。
本格的な話をしても、自分の未熟さが露呈されるだけだろう。
所詮は趣味、対抗する必要はない。しかし牧人はしてしまう。
音楽家としては明らかに間違った姿勢である。
真に上達を目指すのであれば、世間体など捨て去るべきだ。
それは技芸を磨くものなら何事に関しても通ずるところであるが、難しいところでもある。
「………………」
そんな感じで、かつて世話になった先輩とは疎遠になっていくのを感じた。
――まぁ、別にどうでもいいけど。
元より多少趣味が合ったからという程度の親交だった。
途絶えてもさほど堪えなかった。
去るものは日々に疎しとも言う。
そういうことも、まあ、あるだろうと納得した。
「牧人、ポップコーン食べる?」
「食うよ」
差し出された袋に手を入れ、ひとつつまんで口に放り込んだ。
帰り道の駄菓子屋で購入したものだ。
明彦はポップコーン、牧人はコーラ味のグミを買った。
牧人は菓子やジュースの類が好きだった。
とりわけコーラや辛口スナックなど、刺激的なものを好む。
大人ぶった趣味の癖に、嗜好は割と幼い。
「明彦、この前の小テストどうだった?」
「小テスト? 何の授業の話?」
「え? 数学のだよ、あったろ?」
「なかったよ。僕のクラス、牧人のところと先生違うんじゃないかな」
「あ、そっか……、お前って今は違うクラスなんだっけ……」
今日も二人は並んで下校している。
雑談を交わしながら。
明彦は牧人にとって“幼馴染”であり“腐れ縁”だ。
小学校低学年の頃、あるグループ作業で一緒の班になった時、二人の縁は生まれた。
それ以来、なんとなく一緒にいる機会が続いている。
一言で言ってしまえば、二人は自然な友人。
特別趣味が合うわけでもないが、なんとなくいつも近くにいたからお互い一番自然に話せる知り合い同士といったところ。
しかし、だからこそ二人はよくつるむわけでもない。
普段つるむのはお互い別々にいる趣味の合う友人であり、最近ではクラスも異なる彼等が揃うことはあまりなかった。
だが、会えばこうして会話もするし、一緒に登下校もする。
「明彦、たまにはお前んち行っていいか?」
「うん。ゲームでもする?」
「いいな、対戦しようぜ」
しかし、牧人は明彦の前でもギターの話はしない。
彼等はお互いをよく理解している。多少の欠点を見つけた程度で嫌いになるような浅い関係でもない。
牧人のギターの腕前がいかに未熟であろうと、明彦ならば難癖をつけるようなこともなく、鷹揚に笑って流すだろうことはよくわかる。
だが、隣を歩く少年に実際に話せるかというとそういうわけでもない。
――どうせ明彦に言ったって解りゃしねぇだろ。
牧人はそんな根拠のない優越感を抱いていたが、二人の間には互いに踏み込むべきでない領域が存在していたのもまた確かなのだ。
具体的には趣味の違いなどが挙げられる。
例えば、牧人は明彦と音楽の話をすることはあまりない。
逆に明彦も共通しない趣味について牧人に語ることはなかった。
どちらかと言えば、明彦が譲歩している形になる。牧人は専門外の話を聞くとひどく退屈そうな顔をするからだ。
明彦としては興味のない音楽の話でも、熱心に語る牧人の姿を見ているのは楽しいのだが。
その辺りも性格の違いだろう。
だから二人は馬が合うのかもしれない。
そんな二人はこの日の放課後、仲良くゲームをして遊んだ。
「あ、くそっ、また弦切れた……!」
そして自宅。
牧人はギターの練習をしている。
この年代の少年にしては珍しくないが、牧人の自室は乱雑としている。
一言で言うと、とても散らかっている。
読み終わってそのまま放置された漫画や雑誌。古いものは邪魔臭いので部屋の隅に追いやられている。本棚はあるが、年に一度くらいしか整理しない。
部屋の隅、雑誌の山の傍にはホコリをかぶったダンベルやエキスパンダー。
一時期、筋力トレーニングが牧人の中でブームになったことがあった。その時に大量購入したトレーニング用品は、今や雑誌の山の隣にまとめて捨て置かれている。
手軽なものは今でもたまにやるが、道具を使ってのトレーニングはなんとなく嫌になってやらなくなった。筋肉に対して真剣になるのが格好悪いと感じたのかもしれない。
……ちなみに、若年から鍛えていたおかげで牧人の体躯は割に引き締まっている。
元が痩せ型であり、身長も平均程度であるためそれほど筋肉質には見えないが、余計な脂肪のない絞られた体だ。
妙に個性的なデザインのステッカーが貼られたタンスの上に置かれたシステムコンポ。
その脇にうず高く詰まれたCDには所定の収納棚がない。聴いたらそこに積むのが通例である。
オーディオ機器はそれなりに高性能な物ばかりだ。音楽雑誌などを色々と読み漁った結果、音響に関する妙なこだわりが生じた。
MDやその他プレイヤーの類は使わない。CDの音質が一番良いという話を聞いたからである。
親からの誕生日プレゼントにスピーカーやヘッドホンをねだる中学生とは果たしていかがなものか。牧人としてはその異端っぷりが逆に心地よい。
……思春期特有の感性の暴走が、この部屋の随所に見て取れる。
そのような部屋に、最近新たにギターと機材が加わった。
「……よし」
弦の張り替え作業にも随分と慣れた。
両連のペグに弦を巻き、余剰をカットする。ハサミを当てる位置は感覚だ、大体合うようになった。
「予備がない……また買ってくるか」
最近では楽器屋に対する疎外感のようなものも薄れてきている。休日には弦やピックなどの消耗品を買うためによく足を運んだ。
そして、再度ギターを構えて立つ。
変型ギターの多くは座っての演奏に適さないと言われている。牧人のフライングVも同様だ。
プロのミュージシャンの中には変型だからこそしっくり来るという意見の持ち主もいるが、牧人はそうは思わなかった。実際に弾きにくいのだから共感できない。
かといって、今更他のギターを使う気にもなれない。
また、練習前に牧人はカチューシャを装着する。前髪の長い牧人は、練習の際は必ず髪を上げて、それらが邪魔にならないようにしていた。
最初はとてもそんな気になれなかったのだが、一度演奏中に毛先が目に入って大変なことになったので、妥協することにした。
どうせ練習風景など公開しないのだ。上げられる効率は上げなければなるまい。
なお、牧人はコンタクトレンズを使用している。
幼少期から思春期にかけての急激な視力低下にはテレビゲームを始め様々な原因が考えられるが、センスのない視力矯正用レンズ――いわゆる眼鏡の着用はどうして嫌だった。
両親に無理を言ってコンタクトにしたものの、それ以来、前髪との熾烈な戦いが始まるようになる。
多少の不純物が混入しただけでも激痛になるコンタクトレンズ使用者には、毛先が目に入る可能性のある前髪が長いタイプのヘアスタイルは向かない。
しかし、そんな理由で髪型を変えるのは嫌だった。
色々とままならない男、葦原牧人である。
「……っく!」
練習とは多くが地味な作業の繰り返しだ。
上手くいけば気分もいいが、師を持たない牧人は基本的に試行錯誤ばかりである。
だから、時々イライラする。
「…………」
おもむろにカチューシャを外した。
一度ギターをスタンドに置いて、机に向かう。
引き出しから取り出したのはサングラス。
洒落たデザインのスマートなフレームに、威圧的でアウトローな黒のミラーグラス。牧人の所持品の中で最もお気に入りのファショングッズである。
かけて、少し髪型を整えた。
その状態でギターを手に取り、ストラップを肩にかける。
そして、部屋に置かれた姿見の前に立った。
「――――……っっ!」
深呼吸してから、大音量でギターをかきならした。
叫ぶように、喚くように。
コードも何もない、がむしゃらな演奏だ。
ただ、見た目には高速のストロークがなんとなくカッコ良く見える。
「――あっ!」
いいこと思いついた。
適当なところで足を振り上げる。
荒々しくもどこか優雅なそのパフォーマンスは、以前目にしたライブ映像でギタリストがそうしているのを真似したものだ。
そんな自分の姿が鏡に映し出される。
決まり過ぎていた。少なくとも牧人的には。
無論、その姿はひとたび客観視を加えれば子供の背伸びに過ぎなくなる。いっそ微笑ましい程に。
しかし思春期の少年という奴は、なにかにつけ自分が子供であることを忘れがちなのであった。
――いいな……!
そうして、牧人はいい気分になった。
元はカッコつけ目的で始めたギターだったが、実は相当楽しんでいるのだった。
……しかし、問題もあった。
その日の夜、牧人は両親に叱られた。
昼間に部屋でギターを大音量で鳴らしたことが原因だ。
「全く、お前もいい歳をして……、近所迷惑というものをだな――」
元々両親――特に母親は牧人がギターをやっていることに関して否定的だった。
むしろ、二人は音楽というもの全般を不健全なものと見なして嫌悪している節がある。
だから牧人は両親の目を盗んで演奏していた。
普段は二人が仕事に出ている昼間を狙って弾いていたのだが、今日はたまたま家にいる日だったことを失念していた。
「大体お前は受験生なんだぞ。そんなことをしている暇があるならもっと勉強を――」
「………………」
この手の小言は俯いて聞き流す。
勉強を強いる両親には辟易したが、食いついたところで無意味だということを長年の抵抗の末に牧人は悟ったのだ。
適度に勉学に勤しむ振りをしたこともある。しかし、上ばかり求める両親相手にはそれも無駄な取り繕いだとわかってやらなくなった。
故に、牧人の学校の成績は悪い。
葦原家は、優秀な家系だった。
企業家としてその業界では名を成している父と、その秘書を務めている母。
どちらも名を出せば驚かれるような大学を出ており、多数の資格も有している。
世間から見れば、立派な人間ということになるのだろう。
そんな両親の教育を受けてきた牧人だ。基本的に能力は高い。
だがしかし、そうした環境だからこそ育まれてしまった強すぎる反骨精神は如何ともし難かった。
牧人は強制を嫌う。抑圧を嫌う。迎合を嫌う。追従を嫌う。
彼の両親は口を開けばそれらの推奨ばかりだ。いい加減嫌になる。
しかし、牧人の対応も慣れたものだ。
彼にとっては無益極まりない説教を上手く聞き流す術も、年齢に比例して上達してきている。
…………だが――、
「それになんだ、そのおかしな髪型は。そうして可笑しな格好をして、皆からちやほやされたいか。目立ちたがりもいい加減にしろ」
「――っ、そんなんじゃない!!」
図星を突かれると反論してしまう牧人だった。
その日の口論は深夜まで続いた。
決着はつかなかった。
牧人も父親も熱狂し過ぎ、とても議論の体ではなくなったところを母親が止めて、渋々双方退いたのである。
とても、後味の悪い結末だった。
牧人は、両親と仲が悪い。
室内に響き渡る生徒たちの合唱。
二重ガラスなどの防音処理が施されたこの教室内は、歌声とピアノの音がよく響く。
曲目は有名な合唱曲だ。
男女それぞれ二パートに別れ、少年少女は迸る若さを歌声に託す。
教員の熱心な指導により、それは素人ながら様になっている。
毎年初冬に開催されるクラス対抗の合唱コンクールはどのクラスも素晴らしいコーラスを披露する、と保護者の間でも評判の行事だ。
今は、音楽の授業中。
時期的にその合唱コンも近い。教師も生徒も練習に熱が入っている。
そんな中、牧人は教科書にあるテノールパートの歌詞を退屈そうに眺めていた。
「………………」
そして、別に唄わない。
ただ憮然とした表情で他のクラスメイトによる合唱を聞き流していた。
牧人は考える。
どうして同じ音楽なのに、授業でやる音楽はこれほどつまらないのだろうか、と。
家でギターを弾くのは楽しい。
始めてから数ヶ月経つ今では、それなりに曲として演奏することもできるようになった。
しかし、音楽の授業は面白くない。
小学校の頃から数えてもう何年もやっているというのに、未だに楽しさが理解できない。
葦原牧人は、音楽の授業が致命的に苦手だった。そして嫌いだった。
それは今やっている合唱にせよ、小学校の時にやった縦笛やその他楽器にしても同様だ。
おまけに牧人は楽譜が読めない。
――どうしてあのオタマジャクシが音を表してることになるんだ?
授業で説明を受けたが何もわからなかった。感覚として理解不能だった。
そうした彼にとっての難解さも理由の一つだが、最も大きな理由は彼自身もよくわかっている。
単純に牧人はプレッシャーのようなものが嫌いなのだ。
だから、やらされている感の強い音楽の授業は大嫌いというレベルで嫌いだった。
同様の理由で習い事というものも嫌いである。
自主的に始めたことでなければ楽しめない。そういう性質をしていた。
「…………」
だから群を成して歌などを唄う、他のクラスメイトを不気味に感じさえする。
彼等はそうやって大衆に溶け込んでいくことの気持ち悪さを理解していないのだ。
唯々諾々と無個性にある。そのような姿勢を強要する昨今の学校教育に対し、牧人は遺憾の意を禁じえない。
……無論それが彼おなじみの背伸び的発想であったとしても。
――つまんねぇ……、帰ってギターの練習してぇ……。
音楽そのものは今や割と好きである。
やってみてわかった。敬遠していたのが勿体ないくらい、音楽というものは奥が深く楽しいものだ。
センスなど気にせず、音楽をもっと素直に楽しんでいればよかったとさえ思った。
今ならあの先輩に声をかけることだってできそうである。
今更感が伴うので別に連絡はしないが。
音楽そのものに対する熱意はそこまででもない。
雑誌か何かでたまに目にする、“いつか自分も音楽で人を魅了できるようになりたい”などという向こう見ずなフレーズには反吐が出る。
――けどまぁ、話の種くらいにはなるか。
純粋に楽しさは感じている。
趣味として楽しみながら続けていきつつ、自慢話の種にでもできれば僥倖だった。
――高校に入ったら、音楽系の部活に入ろう。
バンドを組みたかった。
練習を重ねてきた今ならばそう無様な姿は晒さないだろう。
本当ならクラスの友人でも誘って今から始めたかったが、時期的に今は受験ムードで、そういう発言ができる空気ではない。
――あぁ……、早く来年にならねぇかな……、大体こんな歌唄ったって意味なんか――
「葦原! さぼってるんじゃない!」
見つかって怒られた。
……音楽は楽しいものだ。
演奏するのは勿論だが、聴くだけでも楽しい。
「………………」
だが、音楽の授業はこのように酷くつまらない。
こうした感覚を抱いているのは決して自分だけではないはずだと牧人は思った。
その結果その人が音楽を嫌いになって、本来の楽しさに触れずにいるとしたら、それはとても勿体ない。
今の学校は音感教育を目指しているという話を牧人は以前どこかで聞いた。音楽の授業が子供に与える感受性への影響を意識し、重要視しているそうである。
その真意は不明だが、だとすれば実に余計なことをしてくれていると思った。
「……………………」
教師の叱責の声を受けながら、牧人は改めてそのように教育委員会に対する不審の念を募らせた。
「冬だねえ」
「そうだな」
今日も牧人と明彦は二人で下校していた。
合唱コンクールを目前に控え、空気は肌寒い。
「来週は合唱コンか、だりぃ……、出たくねぇ……」
牧人は明彦の前だとそういうことも言う。
「ははは。牧人は相変わらず行事嫌いだねえ」
そして明彦もそんな牧人の態度を自然に受け止める。
「当たり前だろ。明彦は何も感じないのかよ?」
「うーん、みんなでなんかやってて、楽しくない?」
「どこがだ、かったりぃだけだろ」
一応、クラスではそうした発言は慎むようにしている。
無意味に反体勢的なことを言って秩序を乱しても、反感を招くだけだからだ。
「それにしても合唱コンともなれば、もう今年も終わりーって感じだね」
「そうだな。来年は俺等も高校生か」
何気なく言って、酷く沈んだ気持ちになった。
――受験、か。
面倒である。
越えなければならない障害だけに、反発する意味もない。
「牧人はどこの高校受験するか決めた?」
「いや、まだだけど……」
別にどこでもよかった。相応のレベルなら。
「明彦はどうすんだ?」
「そうだね。僕は平坂高かな」
地元の高校だった。偏差値もある程度高い。
「そうか。……なら俺もそこにしようかな」
「え? そんな単純でいいの?」
苦笑される。
「いいんだよ。平坂って言ったらランクも結構高ぇじゃん。そんくらいなら、ウチの親父たちも納得すんだろ」
「……相変わらず親御さんと仲悪いんだ」
「ん、まぁな……。いいよ親父たちの話は、だりぃ」
「………………」
一瞬表情を曇らせる明彦。
「けど平坂って結構偏差値あるよ? 牧人勉強してる?」
「するよ、今から。そろそろマジになってもいいと思ってたしな」
しれっと言うが、実際はそうでもなかった。
ただ、このまま現実逃避を続けていても埒が明かないと思っていたのは事実である。
……客観的に見れば相当無謀な発言だったが。
こうして、葦原牧人の進路はさりげなく決定したのだった。
冬。
「………………」
牧人は自室でひとりギターを弾いていた。
この時期特有の、冷たく乾いた空気がかすかに音を残響させる。
アンプを通して発される音は大きいが、部屋を満たすのは閑寂な空気だ。
余韻嫋々。
特定の曲を演奏しているわけではない。
ただ何気なく弦を弾いていたのだ。
映画のワンシーンを思わせる。
視聴者のみが感じ得るバックグラウンドミュージック。
逆に、視聴者はスクリーンの向こう側を感じることはできない。
BGMに意識を向ける自分は視聴者だ。
しかし、現実というスクリーンの中にも立つ。
そうした、奇妙な感覚が満ちていた。
客観性が揺らぐ。
自分が溶けて、世界に沈んでいくような錯覚。
「――――」
その危機感を覚え、意識を戻す。
葦原牧人としての形は一つだ。
漠然たる“衆”に属する曖昧な“個”であってはならない。
だが、時に空想する。
完全なる、独立した個たる存在は……果たしてそのことについて何を思うのか、と。
オンリー・ワンを望む意識は、青少年特有のものなのだろうか。
成熟した大人ならば、ワン・オブ・ゼムであることの素晴らしさにも気付けるのだろうか。そうであったことの幸福を感じることもあるのだろうか。
だとすれば、個を主張する牧人も、彼が卑下してきた多くの少年少女同様ワン・オブ・ゼムに他ならないのでは――――
思考を沈滞させるような慎み深い旋律が、自らの手で爪弾かれている。
自身の演奏。牧人はひとり、それを聞いている。
明確な方向性はない。ゆったりとしたリズムで、無為に弦を弾く。
時間は足りない。
学業は煩わしい。
人間関係は悩ましい。
そうしたややこしい色々を全て破却し、ただ音の波に酔う。
不意に感じる。孤独。
しかしそれすらも今は意識の外へ。
漠然と先のことを考えていた。
この先、自分はどんな人と出会うだろうか。
この先、自分はギターを弾いているだろうか。
この先、自分は…………
様々なことを考えながら、
「…………」
牧人は眠っていた。
演奏は途絶え。日は落ちていく。
自室に一人だった。
連れ添う友にそうするように、ギターを優しく抱き締めた。
そして牧人は、中学時代を終える――