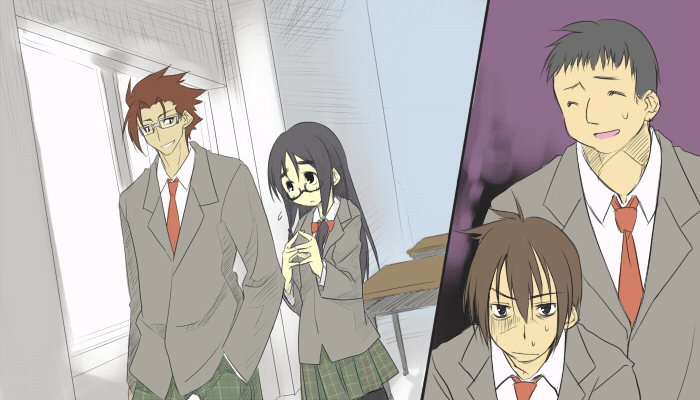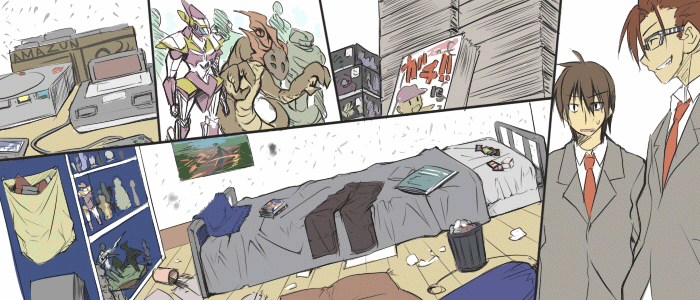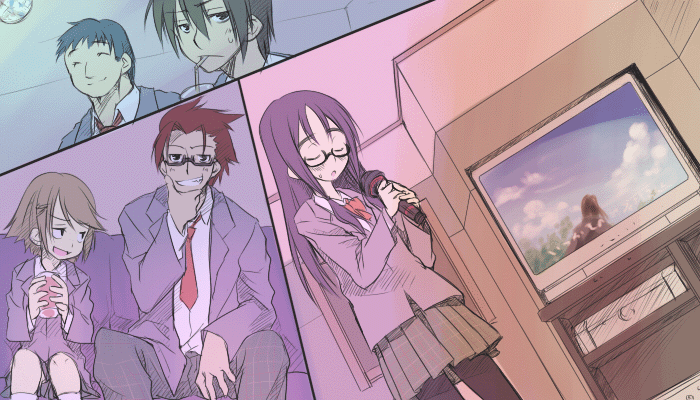吠えない負け犬(仮称)
00
通学路。
「おはよう、マキくん」
朝の日差しの中に彼女はいた。
「おはよ」
牧人は短くそう返す。
テンプレートを嫌うこの少年は、挨拶というものが少々苦手だ。
儀礼的行為にはどうしても無個性な雰囲気がつき纏うからである。
「行くか」
「うん」
けれど、すぐに切り替える。
牧人はさりげない所作で歩を促し、薫も屈託なく笑った。
ここ最近、二人は揃って登校している。
互いに地元民というだけあって、各々の家は割に近所だった。
近頃では牧人が朝食を摂って家を出ると、大体最初の信号で薫と遭遇する。
二人とも、何気なくそのタイミングを選んでいることがわかる。
「だんだんあったかくなってきたね」
「あぁ、そうだな」
彼女の前にいると、牧人は通常時よりも素直になる。
最近では柔らかい表情も増えた。
以前薫に対して感じていた鬱陶しさのようなものも、大分薄れてきている。
対する薫の態度には大きな変化はない。
強いて言うならば、以前に比べて笑顔がより増えた。
牧人が彼女に対して少しだけ打ち解けてきたため、必然的に会話の質が向上したのだ。
そうした自然な会話においては、自然と顔がほころぶ瞬間もままある。
「ふわ……」
欠伸をした。
――眠ぃぜ……。
今やそのように油断した姿も見せていた。
「なに、マキくん寝不足?」
「いや……別に」
薫は微笑するが、牧人は適当に濁すだけだ。
少し前の彼ならば、無意味なうろたえを見せたかもしれない。
それ以前に、彼女の前で欠伸などしただろうか。
感覚的には、唯一の友人である武田明彦に接する態度と似てきていた。
良い意味で遠慮がない。
「おはよう、二人とも」
すると本人が現れた。
「おはよう、明彦くん」
「おはよ」
各々挨拶を交わす。
「ありゃりゃ、牧人は今日も眠たそうだ」
「うるせぇよ。お前だっていつも寝てるみたいな顔してんだろ」
「僕は元からこんな顔なんだよ」
この三人の通学風景も、今や通例になりつつある。
穏やかな風が吹いている。
そんな感じで、牧人は今日もそれなりに生きていた。
01
昼時。
葦原牧人は、気怠げに伸びをした。
どうにも空気がむず痒い。
居心地が悪いわけではなく、単に温暖で浮ついた雰囲気が落ち着かなかった。
牧人は高校二年になった。
クラスの人員も一新されて、顔見知りと初対面の顔ぶれが入り混じる空間となる。
明彦とは今年も同じクラスだった。彼の知り合いだというラグビー部員の男子生徒とも一緒になり、牧人は声をかけられた。
その他にも、前年度の段階で偶々知り合っていた他所のクラスの生徒たちも何名か見かけた。
当然、一年の頃から同じクラスだった連中も散見される。そこには藤宮薫の姿もある。
若く有能だが人望はいまいちの担任教師も一年の時と同じだった。
そのような感じで、馴染み深いようでいてどこか新鮮な日々だった。
そして牧人の立場も似たようなものだった。
去年からの顔見知りとは相変らず微妙な距離がある。
もっとも、一年も共にいれば相応に交流が生まれるもので、そこまで居心地は悪くない。藤宮薫のオマケとして軽い扱いを受けることも別になくなった。
しかし、初期にあった不調和は少なからず影響していて、常に一緒にいるような相手は一年経っても結局できなかった。
そして今年初めて会う相手からも、そうした空気を察されてか、少々敬遠されている。
「…………」
だから彼は今日も一人だった。
だが、それに対して牧人の中に暗い感情はない。
脇役として一年を過ごした彼は、無理をしないことを覚えた。
中学生の頃のように、全ての知り合いに認められる必要などないと思うようになったのだ。
少しずつ。本当に少しずつだが、彼にも余裕というものが出てきたのだろう。
余計な気を使うことはせず、とりあえずは協調すべきタイミングだけ理解しておく。
そう考えれば、日々の生活は案外円滑に回っていくものだった。
クラスでの立場は微妙だったが、幸い彼は孤独ではない。
薫や明彦とは親交を保てている。
彼等と共にいる時にある自然な自分を認識すれば、高校生特有の玉虫色な空気もそう悪いものではない。
この時期の牧人はそのようなことも感じていた。
「あ、マキくん一人?」
一人で学生食堂にて昼食を摂っていると、薫が声をかけてきた。
「藤宮……。今日は弁当じゃないのか」
「うん。今朝は……ちょっと寝坊しちゃって」
「ふぅん」
「ご一緒していい?」
「いいぜ、そこ座れよ」
向かいの席を指示し、薫はそこにトレイを置いた。
「五時間目の数学、宿題できた?」
「いや、さっぱり。計算はどうにも苦手だ」
どちらともなく雑談が開始される。
「計算って、それ算数のレベルじゃ……」
「何でxとか使うんだろうな。わかり難くねぇか?」
「なら、小学生みたいにみかんとかりんご使う?」
「それは――嫌だな……」
「でしょ? あはは」
笑い合う。
「……あ、そういえば今日、学級委員の集まりがあるんだけど」
「あぁ、そういや今日って水曜か……」
今年、牧人は学級委員ではない。
無所属であることが確定した時は、同じ委員会という解り易い関係性がなくなって、彼女とは多少疎遠になるかとも思われた。
しかし、このように二人は会えばそれなりに会話を交わしている。関係は維持されている。
「マキくん、予算の書類とか読み方わかるよね? チェックするの手伝って欲しいんだけど」
「……まぁ、いいけどよ」
そして、このように手伝いをすることもあった。
「よかった。ありがとね」
「……う、うん」
季節は、春であった。
02
少し遡って、一学期開始直後。
牧人のクラスでは今年も委員会決めがHRにて行われている。
何人かが昨年の難航具合を予想し、げんなりした。
昨年の出来事が思い出される。
薫が委員長となり、牧人が副委員長となった。
その当時は急展開に驚愕した、理不尽な理由に憤慨もした。
「………………」
しかし一年が経過し、過去を回想する牧人の表情は穏やかだ。
不平不満を垂れながらも、副委員長としての立場はそれなりに愉快だった。
――今年は……どうすっかな、俺……?
ぼんやりと、天井を眺めている。
「はい」
HRが開始しての沈黙、去年と同じ空気の停滞を見て取ってか、薫は早々に挙手をした。
「他にしたい人が居ないなら、わたし、学級委員に立候補します」
その表情に気負いは無い。
一年の活動を通して、彼女の中にも大分慣れというものが現れてきたのだろう。
そして前年度の彼女の活躍ぶりは多くの生徒が知るところだ。
当然誰も反論しない、むしろ諸手を挙げて彼女の立候補を歓迎した。
「おお、そうか! 今年も頑張ってくれよ!」
担任にとってもこの展開は期待していたところだろう。
かくして藤宮薫は皆の賛同を受けながら、今年も“委員長”になった。
その後も、各種委員が次々と決められていく。
去年あれほど難航した学級委員がすぐに決まって、教室の空気からは殺伐さが抜けていた。
このままスムーズに全てが決まり、時間前に終了して早めに下校できるか、という期待に誰もが胸を踊らせる。
しかし、それから三十分ほど経過し、
「…………」
教室内はまた重苦しい空気が漂っていた。
まだ一つ、席が埋まらない。
――――副委員長。
昨年牧人が勤めていたそのポジションに、また今年も誰も立候補しない。
「………………」
クラス全体が、再び微妙な空気に包まれ始める。
停滞した退屈な空気が、生徒たちの表情に不満感を募らせ始めていた。
そんな中、牧人は何故か右腕を押さえながら教室をキョロキョロと見回していた。
どうにもせわしない。
必死に周囲の状況を把握しようとしているように見えたが、明らかに挙動不審だ。
「誰か、学級委員に立候補する人はいないか?」
担任が言った。
軽い口調は去年と同じ。これで決まるとも思っていないであろう事も、去年と同じだ。
「……っ」
しかし牧人は一瞬反応を示した。
電気でも走ったように、体がびくんと小さく跳ねる。
――どうする? 藤宮と一緒で、俺が挙手するか……?
彼は取るべき態度の選択に迷っていた。
周囲を盛んに気にしながら、自分の行動をあれこれとシミュレートしていた。
……自分が挙手しても不自然ではないだろうか?
…………そのようなことをして、薫との関係を周囲から邪推されたりしないだろうか?
高校生活を一年続けて、人間関係などについて多少余裕は生まれてきても、そうした自意識過剰な部分は相変らずだった。
こういう場に立たされると、どうしても衆目が気になってしまう。
――俺、去年前半はほとんどサボってたし……、ここで俺が何か言っても説得力ねぇって。
頭をがりがりとかいた。
――いや、でも後半は結構真面目に出てたよな……?
「…………」
静かにため息を漏らす。
これでもかというほどの思考のループだった。
禅僧のように自問自答を繰り返している。
思考の循環。
それは停滞と同意である。
自問自答――自ら問い自ら答える、という一連のフェイズには、自ら疑問を起こし自ら解決するといった単純な構造のものはむしろ稀有だ。
最良に到達し解決するなどということはほぼありえない。自問自答とは、言わば尾を喰らう蛇のように、終わらないものとして認識されている。
多くは実力不足や様々な要因による、理想の答えへの不可能性に落胆し、代案たる数多の答えを錯綜させるばかりだ。
足りない力を勢いだけで補える人間などそうはいない。大半は自己憐憫や責任転嫁などによる美しくない理由付けによって断念する、或いは無理に敢行した結果泣きを見る。
牧人には、周囲からの様々な視線を振り切って副委員長として立候補する勇気がまだなかった。
従って、仕方ないと諦めるか、行動する場合は何らかの理由付けを行わなければいけない。
折しも去年、藤宮薫が葦原牧人を推薦した時のように…………、
「せんせー!」
牧人がそんな難儀な思考を抱えていると、一人の男子が声を発した。
「どうした前島? 副委員長に立候補するのか?」
「いいえ、オレじゃなくって。去年も委員長やってた、棗くんがいいと思いまーす!」
前島と呼ばれたその男子生徒は、妙に明朗な声音でそのように言った。
あたかも周囲に言い知らせるかのような、明らかに煽っている口調だった。
――棗……だって?
牧人はその名に強く反応した。
ちょうど教室の中央辺りに座っていたその男子生徒は、突然の指名にも動ぜずに余裕の笑みを浮かべている。
――棗耕平……っ!
そういえば、彼も同じクラスだったのだ。
そして牧人は棗耕平が嫌いだった。
いかなる時も妙に自信ありげで、人を食ったようなにやけ顔が実に気に食わない。
「棗か……確かにお前は去年C組の委員長だったよな?」
「はい、そうですね」
担任が声をかけ、耕平がそれに答える。
この流れは昨年の牧人や薫に少し似ていた。
当人の意思とは無関係に、色々な何かが決まっていく。
「棗は……今のところ何の委員会にも入っていないな」
「そうですね」
だというのに、棗耕平の態度に焦りの様子は全くない。
脚を組んだままというその居住まいは、相対する担任教師すらも嘲っているようだ。
実に大胆不敵である。
「お前が学級委員か……」
教師からするとその態度は少々気に食わないのだろう。若干眉をひそめる。
だが同じ生徒からすれば、その不遜な態度はむしろ見ていて痛快だった。
自然体でありながら、周囲の注意を集める少年。
牧人のように必死な取り繕いによる注目ではない。
薫のように人柄や境遇から好感や同情を持たれるのとも違う。
棗耕平は、ただそこにあるだけで人々を引き付けるのだった。
……いわゆる、カリスマである。
能力よりも性質よりも、その超人間的な個性がまず注目される。
「…………!」
不意に牧人は首を振って、耕平から視線を逸らした。
存在感がある少年だ。何か行動すればそれだけで目立ってしまう。
……目でその姿を追いかけてしまう。
「…………」
牧人は爪を噛んだ。
その姿は……自分がかつて求め、結局届かなかったものと似ていないだろうか……?
「……んなら、せっかく推薦もらったことだし立候補しますかね」
そして、その悠然たる声音が耳朶を打つ。
棗耕平は勢いよく立ち上がり、前方の黒板へつかつかと歩み寄った。
誰もがその動きを目によって追随する。
「よっと」
黒板の前に立った耕平。
未だ何も記されていない副委員長の名前の部分に、素早く自身の名を書き記す。
悠々と縁に白墨を戻し、
「さて諸君、依存はあるかね!?」
背を向けたまま教室全域に問いかける。
……拍手が起きた。
「……はい承認多数と。よろしく頼むぜ藤宮委員長よ」
「あ、はい……」
教壇に立って進行役を務めていた薫に、耕平は告げた。
喝采を浴びてもその立ち居は平常のままだ。
特に喜ぶこともなく、ありのまま彼は皆の激励を受け入れる。
そうした一連の動作は練習したかのようにスムーズで、それだけで注目に値した。
あまりにスマートなその少年の挙動は同級生を一様に忘我させる。
その姿はあまりに決まり過ぎていて、
――くそ、気障な野郎だなぁ……!
皆が感心する中、牧人は一人悔しがっていた。
本当は拍手もしたくなかったのだが、一人だけしないのも不自然だったのでだるそうな動作で手を叩いている。
――皆が決めたことなら、仕方ねぇよな……。
そして負け惜しみのように、心中で言い訳。
ここでもし、牧人が副委員長に立候補していたらどのような結果になっただろう。
「………………」
考えたくもなかった。
学期初め。
そんなことがあった。
03
「……でね、今度牧人も一緒に来ないかって」
「ボーリングか……、そういえばもう二年くらい行ってねぇな」
ある日の昼休み。
牧人は教室で明彦と会話していた。
特に目的のあるわけではない、単なる雑談である。
「でも俺、その日バイトあったなぁ多分」
「牧人ってバイトなんかしてたっけ?」
「あ……」
明彦に問い返されて言葉に詰まる牧人。
そういえば内緒なのだった。そうすることの意味もあまりないが。
「えっと……まぁ、去年の暮れぐらいから……」
「へぇ、そうだったんだ。何やってるの?」
「あの……駅前にある村田ビルっていうところによ……、――――っ!?」
そこで突然、牧人は言葉を打ち切った。
「牧人? どしたの?」
「………………」
明彦の声に耳も貸さず、教室前方の入口を凝視している。
「……おぅい、牧人?」
「静かにしろ明彦」
ぴしゃりと言い放つ。
「…………?」
友人のそんなおかしな挙動に困惑しつつも明彦はとりあえず黙った。
牧人を見る。
廊下の方に注意を向け、よく見れば聞き耳を立てているようだ。
何気なく明彦もそちらの方を見ると、
会話が聞こえてくる。
「……って言われて」
「あー、それで?」
談笑しつつ、藤宮薫と棗耕平が教室に入って来ていた。
「――――」
牧人は、まさしくその二人を睨みつけていた。
その視線は二人を捉えて離さない。
「………………」
「……牧人?」
明彦は再度名前を呼ぶも、牧人は聞こえていないようだ。
「……で、やっぱり変えた方がいいかなあって」
「ふーん、あんまり気にしなくてもいいと思うがねえ……」
席について会話を続ける二人を、
「………………」
牧人は苛立たしげに見つめていた。
そんな姿を眺めて、……明彦は苦笑するのだった。
……またか、と。
ここ最近、葦原牧人にはそのようなタイミングが目立った。
ふと気になって薫の姿を探していること。
そういう時、決まって彼女は棗耕平と一緒にいて、何やら話をしていること。
そして、それを見て妙に腹立たしい気持ちになっていること。
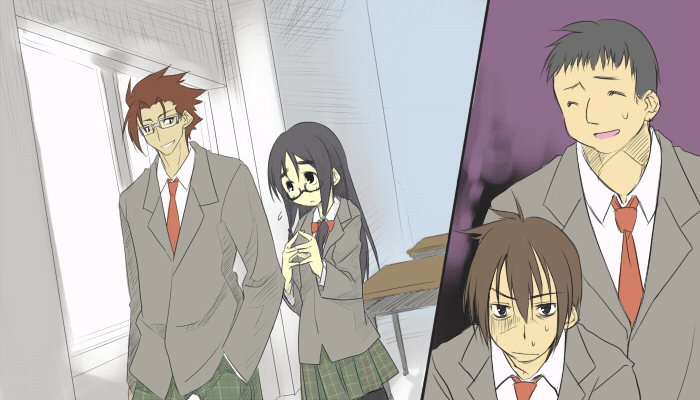
――藤宮……なんで、棗なんかと……。
そしてこのように悶々としていた。
冷静に考えれば、薫と耕平は委員長と副委員長なのだから会話くらいするだろう。
昨年の牧人と薫の関係性のようなものである。自然なつながりだ。
しかし、牧人は気になった。どうにも気になって仕方なかった。
その立場でなくなってからというもの、牧人は二人の間にそれ以上の何かがあるのではと邪推して止まない。
……去年の自分と薫と比較する。
彼女はああも積極的に副委員長たるポストの牧人に話しかけてきただろうか。
牧人は、彼女にとって…………、
「………………………………」
断言できない。
残念ながら、自分が耕平より優位に立てている確固たる自信を彼は持つことが出来なかった。
――まさか……藤宮は棗のことが…………っ?
そして気付けば恒例の意味不明な勘繰りが始まっていた。
だが、少しでもそう意識してしまったが最後である。
もうどうあっても二人の関係にあらぬ疑惑を向けてしまう。
「……ぐ」
かといって、それを本人に聞いて確認するなどということはあり得ない。
牧人にそれを実行する勇気がないのは確かだが、そのような蛮勇は持ち合わせていないのが普通である。
だからこうして歯を食いしばり、悶々と悩んでいた。
そしてそういう時、
――この、棗耕平……ッ!!
悪いのは女ではなく男だと決めつけてしまうのが男子というものである。
……思考停滞から派生する外部への情けない理由付けがここにも存在していた。
まあ、葦原牧人は、自分で思っているよりずっと単純な男なのだ。
元々考えるのは苦手な方なのである。
牧人と薫との関係性は悪くない。
顔を合わせれば会話もするし、よく一緒に登下校もする。
家に遊びに来ることだってある。ギターを聞かせるために。
牧人の知人の中で、牧人の部屋に入ったことがあるのは薫だけだ。
「ふん……」
――だから……藤宮は……っ!
言い聞かせるように。
能力的に劣っていようと、カリスマ的に劣っていようと、耕平に負けたつもりはない。
無論、自分のそうした数値的な色々を敵対する棗耕平のそれと具体的に比較するような真似は決してしない。
……負けた時に受けるダメージを想像すると、恐ろしくてとても無理だったからだ。
だからとりあえず、
そうした自分と薫の関係性を主張するかのように、牧人は棗耕平を睨みつけるのだ。
その点だけでも勝っているとでも言いたげに。
そんなわけで、ここ最近、葦原牧人にはそのようなタイミングが目立った。
……まあ、平たく言うと、ただのライバル視なのだった。
■■■■■■■■■
「なぁ、藤宮」
「……? マキくん、どうしたの?」
その日の放課後、牧人は薫に声をかけた。
昼間に学食で一人食事をしていると、薫が耕平と一緒に入って来たところを目撃したのである。
食べていたカレーを吹き出しそうになった。色々な感情から。
とりわけ、心のどこかで薫と一緒に学食に入れるのは自分だけだと、そんな謎の優越感を抱いていたことに気付かされた事が大きい。
――俺は……なんてダサいことを……!
机に手を突いて自責した。周りの生徒が見ていたが気付かなかった。
一体、自分にとって藤宮薫とは何なのか。
おそらくは昨年の秋辺りから抱き始めていたその疑問。
疑問とは、解答の不明な事柄に関してのみ抱かれるものだ。
ならば、その問いにも隠された解が存在するのだろう。
……しかし、葦原牧人にとって、その解答は、本当に不明なものなのだろうか…………?
よく言う言葉である。
“自分の胸に聞け”と。
問と解が両立し、一つの式として成り立つもの。その解の部分を自ら隠すことで、或いは目を逸らすことで不明なものとする可能性の存在――――
「どうかしたの?」
問い返してくる薫の声で牧人は我に返る。
「いや、あの……」
そしてどもる。
声をかけたものの、何を言えばいいのかわからなかった。
「あ、あの……今日、この後――――」
――……一緒に帰らないか?
……そして俺の家にでも寄っていかないか。
そのようなことをとりあえず言うことにしたが……、
「あっ、もうこんな時間……!?」
時計を見つつ、薫は席を立つ。
「ごめんねマキくん! わたし今日、棗くんと待ち合わせしてるの!」
「………………は?」
牧人はフラれてしまった。
しかも、彼がとても嫌っている男の名前を聞いた気がした。
「じゃあね、マキくん。また明日!」
慌しくもきちんと挨拶をして、薫は教室を飛び出して行った。
いつの間にか大して苦手ではなくなっていた笑顔を見せながら。
対して、一人残されたこの男。
――……藤宮…………俺がどんな勇気を出して声を…………。
貧血を起こしそうになっていた。
――棗と約束って……まさか、まさかだよな……。
先刻、二人が仲良さげに談笑していた姿が、フラッシュバックする。
そんな表情を浮かべる二人が待ち合わせて向かう先と言えばどこだろう?
自分以外の人間に向けられた――自分だけが知っていると思っていた笑顔が、フラッシュバックする。
……葦原牧人、
「――ッ!」
走り出す。
……遂に限界が訪れた。
それはもう、途方もなく情けない嫉妬であった。
■■■■■■■■■
そして、
牧人は電車に揺られていた。
徒歩通学の彼が電車に乗っているとはこれいかに?
「………………」
いつもの仏頂面が、今日は輪をかけて険しい。
彼が優先席に座っているのは、そこが空席だったからではなく、隣の車両を見ることが出来るからだ。
……大体、平日の午後である。座席はほぼ全て空いていた。
「………………」
連結部の脇に設けられた小窓を覗く。
隣の車両にもある同じ窓を通して、中の様子がよく見えた。
牧人は視線を一点に向ける。
車両内に見られる平坂高校の制服姿――その二名を注視する。
扉の脇にある手すりに掴まる一組の男女。
藤宮薫。そして棗耕平だった。
「………………」
鼻息が荒くなりかけた。
あの後、薫は昇降口の辺りまで駆けて行き、しばらくそこで立ち止まっていた。
数分経って、長身の男子生徒がおもむろに現れた。
……言うまでも無い。棗耕平である。
二人はしばらく雑談を交わしていたが、そのまま何処かへ向かって歩き出した。
そして、現在…………。
牧人は二人を尾行していた。
……ぶっちゃけ、ストーカー野郎だった。
幸い牧人の行動は妙に迅速であったため、同じ平坂高校の生徒に、この恥ずべき姿を見られることはなかった。
――何やってんだろ、俺……?
そして牧人自身も、自分の制御不能具合に困惑していた。
薫と耕平、二人の動向を探ることが、如何なる結果を自身にもたらすのか。
牧人が抱く心配(恐怖)が現実のものであったなら、その生々しい現場を目の当たりにし、絶望と敗北感に打ちひしがれることになるのだろう。
逆に杞憂であったなら、今の自分の行為がいかに馬鹿馬鹿しいかを思い知り、また脱力するのだ。
しかし、いずれにせよ見つかれば全て終了である。
結果がどちらであったにしても、こそこそ尾行などしていることが露見すれば、今まで築き上げてきた様々な要素が全て水泡に帰すだろう。
リスキーに過ぎる。二人の仲を探るにしても、もう少し上策はなかったものだろうか。
何も考えずに行動してしまった自分が今となっては口惜しい。
しかし、ここで引き返すということを許してしまって良いものだろうか。葦原牧人というものが。
……無理なのだった。いつだって牧人なのだ。
「次はァー……」
妙に間延びした車掌のアナウンス。
駅名が告げられると同時に、牧人の視線の先にいた二人が動き出す。どうやら下車するらしい。
――!
慌てて牧人も降りる準備を始める。
出口へ向かう二人に気取られないように、車両を出るタイミングを上手くずらす。
偶々大勢の人が下車したことは、牧人にとって都合が良かった。多過ぎず少な過ぎぬ人ごみは、身を隠すにはちょうどいい。
――ここが目的地?
少し戸惑う。下車駅は急行電車なら通過してしまうような小さな駅だった。
周囲も住宅街で、遊べるような場所もあまりなさそうである。
このような場所に来てどうするつもりなのか。
牧人はますます混迷してしまいそうだった。
そんなことをやっていたからか。
――って、あれ……?
牧人は必死に人波を見渡した。
共に下車した人々は次々と改札を抜けていく。
その先頭付近を歩いていた少年少女の姿は、もうとっくに駅の外だ。
――やべぇ……。
見失った。
……一時間程経過。
「…………」
牧人は駅前の自販機でコーラを買った。
緊張によるものか、喉が乾ききっていたからだ。
初夏の気候に黒色の炭酸飲料は実に美味だった。
――そんな場合かよ……。
一口で飲み終えた缶を捨て、うなだれた。
――俺、マジでなにやってんだ……?
自覚した。
今の自分はものすごくカッコ悪いと。
結局、やって来た駅で牧人は二人を見失った。
しばらく闇雲に周辺を探したものの見つからず、あろうことか駅に戻ってくる途中で道を間違えた。
再び駅前に戻ってきた時には既に二十分近く経過していた。
これだけ時間が過ぎている。未だに彼等が駅前に留まっているなどという都合の良いことはないと思われた。
これ以上の追跡続行は不可能と見るべきだろう。
しかし、そこで諦め切れないのもまた牧人である。
このまま帰れば良いというのに、そうした時の後味の悪さを予想すると足が動かなかった。
だが、留まったところで何も出来ない。
懊悩した。
彼女が自分の嫌いなあの男に笑顔を向ける様を想像して、地団太を踏むことくらいしか。
彼女が自分の嫌いなあの男に体を開く様を想像して、歯軋りをすることくらいしか。
そんなことしかできない自分に。
そしてそんなことをしたところで、無様なだけだと牧人は知る。
……それ以前に、そんな想像をする資格が果たして自身にあるのかどうか。
恋人でもない、ただの友人に過ぎない自分が、ある少女についてそのような被害妄想じみたビジョンを浮かべることを許される立場にあるのかどうか。
その自己嫌悪は自慰のように滑稽だ。
その自虐はいかにも高慢さが滲み出ていて苛立たしい。
結局のところ先を越された焦りと、それを許した無力な自分が許せないだけなのだ。
だけど、そんな自分を認めるのも嫌で、牧人は無意味に彷徨している。
帰宅すればそれは敗北。残留しても勝利は見えない。
懊悩していた。
「――あーぁ、……くそっ!」
自販機を蹴った。
そんな自分も嫌になる。
更には、
「おい、物に当たるのはよくないぜ?」
声をかけられ振り返る。
「――随分機嫌が悪いみたいだな葦原。何かいいことでもあったのか?」
そうして当人に見つかってしまう自分は死んでしまえと思った。
……思うだけだったが。
中身の伴わない気取った自己嫌悪は、眼前の男に対する憎悪に変換された。
■■■■■■■■■
「棗……!」
「恐い顔してんなあ」
駅前のロータリーにて、両者は対峙した。
バス停に人気はなく、道を走る車も疎らな午後。
二人の少年が睨み合っていた。
……いや、その表現には語弊がある。
牧人の方が一方的にガンを飛ばしているだけで、耕平の方は相変らず涼しげだ。
彼は一人だった。
周囲に薫の姿は見えない。
「お前、こんなところで何やってンの?」
「………………」
何気ない調子で問う耕平。
牧人の自宅が学校の近辺であるとの情報は彼には伝わっていないはずだ。
「……お前んちってどこだっけ?」
だとしても、牧人の地元駅がここである可能性の低さを耕平は察しているのだろう。
「…………」
しかし牧人は答えない。
相手を納得させられるだけの解答を用意していないこともあったが、仮に言い訳が思いついても耕平への対抗意識が口を開かせなかっただろう。
「ふぅン……」
対峙する少年も、何故自分がここまで露骨な敵意を向けられているかを推理し始めることにした。
ひょうきんな態度の目立つ棗耕平だが、彼は思考の回転はかなり速い。
牧人などよりはずっと流れを察することの出来る少年である。
元々はそうした明晰な姿こそが彼の本性なのだろう。
普段の気軽明朗な姿は対人関係の中で培われてきた非常に優れた仮面なのだ。
仮面――それは牧人のように無理な背伸びをした虚構ではなく、必要性から自然と身についていったものだ。
意識せず出せるようになったそうした対人姿勢は、あつらえたように彼の顔によく収まっている。
……それはさておき、耕平は思考する。
思えば、自身――棗耕平は葦原牧人に最初から嫌われているように思われた。
明確にその嫌悪感が表出し始めたのはごく最近のことだ。視線をよく感じるようになった。
だが、初期の頃から牧人は耕平の存在を好ましく思っていない風であった。
二人が最初に互いを認識したのは果たして如何なる状況だったか…………、
「……む?」
そこで、耕平は思い至る。
触れていたおとがいから手を離し、牧人を見やる。
「なーるほど……そういうことか?」
にやり、と笑った。
「……っ!」
その悠々とした笑みに牧人は戦慄した。
何がしかの行動が開始されるのを感じたからだ。
「なあ、葦原クンよォ……」
耕平の表情は不敵な笑みのまま固定されている。
その静かな態度が余計に牧人の焦燥を誘った。
脅迫には緩急が重要であると言われている。
直前まで静かに微笑んでいた相手が、突然自分に向けて怒鳴り声を上げるという展開には余程肝が座っていなければ驚懼させられるものだ。
恫喝を生業とする暴力団員や博打打といった手合は、その使い分けを見事に行う。
この時の棗耕平の態度は、そんな得体の知れぬ恐怖を牧人に与えた。
歯を食いしばり、ひたすら警戒する。
敵愾心を眼球に集中させ、放つ視線は刃の鋭さを意識する。
――お前なんかに……負けるか!
その姿は、それだけ見れば雄々しさすら感じさせる。
反骨もここまで来れば立派なものだと思えなくもない。
しかし、
「お前これから暇? よかったらウチ来ねえ?」
「…………」
耕平のその言葉で、牧人は一気に力が抜けた。
「オレんちってこの辺なんだ。せっかくこっちまで来たんなら寄ってけよ、茶でも飲み交わそう」
すぐそばまで接近し、馴れ馴れしく肩を回してくる。
「……っ、なんだ、よ」
「実はオレ、前からお前のこと面白いヤツだと思ってたんだよねえ。いい機会だから親睦会しよう、な?」
「ちょ、ちょっと……!」
そしてそのまま強引に連行されてしまう。
押しに弱い牧人は上手い拒絶の言葉も浮かばず、のたくたとついて行くだけだった。
数分後。
「…………」
何も知らずに駅に戻って来た藤宮薫が改札を抜けた。
ちょうど二人が睨み合っていた場所を通過して。
耕平のこの優れた機転を牧人は知らないままだったという。
■■■■■■■■■
「ウェルカム・トゥ・オレルーム」
「…………」
ずるずると耕平の家まで連れてこられ、部屋に通された。
――なんで、こんな……。
まだ自分の状況に納得することができない牧人だった。
「どした? 早く入りなさいよ」
「お、おう……」
踏み込む。
「――!」
何かが足に引っ掛かった。
慣性の法則により、牧人の体は上方だけがそのまま直進しようとする。
「うおっ!?」
結果、つんのめる。
それを必死に留めながら、足元――牧人の足先が引っ掛かった何かを見た。
……サンドバッグだった。
「……………………」
――なんでこんなモンが部屋の入口に……!
危うくこけるところだった。
「ん? あぁ、スマンスマン。別にそれは気にしないでいいよ」
耕平は脇から足を入れて、その円筒状の砂袋を無造作に部屋の隅に転がした。
改めて、室内に入る。
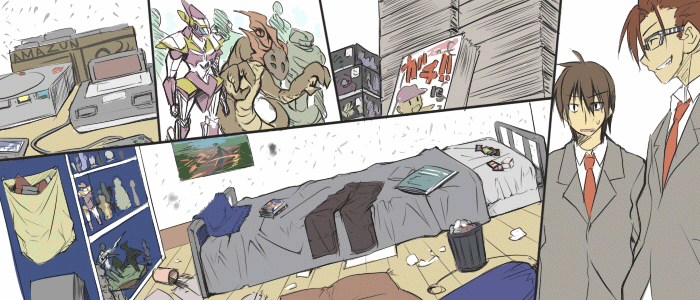
「うわ……」
カオス空間だった。
牧人の部屋も決して整っている方ではないが、散らかり具合ではこの部屋には遠く及ばない。
脱ぎっぱなしの衣類、放り捨てられた雑誌、ゲームやプラモデルの空箱、サンドバッグ、各種トレーニング機器、そして諸々のゴミ。
それらがとにかく無秩序に床に散らばっていた。
バベルのように平積みにされた各種コミックは天井に届く。
本来それらが収まるべき場所は、無数のプラモデルやフィギュアで埋め尽くされていた。
勉強机と思しき台も状況は似たようなものだ。教科書や筆記具の類はどこにも見当たらない。棚に収まり切らなかった玩具と、何故か調味料と包丁セットが並んでいた。
……そのような感じで。
棗耕平の部屋は、少年としての彼の心が見事に閉じ込められていた。
部屋の全てが遊び道具で構成されていると言っても過言ではない。
玩具箱をひっくり返したような、という表現が的確すぎた。
「まあ、突っ立ってないで座れよ」
どこに座れと言うのだろうか。
座椅子のようなものが見えたが、その上に陣取っているのは剣玉やヨーヨーなどの古惚けた各種玩具が詰まった段ボール箱である。
「……どこに座れと」
「まあ待ってろ」
部屋の隅に置かれたトンボを手に取り、耕平はがちゃがちゃと物をどけていく。
夢の島が一回り肥大化する代わりに、二人が座れる分のスペースができた。
「ほれ」
「…………」
どこか釈然としないまま、牧人は床に腰を下ろした。
そして、低い視点から室内を見渡す。
――もう、どこからツッコめばいいやら……。
とりあえず色彩的に目立つ本棚を見た。
各種プラモデルやガレージキット、ソフトビニール人形、食玩、アクションフィギュア等々……。
いわゆるキャラクター物も多いが、全体から見れば特撮映画やロボットアニメに登場した怪獣や機体がほとんどだ。
往年の戦隊ロボットから現代の変身ヒーローまで、新旧入り乱れている。
牧人も幼少期に見ていた格闘アニメのヒロインが、ワニガメをモチーフにした大怪獣に戦いを挑んでいる光景は見ていてなかなかシュールだった。
「棗って……、そういうの好きなのか?」
指差しつつ聞いた。
「ん? こいつらか、好きだぜー」
一つを手に取る。
年季を感じさせる超合金だった。先程の玩具箱といい、随分と物持ちが良いようである。
「今からでもこいつに搭乗して地球の平和を守りたいくらいだな」
「は?」
「そんくらい特撮とロボアニメはオレの人生の大半を構成しているってことだ」
超合金を棚に戻す。
「そ、そんなにか……」
思わず尻込みした。
牧人も一般的な男子である。
幼少にはそのようなものを視聴したこともあった。
しかし、ここまで愛着を覚えることはなかった。造形物に手を出したことはない。
対して耕平の方は模型の数や種類からも、未だに収集を続けていると見ていいだろう。
「ユニバァァァス!」
不意に叫び出した。
「……宇宙?」
「ふん、わかってねーなあ」
鼻を鳴らした。無粋な牧人を見下すように。
棗耕平は今、限りなく女王親衛隊隊長なのだ。
「なんか、ガキっぽくねぇか……そういうの」
「カッコつけちゃってまあ」
牧人は嘲笑気味に呟いたものの、耕平の態度はあっさりしたものだ。
「ガキ臭くたっていいじゃん、好きなんだから」
「………………」
「お前だって好きなモンの一つや二つあんでしょうに。オレにとってのそれが、たまたまこういうオモチャとかマンガとかだったって話よ」
それは、達観した態度だった。
幼さを感じさせる趣味に関して感じる気後れなど、微塵も持ち合わせていないようである。
「んまあ、こんなんただの趣味だし。それだけでオレという人間が判断されるわけでもねー」
「……そう、かな?」
「そだろ? 現にお前はこうして大悪獣ギロンを手にするオレを見て、オレに対する見方が変わったりするのか?」
フォルムが出刃包丁によく似ている怪獣のソフビ人形を突き出す耕平に、牧人は思わず気圧された。
「いや、それは……」
大局的に見れば変わらないのだろう。
普段の棗耕平の能力の高さと社交性を知っていれば、見下す気持ちが今更生じることもない。
しかし、そうではない可能性――幼稚な遊具や漫画を好むその姿を、下卑たものとして嘲弄する相手を想定することはないのだろうか。
「だからさっきも言ったでしょうよ。オレは自分が好きだということを素直に認めてるだけだっつの」
しかし彼は朗々と告げた。
「ガキくさいことは自覚してっから馬鹿にされたって構わないし、興味ないヤツにまで強要したりしねーよ」
そして苦笑しつつ、手にしたフィギュアを棚に置く。
先程から見せている堂々とした態度は、発言の最中にも揺るがない。
それは、彼が普段から見せている余裕ある姿とも、通ずるところがあった。
「………………」
――ああ、そうか……、
牧人は心のどこかで思った。
彼の持つ能力の高さやカリスマに対しては確かに羨望や嫉妬を抱いたことはあった。
しかし、もしかすると自分は、
彼のそうした本心を偽らない部分こそが、本当は最も羨ましかったのではないか、と。
人は様々な理由を付与することで、本来の感情を隠し、心を見栄え良く装飾する。
そうしたことをせず、ありのままの心を保つとは言うは易く行うに難い行動だ。
牧人はそれが出来ない。
体裁や衆目を意識しては、今の自分の姿を常に気にしている。
結果、感情を――好き嫌いを無視し、その果てに無理が生じている。
自分でも気付いてはいた、しかし今更やめることも出来ずにいたのだ。
「あーぁ……」
「ん?」
やおら天井を見上げてため息をつく牧人に耕平は首を傾げた。
――俺、何考えて生きてんだっけ……?
不意に自分の心がどこに向いているのか、牧人は気になった。
今まで色々な何かを気にして呼吸をしてきた彼だったが、そうした色々を取り除いたその心は、一体何を映し出すのだろう。
そうした可能性が、どこまでも広がる虚空のようで、眩暈がした。
世界は、自分は、見限れるものではない。
――俺ができることって……、
少年は想像した。
――俺が好きなものって…………なんなんだろう?
自身の、広がる可能性を。
――俺が好きな人って…………誰なんだろう?
それは、美しい気分だった。
のであるが。
下ろしていた腕を何気なく後方に伸ばした。
床に手を突いて体を支えようとする。
「ん――――?」
すると、手に何かが当たった。
特に意識もせず、その物体にさわさわと触れた。
表面は妙につるりとした感触だった。指先に若干のぬめりを感じる。
そして、なんだか微妙な温度。湿り気を帯びている。
――なんだ……?
どこか不快で、それでいて覚えのあるその感覚が気になって、牧人は前を向いたままその物体をつまんだ。
自分の目の前に引き上げて、
「――――ッッッ!?!」
呼吸が止まった。
人差し指と親指によって吊るされ、眼前に晒されたソレは、予想を遥かに超越する生々しさを以って牧人の脳髄を打ち砕く。
――こ、こ、こ…………!
思考も上手く紡げない。
凝視してしまう。
オブラートなどによく似た薄く透明な皮膜による袋状のソレは、白濁した謎の液体を内部に含有し、口蓋垂のような形状のまま垂れ下がっていた。
手には僅かなべたつき――それは使用時の違和感を減らすためのゼリー状潤滑油である。
しかしこれは使用後のものだ。牧人が感じた粘性の物質も、別の何かである可能性が充分に想起された。
……それは、望まれない命が生まれないようにするための便利なゴム製品だった(使用済み)。
主に薬局やコンビニエンスストアで購入でき、最近では専用の自販機も見かける。
明るい家族計画を謳っている種類もある。
幕末の新撰組局長の苗字などでよく暗喩されることもある。
……まあ、明言はしない。そのようなものだった。
牧人は、
「……っ、は…………」
虚脱した。
「あ!」
牧人がそれを観察するようにぶら下げているのを耕平は発見したが、
「悪い、昨日彼女が来ててさ。そこにゴミ箱あるから捨てといてくれ」
こともなげにそう言った。
まるで気にしていない。
「って、そう言えばお茶出すって言ってたんだよな。待ってろ、とって来る」
そしてばたばたと部屋を出ていった。
……ひとり、取り残されて、
「………………ま――」
使用済みゴム製品を放り捨てて、牧人はがっくりと床に手を突いた。
――負けた……。
そう思ってしまった。
負けず嫌いなこの少年において、それは非常に珍しい感情でもあった。
いつもの強がりを吠えることすらできない。
そのぐらい、完全に負け犬だったのだ。
運ばれてきた麦茶を一気に飲み干して、なんとか沈静化を測った。
「おー、いい飲みっぷりだなあ」
敗北を認めれば気分はむしろ清々しい。混乱はすぐに収まった。
「………………棗って、彼女いたんだな」
意外そうに言ったつもりだったが、なんだか白々しく聞こえた。
にじみ出る悲哀がまるで隠し切れていない。
――そりゃ最近、あんだけ親しげに喋ってればな……、一線超えちまってても不思議じゃねぇよなぁ……、はあぁ……。
自分がもたついている間に、全ては終わっていたということだ。
今更もう何を言っても惨めなだけだと牧人は痛烈に感じた。
すぐ背後にあるベッドを見た。
「はぁーあ……」
そこに横たわる彼女の姿を幻視して、更に絶望的な気分になる。
「……おい? なんでオレに彼女がいて、そこまで落ち込むんだ?」
「うるせぇな……」
もう取り繕っても無駄だと悟り、牧人は惜しげもなくため息をついた。
「棗が……」
――藤宮と……。
敗北であった。完全な。
「んな意外かよ、心外だな」
「二人は……いつから……」
「あ、……なんでそんなこと聞くんだ? 高校入ってちょっとしたらだよ」
「……………………」
――ま、マジかよ…………?
再度、牧人は心の海淵まで沈没した。
少しずつ浮上していたところを深海に送り返される感覚。
――高校入ってちょっとって……、一年の最初、か……?
早過ぎた。自分が交流を持つより先ではないかと思われた。
どうしようもない程の手遅れによる後悔と、そのような状況で気を揉んでいた道化な自分の滑稽さが牧人の心に雪のように降り積もっていく。
心の居場所は深海で心の気候は豪雪だ。およそ人が生きていける状態ではない。
しかし、
「まあ、お互い家も遠いし学校も違うからそんな頻繁に顔合わすわけじゃねえけど」
「…………え?」
その発言で牧人は再び地上に引き戻される。
――学校が、違う……?
「棗――今、なんて……?」
「はぁ? だから、彼女他校だから普段そんな会えねえって…………ん?」
「――――――」
――ま、まさか……俺の、勘違い……? 棗は、藤宮とは……、
牧人は、心がふつふつと活力を取り戻していくのを感じていた。
そして耕平は先程からの牧人の不審な発言の意図がようやく掴めて来た。
「葦原は彼女いねえのか?」
にやつきながら、探るように耕平は問いかける。
「……い、今はいねぇよ」
牧人は何故か時間的限定を付言した。
「藤宮とかどうなんだ? 二人仲良さげだけど」
「ふっ――げほげほっ!?」
そして豪快にむせる。
「あー、はいはい…………」
その反応で耕平の予測は確信に至った。
葦原牧人――彼はいちいち解り易い。
これで天然ものだというのだから、まぁ、ある意味大した男だった。
「にしても、その反応は満更でもないって感じだな?」
「ばっ、お前――誰があんな地味な女と――!」
「ほほぅ? 藤宮は趣味じゃないと」
「……いや、その……嫌いってわけでも、ねぇけど…………」
「ふーん」
「なんだよその馬鹿にした顔は!?」
「……なんも言ってないでしょうに」
喋りながら、耕平は笑いを噛み殺すのに必死だった。
「……むぷぷ」
そして漏れた。
「お、お前だって……最近藤宮と仲良いじゃねぇかよ」
気付けばそんなことを口走ってしまっている牧人。
「あー、そうね。学級委員でダベる機会も増えたしなあ」
「ほ、ホントにそれだけかよ……?」
「……だから彼女いますからオレサマ。そんなにオレがたらしに見えるんスか葦原先生」
言いながら、既に言葉の端々で笑みを漏らしている。
「だって、学食とかでもよく一緒にメシ食ってるし……」
そして牧人も最早ノンストップだった。
「まー、最近はね。ちょっと相談に乗ってたし」
「相談……?」
「藤宮さ、なんかメガネ買い換えたいらしいのよね。んで、彼女今すげえ地味なの使ってるじゃない?」
「……メガネ?」
牧人の視線は自然と耕平のそれに向く。
「んで、今度はオレがかけてるみたいなのにしたいらしくって。いい店がないかと聞いてきましてね」
「……え? え?」
「ちなみに今日その店まで案内してた。ウチの地元にあんのよ」
「……………………………………」
「で、役目を果たして帰宅しようとしたら駅前で君が不機嫌そうにだね――――おい葦原? 聞いてまちゅかー?」
「――! 聞いてるよ、気持ち悪い猫なで声すんな!!」
「超絶上の空だったジャンお前」
「そ、そんなことねぇよ! ああもう、くそっ! ああー!!」
強い口調で反発したかと思えば頭をがりがりとかきむしりはじめた。
「あーぁ、あはははは……」
そして妙に乾いた笑い。
清々したようなその姿を見て、
「ぶっ――!」
……棗耕平、
「ぶわははははははははははははははは!」
笑い出す。
……遂に限界が訪れた。
その後、耕平の軽口に適度に応じながら、日が沈んだ辺りで牧人は帰宅した。
帰り際に浮かべた表情は、実に気分が良さそうなものだったという。
まるで憑き物が落ちたような。
気付けば自分に向けられていた敵意のような気配が、かなり緩んでいることに耕平は気付くのだった。
「あー、もしもし? ゴミ子か?」
牧人の帰宅後。
耕平は自室で電話をかけた。
「今日な、すげえ面白いダチができた。明日お前にも紹介するわ」
何かが、動き出していた。
04
次の日、
牧人はいつも通り薫と明彦と三人で登校していた。
その日の朝、牧人はとても機嫌が良かった。
「なんか、マキくん楽しそうだね?」
「ん? そんなことねぇよ」
その理由は昨日の棗宅訪問にある。
この所、薫と耕平の関係に疑念を抱いていた牧人だったが、それが杞憂に過ぎないということが判明したのだ。
薫が耕平に盛んに接触していた理由が明らかになり、なお且つ耕平には恋人がいるということが解ったのである。
部屋に落ちていた例のゴム製品がその証拠物件だ。
「………………」
それについて追想すると、昨日見せつけられた様々な差を感じて別の意味で落ち込みかけもするのだが……。
とりあえず、棗耕平は藤宮薫に手を出そうとしているわけではないと知って牧人は安心したのだ。
――あーぁ……、俺もつまんねぇことをグチグチ悩んでたもんだぜ……。
こういう切り替えは早いのが牧人だ。
今ではかつての思考が馬鹿馬鹿しい。二十四時間前の自分はもう蔑みの対象である。
「おい、牧人」
登校していた牧人を呼び止める声がした。
「ん……?」
声に覚えがあって、振り返る。
そこには――
「よう、偶然だな」
「耕平か――って、」
昨日自宅を訪問した棗耕平がいて――
「……あ、棗くん」
「おはよう」
「お、藤宮と武田もいたか。一緒に学校行くぞ」
「あれ、そっちの女の子は……?」
「棗くんの知り合い?」
「ウッス! あたし、芥川なつめといいまっす! ソーセキ先輩にはいつもお世話になってますっ!」
威勢良く挨拶をする小柄な少女がいた。
「………………」
牧人は初めて見る顔だった。
背が低く、細く華奢な体格をしている。
体躯に見合った高い声だが、声量はあり快活な印象だ。
「ソーセキ言うなっつーのよ」
「先輩の苗字言うと、自動的に出てきちゃうんすよ」
並ぶ耕平の腕に飛びつく。
身長差があるので、腕を水平に上げれば地面に足がつかなかった。
無遠慮な身体接触――親密な関係が予想された。
だが耕平の彼女は他校の女性という話だったので、平坂高校一年の制服を着ている彼女は、おそらくただの友人なのだろう。
「芥川さん……、一年生、だよね?」
「うぃっす、そですよ。なんで、皆さんよか一年ガキンチョです」
「貴様がガキ臭いのは年齢に始まった話ではないぜ」
耕平が鼻をほじりながら言った。
「なんですよ先輩その言い方はー!? このオトナノオンナであるあたしに向かってなんて失礼な物言いをー!」
「お黙れチビ娘。中学校は逆方向だぞ」
「むぎぃー!」
「フハハハハ!」
そして、会話のテンションが高い。
――なんだ……?
そんな二人の姿を見て、
「………………」
先程まで晴れやかだった牧人の心中に、また何かがわだかまっていく。
「二人は……仲、良いんだね」
「これも何かの縁ということで、先輩がたとも仲良くさせて頂きたくー」
少し気圧され気味の薫に、芥川なつめは勢いよく頭を下げた。
「……こいつ、ヘンな子だからクラスに友達いねえんだそうだ。だから仲良くしてやってくれ」
「んなフォローいりませんから先輩! そしてちゃんと友達もいますかり!」
「あはは。よろしくね、なつめちゃん。わたし、藤宮薫」
「武田明彦、よろしくー」
会話の流れで二人は自己紹介。
「はいっ、よろしくおねがいしまっす」
敬礼をした。
「………………」
「……んで、そっちのクールなお兄様は?」
「そいつが昨日喋った葦原牧人だ」
黙している牧人に代わり、耕平が紹介した。
「おお! お噂はかねがね!」
握手を求められる。
「ん……」
曖昧に応じると、手を掴まれてぶんぶん振られた。
解放される。
「アシワラ、マキト先輩……マッキー先輩って呼んでもいいっすか?」
「あ?」
「決まりーっ、よろしくっすマッキー先輩」
太陽のように笑いかけられた。
――………………。
だというのに牧人は、
――耕平って……女なら手辺り次第ってわけじゃ、ねぇよな…………。
……などとまたしても余計なことを考えていた。
どこまでも疑り深い少年である。
彼の心中に再発した危機感について語るのは最早無駄な様子なので、ここで一旦記録停止――――
■■■■■■■■■
そしてその日の放課後――
「おい牧人、行くぞ」
突然耕平が牧人の席に現れた。
「行くって……なんだよ突然?」
「見ろよ牧人、今日は死ぬほどいい天気だぜ」
窓辺に乗り出した。
「てめぇは少しは俺の話を――!」
「いいか牧人、これからオレとお前、あと今朝会ったチビ娘の三人でカラオケに行く」
「はぁ!?」
そんな予定は一言も聞かされていなかった。
「毎度いちいちデカい声を出すなあ、お前は。何かいいことでもあったのか?」
「カラオケって……なんでそんな、いきなり……!」
「昨日色々喋って、オレはお前のことが気に入った。だから改めて親睦会する」
「親睦会ぃ……?」
何から何まで強引に過ぎた。
言いたいことが山ほどあって、逆に何も言えなくなる。
「せっかくだから藤宮とかも呼ぶか。カラオケは五人くらいが一番楽しい」
言うや薫の席の方へ歩いて行ってしまう。
牧人のことなど二秒で忘却してしまったかのような素早すぎる切り替え。
「おい、待てよ――!」
無視されるのが嫌いな牧人は追いかけてしまう。
基本的に流されやすい牧人である。
強力な空間操作力を有する棗耕平を論破できるはずもなく――――
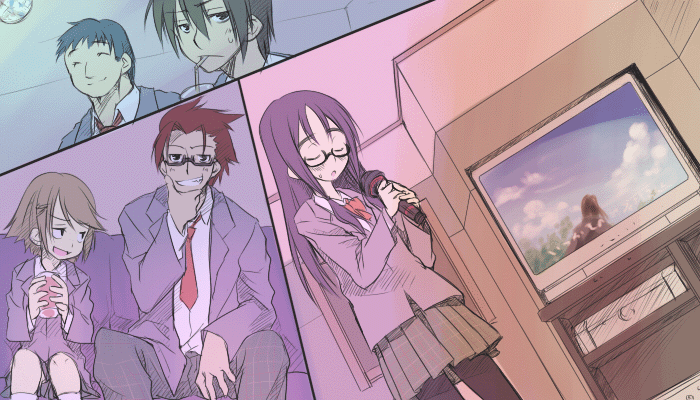
「はじまりはと~も~だちぃ、いつかその境界線こ~え~てぇ~♪」
……気付けば、カラオケ大会なのだった。
「ふふん、唄い慣れない女子が頑張って唄ってんのはどうして見ててこんな楽しいんだろうな?」
「ヘンタイですねソーセキ先輩」
「だから、ぜんぶ抱きしめて~♪ いつもあなたのそばにいるぅぅ~♪」
藤宮薫、十六歳。
……少々、音程が残念なことになっていた。
「わー、カオル先輩かわいーっすー!」
「あ、どうも、どうも……!」
他の面子からの拍手にぺこぺこ頭を下げる薫だった。
「は、恥ずかしいね、一番最初って」
すちゃっと着席。
「ジャンケンによる正当な決定だ、大人しく従うがいいぜ」
「ほっとくと、ソーセキ先輩とあたししか唄わないっぽいですしね」
「…………」
「……………………」
なつめが流し見たのは牧人と明彦の二人だ。
場慣れしていない男二人は揃ってジュースを飲んでいた。
「で、次はゴミ子の番と」
「あーい、いきますー」
マイクを手に起立。
……で、熱唱。
「あぁ~、刹那ボクが夢見るあの世界ぃ~、光り輝くぅう、世界ぃを~♪」
芥川なつめ、ヴィジュアル系好き。
「ふ、普通に上手いね……」
「……声が高いからな」
拍手をしつつひそひそと薫と牧人。
「やーやー、アリガトゥ、ゴザイマスー」
歌声を引きずるような形で応える。
「やはは、カラオケはやっぱいいですねー」
座席にダイブした。小柄なのでそこまで迷惑でもない。
「……お前ってば、いつもあんなんばっか唄うよなあ」
「カコイイじゃないですか、ブイブイ」
「よーわからんぜ。……っし、次はオレだ!」
マイク片手に立ち上がる。
鳴り響く盛大なドラムロール。
「集え、正義の使者よぉお~♪ 今宵、魔を断つ剣となれぇえ~♪(フリつきで)」
イントロからもうノリノリだった。
「……これ、何の歌?」
「よく知りませんー、ソーセキ先輩、マイナーな歌ばっかり唄うんで」
ちなみに耕平が唄っているのは往年の巨大ロボットが多数出演するゲームの主題歌である。
……当然、彼以外は誰も知らない。
とりあえず、
「へぇ……でも、かっこいい歌だね」
「…………」
薫がそう言ったので、牧人は憮然となった。
「ヒュー! オレサマ最高!」
机に上げた足を下ろしながら言う。ノリ過ぎだった。
通常こういう場面で誰も知らない歌を唄うことはタブー視されがちだが、耕平が唄うと皆それなりに盛り上がるのだった。
「マキくん、次マキくんの番だよ?」
「わ、わかってるよ……!」
分厚い目録を繰りながら。
「え、ええと……」
……実は牧人はカラオケに来るのが初めてだった。
故に先程から勝手がわからず、焦っている。
「あ! じゃあマキくん、わたしとデュエットしようよ!」
誘われる。
「い、いいよ……、一人で唄うよ」
しかし恥ずかしい。それが自意識過剰に過ぎないとわかっていながらも。
「そう? 残念だな……」
「う……」
そして今になって後悔するのが牧人だった。
気を取り直して選曲。
「よし――!」
ようやく曲が決まる。牧人の好きな洋楽だった。
曲調は単純で唄い易く、それでいてノリも良い。
日本での知名度は低いので恐らく誰も認知していないのだろうが、先程の耕平がそうであったように、別に知られていなくてもある程度の盛り上がりは期待できた。
そしてマイクを手に、立つ――――
…………特筆すべき要素もなかったため、内容は割愛。
「……次、武田の番」
「うん」
「ちょっと待てよ! なんで俺の時だけ誰も拍手しないんだよ!?」
…………楽しい時間が過ぎていった。
■■■■■■■■■
……少し遡って、季節は春先。
まだ新学期開始二日目のことである。
棗耕平は一人帰路についていた。
「……む?」
その中で、彼のセンサーが反応する。
独特の音を耳が受信し、すぐにその像を視線が捉える。
「よっ……、よっ……」
一人の少女が、河原でヨーヨーを使って遊んでいた。
少女の指に繋がれた紐――その先端で回転する円盤が夕日を反射して光っている。
投げる、引き戻す。投げる、引き戻す。
結果的に見ればそのような単純な作業を繰り返しているだけだが、その二つの間には驚くほど複雑な過程がある。
投げる方向が下とは限らない。上下左右に投げられたヨーヨーは少女の手によって綾取られ、様々に交錯し、縦横無尽に複雑な軌跡を描く。
一心に取り組むその姿と、繰り出されるトリックの数々は、子供の遊びのようでありながらも芸術のように美しい。
……プラスチック製の二枚の円盤を短軸により重ね合わせ、紐を巻きつけたその特徴的な玩具は、かつて日本においては単なる幼児の玩具の域には留まらなかった。
とりわけ戦後、時々に応じて要因は様々だったが、多くの人々が単純なようで複雑なこの遊戯に夢中になったのである。
ちょうど耕平たちの幼少期にも、某玩具メーカーによる高品質ヨーヨーの発売をきっかけにこの遊びが何度目かの流行を呼んだ。
玩具店やデパートでの売り切れも発生し、テレビや新聞にも取り上げられた。
小中学生が好んだ某雑誌とのタイアップも成功の一因と言えるだろう。
かくして、ヨーヨーは一大センセーションとなった。
耕平は生来、こうした遊戯をよく好んだ。
当然、子供たちの流行にもいち早く乗り、曲芸じみた数々の技術を習得していった。
しかし、流行とは廃れるものだ。
当時は最先端の流行であったこの遊具も、今や以前と同様に幼児の玩具として軽んじられるだけになってしまった。
あれほど技術を高め、競い合っていた少年少女も、今では成長し、その大人げない遊びから離れていった。
かつての熱を忘れ、斜に構えて、そのような物に夢中になった自分たちや、流行した社会、その立て役者たる大人たちを嘲笑した。
しかし耕平は、そのようなことはしなかった。
ただ、学校に持って行ってまでやらなくなっただけで、彼は家では度々ヨーヨーを使って遊んだ。
幼少期に親から買い与えられ、段ボール箱に詰め込まれた玩具たち。
それらは決して埃を被っていない。
彼は今でも日々それらを取り出して、共に楽しい時間を過ごすからだ。
そこに、真新しいヨーヨーが一つ加わっただけである。
童心は大切だ、と思う。
そうした幼い日の楽しい思い出が、自分を支えていると彼は信じている。
だから彼が幼少期に戯れた玩具やアニメを未だに愛するのは、ある意味逃避的と言えるのかもしれなかった。
そんな彼にとって、
自分以外の同年代の少女がその遊びをしていたのは、衝撃的だった。
声をかけずにはいられなかったのだ。
「おい、お前」
「おょ?」
ヨーヨーをループしながら少女が振り向いた。
耕平はそこで初めて彼女が自分と同じ高校の生徒だと気付いたが、別にそこは重要ではなかったから無視した。
「いいプレイしてるじゃねえか」
舌を踊るそうした言葉が懐かしい。
近所の公園で、見知らぬ優れたプレイヤーにそうして話しかけた幼少期を思い出す。
「ナンパっすか? あたし、清楚ガールなんでナンパお断りの方向でお願いします」
「違ぇよ!」
日頃、棗耕平の声量は安定している。
聴き取りにくい喋り方はしない。逆に大声を出すこともあまりない。
だから、彼がこうして声を張るのは実はとても珍しい。
「お前、ヨーヨー好きなのか?」
「えーまー。ガキくさいってバカにするとよいですよ」
「だからそーゆーんじゃないってのに、悲しいこと言うなあお前」
「前にもそやってヨーヨー褒めるフリして近づいてきた男の子いました。けどあたし、これをバカにされんのがイチバン嫌いなんで、さよーならー」
いわゆる“犬の散歩”をしながら立ち去ろうとする。
「バカになんかしてねえ! くそっ、見せてやるよ!」
耕平は少女に手を突き出した。見せてやる必要があった。
「……なんすか?」
「貸してみろ、オレの遊びに対する愛情がお前なんかよりずっとすげえことを見せてやる」
「………………」
少女は怪訝な顔をしつつ、ストリングを外した。
或いは、この少年の言葉と熱意に自分とのシンクロニシティを感じたのかもしれない。
「壊したらそこの河に飛び込んでください。あたしの宝物なんで」
「抜かせ!」
そして耕平は、夕日に向かってヨーヨーを投げた。
思いつくままに様々なトリックを決めた。
当時、公式設定されていたものに留まらず、彼が独自に考案したものもいくつか披露した。
トリックの名称はどれも難しい英語のものばかりだ。
頭の悪い小学生だったというのに、そんな名前をいくつもよく覚えたものだ。
そう思い、耕平は苦笑する。
「見ろ、これぞオレの超必殺奥義、ナツメツイスター!!」
……楽し過ぎた。
ヨーヨーを振り回している間、耕平は笑い続けていた。
「……見たかチビ子、オレの実力を」
最後に、ストリングスを指から外して空中に放り投げた本体をキャッチするという大技を軽々決めて、耕平は少女にヨーヨーを差し出す。
「す……」
少女はヨーヨーを受け取ることもせず、
「すげえっす! ま、マジかっこいー! 師匠って呼んでいいっすかー!!?」
諸手を挙げての大喜びだった。
「フハハ、もっと褒めていいぜ!!」
言われた側も最高の気分だった。
「もいっこありますから、二人で色々遊びましょうぜ!」
ポケットから同型の物を取り出す。
「おうよ!」
耕平は迷わずストリングスを再装着した。
……そうして遊んでいる間に日が暮れた。
「いやー、メガロ楽しかったっす! ししょー最高!」
「……なぁに、楽しかったのはこっちも同じってコトよ」
ヨーヨーを返す。
酷使した右腕がさすがに痛んだ。
――ガキの頃は痛くても全然平気だったのにねえ……。
成長した自分の痛覚が哀しかった。
「……てか、なんでヨーヨーなんかしてんのお前?」
右腕をマッサージしながら問う。明日以降の生活に支障をきたすわけにはいかない。
「ふふん♪」
少女は人差し指を立てて、自慢げに胸を張った。
「紐で繋がれて、好き勝手暴れたところで結局は元の場所に戻ってしまうというその有様が、束縛だらけのあたしの人生とダブるような気がしたんすよ」
「……バカじゃねえ?」
間髪入れずに言ってやった。思わず出てきてしまった。
「………………」
直後、少女のヨーヨーが美しい弧を描いて耕平の右頬をしたたかに撃ち抜いた。
「直後、なつめのヨーヨーが美しい弧を描いて少年の右頬をしたたかに撃ち抜いた!」
「なにナレーションっぽく言ってやがるてめえ!」
普通にぶっ飛ばされていた耕平はよろよろと立ち上がる。
「ヨーヨーを人に向けて投げてはいけません! 殺すぞ!」
「おまわりさーん! 今、あたしの青春という名の乙女フィルターがこの人によってカタストロフ寸前ですー!」
携帯電話に向かって叫んでいた。
「電池切れてねえか、それ?」
「ちっ、命拾いしましたね」
携帯電話をしまう。
そこでふと、
「……あん? なんだお前、なつめっつーのか」
少年は自分と少女が同じ名前であることに気がついた。
「そですよ」
「それって苗字? 名前?」
「名前です」
「苗字は?」
「そう言うあなたのお名前は?」
「……?」
それまで多弁過ぎた少女がここに来て妙に渋る。
それが少し気になったが耕平は先に名乗ってやることにした。
「オレサマは棗耕平だ! ちなみに平坂高の二年でもある」
「うぉー! あたしの名前が冠されているではないですか!?」
「バカ、違ぇよ! オレの苗字がお前の名前に冠されてンの!」
「ちなみにあたしピチピチセクシーの一年なんで、ソーセキ先輩と呼ばせてください」
「待ていコラ! どこから現れやがった文豪!?」
「だって、夏目といったらソーセキでしょ?」
「オレサマの苗字はそんな陳腐な字面じゃない!!」
しばらく日本が誇る文豪について熱い議論が交わされた。
「実はあたし、すんげえカッコいい苗字なんすよ」
「オレよりカッコいい苗字の人間は人類にはいねえ」
「なぜそんな自信過剰…………」
「で、お前の苗字がなんだって?」
少女は再度胸を張った。ちなみにこの少女はとても肉付きが悪い。
「あたしの名前は、芥川なつめといいます」
色々と発音的にインパクトがある名前だった。
「娘を使ってギャグをかますとは、お前の両親はなかなかファンキーだな」
「ギャグ言うな!」
再度ヨーヨーが耕平の頬にめり込んだ。
「なにしやがる!」
「人の名前にケチつける子は、地獄の池に堕ちるといいんすよ」
「『蜘蛛の糸』とはまた凝った比喩を言いやがるなてめえ!」
「やー、やっぱ同じ苗字の人なんでマイジャーどころは読んでおこうかと」
「安易なヤツめ。お前のことは今から龍之介と呼んでやろう」
「そんな男らしいあだ名いやっすー!」
「“ただぼんやりした不安”を理由に世を儚むがいい!!」
「遺書の内容ッ!?」
内容以外は全て頭の悪い会話だった。
「ふん、なるほど芥川か。面白い」
そして耕平は不適に笑う。
「俺の苗字に由来する名を持つ上に苗字芥川なお前は、自動的にオレ一門に下るというわけだ!」
悪の黒幕のように手を広げて声高に告げた。
「も、門下?」
「オレはお前のヨーヨーにかける情熱が気に入った。家来にしてやろう」
「願い下げー!」
再度ヨーヨーを取り出した。二刀流だ。
「家来なんて認めませんっ。文豪の名前ダブルで入ってるあたしの方が、ソーセキ単発の先輩より強いっす!」
「なにぃ……っ!?」
「くらえっ、必殺――ダブルブンゴー!!」
なつめはヨーヨーを手にした腕を勢いよく繰り出し、二つのヨーヨーを手から解き放つ。
ダブルブンゴー=ダブルループ
その前衛的過ぎる名前を冠したそのトリックは、左右から耕平の腹部に直撃した。
「ふごぉ……っ!」
悶絶しかけるも、
「効くか、このヘナチョコヨーヨーめ!」
耕平は猛った。
「くっ、あたしのダブルブンゴーが……!」
間合いを取るなつめ。
「うるせえ、片方ドブ川だろうが! そんなものは戦力外だ!」
芥川龍之介は棗耕平によって戦力外通告された。
「なっ、ドブ川っ!?」
「ふ、知らんのか? 芥ってのはゴミ!チリ!クズ!って意味なんだぜ、だからお前の名前はゴミ川だ!」
「な、なんですとーっ!?」
絶叫する。知らなかったようだ。
「い、今までカッコいい名前だって色んな人に自慢してきちゃいましたよーっ!!」
「バカめ! よし、女王陛下の名において、お前にゴミ川ゴミ子の名前を与えてやろう!」
「うわーん、お嫁にいけなくなりましたー!!」
平伏した。
…………これが、棗耕平と芥川なつめの出会いだった。
■■■■■■■■■
「……ということがあってだな、それ以降ゴミ子はオレの一番弟子だ。苗字のくびきからは逃れることはできなかったということだな」
ちなみに芥川龍之介は夏目漱石の門下だったという。
「……とんでもない出会いしてるんだな、お前等」
「マッキー先輩、何をそんなげんなりしてるですよ?」
「いや……」
カラオケの後、何気なく二人の馴れ初めを聞いたら、以上のような話をされた。
牧人の中の常識が音を立てて瓦解していくようだった。
この二人は、彼が今まで出会ってきたどのような人間よりも個性が強かったからだ。
かつて個性を求めて足掻いていた少年からすれば、羨望を通り過ぎて敗北感しか残らない。
「それにしても、ヨーヨー得意なんだね」
「へへー、まあ褒めてくださいよー」
明彦の言葉を受けて、なつめがウインクした。
ポケットからそのヨーヨーを取り出す。常備されているようだった。
「おいゴミ子、一個よこせ」
「だからゴミ子はよしましょうって」
言いつつヨーヨーを投げ渡す。
二人はおもむろにストリングをはめて、トリックを披露し始めた。
あまりにも自然にやっているが、両者ともその技術はかなり高い。
「二人ともすごいねー」
「うん、サーカスみたい」
「………………」
素直に褒め言葉を口に出来ないのが牧人だ。
「あ、そういえば棗くん」
「おょ?」
「なんだ?」
「…………」
薫の呼びかけになつめコンビが両方とも反応した。
「バァカ! 藤宮が呼んだのはオレの事だ、誰がお前のシケた名前なんか呼ぶか!!」
「せ、先輩だって同じじゃないっすかー!」
そして、なつめが耕平に苛められた。
「あっ、やめてあげて、やめてあげて棗くん!」
薫が一応止めに入る。
「……そういや、お前らって名前同じなんだよな」
「そうなんすよ。正確には苗字と名前っすけど」
「呼んだ時にゴッチャになっちゃうねえ」
「どっちかを名前で呼べばいいな」
耕平が提案する。
「ちなみに、オレは牧人のことは名前で呼んでやろう」
「じ、じゃあ俺もお前のことは耕平って呼んでやるよ!」
牧人は対抗した。
「せっかくだからお互いの呼び名会議をしようぜ」
「……何でそんなこといちいち会議しなきゃいけねぇんだ?」
「なら牧人はその辺でいじけてろ、オレら四人でやるから」
「さ、参加しないなんて言ってねぇだろ!」
いいように耕平に翻弄されている牧人だった。
「カオル先輩のことは流れでカオル先輩とお呼びしてますけどオッケです?」
「いいよ。わたしは、どうしようか……なつめちゃんだと棗くんと一緒でややこしいし」
「オレを棗と呼べ! こいつをなつめと呼ぶのは認めん!」
なつめは聞き分けのない子供を見るような目をした。
「……なら、カオル先輩はあたしのことはなっちゃんとお呼びください」
「なっちゃん……、うん、わかったよ」
女子間の呼び名が確定された。
「マッキー先輩はマッキー先輩でいいってさっき言いましたよね?」
「まあ、いいけど……」
正直少し恥ずかしかった。自分のイメージと少し違ったからだ。だが、今更訂正する気にもなれない。
「あたしのことなんて呼びます? ソーセキ先輩名前で呼ぶならなつめって呼んでも問題ないっすけど」
「……別に呼ばないでいいよ。普通に芥川って呼ぶ」
「うぅ、以前は嬉しかったその苗字が……今ではなんだかビミョーな感じに……」
「な、ならどうすりゃいいんだよ……?」
動揺した。女の涙(ウソ含む)に弱い。
「名前で呼べばいいんすよ、なつめと、さあ!」
「な……、…………芥川」
無難だった。冒険が苦手である。
「うわーん! もしかしてあたし嫌われてるー!?」
なつめはいずこかに駈け出した。
「明彦はどうするんだ?」
「僕はまあ、普通に。棗くんと芥川さんで」
「そんなもんか」
簡単だった。牧人も深く追求しない。
「じゃあ、棗くんはどうする?」
「牧人、藤宮、明彦。……以上」
それぞれを指差しつつ言い切った。
「メチャメチャ強引ですねこの人……」
トイレに行っていたなつめが戻ってくる。
「まあ、好きにすればいいんじゃねぇの?」
気怠げに牧人。
少しくたびれた様子だ。
互いの呼び名が決定され、一同はしばし雑談に花を咲かせる。
そんな様子を見て、
「はは、なんだか……」
明彦が不意に笑った。
「急に賑やかになったね」
いつも緩やかに微笑んでだけだったその少年が、
そうして明確な笑いをこぼす場面を、牧人はそういえば初めて見たような気がした。
かくして、彼等は五人の輪を作り上げた…………。
■■■■■■■■■
五人で最初に遊んだ、記念すべきその日――
日は完全に落ち、夜時間となる。
今は耕平と明彦が二人。場所はゲームセンターだ。
あの後、牧人がバイトで離脱したため、そのまま流れ解散となった。
なつめと薫はそのまま帰宅し、男二人は何気なくそのまま遊びに出た。
「遅い! 遅い遅い遅い!! 遅すぎるぜ明彦、これで十四連勝だ!」
「棗くんはゲーム上手いんだなあ」
二人はドライビングシュミレーターを用いたレースゲームで対戦していた。
そして明彦は負け越しだった。
「てめえ! さっきはオレサマのエドモンドをぼっこぼこにしやがったくせに何言ってやがる!」
「棗くんはヘンにセオリー通りだからねえ」
ちなみに最初は二人で格闘ゲームをしていたが、そちらは明彦が強すぎて耕平がまるで勝てなかった。
相性が極端な二人だった。対戦系の遊びが向いていないのかもしれない。
「さすがに疲れたな。あとはまったりUFOキャッチャーでもするか」
「そうだね」
シートを立ち、二人はたらたらと歩き出した。
入口付近の筐体前に立ち、コインを入れる。
「見てろ明彦。オレはこのゲームが超得意だ」
「そうなんだ」
「ククク……、このケースを空にしてやるぜ!」
景品の配置を確認する。どれが一番取り易いかではなく、どれが一番欲しいかを耕平は考えていた。
「あれだ!」
耕平が選んだのは、九十年代に一世を風靡した人型巨大ロボットアニメに登場するヒロインのフィギュアだった。
「あれを美少女フィギュアがまるで似合わない牧人にプレゼントしてやろう」
嫌がらせだった。
苦笑するだけで止めない明彦も、思えば少々意地が悪い。
他のぬいぐるみなどとは異なり、このフィギュアは箱に入った状態で置かれている。
そのため、上部に取り付けられた取っ手のような部分をクレーンで上手くすくわなければならない。
重量もある。ただ引っ掛けたり転がしたりするだけで入手できる普通の景品に比べ、格段に難易度が高そうだ。
「いざ――!」
棗耕平の終わりなき戦いが始まる――――
そんな中、
「棗くんって、プライベートだと大分イメージが変わるね」
「あん?」
明彦はそんなことを言い出した。
「そりゃ一体どういう意味だ?」
クレーンを操作したまま問い直す。
「なんか、学校のクラスで皆の中心に立ってる棗くんと、さっきとか今の棗くんは違うなあと思って」
「ほう……どのへんが?」
クレーンがフィギュアと同一線上に並んだ。
後はもう一個のボタンを押しながら、アーム部分を上手く真上に合わせなければならない。
「うーん、そうだなぁ……」
「…………」
明彦の言葉を聞きながら、耕平は慎重にクレーンを操作しつつ……
「なんか、今の棗くんはワガママだ」
「なにをっ!?」
その言葉で思わず振り向いてしまった。
同時に、ついボタンから手を離してしまう。
「……しまった!」
クレーンは何もない場所で止まる。
そのまま降下し、空を掴んで元の位置に戻ってきた。
筐体から流れ出す電子的なBGMが虚しく響いた。
「おいコラァ! てめえの所為でスカしたじゃねえか明彦ォ!!」
「いや、あはは……」
胸倉を掴み挙げた。
「…………」
「………………?」
しかし、耕平は急に黙った。
普段のにやついたものではなく、どこか空虚な表情で。
「なあ……オレ、そんなに普段と違うかね?」
「全体的には同じだけど。今日の棗くんは本音が多い」
武田明彦は相手の気配を読む。
いつでも、その人物の今の状況に合わせた対応を。
真剣な態度には、真剣に。そう決めている。
「僕は、棗くんがあんなに勝手で人の話を聞かない乱暴な人だとは思っていなかった」
「……全然そう思ってる顔じゃないんだけどよ」
「それが悪いことだとは思っていないからだよ」
いつも通り、にこやかに明彦はそう言った。
「……そうかい」
耕平は目を閉じて微かに口元を緩めた。
勢いで掴んだままだった手を離す。
「おい明彦」
サイフから新たにコインを取り出しながら。
「なんだい?」

「オレはお前を名前で呼んでやるから、お前もオレを名前で呼ぶがいいぜ」
敢えて傍若無人な口調でそう告げた。
「……うん、わかったよ耕平」
かくして、男子三人は名前で呼び合う間柄となった。
友情は時に、一日で醸成される。
そして、参加者の努力次第でいくらでも維持が可能である。
だからこの日の少年は、以降この五人で友情を育んでいくことに決めた。
……人知れず、そう決めた。
ちなみに三十分後。
「な・ぜ・だ!?」
無一文になった耕平が頭を抱えていた。
箱入りフィギュアを狙い続けた耕平だったが、彼の所持金のほぼ全てを投資しても対象は微動しただけだった。
「思ったんだけどさ?」
「なんだ?」
「箱の蓋の部分にクレーンを引っ掛けるのはどうだろう?」
「なにぃ……?」
そして交替した明彦の手により、一回でフィギュアは獲得された。
……後日、これは牧人に贈呈されたが、同日廃棄されることになる。
05
「ねえマキくん、最近はギター練習してるの? また聞かせてよ」
「い、いいけど……、なんならこれからウチ来るか?」
「いいの? ならまた遊びに行くよ」
ある日の放課後、二人はそんな会話を交わした。
牧人の部屋に薫がやって来る。
一学年の秋頃、初めて薫にギターを聞かせてからというもの、牧人は時折こうして薫にギターを聞いてもらっていた。
「………………」
そしてその日も演奏を終える。
「ふー……」
一息ついた。
ピックを弦に挟む。
「お疲れさま、マキくん」
「どう、だった?」
「……うん。上手になってるよ。コードも安定してきたし、前向いて弾けるようにもなってきたよね」
「……そ、そっか」
安堵する牧人。
本当は飛び跳ねて喜びたいような気分だったが、体力的にもそれは無理だ。
ストラップを肩から外し、ギターをスタンドへ。
「でも、マキくんすごいよね。たった半年くらいで、こんなに色々弾けるようになっちゃうんだもん」
「ばっ……、全然すごくなんかねぇよ……。元々練習はしてたんだ、カン取り戻してきただけだ」
「うん。すごいすごい」
「…………は」
思わず笑ってしまう。気が緩んで笑んでしまうとは実にらしくない。
つまり、それぐらい楽しくて仕方がなかったのだ。
彼女にギターを聞いてもらえることが。
彼女と二人きりで部屋で会話をしていることが。
彼女が、自分に言葉をくれることが……とにかく嬉しくて、牧人は、
「もう一回、何か弾くから……その、聞いてもらっていいか?」
再びギターを手に取った。
「うん。今度は何を弾くの?」
「え、えっと……藤宮は何が聞きたい?」
「え? リクエスト聞いてくれるんだ」
「うん……出来るかわからないけど、一応」
「えーとね、それじゃあ……ホルスト!」
「ホルスト……? クラシックの?」
「うん。知ってる?」
「あの……、木星とか、なら」
「弾けそう?」
「……とりあえず、やってみていいか?」
「うん! あはっ、楽しみだな。マキくんのホルストが聞けるんだ」
「…………」
牧人が演奏したのは英国の作曲家、グスターヴ・ホルストの組曲『惑星』――中でもとりわけ有名な第四曲『木星』である。
近代日本においては、ホルスト自身よりも名が知られている感があるこの名曲を、牧人はエレキギター一つで静かに演奏した。
オーケストラを一つの楽器で表現するとなると、どうしても寂しい雰囲気が付き纏う。
だが、一本の楽器のみ故に本来とは異なる独特の風合いを生み出したとも言えた。
……最も、牧人はクラシックという分野にはそこまで明るくない。
有名なフレーズは迷いなく弾けたものの、その他の部分はほぼ即興だった。
「……こんな、感じか? なんか大分適当だったけど」
「うん……すごい良かったよ。楽器が違うと全然雰囲気変わるね」
「……しっかし、意外に覚えてないもんだな。これじゃほとんどオリジナルだ」
「でも、聴いててちゃんと木星ってわかったよ」
「そりゃ藤宮がリクエストしたからだろ。……うん、今度、CD聞いてちゃんとアレンジしとくよ……そしたら――」
毎度毎度、この瞬間に牧人の心臓は早鐘を打つ。
否、牧人にとっては薫と会話する全ての時間が異なる瞬間なのだろう。
「――そしたら、また聞いてくれるかな?」
「もちろん。楽しみにしてるね」
「…………」
無上の幸福感を牧人は感じる。無意識のうちに顔がほころびてしまうほどに。
ギターを置いて、椅子から立ち上がった。
かなり長時間演奏していたためか、節々が微かに痛む。
「…………」
そんな中で、牧人は不意に妙な思考に囚われた。
薫が部屋にいる状態で、ふと耕平の部屋を回想したのだ。
……耕平の部屋にはベッドがあった。
そして彼には他校に通っているという彼女がいる。
夜な夜なその上で行われる営みに、このところ牧人は以前とは別の意味で羨望を抱くようになっていた。
……それに対し、自分は布団。
部屋の隅にたたまれたそれを、毎夜引き出して来ては眠るのである。
仮に、あくまで仮にだが、自分が耕平のような状況に立たされたとしたら、それでいいのだろうか。
…………牧人はそんな疑問を抱いたのである。
ある少女が自室に居て、そこにベッドがある状態……。
「………………」
なんとなく、牧人はそれが素晴らしいものに感じた。
――ば、馬鹿……俺は何を考えて……。
思わず顔を覆った。思考があまりに弛緩して情けないことになっていたからだ。
「藤宮、今日はこれからどうする?」
誤魔化すように話題を振る。
「別に用事はないよ。また、ご飯食べに行く?」
「お、奢るよ」
「え……いいよ。この間奢ってもらったもん」
二人は牧人の家を出て、ファミレスで食事をし、別れた。
結局、今回も牧人が奢った。薫が顔を立ててくれたとも言う。
牧人はいい気分だった。
帰り際、牧人は銀行に寄った。今月分の給料を引き出すために。
とりあえず、必要と思われる量だけを下ろし、残りは貯金である。
牧人が雇用されているのは工業系派遣会社である。
公共施設に置かれた設備の修理や点検が主な仕事内容だった。専門色が強いため仕事はハードだが、ペイが良く、何より事務所が近所だというのが彼にとって気楽だった。
アルバイトを始めてもう大分経つ。
ギターを再開してからと同時期なので、半年近く続けていることになる。
「…………」
今より性能の良いギターを購入するために始めたバイトである。
貯金は着実に増えているが、それでも先は長い。
……薫が遊びに来るたびに気前良く夕飯をご馳走していることも原因の一つなのだが。
そして自室に戻って来て、ふと牧人は想像した。
ギターを弾くためによく座る机の椅子に座って、部屋を見渡す。
――ベッド……置くとしたら、その辺だよなあ……。
今、布団が置かれている場所を見てそのように思った。
「ええと……」
そして気付けば、携帯電話で家具の通信販売サイトにアクセスしていた。
ずらりと並んだカタログをチェックしていく。
牧人は良い物を好む。質が良く、センスが良く、作りが良い物だ。
当然値も張る。
「じ――!?」
最初に目をつけたものは十万円だった。別格である。
十万――牧人の二、三ヶ月分の月収だ。
「…………」
諦めた。
そのまま、商品リストを見て行く。
ちなみに表示順は値段に設定し直した。
――高い……これも高い……これも……。
目に留まる商品はどれも高額だ。まだ自分の手には遠い。
次々と画面をスクロールさせていく。
ようやく、良さそうなものが目に留まった。
「でも、五万か……」
まだ大分高い。
三分程悩んで、やはり無理だと決断した。
「お、折りたたみ式のヤツが二万」
通気性の良い快適そうな構造だ。
おまけに下部には収納までついており、部屋の家具を整理すれば場所もそうとらなそうである。
「これだな」
牧人の中で決まった。値段が決め手だ。割と安直だった。
……しかしベッドとはいえ折りたたみ式である。
そうした簡易製品は基本的に睡眠以外の使用を想定されていない可能性がある。
重圧にギシギシとしなるベッド上での夜の営みとは、果たしてロマン的にいかがなものなのだろうか。若者らしいと言えなくもないが。
「……入金方法は代引きで……、クリックで購入……と」
かくして、牧人はベッドを購入したのだった。
安値とはいえ、それでもなかなかの出費だった。
通信販売とは買い手の購入感覚を薄れさせ、それでいて満足させるから脅威なのである。
――ベッドで寝る……か、考えもしなかったな……。
満足そうに彼は椅子にもたれた。
何かが見えなくなっている。
また彼の良くない病気が発動し始めていたのだ。
こうして、フライングⅤ購入計画は順調に遅れをきたしていくのであった……。
【戻る】