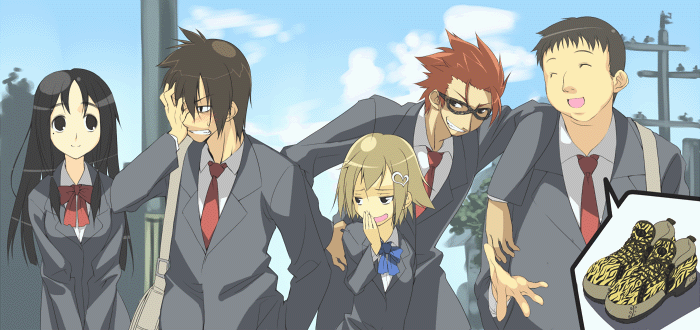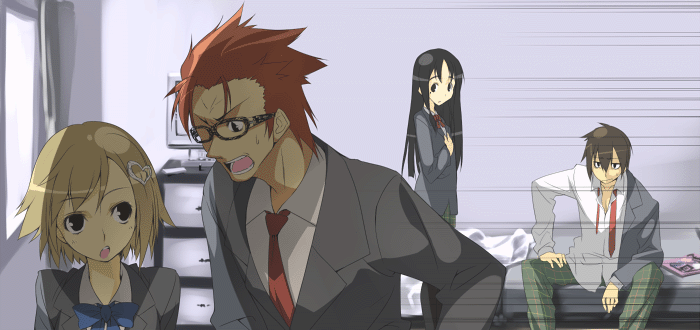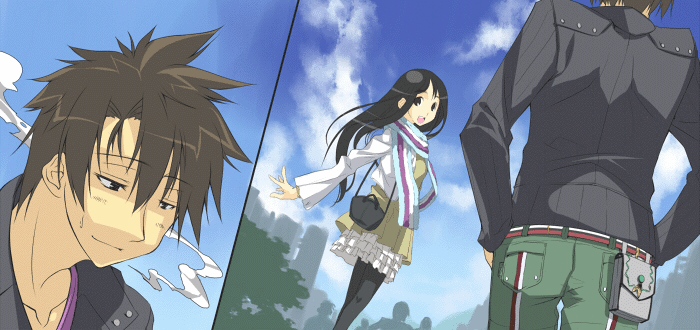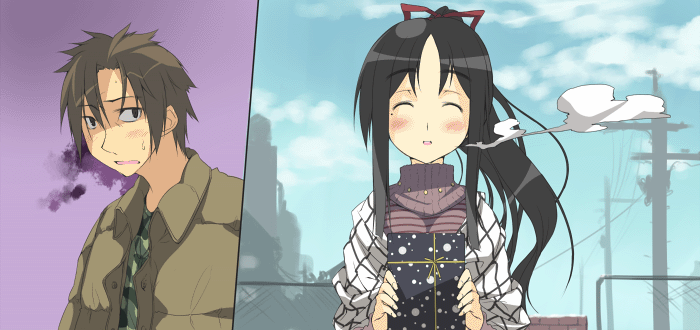愛染甘露
00
通学路。
「おはよう、マキくん」
朝の日差しの中に彼女はいた。
「おはよ、薫」
牧人は短くそう返す。
挨拶は苦手だ。だが彼女との交流は楽しい。
そうして互いに名を呼び合うことで、朝の始まりを実感するような気がするからだろうか。
「やあ」
そこに明彦が加わり、
「モーニン!」
「ぐーてんたー!」
騒がしい二人も合流し、五人となる。
この顔ぶれでの通学も随分と馴染んだものになった。
「いつも見かけるガキどもがいないな。少子化か?」
「今日は土曜だろ。小中学校は休みじゃねぇか」
「あたしたちは学校行ってるのに〜、不公平っすよね〜」
「チビジャリどもがゆうゆう休んでいても、オレらは通学……か」
「ままなりませんね〜」
「ならお前はなんでここにいる? 中学校は反対側だぞ?」
「ソーセキ先輩って、ホンットに同じネタで繰り返し人をいじめますよね……」
なつめがしおれた。
「ってか、土曜休みって……小中の授業って減ってるんすね」
「でも、わたしたちも授業時間は減ってるらしいよ?」
「減る前を知らんから良さがわからんな」
「一日で見ると確かに授業時間は減ってるが、休みも減ってる。平坂高だって、昔は土曜休みだったそうじゃねぇか」
「ゆとり教育の弊害ってヤツですか?」
「困ったもんだ、このゆとりが!」
耕平がなつめの頭をぐしゃぐしゃとかき回す。
「先輩だってあたしと一個しか違わないじゃないですか〜!」
「台形の面積の求め方って、オマエ知ってるか?」
「むぎゃ〜! いわれなきゆとり扱いを〜!?」
「……あんま、ゆとりゆとり言うなよ。歳的には俺らもそんな変わんねぇぞ」
「その通りだが、意識として重要じゃねえか?」
「……まぁ、な」
「まあ今日はコマ数少ないからいいじゃない」
「そこっ、そこ大事っす! 明彦先輩ナイス!」
「明彦の言うとおり今日半ドンだけど、……放課後はどうする?」
「午後は五人でどっか行くか?」
「んじゃとりあえず駅前でランチッチっすね」
「マキくん、お金大丈夫?」
「だ、大丈夫だよ……お前がそんなこと気にすんな……」
「なに君ら、サイフの共有でもしてんの?」
「まるで新婚の夫婦のようですね」
「ち、違ぇよ! 何勝手なこと言ってんだ馬鹿!!」
焦ると早口になる牧人だ。
「じゃ、みんな集合ってことで」
そしてまた明彦がさりげなく軌道修正。
「……あぁ」
「うぃーっす」
「僕、掃除当番だから先に行ってていいよ」
「あー、あたしもちょっと用事が」
「じゃあ、終わったら駅前集合でいいんじゃない?」
「だな」
集合が口約された。
「お、そういや明彦、この前もらったゲームなんだがよ」
「どこまで行った?」
「今40ターンくらいか。結構あちこち制圧したぜ」
「ガード使ってる? 攻撃ばっかりしてると後できつくなるよ」
「……なんの話だ?」
「明彦から少し前に色々貰ってな、おもしろいぜ」
「へぇ……、なら――」
「けどパソコン版しか出てないから、牧人は出来ないな」
「………………」
仲間外れにされて牧人は憮然とした。
「こらこら、そんないじけるな。な?」
「いじけてねぇよ!」
だがこのように、弄られると元気になる。
「代わりに、この前頼まれてたブーツ、ちゃんと落札しといてやったから」
「お、マジか!?」
「マジよ、オレの競売戦略を舐めるなよ」
「どんなブーツっすか?」
「黒いエナメル。ゲオルグのな。レアモデルの固定サイズだったんだが、運良く俺の足と同じだったから耕平に落札してもらった」
「はー、相変らずシブいの履いてるんすね」
「昔はトラ柄とか履いてたのにね」
「ばっ、話さないって約束――! 明彦ッ……!」
「あはは、まあいいじゃない」
朗笑する明彦だったが、既に遅い。
耕平となつめの二人は見るからに楽しそうな表情を浮かべている。
「マジかよ牧人……お前も迷走してた時期があったんだな」
「そーゆー派手な格好も似合うと思いますけどねー、マッキー先輩」
二人してにやにや。
「………………」
牧人は頭を抱える。
また彼等に新たな弄られ要素を与えてしまった。
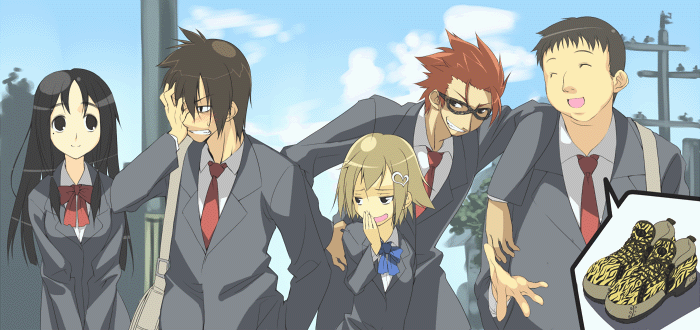
以前は攻撃的なデザインを好む牧人だったが、このところ徐々に落ち着いた風合いを好むようになってきていた。
友人たちの影響もあるのかもしれない。
派手さにおいて耕平やなつめには敵わないとでも思ったのか。
「で、耕平、いくらだった?」
「ええとな……」
携帯電話を操作しながら、値段を告げた。
「ええっ!?」
後ろを歩いていた薫がよろめく。
「どうした藤宮?」
「……マキくん、そんな高いの買っちゃって大丈夫なの?」
案ずるような声。
「そんなもんじゃねぇか。良心的だと思うぞ」
「だよな。これより安く買うのは難しいぜ」
「そんな……、いくらバイトしてるからって、そんな無駄遣い……」
薫は複雑な表情をした。
悲しみとも、自虐的とも取れる憂い顔。
「う……」
薫のそういう表情に弱い牧人だ。いたたまれなくなる。
「い、いや……大丈夫だよ。これはどうしても欲しかったから買ったけど、普段はこんな風に散財したりしない」
「ホント……?」
「ほ、ホントだよ。バイトも続けてるし」
隣に並んで、必死に弁解する。
「尻にしかれてるな」
「ですね」
耕平となつめが囁き合う。
「うるせぇんだよお前ら!」
そしてばっちり聞こえている。
しばし口喧嘩になった。
「……ま、もっと関白を目指そうぜ牧人」
「はっ、ダサいこと言ってるなお前も。偉ぶってるだけの男なんて流行らねぇぞ」
「マッキー先輩って、結構フェミニストなんすね。きゃん、女の子の味方っ♪」
「そ、そんなことねぇよ! 馬鹿、引っ付くなよ!!」
「ううん、マキくんはこう見えて優しいところもあるんだよ」
「か、薫……このタイミングでそんなこと……」
――嬉しいけど……この状況でそんなこと言われたって……。
真っ向からの評価にも弱い牧人だった。
そんな、他の四人の様子を明彦が最後尾から眺めている。
幸せそうな表情を浮かべて。
「なにしてんだよ明彦、いくぜ」
「うん」
一番付き合いの長い少年の呼びかけ。
そういえば彼は最近、歳相応の明朗な口調が増えた気がする。
■■■■■
どことなくガラの悪そうな牧人。
見るからに純朴そうな薫。
整ってはいるが遊び人風の耕平。
そのような三人が並んで立っている姿はそれなりに目立つ。
派手目の少年二人に地味な少女が一人。どこか不穏な空気がしなくもない。
道行く人々の内何割かが意味深そうな目を向けてくる。
「チッ……、ジロジロ見やがって」
そうした視線を最も気にするのは牧人だ。
腕を組みながら、威嚇するように周囲を睥睨する。
「駄目だよ、マキくん」
いさめる声。
「わかってるよ……」
浮きかけていた背中を再度駅の柱に預ける。
そんな姿を慈しむように微笑んで、彼女は文庫本に視線を戻した。
「……にしても、遅いな」
「オレらのクラスが早く終わり過ぎたんだな。明彦はもうすぐ来るだろうぜ」
「ふー……」
牧人はキシリトールガムを取り出して一粒含む。
その微かな咀嚼音と、薫がページを繰る音が周囲の雑踏の音に混じる。
「お、来たな……、おい明彦!」
牧人が一つ目のガムを噛み終わる頃に、耕平が声を上げた。
遠方から大柄な少年がやってくるのを視認する。
「……ほっ、……ほっ」
体躯に似合わぬ軽やかな小走りを終えて、明彦が合流。
「お疲れサン」
「いや、仕事だからね」
大したもので息一つ乱れていない。
「相変らずタフだな、見かけによらず」
「まあHP高そうな外見でもあるしな。壁キャラだな」
「だったら耕平は攻撃力だね」
「牧人は素早さタイプだな。んで防御力が紙、と」
「んだと……!」
「もーっ、いちいちケンカしないのっ」
薫が牧人の手綱を引いて、場は納まる。
「藤宮が保護者になってから、牧人がいい子になっちまってつまらんな」
「棗くんもあんまり煽らないの」
「……へいへい、お姫さんの言いつけには従いますがね」
肩をすくめる。
「そんな言い方するとまた牧人怒るよ?」
「……もう知らねぇよ」
脱力した。
平和な空気が戻る。
「今日はなに食べる?」
「制服だと、あんまアレな店には入れねえな」
「ファミレスでいいだろ」
「だねえ」
「遅れましたー、ごめんあそばせー」
ほどなく、なつめ到着。
「珍しく重役ゴールインだな」
「まあ、たまにはお姫待遇ってことで」
「……姫って重役出勤なのか?」
「さあ……?」
牧人が疑問をこぼすが、明彦は苦笑するだけだった。
「ところで、どうしてなっちゃん私服なの?」
「いったん家帰ったんすよ。今日、置き勉してた教科書全部持って帰ったんで」
「なんでそんなことするんだ?」
牧人のこの問いはなつめが予習復習などするはずもないという前提から発せられている。
「なんかー、ウチのクラス机の入れ替えするらしいんす。だから、机一度カラッポにしろって先生が」
「そういや、オレらが一年の頃は机が妙にボロかったな。あれ新しくなんのか」
「確かに、二年になって机キレイでビックリしたね……」
「去年の学級委員で、一昨年辺りから徐々に設備一新してってるって太田が言ってたよな。ようやく一年生も新しくなるわけだ」
「あたしはああいうボロっちい机の方がガッコらしくて好きだったんすけどねー」
「あ、わたしもそれわかるな。なんか独特の良さがあるよね」
そんな感じで、しばらく机談義。
「なんにせよ、遅れちまいまして」
「まあ、ちょうど小腹も空いてきたところだ」
「行こうぜ。いつものトコだろ?」
歩き出した。
そして一行はファミレスに入った。
先頭に立った耕平が店員に人数を告げ、いつもと同じ席に通される。
彼等はよく来る。顔を覚えてくれているのだろう。
「ま、グダグダ話しましょうよ」
「何食うかな」
ボックス席の奥に座った牧人が、メニューを配った。
メニューは二枚しかないため、それを五人で回し見ることになる。
「オレサマは肉を食う!」
「いーなー、あたしもハンバーグ食べたい!」
野獣二人が惜しみなく食欲を晒していた。
「……食いたいんなら勝手に食えばいいじゃねぇか」
「お金ないんすよねー。ドリンクバーつけちゃうとプラス二百円だから……」
しょんぼりしたなつめの頭を、隣に座る耕平がバスケットボールのように掴んだ。
「むぎゅ」
「豆子、寛大なるオレサマが格別の慈悲をもってオゴってやろうか?」
「うぉお……あたしの尊厳と食欲が天秤にかけられている……っっ!」
頭を抱えて呻くなつめに、牧人はため息を漏らしつつ言う。
「……金ねぇなら俺が貸してやろうか?」
「マッキー先輩金利には、利子はつきますか?」
しかしなつめはセコかった。
「……やっぱり芥川には貸さねぇ」
そして牧人も狭量だった。
「そういや、薫のヤツ遅いな……、店員呼べねぇだろうが」
「ありゃ、そういえばどこ行った? トイレか?」
「多分。……なんかポーチみたいなの持ってったけど」
「………………」
「………………」
「………………」
牧人のその目撃証言を聞いて、他の三人の表情が止まった。
「あいつ……たまにアレ持ち歩いてるけど、なにが入ってんだ?」
そして空気の読めない牧人は未だにそのようなことを言っている。
「……ん?」
そんな少年の肩を、隣に座っていた明彦が軽く叩いた。
息子の成長を願う父親のような表情にて。
「……な、なんだよ明彦、気持ち悪いな……」
「こんだけオトメゴコロのわからないマッキー先輩にも、彼女ってできるんですねー」
「おい、なんだかわからんがまた喧嘩売ってるよなてめぇ……!」
「カオル先輩戻って来ても、中身聞いたりしちゃダメっすよ」
「なんでだよ?」
「ちょいちょい」
手招きなつめ。
「あ?」
耳寄せ牧人。
「かぷ」
甘噛みされた。
「――っ!」
すかさず牧人はなつめの顔面に渾身の掌底を叩きこむ。
「ぶぎぃ!」
顔を潰され、華の女子高生芥川なつめは鈍く呻いた。
「毎度毎度、意味わからんことばっかしやがって、殴るぞ」
「もう殴られてまひゅ」
鼻を押さえながら涙目で言う。
「…………」
牧人は耳たぶに触れてみた。
先程のちょっといい感触だったなつめの唇が思い出される。
――ふざけるなよ……!
それが余計に牧人の憤怒を駆り立てた。
「……で? 何が言いたいんだお前は?」
「カオル先輩はですね――」
「……」
少し悩んで、
「月に一度の女の子祭りの日なので、生贄として女神サマに捧げる卵を産み落としに――」
「………………」
「………………」
言い終わらないうちに牧人と耕平がものすごい勢いでなつめをどついた。
「い、いたい〜! またぶたれた〜! 婦女暴行で訴えますよ〜っ!」
「気色悪いんだお前の例えは!」
耕平が怒鳴り、
「っ、くそっ……!」
牧人が落ち込む。
ようやく話が繋がった。
――……なんてことを口走っちまったんだ俺は……。
そして、またしても不用意な発言だったと認識して自責。
「あ、……おそくなって、ごめんね」
加え、絶妙なタイミングで戻ってくる藤宮薫。
「おやおや」
「おやおや」
机に額を打ち付ける牧人を見て、耕平となつめがにやける。
――く、くそっ……!
牧人、窮地。
「……っ、どけ明彦!」
「えっ?」
牧人は強引にボックス席から脱出し、洗面所に逃げ込んだのだった。
「マッキー先輩も生理ですかね?」
「な、なっちゃんっ……!」
薫は恥らうが、洒落としては少々黒過ぎた。
男子二名は気まずそうに閉口するばかりである。
仕切り直し。
「……で、何を食うか決めたか?」
まだ微妙に血流の早そうな顔で牧人が戻って来た。
「ここのメニューも食い尽くした感があるな」
「でもやっぱりステーキ系がうまいっすよねー」
耕平の広げるメニューをなつめが覗き込んでいる。
そうしている様は仲の良い兄妹を思わせた。
「お、先輩、さっきのページ戻ってください!」
「ステーキか? ほれ」
「ううむ……決めました!」
「オレは最初から決まってるぜ」
「……うん、わたしは……これにしよう」
明彦が肯くのを最後に見て、牧人がコールボタンを押す。
注文を取りに店員がやって来る。
「イタリアンハンバーグと――」
「オレ、イタリアンハンバーグ――」
我先に注文をしようとした牧人と耕平の声がダブる。
しかも二人は同じものを頼もうとしていた。
「…………」
「…………」
互いに言葉を遮られた二人の睨み合いが始まった。
言いしれぬ緊張に場が凍りつく。
「……イタリアンハンバーグ二つで、よろしいですか?」
「違います」
店員の確認に、牧人がぴしゃりと言い放つ。
「……ほう? 何がどう違うと?」
耕平が不敵に笑う。
「俺の方が先だったな?」
「それが?」
冷徹さすら感じさせる牧人の問いを、耕平はにやりと笑いながら受け流す。
「……言わないとわかんねぇか」
「わからんなあ」
毎度お馴染み。火花が散らされ、
「もぉ……、イタリアンハンバーグの二人分に、ガーリックライスセットとライスセット大盛りをそれぞれつけてください。あと、わたしは魚介のパスタで」
また薫が無益な争いを終わらせた。
「ステーキinオムライスひとつ〜!」
「グリルプレート。あとドリンクバー三人分」
セットを頼んだ牧人と耕平以外の分のフリードリンクを明彦が注文する。
最後の者が必要分を頼むのが通例だった。
「……かしこまりました、ご注文を確認させていただきます――」
苦笑しつつ確認を取って、店員は戻っていった。
「もぉ……、どうして二人ともあんな状況でケンカするの?」
「はいっ! 悪いのだ〜れだ?」
「っ!」
「…………」
なつめが声を上げると、互いを指差す牧人と耕平。
「今回はマキくんが悪いよ。……メニューかぶったくらいで気にしすぎ、小学生じゃないんだから」
「……チッ」
薫には逆らえない牧人だ。注意されて大人しく引き下がる。
――確かに、店員前で揉めるのはダサかったな……。
そして、彼なりに思うところもあるのだった。
「てか、カオル先輩の割り込み方には惚れ惚れしたっすよー」
「なんだかんだで、オレらが頼むモン把握してるって辺りはな」
「あたしたちのお母さんみたいなポジションっすね」
「お母さんって……」
持ち上げられて薫は少し照れた。
「明彦先輩はお父さんって感じっす」
「そうかな?」
こちらはあまり動じない。穏やかに笑うばかりだ。
「………………」
「おい、次男坊が明彦のポジションに嫉妬があるようだぜ?」
「誰が次男だ。勝手なこと言うな……」
むすっとする牧人だった。
「戦隊モノで言うと、マッキー先輩って絶対ブラックですよね」
「なんちゃってアウトローだからな。ちなみにオレはレッドだぞ。それ以外認めん」
「じゃあ明彦先輩は――」
「イエロー? 好物はカレー?」
「なんだよそれ……?」
そのように色々な物に各々を当てはめて遊んでいると、店員が料理を運んできた。
「いっただっきま〜す!」
「いただきます」
五人もいると、食卓は大分豪勢になる。
食器の触れる音が途切れなく繋がり、談笑しながらの賑やかな食事。
「肉がうまい!」
「そんな身も蓋もない言い方――」
「カオル先輩、そのエビ一匹くださいな」
「あ、うん、いいよ……、あっ、マキくんコーラこぼすよ!」
「……わ、わかってるよ、ガキじゃないんだから…………」
声が響く。
笑い声、哂い声。
楽しい空間。
その後も、若者たちは遊び歩く。
遊び疲れて日が暮れた。
「悪いが、オレはここで帰るぜ」
「僕もだ」
一人一人、数が減っていく。
「んじゃ、あたしもサイナラしますかねー」
「薫は?」
「うん、わたしも今日は帰るよ。ごめんね」
「……あぁ、わかった」
そして、牧人は一人帰路に就いた。
――今日も、遊んだな……。
肩を回すと心地よい疲労が滲んだ。
…………そんな感じで、牧人は今日も楽しく生きていた。
01
空気が徐々に湿気を失い始め、若干の冷気を帯びるようになる。
季節は、秋から冬へと向かっていた。
今、牧人は薫と共に下校している。
この所、放課後の集合場所は牧人の家というのが日常だった。
さしたる用はなくとも、自然といつもの五人がそこに集まるのである。
理由としては、牧人の家が学校から一番近いという辺りだろうか。
したがって、牧人は帰宅時には誰かしらと共にいた。
今日は薫――と言うより、彼女と二人での下校が圧倒的に多い。
耕平やなつめは寄り道が多い。
明彦は特に寄るべき場所もないが、牧人に気を使ってか、よく耕平たちと行動を共にした。
だから、今日も牧人は薫と二人きり。
多くは会話をする。
が、傍にいて物言わず過ごすのもまた心地よいものだ。
「…………」
不意に牧人は、手に発汗を感じた。
――手を……、
握り、開くことを繰り返す。
――繋いでみるか……!
決意するように、心中でそう宣言した。
……少し前から、牧人と薫は恋人として交際を始めた。
それまでにも割に親密な付き合いがあった二人である。
正式に恋仲となってからの交流も自然なものだった。
休日には部屋で二人過ごすこともある。
その最中、気分が高揚すれば抱擁を交わし、キスをすることだってある。
……それ以上の展開も、ままあった。未だ回数は少ないが。
故に、手を繋ぐことなどとっくに経験済みである。決意など今更もいいところだ。
だがこの時の牧人はどうしたことか、それが非常に重要なことであるように思えたのである。
――いや、ここは男として……繋いでみせねぇと。
どのような基準だろうか。時折、妙な義務感が生じるのだ。
前方を向くと、質素だが端整な横顔が僅かに視界に入る。
「…………っ」
唾を飲み込んだ。
美しい、という形容は牧人にとっては老成し過ぎていた。
かといって、より単純な形容で、薫の良さを説明することも難しい。
隣り合う彼女の空気。
共に過ごした日々。
今、歩いている河川敷――下校時の風景。
そうした様々な要素が、彼女との空間に不思議な感覚を与えるのか。
――どうでもいいだろ……そんなこと……。
牧人は、基本的に苦手であるにもかかわらず、そうした胡乱なことを思考するのが癖であった。
なんにせよ、隣り合う少女の姿に、淡い感動があったのだ。
「どうしたの?」
薫が声をかけてくる。
気付けば、じっと見つめていた。
「……なにが?」
「マキくん、わたしのこと見てた」
「…………悪いか?」
「ううん」
薫、微笑。
普段の牧人ならば、ここで“見てなんかいねぇよ”と嘘をついたかもしれない。
ただ、彼女の前にいると、牧人は通常時よりもかなり素直になるのだった。つまらない嘘をついても仕方ないと割り切っている。
割り切れば行動の早い男、葦原牧人。
「っ――」
そっと、指先が触れ合った。思わず声を発しそうになる。
「…………」
触れてきたのは薫の方からだった。少女の手から伝わってくる、微かな力。
……結局、先を越されてしまっていた。
薫はおっとりしているようで余裕があり、要領もいい。
従って、常に精一杯の牧人の様子を見てリードするのはいつも彼女だ。
或いはそうして余裕ある態度で接することに、彼女も快さを感じているのかもしれない。不器用な少年が慌てる姿には、母性愛に近いものを感じるのだろうか。
牧人的にそれは情けないのだろうが、焦りっぱなしの彼は気付かないことも多い。
「……嫌?」
覗き込むように問いかけてくる薫。
「べ、つに……っ」
握り返す。
逃れるように、牧人は空を仰ぎ見た。
そして、さりげなく互いの指を絡める。
互いの交差した指がより二人の手を密着させ、自然と肩寄せ合う形になる。
「ふふっ……嬉しいよ」
「…………」
牧人は、顔に出さない程度にデレデレした。
交際開始当初、牧人の硬派ぶりは徹底していた。
それは単に牧人が奥手なだけとも言えたが、ともかく大っぴらな身体接触や、所謂バカップル的な行為にはえらく抵抗したものである。
……最も、薫はこの通り誠実な性格であり、男女間の交際にも相応に節度を守る。
したがって彼女からのアプローチも彼氏彼女の間柄としては普通――むしろ大人しいぐらいのものであったが、初心な牧人にとっては些細な接触でも刺激が強すぎたらしい。
しかし、徐々にそうした抵抗(羞恥)も薄れてきている。
付き合いを始めてしばらく経つ今では、牧人の方から彼女に触れることも増えてきた。
ぎこちなくも、不器用な少年は恋愛間において理想的な男子像に必要な甲斐性を着実に身につけつつあるのだった。
……特筆すべきは、牧人自身があまりそのことを意識していないことである。
ある理想像の想定とそれへの妙な執心は、これまで牧人が幾度となく行ってきた。
要するに、カッコつけ――それは、言うなれば困った病気のようなものだ。
だが今のところ、牧人は薫にとっての理想的な相手たろうと思ったことはほとんどない。
現状の彼にはそんなことを思う余裕もない。ただ、彼女との日々を自分なりに楽しく過ごすことだけで精一杯なのだ。
結果的にそれが、前述の理想像に近づくことになっているのだから……、それは素晴らしいことと言えるだろうか?
……言わば、それが二人の変化と言えるかもしれなかった。
「…………」
「…………」
無言。けれど楽しげな二人。
午後の通学路。
手を繋いだ少年少女の影が、伸びている。
■■■■■
「お前ら……」
二人が牧人の家に行くと、
「よう牧人」
「お邪魔してるっす」
耕平となつめが既に自室に上がりこんでいた。
「だから……なんで、家の中にいるんだよ!?」
「ほれ、鍵だ」
平然と差し出してくる。
「だから家に入り込む前に返せって言ってんだろ!」
「鍵なくしたのに気付かないマッキー先輩もアレだと思うんすけど……」
二人はどこからかトランプを取り出して神経衰弱をしていた。
「ホント言うと、そちらが体育の授業やってる間にあたしがマッキー先輩の荷物から失敬したんすよ」
「警察に突き出すぞてめぇ……」
ドスを利かせた。
「あ、あたしはソーセキ先輩の命令に従っただけっすー」
「耕平!」
「おー、恐い恐い」
耕平はトランプを見たままなげやりに言う。
「ったく、揃ってくだらねぇことしやがって……この暇人どもめ」
「ああ、忙しい、忙しい」
なつめが立ち上がり、無意味に室内を往復し出した。
「……むかっ!」
牧人は露骨にいらついた。
「……芥川も最近毎日来てるけど、耕平みたいに彼氏から疑いかけられても知らねぇぞ」
ここぞとばかりに皮肉っぽく言ってみたが……、
「ああ、あの人とはもう別れちゃったからもうどうでもいいんすよ」
さらりとそのようなことを返される。
「え……?」
「なっ――!?」
なつめの発言に牧人と耕平の声が重複した。
こういう時、牧人が絶句するのはいつものことだが、耕平がこのようにあからさまなうろたえを見せることは少ない。
余裕ある態度の目立つこの少年には珍しい反応だ。
「な、なんだよ耕平……どうせお前のことだから最初から知って――」
「おい、なつめ、まさかお前――!」
「はい?」
「ちょっとこっち来い!」
動揺を隠しもせず、なつめの肩を掴んで部屋の隅に連れていく。
そして牧人は捨て置かれた。
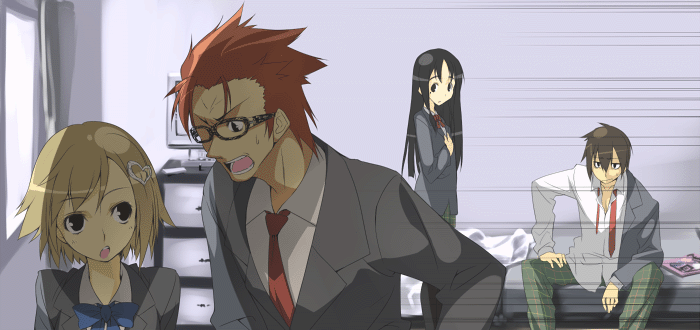
「お前、あの時……確かに言ったけど……」
「え、だって仕方ないじゃないすか…………ムリ……は……」
そのまま何やら密談が始まった。
「お、おい二人とも何の話をして――」
牧人は呼びかけるが、とても立ち入れない空気だ。
「だからって……何も…………まさか、あの時……言ってた……」
「大丈夫ですって……は関係ないっすし……どっちにせよ……」
「…………」
放置された牧人はとても不機嫌になった。
「まーまー! この話はしたって重いだけっすから、この辺で終わりにしましょ! ね!?」
「…………」
妙に明るい口調で、なつめが強引に話を打ち切った。
それに対して耕平は黙るしかないようだったが、ややあって、珍しく動揺していた耕平も平時に戻り、空気はいつもの和やかさを取り戻した。
「…………」
が、蚊帳の外に追いやられた数十秒間から生じた牧人の不機嫌はしばらく残留していた。
――ん? なつめ……?
しかしふと、耕平が耳慣れない呼び方をしていることにも気がつき、牧人は怪訝な顔をした。
そんな中
「――おやおや、今日も賑やかだねえ」
異様に平和な口調で明彦がやって来た。
「牧人がつまらんことで駄々をこねてな」
「待て貴様」
思わず普段より横柄な口調になった。
「まあまあ、みんな一つずつどうだい?」
明彦が後ろ手に隠していた紙袋を差し出す。
中には人数分の肉まんが湯気を立てていた。
「おっ、うまそう」
「いただきましょー!」
元気な二人が飛びつく。
「ほら、牧人と藤宮さんも」
「……あぁ」
牧人は渋々紙袋を受け取り、薫に差し出す。
「ほら、薫」
「ありがとう」
そして五人で談笑しながら肉まんを食した。
勢いよくかぶりつくことで肉汁が溢れ出す。なつめと牧人がそれで舌をやけどした。
それを見て耕平が笑い、牧人がまたしても反発した。
慎ましく生地を咀嚼していた薫が止めに入り、そんな光景を明彦が穏やかに眺めていた。
平和な時間。
会話。談笑。交流。
「三年になってからは受験に合わせた選択授業形式になるみたいね。同じクラスになっても、そんなに顔を合わさなくなっちゃうのかも……」
……学業の話題。
「いいじゃねぇか、最低限で。っていうか、親がいい大学出てるからってどうにかなるわけじゃ……大体教え方が上手いわけじゃねぇんだから、結局のところはやっぱ俺が頑張らないといけないんだよ……」
……成績の話題。
「なーんか、中学の頃から妙に大人びた雰囲気の女の子っていましたけどねー。あたしなんかがやっても背伸びにしか見えなかったと思うんすけど、ミステリーっす……」
……服装の話題。
「さすがに三食カップめんはねえと言われた。だがオレにとって重要なのは時間の短縮であって、味じゃないってことだ。それでも栄養の偏りは考える必要アリとは思うがな……」
……食事の話題。
「……まあ、楽しいんだからいいじゃない」
会話の内容は転々と移ろう。
それは、その内容自体にはあまり意味がないということでもある。
彼等にとって、会話という行為がそれだけで重要なのだ。
それは互いを認識する行為でもあるのだから。
常に五人全員が会話をしているわけではない。
飲み物を取りに階下に降りる者がいる(既に全員が葦原家の間取りを把握していた)。
ふと会話から離れ、読書や音楽鑑賞に興じる者がいる。
それを咎める声もない。強制の無い勝手気ままな集まり。
「……そうだけど、その二人の交際が始まったきっかけには、打算的な考えがあったのは確かだと思うの」
今、薫はなつめと討論している。
「そうなんすけど……いや、でも彼女のお父さんの言葉を鵜呑みにしちゃったってのが、他の友達みんなを刺激することになったわけなんすよね」
「そうだね。ここの一連の展開で、真っ当なことを考えている人なんて誰もいないもんね」
「善悪っつーか、ウソと本音っていうか……弱いところを見せたのが悪かったんすかねえー? そーゆードロドロはあたし、ちょっち苦手で……」
交わされる内容は、二人の間で今流行しているドラマの話だ。
「そこでそいつの彼女がソムリエナイフ片手に電話ボックスから飛び出してきて、忘れものだと叫びながらその時持っていたカバンにだな――」
「でも、その女が犯人とは決まってねぇだろ。事務員はフロントで倒れてたんだ。決め付けるにはまだ早いぜ」
「まだ話は終わってない。ここでそのナイフの持ち主が重要なんだ」
「まさか、三週間前にバックレたあのオッサンが……?」
「そうだ。ナイフがその親父のものであるとすれば、色々と裏が見えてくる……」
「オッサンが裏で糸を引いていたとするなら、女の精神病発言は嘘ってことになるな」
「そういうことだ。だがサロンの引継ぎ帳に書かれたメモのことも忘れるなよ。マネージャが残したあのメッセージの存在が、事件を更にややこしくしている」
「……確かにな。明彦はどう思う?」
「ふーむ……」
牧人と耕平による得体の知れない話を横で聞いていた明彦は、突然意見を求められて、ゆるく唸った。
統一性のない空気が、どこか一箇所で繋がっているような感覚だ。
「そういえば牧人、バーで発見された鍵は何の意味があるんだと思う?」
「……あれはシェフが置いてった。最初の犯行時のアリバイを作るためと考えれば説明がつくだろ」
二人は慌しく会話に戻る。
「…………」
五人が雑多に話し込んでいる姿を、明彦は撮影でもするかのように眺め――観察していた。
平和すぎた。
……緩やかに時間が過ぎていく。
「ただいま」
トイレに行っていた薫が戻って来て、
「……あ、そういやカオル先輩」
それに対して尋ねるなつめ。
「なぁに?」
「この前、レストラン行ったときに思ったことなんすけど」
「うん」
「カオル先輩って、生理重いんすか?」
その言葉で、場の空気が徐々に変化し始めた。
「な、なっちゃん――!」
臆面もなくそのようなことを言うなつめだが、清純な薫は赤面してしまう。
慌てて制止するも、なつめは「お?」と首を傾げるだけだ。
「そ、そういうこと話すなら……男子がいない時にしてよ……!」
必死だ。彼氏もいるのだから当然とも言えるが。
男性陣の一部もなつめの発言には少し反応したが、空気を読んで無視することにした。
「え〜、いいじゃないすか」
「でもぉ……」
同年代の同性とそのような話をしたがるのは、信頼の証と言えなくもない。
薫としても興味がないわけではないが、内心は忸怩たるものがある。
「……で、実際のところは?」
数分の押し合いの結果、さりげなく会話スタート。
「うーん、どうなのかな……量は多いんだけど……」
「あたしは全然軽いんすけどね、この辺がピリッとするだけで」
下腹を指し示しつつなつめ。
「そうなんだ……いいなあ」
「挿入タイプっすか?」
「な、なんで? 普通にナプキンだけど……」
「いやなんとなく……、量が多いと布だと横漏れが心配なんじゃ……って、そんなん棒でも同じか」
「うん。それにやっぱり……入れるのはなんか恐いし」
「かさばらなくていいっすけどね。学校とかに持ってくぶんには」
「学校は……ホントに、ね」
「多い日も安心な夜用ワイドはいいんすけど、邪魔くさくて……」
「体育の時とかいつまで経っても慣れないなあ」
「夏なのに一人だけジャージ……とか」
「うわぁ、みじめ。……わかるけど」
「もう大人しく見学すればいいんすけどね……」
二人してため息をつく。
渋った割に結局熱論を戦わせてしまっているが、薫は気付いていない様子だ。
「でもわたし、サイクルはすごく安定してるから、対策は立てやすいんだけどね」
「あ、そうなんすか」
「うん。ほぼ一ヶ月周期で来る」
「そりゃいいっすね、日付でわかるってことで」
「あと、時期になると肩がこってくるから……」
「……弊害多いなぁー、やっぱ重いんすね。……まあ肩こりはおっぱいの所為でもあんのかもしんないすけど。カオル先輩、地味におっきいし」
「そ、そんなことないよ……」
「え〜、いくつっすよ? こっそり、こっそり」
「…………」
耳を寄せるなつめに、薫が何事か囁く。
「あれ、意外にフツー?」
「だ、だから……」
「むー……、ちなみに今つけてるヤツのメーカー聞いてもいいっすか?」
「な、なんかわたしばっかり喋ってない? 今度はなっちゃんの方から――」
こうして話題は下着の話に移っていく。
いずれにせよ、乙女として男子に聞かれていいものなのかどうか。
「……でな、突然黒いマシンが乱入してきてよ」
「僕が帰った直後に負けちゃったのか。耕平にしちゃ珍しいね」
「…………」
女子間でそのような会話が交わされている中、男子は普通に会話を続けていたが、
「……お〜い、なに聞き耳立ててるよ牧人君」
「う、うわっ!?」
耕平の問い掛けに牧人が不自然に驚く。
「……お前ね、彼女の生理に興味があるのはわかるけど、そこまで露骨なのってどうよ?」
肩を回してくる。
からかうようなにやけ顔で。
「う、うるせぇなっ! 別に聞いてねぇよ!!」
「大きな声を出すなよ。藤宮にバレるぞ」
「く……」
幸い、耕平が上手く誘導してくれたので、牧人の盗み聞きが薫に露顕することはなかった。
「あはは」
「何笑ってやがる明彦……」
牧人は明彦が恨めしくなった。
……そして今日も、日が暮れていく。
02
「うーむ……」
携帯電話のメール画面眺めながら、牧人は唸る。
文面は彼の恋人たる薫がこれから家に来るといった内容だ。
その件に関しては素直に喜ばしい。彼女と共に過ごせることは牧人にとっても望んでやまないことだからだ。
しかし、牧人は難しい表情だ。
「デート……、か」
そういうことであった。
葦原牧人は、デートというものが苦手だった。
苦手と言うよりは、よくわからないと言った方が正しい。
何をしたらいいのか、何をすることが普通なのか、いまいち理解できないのだ。
彼としてもデートと称して薫と共に外出をしたい気持ちはある。
しかし、どこに行けばいいのだろうか。
近隣のデートスポットらしき場所を思考してみる。
――映画?
行ってどうするという意識があった。時間に空白を作るだけではないのか。
――服屋……とか?
牧人がよく赴く服やアクセサリーの店にはカップルの姿もちらほら見られる。
だが薫がそうしたものをゴテゴテと身につける様は想像できない。
――……メシ屋?
どちらもそこまで食い意地が張っていない。すぐに飽きそうだ。
選択肢がいくつも現れ、陽炎のように消えていく。
――それ以前に、あんまホイホイ出かけるのって安易じゃねぇのかな……?
不安になる。普通で良いものか。
多少緩和されたものの、こうして奇を衒いたがる癖はいつまでも抜けない。
しかし、デートに関して牧人が妙に慎重であるのには別の原因もあった。
「…………」
部屋の隅に置かれたベッドを見る。
彼女との付き合いが正式に始まったその日、そこで行われた出来事を回想する。
――ダサい……。
思い返す度に落ち込みそうになるくらい、格好悪い牧人だったのだ。
しかもその直後行われた甘すぎる行為に飲まれ“どうでもいいや”と思ってしまったことが更に彼を迷わせていた。
彼氏として薫とともにいる自分はどのようなスタンスをとれば良いのか。
彼女の前だからこそカッコ良く見せようとすべきなのか、
はたまた彼女の前くらいは無理せず素直に自分を出していくべきなのか、
後者が正しいのだろうとは牧人も理解している。
薫の前で無意味な強がりを見せることはやめにしようと、彼女に告白した時に決めたはずだ。
だが、生来見栄っ張りな牧人としては格好良いところを見せて挽回を図りたい。
そうでなくとも、せめて恋人として自然な姿を出したかった。
しかし、いずれにせよデートにおいて何をすべきなのかがわからない。
「……くっそぉ」
悩んだ。
相変らず余計なことを考え過ぎている牧人だ。
プライベートの牧人を知らない人間が、この思い悩む姿を見れば驚くかもしれない。
普段の牧人は地味だが、強気でクールな印象がある。内実を知っていてもそう見える。
だが実際のところは、こちらが彼の本性なのだろう。
強すぎる自信と劣等感――そうした自意識のバランスが不調和になっている。
捻くれているようで純真なのだ。
「こんにちは、マキくん」
「……あぁ」
来訪。
部屋に二人。
「昨日ね、お母さんに……言われちゃったんだけど」
「ん……?」
適当に座り、しばし雑談を交わした。
そして、一段落したところで薫がおもむろに鞄を開く。
「今日も映画借りてきたよ。一緒に見ない?」
「いいけど……、」
曖昧に肯く牧人を見て、薫は二種類の映画DVDを取り出す。
一つはホラー、一つは純愛。
互いの好みのジャンルを一つずつ。
「マキくんの好きな方からでいいよ」
「……じゃあ、こっち」
ホラー物を。
「……行こ?」
立ち上がり、促す薫。
「あぁ……」
牧人の部屋にはテレビがないため、映画鑑賞には居間に下りてくるのだ。
薫は映画が好きらしい。よく一人で見に行くとも言う。
一緒に見に行こうと牧人もよく誘われている。
それはデートである。完璧に。
――けど……。
しかし映画デートにおける上手な対応を知らない牧人は、安易に承諾することができない。
格好つけたがりだから。その場において、何をするのが最も格好良いのか解っていないと不安だから。
困った薫は、それならばと映画のDVDを借りてきて、牧人の家に遊びに来るようになったのだ。
「あはっ、こういうのって恐くて一人じゃ見れないけど、マキくんと一緒だとそうでもないからいいな」
「……そう、か」
楽しげにケースからディスクを取り出し、プレイヤーに挿入する。
同時に牧人は台所から二人分の飲み物と菓子類を持ってくる。
並んでソファに座り、視聴開始。
今はカーテンを閉めて、電気も消してある。ムードが大切だからだ。
……言ってみればこれは、牧人が映画デートに自然に出かけられるようにするための練習のようなものだった。
薫によってそのような予行練習をさせられていることになるわけだが、全体的に焦っている牧人も、基本的に純真な薫もそのことには無自覚だった。
映画はサスペンスホラー。
エンジンカッターを携えて道行く人々に襲い掛かる謎の怪人。
その中で、怪人による殺人事件を担当する主人公の刑事と、フィアンセたるヒロインの関係性が描かれている。
ありがちな展開にしてはロマンス的な要素も強く、それがどことなくチープな雰囲気を漂わせていた。映画全体で見ればB級などと評されるのだろう。
「……なーんか、イマイチだな」
「そうかな? わたしは結構面白いけど」
内容についての雑談をしながらの鑑賞。
こうしたことが出来るのは自宅にいることの強みかもしれなかった。
物語は後半に差し掛かっていた。
怪人に狙われたヒロインを駆け付けた主人公があわやというところで救出するシーンである。
「こんな怪人が出てきちゃったら、わたし……どうしようかな」
クッションを抱きかかえて薫はそんなことを呟いた。
ホラーやサスペンスの映画を鑑賞中、薫はそうした詮無いことをよく言う。
基本的にそうしたことをいちいち考えていては、ホラー映画など見られないと牧人は思っているのだが、そのような無粋な指摘が許されるのは初回のみだ。
「………………」
しかし、その発言を控えることで牧人は別の発言を考えるようになってしまう。
……強い。天然は。
特に牧人のような、余計な思考の多い者にとっては天敵ですらある。
会話は地雷だらけだ。
「お、俺が……守ってやるよ……」
深呼吸をして、そう言った。
「薫がピンチになったら、俺が……助けにいってやるさ」
恥ずかしい台詞にうなだれながら。
薫が牧人の方を向いて、きょとんとしている。
言わなければよかった。牧人はと言いながら思ったがもう遅い。もう出てきてしまっている。
いつもなら不必要に行ってしまうそうした気取った言い回しが、意識するとどこまでも白々しかった。
「あはは……気障だなあ、マキくん」
そんな恥ずかしがる牧人の姿を見て、薫はおかしそうに笑う。
「……う、うるせぇな。薫がいなくなるのは嫌だからだよ」
「ふふ、ありがとう」
手を握られた。
「……こうしてれば、恐くないね」
「そ、そっか……」
守るように握り返した。
それが小さな自己満足に過ぎなくても、二人が認めていればそれで良いのだった。
だからこのような恋人同士の交流も、まあ、あるのだろう。
無事に怪人を撃退し結ばれる主人公とヒロインの姿を見届けてから、牧人と薫はもう一つの純愛映画を鑑賞した。
――恥ずい……。
作中の男性が吐いた気障な台詞に、牧人は顔を逸らしたくなるのだった。
03
そして牧人は、遂にデートに行くことを決意する。
葦原家での映画鑑賞を五回ほど経てからのある日曜日だった。
「………………」
その日の牧人は、驚異的な完成度で駅前に向かっていた。
いつも気にしている身だしなみには、いつも以上に気を使った。
衣服・香料・整髪料、それら全て牧人の所持するものが最大限に尽くされた。
資源は最上級。更には朝五時に起床し、入念な準備を行った。
過度な装飾は身を滅ぼすと牧人は考えている。
しかし、気になって仕方がなかったのだ。
次から次へと不安が押し寄せてきて、彼に妥協を許さない。
要するに、まだ悩んでいるのだ。
薫の彼氏として、素直な自分を晒す方法――それが未だによくわからない。
……外面を取り繕ったところで、それらに至れるはずもないとは思う。
かといって、どうしたらいいのかわからない。
目指すものが今までと違い過ぎて、どうしようもなかったのだ。
そして、約束の十分前に牧人は駅前に到達。
「あ、おはようマキくん」
「…………」
――ちっ……。
薫が既に来ていたので、負けた気分になった。
「な、なんかすごいね……今日のマキくん」
牧人の全身像を確認して、薫が少したじろぐ。
「そうか?」
「う、うん……なんか気合入ってる」
「…………」
――…………。
水面下の努力(本人的には)を見抜かれて、牧人は更に負けた気分になった。
「……………………」
しかし、
「……馬鹿か」
失笑した。
「え?」
「すまん、余計なこと考えてた」
「……?」
薫の前では変に気取ったところで無意味なのだということを思い出した。
――緊張しすぎだ、俺……。
ため息をついた。それで余計な何かが少し落ちた気分になる。
「待ったか?」
「ううん、わたしも今来たところだから」
「悪いな」
「いいよ」
言いつつ、薫の服装を見る。
彼女も牧人ほどではないにせよ、普段よりは若干気合が入っているようだった。
それに気付き、牧人は嬉しくなった。
「それで、どこに行こうか」
行き先は決めていなかった。
意図があってそうしたわけではなく、ただなんとなく決めていなかった。
「えっと、薫は……どっか行きたい場所あるか?」
「うーん……やっぱり映画館には行ってみたいかも」
「………………」
予想通りの答え。
「でもマキくん、映画館苦手だよね。……電車三つ乗れば遊園地にも行けるから、そっちでもいいよ?」
「………………」
「やだ?」
「いや、やだっつーか……」
――映画館……遊園地……、
牧人は別にそれらの娯楽施設が苦手なわけではない。
無論、得意でもなければ、特別好きなわけでもない。だが、行けば相応に楽しむのであろう自覚はある。
彼が反発している理由としては、それがデートコースとしてあまりに普通だからである。
牧人は普通を嫌う。個性が欲しい。
――もう、そんな姿勢持ったって意味ねぇじゃねぇか……。
そうも思う。薫の前でくらいは無意味なカッコつけはやめて、素の自分を出そうとしているのだ。
特にここ最近は、彼はその二つの狭間で揺れているところでもあったからだ。
しかし、長年の性質からか、安易に承諾しかねるところだった。
「なら、マキくん他に行きたいところあるの?」
「うーん……」
かといって代案が出るわけでもない。
そもそも普通のデートにおける自然な振る舞いなどについて悩んでいたような牧人である。
漠然としたイメージがあるだけで、何をどうすればデートらしいのかも彼にはよくわからない。
ただ、薫の言ったような映画館や遊園地がその漠然としたイメージにすら合致するようなものであったから抵抗があっただけで。
「ならいいじゃない、行こうよ。ね?」
駅前からはその映画館が視界に入る。それを指差しながら、薫は促す。
「けどなぁ、あんなところ行ったって……」
「とりあえず見てみようよ。何か面白いのやってるかもしれないよ?」
「…………」
結局、煮え切らないままにずるずると薫に引っ張られていくのだった。
――っていうか、いつの間にか……。
最初は牧人が薫にどこに行きたいかを尋ねていたはずだった。
しかし今や、主導権は完全に薫にある。
「…………」
――情けねぇ男……。
それに関して、牧人は心中微妙なところである。
このまま流されているばかりでいいのか、自分がもっとリードすべきなのではないか。
またも色々な選択肢が浮かんでは消えていく。
――昼飯ぐらいは、俺が奢らないとな……。
心に決めた。
……しかしそれではいつもと一緒だ。
「ほらマキくん、あれなんかどう?」
「……うん」
「あ……でも、こっちも面白そう。迷うね」
「か、薫はどっちがいい?」
「えっと……じゃあこっち」
「入ろうぜ」
「うん!」
それでも、薫が色々と話しかけてくれる嬉しさで、全てどうでもよくなるのだった。
大切な少女が自分を見て、話しかけ、意見を求めてくれる。
……自分を認識してくれている。
方向性を、存在理由を……世界から許されているかのようなカタルシス。
――なんか……、楽しいよな。
口には出さないまでも、そう思っていた。
愛情を受けることは人の心を豊かにするものだった。
二人の姿からは、高校一年の時の文化祭が思い出される。
あの時も、楽しそうに話しかけてくる薫に対し、牧人は煙たがりながらもその実、快い気分に浸っていたはずだ。
胸に感じた甘い空気は、もしやその頃から継続しているのかもしれなかった。
ただ、あの頃はまだ羞恥心が強かっただけで。
そうして見ると、出せるようになってきているのかもしれない。
ほんの少しなのだろうが……素直な態度というものを。
二時間弱の映画を鑑賞し、二人は再び町へ出た。
その後は喫茶店で昼食を摂り、駅前の商店をあちこち見て回った。
――次は、遊園地に行くのもいいかもな……。
薫と共にねり歩く遊園地は、今までにはない楽しさが待っているに違いない。
デートの終盤、牧人は一人そのようなことを思っていた。
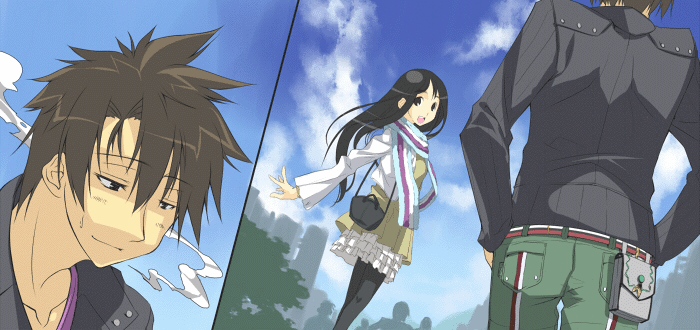
理想の関係を求めて、少年は思考する。
……それはひとえに、彼女のことが好きだからだ。
■■■■■
「今、何時?」
「ええと……」
薫に尋ねられて腕時計を見ると、長い時間が過ぎていることに気がついた。
「もうそんな時間……楽しいと時間過ぎるの早いね」
「そうだな、楽しかった」
「あ、ホント? よかった」
「……なんだよ?」
「だってマキくん、いつも仏頂面なんだもん」
「……わ、悪い。でも、楽しかったのはホントだから……」
「なら……よかったかな」
「…………」
集合場所だった駅前に戻ってきた二人。
今日最初に会った地点に立ったことで、否応なく別れを意識させられる。
足が止まり、視線が絡み合ったまま、少しの時間が経過した。
――なんか……、もっと……。
牧人はもっと彼女と一緒にいたかった。
二人きりで遊び歩くことは勿論楽しかったが、本当に二人だけになりたかった。
いつも、彼の部屋でそうしているように。
「なぁ、薫……」
「どうしたの?」
そう思ったら、牧人は薫に口付けをしていた。
突き動かされるような唇の接触。
完全に勢いだった。感情が勝手に体を動かしたかのような。
「……ん、マキ……くん」
「…………」
すぐに解放したものの、言葉を繋げることが出来ない。
「……び、びっくりしたよ……いきなり――」
「薫……」
名前を呼び、肩を掴んだ。
……なお、物足りなさを感じてしまう。
まだ牧人は帰りたくなかった。
薫に触れたかった。
二人だけの個室で、彼女を抱き締めて、キスをして、もっと……
――うちに、来て欲しいって……、
彼女を家に呼ぼうと思った。
――言ってどうする……?
今日は誰も来る予定はない。
それなのにこのような時間から敢えて彼女だけを呼ぶ理由がない。むしろ下心が見え透いていて白々しい。
だから喉元まで出かけた言葉を飲み込んだ。
百度の発起と百度の躊躇。
しかし、百一回目、
「……薫、……これからうちに来ないか?」
「え……?」
そのように口にすることが出来たのは、彼の彼女に対する感情か、欲求か……。
――やべ、どうしよ……どうしよ……、
そして言ってから慌てる牧人だ。
既に手は彼女の肩から離れ、所在無くぶら下がっているだけだ。
視線が定まらない。呼吸も乱れ、心拍も早まっている。
「ふふっ」
そんな懸命な牧人が可笑しかったのか。
「……いいよ。行こっか」
いつも通り、薫は笑って承諾した。
それもいつも通り。
手を繋いで牧人の家に向かう。
二人だけの個室。
牧人の両親が帰宅するまでの短い間、二人は互いの感情を確かめ合った。
それは、幸福で甘美な時間だったものだ。
…………そんな、いつもの流れ。
04
週末を控えた平日の午後。
夕日の河原に彼等は集っていた。
「なーなー、兄ちゃんもあっちでいっしょにあそぼうぜー!」
しかし、今日はいつもより多人数なのだった。
「うるせぇ……」
広々とした河原に点々と設けられたベンチの一つに牧人は腰掛けている。
自身の膝に肘をついて、相変らずの仏頂面だ。
「そーだよ。あっちの兄ちゃん強すぎてオレらじゃ勝てないんだよー!」
そして今、彼は数人の少年たちに囲まれていた。
皆、年齢は十歳前後――小学生たちである。
「助太刀してくれよ兄ちゃん!」
この年代特有の男女問わぬ甲高い声で、まくし立ててくる。
「そっすよ! あたしとソーセキ先輩じゃどう見てもハンデありすぎっす!」
ちなみに約一名高校生が混ざっているが、違和感がまるでない。
「ほら、チビのねーちゃんもこう言ってるじゃん」
「チビ言うなぁ!」
「なーなー、やろうぜー」
一人の少年に制服の袖をぐいぐいと引かれた。若い両手は活力に満ち、体躯からは予想もつかぬ牽引力を伴っている。
だから牧人も少し強く振り払う。この応酬も既に五度目になる。
「うわっと!」
少年は弾かれたように後退した。
「ちぇ、なんだよー! 暇そうにしてるから誘ってやってんのにー!」
牧人の大人げない露骨な拒絶に、その少年は躊躇わず不快感を露にする。
「ちょっとだけだからさ、あの兄ちゃんが登板してる時だけでいいから!」
しかしすぐに別の少年が声をかけてくる。感情の発露が早く、立ち直るのもまた早い。
「うるせぇなぁ……ずらずら集まってくるんじゃねぇよ……」
ようやく開かれた口から漏れるのはあまりに億劫なそんな言葉。
牧人は子供が嫌いだった。イメージ通りではないだろうか。
「マキくん、少しは相手してあげなよ?」
並んでベンチに座っていた薫がいつも通り、苦笑混じりに言う。
「うっせぇな。俺はガキが嫌いなんだよ」
「駄目だよ。そんなこと言っちゃ。マキくんだって昔は子供だったんだから」
「……ふん」
そっぽを向いた。薫はため息をつく。
「もぉ……どっちが子供なんだか」
ボソッとそんなことを言われた。
「……っ」
牧人は一瞬反応したが、無様なところは見せまいと踏みとどまる。
このところ、沸点が上昇している傾向にあった。
「……ひょっとして兄ちゃん、野球のルール知らないの?」
「ばっ、知ってるに決まってんだろ!」
しかしまた別の少年が口にしたそんな言葉に、牧人はそのように反応する。
「ホントにー? ならいっしょにやろーよー!」
「やんねぇよ。なんで俺が小学生と野球なんか……」
「そんなこと言って、やっぱりホントは知らないんだ?」
「んなわけあるかぁ!!」
激する牧人。
「わーい、兄ちゃんがおこったー!」
「おこったー!」
しかし少年たちは怯えるどころか、諸手を挙げて喜び始めた。
「……チッ、ほら、もうあきらめてあっち行けよ」
上がりかけた腰を下ろしながら、牧人は手を払う。
しかし少年たちは去る様子を見せない。
――なんでこいつら……?
無愛想を自覚している牧人は、なぜ小学生たちが自分にたかってくるのか不思議でならなかった。
牧人は子供が嫌いだったし、自分のように無愛想な人間に好き好んで話しかけてくる意味がわからない。
「ほら兄ちゃん、バット。こいつ使ってよ」
しかし牧人は子供に好かれた。
或いは純粋な彼等は、牧人が押し隠した内側にあるものを見抜いているのかもしれない。
「おい牧人、なにグズグズしてんだよ! 早くお前も参加しろ!」
マウンドに立った耕平がこちら目掛けて叫んでいる。
手にはグローブ。ゴムボールを弄びながらの挑戦的な笑み。
「ほら、あっちの兄ちゃんも言ってる」
「あの馬鹿……少しは歳ってもんを考え――」
「まさかオレサマとの決闘に臆したかー? やれやれだな牧人、お前の根性はそんなもんかーい?」
いつも通りのにやけ面でそのような事を言われ、
「いいぜ上等だてめぇ、ぶっ潰す!」
周囲に集まっていた小学生の一人からバットをもぎ取る牧人だった。
彼の中にある妙な対抗意識が、耕平との勝負は必ず立ち向かわせるのだ。
薫ではないが、どちらも等しく子供である。
「わーい、兄ちゃんがやる気になったー!」
少年たちは喜んだ。
「……ふぅ」
そして薫が“しょうがないなぁマキくんは”とでも言いたげに、その背を見送っていた。
慈しむような、優しい笑みを浮かべながら。
牧人たちが通う平坂高校の少し先には小学校がある。
立地的に近場であることから、必然的に通学路は共通してくる。
この日も、下校時――いつもの河川敷で小学生たちが野球をしている場面に出くわしたのだ。
――おいガキども、オレも混ぜろよ!
大人げない遊びが大好きな棗耕平が即座に食いついた。
いつもと違う遊び相手の突然の参加を、少年たちは快諾する。
明らかな実力差がある面子が混入したことで、試合は確かに混迷を極めたが、それがかえって刺激にもなったようだ。
「どいてろ、俺が打つ」
バットを片手に、牧人はずかずかと打席に乗り込んだ。
唐突に現れた代打葦原牧人にも両チームは自然に対応する。
所詮は小学生の遊び野球である。ルールは曖昧でイレギュラーにも寛容だった。
「牧人、やる気になったの?」
キャッチャーの明彦がそう尋ねてくるのに、牧人は闘争心剥き出しの瞳で肯きを返す。
ちなみに明彦は試合の全工程でキャッチャーを務めている。
耕平曰く、
――明彦、お前はキャッチャーをやらねばならんぜ。主にビジュアル的にな。……ちなみにバンドだったらドラムだからな。ビジュアル的に。
ということであった。結果、明彦はずっとキャッチャーをやらされていた。
明らかに論理性を欠いている説明だというのに妙に納得させられてしまうのは一体何故だろうか。
――昔っから、断るの下手だからなぁこいつ……。
牧人は明彦をそのように見ている。
最近では耕平の妙な思い付きに、いつも一番に付き合わされる可哀相な役回りにされつつある彼に同情を感じていた。
「…………」
しかし当の明彦自身は、そうした立場を苦にするどころか、楽しんですらいた。
断るのが下手なのではなく、そうする必要を感じていないだけなのだ。
「がんばれ兄ちゃん! かっ飛ばせ!」
「マッキーせんぱ〜い! ソーセキ先輩の豪速球をホムーランしちゃってくださいっすー!」
ベンチから小学生たちと、それに混じってなつめが叫ぶ。

「耕平!」
彼等の期待を背負うように、牧人はバットを突き付けた。
ちなみにそのバットは子供たちのうち誰かの持ち物である。
プラスチック製で、妙にポップな書体で前向きな英語のフレーズが書かれている。
「本気で投げてこい! 月までふっ飛ばしてやる!」
そのようなバットを手に、気障な言葉を放つ牧人はとてもシュールである。
耕平は吹き出した。
「はぁ? 何言ってんの、お前がオレに勝てるわけないじゃん」
「……ぶちのめす!」
そして、いつも通り戦いが始まるのだった。
夕暮れの河原を舞台に、多数の観客を交えて。
■■■■■
「で、もうこんな時間……」
呆れた口調でそう漏らしたのは薫だ。
腕時計を見る。時刻は夜の十時近く。
場所は町中の公園。
当然、小学生たちはとっくに帰宅し、今頃は寝入っているだろう。
「もー、マキくんってなんであんなに負けず嫌いなのかなぁ……?」
「見てるこっちは楽しいっすけどねー」
「夢中になりすぎるんだね」
薫が呆れ、なつめが笑い、明彦が肯いた。
「おらぁ!」
そして話題の中心たる葦原牧人は、
「どーした牧人、大分動きが鈍ってきたなあ?」
「言ってろてめぇ!」
公園内に設けられたフィールドで、耕平とバドミントンをしていた。
結局、河川敷で行われた野球対決は決着がつかなかった。
耕平の球を牧人が打ち、塁を進めても、結局次打席の小学生で三振を取られてしまう。
逆の場合も同様。牧人が投げ、耕平が打つがそこまでだった。
結果、牧人と耕平による熾烈な盗塁合戦が繰り広げられ、小学生たちも二人の真似をし始めたためにとても野球の体ではなくなった辺りで試合が強制的に終了させられた。
耕平的には大層愉快な展開だったようだが、彼との勝負をしたかった牧人には納得がいくはずもない。
そのまま駅前に繰り出し、別のゲームで勝敗を決そうという運びになった。
ゲームセンターの各種対戦ゲームを総なめにしてから、同ビル上階の卓球場とバッティングセンターでの決闘を経て、地下の撞球場でビリヤード対決が行われた。
勝敗は五分。
大半は引き分けで、たまにどちらかが勝つ。
しかし、両者の実力は拮抗しているわけではない。多くは耕平が手を抜いている。
彼が専門外の競技では牧人が圧倒的な差をつけて勝つ。だが、そうではないものに関して耕平はいい勝負になるように敢えて実力を抑えて臨んだ。
だから牧人は納得しない。
負ければ当然悔しいし、勝ってもそれは初心者を一方的に痛めつけただけに過ぎず、また引き分けても手心を加えられたと感じるのだ。
そしてずるずると公園に移動し、そこでバドミントン対決と相成ったわけである。
当事者二人は当然として、他の三人もこの時間まで付き合わされていた。
「馬鹿か! ちゃんと見てろよ、どう見てもアウトだろうが!」
「ンなこと言ってもなあ。もう暗くてよくわからんし」
現在二人は線上に落ちたシャトルの判定について口論中である。
試合は終盤で両者の得点は同等。この判定が勝敗を決すると思われた。
「じゃあもうお前の勝ちでいいや。オレもさすがにダルくなってきたから」
「ふざけんな! そんなんで納得できるか!」
見慣れた光景ではあるが、互いによく飽きないものだと傍観者三名は感じていた。
「……はいはい、もうストップだよ!」
終わりが見えそうにない論争に割り込んだのは藤宮薫。
これもいつもの光景。
二人の喧嘩――牧人が一方的に因縁をつける場合も含めて、止めるのは常に彼女だった。
なつめはともかく、明彦も二人の戦いを見て楽しんでいる節があるからだ。
「もう今日はこの辺で終わりにしよ? マキくんはともかく、このままじゃ棗くんたち帰れなくなっちゃう」
「そーだぞ牧人、もう終電も近いんだ。今日はこの辺でしまいにしようぜ」
「チッ……!」
不満そうにラケットを下ろす牧人だった。
「マキくんはもう少し回りを見るようにしないと……」
「うるせぇな、わかってるよ……」
薫に注意されてばつの悪そうな顔をするのもいつも通り。
――馬鹿だな。なんで俺あんな必死に……、
熱しやすく冷めやすいのだ。
「不完全燃焼って感じだな牧人。最後にジャンケンでもして決着つけるか?」
「ジャンケン……?」
「白黒ついたほうがお前的にもいいんだろ?」
「いいぜ、やってやるよ……!」
薫の方を一瞥し、脱力したように彼女が肯くのを確認してから牧人は拳を握り固めた。
そして本日の長きに渡る戦いに終止符を打つジャンケンが始まる……。
「じゃーんけん」
「ぽん」
当たり前だが、掛け声同様に勝負はあっけなかった。
牧人がグー。耕平がパーだった。
「はい、牧人の負けー!」
「くっそぉ!」
本気で喜ぶ耕平と、本気で悔しがる牧人だった。
ようやく二人の長い戦いが終わった。
薫たちは耕平を称えるためではなく、傍観していた互いを労うために拍手をした。
「はー……」
それを見ていたら、牧人はなんとなく力が抜けた。
――しかしなんだ……この虚脱感……?
すっかり冷めた頬に、夜気が冷たかった。
■■■■■
――敗者は勝者の凱旋を見送るがいいぜ!
耕平のその言葉に従ったわけではないが、牧人と薫、それに明彦の三人は駅まで耕平となつめを見送りに行くことにした。
「門限とか大丈夫なのかお前ら?」
「平気だろ、ガキじゃねえんだから」
「あたしの親、その辺テキトーなんで平気っす」
「そうか……」
ちなみに牧人は大幅に門限破りだった。
今日も帰宅したら両親との戦いが待ち受けていることだろう。
――メンドくせぇ……。
自販機でジュースを買った。飲まなければやっていられないのだ。
時刻は最早深夜に近い。
商店街の明かりも消え初め、まだ明かりが灯るのは夜間営業の飲食店ばかりになる。
「うぃ〜す!」
「だ〜!」
その内の一軒――小ぢんまりした居酒屋から、肩を組んだ背広姿の中年二人組がまろび出た。
近隣企業に勤めるサラリーマンだろう。赤ら顔でから笑い、呂律も回っていない。
週末だ。日頃の鬱屈を晴らすが如く、心行くまで痛飲しているのだろう。
頭にネクタイを巻きつけ、だらしなくシャツの裾を出した正装姿には哀愁すら漂わせた。
「もう一件いくぞ〜らァ!」
世に言い知らしめるかのような大声でそう宣言し、中年二人は酒気を纏わせながら夜の町へ消えていく。
「クソ真面目で融通の利かねぇ大人って、嫌だけどよ……」
そんな大人たちの姿を見ながら、気怠い調子で葦原牧人。
「ああいう大人にはなりたくねぇな」
コーラを煽りながらそう言った。
「オッサンがたも、色々大変なんだろうぜ」
「リーマン生活のストレスなんて、あたし考えたくもないっすよ」
「そうそう。気をつけろよ牧人、三十年後は我が身だぜ?」
「……ストレス解消ってのはわかるよ。今は不景気だっていうしな。ストレスなんて溜まる一方だろうさ」
「なら、お前は何が納得いかないんだ?」
「あんなデロデロになるまで酒飲んで、挙句俺らとかに後ろ指さされるのって、どうなんだ? 確かに仕事は大変だろうが、最低限の自意識は持つべきなんじゃないか?」
「まあ、お前の言いたいこともわかるが……つまんねえ見栄とか気にしたくもなくなるくらい、キツイ日々なんじゃねえの?」
「だからってな……見苦しいだけじゃなくて、モラルとかあんだろ? あのまま酒の勢いでヘンなことやらかしたらどうする?」
「ヘンなことって?」
「あたしたちに絡んできたり、とか?」
牧人は肯く。
「あー、なるなる。確かにお前は藤宮があのオッサンに口説かれたりしたらブチギレんだろうな」
「な、棗くん……!」
引き合いに出されて、薫が照れた。彼女もこの手の振りには弱いところがある。
「耕平だって、仮に彼女がなんか言われたら嫌だろ?」
「お……?」
「マキくん……」
意外に冷静な牧人の対応に、一同は少し感心した。
「なんだよ?」
「なんでも」
皆が黙ったので当惑する牧人に、耕平は頼もしく笑って返した。
「……まあ。確かにオレも彼女やお前らに何か手出しされて“酔ってましたから”って理由付けされんのはイヤだろうな」
「でも、あの人たちだってそのぐらいはわかってるんじゃないすかね? いい大人なんだし」
「しかし牧人の言う通り危ういもんだぜ。週末に酒飲んで騒ぐってことは、やっぱそんだけ日頃溜め込んでるモンがあるってことだ」
「えっと、つまり……吐き出せるタイミングを求めてる、ってこと?」
「そうだ。普段言えないようなことを酒の力を借りて言ったりするわけだな。飲み屋の中ならそれでもいいが、外でその矛先がどこに向くかなんてわかりゃしねえ」
「羽目を外すのは居酒屋だけにして欲しいもんだな」
唾棄すべきものであるかのように牧人が言う。
「空気読んでお酒飲んでくれる分には、あたしらも何も言いませんけどねー」
「けど、無様だろ……」
「牧人」
耕平がやや強い口調で。
「あの人たちにも守るべきモンがあるんだ。家族とか生活とかな。あの人らも、そういう自分の大切な人の前ではあんなダセえカッコ晒したりしねえだろうぜ」
「知り合いでもない俺らにいい顔する必要なんてないってことか?」
「違う。違わないが違う」
「……どっちだよ?」
「無関係なオレらにまでそうするほどの余裕がねえんだよ。大人は忙しいからな、八方美人な生き方なんてできねえんだ」
「………………」
牧人は苦悩するように沈思した。手にした空き缶を握り潰す。
「……そういうのって、相反してるってことなのかな?」
「どっちか選ばないといけないってことっすかね」
薫やなつめの中にも、似たような思惑があったようだ。どこか物憂げな呟きがこぼれる。
「まあ、政治家とか見てればわからねえか? 誰からも非難されない振る舞いなんて、できるヤツはいねえのさ」
「……そんな、もんなのか」
「大人ってのはままならないものだからね」
静観していた明彦がため息をつくように言う。
「耕平の言うことは正しいよ。けど、牧人みたいに理想的なあり方を探す姿勢も、大事だと思う」
「そう言うが、成し得ない理想に意味なんかないぜ」
「成し得ないからこそ価値があるともとれないかな?」
「ん? んむー……」
明彦の言葉に耕平も黙考してしまう。
「理想と現実の二つを両方とも守ろうとしたら、人は何にもできなくなっちゃうよ。だからある程度の折り合いはつけていかないといけないんだ」
「つまりはオレの言ったことじゃねえか」
「けど、正しい姿を認識しておくことも大事だとは思うよ。そうしないと、何のために生きているのかわからなくなりそうじゃない?」
「ふーむ……っておい、牧人がなんかオーバーヒートしてねえか?」
「し、してねぇよ……、でも俺、やっぱ間違ってんのかな?」
「間違ってないよ牧人は。ただ、ちょっと色々気になり過ぎてる」
「…………」
「牧人の疑問は難しいんだ。気にし過ぎてもいけないけど、最低限の自意識とか、空気を察する力は持ってないといけない」
「だからさっきのオッサンたちにはそれがないって――」
「あるいは……」
遮るように。
「苛立ちとか、ストレスとか……そういう心に溜まった色々な悪いものを、暴力的な感情に結び付けないためにも、あの人たちはああやって騒ぐのかもしれないよね」
「………………」
牧人、再度沈黙。
「もー、先輩がたの話は難しすぎて何がなんだか」
なつめは頬を膨らませた。
「まあ、ケジメをつけるべき場所とチャラけてもいいタイミングを間違えるなってことだよボウズ」
「ボウズ!? 遂には女子としてすら認識されなくなったんすかあたしは!?」
「お前ら……」
一瞬でいつものノリに戻る二人に牧人は遠い目をした。
「牧人」
背後から明彦が手を伸ばしてきた。
「ソーダ飴。舐める?」
「……ありがとよ」
差し出された袋に手を入れ、一つを取り出した。
舐める。爽快な刺激が舌下に広がった。
「みんなも舐めなよ」
「お、相変らず気が利くな」
「わーい、飴ちゃんおいし」
「ありがとう明彦くん」
――まぁ……、大人の悩みなんて……その時になったらでもいいのか……?
飴を舐めながらため息をつく牧人。
人生の理想。
……彼等はいつまでそうしたものを探していられるだろうか。
夜空の下で繰り広げられる、変わらぬ一同の姿を目に心からそう思った。
05
楽しい時間はすぐに経つとよく言われる。
気付けば新たな年を迎え、季節は冬だった。
冷ややかな空気はますます熱を失い、ガラスのように鋭く澄み渡っていた。
大気が乾きを帯びる。落ちた木々の葉を見ることなくなって久しい。
先日、今冬何度目かの降雪を観測した。
冬が全盛期を迎えていると同時に、牧人たち学生にとってそれは年度の終わりを意識させるものだった。
高校二年も三学期。
彼等の青春も、いつの間にか折り返している。
「……よう」
「おはよ、マキくん」
路肩に雪の残るその日。
二人はもう何度目になるかもわからないデートをしていた。
「今日も、さむいね」
「大丈夫か?」
「うん、平気」
自然な会話。
かつてはあった羞恥も気後れも、いつしか微塵と消えていた。
「手、つないでいい?」
「あぁ」
牧人は戸惑うことなく手を差し出す。
……ふと、思う。
初めて彼女をこの手に抱いた時。
そのときめきは今も続いているだろうか。
「…………」
手袋越しに感じる握力がまだ愛しい。
それを噛み締めるように牧人は目を閉じてみるも、どこか感覚がぼやけている。
「あ、マキくん、あのね……」
「ん……?」
不意に立ち止まり、手が離された。
薫は持っていた鞄をまさぐり、一つの袋を取り出す。
綺麗な包装を施され、豪華な柄のリボンで結ばれたその袋。
「はい、マキくんに、お誕生日プレゼント!」
それを差し出しながら華やぐ少女。
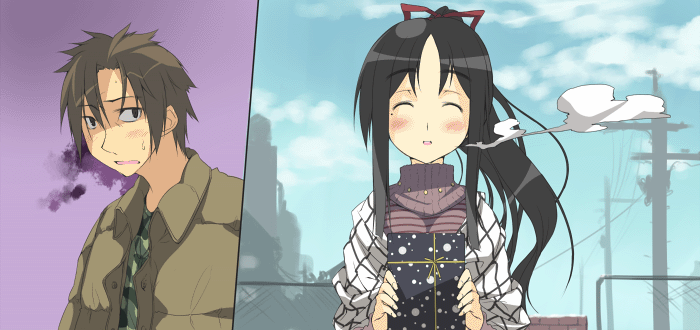
「え……た、誕生日?」
「うん。一昨日、マキくん誕生日だったでしょ?」
「そ、そうだけど……なんで知って――」
「明彦くんにこっそり聞いたの。プレゼント、したかったから」
「え……あ、ありがとう…………」
またも勝手なことをしてくれた明彦に対する怒りよりも、牧人は嫌な焦燥感に苛まれ始めていた。
――プレゼント……って……、
内心では、牧人も薫の誕生日には彼女に対して何かしてやらなければと思っていた。
しかし、誕生日プレゼントを渡したいと思いつつも、その誕生日を牧人は知らなかった。
そして聞き出すタイミングも逃し続けていた。
……挙句、またしても先を越されてしまっている。
月日を経ても、相変らずの牧人と薫。
「……あのさ、薫」
「なぁに?」
「お前の……誕生日って……」
「ああ……、えっとね――」
告げられた日付は三ヶ月ほど前のものだった。
「ま、マジかよ……」
――何……やってんだ俺……っ!?
久々に極大の自責だった。
「………………」
――ずーん(擬態語)。
落ち込む。自業自得なのだが、落ち込まざるを得なかった。
「……ごめん、薫」
「え?」
「いや……、俺、その、お前の誕生日になんにもしてやれなくて……」
珍しく殊勝だった。
「え? い、いいよそんなの。わたしが勝手にプレゼント用意しただけだもん」
「いや……、でも……なんなら今からでも……」
「や、やだよ……それじゃわたしがプレゼントねだったみたいになっちゃう……」
「だって……」
「いや……」
恋人同士の譲り合い。
相手を思うが故に、噛み合わない議論がしばらく交わされた。
そうしているうちに、牧人は立ち直ることができた。
「ホント……悪い、来年は……その、なんか渡すから」
「……うん。待ってるね」
結局最後に、そんな約束を交わした。
そしてその日は外で昼食を取ってから、二人は牧人の部屋へ。
二人のデートは毎回このような感じだった。
どこかへ遊びに行った後に、牧人が恐る恐る部屋に来ることを提案し、薫が承諾する。
そのような流れを何度か経て、牧人も次第に彼女を部屋に呼ぶことに慣れていく。
喉元過ぎれば……とは少し違うが、かつて覚えていた異様な緊張や戸惑いは最早ない。
見る者が見れば、調子付いているとさえ受け取るかもしれなかった。
好意が自然な形で態度に現れている、とも言える。
関係性の模索を放棄し始めた、……とも言える。
いずれにせよ、そのような流れが定番となっていたのだ。
だから今日も……、
「薫……」
「マキ、くん……」
ベッドに並んで座り、二人寄り添う。
「……薫、目……つむって……?」
「は、はい……」
口唇接触。
手馴れてきた愛撫。
二人、触れ合う。
……そっと、溶け合う。
心地よかった。
空気が本当に甘味を帯びているかのような錯覚。
二人は互いに愛を語り、貪りながら、美味なる空気に染まっていく。
……そのような恋人同士の交流も、まあ、あるのだろう。
■■■■■
様々な情事の後に薫が帰宅し、牧人はプレゼントを貰ったことを思い出した。
机の上に置かれた小奇麗な袋を手に取り、リボンを解く。
「……これって」
中には一枚のDVDが入っていた。
トールケースの表紙には、見覚えのある男性が写っている。
「……教則……DVD?」
それは牧人が好きなギタリストが出演している教則DVDだった。
“プレイスタイルだけでなく、サウンドメイキングも徹底解説! これで天才の技術と音があなたの物に!!”
そんな大仰なコピーが踊っている。
「ギター……か」
部屋の隅に置かれたその弦楽器は埃を被っていた。
思えば、またしばらく触れていない。
少し前――薫と恋人同士になる直前辺りまでは、彼女とセッションなどもしていた。
しかし、現在のような間柄になってから、この部屋に来てギターを弾き聞かせたことはそういえば一度もなかった。
彼等には恋人同士として、他にするべきことが数多くあったのだ。
……そちらの方が、優先順位が上だっただけの話。
「…………」
パッケージのギタリストが持っているのは、牧人と同じフライングVだ。
当然、牧人のような安物ではないのだろうが、種類としては同じギターである。
薫はエレキギターに関しての知識はほぼ皆無といっていい。
恐らくは牧人と同じデザインのギターを持っていて、なお且つ名前も聞き覚えがあるから、という辺りが購入の理由だと思われた。
「あ……」
裏面に牧人が昔よく赴いていた楽器屋のシールが貼られていた。
薫にとってはああした店など専門外も甚だしいだろう。
中学生の頃、初めて行った時の疎外感を牧人は思い出す。
他人へのプレゼントだからといって、軽々しく踏み込めるような空気ではなかったはずだ。
「薫……」
そんな慣れない店に彼女は一人で行ったのだ。
牧人の誕生日プレゼントとして、このDVDを購入するために。
「ちくしょう……馬鹿だな、……あいつ」
胸が熱い。
愛しくて涙が出そうだった。
自分のためにそんなしなくてもいい努力をしてくれる彼女が、何よりも大切に思われた。
「ふぅ……」
しかし牧人は、ビニールを剥がすこともなくDVDを机の上に置いた。
そのまま、手にした包みをくしゃくしゃと丸める。
「…………」
ばたり、とベッドに倒れ込んだ。
枕に顔を埋めると、かすかに彼女の匂いがする。
……体が、心地よく疼いた。
「好きだよ、薫……」
思わずこぼれた呟きは、どこか白々しく残響した。
その言葉に喜ぶ彼女の顔を想像して、一人口の端を歪める。
そして……、肝心の言葉は、誰にも届かず掻き消えた。
いつものことだ。
生じ始めた僅かな歪み。
……それは匂やかな少女の体臭に紛れて、少年はまだ気付くことが出来ない。
【戻る】