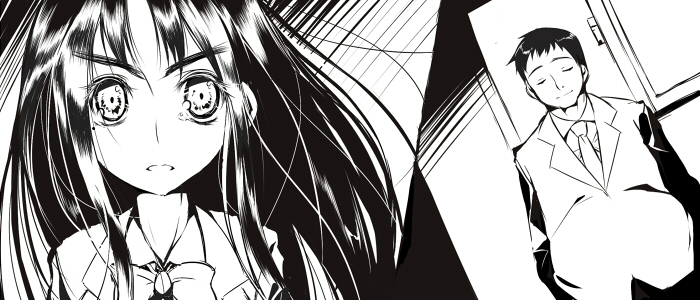モノクローム
00
鈍色の空の下を歩いている。
「……っ」
道端に唾を吐き捨てた。
何故だかそのような気分になったのだ。
心中の荒んだ様相の現出だろうか。
孤独の町を、歩いている。
早い時間。
牧人は奇妙な感覚に囚われた。
――人が、いない……?
登校時間にはまだ早いが、早朝というほどでもない時間。
しかも今日は平日だ。
住宅街は死んだように静まり、突き抜けるように閑散としていた。
空虚。
そんな言葉が似合う空気。
「…………」
だから、いつか感じた寂しさが再び胸に去来した。
平穏な日々の先に控えている、世界の闇のようなものを幻視する。
……牧人は知らぬことだが、それは芥川なつめが怯え、逃げようとしたものだ。
この時の牧人もおぼろげにそうしたものを感じたのである。
平和な生活はいつまで約束されているのだろう。
終焉は訪れるはずだ。
いつか、必ず終わりが来る――――
……今日のように。
家を出て、最初の信号で立ち止まった。
横断歩道を隔てた先には青色の灯火。だというのに、牧人は足を止めてしまった。
長年の習慣がそうさせるのか、或いは何かを期待していたのか。
「……薫」
愛しかった者の名を呼んだ。
すぐに自己嫌悪に陥る。
その、嫌いな自分というものを、牧人は久しぶりに認識した気がした。
…………この日、彼女はこの場に現れない。
孤独の町を、歩いている。
公園の傍を通過した。
語らうために集まった場所。触れ合うために遊んだ場所。見送るために出向いた場所。
僅かな遊具と運動場があるだけの空間に、牧人は色々な意味を感じていた。
雨に打たれた遊具と同じく、空気が錆付いている気がする。
その場が視界の外に外れ、丁字路で立ち止まった。
高校へ向かうには直進すればよいが、牧人は右方へ視線を移した。
無人。
「……明彦」
それは親友の名。
それもまた、過去のものとなってしまったのか。
…………この日、彼はこの場に現れない。
孤独の町を、歩いている。
学校に向かっているという感覚が薄い。惰力で歩行しているようだ。
市内中心部を走る河にぶつかると、景観が大きく変容する。
建造物のない空間は遠くの空まで見渡せる。
どこまでも無人だ。だが聞こえる水音が時間も流れているものと教えてくる。
河沿いの道。駅方面に向かう道がぶつかる地点で立ち止まった。
停止すると、景色に意識が向く。
広々とした河原も、時折友人たちとの遊戯の場となった。
「耕平……、芥川……」
頼もしい仲間たちの名だった。
彼等の纏う騒がしさを牧人は少し苦手としていたが、思い返せばそれは何より楽しかった。
…………この日、彼等はこの場に現れない。
「ん……」
周囲にざわめきを感じ、意識を戻した。
河川敷を、自分と同じ服装の少年少女が歩いている。
所々に、ランドセルを背負った小さな影も行き来していた。
今は通学時間帯なのだ。
生徒児童の一群で、朝のこの場はにわかに活気付いている。
だから思考が現実にシフトする。
陶酔するような早朝が終わる。
「……馬鹿が」
小さな罵声は自身に向けられたもの。
衆人の中でも孤独を感じてしまう、自分。
……夢を見る時間は終わったのだ。
終わらせてしまった。
――取り戻せるものなら……、
過去に甘えたくなる。そんな弱さに端を発する感情は否定したい。
しかし、ふと思ったりもする。
…………強くあろうとした長年の自身の考えが、果たして正しかったのかと。
無様な潔さをもってやり直すには、彼はまだ若かったのだろう。
白い校舎が見えてくる。
そしてこの日、牧人はひとりだった――――
01
教室。
生徒たちの喧騒を、牧人はふと遠くに感じた。
思考に集中していたか、単なる自失か。
現実すら見失い、時間から放逐されたような孤立感覚。
自分が空虚な顔をしているような気がして羞恥心が刺激される。
頭を振るった。無為な空想を追い払うために。
そこで、無意味に薫の座っている席に視線を移してしまった。
「…………」
そこに彼女はいない。
脇に鞄もかけられていない。昨日の放課後から椅子を引かれた様子もない。
不在であろうと、登校の気配が少しでもあればその存在は感じられるはずだ。
それがない。
……欠席、なのだろう。
藤宮薫は、学校を休んでいた。
それが牧人の心に鈍痛を残す。
「………………」
牧人は先日、半年ほど恋人同士として交際を続けていた藤宮薫と別れた。
明確な理由は牧人の中にも存在しない。
ただ、薫と共にいて、ふやけていくような自分に嫌気がさした、ということだった。
――だから仕方ねぇ、ことなんだ……。
そう自分に言い聞かせる。
このまま彼女といては、自分は益々溺れて駄目になっていく不安があった。
彼女と別れる直前の自分の言動を思い返すと寒気がする。
「………………」
それは、なんて無様な男の有様だろう。
だから、別れ話を持ちかけ、一方的に押し通した。
そのように腐っていくだけの自分には、薫と共にいる価値などないように思えたのだ。
牧人はそう考えていた。これも一方的な思考。
当然、薫にはそのような内情は説明していない。
彼女からすれば理不尽にも程があるはずだ。
あまりに突然の理解不能の拒絶。納得出来るはずもなく。
だから別れた直後も、その次の日も次の日も、彼女は牧人に話しかけてきた。
欠点があるなら直そうと思った。誤解があるなら話し合おうと思った。
薫はそう思って問いただすも、しかし牧人は答えない。
必死で素直な薫の言葉を素っ気無くあしらうだけだ。
…………立ち去る薫は、悲愴な顔をしていた。
――これで……いいんだ……! だから、迷うなよ……!
しかし心は悲鳴をあげている。
彼女を拒絶することが、自分を通すことが辛くてたまらない。
その感覚に気付いている。その感情を自覚している。
だが、彼は行為の正しさを信じる。妄信するしかない。
説明のしようもないのだ。
かつては確固とした構造を保持していた牧人の理論も、ここ最近の友人たちとの交遊の中でかなり希薄になってきていたからである。
自分の持っていた考えが、間違いとまでは言わないまでも何か偏った見方であることを彼は少しずつ感じるようになってきたのだ。
だから、これら一連の行動の動機を満足に語ることなど出来ないはずだ。
語ればボロを出すことが予想できた。
或いはそうして穴だらけの説明をすれば、一時の気の迷いとして彼女との関係をやり直すことも出来ただろうか。
……空想に過ぎずとも、客観的にはそう思わずにはいられない。
「………………」
――俺、やっぱり……間違えて……、
今更、そのような不安に駆られる。
もっと他の方法があったのではないか。
少しの時間でも、それを探すことをしてもよかったのではないか。
後悔にも似た感情が入れ替わって行く。
「…………あいつ――」
しかし、もう遅いのだ。
空白の机を眺めつつそう思う。
当初は突然の別れ話に混乱を隠せずも、何とか現状を変えようと奮起していた薫だった。
だが、数日を経ても何も応えようとしない牧人に、彼女はもう話しかけてこなくなった。
愛想が尽きたわけではない。
彼の心が自分の言葉も届かない程に遠くへいってしまったことが単純にショックだったのだ。
ここに来て、彼との復縁が絶望的であることを心底から理解してしまったのだろう。
……そしてこの日、彼女は学校を休んだ。
このタイミングで風邪などということはないはずである。
残酷な事実に、すっかり立つ気力すらも失ってしまったのだろう。
――薫のヤツ……大丈夫――――!?
「……っ!」
歯を食い縛り、思考を切断した。
――何を考えてんだよ。俺が振ったんだぞ? なのに俺が心配なんて、白々し過ぎんだろ……!
目を閉じ、不躾な自身の思考を押さえ込むように頭を抱えた。
意識を強く持とうとする。
強く、強くあらねばならない。
「…………はっ……!」
しかし、そうすることで何かが軋んだ。胸を押さえる。吐息が震えている。
強さを、正しさを……求めているのに心がそれを拒むような不快感。
守るように身体を抱き、耐えようとする。
――なんでこんな……辛い…………?
その拒絶は、自身の心が未だ弱いからか?
それとも、その姿勢自体が本当は間違っているからなのか……?
牧人は解らない。
全てがあやふやで、何が正しくて何をするべきなのか理解できない。
逃げるように窓の外を見た。
単色画のような空が広がっている――――。
■■■■■
しかし、数日が経ったその日、
「おはよう、みんな!」
その明るい声を聞いて、牧人は思わず身を震わせた。
「おー、委員長。風邪はもういいの?」
「もう平気。今日からまたがんばらないとね」
「無理しないでよ? なんかあったら私たち助けるからね」
「うん、ありがとう」
軽やかな足取りで教室に入ってきた藤宮薫は、ちょうど入り口辺りにたむろしていたクラスメイトとそのまま雑談を始めた。
発せられる元気な声。にこやかな表情。

……藤宮薫は、完全に立ち直っている様子だった。
彼女が回復してくれることは牧人にとっても望ましいことだったはずだ。
「………………」
しかし、牧人はどこか納得のいかない心持になった。
――あいつ、なんで……?
全てが帳消しにされたかのような、薫のそんな様子に牧人は戸惑うばかりである。
別れた直後の薫の状態は酷いものだった。
この短期間であのような態度が出来るようになるとは思えない。そんな簡単な状況ではなかった、と牧人は思っていた。
そう、立ち直れているわけがないというのに……。
――なんだよ……。
そんな平然とした様子の薫を見ているうち、思考内が不服な感情で満たされていく。
「季節の変わり目って風邪ひきやすいしね。あたしもこの前休んだしさー」
「ここぞとばかりにそんなこと言うし。あんたのは単なるサボりでしょ」
「あはは」
クラスメイトと談笑する薫の姿。
元気そうな表情には、数日前まで見せていた陰りはまったく見られない。
――なんで、そんな……、
牧人はそれが不満だった。
自分以外の人間に、薫が笑顔を向けていることが落ち着かない。
あれだけ自分にかまっていながら、ほんの数日休んだ程度でけろりと立ち直ってしまっていることが納得出来ない。
……まるで自分の影響がその程度でしかないと言われているようで。
「……ん、藤宮じゃないか。風邪は治ったのか?」
「あ、先生。ご心配おかけしました」
教室に入ってきた担任に会釈する薫。
「もうすぐ忙しくなる時期だからな。ゆっくり休んで、ちゃんと治せよ」
「はい、ありがとうございます」
担任教師は満足げに肯いて、教壇の方へ歩いて行った。
薫の復調を見て、素直に安心している様子である。
「…………」
――そうだよ、俺にはもう関係ないことだろ……。
薫は風邪を引いて学校を休んでいたのだ。
そして普段通りにまで回復し、数日ぶりに復帰してきた。
――もう俺の彼女でも何でもないんだし、心配する資格なんて……。
牧人の中でもやもやと自分への説得作業が続いていた。
赤の他人をそこまで気にかける必要性などないと言い聞かせる。
「始めるぞー、席つけー!」
教壇に立った担任が声を張る。
わらわらと自席に戻る生徒たちの群。
登校時から机に座ったままだった牧人は、そんな教室の雑然とした空気を呆然と感じていた。
――そうさ、関係ない。薫が学校休もうがサボろうが、関係ない関係ない関係ないが……、
「………………」
笑顔で友人たちに手を振りながら、自分の席へ戻っていく薫を何気なく目で追う。
互いの視線は交錯しない。意図的か、偶然か、すれ違う。
――なら……なんなんだよ、この感じ……。
暗中にいるような、見えていない思考だった。
……牧人のそんな懊悩とは無関係に、朝のHRが始まっていく。
「先週末に行った模試の結果を返却するぞー!」
担任の声。
何人かのクラスメイトが哀愁漂う呻き声を漏らす。
「しっかりと結果を受け止めろよー、それが今の自分の実力だぞー!」
それを見た担任がからかうように笑った。
高校三年ともなれば中間期末のテスト以外にも、こうして模擬試験が行われる。
牧人たちの通う平坂高校は近隣の予備校と提携し、三年生の大学受験予定者を対象にこうした試験を行うのだ。
志望校を記入し、現時点での合格率や苦手な分野等の情報が提示される。
そこからの情報が、今後の勉強方法や明確な受験校決定への元になるのである。
……まあ、受験戦争が激しさを増す昨今、詳細は説明するまでもないだろう。
「出席順に呼ぶから取りに来い。葦原」
「…………」
名を呼ばれて席を立った。
……受験。
それは牧人にとって重苦しく億劫な出来事であるはずだ。
――受験……か。
しかし、不思議と大して気にならない。
その他の事に意識が向いているからだろう。
牧人自身は意識しないようにしているのだろうが、どう見ても意識していた。
“自己分析シート”などと銘打たれた、異様に詳細な試験結果を注視することなく眺めているばかりである。
「委員長、結果どうだった? 見せ合いっこしようよー」
「あ……え、っと……うん」
会話が聞こえてきた。
自分にとって何より大切だった薫が、興味もないクラスメイトと会話している。笑い合っている。
朗笑。案ずることなど何もないように見えた。
――……なんだ、この感じ……?
薫は笑っている。見る者を安堵させるような、穏やかな笑みを浮かべている。
その事実が牧人は先程から不満だった。
疎外感のような悔しさのような、心が感じる不快な重量感。
……実際のところ、現状は何も特別なことではない。
彼女は、誰に対してもそうなのだ。
誰に対しても楽しげに話し、誰に対しても穏やかに笑う。
それは温和な性格の少女が持つ、友好の証だからだ。
今までは、牧人がそれを多く見ることのできる機会にいただけに過ぎない。
心のどこかで藤宮薫は自分だけのものだと牧人は感じていた。
……彼女が笑顔を向けてくれるのは、自分だけだと思っていた。
その思考があまりに独善的で身勝手なものだと解ってはいながら、結局はその甘美な感覚を消し去ることが出来なかったのだ。
一度離れてみると、そうした感覚の多さに驚かされる。
結果的に見れば、人はいくら成長しようとも、そうした愚昧な思考を減らすことは出来ないのだろう。
行動にも表情にも出さないだけで、脳内では常に自分勝手な思考を抱き、同量の理性や倫理でそれを抑制しているのだ。
ならば成長とは、そうした理性や表層的な諸所の要素を高めていくことと言えるだろうか。
心の葛藤――牧人風に言えば“ダサい思考活動”というものだが、それらはいくら歳を重ねようとも変わらず生じ続けるものだ。
ただ、過ぎ行く年月の中で得る様々な経験から、それを表出することの問題性を理解していく。
故に、人は自分本位の意見を抑制する術を学んでいくのだ。
とりわけこの国は、そうした調和を尊重する意識が強い。成人には空気を察し、適宜自分を殺す能力が求められる。
一方で西欧諸国では明確な意見を発することこそ大人として重要であるという見方があるものだが……閑話休題。
牧人の中にも、そうした生温い思考が現在進行形で生じているのだった。
薫が他の誰かと話していることが、笑い合っていることが面白くない。
自分以外の人間に、かつて自分だけに向けられていると勘違いしていた彼女の笑顔が向けられている。
それが、今になっても相当に辛い。
耐え切れず、机に突っ伏した。
格好悪い思考をしている自覚があった。そんな考えを抱いている自身の顔を、他人に見られたくなかったのだ。
――馬鹿……ダセぇんだよ、俺……、
目を閉じ、耳を塞ぐ。
外部情報が鬱陶しい。その獲得によって生じる、傲慢な思考が煩わしい。
自分の殻に閉じこもり、何も感じない状態で過ごしたかった。
しかし、
「………………」
目を閉じ、耳を塞いでも、そこに彼女の存在を感じてしまうのだった。
思考から抹消することなど出来ないのだ。
姿は見えず、声は聞こえないが、今も薫は楽しげに話しているのだろう。
友人たちが悪ふざけをしても、笑ってそれを受け止めるのだろう。
――薫は……、俺のことなんか、もう……。
彼女から自分への親愛の情を感じ取ることができない。
薫はもう自分に興味などないのではないか。自分のことなど必要としていないのではないか。
自分のことなど、愛していないのではないか……?
そうした不安が次々と堆積していく。
――俺が、一人でグダグダ言ってるだけ……だってのかよ……?
全身の血が冷水になったような気分だった。
薫と自分が無関係になっていく不安。不確かな繋がり。
その想像は、牧人を殺すに余りある。
……押し潰されそうになっていく。
「…………か――」
思わず名を口にしそうになって、また慌てて踏み止まった。
――そうだ……今更、俺にそんな権利あるかよ……。
……もう自分は、藤宮薫の彼氏などではないのだから。
そしてその状況を作り出したのは、他ならぬ牧人自身なのだ。
とめどない自己嫌悪。
満たされぬ心に、徐々に余裕が失せて来ている。
……それはどこか、彼女と付き合い始める前の段階に似ていた。
思い出される。
彼女と共にいた耕平に対して抱いた嫉妬、疑念。
それを皮切りに、かつての自分が次々と追想される。
記憶の中の自分。
思考も言動も、どれを取っても格好悪さが鼻につく。
思い返すだに恥ずかしかった。
肩身が狭い。みっともない自分が許せない。
――こんなダセぇヤツ……忘れられて当然だよ……。
より強く頭を抱えた。
腕の隙間から自分の弱さが流出していきそうだったから。
「……っ」
――けど、それでもいいんじゃねぇか……?
両腕によって閉塞した空間で牧人は思う。
元はといえば、薫と別れたことはそうした自分の腑抜けた姿と決別するためだったが、それは薫のためとも言えないだろうか、と。
――現に、今日の薫は……、俺なんかいなくても笑ってるじゃねぇか……。
頭脳が志向性を見出し、次々とそちらへ流れていく。
――薫が立ち直ったのなら……いや、もし立ち直ってなくて、今日の笑顔が強がりだったとしても……、
クラスメイトと楽しそうに模試の結果を見せ合う彼女を想像した。
自分よりもずっと社交的な彼女なら、自分以外の誰かともすぐに深く絆を持てるように牧人には思えた。
――そしたら……、薫はそいつとの毎日で本当に立ち直っていって……、俺と一緒にいた時よりも楽しそうに笑って、幸せになって………………、
それはなんと希望ある未来だろうか。
しかし、その夢想には牧人の姿はない。
薫が自分の知らぬ場所で知らぬ誰かと共に幸福な時を過ごしている。
「…………」
無論、それは牧人の本意ではない。
彼女と共にいるのは自分が良かった。
他の誰かに委任する気などまるで起きなかった。
――けど……、そうするのが薫にとっても一番幸せなんだ。
そう信じて疑わない。
疑わない……ことにした。
目を見開いた。
そこには彼女の姿ではなく、間近に机の木目が見えるだけだ。
――だからこれで、いいんだ。
確認するように心の中でそう言いながら、牧人はもう一度、目を閉じる。
瞼の下の暗闇で、自分の行為の正当性を噛み締めようとした。
辛かった。苦しかった。
胸を打つ鼓動が速い。吐き出される息が重い。
痛む心を抱えるように、腕を掴む手に力を込める。
きつく握られた皮膚の痛みが、自分への罰。
牧人は、そう思うことにする。
――昔の俺なら、こんな時どうしただろう……?
ふと、そんな思考が沸いた。
もしかすると、過去の自分との比較に、現在の正当性を求めたのかもしれない。
先の追想が再開される。
薫と耕平の関係を邪推し、二人を追跡した時。
あの時は本当に制御不能だったのだ。
耕平が薫と近づいていく状況。それを見て笑い飛ばすこともできず、先を越されたと焦るだけの自分。余裕と自信の圧倒的な欠如。
そうした無力感や焦燥感に突き動かされ、気付けば暴走していた牧人だった。
その頃の自分なら、この状況に立って何を思っただろうか。
また無様に慌てふためき、何も考えず行動に移していたかもしれない。
牧人は考える。
――こうやって冷静に受け止めてる分、少しは成長したのかな……俺……?
浮上した結論は、なんとも頼りなく心中で響くのだった。
自分への言い訳。
自己を許容する快さ。
生温い感覚が心の奥底から広がっていく。
「………………」
しかし、以前ほどの解放感はまるでない。
今はただその生温い感覚だけが、澱のように残留していた。
不燃感とでも言えるような、停滞した嫌な気分。
五臓六腑が重苦しい。
罪悪感にも似た暗鬱な心地ですらあった。
再び、組んだ腕に頭をうずめた。
目を閉じ、耳を塞いで、自分だけに優しい暗闇に落ちていく。
「あれ!? 委員長、どうしたのそれ!?」
「え……、あ、うん……」
クラスメイトが上げたその声に、牧人はもう気付かない。
後ろ向きな現実逃避に没している彼は、既にいかなる情報も遮断しているからだ。
逃げ出した少年をおいて、時間は流れていく。
■■■■■
そしてまた数日が過ぎた。
「………………」
――ピンポーン。
少女は呆けたようにそこにいた。
大理石の表札にある、“葦原”という名に不思議な感慨すら覚えている。
目の前には扉。
視線を左に移すと、よく彼と映画を鑑賞したリビングが望める。
窓から覗ける室内は無人。しかし微かな人の気配がある。
「……………………」
――ピンポーン。
静まり返った住宅街にベルが鳴る。
周囲に並ぶ家々から感じられる存在の圧力のようなものがやけに薄い。
存在を感じてはいる。だが、酷く弱々しい。
まるでそれを受信する力がないかのような喪失感は、虚無的な何かを心中に残す。
人の気配を感じ取る器官があるとするならば、それはもしかすると精神状態に左右されるのかもしれない。
明朗な気分の時には人々の生命を強く感じ、沈鬱な気分の時には世界から見放されたような孤立感が付きまとう。
彼等がここ最近抱いている感覚の原因もそう言えば説明がつくだろうか。
「…………マキ、くん」
――ピンポーン。
白昼の住宅街。音が響く。
塀の外に張り付いた少女が、懺悔でもするように虚しくベルを鳴らし続けている。
しかし、反応がない。
締め切られたドアや窓はよそよそしく、排他的な雰囲気に満ちている。
家はひっそりと息を殺し、知らん振りをするように来訪者を拒絶しているようだった。
「……マキくん……、どうしてなの……?」
繋がっていないインターホンに向けて呟いた。
「わかんないよ……? ねえ……マキくん…………?」
声に混じる涙は悲愴に乾いていた。
応えは……今日もない。
停滞の無意味さを悟ったように、少女――藤宮薫は踵を返す。
絶望的な足取りで、とぼとぼと歩き去った。
彼女はある時から、こうして彼の家を訪れるようになっていた。
牧人がある程度心の整理をつけて、そう決めてから別れたのに対し、薫はもう全然わけが解らないのだ。
彼と会って話をしたい。そしてできることなら今までのように……
そう思って通い続けては、ふいにされているのだった。
同時刻の屋内――牧人の部屋。
葦原牧人は、死体のように床に寝そべっている。
無為に呼吸を繰り返すだけの、無気力な状態を続けていた。
頭部には重々しいヘッドホンが装着され、怒れるような激しい旋律が漏れ出している。
それなりに高性能な製品だ。余程のボリュームでなければ音漏れなど起こり得ない。
スピーカーから放たれた、エレキギターの歪曲音が耳を貫く。
来客を告げる電子音など聞こえない。
……聞こえるはずもないのだ。
「………………」
溺れるように、逃げ込むように、牧人は音楽を鑑賞している。
まるで楽しくなかった。
――……薫……。
拳を握った。爪が刺さるくらいに強く握ろうとした。
いっそ血でも出たら、格好がつくだろうか。
――ピンポーン。
02
帰路であった。一人の帰路。
夕暮れというにはまだ早い時間、牧人は河原を歩いていた。
通学路から土手を降り、すぐ脇に流れをおきながら歩行している。
歩きやすい歩道をわざわざ逸れて進む物好きは少ない。
草地を踏み歩く足音は牧人のものだけだ。
「おい、牧人」
だが、力強い声音が名を呼んだ。
呼ばれる前から前方にその存在を認識している。
声の主――棗耕平は待ち構えるようにして、そこに立っていたからだ。
牧人はかなり遠方からその姿を発見していた。
「耕平、か……」
呟いて、それが自分のものと思えぬほど掠れていることに牧人は気付く。
会話というものが彼の生活から激減して、しばらく過ぎていた。
互いの表情が明確に解る距離まで接近した。
「……久しぶりだな」
社交辞令のように言う。友に向ける態度ではない。
「久しぶり……?」
復唱する、どこか淡々とした耕平の声。
「声かけようにもお前がチョロチョロ逃げ回ってるからだろうが」
「………………」
普段の彼より一段低い声で告げられる。
安定した声量の耕平には珍しいその語調。
口調は穏やかながら、それだけで糾弾の意思が感じられた。
「朝も一人で登校。休み時間はどっかに失せてて、放課後も誰よりも先に直帰ときやがる」
嘆息するように目を閉じた。
耕平の言う通り、牧人は意図的に友人との接触を避けていた。
……会ってどんな顔をしたらいいか解らなかったからだ。
「六限サボって待ち伏せて……ようやくとっ捕まえられたか」
詰め寄る。
「何か……用かよ?」
後退する。
そんなつもりはなかったが、酷く卑屈な声が出てしまう。
自身の逃避的な行動様式に無自覚の罪悪感でもあったのだろうか。
「用……ねえ」
諦めたように、
「お前、藤宮と何かあったんだろ?」
「………………」
「やっぱりな」
牧人は何も返せなかった。
この場合の沈黙は事実の全てを物語る。
「……別れたのか? なんでだ?」
「…………」
――そんなの余計なお世話だ。
活況にあった頃の牧人なら、そのような強がりを口に出来ただろうか。
「どうして、それを……?」
覚悟のようなものの後に発せられたのは石油のような問いかけ。
「……見てればわかる」
切って捨てるような返答だった。余計な言葉はいらないとばかりに。
合理的で、無駄がない。
「何があったか説明するな?」
「…………」
有無を言わさぬ口調。
一連の耕平の言葉は静かで、嵐の前の凪を思わせる。
「俺は……」
牧人は語ることにした。
或いは、それも逃避だったのかもしれない。
自分のあり方に迷っていた牧人だったから、いつだって正しい耕平の意見を問いたかったのだ。
だからこの時も、そうしてしまった。
藤宮薫との交際後期の日々あった出来事。
その果てに、その間違いに気付いた事。
別れを告げた事。
自分はそれが、ケジメだと思っている事。
そうすることが、薫のためにもなっている筈だという事。
それなりに親密な付き合いがあった仲だ。
己の恥ずべき行動の数々を、牧人は決して美化せず包み隠すことなく語った。
臆病な自分の吐いた言葉にしては、驚くほど誠実で潔いと思われた。
「牧人……」
全てを本人の口から聞き知った耕平は、失笑するようなため息をついて、
「……なんだかお前にはがっかりだ」
牧人が今まで見たこともない、冷然とした目でそう言い捨てた。
思いのほか冷えた反応だったが、そうした言葉をかけられることは予想していた。
「……同じ男としてお前の抱いた後悔や感傷は解らないわけじゃない。それを恥じる気持ちも……まああるんだろうぜ」
「…………」
「しかし、そのあとの対応が理解できねえ。ケジメ? 資格? とぼけるなよ」
気配が迫る。
頭一つ高い位置にある耕平の射抜くような瞳。
「お前はビビリだ」
「……!」
宣告じみた声が振り下ろされる。
牧人の心の装甲を叩き割らんとする戦斧のように。
「ヘタレで、馬鹿で、短気で、見栄っ張りで、ええかっこしいだ」
「…………」
自覚している。明確にでなくとも理解はしている。
「…………けど、純粋で、いいヤツだった」
「……………………」
その言葉が耕平の口から語られる事実に、不覚にも牧人は胸が熱くなりかけた。
敵愾心を燃やしながらも、どこかで届かないものと尊敬していた少年が投げた賞賛の言葉。
彼も内心では自分の事を認めてくれていたのだ。それだけで感動するに余りある。
達成感にも似た高揚が牧人の中で広がりつつも、
「……でもそれ、オレの買いかぶりだったらしい」
次の言葉で氷結させられる。
「もうちょいマシなヤツだと思ってたんだよ」
更に接近してくる。
「っ……」
怯えるように後じさりするが、踏み止まった。
最後の最後でも、耕平への対抗意識の残滓が牧人を奮い立たせたのだ。
そのおかげで無様に恐慌する姿を晒さずに済んだのなら、それは唯一の救いなのかもしれない。
「恐い顔だな。何か言いたい事でもあるのか? 聞くぜ、ふざけた言い訳をよ」
「……耕平っ」
挑発するような言葉に、思わず歯を食い縛る。
しかし何も返せない。
牧人の睨みも踏ん張りも、全て虚勢に過ぎないのだから。
「――今お前は何をしている」
鼻がぶつかり合いそうな至近距離で、胸倉が掴まれる。牧人は反射的にその手を掴み返した。
「無様なお前を笑うこともせず、ただ素直にやり直そうとしてくれてる藤宮を拒絶して、傷付けて……挙句こうやってこそこそ逃げ回って、自分が無力な馬鹿だって言い回ってるつもりか?」
「……っ」
あまりに正確な耕平の指摘に牧人は絶句するしかない。
見られていたのだ。全ての挙動を。
「やり直しなんて……許されねぇよ……、俺なんかに」
「だがお前は、今になって未練たらしく藤宮の様子を伺っている」
「――!」
反論できない。そこまで把握されている。
愕然とした牧人の顔に、眼鏡越しの冷徹な視線が浴びせられた。
更に力強く制服の襟を引き上げられる。
「昔の目だな。拗ねていじけてふて腐れた……死んだ魚みてえな目だ」
静かに凄まれる。
「酔ってんじゃねえよ。お前のルールがまかり通るのはお前の中だけだ。傍から見れば何の意味もねえ、何の理解もできねえ、優しさでも配慮でもねえ……最低の態度なんだよ」
平時から滲む耕平の風格が、圧倒的な気迫となって自分を攻撃してくる。
それだけで、牧人は去勢されたようになってしまう。
「こっち向けよ。目を見てオレの話を聞けよ――」
掴まれた襟首が引き上げられ、逸らしていた顔が戻される。
殴られると思った。
覚悟した。そうしてくれればむしろ楽だった。
だが、
「――――てめえの安いプライドで、女泣かせてんじゃねえよ。下衆」
そんな乾いた罵声を最後に手は離された。

「あ、……」
牧人はくずおれるように地に膝をつく。
言葉を失くした。
殴られなかった。その方が痛いこともある。
その価値すらないと言われているに等しいからだ。
「そうやって何でもかんでも肯定すれば良いとでも思ってるのか? 笑わせるなよ、そんなの諦めてるだけだ。
馬鹿みたいにウンウン悩んで、それでもやり方わかんねえから無様にじたばた踏ん張って……そうやって昔みたく必死になってりゃ、まだ何か言ってやれるんだけどよ」
見下ろす冷徹な視線。
耕平にも、牧人が現在の境地に至るまで、覚悟を決めたことくらいは伝わってくる。
だが彼にとって、牧人の言葉は理解しかできない。
いかなる共感も助言も、そこに示すことはできなかった。
――あぁ……そっか……、
その段階で、牧人は気付いた。
自分が壊してしまったのは薫との関係だけでなく、いつも揃っていた五人の輪であるのだと。
そして耕平は牧人が自分で間違いに気付いて、元の五人の関係に戻してくれることを期待していたのだと。
しかし牧人は、全てを黙って肯定した自分を成長したとした肯定し、打開のための思考を放棄した。
その実態が耕平から告げられた。
牧人の認識した成長が、何の中身も伴わない空虚なものでしかないということが示された。
期待を裏切ってしまったのだ。
……そうしたことを、すっかり冷めた心で悟った。
薫に対しての牧人の態度。
一方的な別れ話。執拗な拒絶。
ようやく気付いたのだ。それすらも逃げであるということに。
……気付いたところで、今となっては牧人に何ができるのだろう。
去り行く耕平の背中。どこまでも遠い。
最早いかなる敬意も親愛も、そこには感じられない。
その脇に没しようとしている夕日に、牧人は何の希望も見出せない。
音が聞こえた気がした。
絆の砕ける音が。
■■■■■
土手を登り、駅へと向かう道に差し掛かったところだった。
「ヘイ、ソーセキ先輩!」
「……おっと」
背後からなつめが抱きついてきた。
密着した体に、少年じみた細い骨格を感じる。
「離れれ」
「うにゃ〜」
「……貴様がそんな声出しても忌々しいだけだと知れ」
なつめは強引にべりべりと引き剥がされた。
「あたた……、そんな拒否反応示さずともー」
「無意味にベタベタするんじゃねえってのよ」
「えはは。まあ、行きますか」
悪びれもしない。
目的地も告げず、なつめは耕平の前に立って歩き出した。
帰り道である駅方面だったので、別に止めはしなかったが。
「……てゆうか、お前はどっから沸いて出た」
「ソーセキ先輩が五時間目終わった時に校門出て行くの見かけまして――」
「なに……?」
耕平の目が微かな驚愕に見開かれる。
「シツレイながらストーキングを少々」
「そう……か」
ということは、牧人との会話もすべて見られているのだろう。
「生まれてこの方、二度もストーキングされるとは、オレサマもてもてだな」
耕平は誤魔化すように戯れた。
「ソーセキ先輩はカッコいいっすからね」
対するなつめの反応は、どこか白けた様子だった。
「お前なあ……そういうマトモな反応すんなっつーのよ」
「思えばそれが、マッキー先輩たちとの付き合いの始まりだったんすねー」
「…………」
葦原牧人。
その名を聞くと、耕平の心のどこかが軋んだ。
「バカなこと言ってねえで、行くぞ」
大股で歩いていく耕平。
「ソーセキ先輩……」
なつめは追い付こうと加速する。
「今日も、町は静かっすね」
どこか遠い目をしてなつめはそんなことを言った。
「……突然何を言い出すんだお前は?」
「静かで……寂しい町」
怪訝な顔をした耕平は速度を緩め、再びなつめが一歩先んずる形になる。
「だって、考えてみてくださいよ――」
両手を広げ、周囲に立ち並ぶ住宅を指し示す。
「こうやってたくさんある家の全部が全部、誰かにとっての大切な場所なんですよ?」
「……大切な場所」
わけもなく復唱した。
「けど、外側からじゃそんなことは全く感じられないし、中の様子もまったくわからないじゃないっすか」
「…………」
「仮に中の人たちがケンカして、誰かがいなくなって、ばらばらになって……、そうやって無意味な場所になっちゃっても、外から見たらなんにも変わんないんすよ――」
溜めるように、息を吸って、
「そうやって、誰からも忘れ去られていくってのは、とても寂しいことじゃないっすか?」
「………………」
「あたしたちにとっては、マッキー先輩の家だったんすかね。それって」
「……………………」
耕平は無言で聞いていた。
言うべきことがないではなかったが、口にする気にはなれなかった。
なつめが語る意味を噛み締めながら、沈黙している。
「牧人の話はすんなよ……」
結果的にこぼれたのは、そんな棗耕平とは思えない、力無き言葉だった。
腹立たしげというよりは、何もかもが億劫といった風である。
「うわ、ソーセキ先輩らしからぬ冷めた反応」
「うるせーな。あんなヤツのことなんかもう知るかっつーの」
からかうようななつめの言葉に反論するように、耕平の口調もおどけたようなものに戻った。
いつもの調子。しかしどこか強がっているようにも見える。
「どーにかなんないっすかねえ」
憂色などまるでない風になつめが言う。
「どーにか……ならなくはねえんだろうな」
それに対する耕平の答えもぼんやりしたものだ。
「…………」
「…………」
その言葉を最後に、沈黙が訪れた。
夕暮れ時の町を、二人ゆったりと歩いていく。
牧人や薫の関係がこのようなことになっている現状。
今、薫は牧人に傷付けられ、牧人はそれを恥じるように自分の殻に閉じ篭っている。
……難儀な状態といえた。
だが現実的に見れば、二人に近しい耕平やなつめが全力でフォローすれば、いくらでも取り戻すことができるだろう。
「ソーセキ先輩?」
「……なんだ?」
「…………」
「………………」
二人もそれは理解していた。
修復する意思はある。それを行う力もなくはない。
だが、実行に移せずにいる。踏み出せずにいる。
「……大人になるのって、難しいっすね」
「何をいきなり……」
どこかに現状に対する安易な諦念があるのかもしれない。
並大抵の努力では、崩れかけた絆を持ち直すことはできないだろう。
相手と心をぶつけ合わなければならない。相手の心に踏み入らなければならない。
費やされる力は、若い彼等には大きすぎた。
「今はまだ無理かもしんないっすけど」
「…………」
「いつか……、どーにかなるといいっすよね」
「まあ、そーだなァ……」
曖昧に吐露される前向きな言葉。
それらは現状に対する自棄や意地張りから創出されたものだろうか。
ただ、今を変えたいという互いの意思だけは確認したいがために。
「ま、世の中生きてりゃ、ままならねーことも色々あるんすけど!」
なつめが立ち止まり、勢いよく振り返った。
言い放つ。
「あたしがここにいて、ソーセキ先輩もここにいて……ゼロではないんすよ!」
「…………」
全世界に告げるような強い声にて。
「まだ何もなくなったわけじゃないから……、今の状態にも我慢くらいはできるんじゃないかって、あたしは思ったっす」
「お前……」
それは、芥川なつめとは思えない、前向きな言葉だった。
それが彼女の本心かどうかはさて置いても、そうしたことを口にしたいと彼女が思ったのは事実なのだ。
……口にすることで、そのように生きていきたいと思ったのだ。
「ソーセキ先輩が言ったんすよ、思い出をいっぱいいーっぱい貯金して、辛い現実に立ち向かっていこうって」
「……そうだな」
「残念ながら、あたしらの前にはその辛い現実がもう出てきてしまったんすよ。予定よりちょっと早めに」
「……そういうことになる、のか?」
「でもあたし、まだ立ち向かう勇気が足りないんす。だから――」
背を向けて、歩き出しながら、
「だからせめて、あたしたち二人だけでも続けませんか?」
聞くに堪えない涙声でそう言った。
「そしたらいつか……、なんとかできるだけの勇気も湧いてくるかもしんないじゃないっすか……!」
背中越しに表情は見えない。見るべきではないとも感じられた。
「……どうだかね」
耕平は、曖昧にそう答えた。
本当は弱い少女を守れる言葉が欲しかった。
力強く頷くことができればよかった。
――マジでそうなったら、いいんだろうけどな……。
自嘲する。
結局は自分も、安い自尊心に振り回されているだけなのかもしれない、と。
「……っ」
耕平は珍しく、……歯噛みした。
歩き出す。
夕暮れの道。
視界には互いの姿のみ。
「……なつめ」
名を呼んだ。
「はい?」
「お前……」
振り返るなつめに、耕平は言おうとする。
「お前……見てたんだろ?」
今更であり、野暮である。
実に棗耕平らしくない話題。
「いいえー、なんのこっちゃらわかりませぬー」
なつめは、朗らかに笑うだけだった。
…………泣き顔のような笑顔だった。
その言葉も、確認のためでしかなかったのだろう。
■■■■■
牧人は耕平とはそれから顔を合わせることがなくなった。
彼と一緒に行動していたなつめとも必然的に会わなくなった。
牧人が特別避けようとせずとも、向こうから関わってくる可能性が全く感じられなかった。
耕平は最早、牧人に対しての興味など欠片もないかのように徹底した無関心を決め込んでいる。
平時は他の友人と適当に会話をしつつ、放課後などは参考書の類を持ち歩いては自習室に出入りしている様子だ。
今や真面目に受験勉強をしているようである。
牧人たちのことなどとうに忘れてしまったかのような切り替えの速さだった。
なつめがどうしているのか牧人は知らない。
元より耕平を介して生まれた関係だったのだ。
彼との交流が断たれてしまった今、なつめとの関係も自動的に消滅した。
「…………」
休み時間。
一人自席に座り、灰色の空を眺めていた。
こうしていることにも大分慣れてきた。
ふと、気付く。
以前は肩越しに微かに感じられた視線のようなものが、今はないような気がする。
そちらを向くと、耕平が隣の席の女子と雑談を交わしていた。
手には単語カード。
受験勉強に関する話題だろうか。
――そういや……、
先日まで彼は、自分の様子を見てくれていたのだった。
それが解除されている。
むしろ、なくなって初めて気がついた。
彼から意識を向けられることにも、そうされることの頼もしさにも。
「………………」
色のない空に視線を戻す。
教室の喧騒が、ますます遠い。
■■■■■
夕刻、学校にて。
「…………」
藤宮薫は階段の踊り場で足を止めた。
――誰も、いない……?
平日の学校だというのに、そこは無人だった。
人気が途絶え、忘れ去られたような空気を残している。
――こわい……。
不意に恐怖を感じた。
最近の彼女は心が不安定である。
平常を装ってはいるものの、果たしてどの程度それで皆を欺けているものか疑問だった。
……実際のところは、かつての恋人にすら見抜かれていなかったが。
薫は精一杯明るく振舞って、笑顔を見せて、クラスメイトに普段通りに接した。
何も知らない他人から見れば、本当に何事も無いような様子だろう。
実情は……、無事であるわけがないのだ。
藤宮薫は、勉強もそれなりに得意であり、成績はいつも上位を維持し続けている。
日々の予復習は欠かさない。真面目な性格によるものだろう。
しかし、先日行われた模擬試験において、彼女は普段の成績からは考えられないような結果を出してしまった。
薫はその結果用紙を即日破棄してしまった。そのため、今となっては詳細な数値は把握出来ない。
――あれ!? 委員長、どうしたのそれ!?
隣席の少女がそのような反応を示していた。
少なくとも、偶々結果を覗き見た友人が、その目を見張る程度には信じ難いものだったのだろう。
模擬試験とは、受験のための道しるべとして、受験者の正確な実力を割り出せるように工夫されているものだ。
それは優秀な予備校講師たちの日々の研究結果であり、万人に適合する程ではないにせよ、ある程度信頼のおけるものとして機能しているはずである。
試験とは、如何なる種類のものであれ体調や精神状態の影響を強く受けるものだ。
そして確かにこの模擬試験は、薫が学校を休み始める前日――牧人が薫を拒絶し続けていた頃に行われたものだ。
ならば、彼女の模試結果が友人を驚かせるほどに惨憺たるものだったのなら……、彼女の状態を表す証拠としては充分過ぎる。
羅列された無数の問を、どのような気分で彼女は解いていたのだろうか。
冷静になれば想像に難くない。
良好な関係性だったものが突然、一方的に断たれてしまった喪失感。
しかもその理由が見当たらず、知ろうと尋ねてもやはり拒絶されてしまうという理解出来ない状況への混乱。
そんな中で、まともな精神状態を維持出来る人間が彼女の年代でどれだけいるだろうか。
だからこそ、不意に現れた孤独の瞬間は彼女の心を揺さぶった。
夕暮れの階段。
乾いた空気が退廃を抱き、傾いだ陽光が温もりの衰微を感じさせる。
暮れなずむ様々な要素が塗り固めた心に生じた亀裂から絶妙に入り込み、内側からその弱さを誘発する。
「マキくん……どうして……?」
思わずかつての恋人の名が、こぼれた。
空間に人が満ちていても、無人の場所はある。
日常は往来がある場所でも、途絶える時間もある。
薫は偶然そうした状況に立ち入っただけだ。
「わかんないよ……、わたし、なんで……?」
しかし、口をついて溢れ出す疑問。
世界の陰にある無人――どこか破滅的な空気すら暗示させるその場は、無垢な少女の正常を容易く奪い去る。
「会いたいよ……、さみしいよぉ……マキくん……」
よろめく身体を手すりに掴まって支えた。
足が震えて立てない。
人気がないために、たがが外れてしまう。
皆の前では気丈に振舞いながらも、一人になると必死にこらえてきた感情が暴発してしまう。
ここ最近は帰宅するといつもそのような感じだ。
自室に篭って、一人泣く。
その空気を、今日は学校で既に感じてしまい、耐えられなくなったのだ。
「……薫?」
そのように名を呼ばれ、薫は打たれたように身体を直立させた。
――この声……?
泣き顔など見せられない。
目元を拭ってから、振り返った。
「こんなところで、何をしてるの?」
上階から降りてきていたのは、……武田明彦だった。
そういえばこの時、明彦は意識して薫を名前で呼んでみたのだった。
……呼んで、彼女が振り返ってから、やめておけばよかったと後悔したのだった。
「明彦……くん」
近づいてくる。
「最近、何かあったね?」
同じ高さまで降りてきた少年は、少女に問いかけた。
未だ残る涙の跡には言及しない。
「近頃、かお……藤宮さんは様子が変だし」
名前で呼ぶ挑戦はひとまず保留することにした。今はそれどころではない。
「牧人の姿も見えないね」
「……っ!」
その名前を耳にすることで、少女は怯えたように身を竦めた。
それだけの反応で、明彦の心に暗い何かが浸潤してくる。
「やっぱり……牧人が、何かしたのかい?」
「違う……違うの……」
既に平静を失いつつある薫だったが、せめて真実を伝えようと思った。
葦原牧人が親友たちからあらぬ誤解を受けるようなことだけは、あってはならないと思った。
だから、話した。
無論、彼女には牧人の心情など理解出来ない。
従って薫の説明は、彼女側から見た牧人の非常に理不尽な態度が目立つ内容であったことは否めない。
前後関係が曖昧な部分もある。薫自身が思い出すのも辛く、語れない部分もあった。
しかし、話を聞いた明彦も概略だけは理解できた。
彼の知らぬ場で何が起きていたのか。そして、そこで牧人が何を思っていたか。
付き合いの長さは伊達ではない。明彦は牧人の性格を誰よりも理解しているし、牧人の心情をかなり正確に察することができた。
……だから、解ってしまった。
「………………」
他者には悟れない無形のため息をつく。
――終わって……しまったんだな。
表情を変えず、少年は落胆した。
いずれ訪れる危惧があった二人の破局が、遂に訪れてしまったという感覚だった。
もう少し踏み込んでいれば、止めることは出来たかもしれない。
だが、そのような過度な進入は、友情と相容れるものだろうか。手出しをして良いものだろうか。
彼の中でも、数度のそんな自問自答があったのだ。
今なお反芻されるそれらは……後悔に近い。
「わたし……もう、なにがなんだかわからなくって……、どうしたら、いいのかも……」
しゃくりあげるような口調。
……限界なのだ。
不器用な少年によって傷付けられた少女の心には、現状は重すぎたのだろう。
せめて、彼女だけでも今という苦しみから守りたい。
――できることは……あるはずだ。
泣きじゃくる薫の姿を見つつ、思う。
現状を解決する策を模索する。
牧人のことを一番理解しているのは自分であるはずだと明彦は思う。
ならば、牧人を動かせるのも彼だけだ。
――しかし、二人の問題に僕がそこまで踏み込んでもいいものだろうか?
親友といえども――否、親友だからこそ、迷う。
牧人の心情を知るからといって、それを自分の都合の良いように操作し仕向けることは果たして許されるのだろうか。
「ねえ明彦くん、わたしが悪かったの? わたしが、うるさくしたから、マキくん嫌いになっちゃったのかな……?」
「違う……違うんだよ」
許すように言った。
――牧人は、何より君の言葉を大切にしていたはずなんだ。
煩いなどと思うはずがないように思えた。
行き場をなくした薫の感情を、どうにか発散させなければいけないと思った。
さもなくば、純粋な少女の心は理解不能な悲しみで潰れてしまう。
……ここで優しさの言葉をかけるだけなら簡単だ。
彼女を抱き締め、思うままに泣き叫ばせれば落ち着きはするだろう。
――しかし、そんなことに何の意味がある?
真に正しくあろうとするなら、明彦は彼女を拒絶しなければならない。
場当たり的な優しさをかけることは、弱った薫の心に付け入るだけだ。彼女が持つ牧人との関係性が完全に千切れ、新たにその場に明彦が納まるだけである。
牧人にも薫にも、裏切りにあたる行為。
悲しみから彼女を救い出すのは彼女の恋人であるところの牧人でなければならないはずだ。
結局は薫の友人にしか過ぎない明彦には、彼女が一人で現状を受け入れて、自身の力で立てるよう励ますくらいが妥当な対応だろう。
……だがそのような毅然たる態度を、今の彼女に求めるのは酷というものだ。
最善が最良とは限らない。
非合理ではある。
効率の観点だけから見れば、一方的に別れ話を持ち出して押し通すような牧人を介したりなどせず、明彦が適当な嘘を並べ立てるなどして薫を立ち直らせる方が余程合理的だ。
――だが、そんな冷めた関係に意味はないはずだ。
だから明彦はそのようなことはしない。できるはずもない。
……心の通わない関係など友人とは呼べない、と彼は考えている。
――そうだ。やはり……、
明彦は決意した。
――僕らは、五人で一つの輪なんだ。
二人だけの問題ではないのだ。
それが集団の中に起きた問題なら、立ち入ってでも解決するべきなのだ。
放置して輪そのものを壊すなど、友のするべきことではない。
「――ふじみ……いや、薫」
だから、次なる希望に意思を託す。
強く、奮起させるように彼女の名を呼ぶ。
「明彦……くん……?」
彼女は俯いていた顔を上げ、涙の残る瞳で明彦を仰いだ。
初めて名を呼ばれた違和感もあったのだろう。そのぐらい唐突だったのだ。
……だが、明彦の言葉に言い知れぬ力を感じたのもまた事実だった。
「牧人のために、何年待てる?」
「……え?」
冷静に、けれど温かく言葉を発する。
安易な優しさではない。不適切な激励でもない。
ややもすれば無粋ととられてしまう、そんな問いかけ。
「もし、もう一度牧人と一緒にいられるなら、そのために薫は何年待てる?」
明彦のその言葉の後、数秒の静寂。
「…………」
顔を伏せ、黙考する少女。
しかし、きゅっと一文字に引き絞られていたその唇は、
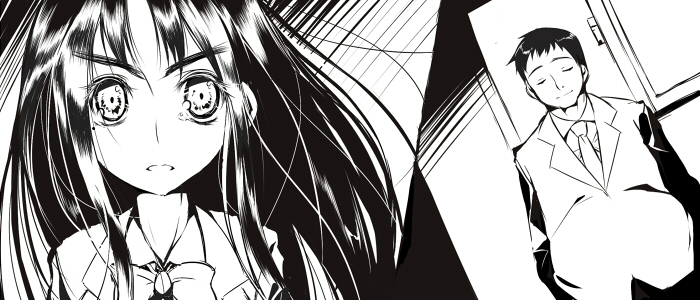
「 」
既に言うべき答えを用意していたかのように、するりとその言葉を産み落とした。
……彼女がどのような事を言ったのか。
彼女自身も、そして明彦も、よく覚えていない。
でもそれは恐らく予想通りの内容で、期待通りの意図だった。
そして、こうした類の言葉は多分、ひとたび文章にしてしまえば、途端に陳腐になるものなのだろう。
美しい言葉というのには二種類ある。
文学として素晴らしい言葉と、人間として素晴らしい言葉だ。
後者に、記録の意味は無い。
……その場にて、その者の口から直に発されたものでなければ真意ではないからだ。
彼女の言葉とは、そういうものだ。
だから、ここで彼女が発した言葉の内容について、敢えて記録は避ける。
仮に記録を残しても、それが彼女の発したものと同等の美しさをもって閲覧者に感受される可能性は低いと思われるからだ。
…………それに正直言うと、こんなに可愛らしい女の子にここまで言わせちゃう牧人が、少しだけ忌々しくもあった。
だから、一時の記録停止。
……その悔しさを覚える人が一人でも少なくなるように。
「うん。解ったよ、薫」
明彦は、旋律に聴き入るように薫の言葉を受け止め、頷く。
最早心に迷いはない。
今はただ、遠い未来に歩き出すのみ。
「それじゃあ――作戦の説明をしよう」
ここまで友情を育んできた少年の口から、解決策が告げられた。
夕暮れの階段に、薫が一人残される。
「……ありがとう」
立ち去り、既にそこにはいない少年に礼を言った。
「う……ぅっ」
まだ少し、涙をこぼしたかった。
顔を覆いながら、心を落ち着けるように息を吐く。
本音を言えば、誰かに縋りたかった。
弱音を吐きたかった。受け止めて欲しかった。
最早それは牧人でなくともいい。ただ心の空白を埋めてくれる存在を求めていた。
だから、明彦が優しい言葉をかけてくれたら、溜め込んだ心のダムが徐々に耐え切れなくなったかもしれない。
しかし、それは先程までの話だ。
――これで……最後……、
この涙を経た後ならば、
ボロボロに傷付いた精神を、少しは持ち直すことが出来る。
明彦の語った五人の輪を取り戻すための方法――、
それを聞かされた今の薫には、そんな風に思われたのだ。
――泣いてちゃ駄目……がんばらないと……、
「マキくん……」
少女は、辛くても生きていくことにした。
03
翌日。
牧人は明彦と会話をすることにした。
――あいつにも、一応言っておかないと……駄目だよな。
漠然とそのようなことを思っていた。
しかし、明確な理由は牧人自身にも解らない。
今更明彦に報告する必要性があるのか判断できない。
薫と付き合い始めた時と似たような状況になったから、無意識のうちにそれをなぞっただけにも思われた。
「明彦……」
「話があるんだろう、牧人」
廊下で待っていた明彦は、牧人が何か言う前にそう促す。
普段温和な少年の言葉尻に、微かな棘があるように牧人には感じられた。
ひょっとすると、既に聞き知ったことなのかもしれない、と。
――だとしても……もういいや。
牧人は諦めたようにそう思考して、明彦に事態を説明した。
ちなみに明彦は既に薫から事実を聞き知っていたが、その点については触れずにおいた。
「もっと素直になればいいのに」
「……なんだと?」
報告を終えた直後、明彦の口から告げられたのはそのような言葉だった。
それは妙に淡白な、それでいて得体の知れぬ圧力を秘めている。
「ダサくたっていいんじゃないかな? 藤宮さんはきっと、牧人のそういうところも全部含めて好きだって言ってくれたんじゃないの?」
「……っ!」
いつも通りの口調と表情で向けられる攻撃の言葉は、牧人の頭脳を驚くほど冷却し、その意味の理解を容易にさせた。
「牧人は結局、自分的にカッコ悪い自分が嫌になっただけなんでしょ? でもそれって牧人自身の問題で、藤宮さんそのものへの好き嫌いとは別に関係ないよね?」
「お前――ッ!」
――勝手なこと、言いやがって……!
この時、牧人は心の底から明彦のことが恨めしくなった。
そのようなことは、今更明彦に言われるまでもなく解っていたからだ。
……解っていたのだ。
牧人の行動は、正しいか正しくないかを迷った末の選択などではない。
結局、全ては自分の都合だったのだ。
耕平に言われて気がついた……否、薫と別れると決めた時から実は薄々気付いていた。
気づいていたが、直視するのが恐くて目を背けていた。
「藤宮さんにカッコ悪いって言われて嫌われるのが恐いから、そうなる前に牧人は逃げただけなんじゃない?」
――そうならないようにする努力を牧人は怠った。
明彦の言葉にはそんな含意が感じられた。
「藤宮さんがそんな心狭いわけないじゃん。素直に認めて、謝っちゃいなよ。一回くらいの間違いで、やり直せないなんてことない」
「俺は……っ!」
喉元まで出た言葉を飲み込む。それを発することは許されない。
明彦の言葉に反論すれば、自分の矮小さをますます露呈することになる。
かといって、凝り固まった自尊心が肯き返すことを許すはずもない。
――俺は……、俺は――!!
求めた姿はどこへ行っただろう。
何度か変遷したようだったが、それはどのような有様に落ち着いたのだろう。
かつての――例えば中学生だった頃の自分が今の自分を見たら……、一体何を思うだろうか?
――もう、わからねぇよ……。
思えば、明彦に報告をしようと思った理由も、耕平に嫌われてしまったから逃げるように明彦の所へ行っただけだと言えなくもないのだ。
ケジメなどと厳しい事を言っておきながらも、結局自分は生温い場所を求めてしまっている。
――情けねぇ……。
結果、耕平と明彦の二人に続け様に感情をべらべら語ってしまっていた。
こうして白い目をされることも解っていながら。
酷い目に遭った反省というものを、まるで生かすことが出来ていない。
――俺……本当に、馬鹿だな……。
ここ数日――薫と別れると決めた日辺りから、脳が正常に稼動していない感覚があった。
まるで逃げるように思考を放棄して、目を閉じ、耳を塞ぐようにして生きていた。
……そして失敗する。
「どこ行くのさ、牧人?」
気付けば黙って背を向けていた。
「うっせぇな。帰るんだよ」
「……そっか」
既に背を向けていた牧人からは明彦の表情はわからない。
……ただ、失望されたのだろうということを感じ取った。
例えそれが牧人の一方的な思い込みだったとしても、彼の心に痛手を負わせるにはもう充分だった。
――明彦にまで……、なに、やってんだよ、俺……?
「愛が――」
それは、牧人に向けた言葉だったのか。
「愛が、足りないんじゃないか?」
独白するような明彦のそんな言葉を、最後に聞いた。
明彦には珍しく、馬鹿馬鹿しくなってしまいそうなほどに率直で、なんの捻りもない言葉だった。
なのに、不思議といつまでも耳にこびりついて離れない、そんなフレーズだった。
それは、かつて誰かが言った言葉だっただろうか?
……誰かが追い求めた、夢の残り香だっただろうか?
以降、牧人は明彦と会わなくなった。
あれほど仲が良かった親友だというのに、疎遠になっていった。
これ以上、心の弱い部分を晒し続けることに耐えられなかったからだ。
……親友だったからこそ、嫌だったのだ。
それが心の弱さだろうか。
■■■■■
そしてこの日、牧人はひとりだった――――
「………………」
一人で帰路についていた。
ここ最近は連日そうだったのだが、牧人はどこかでそれを一時的なものと考えていた。
――けど、もう……、
通学時の人数が増えることはないだろう。
牧人は薫を拒絶した。
牧人は耕平に失望された。
牧人は明彦から逃げ出した。
かつて五人だった輪は自分が欠けたことで瓦解してしまったのだ。
――なんで、俺……こんなこと……、
関係を破壊しようという気持ちなど牧人には微塵もなかった。
ただ、自分が思った方向へ進んだだけだ。
……結果的にこのような形になったわけで、つまりは牧人の思慮が足らなかったということになるのだろうが。
「…………」
単独時には思考は過剰に活性化される。
牧人はここ数日の出来事を反芻していた。
――俺は……、
耕平の期待も今となってはよく解る。明彦の言葉も正しいことは理解している。
……そうするべき、だったのだろう。
「……くそっ」
だが、牧人の小さなプライドが今更発言を覆すことを許さない。
あれほど明確に断絶しておきながら、一週間もしないうちから心変わりするというのは軽佻浮薄も甚だしい。
確固たる自我の不在は、多く不信感を招くものだ。
今更とってつけたように反省の色を示しても、耕平たちの反応は湿気たものになることが容易に想像できた。
「………………」
しかし同時に気付いてもいる。
自分の抱く安易な矜持が、いかに無意味なものであるかということにも。
無様であればよかった。
変に気取って、上手くやろうとしなければよかった。
時には失敗して、笑って、けれども努力して、友から励ましを受けて……。
そんな、無理のない……あるがままの自分を受け入れられたらよかった。
……最初からそうしていたら、もしかしたら――――
――今更、意味なんかねぇよ……。
これでも十数年生きている。
形作られた精神はそう簡単に作りかえられるものではないのだろう。
――けど……例えばここで……変わることができたなら……
その可能性も感じてはいる。
それが最後の機会である感覚も、同時に。
青い時代の終局こそ、変わるべき最後の時なのかもしれなかった。
――けど、……恐いよ……。
上手くやれる自信が持てない。
大切だからこそ、臆病になる。
――そう、大切なんだ……俺は、みんなが……みんなの中にいる俺が……、
取り戻したい。
強く思った。
壊してしまった本人が思うには図々しくとも……もう構わない。
現実に不可能なら、心の中でも素直にあろう。無様に潔く、思うがままに生きよう。
なぜなら、必死な姿を嘲笑する者も、励ましてくれる友ももういないのだから。
そうして考えていたら、いつかはそんな仮面が生まれるかもしれない。
耕平のそれのように、自身の顔に寸分違わず融和する、理想の顔が。
「………………」
牧人はひとりになった。
今はまだ、勇気が足りない。
愁いの空が広がっている。
そういえば最近は曇り空が多い気がしていた。
04
そして、楽しくなくとも時間は流れていく。
季節は冬に近づいていた。
「…………」
牧人は自室で無為に過ごしていた。
ひとりになってしまった牧人は日中することがなくなる。
この日も、勉強をするでもなく、読書をするでもなく、ただぼんやりと空虚な顔で椅子に座っていた。
――どう、すりゃいいのかな……?
虚空を見つめ思考していた。
内容は不明瞭。対象も不確定。彼はただ、悩んでいる。
思い返せば、彼がこうして無気力に陥ったことは今までにも何度かあったことだ。
しかし、この時の牧人はそのいずれの時期より酷い有様だった。
かつての友人間の関係性は、まだ取り戻せていない。
この半年余り、機会は常に伺っていた。
しかしその度に、臆病な感情が邪魔をする。
……再度の拒絶、……更なる失望、……最早不要とされた自分。
そんな可能性が次々に予想されて、足が震え出すのだ。
自分の価値を喪失しそうになる。
――馬鹿が……、言わないといけないのに……、俺が言わないと……、
その意思だけはあるのに動けない、弱い心が恨めしく、情けない。
――俺から始めないと……。
涙をこらえ、拳を握り締めるも……、沈黙していく。窒息していく。
言葉が、心が、死んでいく。
そんな感覚があった。
「…………」
あらゆる感情が出口を求め、震えた息が吐き出される。
呼吸、している――それは生の実感だった。
これだけ悩み苦しんでも結局こうして生き続けている辺り、人間もやはり生物なのだろう。
余程の事でなければ、自ら生命活動を止めようなどとは思えないようにできている。
自己嫌悪にまみれながら、今一度かつての日々を取り戻すという希望にすがり付いている。
それは牧人の自業自得であり同情の余地はないとはいえ……痛ましい姿だった。
楽しかった日々を思えば、取り戻したい気持ちは常に湧き上がるものだ。
しかし、どのように対処すべきかわからない。判断がつかない。
……そして、相談できる相手ももういない。
そのような状況だったから、牧人は一人、曖昧な懊悩を続けていた。
――俺、どうすれば……?
循環し停滞するだけの思考は、自己嫌悪にも似ている。
しかし、以前の彼の得意技だったそれとは、多少趣が違うと見るのは早計だろうか?
抱く苦悩の焦点が、自身だけから他者を含めた周囲へと広がっていく。
実際の牧人の心がそのように向いていたかどうかは本人にしかわからない。
だが、もしかすると、彼がその心的操作に他者というものを介在させたのは、この頃が最初のことだったのかもしれなかった。
「――牧人」
不意に聞こえたくぐもった声で牧人は意識を戻される。
呼びかけは廊下からだった。
「牧人、いるなら返事なさい」
硬質な女性の声。
姿はなくともそれだけで怜悧な印象が伝わってくる。
「……母、さん?」
牧人は驚き、顔を上げた。
彼が自室に鍵を取り付けて以来、両親が部屋までやって来ることはなくなった。
それまでは幾度となく押し掛けては、牧人にとっていらぬ世話ばかり焼いた両親だったが、鍵の設置には流石に明確な拒絶を感じ取ったのだろう。
実際親子とはいえ、顔を合わせる度に喧嘩になってしまう牧人への対応には、両親も困っていたのかもしれない。
……親としてのそのような在り方の是非については語るに尽きないところだが、今は置いておくとしよう。
その両親が、扉越しとはいえ自室までやって来た。
ただの世間話が目的……とは思えなかった。
「少し話したいことがあるの。下まで降りてきなさい」
命ずるようにそれだけ告げて、気配は遠ざかっていく。
「………………」
牧人は判断に困った。
応ずるべきか、無視するべきか。
普段なら確実に後者だろうが、今回は特別な何かがあるような気がした。
経験上、両親と対話をしてもその度に面倒なことにしかならないと牧人は考えていた。だが、わざわざ部屋まで呼びに来る程に重要な話なのかもしれないとも思った。
すっぽかすのは簡単だが、そのことで後から難癖をつけられるのも煩わしい。
「…………」
少し迷ってから、牧人は階下に降りた。
実際のところ、一人で悩むのに疲れたことも理由のひとつと言えたかもしれない。
両親に何か助けを求める気持ちがあったのかもしれない。
誰でも良いから、話し合う相手が欲しかったのかもしれない。
だから牧人は――、
「話というのは、お前のこれから先の進路のことだ」
居間のソファに腰掛けた父親からそのようなことを言われ、酷く残念な気持ちになった。
「…………」
向かいのソファに腰を下ろす。
家でも険しい表情を崩さない父と、冷ややかな面持ちで脇に控える母。
――まるで、面接だなこりゃ……。
我が事ながら苦笑混じりの牧人だった。
思えば、両親が牧人の抱く悩みなど知るわけがないのだ。
牧人が心中で何を思おうと、時間は流れ、今は目前に控えた高校卒業後の進路について、取るべき対応を求められる段になっている。
しかしながら、久方ぶりに交わす会話が、そのような形式じみた内容のものだったということに、牧人は放逐されたような気分になる。
牧人個人としての資質が全く無視されているかのような、疎外感にも似た心地だった。
「………………」
ため息をついた。
――まぁ、この人たちの気にすることなんて……その程度だよな。
むしろ、僅かでも助けを請おうと思った自分が愚かしく思えた。
今まで相手にしていなかった両親に今更何を言おうとしていたのか。
――自分じゃどうにもならないからって、親に泣きつくつもりかよ?
勝手に期待し、勝手に裏切られた。
全くもって迂遠なものだった。自身の内に生じた甘えに失笑すらこぼれてしまう。
「私としてはやはり大学への進学を勧めるが、お前としてはどう考えている?」
牧人の心情など露ほども知らず、父親は話を進めてきた。
苦手な相手からの苦手な話題。
半ば強制的に現実に立ち戻った牧人だった。
冷めていた。
「進学か、就職か、それとも他に何か希望はあるか?」
「…………」
牧人は答えない。答える気になれない。
「いずれにせよ、時期的にもう猶予はないだろう。いつまでも悩んでいないで、いい加減決断しなければな」
「………………」
急かすような物言いも幼少の頃から変わらないと思った。
「仮にも人生の重大な局面だ、お前一人の判断に任せようと静観していたが……、全く動く気配が見られないからな。何をフラフラしているのか知らないが、少し先の自分のビジョンすら見えなくてどうする」
「……………………」
今の牧人には両親の言葉は正論に思えたが、何故こうも心に響かないのかが疑問だった。
「今まで私の言うことにいちいち逆らってきたお前だ。自分のことは自分で決めるようなことを言っておきながら、空威張りに過ぎなかったということか?」
「…………………………」
言い返したい気持ちだったが、事実のような気もするので大人しくしていた。
「何を呆けた顔をしている? 前から思っていたことだが、お前は後継ぎとしての自覚があるのか? 将来は私に代わって社長としてここで働くのだから、進学して実力と教養を身につけてきたらどうだ」
「……ふぅ」
再度、ため息をついた。
……牧人は、やはり両親が嫌いだった。
結局、牧人の進路は進学という形で纏まった。
口論にすらならなかった。
これまでの関係からは想像もつかないほど、円滑な話し合いだったという。
それについて、両親は困惑した表情ひとつ見せなかった。
安心していた。ようやく牧人に心が通じたとでも思ったのだろうか。
「大学、か……」
実感などまるでなかった。
■■■■■
翌日、牧人は銀行にいた。
形だけでも真面目にやっている風に映るよう参考書を買おうと出かけたら、所持金が足りなかったためである。
――なんか、久しぶりに来たな。
自動ドアが開く音を聞きながらそう思った。
一人だと金を使う機会もない。
雑費だけで銀行に通い詰めることなどないだろう。
駅前にあるATMは相変らず閑散としていた。
牧人は無人のこの空間で預金を下ろす作業がなんとなく好きだった。
友人たちと遊びに出かける時に度々立ち寄っていた場所だからだろう。
所持金が減っていく焦りと、次に待ち構える楽しい時間への期待が同居したような不思議な感覚が、実に愉快だったのだ。
「…………」
しかし今は、無人の空間に僅かな物寂しさを覚えた程度だった。
引き落とした金銭の投資先が参考書などという興味のないものだから、というのも確かに理由の一つだろう。
だが、心の多くを占める部分には触れられない。
楽しかった記憶は、輝かしくも辛いからだ。
ポケットから通帳を取り出す。
久しく預金残高を確認していなかったため、とりあえず記帳することにした。
機械音声と共に圧出された通帳を手に取り、記された金額に目を通す。
「うわ……すげぇ貯まってる……」
牧人はこの時もまだアルバイトを続けていた。
辞めるタイミングを掴めずに続けているとも言える。惰性に近い。
何ヶ月分かの給料が加わった預金残高は相当な額になっていた。
――俺、マジで金使ってないんだな……。
自嘲の笑いが漏れた。
その時、
「……ん?」
ふと、その預金残高が目に留まる。
それは、どこか見覚えのある数字――――
「…………」
――ああ、そうか……。
思い至った。
その金額はギターを――純正品のフライングVを購入するために必要な額だったのだ。
アルバイトを始めたのが高校一年の秋頃。
二年以上もかけて、ようやくその金額が貯まったということになる。
――俺って、そんなことするためにバイトしてたんだっけ……。
ギターを真剣にやろうとしていた時期があったのだ。
演奏を薫に聞いてもらいたくて、上手くなったと褒めてもらいたくて。
……時には彼女と音を合わせ、楽しい時間を過ごしたくて。
「……っ!」
最後のそれは、牧人の心に今なお刺すような痛みを残す。
薫とのセッション。
それは甘く楽しい思い出でありながら、牧人が薫と別れようと思うきっかけとなってしまった出来事でもある。
「…………」
――そうだよな、俺……ギター弾けなくなったんだ。
薫と付き合うようになって、恋人らしいことをする日々の中で、次第に音楽から離れていった。
飽きたというよりは、単に優先順位の問題だったのだろう。
ギターを弾くのが嫌になったわけではなく、薫と遊ぶ時間が楽し過ぎたから、ただなんとなく弾かなくなっていっただけだ。
しかし、アルバイトだけは続けていたのだった。
労働の目的を忘れていながらも辞めなかったのは、それが達成出来ていないことを心のどこかで感じていたからか、それとも単純に日々の交際費欲しさか。
ギターは名品だが中古品でもある。いくら高額といえども、そこまで時間がかかるものではない。
仲間五人でつるんでいる間に色々と散財し、薫との時間が欲しくて出勤数を減らし……、そうして寄り道に寄り道を重ね経て、ようやく必要な額が貯まったのだ。
長い時間が――全てが終わってしまうだけの時間が経っていた。
――貯まっちまったよ……。
事実を認識しつつも、どこか夢心地だった。
高校生の牧人が手にするには、やはりこの金額は大きすぎて現実感が乏しい。
――意味、ねぇなぁ……。
だが、結局はそういうことなのだった。
「ははっ……」
再度、自嘲。
自動ドアの音が聞こえて、人が入ってきた。
牧人は失笑を抑え、通帳とカードをATMに投入した。
暗証番号を打ち込む。
「………………」
引き出し金額の入力画面で、牧人はしばし停止した。
――意味、ねぇよなぁ…………。
もう一度脳内でひとりごちた牧人だったが……、
……結局、全額下ろした。
■■■■■
そして牧人は楽器屋に立つ。
店内。奥まった場所にある中古品の棚。
牧人の求めたフライングVは変わらぬ姿でそこにあった。
思えば、よく売れ残っていたものである。
まるでそこだけ時間から隔絶されたかのように、以前のままだった。
……それだけで奇跡のようだ。
「……高ぇ」
値札を見て、苦笑。価格は変動していない。
牧人はポケットの財布を握った。その内側には、詰め込まれた十枚以上の一万円札が飛び出す瞬間を今かと待ち構えている。
かつては夢見た本物のギブソン・フライングVを前にしている。そして手元にはそれが購入出来るだけの金がある。
……そのことについては、それなりの感慨があった。
不可能に見えた壁を、自分は知らぬ間に越えていたのだ。
「…………」
艶めく漆黒のボディ。
自分の所持しているチェリーレッドも嫌いではなかったが、牧人はやはりこちらのカラーリングが好きだった。
鋭く伸びた左右対称のフォルムに、何物にも染まらぬ黒がより孤高な気配を滲ませる。
――やっぱり、カッコいいなぁ……。
中学生の頃から感じていた恍惚とした気分が僅かに蘇り、牧人はしばし快い空気に満たされた。
弾き鳴らしてみたかった。自分の物とは比べ物にならない美しい音色を響かせるのだろう。
想像するだけで、手足が疼く。
「…………ふぅ」
しかし、ため息をついた。
気付けばピックを握る形で固まっていた手をほどく。
――何やってんだ……、こんなの買ったって、俺もう弾けねぇじゃん……。
身体は動きを覚えているものとよく言うが、それよりも鈍り切った腕の重たさの方が強く感じられるものだ。
むしろ、頭では理解していながらも満足に動かない身体のもどかしさは、一層辛いものがある。
――また練習、すれば……、
そう思うが、一瞬で却下される。
今更、何のために練習をすればいいのか解らない。
今から見知らぬ誰かとバンドを組む気力はない。
唯一、楽しみに聞いてくれた薫ももう彼の隣にはいない。
――だから買っても、意味ねぇよ……。
そう思ってしまう。
だから、食指はまるで動きやしないのだった。
ポケットに入った財布を握り締める。
――これで財布落としたりしたら、マジ笑えねぇ。
そんな全く関係ないことを考えながら、牧人は楽器屋を出たのだった。
店先に立って、ふと時間を確認しようと携帯電話を開く。
最近はメールや電話もほとんどしなくなったため、牧人の携帯電話は今や端末型時計と化している。
「ん……?」
開くと、普段の待ち受け画面に見慣れないウィンドウが立ち上がっていた。
“スケジュール”という文字が真っ先に目に入る。
――今日ってなんか、用事ある日だっけ……?
予定などを登録した記憶はない。
何も考えずに、内容を確認した。
件名:誕生日
メモ:「薫の誕生日。今年は絶対忘れんな」
「…………」
涙が出そうになった。
■■■■■
数時間後、牧人はひとり公園にいた。
「………………」
何をするでもなく、ぼんやりベンチに座っていた。
久しぶりにキシリトールガムを噛んだ。口内に広がる清涼感が懐かしい。
見上げる空は雲に覆われて白い。
自身の口から吐き出される同色の息が、紫煙を思わせてどことなく退廃的だった。
――寒いな……。
伸ばしていた手足を引き寄せた。
脇に置かれたものに右手が触れる。上等な紙の質感。
……傍らにあるそれは高級感あふれる紙袋だ。
ラミネート加工がなされた凝った意匠のそれは、電車を三駅乗り継いだ先の大きな町にある百貨店のものである。
優雅な見た目の割に作りも頑丈で、そのまま鞄として使えそうだ。
牧人はわざわざそこに赴いて、買い物をしてきた。
「………………」
覗きこむように中を見た。
そこには白いダッフルコートが入っている。
……ちょうど彼女に似合いそうなデザインの。
高級ブランドである。
学生身分には、眩暈がしそうな値段だった。
「あー!」
思わず空に叫んだ。
「畜生、こんなの……買ったって仕方ねぇだろ……」
そして頭を抱える。
フライングVを買うために貯めていた資金の多くがこれに消えた。
今や再び手の届かぬ存在になった名器。その代わりに購入した白のコート。
しかし、これを渡すべき相手などいない。
「はぁー……」
それはもう、本当に誰が見ても情けない吐息だった。
楽器屋を出て何気なく携帯電話を開いた時に、今日が藤宮薫の誕生日であることを牧人は思い出した。
そう思ったら、足が勝手に動きだしていたのである。
どうしようもなかったのだ。
隣町のデパートまで赴き、様々な売り場を見て回った。
陳列された数々の商品を見て、それを贈った時に彼女が喜ぶ姿を想像しては、心地良い物が満ちていくのを感じた。
しかし、漸次絶望が襲ってくる。間抜けで無意味な行為をしている自分の滑稽さと情けなさ。
……だけど、やめなかった。
そして、結局このコートを買った。
贈呈用の包装を頼んだ店員には嘘を吐いた。
ひきつった顔をしていたから、変な風に思われたかもしれない。
――なに、やってんだか……。
これ以上ないという程に未練がましい自分が自覚できた。
「…………ダッセェなぁ、俺……」
ずるずると脱力した。
手足を伸ばし、死んだように力を抜いて空を見た。
冷えた空から、白色の何かがふわりと舞い降りてきた。
――雪……?
結晶化した水蒸気が、次から次へと流れ落ちてくる。
「……あ…………」
気付いたら、泣いていた。
ふわふわと踊る雪が涙で滲んで見えなくなる。
寒々しい空気の中、乾いた大地が舞い散る白によって塗り替えられていく。
――――移ろっていく、全てが。
少年たちの日々が、終わっていく。

数分間そこに留まりながら、牧人は今年初めての降雪を観察していた。
次の日、牧人はアルバイトを辞めた。
退職の理由は受験勉強が忙しくなるから、というものだ。
……もちろん、嘘である。
【戻る】