そして今、情報は集積される。
――――僕の元に集積され、統合される。
ここから、記録が始まるのだ。
そして今、情報は集積される。
――――僕の元に集積され、統合される。
ここから、記録が始まるのだ。
……最古の記憶は、二人がまだ幼少の頃。
今や互いの人生において、共にいる時間の方が遥かに長い。
子供とは不思議なもので、大人以上に実力主義的な傾向がある。
勉強や運動が得意であったり、絵や音楽などの技能があったりすることが子供の中では力に直結するものなのだ。
小学生、中学生辺りの年代でとりわけ顕著になると思われるそうしたイデオロギーは、武田明彦の通っていた小学校にも存在していた。
明彦のクラスには中心的な男子たちがいた。
その派閥には前述のような、強い児童たちが集まっている。
子供の中においては、集団を取りまとめ、牽引していく力のある者ばかりだ。
クラスは必然的に彼等が舵取りをするような形でまとまり、強い者たちが弱い者たちを率いていく、という構図が自然に形成されていた。
しかし、強い者たちの全てが人格者とは限らない。
自身の力を過信せず、弱きを進んで助けるような面倒見の良い者もいたが、反面、その強さを自負し、自分より弱い者たちに対してのみ嗜虐的である者もいた。
……いわゆる、苛めっ子というやつである。
明彦のクラスにも、そのような子供がいた。名前は新井健太といった。
彼は頭が良く、勉強も運動も得意だったが、突然クラスの一人を槍玉に挙げて、仲間外れにしたり無視したりして楽しむという趣味の持ち主だった。
当然そのような難儀な性質にはクラスの皆が辟易していた。
だが、新井は優れた能力があり、下手に手を出しては自分が標的にされるという意識もまたクラス中にあった。
従って、彼はとりあえずクラスの中心に置かれ、腫れ物に触るような扱いを受けていたのである。
……そのような状況だったためか、彼のイジメがある日爆発した。
標的となっていた桐原真という一人の男子に向かって、突然直接的な攻撃を始めたのだ。
放課後の廊下。
大勢のクラスメイトの前で、うずくまる桐原に新井は猛然と暴力を振るった。
「ざっけんなよ! オラ、なんとか言えよ!」
響き渡る怒声に、桐原は手も足も出ない様子である。
怯えて丸めた背中に新井は拳を振り下ろし、頭を守ろうとする腕を容赦なく蹴りつけた。
皆、新井健太が桐原真にいきなり手を上げた理由がよく解らず、困惑していた。
こう言っては何やら不謹慎であるが、新井は直接的な暴力に訴えるよりも、対象を集団から孤立させるように仕向けるなど、より周到で陰湿な行為を好んだためだ。
子供は残酷なものだとよく言われるが、それは自らの感情の止めるべき部分を正確に認識していないからだと思われる。
酷い行いをして、その後どうなるかを考えられるほどの思考力が未だ養われていない。
新井もまた、行き過ぎた感情を持て余し、爆発させてしまったのだろう。
ともかく彼は、白昼の廊下でクラスメイトに暴行を働いた。
クラスの誰もが突然彼がそのような行動に出たことに驚き、また単純にその光景が恐ろしく、止めに入ることができなかった。
「………………」
幼き武田明彦はそのような状況をやや離れた位置から眺めていた。
当時の彼はあまり目立たない少年で、クラスではやや孤立したような存在だった。
しかし、その穏やかな気質故か、多くのクラスメイトは深入りしてこないだけで好意的であり、こうしてイジメの標的になることもなかった。
特定の誰かと親しかったわけではないが、目の敵にされることもなかったのだ。
適切な距離を維持していたと言える。
――けれど次は、僕かもしれないな。
一人の少年が一方的に暴行を加えられる様子を見ながら、漠然と明彦はそう思っていた。
或いは、それは周りの誰もが思っていることかもしれなかった。
イジメの標的。その選考基準は子供らしく甚だ曖昧なものだ。新井の目に偶然留まっただけで攻撃される場合もあり得る。
次の桐原は自分かも知れないのだ。
従って、このような場で制止に入ることは、次の標的に立候補するに等しかった。
「……ふぅ」
――安易だなあ……。
明彦は呆れたため息を漏らした。
彼は幼少の頃から、このようにどこか老成した感覚の持ち主だった。
子供特有のそうした理不尽さを、そこにいるうちから仕方のないものであると理解してしまっていたのである。
――恐れている、みんな。
実際にイジメている新井も、イジメられている桐原も、今後イジメられる可能性のある他の皆も、一様に恐れている。
そうした理不尽な悪意に晒されることを。
――僕は、恐くない。
強がりではなくそれは本音だった。
まるで理由が伴わない悪意など、がらんどうに過ぎないと思ったからだ。
そのような中身のないもの、気にしなければどうということはない。
……そう思っていた。
だからこそ――、
「このっ! うぜーんだよ、このっ!!」
殴打と共に浴びせられる罵声。
それは暴行というより、最早虐待に近い凄惨な光景だ。
「……?」
それを聞きながら明彦はふと思う。
――イジメに遭うのは恐くない。ならどうして、僕は止めに入ることをしないんだろう?
標的にされるのが恐くないのであれば、この状況を止めるために動いても問題はないはずだった。
だというのにそれを行わない自分。明彦はその辺りに妙な引っ掛かりを覚えた。
言い知れぬ自分の心の有様に、何とも不快な気分になりかけたその時――――、
「やめろー!」
廊下の奥から、“彼”が現れた。
遠くにいたのだろう。少し遅れてこの事態に気付いた彼は、声を上げながら猛烈な疾走でこちらに向かってくる。
そして、こちらに到着する直前で速度を落とし、全身に力を込めて肩を突き出した。
「……だぁッ!」
気合と共に繰り出されたのは、助走をつけた強烈なタックルだ。
少年の突進は足を振り上げていた新井の横腹に直撃し、二人はもつれ合うようにして廊下に転がった。
「ってーな! なにしやがんだ!」
「てめぇがなにしてんだ! 馬鹿なことやってんじゃねぇよ!!」
起き上がりながら、乱暴な甲高い声の応酬が始まった。
互いのシャツの胸倉をつかみ合い、額がぶつかりそうな距離で睨み合う二人。
「ふざけんなよ! オレの邪魔すんじゃねえよ!」
「偉そうにすんな! 自分より弱いヤツイジメて喜んでんじゃねぇよこのザコ新井!」
「ザコ……っ、言ったなおまえ!」
「うるせぇよ! 俺がお前に同じことしてやるっ!」
そうして、今度はこの二人による殴り合いが始まった。
喧嘩だ。周りの子供たちも騒ぎ出す。
一方的な攻撃に比べ、喧嘩というものの相手に対し向けられる感情は絶大だ。繰り出される攻撃も、怯えてうずくまるだけの相手に向けるものとは迫力が違う。
殴り合う二人の拳には殺意にも似た鋭さが宿り、向ける視線も最早敵愾心などというものではない。
「おいおい、あいつらマジでやばいってー!」
ここに来て、観衆だった他のクラスメイトも現状の危険性に気が付く。
男子たちが慌てて二人の間に入る。ぶつかり合う二者に組み付いて引き離し、「とりあえず落ち着け」
などと声をかけている。
その中で女子たちが、未だ床にしゃがみこんだままの桐原を助け出していた。
数分を経ずして、教師たちがやって来る。
見ていた生徒の一人が呼びに行ったのだろう。
事情を聞いていた教師はクラスメイトに押さえ込まれた新井に目を向ける。
教師に見つかって観念したのか、新井は悔しそうに黙っていた。
だが――、
「おい新井! なに黙ってんだよ、その程度の覚悟でイジメなんかするんじゃねぇよ!」
もう一人の男子は未だ大声で怒鳴り散らしている。歯を食い縛り、怒りにぎらつくその眼光は周囲に恐怖すら抱かせる。
彼は今にも新井に飛び掛ろうとしており、新井の倍近い数の男子が必死に制止しているところだった。
「おまえみたいなのがいるから世界は駄目になってくんだよ! どうしてもっと仲良くできねぇんだよ! 足りねぇよ、足りてねぇんだよ、全然!!」
「おい落ち着け葦原! 何が足りないっていうんだ!?」
その男子――“葦原牧人”のあまりの剣幕に、新井に話を聞こうとしていた教師は問いかける。
「先生のくせにそんなこともわかんないのかよ!」
訴えるように叫ぶ葦原牧人は――、

「“愛”とか“優しさ”とか、そういうのに決まってんだろぉ!!」
…………鼻血と共に涙を流していた。
「………………」
そして武田明彦は、そんな少年の様子を遠目から見ていた。
明彦の学年において、葦原牧人はヒーローのような存在だった。
クラスの中心となっていた男子たちの中でも、彼は特に皆から信頼されていた。
牧人は争いを嫌い、平和を愛した。
喧嘩があればすぐさま駆け付けて止めに入った。
イジメや喧嘩があれば見逃さず、必ず弱い者を助けた。
低学年の子供と交流がある場では、積極的に彼等の面倒を見た。
そうして、諍いなく皆が仲良くやっていける場を作ることに本当に真剣に取り組んでいた。
――――弱きを助け強きを挫く。
少年たちの中で、彼のその姿は正義の味方そのものだったのだ。
故に、そのある種の破天荒な言動もまた皆から尊敬と羨望を受けていた。
やり方は少々稚拙で粗雑なものだったが、誰もがその内に垣間見られる純粋な部分に心惹かれ、自然とリーダー的な役が回ってくる。
……葦原牧人はそんな子供だった。
彼は先の出来事で、“愛”や“優しさ”について主張していた。
だが、何もこれはその時に始まったことではない。
争いを止めようと必死になっている時、彼は常々このようなことを言い張るのだった。
…………彼は、本当に心の底から、そうしたものを大切にしたのである。
――愛……?
武田明彦は、彼の口から発せられるその言葉を聞く度に妙な違和感を内に抱く。
小学生――純真さの強く残る年代とはいえ、そのような美しい言葉を何の臆面もなく言えることが明彦の目には奇異に映った。
そして同時に妙な恥ずかしさを覚えるのだ。
牧人は新井を止めに入った。
身を呈して、殴られて鼻血を垂らしながらも、愛と優しさを主張するために。
しかし、明彦を始めとする他のクラスメイトは静観しているだけだった。
狂ったように桐原を攻撃する新井。その圧倒的な暴力を、恐れるように眺めていただけだ。
「…………」
明彦は考える。
葦原牧人には新井健太を止める理由があった。
小学生らしからぬ平和主義に固執する牧人には、新井の行為は許せないものだっただろう。
新井健太には桐原真を殴る理由があっただろうか。
本人にとっては桐原を攻撃する理由があったかもしれないが、それは他者を納得させるものではないだろう。
――……なら、僕はどうだ?
自分には、新井健太の桐原真への攻撃を傍観している理由があっただろうか。
ない、はずだった。
あったとしても、それは新井のものと大して変わらない気がした。
「そうか」
――僕は桐原を苛めていたんだな。
明彦はそのように結論付ける。
新井の行いを止めないことで、間接的に桐原を攻撃していたのだ。
それは別に桐原に対する嫌悪ではない。多くのイジメには意味や理由などありはしない。
その時々の流れであったり、新井のような嗜虐的な部分の暴発であったり、ほんの些細な悪感情であったり、いずれにせよその程度のものだろう。
――あの時、僕の中にも新井と同じ感情があったんだ。
一方的に新井に殴られる桐原を見ながら、自己の嗜虐的欲求を満たしていたということだ。
桐原に対する悪意はなかったが、好意もなかったのだから弁護などできない。
――なら、僕にも“愛”や“優しさ”が足りてないってことなんだろう。
そう思うと、明彦は妙にいたたまれない気持ちになったのだった。
「愛……、葦原、牧人……」
この時を境に、武田明彦は葦原牧人を気にかけるようになった。
クラスの中心で皆に頼られる彼。
……その中核を成す、やや行き過ぎた感さえある道義心。
心の最深から滲み出たそれらが、明彦の胸中に張り付いて離れないのだった。
……そんなことが、もう大分前に、あった。
件名:たすけちー!
内容:
「今日から大学始まったー!フル単の奴等は今年ゼミと卒論だけなんだって。でも俺まだ二十以上残ってるよ!死んじゃえよ!
あと、まだ就職決まんないよ!早く内定もらって髪キンキンに戻したいよ!助けてアッシ〜!?!」
会社に向かう途中に受信したメールは、大学時代の友人浅野からだった。
――お前がサボってるのが俺に何とかできるわけねぇだろうが……。
心中で悪態を吐くものの、牧人は表情がにやけるのを隠せない。
大学を辞めてからも、牧人は浅野と友好的な関係を続けていた。
日々こうしてメールのやり取りをし、休日はよく一緒に遊ぶ。
今では牧人の数少ない大切な友人の一人だった。
――あとで返信しておこう。
牧人は鞄に携帯電話をしまう。歩きながらメールを打つのはあまり好きではない。
そうすることで仕事に向かう意気のようなものが萎えてしまう気がするからだ。
自分は些細なことにも影響されやすい心の持ち主だと近頃牧人は自覚するようになった。
――ナイーブな感性なんて言いたかねぇけど……。
ナルシシズムに浸りたいわけではない。そうした性質そのものをよく理解し、割り切った上で上手くコントロールしていかなければならないと考えているだけだ。
「…………」
我が事ながら非効率で難儀な性質だ。そう思い苦笑する牧人。
しかしそこには、何とも不思議な余裕が見て取れた。
そうして牧人は歩行に集中する。
周囲を行き交う、無数の背広姿に溶け込むように。
基本的に定刻より大分早い時間に、牧人は出社する。
この日はロッカールームで主任と遭遇した。昨夜から残業をしていたのだと思われる。
「あ……、おはようございます」
「うん、おはよう」
慣れた対応。
この主任とは牧人がアルバイトをしていた高校生の頃からの付き合いである。
親子ほど歳の離れた二人だが、仕事仲間として信頼しあう間柄だ。
「やれやれ……結局、朝までかかっちゃったよ。葦原君、今日は任せていいね」
「はい。お疲れ様でした」
礼をすると、主任は穏やかに微笑む。
上下関係はあるものの、二人の態度は自然なものだ。気心の知れた空気がある。
「いやしかし、葦原君が来てくれてもう二年以上か……」
「一昨年の夏前からなんで、ちょうどそんくらいですね」
「ホント助かってるよ。ウチは万年人手不足だからね」
「あ、いや、俺なんてまだ全然……」
「高校出てから何があったのかは知らないけどね、そんなこととは無関係に僕は葦原君がここにこうしていることをとても嬉しく思ってる」
「…………」
「こんな小さな会社だけど、これからも頼りにしてるから」
「……ありがとうございます」
改めてそのように言われると、不覚にも感じ入ってしまう牧人だった。
緩みそうになる涙腺を精神の力で抑制する。
「あ、食べる? 梅味」
「…………」
いきなり牧人の目前に差し出されたそれは飴の袋。
この主任は、この手の菓子類を何故か常に携行している。
休憩時間などには、牧人もこうして度々分けて貰っていた。
「いただきます」
少しだけ戸惑いつつも一粒貰う。
そのまま口に含むと、落ち着いた酸味が口内に広がった。
「それじゃ、今日はよろしく。昨日言ってたアイランドビルの工事、委託先から昼頃に電話来るはずだから。社長に伝えておいてね」
「わかりました。お疲れ様です」
のしのし、とゆっくりした足取りでロッカールームを出て行く主任を見送り、牧人は一人残された。
「……ふぅ」
息をつく。肩肘張るほど短い付き合いでもないが、自然と緊張していたことがいなくなってから自覚される。
……牧人はこの主任という人物が少々苦手だった。
それは仕事の上司だからという理由ではなく、それ以上に彼の性格的な部分が大きい。
温厚な人柄でありながら、それでいて物事を鋭く見通す目を持った冷静な人物。
――似てるんだよな……雰囲気が……。
付け加えるなら、ふくよかなその体躯と旺盛な食欲も共通しているのだった。
「おはーっす」
「うーす」
牧人より数分遅れて出社してきた同僚がロッカールームに入ってくる。
歳が近い者同士、少しだけ空気が弛緩する。
「お前、昨日から連勤だよな。平気か?」
「まーなんとか。葦原もこの間はお疲れ、まさかいきなり隣の県はないよなー」
「下請けのこっちは仕事選べないからな……遠出すんのも仕方ねぇよ。交通費込みだし」
交わされるのは仕事の話題。雑談のようでありながら独特の真剣さが混ざり合う。
公私や緩急がそこには自然と混在していた。
そんな感じで、牧人は今日もそれなりに自立して生きていた。
「………………」
その日、久しぶりに早い時間に帰宅した牧人は、ギターを弾いて過ごしていた。
かつて――働き始めた当初は、帰宅した直後などは仕事の疲れですぐに休んでしまっていたが、最近ではこうして余暇を趣味に利用するようになっていた。
――余裕っていうか……、ただの慣れかな。
弦を弾きながら思う。
人は誰しも、思考を活性化させる動作や体勢のようなものがある。
思えば牧人にとってのそれは、ギターの演奏だったのだろう。
こうして六本の弦と格闘している時が、最も多くの想いを巡らせている。
無論それは音楽そのものや自分の技術についてのことが多いが、毎回徐々にその他の思考へ流れていくのだった。
この日の牧人もそうだった。
懐かしい曲を奏でながら、彼は追憶に浸っている。
……高校時代。彼が回想するのは決まってその年代だ。
それ以前でもそれ以降でもない。
小中学校に通っていた時期の記憶は最早薄い。それらは何も無価値というわけではないが、幼少の記憶として保存され、優しげなセピア色を帯びてしまっている。完全な過去なのだ。
高校を出てからの期間は今の自分と直結している。わざわざ思い出すまでもなかった。
故に、彼の高校時代の記憶は隔絶されていた。
大人と子供の境界とでも言えば適切だろうか。牧人にとってのそれが高校時代だったのだ。
両者の中間に位置したその時期は、やはりどちらにも属しない特殊な価値を持っている。
……牧人にとっては、それが既に届かないものだということも大きい。
当時の友人たちとの交流をほとんど無くしてしまった牧人にとって、その存在は回想の中でしか感じることができないためだ。
「…………」
友人たち。思い出すのはとりわけ薫のことだ。
なぜならこの瞬間の牧人はギターを弾いているから。
牧人にとって、ギターとは趣味の道具でも、名声を得るための武器でもない。
最初はそうだった。始めた動機もそうだった。
……だが葦原牧人にとって、ギターとは楽器である以前に薫とのリンクなのである。
彼女と築いた原初のリンク。つながり。
ギターを弾いていなければ、彼女にギターを聞かせなければ、……牧人の高校時代は全て異なるものになっていたはずだ。
だからギターは彼女との関連性の象徴。演奏は間接的な接触に近い。
いつしか価値が摩り替わったのだ。
……牧人本人が自覚していたかどうかは定かではないが。
「……馬鹿、……何、泣いてんだよ……俺…………」
気付けば指板が濡れていることに気付く牧人だった。
それで記憶の海から浮上する。気付けば深い思考に陥っていた。
心の海溝への潜水は優しく快くもあったが、こうして再び呼吸をした時の虚無感は果てしない。
多くの時が、そうして現実に立ち返るのだ。
今日も、牧人はギターを弾いている。中学生の頃に先輩から譲り受け、すっかり使い古されたそのギターを。
音楽は好きだ。弾くのを止めたことは何度かあったが、音楽自体を嫌いになったことはない。
だが、いざ社会に出た時、音楽に関わる仕事に就く気はなかった。
作曲家や演奏家としてやっていく自信も持てなかったし、ローディーや音響スタッフなどになってそうした人たちをサポートするのも違う気がした。
今だけは夢を内にしまって働きながら、いずれは時機を見て音楽活動のために今の仕事を辞める――そんな選択肢もあっただろうが、そうも思わなかった。
音楽を仕事にする人は素晴らしいと思う。尊敬に値すると心底から牧人は思う。
実際にそれをやっている人も凄いし、なろうと日々努力している人もやはり凄い。
しかし自分はそうではない。
――でも……それで、いいじゃねぇか。
軽んじているわけではなく、諦めているのとも違う。
そもそも……、
――そもそも、俺って自分のために音楽やってたんじゃねぇんだよな。
結局はそういうことだったのだ。牧人はそのことに気付いた。
彼がギターを弾くのは、薫のためだったのだ。
……いつしか、そういう風になってしまっていたのだ。
だから、牧人は自分のギターを彼女以外のために弾くことはないだろう。
彼の意思とは関わりなく……、否、彼の意思はそれ以外に動かない。
「……そういえば」
ふと、牧人は思い立って押入れを開いた。
手前に置かれたダンボールを開き、中身を漁る。
底の方に、それはしまわれていた。
「……あったなぁ、こんなん」
それは、包装のビニールすら破かれていない新品同様のDVDケースだ。
トールケースの表紙には、牧人が好きなギタリストが写っている。教則DVDだ。
“プレイスタイルだけでなく、サウンドメイキングも徹底解説! これで天才の技術と音があなたの物に!!”
そんな大仰なコピーが踊っている。
それは、以前薫に誕生日プレゼントとしてもらったもの。
高校二年生の時のことだ。あれから何年が経過しただろう。
――見てみよう。
唐突にそのように思った。
ギターを持って薫のことなど考えていたからかもしれない。
あの時はギターに冷めかけていたから見る気など起きなかったが、今は少しだけ内容に興味も湧いていた。
今やほとんど遊ぶこともなくなったゲーム機にDVDを挿入する。
正規のプレイヤーは持っていない。実家には置かれていたが、牧人個人の物ではなかった。
発売元や制作会社のロゴがいくつか表示されてから、簡単にタイトルが表示される。
そしたらいきなり本編が始まった。
ステージ上の衣装とは異なる、簡素な私服姿のアーティストが早口の英語で何事か喋っている姿はどこか珍妙だった。
しかし、自分にとってのヒーローとも言える人物が、画面越しとはいえ技術を伝授してくれるということは牧人にとって少なからぬ興奮だった。
「……っと」
画面の字幕を注視しながら、慌てて自分もギターを手にする。
大した前置きもなく、レッスンは始まった。
実際に今からフレーズを弾いてみるから続けてやってみよう、といった内容のことを画面内のアーティストは妙に陽気な口調で言う。
――よし、やってやるぜ……!
幾度かのブランクは経たものの、総合的な歴としてはかなりのものになる牧人だ。
高校を出てからの数年で、失った勘も取り戻しつつある。
少々難しいばかりの内容なら、初見でも追従できる自信が、……少しはあった。
あったのだが……、
「こんなの弾けるわけねぇだろ、アホか……?」
数分とおかず、唖然となる牧人だった。
その後も、画面内のそのギタリストは変わらぬ調子で超絶テクを披露し続け、的確なアドバイスもないままに(少なくとも牧人にとっては)教授は終了した。
――すげぇ簡単そうに弾いてるくせに……!
実際に自分がやると、とても真似できるものではないのだということが解る。
音作りに関しても何か言っていたが、感覚的な部分が多く、大半が意味不明だった。
――なんだこのDVD、こんなの何の役に立つんだよ!
視聴した直後の感想はそれだけだった。
ケースを開いた時の興奮や期待など、とっくにどこかへ失せている。
自分の中のヒーロー像が急激に風化していくように感じられた。
「…………」
しかし、ふと思う。
トールケースの裏側で、軽やかにギターを弾くそのギタリストの写真を見ながら。
――俺がもし、こんくらいギター上手くなったら…………、
…………藤宮薫はどう思うだろうか、と。
その思考は、あまりに自然に浮上してきた。
そのため、いかなる羞恥も自己嫌悪も、彼にもたらすことはなかった。
ギターは彼にとって――、彼女は彼にとって、それほどのものだったのだ。
「………………」
だから、牧人は今日もギターを弾く。
それは創作のためというより、愛犬と戯れる心理に近い。
……趣味とは、そんなものとも言えるだろうか。
「ねえ、起きて……マキくん」
優しげな声と共に体がゆすられて、葦原牧人は目を覚ます。
目を開くと、そこには彼の記憶より少しだけ大人びた彼女の姿があった。
「……おはよう、薫」
「うん。おはよう」
言葉を交わす。
たったそれだけのことでも、彼女がそこにいて笑ってくれていることが牧人は嬉しい。
場所は近所の公園だった。
日頃の疲れが溜まっていたのか、牧人はベンチでうとうと眠ってしまっていた。
「薫……お前、なにやってんだよ」
「ふふっ、ひざまくら」
見上げる彼女の手が、慈しむように牧人の髪を撫でた。
うっかり寝てしまっていた牧人は、気付けばベンチに横たわり、彼女に膝枕されている。
それは何とも快い状況だったが、自らの立場や年齢を思えば少々気恥ずかしい体勢だ。
「……よっと」
慌てて体を起こす。そんな素振りを見せないよう努めながら。
そんな牧人の姿を彼女は少しだけ残念そうに眺めていた。
両足を地面に下ろし、すぐ傍にいる彼女の隣に並ぶよう座る。
平穏な昼時の公園。
ともすれば再びふやけてしまいそうな意識を徐々に先鋭化していく。
寝ぼけた脳裏の情報が整理されていくのを感じる。
「……夢、見てた」
「夢。どんな?」
牧人の言葉を促そうと復唱してくれる。
「高校の時のこと」
「昔の夢だね」
彼女の言葉に牧人は頷き返す。
「……なんかヘンな感じだ。昔のこと夢に見るのって、マンガの中だけだと思ってた」
「あはは、そうだね」
笑み二つ。穏やかな空気。
「高校の、いつごろの夢かな?」
「いろんな頃……、ごちゃ混ぜになってた。楽しいこと」
「三年間――短かったけど、色々あったもんね」
「あぁ……、色々あった」
牧人の言葉を受けて、彼女も回想を始めた。二人して思い出を語り合う。
「文化祭でのマキくん、かっこよかったな」
「あー、あったなそんなことも。あの時は帰り道ですげぇ説得されたんだった」
「よく二人で帰ったよね。あの川原の道」
「たまに小学生が遊んでて、耕平と芥川が混じっていくんだよな」
「そこにマキくんが渋々加わっていく感じ」
「で、たまに俺んち来て遊んでた」
「二人でよくセッションとかしたよね。楽しかった」
「ああ、確かにな。なんつーか、その……付き合ったりするようになってからも、ずっと続けてたからな」
「ね、もっと恋人らしいことしても……よかったのに」
「十分しただろ。映画見たり、遊園地行ったり……」
「えー、でも、わたしはもうちょっとしたかったかな」
「……そっか。実を言うと俺も、もう少し」
「あはは。わたしたち、ちょっと焦り過ぎたのかもね」
また笑い合う二人。
もうあの頃からは長い時が経っていた。
「……みんな、あれからどうしてるんだろうね?」
「そうだな。今でも年賀状は来るけど……、もう会うことはなくなっちまったからな」
「みんな、忙しいのかな。いつか、また会って話せたらいいね」
「そうだな……」
想像する。
大人になり、それぞれの家庭や立場を持つに至った高校時代の仲間たち。
彼等と再び顔を会わせ、互いの近況を語り合うことは……きっと楽しいだろう。
「…………」
しかし、牧人は思う。
確かに今は、薫と二人だけになってしまった。
だが彼にとっては、それだけでもう充分だった。
彼女と共に歩んで来た道のりと、今こうしてここにある生活。
仮にかつての五人の輪が過去のものになってしまったとしても、薫が傍にいてくれれば、今の牧人が生きていくには充分すぎる希望なのだ。
「その後は、大学生だよな」
「同じ大学入れて、よかったよね」
「がんばった甲斐があった……とか言うのもダセぇけど、な」
「ううん、マキくんはがんばったよ。二人で一緒に入学式行く時、わたしすっごく嬉しかった」
「……俺もだよ」
間に流れる空気が面映い。
すっかり大人びたとはいえ未だ歳若い二人だ。
当時の色恋の感覚が追想され、そうした話題には甘やかな含羞を覚えるものだった。
「それでそのまま……結婚しちゃったね」
「学生結婚ってことで、親父たちには随分反対されたな」
「でも、あの時もマキくんはがんばってくれたよ」
「そ、そんなこと……ねぇよ」
「指輪もらった時は嬉しかったなあ……。結婚するって決まって、わたしもやっぱり女の子なんだなあって思ったよ」
「…………」
「…………」
しばしの沈黙があって、彼女が肩に頭を預けてきた。
ぎゅっと腕を掴んでくる手の薬指には今もその指輪がある。
「……楽しかったな、今まで」
「そうだね。でも、わたしは今も楽しいよ?」
「……まぁ、俺もそうだけどさ」
「変わらないね」
「あぁ、変わらない」
頷く牧人の表情は晴れやかだった。
幸福な日々の中で、愁いの表情など浮かぶはずもないのだ。
幸せすぎて、時に怖くなることすらある。
だがそんな時も、隣り合う彼女の存在を感じれば不安など吹き飛んでしまうのだった。
そして――――、
「とーちゃーん!」
呼び声と同時に、快活そうな少年が駆けてくる。
自分とよく似た少し癖のある髪。彼女とよく似た丸く大きな瞳。
まだ幼い体躯には瑞々しい活力に満ちている。
……どこまでも純粋で穢れない、彼等の大切な半身がそこにいた。

「とーちゃん、キャッチボールしよーよ!」
少年は手にグローブを持ち、意気揚々と牧人に話しかけてくる。
きらきらと輝く双眸には、希望の色しか感じられない。
「あぁ、いいよ」
咄嗟に目配せをすると、隣の彼女は楽しそうに頷く。
牧人は、いつの間にか手の中にあった軟球を握り締める。
そして、すぐ脇に自分用のグローブがあることに気付き、手にはめた。
立ち上がる。
「がんばってね、お父さん」
背中からそう声をかけられて、牧人はこれ以上ない程の幸福感に満たされた。
息子の前では彼女は彼のことをそう呼ぶ。
それは牧人にとって少し寂しくもあったが、同時に自らの立場を誇れるものでもあった。
「よし行くぞ、草太!」
「うん!」
息子の名を呼び、強い頷きを返される。
二人の間に子供が生まれた時、名前を決めたのは薫だった。
――お父さんは牧人、わたしは薫、だから牧場に薫る草で――草太。どう?
自分が決めると息巻いていた牧人だったが、薫の考えたその名前があまりに気に入ってしまい、そのままそれに決めてしまった。
だから、牧人は息子の名を呼ぶ時はいつも、心が踊る思いがする。
愛する人との間に生まれた子供は、牧人にとってそれほどまでに大切で、愛しかった。
「とーちゃーん、投げるよー!」
「あぁ、来い」
温かな日差し注ぐ広場に、親子は向かい合った。
――あぁ、なんて……。
陶酔するような彼の心に迷いはない。
順風満帆だった道程は今後も続いていくことが予感させられた。
……理想的。
何の衒いもなく、彼は自身の生き様をありのままそう呼ぶことすらできる。
放られるボール。
それは滑らかな弧を描いて牧人のグローブに納まった。
我が子の投球を受けた瞬間、そこに込められた幼い力を牧人は確かに感じ――――
「――――あ」
寝返りを打つとギシリとベッドが軋んだ。
その音で、牧人は目を覚ます。
…………夢だった。
「――――最、悪……」
顔を覆った。人に見られてはいけないような顔をしている気がしたからだ。
当然、四畳半は牧人を除いて無人。
指の隙間から見える天井は、今だ夜気の中にいて暗かった。
静かな、深夜だった。
「……う」
先程まで見ていた夢が思い出されて、牧人は思わず涙ぐみそうになった。
……嫌な夢だった。
幸福過ぎて、平和過ぎて、心地良過ぎる……悪夢だった。
夢自体は何の問題もない。
問題なのは、こうして目覚めてしまったことだ。
目覚めたこの瞬間の、牧人の胸に去来している途方もない虚しさが、問題なのだ。
夢の中の自分は、なんて素晴らしい人生を送っているのだろう。
薫や他の友人、更には両親との関係にも何の問題もなかった。
二人は同じ大学に進み、そこで結婚し、子供までいる。
牧人はずっとギターを続けていて、薫と楽しそうにセッションできているばかりか、文化祭のステージでライブすらしてしまっていた。
夢の中の彼の人生は、何から何まで、全てが上手くいっていた。
当然、生きていく中で様々な問題はあったが、その全てを愛と理性の力で乗り越えて幸福を掴むことができた。
そんな、理想的な姿を眠りの中で見て……、
「……で、コレが現実の俺か」
狭苦しい四畳半でベッドに横たわる自分を意識する。
夢の中の方が、今の自分よりもずっと明るく色付いていた。
皮肉なものだった。
――どうせなら、あのままずっと目が覚めなければよかったのに……。
一瞬だけそう思って、即座に否定した。
「……馬鹿が」
今の夢は……牧人の後悔であり、憤りであり、虚無感だ。
そうした心境的な閉塞が見せたものに他ならない。
それは現状に対する倦怠感であり、逃避的な欲求であり、生温く弱い自分の象徴ともいえた。
生きることを諦めさせる、甘い誘い。
……内に潜む悪魔の囁きのようだった。
――負けて、たまるか……。
弱い心に押し潰されることだけはあってはならないと思っていた。
押し潰されて、逃げてしまうことだけは。
「……それだけは、もう二度とあったら駄目なんだよ……!」
吐血するように言い聞かせる。
虚勢でも何でも、そうやって強くあろうとしなければ今の彼は立ち行かない。
それが無様でも情けなくても――カッコ悪くても構わない。
そうしなければ、どうにもならないのだから。
「…………?」
そんな、極限的な思考を中断させたのは、携帯電話の着信音だった。
――誰だよ……こんな時間に……。
部屋の電気をつけると、偶々時計が目に入る。
見れば、そこまで遅い時間でもなかった。
牧人が早寝過ぎるのだ。ギターぐらいしかすることがないのだから、そんな日もある。
――っと、電話か……。
連絡が来る相手など決まっている。
牧人は携帯電話を手に取り、開いた。
――通話……?
「……もしもし?」
『あ、マッキー先輩おひさしぶりっすー!』
反射的に受話器を耳に当てると、返ってくるのは懐かしい声。
――え……芥、川……?
芥川なつめが牧人に連絡をよこすのはここ最近では日常的なことだった。
しかし、それはメールに限られたものだ。このように、直接電話をかけてきたことは一度もない。
『うは、なんか声懐かしー! マッキー先輩ってば相変わらず不景気そうなー』
「……う、うるせぇよ、お前こそ能天気なまんまじゃねぇか」
『えは、変わりませんねー、あたしたち』
「…………そうだな」
奇しくも、先程の夢で似たような会話を交わした気がして、牧人の胸が再び疼く。
――忘れろよ、あんなのただの夢だ……。
今すべきは、急にかかってきたなつめからの電話への対応だ。
「……で、いきなり電話してきて何の用――」
『あ、実はですね、あたし今度、結婚するんすよー』
用向きを尋ねる牧人の言葉を遮って、あまりにサラッとそう告げられた。
「け――」
牧人、思わず絶句。社会人になってもこの手の不意打ちに弱い。
――けっ、こん……って?
その単語は重過ぎた。
以前ならば無意味に焦ったり悔しがったりしたかもしれないが、今の牧人には色々な意味で痛烈なだけだ。
――芥川が結婚してて……、夢の中の俺も結婚してて……、ええっと……?
しかし、その結果、無意味なことで苦悩してしまう牧人だった。
『今までと同じでメールでパパッと済ませちゃおうかとも思ったんすけど、やっぱあたしにとってもデカいことですしー』
「……そ、そっか」
まだ声が上ずっている。
『高3の時へたれちゃってたマッキー先輩には教えようか迷ったんすけど、ハブにしちゃうのもかわいそうかなーって。にひひ』
「え……?」
その言葉に、牧人の内に何かが閃く。
――俺……には……?
『……あれ? いやいやいや、マジでヘコまないで先輩! ウソですってば! ちょっとイジワルしたくなっただけっす! あたしはマッキー先輩のことそんな風には思ってないっすからー』
突然大慌てでまくし立てるようななつめの言葉が牧人には少しおかしかった。
この少女も自分を気遣ったりするのだ。
「うるせぇな、別にダメージ受けてるわけじゃねぇよ」
『ありゃら? マジっすか。先輩、高校生ン時より防御力上がったんじゃないっすか?』
「……かもな」
自惚れるつもりはないが、多少は強くなれたと思いたい。
『なーんか変な感じ。メール見た時もよく思うんすけど、マッキー先輩ってなんか仙人みたいになっちゃいましたね』
「え……せ、仙人?」
『ミョーに落ち着いてるとゆうか、ジジ臭いとゆうか……悟ったような感じがちょっと笑えるっす』
「………………」
――仙人? 俺が……?
確かに、高校時代よりは多少視野が広まったかもしれない。
物事を冷静に判断する力も身に付いて、無意味に焦る回数は減ったように思う。
――けど、そんな言われるまで変わったのかな?
成長――変化とは、多くが本人は意外に無自覚なもので、客観的に見ればその変遷は劇的であったりもする。
『まー、変わんないようできっとみんな変わっていくんすよね。マッキー先輩から見たあたしも、あの頃とはやっぱ違います?』
「どうだろうな……」
牧人には正直よくわからなかった。
変わったと言える気がしたが、それは単に高校生から社会人になっただけとも思えた。
それでも充分な変化と言えるかもしれないが、こうして会話を交わしている感覚は、高校時代とそう変わらないものとも思える。
「……まぁ、そんなもんなんじゃねぇの?」
『はい?』
「これでももう二十年以上も生きてんだ、根本的な部分なんてそう変わらねぇよ。状況に応じて表層的な部分を変える頑張りを覚えてきただけなんじゃねぇの?」
『おー……?』
なつめは唸るような呻くような、妙な声をあげた。
「あ? 急に妙な声出してどうした?」
『……なんか、マッキー先輩がそういうこと言うのってヘン! そういう人生トークは明彦先輩の役目じゃないっすか』
「そ、そんなこと言われてもな……」
牧人としては何も人生観めいたことを口にする気などなかった。
ただ、自然に思考が口をついて出てきたに過ぎない。
確かになつめの言うとおり、そのような見方を提示するのは常に武田明彦だった。
自らの在り方や考え方に思い悩み、煮詰まったところでそっと別の意見を考えて、聞かせてくれる。
若い彼等には納得できないこともあったが、そうした多面的な見地を示されることで、冷静に考え直すことができたことは確かだった。
――俺も……そんな風に考えられるようになってきたのかな……?
しかし、今の牧人は明彦がいなくとも、それができるようになっている。
それはたった今、無意識に零れ落ちたような不器用な思考でしかない。
だが、それも成長。それも変化。
「あ――」
――って、そうだ……明彦って――
そこで牧人は思い出す。
先程抱きかけた、その推測を。
「そうだ芥川、お前さっき俺をハブるとか言ったよな?」
『うが、まだ気にしてんすか? そういうネチッコイところは昔から全然変わらな――』
「じゃなくて! お前もしかして、俺以外のヤツとも連絡取り合ってるの?」
『あー、っと……』
なつめの声が不自然に途切れる。まるで自らの失言を悔やむように。
「どうなんだよ? 耕平とか明彦とも俺みたいに連絡し合ってんのか?」
『えーと……、ええ、まあ』
何やら頼りなかったが、なつめは確かにそう言った。
その事実が、牧人には衝撃的だった。
少し前の彼――それこそ大学にいたような頃なら、そう言われても特に何も思わなかっただろう。
しかし、今の牧人は違う。
「なら、教えてくれよ」
『教えるって……なにをっす?』
「あいつら、今何やってんだ? 元気、してんのか?」
尋ねるのだ。彼等の近況を。
……知りたかったから。
彼等が――牧人にとって何より大切だった仲間たちが、今、どこで、何をしているのかを。
それは、第一歩だった。
どれほどの間か願ったか、五人の輪の復縁への、強い強い踏み込み。
「俺、最近思ったんだ。やっぱりあの頃が一番楽しかった。
できることなら、もう一回あの五人で仲良く集まりたいって本気で思うよ」
無意識に、踏み出していたのだ。
今まで立ち止まっていた彼が、ようやく動き出すことを決めた……。
『…………』
電話口の向こう側にいるなつめは、それきりしばらく口を閉ざしていた。
「……芥川? どうかしたのか?」
あまりに長い間なつめが黙っているので、不審に思った牧人が聞き返す。
『そ、そんな不安そうな声しなくたって平気っすよ……、ちょっとくしゃみが出そうだっただけっす』
「ふ、不安そうな声なんかしてねぇよ!」
『えはは……、いや、なんか、その、ねえ?』
「なに?」
『いやー、マッキー先輩……やっぱ変わりましたって、うんうん』
「は? いやだからお前、それはさっき言ったみたいに――」
『じゃなくって、根っこの部分もパワーアップしたって思ったんすよ。今』
「……今?」
前述の通り、成長の自覚とは往々にして本人にはないものだ。
牧人が見栄も張らず、躊躇いもせず、純粋に他者を求めたその姿が、果たしてかつてと同じものと言えるだろうか。
否。否である。あの葦原牧人なのだ。
牧人自身は知る由もないが、先程なつめは本当に口を利くことができなかった。
言葉が出てこなかったというのもあるが、声を出すとそれがカッコ悪く震えてしまいそうだったからだ。
……それほどまでに、牧人が口にした言葉がなつめには衝撃的で、感動的だったのだ。
「おい、久しぶりに喋ってもやっぱお前ワケわかんねぇぞ」
『……やはは、すんませー。もー、おっかしーなマッキー先輩、涙が出ちゃ出ちゃうっすよ』
しかし、当人は気付かないのだ。
だからこそなつめにはそれが可笑しくて、嬉しくて、……羨ましかった。
そして牧人は、なつめから皆の近況を聞かされた。
耕平は東京に出て、大学生をしていること。
薫は今も平坂の実家にいて、地元の大学に通っていること。
明彦もやや遠方の大学に通っているが、最近は忙しいのか連絡がつかないこと。
『カオル先輩は、彼氏いないそうっすよ?』
「ば、馬鹿……そんなこと、関係ねぇだろ……」
そんな言葉に思わずそんなことを言ってしまう牧人。
――薫、か……。
彼女は、酷く傷付けられたことだろう。最早何度悔やんだかも解らない、自分の過去の行為を牧人は思う。
だというのに、なつめの口から語られる彼女は、細かい内情はわからないまでも、有名大学に通うなど順調に生きている様子だった。
大学を中退し、両親から勘当され、工具と油に塗れながら日々細々と生きている自分とは明らかに違う。
きっと、そのままその学歴を評価されて、大学と同じくらい有名な企業などに就職することになるのだろう。
――やっぱ、すげぇな……薫って……。
改めて思った。
藤宮薫は立派だ。尊敬すら抱く。
だというのに自分はそんな彼女を拒絶してしまった。
――馬鹿なヤツ……。
後悔は日々膨張し、耐え難くなっていく。
……それもまた、変化か。
『…………もう、大丈夫なんすね。マッキー先輩』
「あ?」
近況報告が終わり、一段落ついたところでそのように言われる。
不意になつめが告げたその言葉に、牧人は戸惑った。
『もしかしたら、近々何かあるかもしんないっす。電話には注意してくださいね』
「は?」
『いやー、びっくりしたっす。マジで明彦先輩の言うとおりになっちゃうんだから……』
「おい、お前さっきから何言ってんだ? 明彦がどうした?」
『あ、やばし! これはマジモンの失言なんで聞き流す方向で』
「…………?」
そのような感じで、通話は終了した。
電話を切ってからも、数分間妙な興奮が体を熱くしていた。
最後の会話は少々解せないものだったが、皆のことを思っているうちにどうでもよくなった。
冷蔵庫から缶ビールを取り出してきて、一口含む。
そうして、わけもわからず高鳴っていた鼓動がようやく収まった。
「あ……」
その段になって、牧人はなつめの結婚に関して何もコメントしていないことに気が付く。
直後、慌てて掛けなおしたものだ。
……そしたら呆れられた。
そんななつめとの電話は、とても楽しかった。
翌朝。
あの後、深夜から寝直した牧人は目を覚ます。
……夢は、もう見なかった。
ただ何も無い暗闇を通過して、気付けば朝になっていたような感覚だった。
熟睡していたのか、意識が妙に冴え渡っている。
「………………」
しかし昨夜なつめから聞き知った諸々の情報は、冷えた鉄のように牧人の内側で強くその存在を主張していた。
天井を見上げたまま横たわっている。
牧人は起き上がろうとして、思い直した。頭の下に手を敷き、再度天井を見る。
本格的に活動を開始する前に、しばしそうしてぼんやりと思考を整理したかった。
昨夜伝え聞いた皆の近況。誰もがそれぞれの日々をそれぞれに生きている。
そんな彼等のことを一人一人考えていこうと思った。
高校時代に共に過ごし、日々笑いあった四人の仲間たち。
彼等と、もう一度会いたい。会って、話して、今後もその繋がりを育んでいきたい。
そう思おうとして……、
「馬鹿だなぁ……俺……」
顔を覆った。またも人に見られてはいけないような顔をしている気がしたからだ。
当然、四畳半は牧人を除いて無人。
苦笑する。
――薫のことしか、考えられねぇ……。
指の隙間から見える天井は、朝日を浴びて汚れも目立つ。
静かな、早朝だった。
牧人は、薫に会いたくなった。猛烈に会いたくなっていた。
なつめと会話し、仲間たちの近況を知った。
今まで不明だった情報が牧人の中に統合され、会話をすることでそれらが整理されていた。
そうして明確に形を成したのが、藤宮薫に対する想いだったのだ。
思えば、この数年で彼女に言いたいことや知らせたいことが山ほどあった。
そうした要素ができる度に、もう意味がないと胸の内にしまいこんできたのだ。
だがもう無理だった。彼女の今を知ることで、それらの要素は残らず露見し、牧人の中の薫は再び息づいてしまったのだ。
今ある自分を薫に伝えたかった。
また、今の薫のことも彼女自身から聞いてみたかった。
ギターもたくさん練習した。
一人暮らしを始めて家事だって一人でできる。
仕事も日々きついが、辛くても逃げることなどしない。
そんな今ならば、もっと彼女のことを考えてやれるはずだと思った。
だから、
「あぁ……、くそ、薫に会いてぇ……!」
牧人は正直になった。
――会いたい、話がしたい、傍にいて欲しい……。
思い出すのは、昨夜の夢だ。幸せで、穏やかで……、今やどこまでも遠いあの空気。
あの光景を、自分は本当に夢のまま終わらせて良いものなのかどうか。
疑心が生じる。
かつての牧人ならその感情を否定するだけだったはずだ。
自分で撒いた種だと。今更求めるなど図々しいと。
そうして斜に構え、冷静に見定めて……逃げたはずだ。
だが、成長している。
無様でいい。みっともなくても構わない。
千鳥足のように不安定でも、とにかく前に進んで、掴み取りたい。
いつからか、そう在ろうとしていたのだ。それがようやく、彼の中で動き出した。
自然な姿でそのように機構し始めたのだ。
「……ちょっとでいい。ホントにちょっと……勇気、出ろ」
呟いて、彼はベッドから起き上がった。
葦原牧人は立ち上がる。
…………彼はもう、寝転がったままではない。
牧人は、五人の輪を取り戻すために動き出すことに決めた。
崩したのが自分なら、元に戻すのも自分でなければならなかった。
……実際はそのような使命感はあまりなく、彼は単に、そうしたいと思って勝手に動き始めただけだ。
仲間たちと過ごす日々が何より尊く、大切だから、それを再び求めたに過ぎない。
本心に素直に従った。それだけのことである。
……自分の本心というものを、初めて正確に認識し、受け入れたのがこの時だった、とも言えるのかもしれない。
何はともあれ、牧人はそうすることに決めたのだった。
故に早速動き出すことにした。
――しかし、どうすっかな……?
思い悩んだ。いざ動こうとしても、まず何をするべきか。
五人を集めようにも、いきなり召集をかけることはさすがに無茶だろう。唐突過ぎる。
――何か集まる理由を……作るか?
動機付け。なんとなく白々しいことだが、段取りというものは必要だと思った。
それほどまでに、今の牧人は彼等と断絶している。
――時間、かかるかもな……。
何か特別な理由をつけて声をかけるか、一人一人と連絡を取り合って、徐々にでも関係を取り戻していかなければならないと思われた。
――でも、今更連絡するのも、突然集まって会おうとか言い出すのも、結局は同じなんじゃねぇか?
迷う。どうすれば最善なのか。
これは牧人にとっては一世一代の大仕事だ。
別に臆病になって気後れしているわけではなく、慎重に事を運ぶ必要があったのだ。
考えなしに行動して中途半端な結末になってしまうことだけは、なんとしても避けたかったからだ。
「……ふぅ」
ため息ひとつ。何も一人で悩むこともないと思った。
――芥川に相談してみようか。
携帯電話を開く。着信履歴にすぐに彼女の名前が見つかった。
「…………?」
コールが始まって数秒も経たない間に、アナウンスが流れた。
――お客様のおかけになった電話番号は、電波の届かない所におられるか、電源が入っていないため…………、
――電源切ってるのか。
仕事中なのかもしれない。
牧人はこの日は公休だが、なつめのシフトは不規則だ。平日に休みがあったり、週末の夜に忙しかったりするため予測がつかない。
「メールだけでも送っておこう」
アドレス帳を開き、メール作成画面へ。
全て書くと長くなりそうだったので、内容は適当に端折ることにした。
相談がしたいので電話をくれ、と末尾に書いておく。
「これでよし」
とりあえず、なつめからの連絡を待つことになりそうだった。
――けど、なんか……、
しかしそうすると、途端にすることがなくなる。
動こうにも、一人で何ができるだろう。
「落ち着かない……」
呑気にギターなど弾いて待つ気にもなれなかった。
何か、今のうちにやっておけることはないだろうか。
――あ、そうだ……そういえばアレって……。
ふと思い立って、牧人が押入れを開いた時――、携帯電話が鳴った。
「え? 芥川のヤツ、もう電話してきたのか?」
仕事中ではなく、単に電波の悪い場所にいただけなのかもしれない。
そう思って再び携帯電話を開くと――、
「う、そ……だろ?」
そこに映し出された名前に驚愕する。
――なんだこれ……? なんで、このタイミングで……?
「…………」
言葉にならない。
まるで、全てが仕組まれているかのように思われた。
それほどまでに絶妙なタイミングでの、連絡。
――もしかしたら、近々何かあるかもしんないっす。電話には注意してくださいね。
それは誰の言葉だっただろう。
「……へっ」
不適な笑みがこぼれた。
驚きを隠せずも、あまりの整い具合に笑ってしまう現状。
――もしかしてお前なら、こんなこともやりかねねぇか……。
単なる偶然という可能性もある。
だが、なんとなく牧人にはこれが全て彼の思惑なのではないかと思われた。
それならそれで悪くなかった。
上で転がされる手のひらが彼のものだったとしても。
だから、少しでも強がってやろうと思った。
動揺を見せないように、余裕を持って、自然な態度で……、
「よぉ、久しぶりだな……、…………明彦」
親友の名を呼んだ。
『うん、久しぶりだ。牧人』
呼ばれて武田明彦は、変わらず柔らかな声音にてそう返してきた。
それはどこか牧人の言葉に満足するようでもあった。
『いきなりなんだけど、今日は牧人に相談したいことがあるんだ。長電話になっちゃうと思うけど、通話料金は大丈夫かい?』
「馬鹿が。そんなつまんねぇこと気にすんなよ」
――相変わらず、よく気が回るヤツだなぁ、明彦……。
昔からそうだった。牧人自身が気にしていないようなことまで気にかける細やかな気質。
そして、今まで音信普通だった相手にも突然電話をかけてくるという大胆な行動。
改めて感心させられる。
――明彦、お前ってやっぱ……すげぇヤツなのかな?
そう思うと、牧人は涙が出そうなほど心が高ぶってゆくのを感じた。
同時に、そのいきなりの電話に、どこか先を越されたような悔しさがあって、何だか可笑しかった。
雑多な感情をその内に渦巻かせて、通話が……始まる。
小学生の武田明彦が、件の葦原牧人と明確な交流を持つようになったのは、彼が牧人のことを気にし始めてしばらく経ってからのことだった。
「――それでは来週の発表に向けて、どのグループもがんばってください」
担任教師のその言葉に、子供たちは声を揃えて返事をした。
その時期、明彦のクラスでは社会科のグループ演習が行われていた。
各班それぞれ地元の文化を調べ、大きな模造紙にその成果を纏めて発表するというものだ。
小学生の授業とはいえ、調査や構成にはそれなりの工夫が求められる。
五人で構成された班員のチームワークが試される時だった。
……そんな中、あったことだ。
「じゃあ、武田。あとはまかせたからな」
「うん。いいよ」
明彦は同じ班になった少年の言葉に頷く。
机の上には真っ白な模造紙が広げられており、色とりどりのマーカーペンが転がっていた。
「へへっ、武田が一人でやってくれるなんて、ラッキー!」
「こんなデカい紙に、調べたこと全部書くなんてメンドくさいもんな」
その他の少年たちも口々にそのようなことを言っている。
……そんな彼等の様子を、明彦は無関心な瞳で見つめていた。
明彦たちの班は調査を終え、その成果を一枚の紙に纏める作業に入ろうとしていた。
しかし、班員の少年一人がその段になって面倒だなどと言い出したのである。
地元の資料館を巡る調査活動は遊びたい盛りの小学生にとっては予想以上に苦痛だったのだろう。緊張が続かなくなってしまうのも無理はないのかもしれない。
だが、生じ始めた倦怠感は次々と他の班員にも伝染し、この日は作業という雰囲気ではなくなってしまった。
発表は来週。早めに取り掛からねば、後が辛くなる。
――なら、今日は僕が一人でやろう。みんなは先に帰っていいよ。
ため息を隠しながらそう言ったのは他ならぬ明彦だ。本来なら班全体で取り組まねばならない作業を彼は一人でやろうと宣言した。
少年たちはその無謀な言葉を省みることもなく、渡りに船とばかりに彼の申し出に応じたのだった。
……子供は残酷だと言う。情けを知らない幼い頭脳は、基本的に他者の苦労より自らの快楽を優先させてしまう。
未だ他者性の薄い彼等には仕方のないこととも言えた。
――いつかは誰かがやらなきゃならない。なら……それが僕一人でも問題ない。
心中で、明彦はそのように独白する。
ほんの少し先の未来――その時の苦労さえ見据えることのできない班員たちに、小さな失望を抱きながら。
「じゃあ帰ろ! 今日も駄菓子屋寄ってこーぜ!?」
「ああ、いいよ。…………おい牧人、何ぼんやりしてんだよ?」
「……ん? あぁ」
それまでただ一人無言だったのは、葦原牧人だった。
……彼もまた、明彦と同じ班だったのだ。
意気揚々と帰ろうとする他の少年に促されて、牧人は曖昧に返事をする。
「武田がやってくれるって言ってるんだぜ。オレたちは先に帰って遊ぼうよ!」
「……本当に、いいのか? 武田」
仕事を押し付けられているのは明彦だというのに、尋ねる牧人は不満そうな表情だ。
「ああ、葦原くんも先に帰っていいよ。僕一人でもなんとかなると思う」
「…………」
最後まで納得の行かない顔をしながら、牧人は他の少年たちと共に教室を出て行った。
「…………」
――葦原牧人……結局は君も、他のみんなと同じなのか。
声には出さないまでも、明彦は少々残念な気持ちを抱えていた。
「――――」
そして、自分でもその感情の発露に驚く。
――僕は……彼に何を期待していたんだろう……?
かつて、放課後の廊下にて愛と優しさを主張した葦原牧人。
その時に感じられた強い意志のようなものを、自分は彼に無意識のうちに期待していたというのだろうか。
――それは、僕の甘えと言えるんじゃないか?
確かに作業を先延ばしにするのは非合理であると思ったが、それを一人でこなすことが億劫であったのもまた事実だった。
故に、彼の優しさに一方的に期待を抱き、勝手に裏切られて口惜しく思う。
「……まいったな」
呟く。
驚いたのだ。それほどまでに自分の中で肥大化している、葦原牧人の存在に。
クラスメイトが彼を正義の味方と尊信するのにも合点がいった。
誤魔化すように、明彦はマーカーペンを手に取った。
――ぼんやりしている暇はない。やるべき作業は山積みだ。
一人でやると言った手前、それなりの出来では格好が付かないだろう。
その大人びた思考のためか、明彦はこの年代にしては体裁を意識し過ぎるきらいがあった。
物事がよく見えた分、自意識過剰な面があったのかもしれない。
調べたことがメモされたノートと模造紙を見比べて、構成を考える。
――上の方に大きくタイトルを書いて、グラフと表の横に解説を付け加えて……、
様々なアイデアが浮かんでは消えていく。
「……まあ、書きながら考えるか」
とりあえずは下書きをしながらすることにした。
鉛筆を手にし、頭に浮かんだ構成を簡潔に書き込んでいく。
そんな作業を始めて数分ほど経ったその時――、
「……?」
教室の戸が、勢いよく開け放たれた。
――まさか……、
そちらを見て驚いた。
「よぉ……、一人じゃ、大変、だろ」
ぜいぜいと荒い息を吐きながら、入り口に立つのは葦原牧人。
その右手には小さなビニール袋がぶら下がっている。
「……どうしたの? みんなで駄菓子屋さん行くんでしょ?」
やや困惑気味に尋ねる明彦に、牧人は小走りで駆け寄ってくる。
机の上、開かれた模造紙の中心に、右手のビニールがどさりと落とされた。
「俺も手伝う。お菓子買ってきたから食いながら一緒にやろう!」
そう言って、少年は力強く笑って見せるのだった。
「……はー」
疲労困憊といった体で、大きく息を吐きながら明彦のひとつ前の席に座る牧人。
荒い呼吸。見れば、額に汗も垂らしている。
ビニール袋が倒れ、中からいくつもの駄菓子が転がり出る。
どれもが、通学路にある駄菓子屋で購入できるものばかりだ。
――コレを買って、戻ってきたのか。そんな、息を切らしてまで……。
「武田はどれが食いたい? 先に選んでいいぜ」
「…………」
「な、なんだよ? もしかして駄菓子キライなのか?」
「いや……」
明彦は袋を探る。
実際のところ駄菓子は好きだった。常食している。
「これをもらうよ」
「後で他のも食っていいぜ。長丁場になりそうだからな」
とりあえず二人は、一本十円の棒状スナック菓子をもりもりと食したのだった。
「さてと、やるか。書くこと多いから分担しようぜ」
「…………」
食べ終わった菓子の包装を丸めながら、牧人は早速ノートを引き寄せる。
「武田はどこがいい? やっぱ、自分が調べたところにするか、だったら――」
「葦原くん」
発言を遮って、明彦は声をかけた。
不意に名を呼ばれ、牧人は言葉を止める。
「聞きたいことがある」
菓子を食べている間からずっと考えていたことだ。
「――どうして、他の友達を放り出して、僕を手伝ってくれるの?」
武田明彦は葦原牧人とさして親しいわけでもなかった。
だというのに、ここまで献身的な態度を取られるというのは変な気分だったのだ。
「なに言ってんだよ――」
葦原牧人はくだらないとでも言いたげに頭をかき、居住まいを正した。
「――――」
強い意思を感じさせるその瞳に正面から見据えられ、明彦は少々たじろぐ。
――そうか……この目……。
「あのなぁ武田、知ってるか――?」
牧人は咳払いをして、朗々と告げた。
「天は人の上に人を造らず、なんだよ」
「………………」
冷静になってみると、何もおかしなことはない。
……普段の葦原牧人を見ていれば、彼がこうした行動に出ることは容易に想像がつく。
むしろ何故今までそれを疑問に感じていたのかが不思議だった。
ところが実際に直面してみると、それはあまりに奇妙で、戸惑わずにはいられないのだった。
「で、人の下に人を造らず、と続く。わかるか?」
「……うん、まあ」
「これは昔の偉い人が言ってたことなんだ。一万円札の人だぜ、顔ぐらいは知ってるだろ?」
福沢諭吉のその言葉は明彦も知るところだったが、小学生にしてはやや高度な知識だ。
「つまり人間ってのは本来平等なんだよ。どんな理由があっても……なくても、差別とかしちゃいけねぇんだ」
……ちなみに牧人が引用したその言葉は、本来は賢愚や貴賤を分かつのは出自ではなく学問であるということが本来の主張である。要は学問を推奨するための言説であり、純粋な平等論を述べたものではない。
従って実際のところ、牧人がその言葉を正確に理解しているとは言い難く、明彦は彼が持ち出した知識を訂正することが出来た。
「…………」
しかし、それはしない。
ろくに知りもしない偉人の言葉としては間違っていても、明彦の前にいる葦原牧人の言葉としては、これ以上なく正しかったからだ。
偶々どこかに書いてあったものを見て覚えていたのか――ただそれだけの言葉でも、おそらく牧人にとってはこれ以上無く、信奉に値するものだったのだろう。
――その辺は、僕と似ているのかもしれないな。
明彦も、様々なものに触れる中で、そこで得た様々な思想を内部に渦巻かせていた。
表出するかしないかの違いで、両者は共に思考をしているのだ。
「みんな平等なんだ。だから、お前だけが苦労するなんて駄目だ」
自信満々といった表情で、明彦をまっすぐに見据えてくる。
その視線には何の衒いも躊躇いもなく、彼が本心からそのことを主張しているのだと解る。
確かに偉人の言葉からの引用という部分はペダンチックなのかもしれないが、その思想を心から信じ、実行している点では彼には一片の曇りもない。
「そんな……理由で?」
そのような理想論は口にすれば往々にして陳腐な意見に成り下がってしまうものだ。
……少なくとも明彦はそう思っていたし、大人たちもそう思っていただろう。
「なんだよ、悪いかよ?」
「……いや」
だが、すねたような目をする葦原牧人の姿を見て、明彦は反射的にかぶりを振ってしまったのだった。
――なんだろう……? この感じ?
心の奥が焼け焦げる感覚。
それはきっと、羨望だったのだろう。
現実を知り、理想を語ることのなくなった者が抱く、辿り着けぬ場所に対しての。
……そしてそれを語ることのできる純粋さに対しての。
――そうか……、僕は彼のように……なりたかったのか。
美談を、綺麗事を、本来正しく自然なものであるように捉え、誠実に実行する気質。
仮にそれが優しい理想に過ぎなかったとしても、そうしたものを信じて人を愛する気質。
……そんな心が、僕も欲しかった。否、欲しくなったのだ。この時に。
「……葦原くん」
「なんだ?」
だから明彦は、生まれて初めて、積極的にその手足を動かした。
ただ闇雲に、もがくようにばたつかせたのだ。
前に進み、掴み取ろうと。
「僕たちは、トモダチになれるかな?」
そうして求めたものは、牧人との絆だった。
純粋で美しい彼と共にいて、その姿をもっと見ていたかった。傍にいて学び取りたかった。
そうしたら、そのような声をかけていた。
――その切り出しは……どうなんだろう?
言ってから自嘲する。かなり不自然な発言だったと思われた。
しかし、
「なにいまさら言ってんだよ。俺たち仲間だろ。あんな苦労して、いっしょに資料館歩いたじゃねぇか」
またも、そのようなことを言われてしまうのだった
「……そうだったね」
思わず明彦は笑った。
笑みを作らねば、涙がこぼれてしまいそうだったからだ。
……そうして、武田明彦は葦原牧人の隣に立つようになった。
彼の核を成す部分を間近で観察し続け、理解しようとした。
後になって、明彦は牧人の家庭環境を知り、何故彼が平等や平穏にああまで固執していたのかを理解するようになった。
実力ある企業家の両親の姿に、牧人は本当に幼い頃から競争社会の有り様を見出してきたのだろう。
それを疑問に思うようになり、妙に大人びた思考や発想をするようになってきたのが、ちょうど明彦と出会った頃だったのだ。
親に対する不審が芽生え、偶然見かけたような過去の偉人の言葉ばかりを尊ぶようになった。
自身の中に植え付けられたものと明らかに異なる美しいそれら言説は、牧人の記憶に強く焼き付いたのだろう。
そして、数年後――小学校高学年に達した頃に牧人は反抗期に突入し、両親と日常的に対立するようになるのだった。
「誰が勝つとか負けるとか、そんなのはおかしい。
みんな友達なんだ。みんな同じなんだ……それでいいじゃねぇか……」
初めて両親と激突した翌日、牧人が漏らしたその言葉を、明彦は今もはっきりと記憶している。
たまらなく愛しかった。
理想を求めて日々苦悩する牧人。
様々な対象についてその変遷を続けた彼……その支えに少しでも自分がなれていたらいいと、明彦は願う。
……そんなことが、もう大分前に、あった。
『そうか、今は一人暮らしなのか』
「知らなかったのか? 芥川とは連絡取り合ってたんだろ?」
『牧人が元気にやっているとは聞いていたけどね、細かい環境については知らなかった』
「……そうなのか」
過去、そのようにして出会った牧人と明彦は、今は電話で会話をしている。
本題に入る前に、明彦は高校を出てから牧人がどうしていたかを尋ねた。
大まかに説明するつもりが、気付けば随分長々と語っていることに牧人は気付く。
――俺、舞い上がってるのかな?
久々に誰かと昔の話をしていることが、嬉しいのかも知れなかった。
「っと、俺の話はそんなところでいいか。お前も聞いてるばっかりじゃつまんねぇだろ」
『いいや、楽しかったよ。牧人にも色々とあったんだね』
「色々ってお前……」
――そう言われると、何だかあっけないな……。
複雑な気分になりながらも、明彦に言われると不思議と悪い気はしない。
明彦は牧人が話している間、高校時代にあったことについては何も触れようとしなかった。
確かに彼は耕平のように牧人を見限るような風ではなかったが、まるでそのことがなかったかのように、以前と全く変わらない態度で牧人の話を聞いていた。
そのことに多少戸惑いながらも、牧人は安心していた。
――明彦は、まだ俺の話を聞いてくれようとしているんだ。
それは、希望が繋がったこと――五人が再び輪を作り出す可能性を示しているからだ。
――もしかしてこいつ、俺を待っててくれたのかな?
そうだとしたら本当にありがたいと思った。
あのような情けない姿を見た後でも、まだ自分を見守ってくれていたのだから。
「お前はどうなんだ? 高校出てから、今まで何やってたんだ?」
牧人は尋ねる。
更に会話を繋ごうと。
『そうだね。僕のほうは牧人ほど波乱に富んだ感じじゃないけど――』
そう言って互いに笑う。
『うん、それを話しながら……本題に入っていこうか』
明彦は穏やかな口調を変えないままに、どこか真剣な色を纏わせた。
……そうして牧人は、今度は明彦の話を聞いた。
高校を卒業して、彼が何をしていたか。
――――その中で彼が何を思い、今後何をしようとしているか。
明彦はじっくりと時間をかけて、彼の考えを牧人に語った。
牧人はそれを一つ一つ噛み締めるように、大切に聞いた。
「……そっか」
一通りの話が済んだ直後、牧人は短くそれだけ言った。
『急に連絡して、こんな話してごめんよ。驚いた?』
「まぁ……な」
明彦の語った内容は牧人にとって少々驚きが大きかったが、納得しうるものだったからだ。
「けど……、もう決めたことなんだろ?」
『うん。悪いね』
「……馬鹿。悪くなんかねぇよ、お前、昔からそういうの好きだったんだろ」
『よかった、覚えていてくれたんだね』
「……まぁな。やったじゃねぇか、夢……だったんだろ?」
『うん』
明彦の言葉には迷いがなく、語りは理路整然としていた。
そこには、彼の強い信念が込められていると牧人には思えた。
自身の道を見定め、歩んでいく気概。それを語る言には、力が宿る。
――なら、俺が何か言って、それを鈍らせるようなことはしちゃいけねぇ。
今の牧人には、それが理解できた。
『だからさ、牧人に協力して欲しいことがあるんだ』
「協力?」
『そう――』
おもむろに切り出された明彦のその言葉に、牧人は深く考えることなく聞き返し――、
『最後に、同窓会みたいなことをやりたいんだ』
「同窓……会?」
その言葉で、何かが内に生じるのを感じた。
『僕ら五人だけの同窓会だ。だから、他の三人の予定を合わせて欲しい、牧人に』
「俺が? 何でそんな……大体同窓会って――」
『これから先、牧人やなつめちゃんだけじゃなく、僕たちも社会に出て、それぞれの道を歩んでいく。きっとそれはそれぞれにとって険しいものだろう。だから……お互い励まし合わないといけないだろ?』
「……励まし、合う……?」
『そうだ、人は一人じゃ生きていけない。何かに必死な時は平気でも、ふと一人になれば孤独や悲しみが積もってすぐに疲れてしまうよ』
その感覚には覚えがあった。
日々の仕事をこなす中、心身に何も問題はなくとも、その裏で何かが削れ落ちていく不安。
『だから、それを何とかするために、仲間が必要なんだろ?』
仲間。
「それで……高校の時の俺たち五人ってわけなのか?」
『そう。僕はそれが最善だと思った、五人のうち誰にとっても』
電話越しなので見えないが、明彦が強く頷く様をイメージさせられた。
『僕は、あの五人が好きだ。五人で作った空間が好きだ』
「…………」
――そういえば……、
強く告げられるその言葉を聞いて、牧人は思う。
『あれは、僕も牧人も――みんなが自然体で、無心のまま自分自身であれた場所だから』
「………………」
――明彦が一番、俺たち五人を五人として見ていたんじゃないか?
どんな時にも、最後尾から見守るように優しげに全体を眺めていた明彦。
『それを許される五人だったはずだろ?
ならそれはきっと、何よりも尊いつながりだよ』
「…………あぁ、そうだな」
――明彦が一番、俺たちを五人として好きだったんだな……。
故に静かに後列に立ち、誰よりも率先して五人の空気を守ろうとした。
進んで裏方に回り、全体の調和を最優先した。
そして、他の四人の言葉を真剣に聞き、求められれば意見を述べた。
『だから……もう一度会おう、牧人。終わりにしちゃいけないよ。僕たちが、これからも強く生きていくために、ね』
「…………」
いつも彼がそうしていてくれたから、自分たちは維持されていたのだと牧人には思えた。
そして、そうした苦労をまるで感じさせない。
牧人があれほど悩んだ理由も、明彦が言うと驚くほど自然だ。
牧人にとって、それは願ってもない言葉だった。
……薫に会いたい、耕平やなつめとも昔みたいに仲良くしたい。
もう何度思い返したかも解らないほど、あの時代の大切さを胸に抱いている。
それを取り戻す機会をくれるなら、協力する以外の選択肢があるはずもなかった。
――お前、やっぱすげぇよ……。
電話でよかった、と牧人は思う。きっと自分は、泣きそうな顔をしているだろうから。
「……なぁ、明彦」
『うん?』
だから、牧人は問いかける。
「どうして、俺なんだ?」
そのことを確認しなければならないと思ったからだ。
「俺はあの時、自分勝手な理由でその輪をぶっ壊したじゃないか」
彼の与えてくれた機会――それを受け取る資格が自分にはあるのかどうか。
「あの時は耕平を失望させたし、薫のことだって傷付けた。お前だって――!」
その点に触れずにいてくれた彼の優しさには感謝する。
何も言わず、昔と同じように自分を頼りにしてくれたことに感謝する。
「お前だって……俺のこと、駄目なヤツだって思っただろ…………?」
だが、だからこそその理由を追求しなければならない。
彼の無償の友愛に、そうしなければ応えられない。
『……僕は…………』
明彦は、少しのあいだ沈黙していた。
しかしそれは、言葉に迷ったわけではない。
牧人の告げたその問い掛け――そこに乗せられた思いが、大切に感じられたのだ。
他者に向けて、自己の弱さを問うことができるまでになった彼。
その少しの間は吟味する時間だった。牧人の言葉を受け止め、心の深部に快く根を張らせるための所要時間。
『僕は牧人のことを、駄目だなんて思ったことは一度もないよ』
故に、告げる。本心を。
『大丈夫だ、迷わなくても。僕は、ちゃんとわかってるから。一度くらい失敗して、立ち止まることだってあるさ』
明彦の、何の衒いも躊躇いもないその言葉に、牧人は逆に焦燥に駆られる。
「け、けど……っ、俺は……俺は弱くて――自分ひとりじゃ何もできなくて……」
『ああ、確かに牧人は弱いね』
「だから――っ!」
『けど、とても優しくて……、とても前向きだ』
「………………」
それは、いつの姿を指し示したものだろう?
牧人は追想する。それは今か、高校時代か、それとも――
『だから迷わないで大丈夫だ。牧人はただひたすら、ホントになりたい自分を探して、ホントに望む場所を見つけて、歩いていくだけでいいんだよ。
そうして仮にそれが間違っていたとしても、きっと僕たちが正してあげられる。だって、僕らは仲間、なんだろ』
「…………明彦、は――」
――なんで、お前はそんな……甘いのかな、俺に……?
価値を、勘違いしてしまいそうになる。
罪を、許してしまいそうになる。
『それに、今喋っていて思ったよ。牧人は一人でもちゃんと立って歩いてる。全然昔のままなんかじゃない。
強くなろうとがんばってる。より良い自分になろうと努力してる。その結果、驚くぐらい強くて優しく、そして立派な自分になれてる』
「…………そんなっ、こと……!」
――簡単に言うなよ……っ!
過度な期待をされても困ると思った。
何故なら、もう痛いというほど感じている。
……自分一人の力では立ち上がれない。だから前にも、進めない。
そんな弱い自分を痛感して、だからこそ共にいてくれた彼等が大切だと気付いたのに。
だというのに……、
『そういう牧人だから、僕も安心して任せられるんだ』
「…………そんな――――」
――そんな風に言われたら、もう断れねぇじゃん……。
例え自分に力がなくとも、その立場に見合わずとも、拒否することは逃げ出すこと。
それは、彼がもう二度としないと決めたことだ。

『だから、がんばれ。
……やれるさ、牧人なら』
「あ……ぁ……」
――どうして……お前は――いつも一番欲しい時に、その言葉をくれるんだろう?
歯を食い縛る。
――ダサいところも汚いところも、山ほど知ってるはずなのに……。
親友が向けてくれた信頼が、優しさが、久しぶりに感じる互い絆が、不相応に感じられつつも……何より心強い。
「…………」
顔を上げ、浮かびかけた涙を拭う。
ならば、それに応えるだけだ。
――それくらいしか、無力な俺にはできないんだから……!
もがくことに決めた。必死になって、拙く手足を動かそうと。
そうすることで何かが見えたら――、
――いつか、こいつの言葉に報えるかもしれない。
そう、思ったからだ。
「なぁ明彦……お前ってさ」
『うん?』
だから、最後にせめてひとつだけ。
「お前ってホント、昔っから……ズルいヤツだよなぁ」
牧人は誤魔化すように、そう言ってやった。
それは、牧人なりの彼への甘えだった。
――ありがとう明彦、後は俺一人でもやって行くさ。
そんな言葉は、恥ずかしくて口にできない。
けれど彼ならば、言葉にせずともそんな本心を汲み取ってくれるだろう、と。
当然、明彦はそれを察して素早く動く。
敢えてそのまま牧人に合わせ、おどけるように言うのだった。
『……なんだ、牧人にはバレてたのか』
そんな彼の言葉が可笑しくて、牧人は声に出して笑った。
その後二人は、薫や耕平と出会う前――まだ二人だった頃の思い出話もしてみた。
しかし、色々思い出そうとするも、上手く出てこない。
それらは断片的な記憶でしかなく、繋がらない。物語にはなりえないのだった。
『つまり僕たち二人は、それくらい昔からいたんだ』
「……そうだな」
二人の時間は長かった。
五人の時間は尊かった。
……それが解れば、充分だった。
「――ってことに、なったんだけどさ」
『ま、マジっすかー! いきなりすごいじゃないっすか!』
明彦との電話を終えて数分と経たないうちに、なつめから連絡があった。
牧人はそのまま同窓会の件をなつめに伝える。
彼女は当然であるとばかりに賛成の意を表したのだった。
「よかった。じゃあ芥川は参加してくれるんだな」
『当たり前っすよー! うは、楽しみー。マッキー先輩ともなんだかんだで高校卒業以来っすからねー』
「……そうだな」
なつめの参加に関しては聞かずとも解っていた部分ではあるが、それでも牧人は安堵を隠せなかった。
「それで、確認したいんだけどさ」
『はい? なんでしょ?』
「耕平と薫の連絡先って、変わってたりするかな? そしたら、教えて欲しいんだけど」
『えっ?』
なつめは喉に何かを詰まらせたような声を出した。
「ど、どうした?」
『……それって、マッキー先輩がみんなに声かけて回ってるってことなんすか?』
「ん、あぁ……そうだよ。発案は明彦だけど、連絡は俺が取ってる。で、ちょうどお前から電話が来たから――」
『ま、まさか、あのヘタレだったマッキー先輩が……そんなことまで……!』
「……おい、聞こえてるぞ馬鹿。電話なんだから」
『あー、いやいや。褒めてるんすよ! カオル先輩はともかく、ソーセキ先輩にはあんだけボコボコにされたのに、自分から声かけるなんて偉いなーって』
「じ、自分でじゃねぇよ。明彦にやれって言われたからやってるだけだ」
言いながら牧人は何故なつめが耕平とのことを知っているのか気になった。
――本人から聞いたりしたのかな?
『ぶっちゃけ大丈夫っすか? ソーセキ先輩にだったら、あたしからテキトーな理由言って連れて来てもいいっすけど……てゆうか、その方が流れ的にはアリなんじゃ――』
「いや、いいよ。やっぱ俺がやんないと意味ねぇ気がするし」
なつめの言葉が終わらないうちに牧人は言う。
「元はといえば、みんながバラバラになってんのだって最初は俺の所為なんだ。だから、元に戻すのも最初は俺じゃねぇとな」
『マッキー先輩……』
「……まぁ、偉そうなこと言うつもりなんてねぇけど。ケジメっつーかオトシマエっつーか、さ」
『…………』
「そんなわけだから、お前は何にも気にしないでいいよ。耕平は俺からの電話なんて出ないかもしれないけど、そこは黙って待つさ」
『ソーセキ先輩は――』
「ん?」
『結構キッツイこと言ったっぽいんですけど、あれって多分、スネてるだけっすから』
「……は?」
『マッキー先輩がしたことがどうこうっていうのより、単にみんなで遊べなくなったのがつまんなくてふてくされてるだけっぽいですよ。んで、そのまま意固地になっちゃって今更自分から切り出せない感じ』
「ちょ、お前、何言ってんだ……? ふてくされてる? 耕平が?」
それではまるで自分ではないかと牧人は思った。
牧人の中の棗耕平は、そのような些事で意地を張るような狭量な性質をしていない。
『マッキー先輩とかには知られないように必死に隠してるだけっすよー。だからきっと、マッキー先輩がオトナな対応すれば、アッサリ折れてくれますよ』
「そう、なのか……?」
どうにもその言葉を鵜呑みにはできない牧人だった。
『ま、なんにせよ楽しみにしてるっすー、同窓会』
「……あ、あぁ。なるべく早く連絡するよ」
『はーい!』
元気のいいなつめの返事。
集まる理由という当初の用は既に解決済みであるため、これで一応なつめと交わすべき会話は終了した。
『あ、あのー、マッキー先輩』
その旨を告げようとした時、なつめがおもむろに名前を呼んできた。
「どうかしたか?」
『え、えっと……上手く言えないんすけど』
「ん? うん」
『なんつーか、今よりチョッと立場変わったら、あたし先輩のこと思わず好きになっちゃってたかもです。らびーん』
「はぁっ――!?」
不意にそのような事を言われて、牧人は言葉を詰まらせる。
「好き……って、いきなりお前なに言ってんだよ……!?」
『いやー、なんでもないっすよ。ちょっとそういう風なことを言ってみたくなっただけっつーか、ね。えへ』
「えへじゃねぇよ。相変わらずふざけたこと言って――!」
口では反論するが、そうした言葉にとにかく弱い牧人だ。
なつめが何を思って突然そのようなことを言い出したのかは解らなかったが、既に顔面が熱くなり、鼓動と呼吸が加速していくのが自分でも感じられる。
『えはは、テレてるー!』
「テレてねぇよ!」
そのような感じで、芥川なつめとの通話は終了した。
なつめとの電話を終え、牧人は台所に行き水を飲んだ。
口の中が妙に乾いていて、自分が緊張状態にあったのだとわかる。
――芥川相手でもこんな調子でどうする。もうちょっと頑張れよ、俺……、
頬を叩いて気合を入れた。
本当に頑張らなければならないのはこれからなのだ。
「それじゃ――」
牧人は机に置かれた携帯電話を掴み、深呼吸をした。
「まず、耕平に電話するか」
そして決意するように開く。
再度の深呼吸。
――落ち着けよ……ビビッてたら駄目だぞ。
怯えた態度など見せれば、棗耕平からは更なる失望を買うだけだ。
――マッキー先輩がオトナな対応すれば、アッサリ折れてくれますよ。
なつめが言ったような楽観視は正直牧人にはできなかった。
耕平がそこまで簡単な反応を示すとはとても思えず、だがそうなると何を話せばいいのか、何を示せばいいのかまるで解らない。
「けど――」
――見せよう。今の自分を。
少なくともそう思うことはできた。
正直なところを話せば、伝わりはするはずだ。
今更許されなくてもいい。理解されなくてもいい。
自分はそれだけのことをしたのだから。
ただ、明確な意思だけは表明しよう。まずはそこからだ。
今からできることなどそう多くはないのだから――
一度決意すれば、実行に移すのは早かった。
牧人は電話帳から棗耕平の名を探し出し、受話器を耳に当てていた。
数回のコール。
その十秒にも満たない時間が嫌になるほど長い。
知らぬ間に番号が変わっていたのか。電波の悪い場所にでもいるのか。
……それとも棗耕平は、自分などと話す気はもうないのか。
繋がらない理由が次々と脳裏を巡る。
「耕平……」
思わず名前を呼んでしまう。
すると、それに応えるかのようにコールが止んだ。
少しの間があって、通話が開始される気配。
『………………』
しかし、電話に出たというのに相手側からは何も返答がなかった。
ただこちらを試すような沈黙が続いている。
彼の携帯電話にかけているとはいえ、こうなるとこれが本当に棗耕平であると判断する要素は何もない。
「………………」
だが、牧人は何となくそれが耕平本人であるように思えた。
そして彼が、久しぶりに連絡をよこした牧人に言うべき言葉を捜しているのだとしたら、と考え、
――だったら、なんか嬉しいな……。
そう思うと、勇気が湧いてきた。
「おい、電話出たのはそっちなんだから先になんか言えよ」
だから、気付けばそのようなことを言っていた。
そのような横柄な口調で話したのは久しぶりであることに気付く。
――構うもんか、相手が耕平なら……、強気にならない俺なんて、ウソだ。
そうした言葉が出るのは、ひとえに彼への信頼の証なのだから。
『……ぷっ、ぶはははは!』
故に、こうして棗耕平が笑い出したのを聞いて、牧人は思いが通じたと確信した。
『おい牧人。お前って相変わらず、オレに対してだけは強気なのな……』
呆れたような、それでいて余裕に満ちたその声。
……数年ぶりに言葉を交わす、棗耕平だった。
「なら、お前も昔みたいに、俺をいいように言いくるめて見せろよ」
そうと解れば、軽口は勝手に転がり出てくるのだった。
つい先程水を飲んだというのに既に口内は乾き、首筋には微かな発汗がある。
そんな適度な緊張が、牧人の意識を冴えさせていた――
二人は、高校を出てから何をしていたかを簡潔に語り合った。
明彦の時に比べて、明言化が少なかったのは互いが緊張していたためか、元より多くを語らない間柄であったからかは定かではない。
しかしその中で、久方振りでやや遠慮がちな空気も徐々に緩和されていった。
勘を取り戻してきた――というより、相手の空気を思い出してきたのだろう。
『さて……それじゃあ牧人、本題に入ろうや』
ひとしきり話が済んだところで、切り出したのは耕平の方からだった。
陽気な口調の中に潜む怜悧な気配に、牧人は思わず身を固くする。
『お前だって、わざわざオレの近況聞くために電話してきたワケじゃねえんだろ?』
「…………」
耕平のその口調に、牧人の中の何かが心地よい熱を帯びる。
……耕平は変わらず強い。
彼の語った近況の中には、それまでの彼の価値観を変化させる出来事がいくつもあるように聞こえた。
遠方での一人暮らしや、恋人との別離などがそれである。
『何か言いたいことがあるんじゃねえのか?』
だが牧人には、耕平の余裕が電話越しにも伝わってくるように感じられた。
仮にそれが、相手が自分程度だから見せられている虚勢なのだとしても、その在り方を維持し続けられている辺りに、牧人は自分以上の強さを耕平に感じ取るのだった。
――なら、俺はそこへぶつかるだけだ。
「あぁそうだ。耕平、実はさ……今度、同窓会をやるんだ、俺と明彦と、芥川と、あと薫も呼んでさ……俺たち五人で。だから――」
そう思ったから、
「――だからお前も、来てくれよ」
牧人は何も考えず自分が伝えるべきことを告げる。
そこにはいささかの誇張も見栄もなく、ありのままの自身がただそこにあった。
『同窓会ィ……こんな時期にか?』
「あぁ。お前は東京にいて、こっちまで来るの大変かもしれないけど、そこをなんとかならねぇかな?」
『なんとかって言うけどな、お前……』
「実はこれ、明彦の発案なんだ」
『何……明彦……?』
その名前に耕平が少しだけ妙な反応を示したが、牧人は気にしなかった。
「その中で明彦が言ってたんだ。俺たちはこれから大人になって、社会に出て行くけど、それでも強く生きていけるように、協力し合わないといけないって」
『………………』
「そうしていくのに、あの五人が一番最適だって明彦は言ってた。俺もそう思う、だからこうやって電話かけて回ってる」
『なるほどね。……あの野郎』
「え?」
『……いや、なんでもねえよ。話はよくわかったぜ』
「……どう?」
『ふーん…………』
しばらくの間、耕平は黙していた。
彼がその中で何を思考していたのか、牧人は知らない。
故にその静寂が恐かった。
「あのさ、耕平」
『ん? なんだ?』
「もし高校三年の時のことで、お前が俺のこと気に食わないってんなら――」
『あー、その話か。それだったらもういい、気にすんな』
不安に駆られて言っただけに、耕平のその発言に牧人は面食らった。
「気にすんな……って、え? だって、お前……」
『なんだぁ? 牧人はオレに言葉責めされるのがそんなに良かったのか?』
「ち、違ぇよ! ただ、お前がそんな風に言うのって、なんか……」
『変か?』
「まぁ……うん」
『そーだねェ……』
納得の行かない様子の牧人に対し、耕平の反応は淡白なものだった。
『ま、オレも色々考えるところがあってな。確かにお前のしでかしたことは許せねえけど、頭ごなしに否定するのもどうかと思っただけだ』
「耕平、それって……」
――マッキー先輩がオトナな対応すれば、アッサリ折れてくれますよ。
ふと、先程なつめに言われた言葉が蘇る。
『ま、馬鹿でマヌケで押しに弱いお前が、よーやくそんだけのこと言えるようになったんだ。なら、オレもこれ以上ゴチャつく気はねえよ』
「…………」
耕平も、耕平なりに思考し、悩んでいる。そのことが牧人には感じられた。
同時に今は彼の存在が、自分からものすごく近い位置にあるようにも。
『今度は、ダサイところ見せるんじゃねえぞ』
言葉に満ちた鼓舞するような気配。
そこには最早、侮蔑の情は微塵も感じられない。
「耕平……俺……、俺さ――」
そのことが――耕平がもう一度チャンスをくれたことが、牧人には何よりの救いだった。
だが、その感情を言い表すには牧人は不器用すぎた。
言葉は何も浮かんでこず、辛うじて救い上げたものも即座に零れてしまう。
そのまま何を言い返すべきか悩んでいると、観念したようなため息が受話器の向こうから聞こえてきた。
そして――、
『なんつーか、その……悪かったな』
「え……?」
その時、牧人は信じられない言葉を聞いた気がした。
――耕平が、俺に……謝ってる?
「耕平、今……お前――」
『で、同窓会だったな。いいぜ、行ってやるよ。他のメンバーの都合わかったら教えてくれ。そしたらそっち戻る』
「え、あ……その……」
『なにシドロモドってやがる牧人。何かいいことでもあったのか?』
「あ、いや……うん」
『……おいコラ、なに素直に頷いてんだよお前? オレの善意あるフォローが台無しじゃねえか』
「って、そんなことより、ホントに来てくれるんだな耕平!?」
『あーもう、なんかうるせえな今日のお前! 行くよ、行くって行ってんだろォ! ってかよ、実を言うと暇なんだよオレ。就職も決まってるし、やることもねえからまた実家帰ろうかとも思ってたんだ』
「そ、そっか……ありがとう」
『礼などいらん! 別にお前のためじゃねえ!』
「わかってる。俺じゃなくて、俺たちのため、だろ?」
『チッ、しばらく見ねえうちに、ますます恥ずかしいこと言うようになりやがって……』
電話の向こうで微かな笑い声。
これまで幾度となく見てきた、余裕のある姿がイメージされた。
『ふん、オレも来年からは社会人だ。お前にゃ先を越されたが、すぐに追い抜いてやるぜ』
「いや、どうやって追い抜くんだよ……?」
牧人がそう言って、二人は笑った。
その後、他愛のない会話をいくつか交わして、耕平との通話は終わった。
耕平が今になって自分にあまり厳しくなくなった理由が、牧人にはいまいちよくわからなかったが、追求するのも無粋な気がしたため黙っておいた。
その程度には、彼も空気を読めるようになったのだ。
『おい牧人、藤宮にはもう連絡したのか?』
電話を切る直前、耕平はいきなりそのようなことを尋ねてきた。
「いや、これからだけど……」
『そっか、なら――』
そして、最後にこう言い残して通話を終えた。
『オレが言うとイヤミみたいだけどよ、……なんつーか、その……がんばれ。オレと違って、お前はまだまだやり直せるレベルだと思うからな』
それは、普段快活な棗耕平らしからぬ、妙に静かな口調だったという。
耕平との通話を終えて、牧人はもう一度水を飲みに行った。
それだけでは落ち着かなかったので、洗面所に行き顔を洗った。
いっそシャワーでも浴びようかと思ったが、逆に気持ちが萎えてしまいそうだったのでやめた。
洗面所の鏡に映った自分を見つめ、牧人はため息をつく。
――あぁ、俺って何やってたんだろうなぁ……。
反省か自嘲か。先程からそのような思考が繰り返されている。
こうして高校時代の仲間たちと会話してみると、その年代が自分にとって途轍もない時間だったのだと牧人は実感させられた。
現在は、毎日が必死だ。
働くばかりの日々は、満ち足りているというよりは圧倒的な何かによって外側から否応なく満たされているという方が正しい。
恐らくは自分でなくとも、同じ境地に立たされれば今の自分と同じ感覚を抱くのだろうと牧人は思う。
だが、高校時代の牧人のいた場所は、牧人でなければ成り立たなかった。
葦原牧人がいなければ、或いは別の誰かだったら、あの五人の輪は全くの別物だ。
牧人を含まないパラレルの輪が牧人の属したあの輪より良いか悪いかは解らない。
だが、異なるものである以上、彼が当時感じていた空気と全く同じものは生じ得なかったはずだ。
故に、あの場に立つのは牧人でなければならなかった。それは薫も耕平も同様。誰か一人欠けても代わっても、“あの輪”ではない。
五人の中において葦原牧人という少年には、ただそこに存在しているだけで揺るぎ無い価値があり、誰もが暗黙のうちにそれを認めていた。
…………そんな空気。
――奇跡的だ。
そう思う。自意識過剰な思い込みかもしれないが、仮に高校時代の彼等にそれを提案したとしても、恐らく誰も否定することはないだろう。
それほどまでに、あの五人の輪は調和していたのだから。
“奇跡”だったのだ。
冷静に見れば人と人との結びつきには、往々にしてそのような部分がある。
人は無数の奇跡を経て、無意識のまま通過している。
――あの時、ああしてればよかったのかな……。
言葉にすると酷く陳腐な色を帯びる思考だったが、その感情の表現をそれ以外に牧人は知らなかった。
知らず満たされていた状況。無条件で提示されていた自分の価値。
それを独力で得ることがどれほど困難か、孤独となった牧人は悟る。
無くしてから気付く宝物の価値、とはまた使い古された言い回しかも知れないが、牧人は今まさにそれを思い知っている。
…………過去の愚行を嘆く。後悔に近い。
居間に戻ってくる。まだはらはらしている。
机の上に煙草を見つけて、吸おうと思ってやっぱりやめた。
「ああもぅ……」
牧人はベッドに転がった。
身悶えするように、自身の体を押さえ込む。
手足は震え、動悸も呼吸も今までよりずっと激しくなっている。
ふと時計を見ると、耕平と話し終えてからかなりの時間が経過していることに気付いた。
その間ずっと思考していたのだ。
武田明彦が立案した突然の同窓会。彼等五人の同窓会。
その件を芥川なつめと棗耕平に無事伝え終えた牧人は、最後の一人――藤宮薫に電話をかけようとしている。
牧人は体を起こし、ベッドに腰掛けた。
頭をかきむしりながら、携帯電話を掴み、開く。
……その手が震えていた。
――くそっ……なんなんだよ俺……!?
先程からこのような調子だった。
薫に電話をかける段階になってからというもの、落ち着かなくて仕方ない。
異様なまでの緊張感。耕平に電話かけた時以上だ。
今になってそれを感じるようになったのは、耕平に電話をかける時にはそのことで頭がいっぱいだったからだろう。
――馬鹿野郎……逃げるな、俺がやらないと……薫にも……!
そう思うが、体は頼りなく震え、頭脳は真っ白なままだ。
彼女に対してどのような態度でどのようなことを言えば良いか、何も考えられない。
……数年を経てこの様では、薫はどのように思うだろうか――?
その思考でハッとする。
「……あぁ、そうだよ。馬鹿だな……俺」
失笑が漏れた。
同時に、硬直していた体も少しだけ動き出してくる。
唾を飲み込む。乾いた喉に通過する液体をもって、決意とした。
――なに、カッコつけようとしてんだよ……俺……?
数秒前の自分を嘲笑う。
それが駄目なのだ、ということをまた忘れそうになる自分を蔑む。
――いいんだよ、ダサくたって……、気取ってない、普通の俺じゃなきゃ意味ねぇだろ……
まして相手は、あの藤宮薫なのだから。
自分が誰よりも素直にありたかった相手なのだから。
「……やろ」
実行に移す。そのための言葉は短くていい。
相変わらず手は震えている。心拍も依然として信じられないほどに速い。
何を言うべきかも思い付かない。思い付いても整理できなそうだ。
――けど、まぁいいや……。
どこか諦めたようなその思考は別に投げやりなわけではない。
その方が自然な自分がそこにあると思っただけだ。
急ごしらえの虚飾に満ちた自分など無意味だ、と。
――それに……、
これで何も言えないようなら自分はその程度なのだと思ったのだ。
電話帳から薫の名を検索し、送信を開始する。
その動作はよどみなく、迷いは僅かばかり。
――昔どうだったかは関係ない……いや、関係なくはないけど、今はいい。
コールが長い。
薫は電話に出てくれないかもしれない。
それなら牧人は待つだけだった。
――今はただ、自分がするべきことを……動くべき機会を見逃さないように――――
その感覚を持っていれば、いつまでも待つことができそうだった。
先程まで及び腰だった自分が信じられない。心は帯電したように、熱を持ち続けていた。
――薫と話す。ありのままの俺を伝える。そして――
…………奇跡を取り戻そう。
今はただ、それだけを胸に宿して。
『もし……もし……?』
コールが途切れ、弱々しく聞こえてきたその声。
それを聞いた瞬間、牧人は自室にまばゆいばかりの光が差し込む様を幻視した。
深く長い暗闇を潜り抜け、今ようやく青天の下に身を晒したような心地になった。
だから、言った――、
「久しぶり……、薫」
かつて誰よりも大切だった、その少女の名を。
『マキ……くん――!』
感極まったような彼女の声。
その声が未だその名を口にしてくれることに、牧人はたまらない愛しさを覚えるのだった。
牧人は進み始める。再び身を置いた光の中を。
高校時代の仲間たち。
その全員と連絡を取り、同窓会を行う旨を伝えた。
皆の予定を照らし合わせると、集合は割に近い日取りに決まった。
そのことを再度全員に連絡して、同窓会は無事に開かれる運びとなった。
「…………」
やるべきことを全て終えて、牧人はベッドに転がった。
電話を切ってからも、妙な興奮が体に残留したままだった。
未だ動悸が早く、顔が熱い。
「……はぁ」
ため息が漏れた。
喘ぐように吐き出されたそれは火照ったようで、機械の排熱を思わせる。
緊張とはまた違う、奇妙な高揚感に牧人は包まれていた。
「あー……」
今度は呻いた。意識を外に向けるように。
だが、そのようなことをしても、脳裏にこびり付いたイメージは消えない。
「情けねぇよなぁ……俺……」
呟く。泣き笑いのような表情にて。
「諦め、切れねぇんだもんなぁ……」
牧人は現実を認めることができずにいた。
故に先程から、妙に無気力に転がるばかりだった。
そんな自分を都合が良いと感じ、情けなく思う。
悲しい性などと陳腐なことを言うのもおこがましい。
しかし、どうしようもなかった、
「駄目だ……俺、やっぱ……」
顔を覆った。
「――――薫がいないと、駄目みてぇだ……」
一人寝転んで、その事実を口にした。
気付いたのはつい先程、同窓会の日程を伝えるため、藤宮薫に二度目の電話をかけた時だ。
久々に彼女の声を聞いて、いくつかの言葉を交わして、牧人は思い知ったのだった。
彼女のことを想うと、彼女がそこにいないことにたまらなく違和感を覚えるのだ。
――そうだよ……俺は、いつだって薫が傍にいてくれないと……
「駄目なんだな……もう、滅茶苦茶だ」
この不安に比べれば、さっきの電話をかける前に感じていた焦りなど塵のようだった。
一度意識してしまうと、もう落ち着かない。
まるで自分が自分でないかのようで気持ちが悪かった。
体を起こし、膝を抱えた。
背部の壁に体を預け、差し込む午後の日差しの中に自分を感じ取ろうとした。
狭い自分の部屋。机とベッドと、その他いくつかの家具でもう満杯だ。
目に付いたのは、壁際に置かれた一台のテレビだ。
実際はあまり見ることはないが、一人暮らしを始めるにあたり、中古で安かった物を見つけて購入したものだ。
今、そのブラウン管には当然何も映し出されていない。
「くそ……、結局、こんな風かよ……」
牧人は何故か自分がそのテレビであるように思えた。
テレビは見る者が――見てくれる人がいなければ、映らない。
映る意味がないからだ。
それは黒く沈黙するだけで、壊れているのと変わりない。
そんな見る者のいないテレビと、今の自分が重なって、
「――――」
牧人は性急に考えを決めた。
テレビから視線を外し、立ち上がる。
「もう一回……付き合おう、薫と」
無人の部屋で静かに告げる。
小さな声、されど世界中に宣言するように。
立ち上がると、机の脇に立てかけられたエレキギターが目に入る。
思えば、最初に演奏を聞かせた時点から、牧人の行動の中心には常に彼女の姿があった。
――ずっとベタ惚れだったんだろうな、俺って……。
自分をここまで維持していたのは藤宮薫だ。
彼女が隣にいて自分を見ていてくれたから、牧人は自身のあらゆる行動を肯定することができたのだ。
……彼女がいない違和感の正体はそれに違いないのだ。
それを思うと、過去の自分が明るみに出る。
自分の馬鹿さ加減に絶望し、薫と別れた自分。
薫がいなければ成り立たないのに、それを自ら切り捨てる……その馬鹿さ加減に自ら気付く。
「なーにカッコつけてんだよ俺、カッコ悪ィ……」
自嘲気味に口元を緩める牧人。
その表情は、今まで浮かべてきたどんな顔より晴れやかでいるような気がした。
思ったのだ。自分は変に気取っているよりも、そうして不恰好に苦笑している様が似合うのではないかと。
「………………」
牧人は決然と立ち上がり、押入れを開く。
積まれたいくつものダンボール。
それを次々と引きずり出し、中身を検めていく。
探すものがあった。
――あったはずだ、まだどこかに……。
捨てた記憶はない。捨てるはずもない。
表向きでは拒絶していても、彼の中核がそれを許すはずがないからだ。
「――あった!」
独立してから封印され続けていた押入れの最深――そこには、自らの存在を主張するように……白い紙袋が置かれていた。
身を乗り出して、それを引き寄せる。もう離すまいと強く掴む。
長年押入れにしまいこまれていたため、かつては高級感すら漂わせていた白い紙袋はすっかり埃を被っていた。
急いで台所から布巾を取ってきて、入念に拭き取った。
――袋はこんな有様だけど、中身は無事かな……?
これで虫にでも食われていたとしたら、本当に絶望的だ。
「……っ!」
思い切って袋を開き、中身を取り出す。
手のひらに柔らかな感触があって、袋と同じように白く美しいものが引き出された。
両手でそれを広げ、全体を確認する。
「……よかった」
どこにも損傷がないことに牧人はまず安堵した。
「渡すんだ、コレを。……それで、言うんだ」
葦原牧人は、そのように決意したのだった。
これを渡すことが彼女との、再出発の契機になれば――――
その日の夜、牧人はコンビニに赴き、煙草ではなくキシリトールガムを買った。
もう煙草はやめることにした。
理由はなんとなく仲間たち――特に彼女が煙を好まない気がしたからだ。
「…………」
そして、余っていた分をどう処分するかを考えて、牧人は妙な考えに取り付かれた。
急に、馬鹿なことをやってみたくなったのだ。
自室や背広のポケットを探ると、数箱の煙草が見つかった。
牧人はそれらを持ってベランダに出ると、残らず箱を開封し、何十本もの未着火の煙草を灰皿にしている缶に放り込んだ。
「今から、俺のタバコ卒業式を始めます」
火のついたライターを掲げて、牧人はそう宣言した。
無人のベランダで大真面目な顔をして灯火をかざすその姿は……何というかシュール過ぎた。
そして牧人はガムを噛みながら火をつけた。
火は一本から別の一本へ燃え移り、たちまち缶の中で炎となった。
ごうごうと燃える煙草の山、そこからは当然のように甚大な量の煙が立ち上る。
一本なら微かな副流煙も、束になると煙突を思わせる巨大さだった。
「…………」
夜空に立ち上っていく煙を見上げながら、牧人はぼんやりと思考に耽る。
……それはどこか火葬に似た光景だった。
或いは牧人のこの妙な行動は、過去の自分を完璧に葬り去るためのものだったのかもしれない。
灰色の年代を象徴する物品を焼却することが、越境を暗示していたのだろうか。
玉虫色を経て、灰色に至り、そして進むのだ。
……彼自身の新たな色へ。
後日。
周辺住民と大家から、大量の煙が発生した件に関しての苦情が牧人の元に殺到した。
牧人は近隣の一軒一軒を全て、丁重に謝罪して回った。
――目ぇ付けられたっぽいなぁ……、次なんかやったら立ち退きか。
そんな危機感を覚えながらも、心は妙にうきうきしている牧人だった。
煙が立ち上っていった夜空の広さが、忘れられなかったからだ。
……そして、その日が来た。
「………………」
時刻は午前五時。
期待と不安で眠れなかったこの日の牧人は、結局徹夜してしまっていた。
――遠足前日のガキかっつーの俺は……、
徐々に白んできた東の空を見ながら、そんなことを思う自分が窓に映る。
その姿は思いのほか大人びていて、なんだか可笑しかった。
……そして不思議と、悪い気分ではなかった。
牧人は携帯電話を見ている。窓を開けて、早朝の空気を肌で感じながら。
受信されたメールは大学時代の友人――浅野からのものだ。
件名:(無題)
内容:
「今日どっか遊びいこーぜー」
つい先程――真夜中に送られてきたそのメールの文面はたったそれだけだった。
自由奔放を絵に描いたような浅野からのメールは大体がそのような簡潔すぎる内容だ。
牧人は浅野にシフトを教えているため、彼はいつ牧人が休日であるかを大体把握している。
従ってこの日も、牧人が休みであることを想定しての誘いであった。
――しっかし、それを前日の……しかも真夜中に送ってくるってのもどうなんだよ……?
思ったが、その手の指摘は挙げていくときりがないのでやらない。
牧人はメールを打つ。
浅野とどこかへ出かけるのは今の牧人にとって楽しみの一つではあるが、今回は遠慮しなければならなかった。
「……今日は、あいつらと会うんだからな」
事実を確認するようにひとりごちた。
明彦に促されるまま奔走したというのに、牧人は未だにどこか現状を信じられずにいたからだ。
「とりあえず……浅野にメールするか」
――今日は人と会う用事があるから、悪いけどパス。
そのような内容のメールを送った。
数分と経たず、返信が来る。
件名:Re: Re:
内容:
「人と会うって、アッシーって休みに会うようなトモダチとかいたっけ?」
「……おい…………」
そのようなメールを見て、牧人は閉口せざるを得ない。
確かに高校時代の友人四人のことを浅野に話したことはなかったが。
――けど……そんな心底不思議そうに聞かなくたっていいだろ……。
浅野に自分は友達のいない男だと思われているらしかった。
あながち否定できない所もあるため、何とも複雑な気分である。
「畜生、なら教えてやるか……!」
その感情が、徹夜の牧人に火をつけた。
浅野にわからせてやる必要があった。自分が、どれだけ素晴らしい友達に囲まれているかを。
「……って、何――やってんだ俺……?」
そして冷静になったのは、メールを送信し終えてからだった。
気が付けば日はとっくに昇っており、送信したメールは驚くほど長大なものになっていた。
「うわ……何書いてんだ俺……」
冷静になってその文面を読み返してみると、その内容の青臭さに赤面してしまう。
明彦について、耕平について、なつめについて、薫について。
メールでは四人のことがひたすら延々と語られている。
それぞれ、彼等がどのような人物で、自分にとってどれほど大切なのかが赤裸々に書かれていた。
「うー…………」
我ながら目を逸らしたくなる、言い知れぬ恥ずかしさを感じさせる文章……言ってみれば友情惚気メールだった。
「けど……、別に……いいか」
だが牧人は気にしないことにした。
諦めたようにため息をついて、電池が一本減った携帯電話を閉じる。
「知られて困るものでもないしな」
それどころか、今の牧人は誇ることさえできる。
聞かされる浅野はいい迷惑だったかもしれないが、それは紛れもない牧人の本心であるのだから。
知っておいてもらうのも悪くない。むしろ、知っていて欲しい。
「――そうだな、俺は……あいつらのことが好きだ、本当に」
改めてそのことを口にした。
そんな彼等との集合時間は夕方。
あと半日以上も時間がある。
「…………」
だが、会って何を喋るかを考えているだけでその時間を過ごせそうだと牧人は思った。
ベッドの脇に置かれた白い紙袋。
じっとしていると高鳴っていく胸の鼓動が、今は何とも心地よい。
窓の外に見える桜。
その枝に咲いていた花は、今はもうほとんどが散ってしまっている。
「…………」
見上げた空にあるのは青色。
……唐突に牧人は、花見がしてみたくなった。
大切な友人たちと一緒に。
…………そして集合時間になった。
――なんだか落ち着かなくて、早く来ちゃったな。
だから、すぐには集合場所には行かないで、近くでちょっと休憩していよう。

「……いちばんのりー、っすかね?」
集合場所に最初に現れたのは、芥川なつめだった。
高校時代よりやや大人びた感のある私服を纏いながらも、見た限りでは以前と大して変わりない様子だ。逆にそれが安心できる。
目印となる曲がり角に彼女は舞い込んだ。
飛び乗るようにして自動車よけのポールに腰掛け、携帯電話の時計を見た。
集合時間まで、あと一時間以上もある。
「……ちょい、早いか」
常識的、というにも早過ぎた。
彼女も落ち着かなかったのかもしれない。
そのまま大人しく待つことにした。
手鏡など取り出し、身だしなみをチェックし始める。
「……むー、今さら枝毛発見」
どうにか隠そうと努力してみる。
なつめにとって、あの五人は身だしなみに気を使うほど色気ある集団でもない。
だが、顔を合わせるのは数年ぶりなのだ。
それが原因なのかどうなのか、何とも言えない緊張が、彼女の中にもあった。
普段は気にならない自分の身なりを、今日ばかりは妙に意識してしまう。
「いいや、切っちゃえ」
従ってそれを誤魔化すかのように、服飾にも少なからず気合が入ろうというものだった。

「路上で化粧直しなんかしてんなチビ野郎」
「いった!」
パシン、と音がして後頭部がはたかれる。
危うく落としそうになったハサミをあたふたと受け止めながら、なつめはポールから下りる。
そして素早く身を翻し、フェンシングのようにハサミを構える。
「挨拶もなしにそんな乱暴するのあなたは……どー見ても棗ソーセキ先輩!」
「……なんだその説明クサイ台詞は」
呆れたように息を吐くのは棗耕平。
……彼もまた、集合時間の大分前にそこに現れたのだった。
「ってかあぶなー! ハサミ持ってる時にボーリョクはよくないっすよ!」
「ほう、それ以外の時は別に構わないと言っているように聞こえたな」
「願い下げー!」
「あだーっ!」
なつめは耕平の下あごをはたき、耕平が割と洒落にならない声で呻いた。
それが原因でしばらく無益な口論になる。
「ふっ……相変わらずシケた町だぜここは」
ひとしきり罵声を浴びせ合った後、耕平が殴られたおとがいをさすりつつ呟いた。
「うっわ、ここぞとばかりにシティー発言。 “なじめない〜”とかって前に泣いてたくせに」
「泣いてない。……あとお前、それ他のヤツの前で言ったらナツメツイスターな」
「ダブルブンゴーには勝てないっすよ」
「……その奥義も、最早使用期限の秒読みに入ったな」
「結婚すると使えなくなる必殺技って、なんとなくやらしーですね」
他人が聞いたら眉根を寄せそうな会話を経て、二人は破顔した。
唐突な笑みは、安堵に満たされている。
……両者とも、ここ数年で様々な経験をし、その度に自身の有り様を探してきた。
自己が変質していく不安を覚えていたのだ。
「ソーセキ先輩は、相変わらずチャラチャラしてますねー。なんかギャルっぽー」
「うるさいわ。ギャルっぽ言うな。トーキョーじゃこんなん地味な方だぜ」
しかし、顔を合わせれば自然と出てくるかつての交わした言葉たちに、二人は途方もない安心感を得るのだった。
自分たちが、根本的にはあの時のままなのだと。
「そういうお前は、少し髪が伸びたな」
「へ? そっすか?」
「あぁ、前は束ねるほどの長さも無かっただろ。それ解いたら、肩まで届くんじゃないか?」
確かに今日のなつめは髪をアップに束ねていた。
俗に言う、お団子ヘアという奴だろうか。
「あぁ……そんなに、短かったですっけ、あたし」
それに対して、なつめはほんの少しだけ動揺したように呟いた。
まるで、当てが外れたとでも言うように。
「当時の長さにあわせて切ってきたつもりなんすけどねぇ……えはは、自分の髪型なんて、結構覚えてないもんすね」
「そっか」
誤魔化すように笑うなつめに対し、ぽつりとそれだけを返す耕平。
「ついでにネタ晴らししちゃうと、あたし……傷心のたびに髪の毛切ってるんすよ、実は」
「は?」
「だから、多分当時の私、微妙に髪の毛伸びたり短くなってたりしてたと思うんですけど」
「そう、だったか……?」
「はい。ま、細かく覚えてませんけど」
ここに来て、なつめは少しだけ恥ずかしげにそっぽを向いた。
「ジンクスなんですよ」
「ジンクス?」
「自分で居続けるために、髪の毛を伸ばすんです。で、今の自分をやめたくなったら、髪を切るんです」
「そんなことしてたのか」
「でへへ。ロマンチックっしょ?」
彼女がこの場でこんな発言をする意図が、耕平には解ったような気がした。
解ったような気がしたが、やはりそれだけだった。
「その割には、ロングのお前を見たことがないぜ?」
誤魔化すように一笑する。
「気が短いんすよ」
彼女も、それに釣られて苦笑した。
そこで会話の間が途切れた。しばしの沈黙。
――ジンクスなんですよ。
初耳だった。
そして本能的に、もう二度と同じ言葉は聴けないのだと察した。
そんな、貴重だったかもしれない会話の腰を自分から折ってしまったことを気にしてか、耕平は話題を探すように彼女の体を観察する。
「ん?」
そうしてなつめの姿を視界に納めながら、耕平はふと違和感を覚えた。
どうも、焦点が合わないような感覚がする。彼女の姿を見るのが久しぶりだからだろうか。
「……むぅ?」
眼鏡のズレを直しつつ、なつめの頭部辺りを凝視する耕平。
「な、なんすかソーセキ先輩……さっきから、そんな見つめられたら、あたし濡れますってばー!」
「相変わらず下品だなお前。ゲビ子って呼ぶぞ」
「またヘンなあだ名増やすしー! やめてくださいってのにー!」
両手を挙げて反論するなつめの姿。
「あー、そうか」
「はい?」
それを見て、違和感の正体に気付く。
「おいゴミ子。お前――」
「ひゃい!?」
目の前の少女の頭を鷲掴みにする。
かなりの身長差があるからこそできることだが、それでもやはり以前ほど容易くはない。
……それは彼女の頭部の位置が、以前より少しだけ高くなっているからだ。
「やっぱり、高校の頃からなんも変わってねーな!」
「ぎょわー!」
頭を揺すられて、なつめは悲鳴を上げた。
自らを捕らえる耕平の手をぽかぽか殴り、ようやく開放される。
「いきなりなにすんですかー! うぅー、お団子が……」
なつめは、頭を掴まれた事で崩れてしまった髪を直そうと奮闘する。
「いや、相変わらずチビだなーと思って」
「ふふーん」
不意にそのように鼻を鳴らす芥川なつめ。
「実はこれでも……高校の時より4センチも背伸びたんすよ!」
得意げに胸を張る。ちなみに肉付きは相変わらず悪い。
「ほほー……」
言うだけあって、なつめの身長は高校の時より確かに高い。
……だが耕平は敢えて気付かない振りをした。
「ま、オレサマに比べればお前など変わらず幼稚園児のようなものだ」
本当は気付いていた。遠目から彼女を見た時から以前と異なる感覚があったのだ。
それは成長のようにも見えたし、単純な変化にも見えた。
だが、敢えてそのように言った。
別に耕平の中に、芥川なつめの変遷に好悪の情があったわけではない。
そうした方が、単に過去と現在の距離を、より近いものにできるような気がしたからだ。
「ふんだ! いつかセクシーナイスボデーになってから後悔しても遅いんすからね!」
開き直ったのか、なつめは既に髪の毛のお団子を解いている。
「平成ノストラダムスのオレサマが予言してやるが、お前は27歳になってもロリ体型のままだ」
「恐怖の大王ばりの美巨乳になってますー! ぼいんぼいーん!」
そのように反論するなつめも、もしかしたら同じことを思ったのではないだろうか。
見ている限りでは、そう思う。
軽くウェーブした髪は、やはり肩に触る程の長さでとどまっていた。

「……や、やっぱり、耕平君となっちゃんだ」
「ん?」
「あー!」
そんな二人の言い合いを制したのは、角を曲がってきた薫だった。
その姿を認識したなつめが目を輝かせ、耕平が不適に笑う。
「カオル先輩! 超おひさですー!」
「久しぶりだな藤宮」
「う、うん……二人とも、全然変わってないね」
やや緊張気味に微笑む薫も、昔より多少大人びている。
髪型が以前と異なっているほか、視線の高い耕平には彼女の背も少しだけ伸びていることが解ったが、どちらも敢えて口に出さなかった。
「うわーん! カオル先輩会いたかったっすー!」
「え、なっちゃ――きゃあ!」
なつめが薫に抱きつき、そのまま陶酔するような表情になった。
「むきゅー、相変わらずやわっこいっすーカオル先輩……、愛してますー」
「もぉ……変わらないなぁ、ホントに……」
呆れながらも、なつめから加えられる力は薫には心地良かった。
胸辺りに位置する頭を撫でる。彼女の瑞々しい頭髪の感触が懐かしい。
「うきゅー」
なつめ、再度忘我。
「二人って、相変わらず声おっきいね……クリーニング屋さんの前歩いてる頃から声、聞こえてたよ?」
「えはは、ヘンなこと言ってませんでしたかね?」
薫に引っ付いたまま、なつめが首をかしげた。
「大丈夫だと思うけど……気をつけないとダメだよ」
「は〜い」
諭すような薫の言葉に、なつめは満足げに目を細めた。
そうしてじゃれ合っている様は仲の良い姉妹のようだった。
「藤宮は相変わらず国宝級の普通少女っぷりだな」
そんな薫の態度を見ていたら、また耕平は思ったまま口に出している。
「もぉ、それってバカにしてるの、耕平くん」
「さてな。オレとしちゃベタ褒めなつもりなんだが」
「相変わらずイジワルなんだから」
そう言って息をつく薫の表情が不意に和らぐ。
「……なんか、安心した。二人とも全然変わってなくて」
薫は自分でも驚いていた。抱きついてきたなつめへの対応が、あまりに自然に行えたことに。
「さっきから変わってないって単語が大流行っすね。なんかそれはそれで成長してないみたいでビミョーな気分っす」
「ち、違うの……わたし、ちょっと不安だったから」
「不安って?」
「わたしたち、高校を卒業する辺りからずっと会ってなかったでしょ? だから、こうやって会うことになっても今までどおりでいられるのかな、って」
「…………」
「…………」
その不安は、尋ねた耕平も抱きついているなつめも同じくするところだった。
だが、それが杞憂に過ぎなかったことも、最早共通の認識である。
「……そりゃ気にしすぎってヤツだぜ藤宮。牧人はともかく、オレとお前は別に仲悪くなってたワケでもねえだろう?」
「それはそうだけど……って、え? 耕平くんって、マキくんとケンカなんかしてたの?」
「ありゃ? もしかしてカオル先輩、そのこと知らないんすか?」
「う、うん……わたしはマキくんと仲悪くなっちゃったけど――もしかして、それだけが原因じゃないの?」
「……おいゴミ子、近く寄れ」
「……なんすか?」
二人は薫に背を向けて顔寄せ合う。
「もしかしてオレ、地雷ったか?」
「不覚っすねーソーセキ先輩。マッキー先輩に貸し一つっすよ」
「あちゃあ……」
耕平は天を仰ぎながら目頭を押さえた。
「まー、それはさておき……」
振り返る。
「藤宮はオレらと別に仲悪かったわけじゃねえんだから、気にすることもないぜ」
「そうっすよー」
「うん……でも、やっぱり……ね」
どこか、はにかむような表情。
「……会わないと、つながりって薄れていっちゃいそうだから」
「むー」
「……まあ、それはな」
向かい合って三人。誰もが神妙な面持ちだった。
「それはさておき、マッキー先輩はソーセキ先輩とのケンカの話、カオル先輩に知られたら怒るんじゃないっすか?」
「なんでそんなこと――って言えないのが牧人だよなあ、くそー……」
耕平はうなだれつつ、ポケットの財布を叩く。
「藤宮……ワンドリンクおごるから今の話忘れてくんない?」
「うわ、ワンドリンクってセコ……」
「べ、別に気にしないでもいいよ。マキくんに喋ったりしないから……」
苦笑する薫に、耕平は合掌した。
「すまなんだ。オレとしたことが、なんたる空気読まない発言……まるで誰かさんのようだぜ」
「――誰みたいだって?」
不意に低い声が響き、三人は打たれたように硬直した。
声のする方へ向き直る。
するとそこには――、

「……久しぶり、みんな」
白い紙袋をぶら下げた、葦原牧人が立っていた。
「…………」
「…………」
「…………」
迎える三人は、呆気に取られていた。
なぜなら彼等の記憶には、仏頂面の牧人が強く焼きついているからである。
彼がこのような優しげな目をする時は、ほんの一時に限られていると認識していたのだ。
「な、なんだよみんな……俺、なんかヘンか?」
だが、今の牧人は驚くほど棘がない。
不自然とさえ思える程に柔和な表情だが、照れ臭そうな仕草は昔のままの辺りが何とも言えない雰囲気である。
「ヘンだ」
「ヘンっすね」
「…………」
耕平となつめが即答し、薫だけは良心の力で沈黙を貫いていた。
「牧人がこっちまっすぐ見て喋ってる」
「ホントっす。それに“久しぶり”とか言ってるし。前はそんなこと絶対言わなかったのに」
「え? ウソだろ、俺そんな根暗なヤツじゃねぇよ」
「……マジで? 自覚ナシっすか先輩」
「……言ってやるななつめ、本人にとっちゃサッサと忘れたい過去なんだろうぜ」
「お前らなぁ……いい加減、内緒話は聞こえないようにするってことを覚えろよ……」
牧人が以前のように吠える事を想定していた耕平となつめは、また奇妙な顔をしたのだった。
「それにしても……」
一区切りついたところで、牧人が腕時計を見る。
「ったく、みんな考えることは同じかよ……、集合時間までまだ三十分近くあるぞ」
「なんだかんだで、やっぱみんなビビリってことっすかねー」
「全くだ。ヘタレな牧人はさて置いてもな」
「うるせぇな、悪かったよヘタレで」
「…………」
「…………」
「だからさ、なんで黙るんだよお前ら?」
二人は顔を見合わせて空を見た。
牧人が素直に肯定するなど雨でも降るのではないだろうか、と。
「……なんだか、マキくん雰囲気変わったね」
「……そう、か?」
「う、うん……」
薫のそのようなフォローに牧人は少しだけ落ち着かない気分になる。
彼女に対してだけは、やはりそのまま以前と変わらずに、というのは難しいようだった。
「これで残りは明彦だけか……、遅いな」
「だから、俺らが早く来すぎなんだって……」
「……このオレサマにツッコミなんて十年早いぜ、葦原さんよ」
「チッ、変わらねぇなぁ耕平は……」
「うわー、オトナな対応のマッキー先輩って、なんか妙な感じっすー!」
なつめが身震いした。茶化しているのではなく、本当に奇異に感じているようだった。
そのような反応ばかりの二人に、牧人の方も調子が狂う。
「……とりあえず、早く来いってメールしてみるか」
「そうだね」
「………………」
武田明彦は葦原牧人からメールを受け、急ぎ足で集合場所へ向かった。
「お、来たな……おい明彦――って、明彦かアレ!?」
牧人がメールを送って数分後、突如耕平が頓狂な声を上げる。
それにつられて他の三人もそちらを向く。
「え、どこだよ?」
「あっ、もしかして――」
「わ、わわわ……! 明彦先輩っすよ!!」
視線を向ければ、遠方からこちらへ駆けて来る人物が目に入る。
確かにそれは、皆の記憶にある武田明彦の姿と適合する。
……部分的に。
「……ほっ、……ほっ」
軽やかな小走りを終えて合流したのは確かに武田明彦。
「みんな、久しぶり!」
変わらぬにこやかな微笑を浮かべて、皆に言葉を投げかける。
大したもので息一つ乱れていない。
だが、それ以前に皆を驚かせたのは――、
「お前……ホントに明彦……か?」
「何言ってるんだよ牧人。忘れちゃったのかい?」
「いや、なんつーか……」
牧人が言葉を詰まらせるが、それは他の三名も同様だった。
「お前……ずいぶん、痩せたな……」
「そうかな?」
首を傾げる明彦だったが、牧人以外の三人はしきりに頷いた。
確かに、高校時代と比べて明彦は目に見えてスリムになっていた。
だが本人は言われるまでそのことに気付いていなかった。
何故なら現在の彼の周囲には誰も高校時代の体型を知るものがいなかったからである。
……指摘してくれる人は、いなかったのだ。
「す、すげーダイエットしちゃいましたね明彦先輩……」
「ホント……元々背が高いから、余計スマートに見えるよ……」
肥満に対して並々ならぬ恐怖を抱く女性陣二人は、明彦の激変に動揺を隠せない様子だった。
「その体型だと、なんか異様にサバイバルな感じがするな」
「どういう意味?」
「いや、なんつーか軍人みてえよ今のお前? 今までは壁キャラだったが今じゃスピードタイプだ、んで牧人より全然強そうだ」
「またその例えかよ……お前好きだよなそういうの」
「あはは、そりゃ言いえて妙だね。そうか、僕がスピードタイプか……」
明彦は耕平の言葉を噛み締めるように復唱してから、
「安心したよ。みんな、あの頃とおんなじだ」
慈しむように笑んだのであった。
……五人同士の相互理解は、それで既に充分と言えたように見えた。
「お店に予約した時間まで少しあるね、しばらく話をしようよ」
「そうだな」
「さんせーっす!」
そして誰からとなく、昔話に花を咲かせる一同。
五人の輪。懐かしい空気。
「…………」
その中で、牧人はふと少し前に見た夢のことを思い出した。
薫と共にいて、何もかも成功している幸福なイフの未来。
「そうだ、やっぱり――」
痛感した。
――あの夢の中は幸せだったけど、やっぱこうやって揃ってなくちゃ、御免だぜ……。
そのことを、実際に再びその中に身を置いたことで、強く強く――、
「どうした牧人? ニヤニヤして」
「いや……なんつーかさ……」
……だから余裕ある気持ちになれていたのだろう。
「俺、お前らがいて……ホントによかったなって、思ってさ」
――――そんな言葉が牧人の口から出るなど、誰が予想しただろう。
一同の中に笑いが起きて、牧人一人がきょとんとしていた。
しばしそのことで会話が続き、その後は近況報告や高校を卒業してからの話になった。
無論、既知の情報も多くあった。だがそれは断片的なものだ。
一応連絡を取り合っていた彼等だったが、それは各々バラバラなものだった。
この瞬間までは、彼等の繋がりは個々のものだったのだ。
それが改めて輪となって、集団となる。
自分一人だった期間、他の四人が何をしていたかが明らかになる。
一本だけだったレールは明確な五本となり、それだけで心強い何かを彼等の中にもたらす。
何の問題もなく共にいた高校時代も例外ではなかった。
懐かしさに任せて、その時々の思考や行動を語り合う彼等。
その中には、今になって初めて知ることも数多かった。
あの時牧人はこんな風に思っていた。あの時なつめはこんなことをしていた。
会話を経て、集積される。
情報が蓄積され、集約され、五人の共通の理解となった。
――――僕の元に集積され、統合される。
懐かしい昔語りを経て、五人で入ったのは商店街にある居酒屋だった。
まだ時間は早い方で、店内の人影はまばらである。
これがあと数時間もすれば、帰宅途中のサラリーマンなどでごった返すようになることだろう。
……ちなみに以前、葦原牧人はこの店から出てきた泥酔した大人たちを見て、大人の有り様の難しさを語ったことがある。
そんな彼等が、今や未熟ながらも大人となって、その店に足を踏み入れていた。
何とも不思議なものである。
「あー、このお店って確か……」
予約した席に通される最中、なつめが呟いた。
記憶の中には忘却されていくものもある。
この店の前を歩きながら交わしたその会話を覚えていたのは彼女だけだったようだ。
「マッキー先輩がここの予約したんすか?」
「? したのは俺だけど……店は明彦が指定してきたんだぜ。ここがいいってな」
「………………」
「なんだいなつめちゃん?」
「いいえー、明彦先輩ってなんつーか……」
「なんつーか?」
「……いや、やっぱなんでもないっす」
なつめはそれ以上何も言わなかった。
彼女の思ったとおり、明彦はその時の出来事を改めて自分たちに反映させてみたくなり、この店を選んだ。
そうと気付けばどことなく作為的なものだろう。
それについて言及されて困ることはなかったが、無理に言わせることもないだろうと明彦は判断し、追及をやめた。
円卓を中央に置いた座敷に通され、五人は車座になる。
いい席だ、と思った。皆の顔がそれぞれ良く見える。
適当に注文を始め、各自思い思いに飲食をし出した。
自分が飲み食いしたいものを、次々注文していく一同。
一同の中にあるのは以前と変わらない、そうした強制のない空気だ。
職業柄なのかは知らないが、なつめはザルだった。あれほど痛飲しながらも表情一つ変えない。同じく強い耕平と、先程から店のアルコールを全種類制覇する勢いだ。
だが、不思議なことに二人ともあまり酔わない気質のようで、素面の時とあまり変わらないように見えた。
対して牧人はアルコールにとても弱いらしい。すぐに赤くなる。そんな様子を耕平たちにからかわれて、悔しそうな顔をしているのはイメージ通りだろう。
意外だったのが薫で、大人しそうな顔をしながら先程から強い酒ばかりを頼み、ちびちびと慎ましやかにそれを飲んでいる。
無理にビールを飲もうとしている牧人が心配らしく、そちらばかり見ている。彼女の方が圧倒的に酒に強いと気づいた時、牧人は落ち込むのではないだろうか。
そのようにして、ささやかな酒宴が続く。
……もっとも、酒宴という言葉が適切かどうかは微妙なところだ。
良くある羽目を外す場としての集まりというには、五人の様子は落ち着き過ぎていた。
大声で騒ぐというより、彼等は普段どおりの淡々とした調子で会話を重ねた。
彼等の話題は多くが昔のことだ。
先程から続いているのは過去あったことを互いに確認し合うもの。
あの頃あんなことがあった。あんなことを話した。
一つの話題を経る毎に、彼等は距離を縮めていった。
言わば、絆の修復作業といえるだろうか。共に歩いた道を、今もう一度眺めている。
今、ここに向かい合うのはあるがままの彼等だ。
相互に光を放ち、分散させ、心の虹を作り合うプリズム――それが彼等だ。
あるがままの姿で輝きあうことができる、そんな繋がりだったのだ。
今やその空気を取り戻している。
対話をしているうちに、一時期存在した不和はいつしか完全に消えていた。
全体がその空気を実感し始めた頃、五人のうち三人が別の空気の存在に気付く。
「………………」
「………………」
「………………」
耕平となつめが顔を見合わせ、明彦がそれを見て頷く。
三人の気配が向いているのは葦原牧人だ。
先程から彼は、持参してきた紙袋の紐を固く握りしめて、何かを伺うように視線を巡らせていた。
その様子を見て、今更何も思わない三人ではない。
大体、友人同士の酒飲みの場に持ってくるには、その紙袋は明らかに異質だ。
……言うまでもなくばれている。
紙袋の中身を、牧人は薫に渡そうとしている。
その見え透いた決意が何とも牧人らしく、皆その不器用な頑張りを応援したくなったのだった。
「……え、えっと」
牧人を中心に他の四人が沈黙してしまったので、残された薫が戸惑った。
何か話題を探そうとして、腐心している様子である。
思えば、彼女はこの日集合してから、牧人とはほとんど対話していない。
気まずさなのか、単にどのような態度をとればいいか解らないのか、どちらともなく目を逸らしてばかりだ。
そんなぎこちない空気が続いている。
……それも、限界に達していた。
「悪い、俺……ちょっとトイレ」
耐え切れなくなった牧人が逃げ出した。
顔を伏せ、泣きそうな表情で、すごすごと座敷を後にする。
「………………」
「………………」
「………………」
その背中に向けられる三つの視線を、牧人はどのように受け止めていたのだろうか。
「なーんか……」
なつめが牧人の消えた襖を眺めながら言う。
「ちょっち、かわいそうっすね」
「お前、ホントにそう思ってるか?」
「ぶっちゃけるとそんなでも。ただ、あの辺は昔となーんも変わってないなーマッキー先輩はー、と思ったんす」
「……まあ、なあ」
そう言って二人は、牧人の置いていった紙袋を見る。
中に何が入っているのか。その興味が湧かないわけではない。
覗き見てやりたい欲求に駆られるが、その手の悪戯心を出す場でもないだろう。
「大丈夫だよ」
そんな二人に対して、明彦が微笑みかける。
「――牧人は、強くなった」
その言葉には、皆が一様に頷いた。
「うー……」
襖一枚を隔ててそのようなことを言われているなどとは露も知らない葦原牧人。
居酒屋の通路などで唸っていると、悪酔いした客と勘違いされる。事実、何度か店員に声をかけられた。
いっそ酔っていれば、こうして悩むこともなかったのだろうか。
だが酒の力を借りて出た言葉にどれほどの力があるだろう、と牧人は思う。
故に言わなければならない。素面のまま、本心を全て包み隠さず。
だが――
「やばい……」
――なんか滅茶苦茶、緊張してきた……。
胸を押さえると、信じられないくらいの速度で心臓が拍動している。
別の意味で吐きそうになるのを堪えながら、襖に手をかける。
――コレから、言うんだ……俺の気持ち、薫に……。
今しかないと思った。全体の不調和が消失し、かつての空気を取り戻し始めた今しか。
だが、そう覚悟したその瞬間から、緊張は肥大していくばかりだ。
何か口にしようとしても、すぐに頭脳は初期化されてしまう。
――ああくそ……どうすりゃいいんだよぉ……?
頭を抱える牧人。別の客が怪訝そうな表情でその脇を通過していく。
「いや……」
そのような視線にまるで気付かず、牧人はかぶりを振った。
――カッコつけなくたって、いいんだ……いつもの俺で……でも……、
「…………いつもの俺って、なんだ?」
唐突にそんな疑問を抱いてしまった。今まで考えたこともないようなことを。
かつてはどのように薫に接してきたか。どのような顔で、どのようなことを言っていたか。
思い出すも、出てくるのは見るに耐えない、稚拙な自分の姿ばかりだ。
「…………」
それ以前に、大前提として、彼女は今でも自分を受け入れてくれるのだろうか。
――あんなことがあったんだ……ふられたって思ってる――なんてレベルじゃねぇよな……
「俺は……どうだ?」
――俺は今でもホントに、薫が好きか?
自問。心がかつてなく波打っている。
その状態はどこか懐かしくもあったが、途方もなく不安だった。
――何が好きなんだ? どの辺が好きなんだ? どのくらい、好きなんだ?
問えば問うほど、答えは出ない。
――くそっ、変な理由付けで逃げるな……、ここでやらなきゃ、きっと一生……後悔する……!
そう思い、震える手を再度持ち上げようとした時、
「――っっ!?」
自分のポケットから鳴り響いた着信音に、牧人は飛び上がる程に驚いた。
――め、メール……!? こんなタイミングで一体誰だ――、
折角の決意が揺らいでしまう。牧人はそれを焦った。そのようなメールなど無視して、今はこの扉の向こうへ……、
「………………」
それでもやはり気になって、牧人は携帯電話を開いてしまった。
――あー、結局逃げてるじゃねぇか俺……マジで最低の馬鹿――
そして後悔する。自己嫌悪。
自分に呆れ果てながら、牧人は送り先を確認することもせずメールを開き、
件名:ハッピーウエディング
内容:
「あ、そういや今朝言ってた藤宮香ってコ、アッシーの彼女? あ、で、久しぶりに会うのか、なんだよー、もうそのまま結婚しちゃいなよー、ばーかばーか」
「おい浅野……」
あまりに絶妙なタイミングで送られてきたその内容に、牧人は送り主――浅野がすぐ近くで見ているのではないかと疑念を抱いた。
無意味に周囲を見回してから、そんなわけはない、とため息をつく。
――結婚しちゃいなよー。
しかし、何故か最後の一文だけ、浅野の声で脳内再生された。
……その言葉の威力に、牧人は一瞬眩暈を覚える。
「……結婚なんて、軽々しく言いやがって……あの馬鹿」
苦笑した。
改めて好きだ、とさえ言えない今の自分に、結婚など夢のまた夢だ。
「けど、なんか……」
牧人は携帯電話をポケットにしまい、改めて深呼吸。
先程までの緊張は、いくらか和らいでいる。
……これならば、何とか耐え抜くこともできそうだった。
――浅野、お前にはホント……色々助けられてるな、今度、ちゃんとこいつら紹介するよ。
心の中で牧人は友に約束する。
「けどな、香じゃなくて薫だ。……間違えんじゃねぇよ」
不適に笑いながらそう言って、牧人は襖を開け放った。
そこには最早躊躇いはない。
上手くやれるかはわからない。無様で情けない姿かもしれない。
……だが、とりあえず潔くあろうと思った。
そうすれば、きっと――
戻ってきた牧人の表情は、晴れやかだった。
何もかも振り払ってきたような、落ち着いた気配すら滲ませる。
「悪い、待たせた」
それは果たして誰に、何に対して告げた言葉だろう。
そうして、改めて席につく牧人。
その姿を見て、三人の仲間たちの胸に……途轍もない安心が広がった。
「はーい!」
一番に動き出したのはなつめだった。
席を立ち、挙手をする。
「あたしちょっと、タバコ吸ってきますー」
「え?」
本当なら、なつめは煙草を吸わない。サービス業においては珍しいことである。
そのことを牧人は聞いている、故に混乱した。
しかし、そのことについて他に誰も指摘しなかったのは、皆なつめが非喫煙者であることを知らなかったからではないはずだ。
「お、おい、芥川――」
このタイミングで消えようとするなつめに、牧人は戸惑う。
だが、なつめはそんなものは無視するように、テケテケと座敷を飛び出していった。
「あ……」
襖を閉じる直前に見せたウインクが、自分を激励しているように思われた。
続いて、ゆっくりと明彦が立ちあがる。
「あ、明彦……?」
見上げる牧人に明彦は笑顔で手を振る。
「僕もちょっと大学から電話が来ててね。急ぎの用事なんだ、出てくるよ」
机に置かれた携帯電話を拾い、そのまま悠々と座敷を後にする。
動きはゆったりしていたのにそこには一言も差し挟む隙がなかった。
なつめ、明彦が相次いで消え、座敷は三人だけになる。
「…………」
「………………」
突然面子が減ったことで、妙な沈黙が訪れた。
「ふー」
それを破ったのは、棗耕平のため息。
「……あいつら、揃って手が早いな……このオレサマが先を越されるとは思わなかったぜ」
「耕平……、お前ら……?」
最早、彼等三人が何をしているのか気付かない牧人ではない。
ただあまりに唐突だったので、慌てている。
……とりあえず、自分の計画が周知の事実になっていることについてはどうでもいいようだった。
「牧人よお……」
「な、なんだよ?」
しまらない態度で耕平も席を立った。
「今のお前なら安心だと思う。だから、なんつーか、その――」
眼鏡のズレを直す仕草が、どことなくわざとらしかった。
「――うまくやれよ?」
そう言って、耕平は握った拳で牧人の頬を軽く殴った。
痛みなどまるでなく、そこにはただ友に対する激励だけが乗せられている。
「耕平……」
「あーあ、だせえだせえ。オレも落ちぶれたもんだぜ」
気怠げにそう言いながら、ぶらりと座敷を出て行った。
何をしに出て行ったのか全く告げていないが、そのことに気付いた時には、耕平はとっくに姿を消していた。
「………………」
「………………」
そして座敷には、牧人と薫の二人が残された。
――な、なんだ……これ?
鈍い牧人も相次いで消えた友人三人の意図くらい察している。
だが、決意したものの展開の速さについていけなかった。
喉が渇いてグラスを掴むも、今酒を口にするのはまずいと踏みとどまる。
「み、みんな……どうしちゃったんだろうね、突然……」
用心しいしい、そのように言う薫。
――か、薫にも……もう、バレてる……のかな……?
だとしたら途轍もなく格好悪いと思い、別に構わないとも思った。
どちらも肯定できてしまう。だからこそ、思考は纏まらず、混乱していた。
「な、何か……話してようか」
「そう……だね」
――いきなりは、マズイ……、会話の中から、タイミング、探さねぇと……。
世間話を交わそうと思った。
「マキくん、はさ……」
「う、うん」
ぎこちない。
「マキくんは、大学とかで彼女なんて……できたの、かな……?」
「えっ……?」
牧人は過呼吸に陥りかけた。
――今、その質問するなんてのは、何か意味があるのか……?
そして深読み発動。
「いや、全然……、薫、は?」
「わ、わたしも……。あはは、相変わらず、もてないんだね、お互い」
「ハハ、ハ……」
――ば、馬鹿……過度な期待なんかすんなよ、単に場繋ぎの言葉ってだけかもしれないだろ……。
「不思議だなあ……、マキくん、こんなにカッコいいのに……」
「かっ――!」
今度こそ過呼吸だった。酸素が妙な場所に入り込み、息ができない。
「そ、そんなこと言うけど……薫だって――」
「え、わたし……?」
「薫だって、こんな……かわ――げほっ」
むせた。机に突っ伏す。
――違うだろ俺っ! そんなこと、今更言ったって仕方ないだろ……!
そうした表層的な賛美は、今の牧人には何だか遠い。
――そんなんじゃない……可愛いだとか、綺麗だとか……、そうじゃなくて、今は、俺が薫のこと、好きかどうかってことで……、
「ま、マキくんっ、どうかしたのっ? 気持ち悪い?」
突然机に倒れこんだ牧人を見れば、誰もがそう思っただろう。
薫がすぐ傍まで寄ってくる。
「い、いや……平気――」
それを感じて、牧人は何とか顔を起こして――、
「無理、しないでね……お酒苦手だったら、仕方ないもん」
見下ろしてくる彼女の視線と、机に伏したままの自分の視線が交錯する。
「あ……」
「え?」
目が合って、牧人は思わず声を発した。
――馬鹿だ……、俺……カッコ悪すぎるぜ……ホントに……、
そこにいるのだ。
藤宮薫がすぐ傍に。
――そうだよ、それが嬉しいんじゃねぇか、……なにがどう、とか関係ねぇよ……、全然。
「ま、マキ……く――」
その事実に、涙が出そうだった。
否、既に流れてしまっているかもしれない。
――好きなんだ。……ただ、好きで、死ぬほど好きで仕方なくて……。
「薫……」
そう思えば、後はもう動くしかなかった。
牧人は体を起こし、まっすぐに薫を見据える。
「あ、ぅ……」
すぐ近くに互いの顔がある。
その事に薫も気付いたらしく、恥ずかしげに少し身を引いた。
……逃がさない。
今ここで彼女を行かせたら、もう捕まえられない。
そう思って、牧人は掴む。
――俺は……お前と――!
「あのっっ、あのさ――」
牧人はもう止まらない。止まれない。
「聞いて欲しいんだ、俺ずっと薫に話したいことが、あって……」
「ま……マキ、くん……?」
戸惑う薫の手を掴む。抵抗はない。
「俺、その……自分のことばっかりで……言いたいことだけ言って、自分が悪いからって懺悔するみたいに……、そんで、お前の気持ちなんか少しも、考えないで……」
ここまでわざわざ運んできた、純白の袋を掴む。
……高校時代までの自分なら、薫の方から尋ねてくるまで渡すのを待っていたりしただろうか。
ふと、そんなことを思った。
「で、傷付けて……謝りたくても、カッコ悪くて謝れなくって……」
だけど、今はそんな悠長なことをしている暇はないし、そんな態度自体がもう許せない。
――だから俺が自分から言うんだ……!
「ごめん薫。泣かせてごめん、たくさん傷付けてごめん。だからもう、これが最後でいい」
「……っ、待って、マキく――」
両手で掴み上げたその袋を、薫に突き出す。彼女がそれは何かと尋ねるのに先んじて。
些細な違いでしかない。
だが、牧人にとっては、とてもとても大きな一歩――
「最後のチャンスをくれ、もう一回言わせてくれ――」
彼女との距離を縮めるための、とても大きな一歩。
「俺はお前と、一緒にいたい。お前と一緒がいいんだ。お前と一緒じゃなきゃ、駄目なんだ。だって俺は――」
夜の居酒屋。小さな座敷に二人はいる。
周囲の部屋には他の集団が酒を酌み交わし、騒いでいる。
だというのに、周囲の喧騒が、今は嘘のように聞こえない。
「――俺はお前が、好きだから……!」
その言葉は、二人の耳に、はっきりと残った。
「マ、キ……くん……」
恐る恐る手を伸ばし、牧人の差し出すものに触れる。
互いの手を重ね合いながら、それは彼から彼女に渡された。
「遅くなってごめん、誕生日おめでとう……」
「え――?」
虚を突かれて目をぱちくりさせながらも、その袋を開く薫。
「こ、これって……」
中身は……、いつだったか購入した、白のダッフルコート。
ちなみに今の季節は初夏。去年のでも今年のでも、薫の誕生日からは程遠い。
「別れた後、お前の誕生日にさ……なんでかよくわかんねぇけど、買っちまってて……」
「え、でも……これ……すっごくいいやつだよね……? こんなお金……」
「あ、えーと……ホントはギター買うために貯めてた金で、さ……」
そこで本当のことを言ってしまうのが牧人だ。
「まぁ、そのおかげで今でもあのボロギター使ってんだけど……、そんなの――」
「ぷっ……」
「え?」
しかも自覚がない。思わず薫は吹き出してしまう。
「はは、もぉ……ばぁか。そーいうこと、言っちゃう? 普通」
「ヘ、ヘンな見栄張ったって仕方ねぇ……だろ」
言うことは素直になっても、照れ屋な部分は変わらない牧人は視線を逸らしつつそんなことを。
自分でも大分変だとは思っていた。相変わらず要領が悪い、とも。
「まったく……、相変らず駄目だなぁマキくんは」
そんな姿が薫も懐かしくて嬉しくて、泣き笑いの顔をコートにうずめる。
「こんな時にいきなり誕生日プレゼントなんて……、こんなの、見てるだけで暑苦しいよ」
「……で、でも、どうしても薫に貰って欲しかったから……」
「ばか……、そんなの、わかってるよ……言わなくていいの……」
「う……」
表情は見えないが、薫の涙声は呆れ果てているように聞こえた。
なんというかもうぐだぐだだった。
「……あー、俺、今メチャクチャ格好悪いよな、すまねぇ」
痛いほど思い知ったその事実。
けれど、今更どう思われてもいい牧人だった。
どのようにカッコ悪くても、彼女がそれを受け入れてくれさえすれば……。
「ううん……」
まして、
「そんなマキくんが、……大好きだよ」
……そんな言葉が貰えるのなら、もう本当にどうでもよくなる。
寄り添う薫を抱き寄せる。
ダッフルコート越しに、懐かしい温かさがそこにあった。
「はは、なんつーか……」
――もうホント、どうしようもなく陳腐で……とっくに言い尽くされてる言葉だけど……、

「……夢、みてぇだ」
本当に……見ている方がため息をつきたくなるほど幸せそうな表情で、
牧人は、そう呟いていた。
けれど、そう思うのは見ている方もそんな二人を祝福しているからなのだろう。
「いゃー、よかったっすね」
「へっ、よーやく男見せたかあの野郎。遅いっての」
「ホント、よかったね。牧人」
通路で向かい合いながら、ガッツポーズをする三人。
座敷の襖が少しだけ開いているのは、牧人たちには秘密だ。
宴もたけなわ、という状況も過ぎた。
五人の再会を祝う集いは、終息に向かいつつある。
「さて、じゃあ最後に僕から一つ話をさせてくれ」
故に武田明彦は初めて自分から話題を出した。
店に入ってから早数時間。そろそろラストオーダーとなる。
突然の明彦の宣言に、一同の視線が集中した。
「……なつめちゃん」
「なんすか?」
「君は前に、色々な社会のルールや他者との関わりを、両手で貯めた水に例えたんだよね?」
「や、そりゃあの頃はあの頃でして、今はもうちょっと大人になりましたというか、その」
うろたえるなつめが言うあの頃、というのは耕平と共に海に行った時のことだ。
先程まで二人だけの記憶だったそれは、昔語りを経て全員が知るところとなっている。
「そう? あれは悪くない例えだと思うけど……まあそれはさておいてさ」
なつめの反応を気にすることもなく、続ける。
「耕平はその水を支える辛さを抑えるために、大事な思い出や友達を溜め込めって言ったんだよね」
「……あーそうだよ、つか、何でいちいち掘り返すんだ。改めて言われると恥ずかしいぜ」
「そうだね。まあ僕もこれからかなり恥ずかしいことを言うわけだから、その辺りは勘弁して欲しいな」
そっぽを向く耕平だったが、明彦はまたも動ずることはない。
「牧人、この二つ、なんだかおかしいと思わない?」
「あ? おかしいって、どういうことだ?」
突然自分に話題を振られ、牧人は怪訝な顔をした。
「あの……それって結局同じ事だよね? なっちゃんは、水を抑えるのが嫌だって言ってるのに、棗くんは……その例えで言うなら、もっと水を貯めろって言ってるのと同じじゃない?」
牧人に先んじて反応したのは薫だった。
言われて牧人も得心がいったように頷く。
この二人も、耕平となつめのあの会話には共感する部分があったということか。
「そう。友達同士だって、煩わしさはある。一時の牧人と薫みたいに。人間は中々上手くいかないよね」
「なぁ……、まだ続くのかその話。既にかなり寒いぞ」
「むしろここからが本番だよ。……まあ、寒い寒い言ってるのも、ある意味僕らが大人になったからだよね。でも、今だけは子供に戻って欲しいな」
「あーぁ、わかったよ。……続けてくれ」
明彦のその要請に思うところでもあったのか、牧人は引き下がった。
「……それじゃ、失礼して。まあ薫の言った通り、僕たち五人の思い出だって、保持し続ける事が難しいのは変わらないんだよ。だから耕平の言ってる事はある意味詭弁なんだ」
「……そうかい」
言われて耕平が残念そうな顔をするのは、彼自身もそのことを意識していた部分があったからかもしれない。
「ああ待って、これには続きがあるんだ。正確に言うと、耕平は水を増やすよう言ったわけじゃない――水の中に砂金を落とせって、そう言ったんだよ。わかる?」
……砂金。
今まで登場したことのない単語が突如現れ、一同は水を打ったように静まった。
皆、思考している。明彦の言葉を吟味し、理解しようとしている。
砂金と呼ばれた何かの真意を。
「水の中の砂金は、社会の煩わしさや苦しさの底に沈んだ大事な思い出――だから、わたしたちはきっと、必死になってそれを守る」
最初に応えたのはまたしても薫だった。
その言葉に全体の異論がないことを感じ取り、明彦は頷く。
「そう。怠惰でいれば、何かに溺れれば、きっと水の中の砂金を見逃すように、僕らは思い出を忘れていく」
開いた手のひらには、今は何も乗っていない。
だが、そこには目に見えぬ輝くものがあるはずだった。
「だから僕たちは、人間の尊厳を保ち続けるため社会に順応し、水の中の砂金を零さないよう――結果として、水をも必死で守り通す。
1を忘れると、人は大抵10や20を忘れてしまうものだから――そうだよね、牧人」
「……あぁ、そうだな」
「素直になったね。あの頃からは考えもつかない」
「……ふん」
牧人は鼻を鳴らす。不機嫌なのではなく、単に照れているだけだと皆知っている。
「ぶっきらぼうは直らない、か。まあ良いや、その方が牧人らしい」
微笑んで、明彦は全体に向き直る。
牧人の反応は嬉しかったが、それは脱線だ。
「……僕らはさ、互いが水の中に混じった砂金を、後生大事に守ってきた」
それは、共にいた日々のこと。
「でも、一人じゃ思い出はすぐに薄れる。積もりゆく他の色々なもので水は濁っていって、その中に溶け込んだ砂金は……いつしか見ることも難しくなる。
……僕は卒業してから今までの時間で、そして、今まさにそれを痛感してる」
たった今、様々な会話をし、情報は蓄積されてきた。
それはつまり、こうして話をするまでは、認識できる場所になかった――忘れていたということになる。
「こうして五人集まって、互いに色んな事を話しても……まだまだあの三年間は穴だらけだ」
一夜で語り終えることができる量ではない。
あの密度が、その程度のものであるはずがない。
交換されていない砂金がまだあるはずだった。
「……正直、皆と再び連絡を取って、同窓会を開くのは――結構、緊張した」
その発言に、誰もが意外そうな顔をした。
動き回ったのは牧人でも、企画したのは明彦だと誰もが知っている。
「でも、砂金を一人で守り続けるのは、本当に疲れるから。皆もきっと、そうだろうなと思ったから」
その感情を明彦も感じていた。そのことが露見したのはこれが最初だっただろう。
故に一同は驚くと共に、不思議な一体感を覚えていた。
「……ねえ、牧人。そのコップの水、ここに落としてくれない?」
言いつつ両手で椀を作る明彦。
「あ?」
「おいおい、そこまでやるのか」
自分の語った論をここまで掘り下げられるのはさすがに耐え難かったのか、耕平が呆れた顔をする。
「僕だってたまには、我侭言っても良いと思わない?」
「ったく……かなわねえなあ」
頭をかきながらそっぽを向く耕平。
「……どれくらい、入れるんだ?」
「牧人の入れたいように」
「…………」
牧人は、何故自分がその役に抜擢されたのかがまだよく解っていない。
渋りつつ、コップの水を手の中いっぱいになるまで入れる牧人。
「ありゃりゃ。ギリギリだね」
言いながらも、既に少しずつ水は零れている。
「耕平」
「あ?」
「何ぼうっと見てるの? この水の中には、僕たちの砂金が入ってるんだよ?」
こぼれないように押さえなきゃ、と明彦は目で促す。
「――ちっ、なんだテメェ、オレやなつめなんざ目じゃねえくらいキザじゃねぇか」
諦めたようにそう言いながら、明彦の手の下に、手を重ねる耕平。
「さあ、次はなつめだ」
「あ、はい、了解っす!」
なつめは楽しそうだった。
多分彼女は言葉にならないだけで、感覚としては一番理解している。
「次は薫」
「え? う、うん」
薫は、言葉では理解しながらも、認識としてはやや遠い。
一番健全な彼女は、実感として薄いのだろう。手を添える動作も、おっかなびっくりだ。
「さあ、牧人」
「……けど」
最後に声をかけられた牧人は、ためらう。
ここに来て、以前その砂金を自ら捨てようとしたことに思い至ったのだ。
彼が本当に全てを投げ打ってしまえば、ここに再び会することもなかっただろう。
故に、改めてそれに触れる資格が自分にはないと思っている。
「良いんだ、牧人」
そんな彼を明彦は常に強く励ます。
「何を間違えたからといって、この思い出の所有権を君が失うわけじゃない」
今までだって、ずっとそうしてきたのだ。
「――そうか」
そして牧人は言葉に応じた。
悩むくらいなら手を伸ばすことを、彼は知ったからだ。
そして、全員の手が重なった。
「ここに入っているのは、今日集まった中で埋められ、補い合った僕たち全員の思い出だ。
この底に沈んでいるのは、僕ら五人分の砂金だ。だから互いが互いを支え、僕たち皆で守るんだ。守っていかなければならない」
重なり合う五人の手は、最早頼りない椀ではない。
一滴の水も落とすことのない、力強い結びつき。
「こうすれば――――こうして皆で支えあえば、水も砂金も、そう簡単に落ちはしない」
各々の伸ばされた手の先に湛えられたその水を、皆が眺めていた。
その底には、確かに見えない黄金がある。
……だから全員が必死で抑えた。
互いの手を握り合うように、支えるように。
…………手を、繋ぐように。
「僕は、この五人で居られた事を、心から幸せに思ってるよ」
「……明彦」
誰ともなく名を呼んだ。
「だから皆もそうであると、信じたい。
これからも、ずっと、ずっと――――僕らは、友達だ」
その言葉に、全員がうなずいた。
もう誰も笑わない。
無言で、静かに、けれど力強く。
それを見届けた明彦は、フ――と短く笑って、
「耕平、まだ支えててね」
「あ?」
そっと両手で作った椀を解き、中の水を落とした。
水は、当然明彦の両手を支えていた耕平の両手へと移る。
「お、おい明彦」
「写真、撮っておこうと思って」
「おいこら……何もそこまで――っ」
そこまですることはない。
そう思ってカメラを探して鞄を漁る明彦を制したいところだったが、そうすれば水は落ちてしまう。
「良いじゃない、もうこんな機会ないだろうし。これもある意味お酒はいってるから出来ることだよね」
「お、お前なあ……」
そのように言う明彦も、耕平たち同様、素面の時とまるで変わらない。
酔っているように見えるのは顔が赤い牧人だけだ。
「まあまあ」
言いつつ、鞄からようやくインスタントカメラを取り出す明彦。
「……いまどきポラロイドかよ」
「雰囲気があって良いだろ?」
指摘しつつもレトロなその物体は明彦に似合っていると耕平は思った。他の皆も思った。
「それじゃ、撮るよ―――」
――パシャリ。
フラッシュが炊かれ、すぐに写真が出てくる。
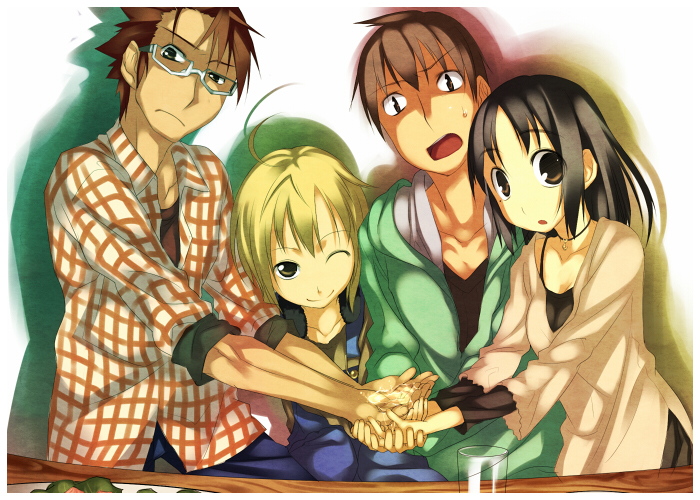
「お、おい、チーズとか何か言えよせめて!」
不意の眩しさに目を細めながら、牧人。
「だって、こんな構図で四人とも笑顔って……不気味じゃない?」
「でも心の準備欲しかったっすよーぅ」
「あはは、でもさ……、良い感じだよ」
言って、印刷された写真を見せる。
「素のままの皆が出てる。僕ららしくて良いじゃない」
「……チッ」
舌打ちしたのは牧人だ。その写真には、明彦が写っていない。
……彼は、その意図に気付いたのだろう。
「ってゆーか先輩、だったら五人そろってないと駄目じゃないっすかー」
他の三人もそのことに気付き、なつめがそれを指摘した。
「あはは、それがそうでもないんだ」
明彦は笑ってカメラをしまい、
「僕、もう少ししたら留学するんだ。だから余程の事がなきゃ、もう皆とは会えないね」
その言葉に、耕平が水を落とし、なつめが水を落とし、薫が水を落とし、牧人が水を落とし……そうになるところを何とか堪えた。
さすがに牧人だけでは支えきれず、いくつもの雫がテーブルに滴る。
「ありゃりゃ、零しちゃったね――ごめんごめん、驚かせちゃったみたいだ」
言いながら、ポケットからハンカチを取り出し、水をふき取る。
その水が、皆の零した涙に見えた。
……だから――明彦はこれを、誇りに思おう。
これは、皆が“僕”のために流してくれた涙なのだと、そう思おう。
そして……最後に立つ牧人が、それを受け止めてくれた。
だから、もう彼に任せても大丈夫なのだ。
「お前、留学って……なんで……」
すがるように明彦に近寄る耕平。そこには普段の余裕が欠片もない。
「文化人類学研究会って、覚えてる? 実は僕は高校時代、そんな部活に所属してたんだ」
「あ……、もしかして、文化祭の時、発表してた……」
薫がそのことを思い出してくれる。
思い出、一つ。
「やっぱりお前……その話するつもりだったんだな、長い前振りしやがって」
嘆息したのは牧人だ。
「既に知ってる牧人には退屈だったかな」
「いや……途中まで気付いてやれなかった、悪い」
「いいさ」
近くにあったコップの中に、牧人はそっと手の中の水を注ぐ。
それを大切に保存しておくかのような、慎重な動作で。
……そう、彼は既に知っている。
「え、あの……どういうことっすか? マッキー先輩既に知ってるって?」
「牧人には、最初に電話をした時から、既に話してあることだったんだ」
「ええっ!?」
「牧人お前、何でそんな重要なこと黙って――!」
耕平となつめが向いた先にいる牧人は、悔しげに歯を食い縛っている。
「牧人を責めるのはやめてくれないか。僕が無理にお願いしたんだ。皆このことを知ったら自棄になって集まる気をなくしてしまうかもしれないから黙っていてくれ、ってね」
「なるほど……。チッ、そういうところには気が回るな、明彦さんよ!」
降参したように耕平が手を挙げた。
実際に知らされていたら、今言った通りになっていた可能性を感じたのだろう。
「お前らは、知らないかもしれないけどさ――」
牧人が重い口を開く。
「それって明彦の昔からの夢だったんだよ。明彦、小学生の頃から、そういう歴史とか文化とか……調べたりするの好きだったんだ」
「……驚いた。そんなことまで覚えていたのか、牧人は」
「お前に言われて思い出したんだけどな。“あの発表”とかしてる時とか、お前楽しそうだったなあ、って」
嬉しい。牧人も、そんな古い記憶を覚えていてくれた。
「……じゃあ、あたしたちがワガママ言って止めるわけにもいかないっすね」
「そうだね……、そんな昔からの夢なら、わたしたちだって叶えて欲しいもの」
黙していたなつめと薫も、戸惑いがちに伏せていた顔を上げる。
「元々研究とか、考えるのが好きなんだ。その中でも特に、人間同士の在り方とかに興味があってね。人類学ってのはそれをテーマにした学問だからさ」
そして、武田明彦は語る。
自分の道を。初めて、愛すべき親友たちに。
「高校ではそれをやってる集まりがあったから参加して、大学でもそれをやろうと思ってその分野で優れた教授がいる大学を選んだ。でも、いざ自分が本格的にやると決まった時、迷うようになったんだ」
人類学の基本は文献主義ではなく、フィールドワークと言われる。
現地に赴き、その生活集団に実際に属することが、書物を紐解くことより重要な研究行為とされるのだ。
……つまりは、必然的に一所に留まることが難しくなる。
「けれど、やらないわけにはいかない。というか、この道を志した以上、通らなきゃいけない道だったんだよね。僕は結論を先延ばしにしてただけだったんだ」
「じゃ、じゃあ、もう……!」
なつめが泣きそうな顔をする。
「うん、僕はここでリタイヤだ。提案しといて押し付けるっていうのも、なんだけどさ――後は、四人で支えあっていてくれると、僕としては嬉しい」
「お前、ふざけんな――!」
「ごめん。でも、もうどうにもならない」
「……っ!」
耕平も歯噛みするしかない。
「どうしても、行かないといけないの?」
「うん。もう決めちゃったしね……決めちゃったからこそ、最後にどうしてもみんなと会っておきたかった。決断することができたのも、みんながいたからだ」
「そう、なんだ……」
薫も悲しげに口を閉ざしてしまう。
「…………」
ただ一人、牧人だけは、まっすぐにこちらを見ている。
皆の砂金を沈めた水。そのコップを握り締めて。
……明彦はそれが、心強かった。
「留学して、場合によっては向こうに永住しちゃうこともあるし、また他の国に移るかもしれない。日本にもいつ帰ってくるか解らない」
……その視線を頼もしく思いながら、明彦は語る。
「そうして、僕は、もしかしたらそんな日々の中で、……みんなの事を段々と考えなくなっていくのかもしれない」
……訥々と、語る。
「思い出は残留する。けど、きっと、長い時間が経てば経つほど、みんなに会うのが怖くなる」
……夢と友情の天秤についてを。
「今日会うのだって、怖かった。みんなが変わってないか、あるいは僕自身が変わってしまってはいないか、僕とまだ友達でいてくれるのか、怖かったんだ」
……その選択に立つ自分の冷静な心を…………、
「だから、多分、今後日本に帰ることがあっても、もう、僕は君たちと会わなくなっていると思う」
……僕は語る。
…………包み隠さず、心を詳らかに。
「今日のこの時の喜びも、永遠に残ったりなんかしない。どんなに言葉を飾ったって、会わない人間関係は劣化するんだ。どんな親愛も少しずつ磨耗し、いつしか跡形もなく消え去っている」
――みんなは、僕を憎むだろうか?
「卒業してから今まで、みんな、時々は高校の思い出を振り返ったと思う。僕もそうだった……。けど、だから連絡をとって会おうと思った人は、いなかったはずだ。
僕だって、留学で、会いたくなってももう会えなくなるって解ったから踏ん切りがついただけだし」
――それとも、僕を忘れ去るだろうか?
「きっと、僕らはもう会うことのない関係になっていた。会えないんじゃなくて、自然と、会わなくなっていく。僕が戻って来る来ないにかかわらず。だから――」
上を向いた。
皆の顔を見たら、決意が鈍る気がしたからだ。
――かまわない。彼等の中の僕が、どのような結末を迎えても……、ただ――
そうして、これまで育んできた全ての友愛を込めて、断ち切るように告げる。
「だから――――五人は、今日が最後だ」
誰もが無言だった。
理解していたからだ。
それが起こりうるのだと言うことを。
今どんなに吠えたところで、何を喚いたところで、それが避けられないということを。
……負け犬はやはり吠えないのだ。
「でも、四人はこれからも一緒だ。だから、もしかしたら、ずうっと関係を維持できるのかもしれない――いや、僕としては是非続けて欲しいと思ってる」
……もしかしたら、自分は今、涙を流しているかもしれない。
笑みを作ることは得意だが、それもさすがに限界だろうか。
「最初に抜ける僕が言うと都合の良い言葉に聞こえるかもしれないけど……」
棗耕平、芥川なつめ、藤宮薫、……そして、葦原牧人。
「みんなは、こんなに……いいやつらじゃないか」
僕が手を広げてそう言った瞬間――、
芥川なつめは憚らず泣いていた。
棗耕平は決意したように壁を睨んでいた。
藤宮薫は涙を拭いながら微笑んでいた。
そして、葦原牧人は、明彦の目をまっすぐ向いて、頼もしく頷くのだった。
「……頑張ってね」
全体に向けた言葉だった。
「ああ、俺が……ここにいるよ」
それに応えたのは――、
だから、もう安心だ。僕の役目は全て彼が引き継いでくれる。
一人減っても続いてくれる。
僕の考えた親愛のモジュール。
きっとこれからも、彼等の中で動いていくだろう。
………………静かに、強く、動いていくだろう。
――例えば三人称の小説などを読むとき、それが誰によるものかを考えたりはしないだろうか?
それは誰でもない、いるはずのない存在によるものだ。
従って本記録の最後には、その記述視点についての言及をしておこうと思う。
まず本件の記録者について触れておこう。
記録者は“僕”だ。
“僕”が記録を決意したのは、この瞬間――つまり、牧人たち友人四人との再会と別離を果たしたすぐ後のことだ。
“僕”は当初、人と人との繋がりは、時と共に薄れ、消え去っていくものと考えていた。
……去る者は日々に疎し、と言う。
会うことがなければ、人は相手を忘れていき、関連性を維持することができなくなっていくのだ。
従って、“僕”が僕等五人の輪を抜けると決まった時は、潔くその絆を断ち切るべきだと思った。
仮に再会を約束しても、それを果たすことが可能か否か不確定な環境に“僕”は身を置くことになる。そのような立場から、再会の可能性を匂わせ、その中で日々薄れていく関係性を維持する労力を彼等に負わせることは許されないと思ったからだ。
また、この集いは、断ち切るためでもあった。
そうしなければ、今後の“僕”に求められる行動にも“未練”という度し難い影響が生じてしまうとも思われたのだ。
故に、“僕”は別れを告げた。
その結果、五人の輪を抜け、一人異なる場所で生きていく決意を固めることができる――はずだった。
――だが実際は、不可能だった。
牧人、薫、耕平、なつめ。
彼等四人との絆は、一時腹を割って話す程度で割り切ることのできるものではなかった。
……この辺りに関しては、自身の精神力を過信していたと言わざるを得ない。
“僕”は自分で思うよりずっと、情に厚い人間だったらしい。
去る者は日々に疎し。その思考を改めねばならない。
数年離れた程度ではこの五人の繋がりは殆ど揺らぐことはなかったのだ。
故に、もう一押し必要だった。
それが本件である。
本記録の意義としては、身も蓋もない言い方になるが、単に記録者の思考整理に過ぎない。
彼等四人との日々をもう一度見直すことで、今度こそ一人立ち向かう気力を得ようと試みたのである。
文章はコメンタリー形式で記した。その時々の臨場感こそが重要な要素だと思ったからである。それを上手く表現できているかどうかは、この拙い文章では甚だ怪しいところではあるが、許して欲しい。
再会時の会話から得た情報を参照しているため、かなり正確に流れを追うことはできていると思われる。
また“僕”は輪の中にいた当時、集団全体の空気をとりわけ尊重すべく動いていた。
五人を五人として見て、その中で育まれていく友情を大切にしようと考えていた。
そのため、結果的に全体の空気を感じ取ろうとするタイミングが増え、傍観者的な立場が多くなったように思われる。
それについて疎外感を覚えることはない。自身で進んでした行為だからだ。
むしろ、そうして傍観していたからこそ、今こうして記録を残すことができたのだと思っている。
しかし、その作業ももう終わりだ。
この集団から離れることをもって、“僕”の記録も終了となる。
……これ以降の物語は、彼等のものだ。
こうして記録をした結果、“僕”は五人の輪から離れ、自身の道を歩んでいくことができるようになっただろうか?
それは未だに解らない。記録者たる“僕”は過去に遡行するものであり、未来を見ることは叶わないのだ。
ただし、思考の整理はできた。それが良い方向に作用するよう、後は“僕”が努力を怠らなければいい。
だが同時に、“僕”には別の“未練”が発生してしまった。
本記録を自身の中のみに留めておくことを惜しく思うようになってしまったのである。
記録をすることで“僕”の思考は整理され、その上でこの友情がログとして残す価値のある、尊いものであると心底から再認識させられたのだ。
故に、記録を開始した当初は誰にも見せず破棄する予定だった当記録を、ここに残していくものとする。
……しかしながらこれは、お世辞にも読み物として出来が良いとは言えない。
何故って、おおげさな冒険も、頓狂な怪奇も、劇的なロマンスも、大層な事件も、綿密なドラマも、何もない。
単なる、五人の思い出話。
心の中に残った小さな絞りカスの話。
だから、多分娯楽小説としては陳腐だし、退屈なところも数多いだろう。
僕らは何か特別なことをしたわけじゃない。
大きな努力と成功を成した訳でもない。
むしろ失敗とすれ違いばかりだったようにも思う。
毎日を胡乱に過ごし、大事な局面を致命的に間違える。
そんな僕たちの日常は、ことごとくナンセンスで――傍目に見れば、きっと格好悪い。
馬鹿みたいに矮小で、格好悪くて、ふと客観視すれば笑えてくる事さえある――でも、それが青春って奴なのだ。多分。
だから、それは嘘偽りなく、僕らの大事な思い出だ。
もしこの世界のどこかに僕らと同じ気持ちの人がいるならば、同じ境遇の人がいたならば、きっと、この思い出のモチーフはその人達の為のものなのだろう。
…………そうなったとしたら、それはそれで“僕”は嬉しい。
さて、最後になるが、本件の特徴を一つ挙げておこう。
それは文章の視点が記録者ではなく“葦原牧人”に置かれていることだ。
これには一応理由がある。
結果的に、本記録は僕等五人の思い出を纏めたものになったが、“僕”が現在の位置に立つに至った最初のきっかけは彼の存在によるところが大きいからだ。
従って“僕”は、僕等五人の輪の中における、彼の存在を強調したかった。
折角揃った情報を熟読する意味合いも込め、恩人たる彼の見てきた日々を辿ろうと考えた。
彼の人生と、“僕”が記録に費やした時間が等価であるなどとは決して思わない。
だが、結果的には彼の人生にそのまま共感するかのような、素晴らしい経験をすることができた。
本当に、彼にはいくら感謝してもし足りない。
その感謝がまた未練となって、再び“僕”の内に彼との再会を願う意思が現れたとしても、それはもう、むしろ喜ぶべきことのように思える。
それまでは、この記録を、アルバムのようにしまいこんでおくとしよう。
僕ら五人の、思い出話として――――
ああ、本当に――
彼等の今後を見届けられないのは、本当に悔しい。
選ばなければならないのは、本当に辛い。
だけど、そういうことになっちゃったから。
ああ言っておいてなんだけど、僕だって別れは寂しいし嫌だから。
僕は思うだろう。
一人遠く離れ、皆の姿を見ることすら叶わなくなっても。
――みんなは、今日も元気?
それでは、これをもって本記録は終了となる。
閲覧してくれた方々に、心よりの感謝を表して。

「それじゃみんな、行ってくるよ」