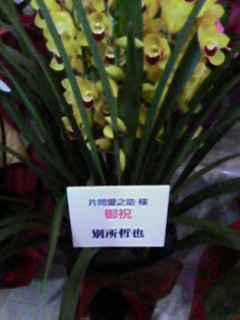年 (平成
年 (平成
 年)
年)
 月
月
新春浅草歌舞伎 浅草公会堂
1月2日(火)〜1月26日(金)
| 前へ |
| 感想 その1 |
|
1部も2部も、13日に前方中央で観劇。
1部のお年玉挨拶は獅童丈。
義経千本桜 すし屋
まず、お里(芝のぶ丈)が可愛い。
さて、権太(愛之助丈)。
結局お米はお金を渡してやるのだが、引き出しにかけられた鍵を開ける権太に「器用な子だねぇ」って、おい!
いろいろあって弥助が維盛ということがわかり、権太は「賞金首ゲットだぜ!」とばかりに駆け出していく。その前にお金を入れたすし桶をつかむのだが、間違えて生首の入った方を持っていってしまう。
権太は梶原を騙したことを告げようとした瞬間、弥座衛門に刺されてしまう。
最後、実は頼朝は最初から維盛を助けるつもりだったことがわかる。では、権太は妻子を差し出す必要はなかったのか? しかし、差し出してしまったからには、権太の妻子は助けてもらえないだろう。
首実検で権太も緊張しただろうが、梶原もあの悪人っぽい顔の下で「ここで本物の首を渡されたら、俺が頼朝様にド叱られるじゃん」と、更にドキドキビクビクだったに違いない。 |
身替座禅
「真面目なイメージの勘太郎丈が浮気亭主?」と思っていたけど、奥方の尻に敷かれる亭主役が似合っていた。浮気して朝帰りする時、ほろ酔い加減で幸せそうな、名残惜しそうな様子が上手だなぁと思った。
獅童丈の玉の井は反則。出てくるだけ、動くだけで笑いが起きるんだもん。“なんだかよくわからんが、とにかくスゴイ生き物”だった。姿もスゴイが声もスゴイ。時折ひっくり返って、捨助(「新選組!」)になっていた。
愛之助丈の玉の井はブサイクだけど、おかめ顔で愛嬌があって、「若い頃は綺麗だったのかも」と思った。同時に「(写真でしか見てないけど)『源氏物語』の夕顔や『宿無団七時雨傘』のお富も年をとるとああなるのか…?」とも思った。 太郎冠者(七之助丈/亀鶴丈)はどちらも情けない感じがよく出ていて可愛かった。ついつい、八の字眉毛にばかり目が行ってしまった。「う゛わ゛あ゛ぁぁぁあああぁあぁーーーーーーーっ!!!!!」と飛びのく様子や「しばらくっ」と逃げ惑う姿がおかしい。
1部も2部も重い演目の後だったので、これで笑って帰れるのはいいなと思った。 |
|
2部のお年玉挨拶は愛之助丈。 口上の時と同じ裃姿で中央にちょこんと正座したままご挨拶。だいたいの内容は↓な感じ。 義経千本桜は3大名作の1つで義経にまつわる人を千本の桜にたとえている。 渡海屋・大物浦は「この人実は○○」ということが多い。 私がここで説明すると混乱するので、番附を買って読んでください。 イヤホンガイドも借りてください。 身替座禅の奥さんはダンナさんが大好き。でも、ブサイク。 舞台を見て「いいな」と思ったら拍手してください、面白かったら笑ってください、悲しかったら泣いてください。
義経千本桜 渡海屋・大物浦
渡海屋に押し入った相模五郎(亀鶴丈)と入江丹蔵(愛之助丈)が渡海屋銀平(獅童丈)にやりこめられる。銀平に刀を曲げられて、「石で叩いて直せ」「石を探せ」「こんなところに都合よく石が…」などと漫才コンビみたいだった。
奥に泊まっている客が義経の(勘太郎丈)一行とわかり、お柳(七之助丈)は出立をすすめる。その後、銀平が新中納言知盛で、お柳が典侍の局、子供が安徳天皇であることが明かされる。
知盛の策略は義経に知られており、返り討ちにあう。典侍の局と安徳天皇の元に、相模五郎と入江丹蔵が次々とご注進にやってきて、壮絶な最期をとげる。亀鶴丈はビシバシと見得を切るお役が似合うなぁ。愛之助丈は敵を自分の体ごと貫いて海に飛び込む。どちらもかっこよかったなぁ。
知盛がボロボロになりながらも敵を追い払い、典侍の局と安徳帝を探しにやってくる。
典侍の局と安徳帝をつれた義経が現れ、知盛が恨みを晴らそうと襲い掛かるが、弁慶(男女蔵丈)がそれを阻む。
…さて、安徳帝を預かったはいいが、義経はこの後滅ぼされてしまう。安徳帝はどうなったの? この演目は二段目で、三段目がすし屋、四段目が狐忠信の話らしいけど、河連法眼館に安徳帝もいたの? 全部通しで見たら謎が解けるの? 私が何か激しく勘違いしてるの? それとも、そこは突っ込んじゃいけないところ? |
| 感想 その2 |
|
19日1部を1階真ん中辺り、2部を3階1列目上手側、20日1部を3階1列目真ん中辺りで観劇。
3階上手側はこんな眺め。
3階中央はこんな眺め。
上から見ると、お里が膝の上に右の袖を乗せて手を乗せる姿や、右京さんが「手討ちにしてくれる」と刀に手をかけた時に長袴がびろろんと前に広がる様子が綺麗に見えた。(勘太郎丈はすいーすいーと動いているけど、長袴で歩くのって難しそう。) お年玉挨拶 皆、「3月に歌舞伎座で『義経千本桜』の通しが上演されるので、ぜひお越しください」と宣伝していた。
19日1部は男女蔵丈。
19日2部は亀鶴丈。
20日1部は獅童丈。 すし屋
愛之助丈が「芝居は3回観ても、毎回新しい発見がある」というようなことをインタビューで言っていたが、私は見るたびごとに維盛(七之助丈)が嫌いになっていった。 首実検の時は、梶原(獅童丈)だけでなく、権太(愛之助丈)の表情をちらちらと見ていた。権太にとっては命懸けのペテンだったんだよなぁ。最期、権太が満足そうな表情になったのが救い。 身替座禅 勘太郎丈の右京は「うふふふ」と笑っても、泥酔しても、可愛げがあるなぁと思った。手を合わせて山の神の様子をうかがう姿が可愛かった。私みたいな初心者にも、踊りが上手いのがよくわかった。(が、どこがどう上手いかと問われたら答えられない。)
1部と2部で「あ、違う」と気付いたのが下の箇所。 渡海屋・大物浦
上からだと全体が見渡せるけど、これは近くで観た方が迫力があってよかったかも。 |
| おまけ 13日編 |
 
浅草について、まずはおまいり。
観劇後仲見世通りを歩いたら、半分くらいのお店が閉まっていて、開いているお店も閉店準備をしていた。ちょっと寂しかったなぁ。その後、東京で一人暮らしをしている友達と待ち合わせてイタリアンの食べ放題へ行く。美味しかった。食べ過ぎた。
愛之助丈に届いていたお花。
仁左衛門丈(孝夫時代)の手形。
公会堂の近くにいた猫。
見えにくいけど、のぼり。
通りにはまねき?が… |
| おまけ 19, 20日編 |

舞台写真は、愛之助丈は22種類。
2階席ロビーからの眺め。
4人分のお年玉挨拶を聞くとポスターがもらえるということで、もらってきた。(部屋には貼らないけど、せっかくなので。) 別の回を4回観劇すればいいのではなく、あくまでも挨拶4人分なのね。わざわざ半券とお年玉挨拶の表と照らし合わせてたよ。
愛之助丈ののぼり。
最後にちょっと愚痴。 |
| 「すし屋」の悲劇 |
|
「すし屋」という物語が、何故こんなに切なく悲しいのか考えてみた。親子の別れや、権太の命懸けの策が相手に悟られていたこともさることながら、私は「惟盛ってそこまでして助ける価値があったの?」という疑問に行き着いてしまったことが一番悲しい。
だいたい、この惟盛って人は何のために生き延びようとしているの?
あと、若葉の内侍も好きになれない。
そして何より、惟盛のお里への仕打ちは許しがたい。山陰右京さんよりよっぽど女の敵だ。
お里だって「雲居に近いお方に、すし屋の娘が惚れられようか」ということがわかっている。最初から三位の中将が相手と知っていれば、一夜の情けを一生の思い出としたかもしれない。しかし、弥助として手を出しておいて、「実は惟盛です。あなたを妻にはできません」ってのは、結婚詐欺だぞ。
…なんだか、単に「惟盛嫌い!」というだけの話になってきたが、長々と書きたくなるほど惟盛に腹が立って仕方がなかったのだ。 |