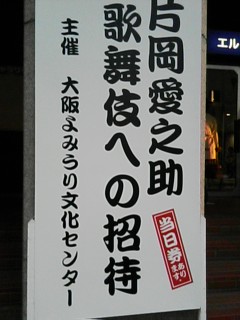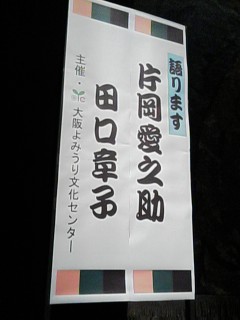前方中央で観劇(劇、ではないけど。)
覚えてる部分を少しだけレポ。
聞き間違い、覚え間違いなどあったら、ごめんなさい。
「第一部 語ります」
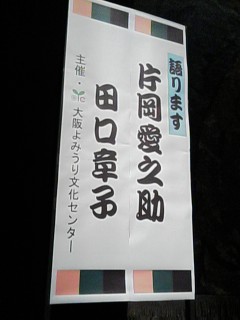
最初、司会のお姉さんが登場。
続いて田口章子先生と愛之助丈が登場。愛之助丈はスーツ姿。大向こうが掛かってた。
まず、この会場(=エル・シアター)が思い出の劇場であるというお話から。
「若鮎の会」の第1回目がこの会場だったそうだ。(当時、愛之助丈は8歳くらいの子供)
十三代目さんや松嶋屋の三兄弟が指導してくれて、最初は少しだけ出演してくれたのだとか。(チケットを売らないと成り立たないから。) 愛之助丈も、子供ながらに客入りを気にしていたそうだ。
愛之助丈「終わったら、皆でお金の計算でした。僕も数えた覚えがあります」
愛之助丈はこの公演を引き受けたとき、「エル・シアター」が昔の「労働会館」だということをわからなかったらしい。階段の匂いは昔と変わらないんだとか。
愛之助丈の生い立ち、部屋子になったいきさつ、養子になったいきさつを語る。(いろいろなところでお話されていることなので、割愛)
去年7月の『鳴神』代役の話。
愛之助丈「僕、海老蔵さん大好きなんです。すごくいい人なんですよ。心が熱い人なんです」
テレビのトーク番組が1時間だと、収録は2時間。オンエアされる箇所によって、誤解されたりすることもあって難しい、みたいなことを言っていた。(…なので、トークショウのレポはあまりしない方がいいのかなぁと思ったけど、少しだけ)
海老蔵丈は『鳴神』が終わると、顔が鳴神上人のまま、愛之助丈の楽屋に来て、「大丈夫? 顔色悪いんじゃない?(←声真似)」と体調を気遣ってくれたんだそう。
海老蔵丈「冷蔵庫開けていい?」
愛之助丈「どうぞ」
海老蔵丈「これ、身体に悪いから、全部捨てて!」
愛之助丈は「捨てちゃあかんやろー」と思ったらしいが、海老蔵丈は代わりに身体にいいものを入れておいてくれたのだとか。
昼夜5本に出ている愛之助丈の身体を一番心配してくれたのが海老蔵丈だったそう。
愛之助丈「その彼が…(怪我で休演) その日、13日の金曜日だったんですよ」
代役初日、御簾が上がったときに拍手をもらって「そんなに拍手されたら、台詞忘れるー! 最初の台詞はなんやったっけ? 落ち着け落ち着け」、坊主二人が引っ込むときは「僕も一緒に連れてってくれー! 置いてくなー! あー、行っちゃった。あと40分くらいどうしよう…」と思っていたとか。
海老蔵丈に教わって成田屋さんの型で演じたらしい。
浪花花形歌舞伎の「妹背山婦女庭訓」について。
鱶七は吉右衛門丈に習ったそうだ。。「のびのびと大きくやって」と教わったとか。
田口先生「鱶七はお三輪を殺しておいて、『あっぱれ、北の方』って… 鱶七っていい人? 悪い人?」
この辺りで、田口先生が強引に「お三輪みたいな健気なタイプはどうですか?」「好みの女性は?」「独身ですか?」などという超変化球を投げる。
先生、ちょっと強引過ぎ(笑)。愛之助丈もたじたじだった。
愛之助丈「恋愛している暇がないんですよ。イイワケって言われるんですけど… 出会いがないんですよ」
今後の仕事の紹介もあり。
愛之助丈「新入社員の歓迎会とか人事異動とか言わないで、ぜひ(浪花花形歌舞伎を)見に来てください」
↑愛之助丈はお勤めの経験がないため、お友達に言われて、初めて歓迎会やら人事異動やらの季節ということを知ったらしい。
七月松竹座の演目は決まりつつあるけれど、まだ言えないそうだ。八月花形新派公演『紙屋治兵衛』では、秀太郎丈が指導(監修だったかな?)してくださるのだとか。
映画で丸刈りになるそうで、すごく悪い役で1シーンとのこと。あと、秋にも映画の予定があって、名古屋ロケだそう。
上方歌舞伎について。
歌舞伎座の前を歩いているお客さんは「今月、○○が来てる」と役者の名前が出てくる。しかし、松竹座の前のお客さんは「あ、歌舞伎が来てる」と“歌舞伎”でひとくくり。大阪でたくさん芝居を開けたい。
ぜひ、歌舞伎を見たことのない人を劇場につれてきてほしい。見たことないものに一万円は出せないと思うから、最初は3階で見てもらって、面白いと思ってくれたら、次は2階や1階で見てもらえたら。
今は何でも東京発信だけど、大阪で作ったものを東京へ発信したい。
…と、いうようなことを熱く語っていた。
愛之助丈はリラックスしているように見えた。トークはとても面白かった。
文字じゃ伝わらないのが残念。
「第二部 見せます」
10分の休憩の後、羽織袴(薄いグレーの紋付)に着替えた愛之助丈が登場。
それから、千蔵丈と松之丈が登場。(お二人は黒の紋付)
愛之助丈は千蔵丈の紹介で喋る喋る。
「千蔵さんみたいな大きな顔になりたい(とかいう感じのこと)。歌舞伎役者は顔が大きい方がいいんですよ」「十三代目の最後のお弟子さん」「(視力の衰えた)十三代目をおんぶした役者は彼くらい」「最近は、殺陣師として重要な仕事をまかされることもある」「馬と言えば千蔵さん」「今月の檀特山で山城屋さんの馬の中に入ってる。…白馬ですよ」
散々突っ込みを入れて、ようやく次へ… と思ったら、思い出したかのように「子供さんが生まれたばかりなんですよ。今日、連れてきてくれると思ったのに…」って、どこまででも突っ込み続ける勢いだった(笑)。 千蔵さん、いい人だ…
それから、後ろの方で控えていた松之丈を前の方へ引っ張ってくる。
愛之助丈「僕の弟子になりたいという奇特な男がいるとききまして、『僕には無理です』と何度もお断りしたんですよ」
弟子を持つということは人一人の人生を預かることになるからだそう。それでも、弟子を持った方が責任が出来ていいだろう(というようなこと)を言われて、引き受けたのだとか。
愛之助丈「その、奇特な男が彼(=松之丈)です」
3人で木刀を持って、立ち回りを実演。
「ヤマガタ」「カラウス」「霞」「天地」「柳」「鬼飛び」などを披露。
附け打ちさん(狂言方の小西さん)と鳴り物(録音されたテープ)も入る。
それから、客席から参加者をつのったら、希望者が多かったのでじゃんけんで6人を決める。
千蔵丈と松之丈のお手本に合わせて6人が真似をするんだけど、流石に舞台がせまい。
松之丈が金屏風に木刀をコツンと当ててしまい、愛之助丈に「壊したら、弁償しないといけなくなる」と突っ込まれてた(笑)。松之丈、パッと見はコワモテだけど、にこにこした顔は優しそうだった。
参加したお客さんには手拭がプレゼントされ、お客さんは客席へと戻る。
その後、愛之助丈、千蔵丈、松之丈で立ち回り。(この立ち回りを考えたのは、千蔵丈なんだって。)
これが思ったより長くて、かっこよかった。大向こうも掛かってた。松之丈はトンボ返ってた。
優しいお顔立ちの愛之助丈が素顔で見得をすると、ちょっと不思議な感じ。
愛之助丈「練習の中で、一番うまくできました」
皆さん、本番にお強いのね。
最後は大阪締め。
一部のトークが少し時間オーバーしたけど、終了時間はぴったりだった。
いやー、いいもの見たなぁ。



 年 (平成
年 (平成
 年)
年) 月
月