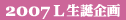
▼ L視点
(0802/鹿嶋)
「――あっ、今日はハロウィンか」
目が覚めると部屋は黒とオレンジに彩られていた。色とりどりの菓子。そしてジャック・オ・ランタン。
呟く月は何気ない様子を装っても声が明るく弾んでいる。
彼にも年相応なところがあるのだ。そう微笑ましい気持ちになるよりもさきに、彼が発した声のなかどこかに演技の痕跡がないか、まず疑ってしまうのは仕方がない。これはほとんど職業病だ。
しかも彼、夜神月はキラであるとこの私が確信している人物なのだ。――いや、確信していた、と云いかえようか。今になってその確信は少しずつ揺らぎ始めている。
まるでそれを裏づけでもするように、今日もまた彼の声から不審な点は見当たらなかった。
一ヶ月に及ぶ監禁生活。そこから解放されたかと思えば今度は私と手錠で繋がることを余儀なくされ、この捜査本部で結局また軟禁されているのと変わらない。たとえ彼が強靭な精神力を持っていようが、さすがに疲れもでてくるだろう。
こんな飾りつけひとつにさえ慰められるのかカボチャのひとつを手に取ると、月は愛しそうに眺めている。
彼が監禁を解かれてから、月に関して私の勘は外れっ放しだ。
――夜神月、キラではないのか?
「なあ竜崎、ハロウィンはもともとケルトの収穫祭から来てるって……おまえなら知ってるか」
「ええ、まあ……」
頷く私に月は苦笑ともつかない独特の表情を浮かべてみせた。その顔が思いのほか幼くて私は一瞬胸を突かれる。
今は会えない家族のことでも想うのか、遠く懐かしいものでも見るように月はじっと己の手許へ視線を落としす。
10月31日。
多くのものにとっては今日はハロウィンを意味する日だ。だが私に取ってこの日はもうひとつの意味を持つ。
そう――今日は私の誕生日なのだ。
「あれ、何だか良い匂いがする」
不意に顔をあげ月がぴくんと鼻をひくつかせる。小動物めいたいとけない仕草に自然と笑みが零れてしまう。ソファに腰を降ろしながら私は月に応えて云った。
「ワタリがケーキを焼いているようです」
「へえ、楽しみだな」
必ず毎年私の誕生日にワタリは特製のケーキを焼く。制約の多い人生のなか数少ない楽しみのひとつだ。
誰彼かまわず個人情報を明かせるような立場ではないし、それだけのことでも充分だと思って生きてきたが。
今年に限っては、月にも私の誕生日を祝って欲しい。そう思ってしまうのを止められなかった。
キラかも知れない、いや私はきっとキラだと確信している。その夜神月に己の誕生日を明かすのはあまりにも馬鹿げたことだろうか?
こんな些細な情報で、まさか私の本名まで辿り着くとは思えないが……。いや、油断してはならない。彼なら充分その可能性も考慮しなければ。ああ、だが。
「どうした竜崎、今日はずいぶん大人しくないか?具合でも悪い?」
ソファが軋んで音を立てる。云いながらひょい、と月が私の顔を覗き込んだ。顔が近い。
額に落ちかかる前髪を月が軽く払いのける。息が触れ合う至近距離でも毛穴の見えない滑らかな肌、飴色の瞳、けぶるような長い睫、少し心配そうに眉を寄せ、うっすらとあいた仄赤い唇から白い歯とピンクの舌が覗いて見える。
無防備すぎますよ、月くん……。
このまま簡単に唇を奪えそうで私は理性と戦った。が、ふと思うのは、これは戦う必要があるのだろうか?素直に負けてしまいたい。
誕生日だからキスさせろとか。駄目か?
「あのですね、月くん……」
「ん?」
こちらを見上げ首を傾げる月を見て、誘われるまま思わずぐらりとよろめきかけ。
まるでそれを見越していたようなタイミングで部屋の扉がノックされる。はい、と応えて月はさっさと立ち上がった。
「…………」
今、さりげなく私の顔面を押し退けなかったか?
それにしてもこの私を惑わすとは、もしやこれもキラとしての策略なのか。私としたことがあやうく罠にかかるところだった。まさに間一髪。
ふう、と安堵の息を漏らしつつ。
それにしても邪魔したのがもし松田だったら殺す、と扉のほうを伺えばワタリがケーキを持ってきたところだった。残念なことに松田ではなかったが、やはりあとであの馬鹿を蹴っ飛ばそう。そう私は心に決めた。
「竜崎、ケーキ出来たって!」
トレイに乗せたホールケーキを月が私に掲げて見せる。ワタリめ、どうやらまた腕を上げたらしい。
ハロウィンの飾りつけにはしゃいでいるのか、珍しく今日は月のテンションが高い。彼が笑えば部屋が明るくなるようだ。
「ええ、今行きます」
ワタリが静かに微笑みながら丁寧に紅茶をいれている。
まあ実のことを言えば、私だって内心嬉しい。ワタリのケーキは絶品だし、月がこれだけ楽しそうに笑っていてくれるのならばそれだけでも充分に……。
立ち上がろうとしてふと何かが引っかかる。無意識のうち力任せに引っ張ってから、私はソファの肘掛けに手錠の鎖が絡まっていることに気づいた。
「――――っ!」
勿論。手錠のさきには月がいて、普段の彼ならこれくらいでよろめきこそすれ転ぶことなどあり得なかったが、運悪く今日は彼の足許にカボチャ細工が転がっていた。
ケーキは宙へ放り出され、万有引力に乗っ取って、彼の上へと降り注いだ。
部屋に立ち籠めるのは、いれたての紅茶の芳しい香りと噎せ返るような甘い匂い。
「ただいま新しいものを用意して参ります」
ほとんど表情を変えぬままワタリは静かにそう云った。ああワタリ、おまえの忍耐力は本気で尊敬に値する。
そのまま彼が立ち去ると、部屋のなかには私とケーキまみれの月だけが取り残された。
まあ。さすがにコレはふたりで片付けろと言うことなんだろう。
私は月のもとへ赴くと彼のまえにしゃがみこんだ。
「何をやってるんですか、月くん」
「〜〜っ、竜崎おまえは!何を人ごとみたいにっ……!」
「ですが、ケーキをひっくり返したのは月くんですよ?」
「くそっ、おまえが手錠を引っ張るからだろう!」
濡れた犬のように月がぶるぶると頭を振ると、スポンジの残骸がカーペットのうえに飛び散った。反射的に勿体ない、と思ってしまう。
「うぅ、何だよもう、ベタベタして気持ち悪い……」
高い鼻梁から唇にかけて、溶けかけた白い生クリームがゆっくり滴り落ちて行く。嫌そうに月はそれを指で拭った。
いつも綺麗に整えられた前髪をねっとり汚す白濁色。男なら誰だって、アレを想像せずにはいられない。
「月君、このケーキは朝からワタリが作ってくれたんですよ。材料だって事前に用意し、手間暇かけて仕込んだものです」
「なに……」
戸惑う月の指を掴む。生クリームで汚れたそれを自分の口へと差し入れた。
甘い。舌が蕩けそうだ。
爪の形を確かめて、指の股に堪ったクリームをチロチロと舌でこそげとる。揺れる瞳。合わせた視線を逸らさぬまま、指の一本一本を私は執拗にねぶリ続けた。
びくり、と肩がおののくが私は彼を許さない。
抵抗したいだろうに。月は自分の汚れを気にしてか、私に触れるのを躊躇う様子だ。
「竜崎、も・止せっ……」
どこか切羽詰まった掠れた声、嫌がる言葉なのに甘く響く。
もう生クリームの味がしなくなっても、何故こんなに美味しいのだろう。足りない、もっと、食べたい。
掌の真ん中を集中的にくすぐりつつ、手首のくるぶしへ私は軽く歯を立てた。
「んっ……!」
まるで電流でも流されたように、月はびくりと身を竦ませた。頬は僅かに紅潮し吐き出す息が震えている。
まだ気が済んだわけではなかったが、名残り惜しくも解放する。彼の手は私の唾液でドロドロだ。
小さく安堵の吐息を漏らし、ついではっとしたように月はきつく言い放った。
「何するんだよ、この変態!」
まったく、そんな潤んだ瞳で睨まれてもこちらは昂奮するだけなんだが……。
続く月の罵詈雑言を意識の外へ追いやって私はしばし考えた。
せっかくワタリが用意してくれた私の誕生日ケーキ、それを台無しにしてくれた月を一体どうすべきか。
さて。
目が覚めると部屋は黒とオレンジに彩られていた。色とりどりの菓子。そしてジャック・オ・ランタン。
呟く月は何気ない様子を装っても声が明るく弾んでいる。
彼にも年相応なところがあるのだ。そう微笑ましい気持ちになるよりもさきに、彼が発した声のなかどこかに演技の痕跡がないか、まず疑ってしまうのは仕方がない。これはほとんど職業病だ。
しかも彼、夜神月はキラであるとこの私が確信している人物なのだ。――いや、確信していた、と云いかえようか。今になってその確信は少しずつ揺らぎ始めている。
まるでそれを裏づけでもするように、今日もまた彼の声から不審な点は見当たらなかった。
一ヶ月に及ぶ監禁生活。そこから解放されたかと思えば今度は私と手錠で繋がることを余儀なくされ、この捜査本部で結局また軟禁されているのと変わらない。たとえ彼が強靭な精神力を持っていようが、さすがに疲れもでてくるだろう。
こんな飾りつけひとつにさえ慰められるのかカボチャのひとつを手に取ると、月は愛しそうに眺めている。
彼が監禁を解かれてから、月に関して私の勘は外れっ放しだ。
――夜神月、キラではないのか?
「なあ竜崎、ハロウィンはもともとケルトの収穫祭から来てるって……おまえなら知ってるか」
「ええ、まあ……」
頷く私に月は苦笑ともつかない独特の表情を浮かべてみせた。その顔が思いのほか幼くて私は一瞬胸を突かれる。
今は会えない家族のことでも想うのか、遠く懐かしいものでも見るように月はじっと己の手許へ視線を落としす。
10月31日。
多くのものにとっては今日はハロウィンを意味する日だ。だが私に取ってこの日はもうひとつの意味を持つ。
そう――今日は私の誕生日なのだ。
「あれ、何だか良い匂いがする」
不意に顔をあげ月がぴくんと鼻をひくつかせる。小動物めいたいとけない仕草に自然と笑みが零れてしまう。ソファに腰を降ろしながら私は月に応えて云った。
「ワタリがケーキを焼いているようです」
「へえ、楽しみだな」
必ず毎年私の誕生日にワタリは特製のケーキを焼く。制約の多い人生のなか数少ない楽しみのひとつだ。
誰彼かまわず個人情報を明かせるような立場ではないし、それだけのことでも充分だと思って生きてきたが。
今年に限っては、月にも私の誕生日を祝って欲しい。そう思ってしまうのを止められなかった。
キラかも知れない、いや私はきっとキラだと確信している。その夜神月に己の誕生日を明かすのはあまりにも馬鹿げたことだろうか?
こんな些細な情報で、まさか私の本名まで辿り着くとは思えないが……。いや、油断してはならない。彼なら充分その可能性も考慮しなければ。ああ、だが。
「どうした竜崎、今日はずいぶん大人しくないか?具合でも悪い?」
ソファが軋んで音を立てる。云いながらひょい、と月が私の顔を覗き込んだ。顔が近い。
額に落ちかかる前髪を月が軽く払いのける。息が触れ合う至近距離でも毛穴の見えない滑らかな肌、飴色の瞳、けぶるような長い睫、少し心配そうに眉を寄せ、うっすらとあいた仄赤い唇から白い歯とピンクの舌が覗いて見える。
無防備すぎますよ、月くん……。
このまま簡単に唇を奪えそうで私は理性と戦った。が、ふと思うのは、これは戦う必要があるのだろうか?素直に負けてしまいたい。
誕生日だからキスさせろとか。駄目か?
「あのですね、月くん……」
「ん?」
こちらを見上げ首を傾げる月を見て、誘われるまま思わずぐらりとよろめきかけ。
まるでそれを見越していたようなタイミングで部屋の扉がノックされる。はい、と応えて月はさっさと立ち上がった。
「…………」
今、さりげなく私の顔面を押し退けなかったか?
それにしてもこの私を惑わすとは、もしやこれもキラとしての策略なのか。私としたことがあやうく罠にかかるところだった。まさに間一髪。
ふう、と安堵の息を漏らしつつ。
それにしても邪魔したのがもし松田だったら殺す、と扉のほうを伺えばワタリがケーキを持ってきたところだった。残念なことに松田ではなかったが、やはりあとであの馬鹿を蹴っ飛ばそう。そう私は心に決めた。
「竜崎、ケーキ出来たって!」
トレイに乗せたホールケーキを月が私に掲げて見せる。ワタリめ、どうやらまた腕を上げたらしい。
ハロウィンの飾りつけにはしゃいでいるのか、珍しく今日は月のテンションが高い。彼が笑えば部屋が明るくなるようだ。
「ええ、今行きます」
ワタリが静かに微笑みながら丁寧に紅茶をいれている。
まあ実のことを言えば、私だって内心嬉しい。ワタリのケーキは絶品だし、月がこれだけ楽しそうに笑っていてくれるのならばそれだけでも充分に……。
立ち上がろうとしてふと何かが引っかかる。無意識のうち力任せに引っ張ってから、私はソファの肘掛けに手錠の鎖が絡まっていることに気づいた。
「――――っ!」
勿論。手錠のさきには月がいて、普段の彼ならこれくらいでよろめきこそすれ転ぶことなどあり得なかったが、運悪く今日は彼の足許にカボチャ細工が転がっていた。
ケーキは宙へ放り出され、万有引力に乗っ取って、彼の上へと降り注いだ。
部屋に立ち籠めるのは、いれたての紅茶の芳しい香りと噎せ返るような甘い匂い。
「ただいま新しいものを用意して参ります」
ほとんど表情を変えぬままワタリは静かにそう云った。ああワタリ、おまえの忍耐力は本気で尊敬に値する。
そのまま彼が立ち去ると、部屋のなかには私とケーキまみれの月だけが取り残された。
まあ。さすがにコレはふたりで片付けろと言うことなんだろう。
私は月のもとへ赴くと彼のまえにしゃがみこんだ。
「何をやってるんですか、月くん」
「〜〜っ、竜崎おまえは!何を人ごとみたいにっ……!」
「ですが、ケーキをひっくり返したのは月くんですよ?」
「くそっ、おまえが手錠を引っ張るからだろう!」
濡れた犬のように月がぶるぶると頭を振ると、スポンジの残骸がカーペットのうえに飛び散った。反射的に勿体ない、と思ってしまう。
「うぅ、何だよもう、ベタベタして気持ち悪い……」
高い鼻梁から唇にかけて、溶けかけた白い生クリームがゆっくり滴り落ちて行く。嫌そうに月はそれを指で拭った。
いつも綺麗に整えられた前髪をねっとり汚す白濁色。男なら誰だって、アレを想像せずにはいられない。
「月君、このケーキは朝からワタリが作ってくれたんですよ。材料だって事前に用意し、手間暇かけて仕込んだものです」
「なに……」
戸惑う月の指を掴む。生クリームで汚れたそれを自分の口へと差し入れた。
甘い。舌が蕩けそうだ。
爪の形を確かめて、指の股に堪ったクリームをチロチロと舌でこそげとる。揺れる瞳。合わせた視線を逸らさぬまま、指の一本一本を私は執拗にねぶリ続けた。
びくり、と肩がおののくが私は彼を許さない。
抵抗したいだろうに。月は自分の汚れを気にしてか、私に触れるのを躊躇う様子だ。
「竜崎、も・止せっ……」
どこか切羽詰まった掠れた声、嫌がる言葉なのに甘く響く。
もう生クリームの味がしなくなっても、何故こんなに美味しいのだろう。足りない、もっと、食べたい。
掌の真ん中を集中的にくすぐりつつ、手首のくるぶしへ私は軽く歯を立てた。
「んっ……!」
まるで電流でも流されたように、月はびくりと身を竦ませた。頬は僅かに紅潮し吐き出す息が震えている。
まだ気が済んだわけではなかったが、名残り惜しくも解放する。彼の手は私の唾液でドロドロだ。
小さく安堵の吐息を漏らし、ついではっとしたように月はきつく言い放った。
「何するんだよ、この変態!」
まったく、そんな潤んだ瞳で睨まれてもこちらは昂奮するだけなんだが……。
続く月の罵詈雑言を意識の外へ追いやって私はしばし考えた。
せっかくワタリが用意してくれた私の誕生日ケーキ、それを台無しにしてくれた月を一体どうすべきか。
さて。