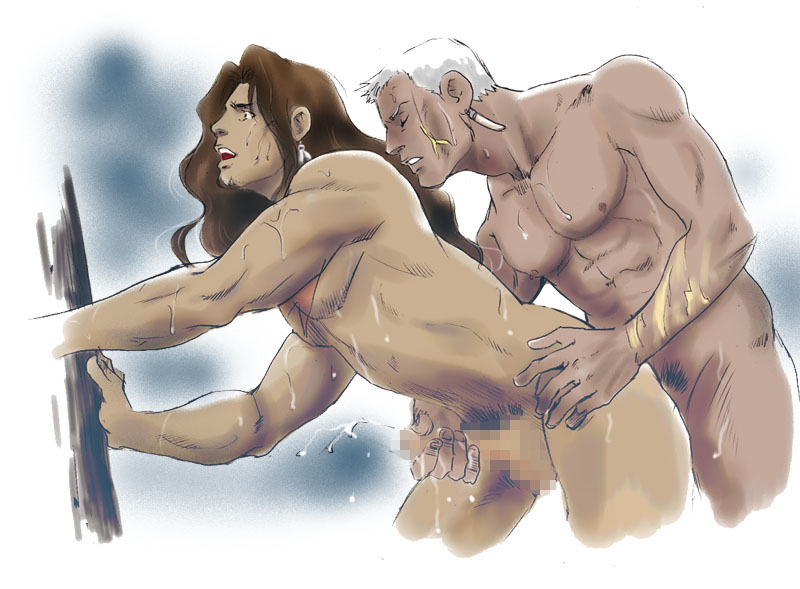
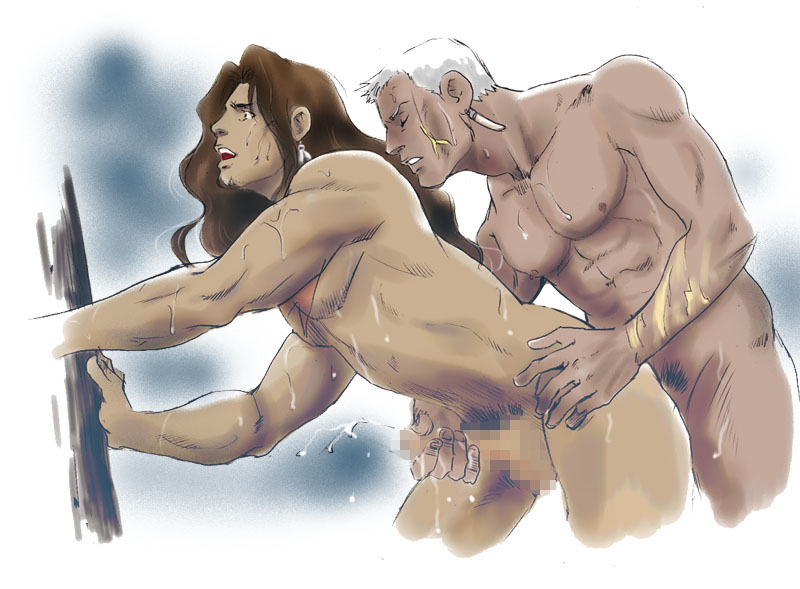
|
昼なお暗い森の奥深くでは、獣の呻きにしか聞こえぬ恐ろしい声がずっと響いていた。もし近くを村人が通りかかったならば、猪か、狼か、熊かはわからぬが、何か獰猛な野獣が潜んでいるのだと思って、逃げ出してしまうに違いなかった。
獣の正体を見たところで、彼らの恐怖は頂点に達したに違いない。 褐色の肌の軍師と、同じ褐色の肌のもう一人の侍とが、素裸で喘ぎ、汗まみれで交わっているのだった。 「おぬし、聞くところによると、古女房がいるくせに、近頃ではもう一人の愛人ともよろしくやっておるのだそうだな。全くいい気なものよ」 「そういうおぬしも……、新しい思い人を見つけたのであろうに……」 「某は、おぬしのように気楽にはいかぬ。苦しい恋よ……。だからやりたい放題のおぬしが妬ましくてならぬのだ……」 カンベエが一本の大木に両手をつき、ようやく身体を支えていると、ゴロベエは腹から逸物が突き抜けてしまえとばかりに、がつがつと後ろから貫いて来る。 「おぬしなど、こうしてくれる。夜に古女房や愛人を抱こうとしても、もう腰が動かぬほどに、精が一滴も出ぬほどに、搾り取ってくれようぞ……」 「ああ〜っ!」 軍師が腰を震わせると、樹齢を経た木の幹に、もう幾度めかの濃く白い液体がぴしゃりと吐きかけられた。 |