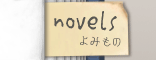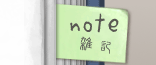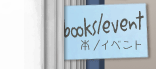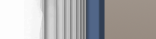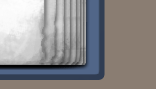派遣少女――Agent.2 錦土更紗――
オレ、山下は入社三カ月にして早くも後悔していた。
憧れの銀行業界に入って、たったの三カ月だ。
「早く資料持ってこい!」
なんだよ。個人融資の膨大すぎる書類の山は。
最初は真剣に嫌がらせなんじゃないかと悩んだ。悩みぬいた。
下手したら広辞苑を超える厚さの書類を持って、課長に見せる。
昨日徹夜で頑張った、住宅ローンの書類だった。
「いきなり間違ってんじゃねーか!!」
なんだと、このハゲ親父。課長だからって適当なこと言ってんな。
「ここ、見ろ!」
「なんですか」
徹夜で一生懸命仕上げた書類に、いきなり不備があるわけがないだろ。
オレは不機嫌を顔前面に押し出し、書類を覗き込んだ。
「……あ」
「あ、じゃねえ!! ふざけんな! どうすんだこれ」
「…………」
「二万の収入印紙を貼るところに、二十万の印紙貼ってんじゃねーか!」
言われるまでもない。二十万円と書かれた印紙が、オレの目にも見えている。
「お前、もう入社三カ月だよな」
「はい」
それがどうした。
「二千万円の融資に必要な収入印紙は?」
「二万円ですか」
そんなことは知っている。今まで毎日間違えずにやっていたのだから。
「――ですか、じゃねえだろ! 割り印まで押しやがって」
割り印とは、印紙と台紙の境目に押された印鑑の事だ。
なんて説明してる場合じゃねえ!
事の重大さにいまさら気付いた、オレ。
「剥がしても…ダメですかね」
「印鑑押されてるだろうが」
「上から二万円の収入印紙を貼り付けても?」
「なんの解決にもなってねえだろうが! 二十万の収入印紙をどうすんだって聞いてんだ」
それはこっちが訊きたい。どうすればいいんだ。
「差額十八万。お前払うか」
「……すみません」
徹夜の残業なんかさせるからだ。
腹の中は煮えくりかえっているが、ミスはミス。
社会人として謝らなければならなかった。
「どうすんだこれよ」
一転して、低い声を出して脅してくる。
だから、どうするのかはオレが訊きたいんだっての。
「あの、失礼いたします」
同僚の佐藤さんだろうか。
可愛い声が響く。
怒られているオレを見かねてお茶でも持ってきてくれたのか。
「収入印紙の間違いでしたら、税務署で還付手続きを受ければよろしいかと」
佐藤さんじゃない。あの子にこんな知識はない。
愛想だけで生き抜いているような女の子なのだ。そんなところが可愛いと評判でもあるのだが。
「割り印を押す前に確認すべきでしたね」
当然のことを言う、誰かの可愛い声。可愛いくせに厳しいことを言いやがって。
オレは声のする方を見た。
「――なんだお前」
こんなチープな言葉しかでなかった。
そこにいたのは、長い黒髪が綺麗な眼鏡の少女。
少し吊り上った大きな目が、黒ぶち眼鏡の奥から挑戦的に輝いている。
子どもが嫌いなオレなのだが、こいつは『可愛い』。
「税務署の位置はわかりますね?」
「だからお前はなんなんだ」
オレや課長より流暢な日本語を使う少女に、不信感を覚えた。
「私は、錦土更紗(にしきど さらさ)。今日からこの個人融資部門に配属されました」
少女はそう言って、オレに頭を下げる。
八歳くらいか。いとこの娘と同じくらいの歳に見えるが。
「まあ、配属と言っても派遣社員なのですが」
そう言って、眼鏡の位置をくいっと直す少女。
課長はオレたちの様子を見て、にやにやと嫌らしい笑いを浮かべていた。
「可愛いだろう。『派遣少女』というサービスを頼んでみたんだが、お前よりよほど役に立ちそうだな」
このロリコンハゲ親父が。
叫びそうになったが、ぎりぎりのところでオレの理性が言葉を飲み込んだ。
よくやったオレの理性。
「そうですね。還付手続きに行ってきます」
「心配なので、私もついていきましょうか」
「おう、そうしてもらえや」
真面目な表情の美少女と、にやにや笑うハゲ親父。
その対比に混乱したオレは、咄嗟にこう言っていた。
「――結構です」
「そうですか」
オレは、マグマのように煮え立った腹を抱えて、税務署へと走った。
「おいこら!」
書類を忘れた。
すぐに課長から書類をひったくって、再度税務署へ走った。
「その企業のコンプライアンスは――」
錦土更紗が、小さい体を精いっぱい伸ばして企業融資部の奴らと話し合っている。
っていうか、お前は個人融資部に派遣されたんじゃないのか。
オレの視線に気づいた少女は、こちらに近づいてきた。
「なんですか」
「いや、なんでもない」
「早く書類を片付けないとまた徹夜ですよ」
可愛くないやつ。
「これを差し上げますから、頑張ってください」
「ん?」
そういって、少女が差し出してきたのはいびつな形のくまのクッキーだった。
「友人が作ったのですが」
うまい。味は文句なく美味しかった。
「お前が作ったんじゃないのか?」
オレは少女に問いかけた。
よく考えたら小学校低学年程度の少女に対する口の聞き方じゃないよなとは思いつつ。
「私は、手先が器用ではありませんし」
少し恥ずかしそうに俯く、更紗。
なんだ可愛いじゃないか。
「そんなことより、私の友人の大切なクッキーを差し上げたからには頑張って仕事を終わらせてください」
前言再撤回。可愛くねー奴。
「おい、山下」
昼過ぎ頃、オレを呼ぶハゲ課長の声。
「なんでしょうか、は――課長」
危ない。はげと呼ぶところだった。
「ぼさっとしてんな、走ってこい!」
「はい」
出来る限りゆっくりと走るオレ。
「この書類を今日中に処理してくれ」
「――は?」
課長の机の上には、ちょっと尋常じゃない量の書類が載っていた。
「これくらい余裕だろ」
「ちょっと待ってくださいよ」
自分の仕事も定時では終わらない量が山積みになっている。
その上、広辞苑三冊分もの仕事が追加されるなど、いじめに等しい。
「無理ですよ、今日中なんて」
「更紗ちゃんをお前に付ける」
更紗『ちゃん』と来たか。このロリコン。
「仕事を教えながら、さらにこの書類の山をこなしてくれっていうことですか」
「違うな」
「違う?」
オレが訊き返すと、課長はにやりと顔を歪めて言った。
「更紗ちゃんの足を引っ張らないように、この書類を『やれ』って命令してるんだ」
「…………」
言い返す言葉もない。
「なんでオレなんですか」
「は?」
「オレじゃなくても暇な人はいるでしょう」
「ダメだな。みんな優秀だが忙しい」
「…………」
「それにな」
「…………」
「お前には妹がいたろう?」
「は?」
「だからだ」
「意味がわかりませんが」
「今にわかる」
わからん。
分かりたくもないし、歳の離れたうるさい妹がいるから子ども嫌いになったんだが。
その辺わかってんのか、はげ。
「とにかくやれ!」
オレはしぶしぶと、自分の机へ書類を運んだ。
もうすぐ自分の机ってところで、声をかけられた。
「重そうですね」
見りゃわかるだろ。
「錦土か」
「更紗の方が可愛くて気に入ってるのですが」
自分で言うか。
「それじゃ、錦土。この書類をやれってさ」
「はい。課長から伺ってます」
「できるわけないだろ」
「今日中には無理、ということですか?」
「そうじゃない。お前にできるわけがないと言ってるんだ」
少し悔しそうに俯く少女に、心がずきりと痛む。
言いすぎたか――
「あなたに――」
「ん」
少し優しい表情を浮かべようとして、オレにそんな表情なんか無いことに気付いた。
少女は、オレの目をきっとにらみ返して口を開いた。
「あなたにできることで、私にできないことはひとつもありません」
オレの表情が中途半端な状態でびしっと固まった。
可愛くねえやつ!
数時間後、もう一度思った。
「終わりましたよ」
「は?」
「ですから、書類の処理が終わりました」
「なんだって?」
どう考えても、徹夜しても終わらない量があったはず。
個人融資の書類は量が多く、本当に面倒なのだ。
客に提出してもらう書類の不備の確認ならまだいい。
面倒なのは信用情報の確認だ。
確定申告票の精査。融資対象の借金の状況を調べるための書類も必要なのだが、クレジット会社と銀行とで幾つかの手続きが必要になる。
細かく収入印紙もはらなけりゃならないし、文字の訂正には訂正印が必要だ。
とにかく面倒な作業なのだ。
それを――
「終わりましたが」
錦土更紗は、上目づかいでオレを下から覗き込む。
蛍光灯の光を映しこんだその目は、きらきらと輝いて眩しかった。
「本当にできたのか」
「どうぞご確認ください」
確認だけでも二時間かかった。
どれもこれも完璧の一言。
字もオレより上手いし、ミスは一つもない。
「すごいなお前」
オレの口から出たのは、正直なその言葉だけだった。
「どうも」
少し俯く少女は、ぶっきらぼうな口調に反して少し嬉しそうに見えた。
それでもオレは完全に打ちのめされていた。
「錦土っていま歳いくつなんだ?」
「八歳ですが」
「やっぱりか」
「やっぱり?」
「いとこの娘さんが八才なんだ」
「私と同い年なんですね」
なぜか、少し嬉しそうな少女。
「まあお前より可愛いけどな」
「…………」
言い返してこない。
なんかオレが悪いことしたみたいじゃないか。
「……どこで仕事なんか覚えたんだ?」
気まずくなったオレは、ふと訊いてみた。
オレも今年で二十五になるというのに、八歳の少女に負けているわけにいかない。
何か秘訣があるなら、八歳の少女からでも学んでやる。
「…………」
オレの方を見つめたまま、動かない少女。
「そんな小さいのに仕事ができてすごいな」
書類に目を落とす。
全ての書類が自分の『山下』という印鑑で決済されている。
本来は派遣の少女になど、書類を見せることさえ許されない。
それなのに、処理までさせてしまっている。
表沙汰になっては問題がある。
そこまで考えてオレの印鑑で書類の処理をしたのだろう。
抜け目のない少女だった。
「……暇だったから」
「ん」
少女が、オレをまっすぐ見つめたまま口を開いた。
「父さまも母さまもお仕事で忙しかったから」
少女の目から、視線をそらすことができない。
「私は、二人が好きなお仕事を覚えたかった」
少女は、目にかかった髪をすっとかきあげる。
細い指にペンダコが見えた。
「……そうか」
他に何を言えというのだ。
「父さまと母さまと同じことがしたい」
一人が寂しかった少女。
彼女は、自分が子どもだから一人ぼっちだと思ったのかもしれない。
大人になるために真剣に学んだのか。
「…………」
オレは何も言えずに、残りの仕事に取り掛かった。
少女も隣の机で、もうオレに声もかけずに黙々と別の作業をしている。
「よう」
「課長なんですか」
「もうちょっと仕事してけよ」
どさっと渡されたのは、法人部の決裁書類。
「法人部の仕事じゃないですか」
課長は、座っているオレをにやにやと見下ろしていた。
「お前簿記二級持ってないだろ。FPも」
簿記三級なら持ってるぞ。銀行入社前に取った。
だが、FPってなんだ。
「FPって必要なんですか」
「お前もしや、FP知らないんじゃないか」
「…………」
「ファイナンシャルプランニング技能士」
ああ、それか。
確か国家資格で、個人の資産形成に助言するプロというお墨付きが得られる資格だ。
日々忙しくて忘れていた。
「とにかく、法人部の仕事も経験しておくと試験の参考になる」
銀行はいくつになっても資格取得との戦いだと言う。
実際に先輩も、証券外務員の一般会員二種というよくわからない資格の取得に四苦八苦していた。
「資格が取れんと昇進も無いぞ」
「…………」
その瞬間に、定時を告げる十七時半のチャイムが鳴った。
「オレ、法人部の書類の処理なんかわかんないんスけど」
個人融資部の仕事だけでも、まだわからない部分があるというのに。
「私がさっき覚えましたので大丈夫です」
横から錦土更紗が口を挟む。
「いいです、オレがやります」
これ以上、少女に負けているわけにはいかない。
「そうか。オレは仕事が終わればなんでもいいからな」
「はい」
「それじゃ、俺は帰るわ」
人に仕事を預けて自分はすぐに帰ってしまう。
なんて無責任な上司なんだ。
お疲れ様です、と、いくつもの声が降っては消えた。
外は暗く、しんと冷えているようだ。
課長からもらった仕事も机から崩れそうなほど山積みのままだった。
「――この書類は、ここに気を付けて確認をして」
本当によく覚えているものだ。
少女は事細かにオレにアドバイスをくれた。
「あとはこのマニュアル通りに」
そう言って一つのファイルを差し出してきた。
「ありがとう」
オレの口から素直な言葉が出た。
少女が少し驚いた顔をしたが、一番驚いたのはオレ自身だ。
どうしたんだオレは。
「さて、やるか」
内容に目を通すと恐ろしいことがわかった。
全ての書類の決済期限が、明日か明後日。
今日中に片付けて、明日上司に見せないと大変なことになる。
法人部の奴ら、なぜこんなに書類を残しておいたんだ!
「頑張って終わらせてしまいましょう」
「おう」
オレと錦土更紗は同時に机に向かい、仕事にかかった。
マニュアルをめくりながら仕事をするうちに、だんだんと集中力が高まってきた。
仕事がどんどんと片付いてゆく――気がした。
「――っふ」
隣の少女が、小さく変な息を漏らす。
「?」
そちらを盗み見ると、真剣に書類に向かっている。
「――はあっ」
ごとん、と少女の頭が机に落ちる。
なんだ!?
「おいっ、どうした――!?」
少女の肩に手をかけると、その肩は熱かった。
「おいっ! お前」
顔が赤い。
息が荒い。
小さな肩が、荒く揺れている。
「なんでこんなになるまで黙ってた!」
少女の全身は異常なほど熱かった。
この熱さは、今発症したものではない。
今朝出勤してきた頃から具合が悪かったに違いない。
すでに皆帰ってしまっていて、オレの他には誰もいなかった。
「佐藤さんでもいれば――!」
彼女は体が弱く、大抵の薬を常備していた。風邪薬もあったろう。
だが、その彼女も今はいない。
「病院――!」
オレは、近くの病院を頭に思い浮かべる。
あった。ここからタクシーで五分の位置に内科が。
今の時間は午後八時。まだやっている保証はない。
そうでなければ、他に救急指定の病院は――
思案するオレの服の裾を、少女の小さな腕が引っ張ってくる。
「……仕事、終わらせないと」
そうだ。今日中に終わらせないと。
「私は大丈夫だから」
細い腕を机にかけて弱々しく起き上がる少女。
「仕事はちゃんとやらなくちゃ」
この、少女の仕事に対する責任感はなんだ。
オレは、昨日ここまでの想いで仕事をしていたか。
あまりの仕事量に不貞腐れて、手を抜いてはいなかったか。
「…………ふう、はぁ」
少女が重い息を吐く。
あれほど的確だった腕の動きが、今は緩慢で頼りない。
小さい肩が、まだ荒く上下している。
喉の奥からもひゅうひゅうと息が漏れているのが聞える。
「――待てよ」
オレはまた、少女の熱い肩に手をかけた。
「これは、お前の仕事じゃない。オレの仕事だ」
少女は熱で潤んだ瞳で、オレの事を睨む。
眼鏡が少しずれているのに、気付いていないのか直しもしない。
「……私を邪魔にするんですか」
「違う」
「子どもだから、任せられないんですか」
「……違う」
少女の目の潤みは、熱によるものだけなのか。
オレを見ていないように、少女の焦点は合っていなかった。
「子どもだから、お仕事なんかさせないって言うんですか――」
「…………」
厳しさのこもってきた少女の言葉に、オレは声をつまらせてしまう。
「お仕事させてくれないんですか……あなたも!!」
そこまで言うと、少女はまたごとりと机に頭を落とす。
「――あなたも、か」
想像に難くない。
少女の成長に、両親も最初は喜んだのだろう。
しかし、それでも自分の子ども。
付き合いなどで愛想笑いが必要なこともあれば、嫌な人間にへつらうことも必要なのが仕事の世界。
生臭いお金の話も聞かせたくはない。
オレだって、こんな少女をうちのハゲ課長の下に置いておきたくはない。
だから、両親はこんな優秀な少女に仕事をさせなかったに違いない。
「それが、くやしかったんだろうな」
少女が、熱い息を短くぜいぜいと吐き出す。
「お前は――」
本当に可愛くない奴だ、と言おうと思った。
だが、意に反してこんな言葉しかでなかった。
「――本当に可愛い奴だよ」
オレは、携帯を手にとって迷わず『ある番号』に電話をかけるのだった。
「何やってるんだお前! ミスだらけじゃないか」
「……すみません」
法人部の仕事は何とか期限内に終わらせたものの、急いだためか不備がそこかしこに見つかった。
「それと、この請求書はなんだ」
そう言って、課長はオレが提出した請求書を目の前に出す。
「何って、救急車の配送代と病院代、薬代に帰りのタクシー代ですが」
「お前、こんなものが通ると思うか」
オレは、胸を張って言う。
「八歳の少女が、オレに仕事への心構えを教えてくれました。その授業料を会社が払わなくてどうするんです?」
ハゲ課長は、一瞬あっけにとられたように止まった。
「失礼します。書類を直さなければならないもので」
課長の机に置いた書類を持ち上げ、背を向けて歩きだす。
後ろから、怒声が響くと思った。
しかし――
「あっはっは」
聞えてきたのは、ハゲ課長のうざい笑い声だけだった。
「あの」
オレが二日目の徹夜で頭がぼうっとしていた昼下がり。
少女に声をかけられた。
「昨日は失礼いたしました」
錦土更紗だった。
「おう、体は大丈夫か」
「もう大丈夫です」
オレは、少女の額に手を当てる。
「まだ熱いじゃないか」
「あ、いえ」
なんだか、ほほも赤い気がする。
「ゆっくり寝てなきゃだめだろう」
「はい。あの」
少女は少し俯くと、意を決したようにカバンから何かを取り出した。
「これはなんだ?」
「見ての通り、クッキーですけど」
黒々と良く焼けたクッキーだ。
形もいびつなら色も真っ黒。
……まあ、言われてみればクッキーに見えないことも無い。
「クッキーなのか」
「私が焼いてみたんですが」
病み上がりの朝にか?
「わざわざなんで」
「お礼です」
固いことを言う少女だ。
「そんなこと気にするな」
「食べてみてください」
「……ああ」
オレは、クッキーらしき物体をひとつつまむと口に入れた。
「…………旨い」
「無理しなくてもいいんですよ」
正直苦い。炭を直接口に入れたレベルで苦い。
苦いが気持ちだけはこもっているクッキーだった。
「大丈夫だ。旨いよ」
オレの言葉に、少女はくすりと笑って言った。
「本当に嘘が下手ですね」
「ほっとけ」
ふと、少女がふらりとよろける。
「すみません」
「無理をするなっていうのは、オレの言葉だったな」
少女は、少し俯いて言った。
「無理してるつもりはないんですが」
早く大人の仲間になりたい少女は、背伸びしすぎて自分の身長が分からなくなってしまったようだった。
だから身の丈以上の事をしようとして、苦しむ。
少女の苦しみは、いかばかりだろうか。
オレは『苦い』クッキーを噛みしめて少女の『苦しみ』を見た気がした。
「更紗、お前も少しは大人に頼れ」
「えっ」
驚いた表情の更紗。
「更紗と呼べと言ったのはお前だろう」
「あ、いえそこではなく」
「なんだよ」
少女はまたくすりと笑って言った。
「あなたに優しくされたのが意外で」
「ほんっとに可愛くないやつだな」
そしてオレたちは、目を合わせて笑ったのだった。