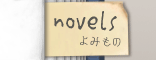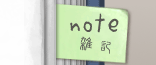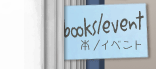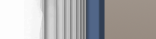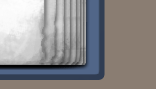ヒーロー
――キーン、コーン、カーン、コォーン
「うう、古典の時間やっと終わった…」
私、宮下サツキ(みやのしたさつき)は、都立独楽(こま)高校に入学して、はや一ヶ月。どうしても古典の授業が苦手だった。
教科書は、私が十五年間も親しんできた漢字と平仮名で書
かれているのに、何が書いてあるのか意味不明。壇上の先生も、どこの星の言葉で話しているのかわからない。
敵は眠気。そして、いかに先生から当てられたときに、バレないように隣の子に答えを聞くかということだった。
(っていうか…黒板に書いてある「いとおかし」ってなんだっけ。糸でできたお菓子?)
黒板には『枕草子』なんて書いてある。「まくらくさこ」さんがどうしたって言うのだろう。
「サツキ、授業終わったよ。いい加減に起きなさい〜」
少し高い声が寝ぼけ頭に涼やかに響いた。よく知ったその声は、親友の村上ミツキだった。
ミツキは、まだ机にしがみつくように寝ていた私の背中をぽんっと叩いた。古典の授業との戦いに敗れ、一時間も寝つづけた私の体に、ミツキの暖かい手がエネルギーを充電していく。背中に置かれた手から広がる暖かさが心地よかった。
顔を上げると、ミツキが満面の笑みで私を覗き込んでいた。腰に手を当て、まだ椅子に座っている私の視線の高さまで、頭を下げている。この子は、こういう格好をすると、すごくかわいい。
そして、イヤでも眼を引く巨乳。男子だけじゃなくて、女子からも注眼の的だ。とても羨ましいミツキの胸を見ていると、私はいつもこう思う。
(ぜんぜん成長しない控えめな私の胸よ。ミツキの胸を見習って、もうちょっと向上心見せてもいいじゃない)
そして、一人になったとき、なだらかな胸を撫でてため息をつくのだ。
「サツキ、よだれでてるよ?」
そう言ってミツキは、口を右手で覆い隠して笑った。私のようにガサツじゃない上品な笑い方が、嫌味じゃないのが羨ましい。
「ミツキってさ…」
私はそこまで言って、ミツキをまじまじと見直した。
ミツキの少し色素の薄い茶色の髪には、天然のウェーブがかかっていて、つややかに肩まで流れている。美人さんではないけれど、小さな顔に控えめな眼と形の良い鼻がちょこんとついていて、本当にかわいい。雰囲気も焼きたてのスポンジケーキみたいにほわっと柔らかくて、私はミツキが好きなのだ。
ミツキとは、もともと同じ中学に通っていた。中一のときに同じクラスで、出席番号が一個違いでたまたま隣の席に並んだ。私の第一印象は「可愛い子がいるなぁ」だったんだけど、ミツキの私に対する第一印象も「可愛い子がいるなぁ」だったらしい。
名前も「ミツキ」と「サツキ」でそっくりだね、って話も弾んで、それから姉妹のように仲良くつきあっている。せっかちで子どもっぽい私とは正反対の性格をしているのに、なぜかすごい気が合う最高の親友なのだ。
「な、なに? そんなに見られると照れるんだけど…?」
頬を赤く染めたミツキが、照れた顔を両手で隠した。本当に、かわいいヤツめ。
「いや、ミツキってかわいいから、食べちゃいたい」
私は真顔でそう言った。
ミツキはさっきまで顔を隠していた両手を口に当てて、噴き出した。
「あははは。またサツキはそんな冗談言って〜。食べるんなら私じゃなくて、ドーナツでもどう?」
私の冗談を軽く受け流したミツキは、そう言って上品に笑った。その笑い声に答えるように、開け放たれた教室の窓から、緑の香りのする心地よい風が吹き込んできた。
「行く行く! いつもの駅前のドーナツ屋さんで豆腐ドーナツ食べよう!」
それを聞くと、ミツキはまた「ふふふ」と笑った。
ミツキと一緒にドーナツを食べて幸せになっている1時間後の私を想像して、自然と唾液がでてくるんだから、人間って不思議だ。古典後遺症の眠気は、完全に頭からふっとんでいた。
「それじゃ、急いで帰る用意しちゃうから待っててー」
「おっけー……!」
笑顔で、手を振ったミツキの顔が、教室の入口の方を見たまま、突然凍りついた。
「おーい!」
遠くから男の大声がしたが、私は意識的に無視をした。考えたくも無いけれど、たぶんアイツだからだ。
「おいっ、おいって!!」
大声とともに、大きな足音も聞こえるほどに近づいてきた。足音だけで、ガサツな人間だとわかる歩き方だった。
もう間違いない、確実にアイツだ。
「おい、サツキ! いい加減に自分に素直になってオレの彼女になれって」
顔を見るのも嫌だけど、反応しないと回りに、特にミツキに迷惑がかかりそうなので、一応反応してあげることにした。
「うるさいなあ…近所迷惑だから大声出さないでよ」
私は、そう言って眼の前の大男に顔を向けた。
やっぱりコイツか…。私は心の中で舌打ちをした。
品川元(しながわはじめ)。
がっしりした体格で、身長は180以上あるみたいだ。刺さりそうなくらいガチガチに逆立てている黒髪と、返り血を浴びたように一房だけ赤い髪が、品川の凄みを増していた。
今時、この学校を「仕切っている」らしい品川は、見た目のとおりケンカに強くて、ここらの不良の間では名前が通っているらしい。知りたくもないのに、同じクラスの男子が、そう教えてくれた。
そんなヤツが、入学式の日に私に一目惚れしたらしく、毎日執拗に迫ってくるのだ。
はっきりいって、めちゃくちゃうざい。
「照れるな。わざわざオレが迎えに来てやったんだから」
品川は満面の笑みで私の肩を叩く。この自信はどこから出てくるのだろう。余りに頭に来たので、乱暴に手を払ってやった。
周囲の空気がピリッと張り詰めるのを背中越しに感じる。近所でも『評判』の不良をこれだけ邪険に扱っているのだから、回りにしてみたらヒヤヒヤものかもしれない。
だけど、品川は全くひるむ様子もなく、笑顔のままで私を見つめていた。
「先輩は三年生でしょう。ご自分の教室に帰ったらどうですか」
私は、努めて冷たい言葉を吐く。
「照れんなって。カラオケ行くぜ」
私の精一杯の冷波攻撃も通用しないらしい。椅子に座っている私の顔に、暑苦しい顔を近づけてきた。
湿った息が私の顔にかかる。不快指数も完全に我慢の限界を超えた。
「ミツキ! こんなヤツ無視して行こう!」
私は、ここ高校に入ってからの一ヶ月、古典の授業で唯一学んだ兵法を実行することにした。
――三十六計逃げるにしかず。
誰が言った言葉だったかは忘れちゃったけれど、怒鳴ったりすると余計に品川は喜ぶので、逃げるのが一番だと私は学んだ。
私は、ミツキの腕を引っ張って教室を出る。
「サツキ、待てって!」
後ろでアイツが叫んだのが聞こえたけれど、意識的に無視をした。
「サツキって強いよねぇ」
ミツキはチョコレートのたっぷりかかったドーナツにかぶりつきながらしみじみと言った。
「あんな怖そうな人によくあれだけはっきり言えるね」
ミツキのこの発言に、品川のことを思い出して、豆腐ドーナツにかぶりついて幸せだった気分が少し冷めてしまった。
「あんなヤツ、怖くないって。無視しとけばいいのよ」
「でもさー、あの人悪い噂いっぱいあるし…」
そうなのだ、品川にはいくつもの噂があった。
入学してからこの一ヶ月。いくつもの噂を(別に知りたくも無いのに)周囲から教わった。
曰く、気にいらない他校の生徒を病院送りにした。
曰く、一人で全国大会出場の柔道部員五人を相手にして全員病院送りにした。
そんな、よく聞く典型的な噂話だった。私はしょせん噂だと思ってあんまり気にしてなかった。
「だいじょうぶだって! 実際アイツそんなに強くないから」
私は、笑って砂糖のついた右手をヒラヒラと振った。
「心配なのよぅ…」
ミツキはチョコドーナツをほお張りながら、本当に困ったような顔をしていた。本気で心配してくれているのに申し訳ないけれど、小動物みたいでかわいく見えてしまう。
「あはは、ミツキかっわいい〜」
「もうっ、本気で心配してるんだからね」
私と違っていいヤツなのだ、ミツキは。
「ごめんごめん。心配ならもう一個豆腐ドーナツおごって〜」
品川のことを考えると不愉快でめまいがする。もう考えたくも無かったからおどけて話をそらした。
「何でそうなるの!」
「あはは。やっぱダメか」
そうして、私たちは他愛も無い話を続けたのだった。
ミスドからの帰り道は、人通りがない上に、すでに午後八時を回っていたせいで、暗かった。
門限の午後七時を完全に過ぎていたから、私は普段は絶対に通らない裏道を走っていた。
右手には、お墓の塀。左手には何を作っているのかよくわからない工場のブロック塀。車が一台しか通れないような細い道の圧迫感。街灯がまばらにしかない恐怖感。
あまりの恐ろしさに、もう五月だというのに背中に寒気を感じた。自然と歩調も早くなる。
「こりゃ、お母さんにかんぺき怒られるなぁ」
うちの母は厳しくて、夕飯の時間には家族そろって食卓についていないといけない、というルールがある。友達に話すと「ありえなーい」って必ず笑われるけれど、門限に遅刻すると「夕飯抜き」というのが、わが宮下家の鉄の掟なのだ。
いつもは絶対に門限は守るのだけど、今日はミツキとのおしゃべりに夢中になりすぎて、完全に破ってしまった。
お母さんの怒った顔が、頭に浮かぶ。歳の割りに若くてキレイなんだけど、抜けるような白い肌に切れ長の眼が、怒ると本当に怖い。
生暖かい風が吹き抜ける。寒くも無いのに身震いがした。
そのとき、私の後ろから車が走ってきた。狭い道だから車のヘッドライトで全体的に明るくなる。なんとなく人が来たという安心感があって、私は少しホッとした。
だけど、その車は少し様子がおかしかった。
私を追い越したところで、突然その車は止まったのだ。周囲に私の他に人はいないし、自動販売機さえもない。
私以外の何かに用があるとは考えづらかった。
(誰? なんだろ…? お父さん…なわけないよなぁ。もうご飯食べてるだろうし、何よりうちにワゴンなんてないもん)
私が立ち止まって混乱していると、車のドアが開いて、中から絶対にモテなそうな男が五人現れた。小太りの男が、ふごふごと鼻を鳴らしている。異常に細くてひょろ長い男もいる。あとの三人は、ヘッドライトで逆光になっていて、よく見えなかった。ただ、男達の血走った眼が異様にギラついているのだけはなぜだかわかった。興奮しているようだ。私は背中に冷たい汗が流れるのを感じた。
「いくぞ。声を出されないようにしろよ」
ひょろ長い男が言った。
「あぁ、せーのでいくぞ」
「せーの」
小さい声で合図をすると、男たちは私に飛び掛ってきた。
「な、あんた達なんなの………!!」
一人に口を抑えられて声を出せなくされた。さらに二人に体を抱え上げられ、残りの二人は見張りをしているようだ。
「早く車に乗せろ! 見つかる前に連れてっちまうぞ」
連れ去られそうだ、と私の頭が理解するより前に、私の体を恐怖が貫いた。男達のゴツゴツとした手の感触がおぞましい。寒気と共に、皮膚の下をミミズが這いずりまわるような嫌悪感を覚えた。
(怖い…怖い。誰か助けて)
叫びたかった。だけど口を抑えられていたからそうもできなかった。鼻と口を同時に抑えられて息ができない。苦しい…。
だんだんと、意識も遠のいてきた。
「おい、お前ら! オレのサツキに何しやがる!!」
突然私の後ろから誰かが出てきたらしい。口を抑えた手が驚きで少し緩んだ。急いで息を吸うと、新鮮な空気が肺に流れ込んできた。空気が美味しいと感じたのは初めてのことだった。
怖いし気持ち悪いし、何より混乱していたのに、私には声の主の正体が、すぐに分かってしまった。
――絶対アイツだ。
暗い中で、しかもあまりの怖さで涙眼だったのに、電信柱の陰から出てきたアイツを見つけた。
「この品川元さんの女に手を出すとはいい度胸だな、オイ」
アイツの女になった覚えはないけど、まだ口を抑えられているため、否定もできない。でも、体格のいい品川を見て少し安心してしまった私がいるのも感じた。
「コイツやばそうだよ、どうする?」
「こっちは五人もいるんだ。殺っちまうか」
また、ヒソヒソと、ひょろ長い男を中心に、モテなそうな男たちは相談している。私に対したよりも、ぎょろりとギラついた十個の眼が、夜道で異様に光っていた。
見張りの男が車から鉄バットを五本取り出し、全員に配った。
明らかに殺意のこもった声が、耳に響いた。本当に小さい声なのに、異様に私の頭にずしんと響いた。
いくらアイツでも凶器を持った五人を相手にするのはきついはずだ。
――ふと、気づけば私の口をおさえていた男の手が緩んでいた。
私は男の毛深い手を、思いっきり噛んでやった。じゃりっと、毛と人の手を噛んだ気色悪い感触が顎から伝わってくる。
「痛っ!」
手を離す毛深い男。口が自由になった。
私は、大きく息を吸い込んで、叫んだ。
「きゃー! 誰かーー!!」
あらん限りの声を出す。自分でもびっくりするほどの大声だ。
男たちは私の叫び声に、動揺したらしい。完全にパニック状態に陥っていた。
その隙を見逃さず、品川が見張りの男に飛びかかった。
ニ対一だった。品川は金属バットの攻撃をかいくぐり、一撃づつで見張りの二人を倒してしまう。
(アイツって本当に強かったのね…)
私は、品川に安心感を感じ始めていた。
その時、どこからともなく、耳障りな高笑いが聞こえた。
「はーっはっはっは! お困りのようだねガール」
高笑いと共に、芝居がかったようなセリフが風に乗って聞こえてくる。
「どちらを向いているのだエブリワン。こっちだこっち」
私達は全員、状況も把握できずに、言われるまま声のする方を見た。
品川が出てきた電信柱の――上だった。
月明かりがスポットライトのようになって、声の主の姿を照らし出していた。普段は平等に照らし出すはずの月明かりが、なぜかその男だけをヒイキして、余計に明るく照らしているように感じた。
電信柱の上に立っていたのは、ラメがちりばめられて光沢のある赤い全身タイツに、赤と青のストライプの派手なマントを羽織った、仮面の男だった。そこだけが明るく感じたのは、男の異常に派手なコスチュームがギラギラと輝いているからなのだとわかった。
バットマンみたいな白い仮面…と言えば聞こえはいいけど、見た眼はなりそこないのパーマンだ。
つまり、眼と鼻だけを隠した仮面で、アゴから口にかけて仮面の下から出ているのだ。
しかも、見たくないことに――
「オレのサツキを見てあそこモッコリさせてんじゃねぇ!」
『オレの』は余計だ!
けれど、確かに品川の言う通りだった。気持ち悪いことに、ぴったりとしたタイツをはいているために、ハッキリと『ソレ』の形がわかる。
男は、高笑いと共に、さも楽しそうに叫んだ。
「はっはっは。チャーミングだろう?」
「イミわかんないんですけど…」
私はつい呟いてしまった。
「何者なんだアンタは!?」
私の口を抑えていた毛深い男が、我慢できずに聞いてしまった。
だめだって! こういうヤツはほっとかないと!
――三十六計、逃げるにしかず。
こういう他人の話を聞かない人間は、相手にせずに逃げるに限る。何か反応を返すと増長するからだ。私は、嫌というほどこの一ヶ月でそれを学んでいた。
案の定、変態タイツ仮面は待ってましたと言わんばかりに口を開く。
「汚(よご)れてしまったこの世界、空気の力で浄化する。穢(けが)れた悪がいるのなら、世界の果てまで飛んでいく。正義のヒーロー! 超空人エアリンサーだ!!!」
自分でヒーロー名乗ったよ……。
私はもう怖かったこととか品川のヤツがうざかったことなんかも、完全に忘れてしまっていた。
ここから逃げ出したい。ここにいるのが恥ずかしい。その気持ちでいっぱいだ。
「やあ、そこのチャーミングなガール。私が助けてあげるから安心したまえ」
できればあんな変態タイツ仮面なんかに助けて欲しくない。それに、タイツ仮面のアソコなんかと同じ「チャーミング」なんて褒められ方したって嬉しくないし…
「とうっ!」
そう言って変態タイツ仮面、もといエアリンサーは電信柱の上から飛び降りた。
地上五メートル強。音もなく着地した。
後からふわりと舞い降りるマントが、夜空に鮮やかだった。
私が不覚にも見とれていると、エアリンサーはビシッと私を捕まえている男たちを指差し言った。
「悪人達よ。空気の力を思い知るがいい!」
さらに続いてこう叫んだ。
「秘技、風槌撃(ふうついげき)!!」
すると突然、突風が吹きぬけた。
きゃっ!
私はとっさに両手でスカートをおさえた。
(……あれ?)
さっきまで二人の男に両手をおさえられていた…ハズだった。
ふと振り返ると私をおさえていた男たち三人は五メートルほど吹き飛ばされていた。
気絶しているらしく、ぴくりとも動かない。
「な、何したの…?」
私は呆気にとられ、とっさに訊いてしまった。
「はっはっは。簡単な事だよガール。私は空気を操る事ができるのさ。世界中の悪を空気の力で浄化するのが私の使命だ」
そう言って右腕でガッツポーズをする。
(……やっぱりイミわかんない。危ないんじゃないかな、このおっさん)
それでも、私は暴漢五人組が倒されたから、これで逃れられるとほっと息をついた。一件落着だと思って、無い胸をなでおろした。
だけどエアリンサーと名乗った男は品川に向かってさらにこう言ったのだ。
「さぁ、貴様も覚悟するのだ!」
そう言うとまた、ビシッと指を指した。
「ちょっ、待…」
「秘技! 風追撃!!」
言いかけたところで、心地よい風が吹きぬけた。品川もすごい勢いで吹き飛ばされたのだ。
品川が私を助けようとしてくれたところは、このヒーローは見ていなかったらしい。見た眼で悪と断定されてしまったようだ。確かに、悪人面だ。それでも私を助けてくれたのだ。
品川にちょっと罪悪感を覚えた。
エアリンサーは、遠い眼をして、私だけに向けて決め台詞を吐いた。
「人はみな、空気無しには生きてはいけない…」
五月だと言うのに、冷たい風が私の体の中を吹き抜けた気がした。非常に寒い。
ファンファンファン…
遠くからパトカーの音が聞こえてきた。誰か付近住民が呼んだらしい。
あれだけ叫んだり騒いだりしていれば当然の事だろう。普段は静まっている夜道が、俄かに騒がしくなってきた。
「また困った事があれば私を呼びたまえ。さらばだ、ガール!」
そういって、エアリンサーは派手なマントを翻し、風と共に颯爽と去って行ったのだった。
「ちょっとぉ、サツキ聞いたよ〜」
一時間眼の英語の時間を休んで登校した私に、ミツキが声をかけてきた。心なしか、顔色が悪い。よほど私のことを心配してくれていたのだろう。
「警察とか大変だったんだって? もう、だから心配なのよ〜」
あれから確かに大変だった。
品川は警察に捕まって犯人扱いされるし、犯人が皆気絶してたから私が全員気絶させたんじゃないか、とか疑われるし…。
私は、空手の達人でも、ゴリラ女でもないっての。あの刑事失礼なこと言ってくれちゃって。
「もう、最悪だったよ〜。変態に助けられたり、ゴリラ扱いされたり…もう意味不明」
ミツキはそれを聞いてきょとんとしていた。全く意味がわからなかったようだった。
ひとつだけ、いい事もあった。品川が私に言い寄ってこなくなったのだ。
あんな派手なヒーローもどきに気絶させられたのがわかってしまったら、不良としてメンツが丸つぶれなのだろう。
私を避けるようにさえなったのだ。
(品川も可哀想だとは思うけど…)
アイツの家は学校から見ると電車で反対方向にある。
偶然、私の家の近くを通る事なんて、絶対にありえない。
つまり、私の後をつけていたのだ。自業自得と言えなくもない。
「アハハハ、これ以上思い出したくないや。ごめん聞かないでミツキ」
ミツキは納得いかない顔だったけど、私の気持ちを汲み取ってそれ以上聞かないでくれた。
後から、若い刑事が私に教えてくれた。
「あそこには、赤いタイツの変態が出るから、夜は一人で歩かないように」
その変態に助けられたとは、言えなかった。
思い出すたびに顔から火が出そうなほどに、恥ずかしい。それこそ「お嫁にいけない」。
今でも笑い声が聞こえるとあのタイツ仮面を思い出して、びくっとしちゃうくらい、あれは私には刺激が強すぎたのだった。
■エピローグ
事件から一ヶ月くらい経った後、古典後遺症で机を枕に眠っている私の元を、大男が訪ねた。
突き刺さりそうなほどに黒髪を逆立て、一房の赤い髪が返り血を浴びたように光っている。
身長は185センチ。体重85キログラム。
かなり体格がいいはずなのに、今はなぜだか小さく見えた。
「あのさ、サツキ…一緒にカラオケでも…」
意を決して、声をかけてきたのだろう。
今でも高笑いが聞こえると、頭を押さえてうずくまってしまうほど、品川には事件がトラウマになっているようだった。
近隣の高校でも有名だったこの不良は、近頃では大人しくなっちまった、と不良の間では蔑まれるほどだった。
「サツキ、カラオケに行かないか?」
控えめに私の眼を覗きこんでくる大男。なんだか可愛く見えた。
私はおもむろに立ち上がり、品川にヘッドロックをかけて、言った。
「カラオケ、行きますか。先輩」
品川の顔が、唖然としていた。
口も眼もだらしなく開いて、酷くマヌケな顔だった。
あの品川が、私に頼みにくるなんて。
なんだかそれがおかしかった。
「お、おう。行くか。行くのか?」
半信半疑の品川に、私は言った。
「もちろん、先輩のおごりですよ」
窓の外でヒバリが鳴いた。カーテンの隙間から漏れる太陽の光が暖かく私の顔を照らした。
楽しい学校生活の幕が、濃い風と共に開いたような気がした。