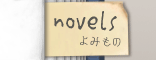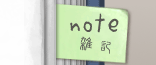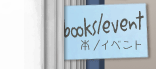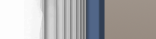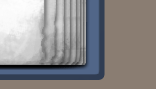奇妙な美女と不思議な湖
寝不足の私の目を、春の眩しい日差しが貫いた。
朝露の残る木々の緑と、木漏れ日が鮮やか過ぎて痛いほどだ。
そして、濃い緑と土の匂いが、私の空っぽの胃を刺激する。
「ここどこよ〜」
私は大学の友人であり、寮のルームメイトである平良沙綾(ひらら さあや)に起こされ、彼女の運転する車に乗せられたのだ。
しかも、巨大な荷物を持たされて。
「まぁまぁ、来ればわかるって」
沙綾は思い立ったが吉日というか、猪突猛進というか、思いついたことは即実行しなければ気がすまないところがある。
しかも周りを――主に私を巻き込みながら最後まで何の説明もなく、だ。
「沙綾〜。まだ目的地につかないのー」
「まあまあ、みーちゃん。もうちょっとで着くから」
みーちゃんとは支那原未来(しなはらみらい)、私の事だ。
まだ暗い早朝四時に起こされ、一時間半ほど車に乗ってから、さらに一時間は歩いただろうか。
鳥が、「ぎゃあぎゃあ」やら「きゅーきゅー」やら、いろんな声で鳴いているのが聞こえる。
私は、どんな秘境に連れてこられたんだろう。
それでも、眠気が覚めてくると木々の間を歩くことがだんだんと楽しくなってくるから不思議だ。
私達はしばらく森を歩いた。
「なんか気持ちいいね、沙綾」
「だよね。みーちゃん」
沙綾は、大きな眼を細めて、笑顔で私を振り返った。
早朝の木漏れ日を浴びて、天使のようだ。
腰まである黒髪があまりに綺麗で、本当に眩しい。
彼女は、『なんでテレビにスカウトされないの?』っていうほど美人だ。
そりゃもう、最初のうちは大学内でよく声をかけられた。だけど、みんな五分足らずで諦めて去っていく。
会話が、通じないのだ。一切。
この間なんか、かなりカッコいい大人の男性が声をかけてきたのだけれど、
「君の好きな所に連れて行ってあげるよ」
って、言われて沙綾は即答だった。
「セミ取り?」
あの時の男の人の顔、おかしかったなあ。遠回しに断られたと思ったらしい。
沙綾は、頭が良くて笑顔がきれいで、料理もできる。
私なんか、同じ部屋に住んでいるのをいいことに、料理に掃除、下着の洗濯まで彼女任せなのだ。
黙っていればモテるだろうに。
南の、秘境のような島出身の彼女は周囲からは恐ろしくズレていた。
「着いたよみーちゃん」
ぼーっとしていた私は、沙綾の声で我に帰った。
「わぁ!!」
思わず歓声を上げてしまった。
それほどすばらしい景色が広がっていたのだ。
「きれいでしょ?」
沙綾は得意げに胸を張って言った。
「うん、すごい。なんてキレイな湖…」
目の前には、澄んだ湖があった。
少し小さいけれど鏡のように澄んだ湖面は、空の青さと白い雲、それに周囲の木々の緑を映し出して、一枚の絵画のようだった。
その、綺麗な湖が太陽の光を反射して、キラキラと輝いているのだ。
「みーちゃん。荷物ちょうだい?」
「うん。これね」
私は荷物を沙綾に差し出した。
沙綾は中からなにやら棒状のものを取り出し、てきぱきと組み立てて行く。
出来上がったソレは、釣りざおだった。
「みーちゃん、そこのエサを出してくれない?」
「エサってこのタッパーに入ってるやつ?」
沙綾は頷いた。
私は言われるがままタッパーをあけ、素手で中身を取り出そうとした。
取り出そうとして凍りついた。
中にはタッパーいっぱいのミミズがいた。
「ぎゃーー!!!」
「もう、みーちゃん。せっかく私が昨日苦労して集めたんだから大事にしてよね」
「き、昨日?」
「そうそう。寮の庭がいい土だから、いっぱい取れたよー」
そう。こういう子なのだ。
なんだか子どもっぽいというか、野性的というか。
素手でセミを捕まえたり、蝶を追いかけたり。
本当、これさえなければモテモテだろうに。
「ご、ごめん沙綾。ミミズは勘弁…」
「えー、新鮮でおいしいのにー」
「おいしいって、『魚の気持ちになったら』ってことよね?」
沙綾は、笑顔のまま返事をしなかった。
もう大学に入学してからだから、彼女とは二年の付き合いになる。
それから気をつけていることが一つある。
絶対に『沙綾の料理中は台所に入らない』ことだ。
とにかく、どんな材料を使っているかわからない。
沙綾が食材の買い物をしているところを見たことがないのだ。
飼っていたカエルがいなくなったその日に、『疑惑のからあげ』が食卓に上ったこともある。
最初の頃は不安だったけど、最近ではどうせ美味しいのだから原材料を「聞かない」事にしている。
「じゃあみーちゃんこれね」
そう言って沙綾は、私にミミズの付いた釣りざおの一本を渡す。
「これって適当に投げればいいの?」
「そうそう、なんとなく遠くに」
沙綾は、非常に手馴れた手つきで竿を振る。
私も見様見真似でエサの付いた針を遠くに投げた。
暖かい日差しとキレイな景色。
ミミズさえなければ、釣りって気持ちよくて楽しいかもしれない。
「結構楽しいね。沙綾?」
ふと沙綾の方を見ると、なんだか忙しそうだった。
って、言うか。
「11…12…13…14…」
ぶつぶつと数を数えながら、すごい勢いで魚が釣れていた。
沙綾の手元が恐ろしいほど素早く動いている。
釣りって初めてだったけど、こんなに釣れるものなのだろうか。
いや、絶対にそんなことはないだろう。テレビで見る釣り名人だって、座ってゆっくり釣っていた気がする。
私は、沙綾は気にしない事にした。
「みーちゃん何匹釣れた?」
「何匹? って言われてもまだ来たばっかりじゃないの」
「えー! まだ釣れてないのー!?」
「初めてなんだから仕方ないでしょ」
「そっかー。じゃあワタシはもう夕飯の分釣ったから大物狙おうっと」
夕飯の分、と言いながら4、50匹の魚がクーラーボックスに詰め込まれていた。
「大物って、ここでは大きい魚でも釣れるの?」
「うん。こないだはねぇ、ワニが釣れたよ」
「へえ、ワニって日本にいるんだねえ」
「ね、みーちゃん。ワニ美味しかったでしょ?」
そうか、私はワニを食べた事があるのか。
私は、沙綾に笑顔で「うん」と返事を返す。沙綾の料理が美味しくなかったことなどないもんね。
沙綾は、会話に飽きると今までより遠くに竿を投げた。
私はまたぼんやりと、半分日向ぼっこのように自分の浮きを見つめていた。
(暖かいなぁ。ちょっと眠いかも…)
バシャッ。バシャバシャッ。
なんだかまた隣が騒がしい。大物が釣れたのだろうか。
今晩のおかずはなんだろうか。考えているとよだれが出そうだ。
私は、期待を込めて沙綾を見る。
すると、竿がありえない角度で曲がっている。
気づけば、湖に引き込まれないように、本気で両足で踏ん張っていた。
「ちょ、ちょっと沙綾! それやばいんじゃない!? 手伝う?」
「これくらいなら、ぎりぎり大丈夫――かな」
「そうは言ってもじりじり湖の方に引きずられてるじゃない!」
私は、慌てて沙綾の細い腰に抱きついた。
二人で格闘すること約三十分。ようやく魚の背が見えてきた。
鈍い銀色の背中。丸々と太った腹。
体長は、一メートル以上はあるだろうか。
そんな巨大魚が、沙綾の細腕で釣りあげられていた。
ただ、その巨大魚は――料理を一切しない私でも、見覚えのある魚だった。
沙綾は、満面の笑みで私に言った。
「うん。みーちゃん、今夜はマグロのお刺身だよ」
「ま、マグロ!?」
マグロは海に住む魚だと思っていた。こんな湖にいるなんて。
だけど、沙綾が釣り上げて陸上でパタパタはねているそれは、明らかにマグロだった。
「うーん。百キロくらいかなぁ。ちょっとちっちゃいね」
「そ、そうなの?」
私より細い沙綾の腕のどこからあんな力が出てくるのだろうか。
もう沙綾の奇行には慣れたはずの私にでさえ、心の許容範囲を超えかけていた。
「あ、みーちゃん。引いてる引いてる!」
「え、え? 何が?」
「竿だって! 引いてる引いてる」
私はここに座っている目的をすでに忘れていた。
気付けば椅子に立てかけていた竿が、引いていたのだ。
「どうしようどうしよう! 沙綾どうすればいい?」
「逃がさないようにそーっとリールを巻いて。慌てずゆっくりね」
「リール?」
「手元の糸巻きみたいなやつ」
私はようやくテレビ番組で見た釣りの光景を思い出した。
釣りざおの手に持つ部分の少し上に、釣り糸を巻く『リール』という部分がある。
それをゆっくり回すと、魚が釣れるのだ。
「そうそう、みーちゃんその調子」
「ゆっくり、慌てず、よね」
引きはあまり強くない。そう大きくはないみたいだ。
ゆっくり糸を引いていくと、魚が見えた。
「すごいよみーちゃん! 今夜はフグチリも食べられるね!」
ここはどんな湖なんだろう。
私の釣り糸の先で、ハコフグがぷくっとふくれっ面をしていた。
「でもフグって免許ないと調理できないよね?」
そう言って沙綾を見ると、フグ調理の免許証を私に向かって誇らしそうに掲げていた。
「あ、沙綾がさばけるのね…」
「ここでフグ釣るなんてすごいよ! さすがみーちゃん」
なんで湖にフグがいるかはもう気にしない。
やっぱりはじめての釣りで魚が釣れたのは嬉しいのだ。
「釣りって面白いね、沙綾」
「・・・・・・・・・」
「沙綾?」
沙綾はまた何かと格闘していた。
今度は釣り上げるのに時間はかからなかった。
それだけ小さい魚だったのだけど、釣り上げてからさらに格闘していた。
「沙綾、それって…」
私が沙綾に問い掛ける。絶対にありえない魚に見えたのだ。
鋭い牙を持っていて、釣りあげられてからも沙綾に噛みつこうとする獰猛さ。
こんな魚を、私はあまり多く知らない。
「うん、ピラニアだね」
沙綾はそう言うと、素早くピラニアに手刀を放った。
それまで元気だったピラニアは、一瞬で気絶した。
「ぴ、ピラニアもいるのねここ」
「前に来た時はいなかったんだよ。たぶん心無い人間が飼いきれなくなったからって捨てたんだと思うよ」
沙綾は本当に怒っていた。
「まったく。この湖の生態系が崩れたらどうしてくれるのかしら!」
ピラニアはダメでも、マグロとかフグがいるのは生態系としていいのだろうか。
でもまあ、沙綾の言うことも確かに一理ある。
ピラニアなんかを普通の湖に捨てたら、間違いなく湖の生態系は崩れるだろう。
それに、人間の都合で飼われたくせに、人間の都合で捨てられたピラニアも可哀想だ。
「それ、どうするの?」
すると沙綾は、キレイな笑顔をした。
「食べるの」
「そっか――」
今晩のおかずは、マグロとフグとピラニアに決定したらしい。
そんなに食べられるかなあ。
私は考える事を辞めて、釣りに集中した。
どうせ、おいしい夕飯になるに違いない。今のうちに動いてカロリーを消費しておこう。
私が決意すると同時に、竿に手ごたえがきた。
「沙綾! きたきた」
「それは重そうだけど弱った感じの引きだねぇ」
沙綾の言うとおり、重さはあるけど手ごたえが軽く、逃げるそぶりが見られない。
「それなら一気に引いちゃっていいと思うよ」
「よーし」
私はさっき釣ったフグの手ごたえを思い出し、ワクワクしながら糸を巻いた。
私は釣ったソレを見て、声もでなかった。
ちょっとツリ目で大きい目。細い体に細い腕。そして、とがった耳。
昔の映画で見たような、コイツは――
「こ、これ……」
「うん、宇宙人だね。また心無い人間が飼いきれなくなって捨てたんだよ」
「――沙綾。さすがにこれは飼わない」
あまりにありえない出来事に、私はかえって冷静になってしまった。
「えー、だって前はいなかったよ?」
「そりゃいないでしょうよ…」
なんだか頭痛がしてきた…。
すると沙綾が上目遣いに私を見る。
それなりに付き合いの深い私にはわかる。
以前この『上目遣い』をしたときは、公園に捨てられていたカメレオンを拾ってきたときだった。
飼いたいと言って絶対きかなかったのだ。
そのカメレオンが死んだ次の日に、疑惑のハンバーグが食卓に上ったけれども。
沙綾の上目遣いは危険な『おねだり』の目だ。
「みーちゃん、これ飼わない?」
当り前のように、沙綾が言った。
心なしか、宇宙人も涙目でこっちを見ている気がする。
「捨ててきなさい」
「だって可哀想じゃない。この子」
「そんな気味の悪いものと同じ部屋で寝れないよ?」
「えー、かわいいじゃない」
全身が銀色のメタリックな皮膚をしていて、必要以上に大きな目の人型の生物。
私には絶対可愛くは見えない。
「ほら、この潤んだ瞳。チワワみたいじゃない」
「他の部分がチワワとかけ離れてるじゃない」
「えー、本当にだめ?」
また上目遣いの潤んだ目。
顔がかわいいだけに、強烈な破壊力を持っている表情だ。
女の私でも、ついみとれてしまう。
すると、突然甲高い声が響いた。
「ねーさん、ねーさん」
「だ、誰!?」
「私ですわ。目の前の私です」
目の前にいるのは、沙綾とそして…
「そうですねーさん。私ですわ」
「宇宙人さんしゃべれたのね」
沙綾の目が輝いている。
もうだめだ。カメレオンの次は宇宙人を飼うことになりそうだ。
「いやー、私の宇宙船が壊れてしまいましてなー」
宇宙人は口を動かさずにしゃべっている。
それがすごい気味悪い。
「なんでエセ関西弁なのよ…」
どうでもいいところに突っ込んでしまった。イントネーションがおかしいのだ。
「そりゃ、ねーさん。私の船が大阪っちゅうところに落ちよったんですわ」
「へぇ、大阪ねぇ」
沙綾が、新しいおもちゃを見つけた子供のような輝く眼で宇宙人を見つめて言った。
「私がガキの時分でしてな。両親はそれで死んだんですわ」
宇宙人は口を動かさないまま、身の上話を始めた。
「可愛いガキの私には、一人で生きてくだけの力はあらへんもんでさまよってたんですが…」
「うんうん、大変だったのねぇ」
そう言って沙綾は宇宙人の頭をなでる。
「そんで、権蔵っていうおじいさんに拾われたんですわ」
「ゴンゾウさん? 二丁目の?」
沙綾の知り合いらしい。
「そうです。権蔵じいさんにはよくしてもろうたんですが…」
「先月死んじゃったもんね」
悲しいことをさらりと言う沙綾と無言で頷く宇宙人。
沙綾と権蔵じいさんがどんな関係かは聞くまい。理解できないだろうから。
「権蔵さんが死んでもうた時に、息子さん達に『大きくなりすぎたからもう飼えない』言われて捨てられてもうて…」
本当に『飼われてたのが捨てられた』のだとは思わなかった。
あとで沙綾に謝ろう。
「可哀想に…」
沙綾は、もう飼い主にでもなったかのような、慈愛の眼差しを宇宙人に注いでいた。
「それで、宇宙人くんは何が言いたいのかな?」
「それなんや。権蔵じいさんも、私を飼うのにえろうムリしたねん」
「ムリって?」
「私、お坊ちゃん育ちやったから天然モノの高級な食材しか食われへんし、それに私をかくまうのにそりゃもう難儀してん」
「そりゃ難儀したろうね」
と私。
「それでや。そちらの優しいねーさんに迷惑かけたくはあらへんから…」
そこで大粒の涙を流す宇宙人。
「わ、私のことは…ほっといてんか……」
血のような赤い涙を流す宇宙人と、必殺の涙目を向ける沙綾とに、私は追い詰められた。
「私は…もう人間様に迷惑かけとうないねん……」
そういって地面に座り込んで泣き出す宇宙人。
なんか可哀想かな…。
「私なんか、生まれてこなきゃよかってん。おとんやおかんと一緒に死んどけばよかってん」
「あ、あのさ宇宙人さん…」
私は居たたまれなくなって宇宙人の肩に手を置いた。
「私、ひどいこと言ってごめんね」
「ねーさん、私、クー、クーックーックーーーーッ」
引きつったような泣き声が、静かな湖にこだました。
(宇宙人ってやっぱり変わった泣き声するのね)
私がそう思ったその時だった。
沙綾が突然、地面に伏して泣いている宇宙人の頭を掴んだ。
「クーックークククーーッ」
私たちのそれと寸分たがわない、笑顔がそこにはあった。
「あんた、笑ってんの?」
「な! なに言うねんねーさん。これは私らの世界じゃ泣き声いうねん」
沙綾は私に背を向けて、宇宙人と向かい合った。
宇宙人は、最初笑顔だったのが、突然だらだらと脂汗をかいて、恐怖に引きつったような顔にかわった。
「す、すみませんねーさん…」
よほど怖い顔でも見たのだろうか。
沙綾が地面に下ろしたときには、すっかり宇宙人はしおらしくなっていた。
「あんた、笑ってたよね?」
と、私が問い詰める。すると宇宙人がいきなり土下座を始めた。
「すみませんでした! 本当はご飯食べすぎで追い出されたんでした!」
宇宙人は、訊きもしないのにあっさりと白状した。
どうやら、自業自得で捨てられたらしい。
「今まで話してたのは全部うそ?」
「私、一食で米を十合食うもんで、食費が足らんくなってしもたらしいんで」
「一食で十合って…」
「みーちゃんと私が一日かけて食べる量じゃない」
私は、同意のために頷く。
「ねーさん方も、大概大食いでんな」
「あんたには言われたくないわ!」
私は、宇宙人を小突く。
「いやー、地球は飯がうまくてうまくてかなわんです」
「それで? あなたは私たちにどうしてほしいの?」
沙綾が宇宙人に問い掛ける。
「できれば…私を飼うてくれるといいな、なんて思てんですけど…」
「ワタシ達にはそんなにお金ないわよ?」
沙綾が言った。
お金の心配より、宇宙人を飼うっていう世間体の方を心配して欲しい。
「私、なんでもしますから。こう見えて結構芸達者ですねん」
「へぇ、何ができる?」
沙綾は興味を持ったようだ。
「へい。釣りのエサになるミミズを探したり、室内のゴキブリを捕まえたりできます」
「それ役に立たないじゃん! 沙綾できるし!」
私はつい、ツッコミをいれてしまった。
「じゃ、じゃあえっと、その…」
「何? まだなにかあるの?」
私は、銀色の肌をした宇宙人との会話に慣れている自分に呆れながらも、聞いた。
「ありました! ありました! 取って置きのが!!」
「なになに?」
宇宙人の取って置きの特技…気になる。
「へい。私の目、透視できますねん」
「へぇ! それでそれで?」
「洋服くらいなら透けて見えますねん。ねーさんの今日の下着は白?」
「な…!」
私は本気で蹴りを宇宙人の頭に放った。
だけど一瞬早く、沙綾が宇宙人の頭を掴んで持ち上げていた。
そしてそのまま、野球の遠投のように――
ヒュー…………ぼちゃっ。
池に投げ捨ててしまった。
「沙綾思い切った事するわね」
「みーちゃんの下着は私以外には見せたくないもの」
沙綾はしれっと言った。
本気か冗談か、表情からはわからない。
「食べない宇宙人は湖に返すのが礼儀よ、みーちゃん」
「キャッチアンドリリース?」
「それそれ」
沙綾はそう言うと、笑顔で口笛を吹いた。
「どうしたの沙綾?」
「んっとね。知り合いに連絡取ったの」
「知り合い?」
「うん。波長を合わせるのに時間掛かるから、ちょっと待ってね」
沙綾はそう言うと、口の中でなにか呟き始める。
「こちら、三丁目の沙綾。応答してください――」
もう、何が来ても驚かないぞ。
「――そうそう。迷い宇宙人が一人」
嫌な予感がしてきた。
沙綾の交友関係の広さを、完全に侮っていた。
「ねーさん。ありがとう! 星に帰れそうや!!」
もう見えないけれど、宇宙人の声が湖に響く。
風景にはなんの変化もなかったけれど、ただ声だけが響いて、消えた。
沙綾は、空を見上げて手を振りながら言った。
「私の島でね、子供のころ隣に宇宙人が住んでたの。今でも友達なのよ」
「いいなあ」
私は素直にそう思ってしまった。沙綾の交友関係はなんだか楽しそう。
「内緒よ?」
沙綾は指を一本立てて私に言う。
なんて可愛いんだろう。
「なんかすごい湖だねここ」
私が話しかけると、沙綾はすでにテキパキと帰り支度を始めていた。
「ここは、私がお父様に教えてもらった秘密の湖なの」
「お父様って、漁師の?」
「うーん、いまはトレジャーハンターって名乗ってるみたいだけど」
沙綾のお父様は、元々沖縄の漁師である。
突然『冒険したい』とか言って家を出て以来、今は何をしているか沙綾でもわからないらしい。
「秘密の池だから、みーちゃん、ここ内緒にしてね」
そう言って沙綾は、その麗しい容姿をいかんなく発揮し、お願いのポーズを取った。
私は、そのポーズに一瞬みとれながら、さすがに『どうせ誰も信じてくれないから大丈夫』なんて言えないなあ、と思っていたのであった。
「今日のご飯、楽しみにしててね」
沙綾が、天使のような笑顔で言う。
「うん!」
もはや、宇宙人のことなど私の頭から消え去った。
「それにしても、沙綾って人間の友達いるの?」
「みーちゃんがいるじゃない」
「えー。意外と私たちって噛み合ってないと思うけど?」
「ううん。私とみーちゃんって波長が合うのよ」
「なにそれ」
私たちの笑い声が、風を呼んで湖の湖面が揺れる。
風がとても心地よくて、私は『また来たいな』と思った。
朝露の残る木々の緑と、木漏れ日が鮮やか過ぎて痛いほどだ。
そして、濃い緑と土の匂いが、私の空っぽの胃を刺激する。
「ここどこよ〜」
私は大学の友人であり、寮のルームメイトである平良沙綾(ひらら さあや)に起こされ、彼女の運転する車に乗せられたのだ。
しかも、巨大な荷物を持たされて。
「まぁまぁ、来ればわかるって」
沙綾は思い立ったが吉日というか、猪突猛進というか、思いついたことは即実行しなければ気がすまないところがある。
しかも周りを――主に私を巻き込みながら最後まで何の説明もなく、だ。
「沙綾〜。まだ目的地につかないのー」
「まあまあ、みーちゃん。もうちょっとで着くから」
みーちゃんとは支那原未来(しなはらみらい)、私の事だ。
まだ暗い早朝四時に起こされ、一時間半ほど車に乗ってから、さらに一時間は歩いただろうか。
鳥が、「ぎゃあぎゃあ」やら「きゅーきゅー」やら、いろんな声で鳴いているのが聞こえる。
私は、どんな秘境に連れてこられたんだろう。
それでも、眠気が覚めてくると木々の間を歩くことがだんだんと楽しくなってくるから不思議だ。
私達はしばらく森を歩いた。
「なんか気持ちいいね、沙綾」
「だよね。みーちゃん」
沙綾は、大きな眼を細めて、笑顔で私を振り返った。
早朝の木漏れ日を浴びて、天使のようだ。
腰まである黒髪があまりに綺麗で、本当に眩しい。
彼女は、『なんでテレビにスカウトされないの?』っていうほど美人だ。
そりゃもう、最初のうちは大学内でよく声をかけられた。だけど、みんな五分足らずで諦めて去っていく。
会話が、通じないのだ。一切。
この間なんか、かなりカッコいい大人の男性が声をかけてきたのだけれど、
「君の好きな所に連れて行ってあげるよ」
って、言われて沙綾は即答だった。
「セミ取り?」
あの時の男の人の顔、おかしかったなあ。遠回しに断られたと思ったらしい。
沙綾は、頭が良くて笑顔がきれいで、料理もできる。
私なんか、同じ部屋に住んでいるのをいいことに、料理に掃除、下着の洗濯まで彼女任せなのだ。
黙っていればモテるだろうに。
南の、秘境のような島出身の彼女は周囲からは恐ろしくズレていた。
「着いたよみーちゃん」
ぼーっとしていた私は、沙綾の声で我に帰った。
「わぁ!!」
思わず歓声を上げてしまった。
それほどすばらしい景色が広がっていたのだ。
「きれいでしょ?」
沙綾は得意げに胸を張って言った。
「うん、すごい。なんてキレイな湖…」
目の前には、澄んだ湖があった。
少し小さいけれど鏡のように澄んだ湖面は、空の青さと白い雲、それに周囲の木々の緑を映し出して、一枚の絵画のようだった。
その、綺麗な湖が太陽の光を反射して、キラキラと輝いているのだ。
「みーちゃん。荷物ちょうだい?」
「うん。これね」
私は荷物を沙綾に差し出した。
沙綾は中からなにやら棒状のものを取り出し、てきぱきと組み立てて行く。
出来上がったソレは、釣りざおだった。
「みーちゃん、そこのエサを出してくれない?」
「エサってこのタッパーに入ってるやつ?」
沙綾は頷いた。
私は言われるがままタッパーをあけ、素手で中身を取り出そうとした。
取り出そうとして凍りついた。
中にはタッパーいっぱいのミミズがいた。
「ぎゃーー!!!」
「もう、みーちゃん。せっかく私が昨日苦労して集めたんだから大事にしてよね」
「き、昨日?」
「そうそう。寮の庭がいい土だから、いっぱい取れたよー」
そう。こういう子なのだ。
なんだか子どもっぽいというか、野性的というか。
素手でセミを捕まえたり、蝶を追いかけたり。
本当、これさえなければモテモテだろうに。
「ご、ごめん沙綾。ミミズは勘弁…」
「えー、新鮮でおいしいのにー」
「おいしいって、『魚の気持ちになったら』ってことよね?」
沙綾は、笑顔のまま返事をしなかった。
もう大学に入学してからだから、彼女とは二年の付き合いになる。
それから気をつけていることが一つある。
絶対に『沙綾の料理中は台所に入らない』ことだ。
とにかく、どんな材料を使っているかわからない。
沙綾が食材の買い物をしているところを見たことがないのだ。
飼っていたカエルがいなくなったその日に、『疑惑のからあげ』が食卓に上ったこともある。
最初の頃は不安だったけど、最近ではどうせ美味しいのだから原材料を「聞かない」事にしている。
「じゃあみーちゃんこれね」
そう言って沙綾は、私にミミズの付いた釣りざおの一本を渡す。
「これって適当に投げればいいの?」
「そうそう、なんとなく遠くに」
沙綾は、非常に手馴れた手つきで竿を振る。
私も見様見真似でエサの付いた針を遠くに投げた。
暖かい日差しとキレイな景色。
ミミズさえなければ、釣りって気持ちよくて楽しいかもしれない。
「結構楽しいね。沙綾?」
ふと沙綾の方を見ると、なんだか忙しそうだった。
って、言うか。
「11…12…13…14…」
ぶつぶつと数を数えながら、すごい勢いで魚が釣れていた。
沙綾の手元が恐ろしいほど素早く動いている。
釣りって初めてだったけど、こんなに釣れるものなのだろうか。
いや、絶対にそんなことはないだろう。テレビで見る釣り名人だって、座ってゆっくり釣っていた気がする。
私は、沙綾は気にしない事にした。
「みーちゃん何匹釣れた?」
「何匹? って言われてもまだ来たばっかりじゃないの」
「えー! まだ釣れてないのー!?」
「初めてなんだから仕方ないでしょ」
「そっかー。じゃあワタシはもう夕飯の分釣ったから大物狙おうっと」
夕飯の分、と言いながら4、50匹の魚がクーラーボックスに詰め込まれていた。
「大物って、ここでは大きい魚でも釣れるの?」
「うん。こないだはねぇ、ワニが釣れたよ」
「へえ、ワニって日本にいるんだねえ」
「ね、みーちゃん。ワニ美味しかったでしょ?」
そうか、私はワニを食べた事があるのか。
私は、沙綾に笑顔で「うん」と返事を返す。沙綾の料理が美味しくなかったことなどないもんね。
沙綾は、会話に飽きると今までより遠くに竿を投げた。
私はまたぼんやりと、半分日向ぼっこのように自分の浮きを見つめていた。
(暖かいなぁ。ちょっと眠いかも…)
バシャッ。バシャバシャッ。
なんだかまた隣が騒がしい。大物が釣れたのだろうか。
今晩のおかずはなんだろうか。考えているとよだれが出そうだ。
私は、期待を込めて沙綾を見る。
すると、竿がありえない角度で曲がっている。
気づけば、湖に引き込まれないように、本気で両足で踏ん張っていた。
「ちょ、ちょっと沙綾! それやばいんじゃない!? 手伝う?」
「これくらいなら、ぎりぎり大丈夫――かな」
「そうは言ってもじりじり湖の方に引きずられてるじゃない!」
私は、慌てて沙綾の細い腰に抱きついた。
二人で格闘すること約三十分。ようやく魚の背が見えてきた。
鈍い銀色の背中。丸々と太った腹。
体長は、一メートル以上はあるだろうか。
そんな巨大魚が、沙綾の細腕で釣りあげられていた。
ただ、その巨大魚は――料理を一切しない私でも、見覚えのある魚だった。
沙綾は、満面の笑みで私に言った。
「うん。みーちゃん、今夜はマグロのお刺身だよ」
「ま、マグロ!?」
マグロは海に住む魚だと思っていた。こんな湖にいるなんて。
だけど、沙綾が釣り上げて陸上でパタパタはねているそれは、明らかにマグロだった。
「うーん。百キロくらいかなぁ。ちょっとちっちゃいね」
「そ、そうなの?」
私より細い沙綾の腕のどこからあんな力が出てくるのだろうか。
もう沙綾の奇行には慣れたはずの私にでさえ、心の許容範囲を超えかけていた。
「あ、みーちゃん。引いてる引いてる!」
「え、え? 何が?」
「竿だって! 引いてる引いてる」
私はここに座っている目的をすでに忘れていた。
気付けば椅子に立てかけていた竿が、引いていたのだ。
「どうしようどうしよう! 沙綾どうすればいい?」
「逃がさないようにそーっとリールを巻いて。慌てずゆっくりね」
「リール?」
「手元の糸巻きみたいなやつ」
私はようやくテレビ番組で見た釣りの光景を思い出した。
釣りざおの手に持つ部分の少し上に、釣り糸を巻く『リール』という部分がある。
それをゆっくり回すと、魚が釣れるのだ。
「そうそう、みーちゃんその調子」
「ゆっくり、慌てず、よね」
引きはあまり強くない。そう大きくはないみたいだ。
ゆっくり糸を引いていくと、魚が見えた。
「すごいよみーちゃん! 今夜はフグチリも食べられるね!」
ここはどんな湖なんだろう。
私の釣り糸の先で、ハコフグがぷくっとふくれっ面をしていた。
「でもフグって免許ないと調理できないよね?」
そう言って沙綾を見ると、フグ調理の免許証を私に向かって誇らしそうに掲げていた。
「あ、沙綾がさばけるのね…」
「ここでフグ釣るなんてすごいよ! さすがみーちゃん」
なんで湖にフグがいるかはもう気にしない。
やっぱりはじめての釣りで魚が釣れたのは嬉しいのだ。
「釣りって面白いね、沙綾」
「・・・・・・・・・」
「沙綾?」
沙綾はまた何かと格闘していた。
今度は釣り上げるのに時間はかからなかった。
それだけ小さい魚だったのだけど、釣り上げてからさらに格闘していた。
「沙綾、それって…」
私が沙綾に問い掛ける。絶対にありえない魚に見えたのだ。
鋭い牙を持っていて、釣りあげられてからも沙綾に噛みつこうとする獰猛さ。
こんな魚を、私はあまり多く知らない。
「うん、ピラニアだね」
沙綾はそう言うと、素早くピラニアに手刀を放った。
それまで元気だったピラニアは、一瞬で気絶した。
「ぴ、ピラニアもいるのねここ」
「前に来た時はいなかったんだよ。たぶん心無い人間が飼いきれなくなったからって捨てたんだと思うよ」
沙綾は本当に怒っていた。
「まったく。この湖の生態系が崩れたらどうしてくれるのかしら!」
ピラニアはダメでも、マグロとかフグがいるのは生態系としていいのだろうか。
でもまあ、沙綾の言うことも確かに一理ある。
ピラニアなんかを普通の湖に捨てたら、間違いなく湖の生態系は崩れるだろう。
それに、人間の都合で飼われたくせに、人間の都合で捨てられたピラニアも可哀想だ。
「それ、どうするの?」
すると沙綾は、キレイな笑顔をした。
「食べるの」
「そっか――」
今晩のおかずは、マグロとフグとピラニアに決定したらしい。
そんなに食べられるかなあ。
私は考える事を辞めて、釣りに集中した。
どうせ、おいしい夕飯になるに違いない。今のうちに動いてカロリーを消費しておこう。
私が決意すると同時に、竿に手ごたえがきた。
「沙綾! きたきた」
「それは重そうだけど弱った感じの引きだねぇ」
沙綾の言うとおり、重さはあるけど手ごたえが軽く、逃げるそぶりが見られない。
「それなら一気に引いちゃっていいと思うよ」
「よーし」
私はさっき釣ったフグの手ごたえを思い出し、ワクワクしながら糸を巻いた。
私は釣ったソレを見て、声もでなかった。
ちょっとツリ目で大きい目。細い体に細い腕。そして、とがった耳。
昔の映画で見たような、コイツは――
「こ、これ……」
「うん、宇宙人だね。また心無い人間が飼いきれなくなって捨てたんだよ」
「――沙綾。さすがにこれは飼わない」
あまりにありえない出来事に、私はかえって冷静になってしまった。
「えー、だって前はいなかったよ?」
「そりゃいないでしょうよ…」
なんだか頭痛がしてきた…。
すると沙綾が上目遣いに私を見る。
それなりに付き合いの深い私にはわかる。
以前この『上目遣い』をしたときは、公園に捨てられていたカメレオンを拾ってきたときだった。
飼いたいと言って絶対きかなかったのだ。
そのカメレオンが死んだ次の日に、疑惑のハンバーグが食卓に上ったけれども。
沙綾の上目遣いは危険な『おねだり』の目だ。
「みーちゃん、これ飼わない?」
当り前のように、沙綾が言った。
心なしか、宇宙人も涙目でこっちを見ている気がする。
「捨ててきなさい」
「だって可哀想じゃない。この子」
「そんな気味の悪いものと同じ部屋で寝れないよ?」
「えー、かわいいじゃない」
全身が銀色のメタリックな皮膚をしていて、必要以上に大きな目の人型の生物。
私には絶対可愛くは見えない。
「ほら、この潤んだ瞳。チワワみたいじゃない」
「他の部分がチワワとかけ離れてるじゃない」
「えー、本当にだめ?」
また上目遣いの潤んだ目。
顔がかわいいだけに、強烈な破壊力を持っている表情だ。
女の私でも、ついみとれてしまう。
すると、突然甲高い声が響いた。
「ねーさん、ねーさん」
「だ、誰!?」
「私ですわ。目の前の私です」
目の前にいるのは、沙綾とそして…
「そうですねーさん。私ですわ」
「宇宙人さんしゃべれたのね」
沙綾の目が輝いている。
もうだめだ。カメレオンの次は宇宙人を飼うことになりそうだ。
「いやー、私の宇宙船が壊れてしまいましてなー」
宇宙人は口を動かさずにしゃべっている。
それがすごい気味悪い。
「なんでエセ関西弁なのよ…」
どうでもいいところに突っ込んでしまった。イントネーションがおかしいのだ。
「そりゃ、ねーさん。私の船が大阪っちゅうところに落ちよったんですわ」
「へぇ、大阪ねぇ」
沙綾が、新しいおもちゃを見つけた子供のような輝く眼で宇宙人を見つめて言った。
「私がガキの時分でしてな。両親はそれで死んだんですわ」
宇宙人は口を動かさないまま、身の上話を始めた。
「可愛いガキの私には、一人で生きてくだけの力はあらへんもんでさまよってたんですが…」
「うんうん、大変だったのねぇ」
そう言って沙綾は宇宙人の頭をなでる。
「そんで、権蔵っていうおじいさんに拾われたんですわ」
「ゴンゾウさん? 二丁目の?」
沙綾の知り合いらしい。
「そうです。権蔵じいさんにはよくしてもろうたんですが…」
「先月死んじゃったもんね」
悲しいことをさらりと言う沙綾と無言で頷く宇宙人。
沙綾と権蔵じいさんがどんな関係かは聞くまい。理解できないだろうから。
「権蔵さんが死んでもうた時に、息子さん達に『大きくなりすぎたからもう飼えない』言われて捨てられてもうて…」
本当に『飼われてたのが捨てられた』のだとは思わなかった。
あとで沙綾に謝ろう。
「可哀想に…」
沙綾は、もう飼い主にでもなったかのような、慈愛の眼差しを宇宙人に注いでいた。
「それで、宇宙人くんは何が言いたいのかな?」
「それなんや。権蔵じいさんも、私を飼うのにえろうムリしたねん」
「ムリって?」
「私、お坊ちゃん育ちやったから天然モノの高級な食材しか食われへんし、それに私をかくまうのにそりゃもう難儀してん」
「そりゃ難儀したろうね」
と私。
「それでや。そちらの優しいねーさんに迷惑かけたくはあらへんから…」
そこで大粒の涙を流す宇宙人。
「わ、私のことは…ほっといてんか……」
血のような赤い涙を流す宇宙人と、必殺の涙目を向ける沙綾とに、私は追い詰められた。
「私は…もう人間様に迷惑かけとうないねん……」
そういって地面に座り込んで泣き出す宇宙人。
なんか可哀想かな…。
「私なんか、生まれてこなきゃよかってん。おとんやおかんと一緒に死んどけばよかってん」
「あ、あのさ宇宙人さん…」
私は居たたまれなくなって宇宙人の肩に手を置いた。
「私、ひどいこと言ってごめんね」
「ねーさん、私、クー、クーックーックーーーーッ」
引きつったような泣き声が、静かな湖にこだました。
(宇宙人ってやっぱり変わった泣き声するのね)
私がそう思ったその時だった。
沙綾が突然、地面に伏して泣いている宇宙人の頭を掴んだ。
「クーックークククーーッ」
私たちのそれと寸分たがわない、笑顔がそこにはあった。
「あんた、笑ってんの?」
「な! なに言うねんねーさん。これは私らの世界じゃ泣き声いうねん」
沙綾は私に背を向けて、宇宙人と向かい合った。
宇宙人は、最初笑顔だったのが、突然だらだらと脂汗をかいて、恐怖に引きつったような顔にかわった。
「す、すみませんねーさん…」
よほど怖い顔でも見たのだろうか。
沙綾が地面に下ろしたときには、すっかり宇宙人はしおらしくなっていた。
「あんた、笑ってたよね?」
と、私が問い詰める。すると宇宙人がいきなり土下座を始めた。
「すみませんでした! 本当はご飯食べすぎで追い出されたんでした!」
宇宙人は、訊きもしないのにあっさりと白状した。
どうやら、自業自得で捨てられたらしい。
「今まで話してたのは全部うそ?」
「私、一食で米を十合食うもんで、食費が足らんくなってしもたらしいんで」
「一食で十合って…」
「みーちゃんと私が一日かけて食べる量じゃない」
私は、同意のために頷く。
「ねーさん方も、大概大食いでんな」
「あんたには言われたくないわ!」
私は、宇宙人を小突く。
「いやー、地球は飯がうまくてうまくてかなわんです」
「それで? あなたは私たちにどうしてほしいの?」
沙綾が宇宙人に問い掛ける。
「できれば…私を飼うてくれるといいな、なんて思てんですけど…」
「ワタシ達にはそんなにお金ないわよ?」
沙綾が言った。
お金の心配より、宇宙人を飼うっていう世間体の方を心配して欲しい。
「私、なんでもしますから。こう見えて結構芸達者ですねん」
「へぇ、何ができる?」
沙綾は興味を持ったようだ。
「へい。釣りのエサになるミミズを探したり、室内のゴキブリを捕まえたりできます」
「それ役に立たないじゃん! 沙綾できるし!」
私はつい、ツッコミをいれてしまった。
「じゃ、じゃあえっと、その…」
「何? まだなにかあるの?」
私は、銀色の肌をした宇宙人との会話に慣れている自分に呆れながらも、聞いた。
「ありました! ありました! 取って置きのが!!」
「なになに?」
宇宙人の取って置きの特技…気になる。
「へい。私の目、透視できますねん」
「へぇ! それでそれで?」
「洋服くらいなら透けて見えますねん。ねーさんの今日の下着は白?」
「な…!」
私は本気で蹴りを宇宙人の頭に放った。
だけど一瞬早く、沙綾が宇宙人の頭を掴んで持ち上げていた。
そしてそのまま、野球の遠投のように――
ヒュー…………ぼちゃっ。
池に投げ捨ててしまった。
「沙綾思い切った事するわね」
「みーちゃんの下着は私以外には見せたくないもの」
沙綾はしれっと言った。
本気か冗談か、表情からはわからない。
「食べない宇宙人は湖に返すのが礼儀よ、みーちゃん」
「キャッチアンドリリース?」
「それそれ」
沙綾はそう言うと、笑顔で口笛を吹いた。
「どうしたの沙綾?」
「んっとね。知り合いに連絡取ったの」
「知り合い?」
「うん。波長を合わせるのに時間掛かるから、ちょっと待ってね」
沙綾はそう言うと、口の中でなにか呟き始める。
「こちら、三丁目の沙綾。応答してください――」
もう、何が来ても驚かないぞ。
「――そうそう。迷い宇宙人が一人」
嫌な予感がしてきた。
沙綾の交友関係の広さを、完全に侮っていた。
「ねーさん。ありがとう! 星に帰れそうや!!」
もう見えないけれど、宇宙人の声が湖に響く。
風景にはなんの変化もなかったけれど、ただ声だけが響いて、消えた。
沙綾は、空を見上げて手を振りながら言った。
「私の島でね、子供のころ隣に宇宙人が住んでたの。今でも友達なのよ」
「いいなあ」
私は素直にそう思ってしまった。沙綾の交友関係はなんだか楽しそう。
「内緒よ?」
沙綾は指を一本立てて私に言う。
なんて可愛いんだろう。
「なんかすごい湖だねここ」
私が話しかけると、沙綾はすでにテキパキと帰り支度を始めていた。
「ここは、私がお父様に教えてもらった秘密の湖なの」
「お父様って、漁師の?」
「うーん、いまはトレジャーハンターって名乗ってるみたいだけど」
沙綾のお父様は、元々沖縄の漁師である。
突然『冒険したい』とか言って家を出て以来、今は何をしているか沙綾でもわからないらしい。
「秘密の池だから、みーちゃん、ここ内緒にしてね」
そう言って沙綾は、その麗しい容姿をいかんなく発揮し、お願いのポーズを取った。
私は、そのポーズに一瞬みとれながら、さすがに『どうせ誰も信じてくれないから大丈夫』なんて言えないなあ、と思っていたのであった。
「今日のご飯、楽しみにしててね」
沙綾が、天使のような笑顔で言う。
「うん!」
もはや、宇宙人のことなど私の頭から消え去った。
「それにしても、沙綾って人間の友達いるの?」
「みーちゃんがいるじゃない」
「えー。意外と私たちって噛み合ってないと思うけど?」
「ううん。私とみーちゃんって波長が合うのよ」
「なにそれ」
私たちの笑い声が、風を呼んで湖の湖面が揺れる。
風がとても心地よくて、私は『また来たいな』と思った。