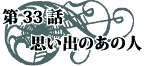
「短い距離ですが、歩くよりは速いくでしょう。スクーレからティゴル谷は南西へ、リーヴェなら 北へ二十日も歩けば着きます」 「ありがとうございます。ジョカミ殿」 レイラントの街に着くと、ちょうど隊商の馬車がスクーレへと出立する頃合いだったので、R・Rの 交渉により同乗させてもらえることになった。夏の間を歩きっぱなしだった一行にはありがたい できごとだった。 「私もずっとご一緒できればよかったんですが、私はゼレス市領を出れない身ですので、ご容赦ください」 R・Rは残念そうに頭を下げた。団長は自分から手を差し出した。 R・Rには戦略を立てる上で数々の助言を与えてもらったし、何より団長の眼を通してみる彼は…… 「……もう、お会いする機会は無いかもしれませんが、R・R殿には大変感謝しております」 R・Rは本当に嬉しそうに笑い、手をしっかり握り返してきた。大きな厚い手の平だった。 「あなたが精霊の加護を受けてるように、私の血は御使いの加護を受けております。 私の寿命が終わっても息子が跡を継ぎます。ちょっと熱くなりやすい馬鹿なんですが、 次にゼレスにいらっしゃった際には会ってやってください」 「ええ、ぜひ」 この瞬間に手に残った感触を、忘れないでいたかった。 団長は一礼をして、すでに全員が分乗し終わっている馬車へ向かった。 ワイズは幌に持たれかかって二人の様子を眺めていた。 他の団員達とは別れて、わざと荷物がぎゅうぎゅう詰めの最後尾の車両に一人で乗っていた。 隣に乗ってきた団長を見上げた。 「あいつのことをどう思う?エヴァンス君」 「先達として、勉強になる話しをたくさんしていただきました」 「悪く言うつもりはないが、胡散臭くなかったかい?」 「……」 ワイズの指摘に、団長は戸惑った。確かにR・Rの発言の数々は、部外者にしては核心を突くことが多かった。 困った団長は少し照れなが答えた。 「……ジョカミ殿の声が、その……前団長と似てまして。身長も同じくらいでいらっしゃって、お話していると 前団長のことを思い出してしまって、その……」 ワイズは意外な答えに驚いた。 そうだ、エレオノーレが真面目に任務に当たる騎士だとしても、まだ16歳の女性だったのだ。 (……心まで使命のために犠牲にしろとは、言えないな) 若さゆえに惑わされるのも経験のひとつだ。ただ、彼女の場合は失敗が致命的になることが問題だったが、 釘を刺してやる元気がワイズに残っていなかった。 「今回のことがなければ騎士団なんて無縁だったから、前の団長のことは知らないな。 どんな人だったんだい?R・R・ジョカミみたいな策略家だったのかい?」 団長はワイズの隣に座り、背を幌に持たせかけた。 先頭車両の御者の声が響き、隊商はゆっくりと動き始めた。 外を見ると、R・Rが手を振って見送ってくれていた。 団長は手を振り返えした。 「いいえ、頭脳労働は苦手な方でした。私が配属された途端に記録の作成から報告書まで、書類処理は 全部私の仕事になりました。警備に出る、と言ってはすぐに本部を開ける方でした。 お酒をたしなまれるのがお好きで、よく酒場に長居されてましたし、飲酒の後に高揚されると、 壁に攻撃を仕掛けるような方でした」 団長は本部の執務室の壁の穴のことを思い出した。ヴィヴィ・オールリンのポスターで無理やり隠した 思い出の壁の穴だ。 「聞く限り、あまり騎士としては褒められた印象は受けないね」 ワイズの答えに、団長は表情を緩めた。 「そうです。まったく困った方でした。毎日翻弄させられて、街中を探し回って、追いついてもすぐに 逃げる方でした。それでも、私にとっては尊敬に値する方です」 前団長の話をするエレオノーレの表情は今まで見たことのないものだった。 エルヴァールの前でも、こんな顔をしたことはなかった。 元々の顔立ちは悪くない女性だ、こんな表情をされれば大抵の男は心を動かされるだろう。 団長は人差し指を唇に当てた。 「これ以上は職務上の秘密によりお話できませんが、前団長は騎士の中の騎士だと私は誇っています」 「ふ〜ん、君がそんな風に言うなら、よっぽどなんだろうね」 幌に切り取られた風景がどんどん流れていった。地平線が視界の上方へ移動した。 馬車は斜面を登っていった。轍に合わせてガタゴトという振動が伝わってきて、 尻が痛くなってきた。団長は横座りになって、体重のかかる位置を変えた。 ワイズはずっと同じ姿勢のまま、ボソリと呟いた。 「エヴァンス君、僕の峠は……」 それだけ言うと、ワイズはうなだれた。 団長の頭からフィニーが飛び立ち、ワイズの帽子に留まった。 三日月の飾りはフェルフェッタが持ったままだったので、帽子の先端が空しく揺れた。 「……すまない。聞かなかったことにしてくれ。悪いけどちょっと横になってもいいかい? 体がダルいんだ」 どうぞ、と団長は言ってできるだけワイズのために場所を空けた。 重たそうに横になったワイズに、団長は荷物の底から古い赤い外套を取り出し、 かけてあげた。ワイズは短く礼を言い、しばらくすると規則正しい寝息を立て始めた。 団長は彼の周りに浮かぶ、彼の人生の峠を表す数字をじっと眼で追った。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 暗い地下室で少年は自分の眼を疑った。 自然の光を長い間見なかったため、眼がおかしくなったのかとも思ったが、 地下水路で育った自分にはそんなことはありえないという自負があった。 「質問があるならするがいい」 目の前の少女が言った。 白い防護服に身を包んだ人物はどう見ても15、6歳の年頃の少女だった。 黒い髪の根元はやや金色がかり、バートヘルメットの隙間には見覚えのある黒い痣があった。 「無いなら、早く餌を与えてやってくれ」 少女は顎で少年の隣を指した。 彼が握っている手綱の先には若い活きのいい馬が繋がれていた。 最も、今は薬で大人しくされており自分で歩くことができる程度の自由のみが与えられていた。 少年は持っていた鞭で馬の尻を叩いた。驚いた馬はいなないて前進を始めたので、 手綱を手放した。馬の蹄が石作りの床を蹴る音が二、三した後に急に消えた。 代わりに甲高い悲鳴とぬめるような水音が聞こえてきた。 悲鳴は段々とか細くなり、やがて静まり返った。何かが床をはいずる音が迫ってきたが、 彼の目の前に剣を構えた少女が立ちはだかると、音は引いていった。 「ふむ。だいぶ質量が増えてきたな。そろそろこの部屋では問題が生じてきそうだ」 少女が彼を振り返った。口元に面影が残っていた。 認めたくはなかった。 しかし、認めなくては、彼女の存在に説明がつかない。少年は意を決して少女に声をかけた。 「メルレーン先生……」 「質問か?」 少女はバードメットの庇を上げた。 人を見下すような色を宿した、見慣れた瞳が彼を見上げていた。 目の前の少女は、メルレーン・ウシュ博士その人だというのだ。 少年は胃のあたりがムカムカしてきた。この部屋に立ち込める黒い物体の臭気にあてられた だけではなかった。 この人の前では無様な姿を見せたくない、弱みを決して見せたくない! その一心で吐き気をこらえて、両足を踏ん張って彼女と対峙していた。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 夢を見ていた。昔の夢だ。 黄色の花が咲き乱れる、グラツィアの夏が背景だ。 「あなたって、本っっ当に失礼ね!」 そう言って神官見習いの少女に張り手を喰らって、僕は間抜け面で立っていた。 顔をはたかれたのは生まれて始めてことだった。 彼女は僧坊の階段を一気に駆け上がり、二階の廊下を走っていってしまった。 「なんだ、振られたのか?ウェローの」 後ろからメルレーンの声が聞こえてきた。 「派手に振られたね〜」 ついでにトラトリアのからかい声も聞こえた。 僕は頬をさすった。こんな広場での茶番劇だ、見られていて当然なことを失念していた。 「……予想外だな……」 僕は観念して振り返った。 モルサガルサ代表のトラトリアがニヤニヤしながら僕を覗き込んだ。 「え〜?シーテ君の答えこそが予想外だよ。自信があったの?」 僕は答えなかった。 そうではなく、あんな娘に心を動かされたことが予想外だったのだ。 小賢しいトラトリアから目をそらしたら、サイラス代表のメルレーンと目があった。 「セオリー通りに行くなら、ここは追いかけたほうがいいと思うが?」 彼女は笑いを含んだ声で僕に助言をくれた。 「いいや。もう馬車が出る時間だ。逃してしまうとウェローに帰るのが一日後れてしまう」 「べっつに、ちょっとくらいは待ってくれると思うけど?」 「モルサガルサの。彼は自分のせいで馬車の出立予定を狂わせることなんて耐えられないのさ」 「あっそ」 トラトリアは面白くなさそうに、盛大に鼻息を出してから踵を返して馬車に飛び乗った。 メルレーンも肩をすくめて馬車に足をかけた。僕も続くために、そちらへ歩き出した。 「女心が分からん奴だなぁ、ワイズ・シーテ」 メルレーンは振り返らずに言い放った。 僕の足が止まった。 石畳には夏の日差しによって、僕型の濃い影が落ちていた。 僕の足が動かなかった。 馬車に乗り込んだメルレーンは頬杖をついて僕を見ていた。 どこか僕を哀れむような、不愉快な眼差しだった。 「理論や数値だけでは、勝てない戦局もあるんだよ、今年の優勝者殿」 彼女のその一言で、僕の足はようやく動いた。 夏の暑さで眩暈がしそうだ。 黄色の花が咲き乱れる、グラツィアの夏が背景だ。 夢を見ていた。昔の夢だ。 そうだ、グラツィアであった弁論大会での思い出だ……。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 遠い北の地で少年は手紙を書いていた。 「お母さん宛て?」 隣の席のクラスメートがおっとりとした口調で尋ねた。 「ううん、これは友達宛て」 手の中の羽ペンをくるりと回して答えた。 「ヴァレイの友達?」 「んー、ちが〜う」 「カノジョ?」 「あっは!」 興味深々の友人にこれ以上詮索されないように、少年は手紙を中断してバインダーに挟んで 隠した。 「あれっ、ごめんね?」 「いいよ。まだ書くことまとめてなかたから、もうちょっと色々と考えたいんだ」 「そっか〜」 クラスメートはそのまま机に両手を伸ばしてだらしなく伸びた。 「ふぁ〜あ〜……。退屈ゥ……。ねぇ、シーテ。君はお父さんの跡を継ぐの?」 「なんで?」 少年は少し不機嫌な声で答えた。 「そりゃやっぱ、君のお父さんは有名人だもん。王様の同級生で大陸弁論大会を二連覇して、 特殊研究機関に就職したのに、先生になって司書やって、今は『あの』流星騎士団で旅してるんだよ。 すごいよねー」 「……父さんがすごい肩書きを持ってたからって、僕には関係ないよ」 そうは言いつつも、自分がウェローに留学ができたのは、父の七光りの威力もあることを 察してはいた。父の元から飛び出したくて、実家を離れて留学したはずだったのだが、 今となっては父親当人が家を空けてどこかをほっつき旅しているのだ。 なんだか本末転倒だった。 「はぁ……母さん、一人で大丈夫かなぁ……」 独り言を無意識に呟いてからハッとしたが、遅かった。 クラスメートはにやにやしながら横目で彼を見上げていた。 「やーい、マザコン!」 自覚はしてるので反論はしなかった。 大体、母さんを一人にして騎士団なんかに入るなんてどうかしてる。 父親の顔を思い出すだけで腹が立ってきた。 授業後、自分の部屋に戻ると、すぐに手紙の続きを書き始めた。 最近、相手を食堂で見かけないことに対する気遣いと、今後の自分の進路についての悩み。 近隣の村を魔物が荒らしていることに関しての思うところ、等々。 自分で決めたルールで、手紙は一枚に収めるようにしている。 あまりたくさんのことは書けない。 相手から返信は一度も来たことがなかったが、少年は手紙を出すことを止めなかった。 相手がおいそれと返信を書けるような立場にいないことは承知していた。 ありがた迷惑かとも思ってはいるが、食堂で彼を見かけるたびに、 誰かを探してる様子を見ると、ついつい次の手紙を書きたくなってしまう。 便箋を封筒に入れて×点で封をした。それを机の上に置いて表面に指で簡単な図形を描いた。 封筒はくしゃくしゃと歪み始め、鳥の形になった。 あとはチョイッと魔力を加えれば宛先の元に羽ばたいていく。 今度、渡り廊下に佇む彼を見かけたときに送るだけだ。 「う〜ん、ここのディティールがイマイチ……」 紙細工の鳥の形が気に入らなく、少年は再び指で図形を描いて変形を繰り返した。 「よしっ!かっこいい!!」 満足の行く造詣になった手紙鳥をしばらく眺めて悦に入った後、今度は王都に住む母親に向けて 手紙を書き始めた。 「拝啓、アルフィナ様……と、お変わりありませんか……」 前の話 次の話 |