TOP > データベース > 2019年(平成31年/令和元年) >六月大歌舞伎 歌舞伎座
六月大歌舞伎 歌舞伎座
2019年6月1日(土)~6月25日(火)
配役
昼の部(11:00開演)
一、寿式三番叟(ことぶきしきさんばそう)
三番叟:十代目 松本幸四郎
三番叟:二代目 尾上松也
千歳:六代目 中村松江
翁:六代目 中村東蔵
二、女車引(おんなくるまびき)
千代:二代目 中村魁春
八重:六代目 中村児太郎
春:五代目 中村雀右衛門
三、梶原平三誉石切(かじわらへいぞうほまれのいしきり)
梶原平三景時:二代目 中村吉右衛門
大庭三郎:三代目 中村又五郎
俣野五郎:三代目 中村歌昇
梢:五代目 中村米吉
大名山口十郎:初代 大谷桂三
同 川島八平:六代目 中村松江
同 岡崎将監:初代 中村種之助
同 森村兵衛:初代 中村鷹之資
囚人剣菱呑助:三代目 中村吉之丞
奴萬平:二代目 中村錦之助
青貝師六郎太夫:五代目 中村歌六
四、恋飛脚大和往来(こいびきゃくやまとおうらい) 封印切
亀屋忠兵衛:十五代目 片岡仁左衛門
傾城梅川:初代 片岡孝太郎
丹波屋八右衛門:六代目 片岡愛之助![]()
阿波の大尽:五代目 澤村由次郎
槌屋治右衛門:初代 坂東彌十郎
井筒屋おえん:二代目 片岡秀太郎
夜の部(16:30開演)
三谷かぶき
月光露針路日本(つきあかりめざすふるさと)風雲児たち
みなもと太郎 原作
三谷幸喜 作・演出
大黒屋光太夫:十代目 松本幸四郎
庄蔵、エカテリーナ:四代目 市川猿之助
新蔵:六代目 片岡愛之助![]()
教授風の男:二代目 尾上松也
キリル・ラックスマン、アダム・ラックスマン:八嶋智人
マリアンナ:初代 坂東新悟
藤助:三代目 大谷廣太郎
与惣松:初代 中村種之助
磯吉:八代目 市川染五郎
勘太郎:初代 市川弘太郎
藤蔵:二代目 中村鶴松
幾八:四代目 片岡松之助
アレクサンドル・ベズボロトコ:二代目 市川寿猿
清七、ヴィクトーリャ:三代目 澤村宗之助
次郎兵衛:三代目 松本錦吾
小市:六代目 市川男女蔵
アグリッピーナ:十一代目 市川高麗蔵
ソフィア・イワーノヴナ:五代目 坂東竹三郎
九右衛門:初代 坂東彌十郎
三五郎、ポチョムキン:二代目 松本白鸚
データ
筋書
愛之助丈関連
舞台写真:「封印切」丹波屋八右衛門:4枚
舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(船の上):2枚
舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(ヤクーツクまで):5枚
舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(犬橇):1枚
舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(イルクーツクから):5枚
舞台写真:「月光露針路日本」新蔵(ラスト手前):1枚
61~62ページ:「花競木挽賑」(1/3ページ)
舞台写真
愛之助丈は、
「封印切」丹波屋八右衛門が5種類(仁左衛門丈の忠兵衛との2ショット1種類を含む)
「月光露針路日本」新蔵が22種類
(以下を含む)
・船の上 2種類
・ヤクーツクまで 8種類(幸四郎丈の光太夫と猿之助丈の庄蔵との3ショット1種類、集合写真1種類含む)
・犬橇 4種類
・イルクーツクから 8種類(彌十郎丈の九右衛門との2ショット1種類、新悟丈のマリアンナとの2ショット2種類、猿之助丈の庄蔵との2ショット1種類、集合写真1種類含む)
料金
1等席:18,000円
2等席:14,000円
3階A席:6,000円
3階B席:4,000円
1階桟敷席:20,000円
筋書:1,300円
雑誌
「act guide(アクトガイド)」 2019 Season 2 (TOKYO NEWS MOOK 803号)
愛之助丈関連
3ページ(目次):舞台写真「月光露針路日本 風雲児たち」犬橇の場面
8~11ページ:松本幸四郎、市川猿之助、片岡愛之助 鼎談
9ページ:3ショット(カラー)
14ページ:「月光露針路日本 風雲児たち」稽古場レポート
15ページ:八嶋智人インタビュー(稽古場の写真あり)
16ページ:舞台写真「月光露針路日本 風雲児たち」
写真はすべてカラー。
→act guide[アクトガイド] 2019 Season 2 (TOKYO NEWS MOOK 803号)
感想
昼の部
23日に中央花道寄りで観劇。
寿式三番叟
最初は千歳(松江丈)、翁(東蔵丈)が厳かに舞っていたが、三番叟(幸四郎丈&松也丈)の踊りはだんだんと激しくなっていく。
花道で足を踏み鳴らすところですごい音がなっていた。
何年経っても踊りはわからないが、2人が並んで同じ振りを踊ると、個性というか、違いというか、わからんなりにわかるなぁと思った。(←何がだよ。)
女車引
千代(魁春丈)、春(雀右衛門丈)、春(児太郎丈)の女形3人の華やかな踊り。
やっぱり踊りはわからなかったので、きれいだなぁと思って見てた。
梶原平三誉石切
歌六丈の六郎太夫、又五郎丈の大庭三郎、歌昇丈の俣野五郎、米吉丈の梢、種之助丈の梶原方大名と播磨屋さん勢揃い。
吉右衛門丈は重厚なイメージなのだが、梶原平三はどこか軽みがあって爽やかな感じ。
つっこみどころがないくらいまとまった舞台だった。梢がひたすら可愛かった。
そして、供侍の愛治郎丈をつい目で追ってしまった。
封印切
もしかしたら、この演目を一番よく見てるかもしれない。
今回は、仁左衛門丈の忠兵衛、孝太郎丈の梅川、秀太郎丈のおえん、愛之助丈の八右衛門、彌十郎丈の治右衛門で、松嶋屋型の封印切。
松嶋屋型を見るのは2回目。前見た時より、成駒屋型との違いにあれこれ気付くことができた(が、すでに忘れつつある)。
愛之助丈は、仁左衛門丈相手で力が入ってるのか、ちょっと表情が大袈裟な気がした。
仁左衛門丈は封印を切った時の魂の抜けてる表情が素晴らしい。それを見つめる愛之助丈の驚愕の表情もよかった。
八っつあんは絶対に忠さんの金子が為替の金ってわかってるよね。「うわ! マジか! こいつ、ホンマに切りよったで!」って顔だった(と、私には見えた)。
夜の部
22日に2階から観劇。
↓席からの眺め。
三谷かぶき
月光露針路日本 風雲児たち
細かい場面を上げているときりがないので、大雑把な感想。
開始前に幕が開いて、波のセットが出てきた。
花道から教授風の男(松也丈)がスーツ姿で現れ、現代劇のような幕開けだった。
それから、舞台は難破船の上に移る。
大黒屋光太夫(幸四郎丈)、庄蔵(猿之助丈)、新蔵(愛之助丈)ら船乗りがあれこれ言い合っている。
庄蔵は文句ばかり、新蔵は自分勝手な印象。
しかし、新蔵はおかしくなった小市(男女蔵丈)を気にかけているし、死にそうな仲間を鼓舞するために「昆布が流れてきた」と優しい嘘をつくし、まあなんというか、ツンデレ。
庄蔵はことごとく美味しいところをかっさっていってたような…?
一向はロシアのアムトチカ島に流れつき、その後各地を転々とする。
序盤、だれてるように感じるが、三谷脚本では、それこそが伏線というか、最後の悲劇を際立たせる効果があるんだよなぁ…
前述の優しい嘘がラストの磯吉(染五郎丈)の「富士山です!」につながってくるところが、よく考えられてるなぁと思う。
雪原を犬橇で進む場面は圧巻。上から見れてよかったかも。愛一朗丈、頑張ってたね。
マトリョーシカみたいなロシア娘(高麗蔵丈&宗之助丈)と父親(千次郎丈)とのやりとりはロシア語のためさっぱりわからず。松也先生、木に化けてるヒマがあったら解説してくれ。
ラックスマン(八嶋智人さん)は上手いし、客席の受けもいいんだけど、パワフル過ぎてパワーバランスが崩れてる感じがしなくもない。
エカテリーナ(猿之助丈)との謁見の場面は「これ、何の芝居?」状態。俳優祭の宝塚パロが始まったかと思ったわ。
ポチョムキンの白鸚丈はロシア貴族の扮装が似合い過ぎ。
ソフィア・イワーノヴナ(竹三郎丈)とアレクサンドル・ベズボロトコ(寿猿丈)の“御年合わせて176歳”カップルには驚いた。
光太夫と庄蔵、新蔵との別れの場面には泣いた。
新蔵がかっこつけたままで終わらず、「連れてってくれ!」という魂の絶叫を入れてくるあたり、実際の手記をもとに描かれてるだけあると思った。
最初は17人だった仲間がとうとう3人になり、小市もついに力尽きる。
生きて日本に帰ったのは、光太夫と磯吉のみ。
光太夫のセリフに合わせて、全員の幻が現れるところもよかった。
最後はダブルカーテンコール。
笑いあり涙ありで楽しく見れた。細かいところを見落としていると思うので、DVDを出してほしい。
おまけ
幕間にめで鯛焼きを買おうと3階に行ったら、あと少しというところで売り切れた。大入り満員ってわかってるんだから、数を増やしてくれればいいのに…

↑代わりにあんみつを食べた。(夜の部の幕間)

↑歌舞伎座近くのトレオンというお店でちょっと遅めの夕食。
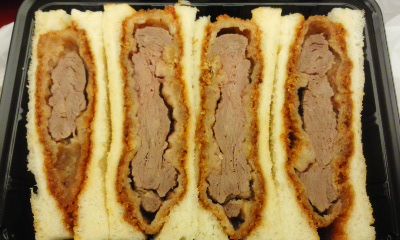
↑昼の部の幕間は木挽町広場で買ったビーフサンドを食べた。
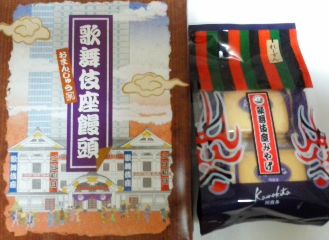
↑お土産は歌舞伎座レーズンサンドと歌舞伎座饅頭。