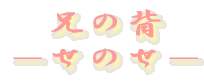 |
||||
| 俺が今一番気を使っている身嗜みって奴は、爪だった。 こう言っちゃあなんだが、俺は結構洒落者だ。 身なりには、帯一つとっても煩い。 稽古で使う面の紐だって、皆と違い自分の好きな赤色にするぐらいだし、俺自身だけじゃなく、総司の格好もあいつが子供の頃から、俺が見立ててやってた。 だから、爪だって今まで不精に伸ばしていたことはないんだ。 けど、俺は今、前よりいっそう気をつけるようになった。 その理由は、総司の背中に派手な蚯蚓腫れを、俺が作ったからだ。 総司が元服した夜、俺は総司と初めて情を交わした。 奴の想いに絆された形だったが、真摯な想いに応えてやりたかったから。 もちろん、俺も総司を想っていたし。 その夜は初めてなのにもかかわらず、時が経つのを忘れて、抱き合った。 それこそ、身が蕩けるぐらいに。 で、そのあくる日、さすがにいつもより遅く、朝の日課である素振りを繰り返してる総司を、俺は部屋の中で布団に包まりながら、惚れ惚れと眺めていた。 いつもなら、俺も一緒にするんだが、今日はとても出来そうもなかったから。 そして、総司が一心不乱にしているように見えて、こっちをちらちらと見るのが面映かった。 そこへ、この家の主の鹿之助さんが現れた。 天然理心流の後援者でもある鹿之助さんは、昨日の総司の元服に際し、宗次郎を『総司』と名付けた名付け親だ。 総司の甲高い居合いの声が、良く響いていたから気になって見に来たんだろう。 あいつの声は良く響くんだ。それに特徴があるから、すぐに分かる。 素振りを終えた総司は、鹿之助さんと笑いながら傍の井戸へ行き、汗を拭おうと諸肌脱ぎになった。 汗できらきらと光る総司の躯は、張りがあり瑞々しい若さに溢れていた。 あの躯に昨夜抱かれたのかと思うと、躯の芯がそれだけでまた熱くなりそうだった。 だが、井戸の釣瓶を上げるために、向こうを向いた総司の背中を見て、俺は思わす「あっ」と声を出しそうになった。 その背にはくっきりとした蚯蚓腫れが、幾筋も。 それを隠したくて体を浮かしかけた俺だったが、部屋の中ではどうすることも出来ず。 総司は当然そんなものがあるなんて、思っても見なかったに違いない――なにせ、あの最中は互いが夢中で気遣う余裕なんてなかった――が、水を被った途端気付いたみたいだ。 多分、傷に沁みたんだろうな。 はっとしたように、身をいったん硬くした後で、何気ない素振りを装い、着物を着たけど。 でも、鹿之助さんには、なんの傷かばれたろう。 なんせあの至近距離だ。見間違えるはずがない。 そりゃ、総司も男だ。 ああいう傷が背に付く行為をしていたとしても、可笑しくはない。 可笑しくはないのだが、如何せん、傷が新しすぎた。 どう見ても、昨日今日ついたばかりの真新しそうな傷では、女につけられた傷だとは言い難い。 何故かって言やあ、総司は元服の儀式のために、二日前からここに逗留してるし、そんな総司に女が近づく余裕なんてなかった。 総司と一緒に素振りもせず、布団の中に居て一歩も動かない俺――いや、実際には体がいうことを聞かず、動きたくても動けなかったんだが――と、どう考えても情事でつけられたに違いない傷。 この二つを組み合わされば、答えは一つしか思い浮かばないと自分でも思う。 俺の身なりは一応きちんと整えられてたし、表面上は――寝巻きの下には総司の付けた鬱血の痕が散らばっていた――総司との情交の痕など留めてはいなかったが、きっとばれたに違いない。 俺の方を鹿之助さんは、とっさに振り向いたもんな、あの時。 それだけで、何も言わずにいてくれたのは、有り難かったが。 俺はそれ以来、爪の手入れには気を使う。 殊更短く丁寧に爪を切り、総司の肌に爪を立てても酷い傷にならぬように。 本当なら爪を立てなければいいんだが、それは俺にはどうやっても無理だった。 何でかというと、以前は痛みを堪えるためだったが、今は快感を堪えるためにどうしても立てずにいられなくて。 二度目の時も気をつけていた筈なのに、途中から我を忘れて結局総司の背に派手なのを作ったし。 自分の躯に痕が残るのはいいんだ。 総司に付けるなとは言いたくないし、むしろ残っていて欲しいとも思う。 けど、総司がとやかくからかわれたり、煩わされたりするのは、我慢できなかった。 そうならないように、気をつけるのが年上たる俺の役目だろう。 だから、今日もせっせと爪の手入れを怠らない俺だった。 |
||||