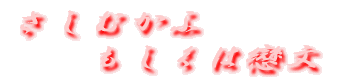 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 「ふふっ」 総司のすこぶる嬉しそうな笑い声が、歳三の耳に届いた。 「なんだ?」 情交の後のだるい躯を、仰向けにして寝転がっていた歳三は、隣で肘をついて何かを覗き込んでいる総司を横目で見遣った。 「えっ、だって、嬉しいじゃないですか」 歳三に振り向いて、総司はにこにこと、笑いかける。本当に心から嬉しそうだ。 「なにが?」 額に纏わりつく髪を掻き揚げ、訝しげな歳三に、 「だって、これ」 そう言って、総司が歳三の目の前に差し出したものは、歳三が総司に渡したもので。 「歳さんから、こんなの貰うなんて……」 そう言いながら総司は、歳三に貰った時を思い出していた。
総司が、歳三からそれを貰ったのは、日野へと歩む、その道中だった。 試衛館一党が京への上洛を決め、各所への挨拶回りにそれぞれが奔走し、総司と歳三もそれに漏れず、郷里へと一緒に足を運んだのだ。 総司は、日野に住む姉みつの元へ。みつの婿林太郎が、白河藩の籍を離れて以後、林太郎の生まれ育った日野で生活をしていた。 歳三も同じく、日野へ嫁いでいる姉のぶの元へ。既に家を継いだ次兄のいない土方家よりも、歳三にはのぶのいる佐藤家のほうが家らしく、実家よりも先にこちらに来ることにした。 同じ場所に向かう二人だ。朝早くに試衛館を出て、途中持ってきていた握り飯など食べながら、特に急ぐでもなく日野への道中を歩いていた。 少し雪のちらつく中、一休みしようと地蔵の祠の前で、二人軒を借りて腰を下ろした。 「京って、いったいどんな処なんでしょうねぇ?」 竹筒に入れてある水で喉を潤しながら、遠く空の彼方を眺めながら、総司は呟いた。 「千年王城の地、でしょう? 江戸とは、だいぶ違うんですかね?」 歳三がその顔を見ると、総司の眼はわくわくと輝き、不安は微塵も感じられない。その表情に、どこかほっとしつつも、歳三はそっけなく応えた。 「さあな」 眼を総司から逸らし、歳三も彼方の空を見上げた。二人はしばらく、無言で空を見ていた。 「お前、本当によかったのか?」 歳三のどこか沈んだ声音に、総司は歳三の顔を覗き込んだ。 「何が、です?」 感情を削ぎ落としたかのような歳三の顔を、総司は見詰めて訝しげに首を傾げる。 「京に行くことになって、お前は本当によかったのか?」 「勿論ですよ。どうしてです?」 「…………」 如何胸の内を伝えようかと迷っている様な、そんな歳三の様子に、ますます総司は首を傾げる。 何を思い煩うことがあるというのだろうと。 「お前は、天下国家のことには、興味はないだろう?」 「ええ」 「それに、武士になりたいという夢もない」 総司は歳三と違って、下級とはいえ、名字帯刀を許された武士だ。だから、武士になりたいと思うことはあり得ない。 「…………」 歳三の言いたい事が分からず、戸惑いの中で総司は沈黙するしかない。 「俺や、勝ちゃんは、百姓だ。こんな格好をしていても、武士じゃない」 歳三の格好は、町人髷でなく、総髪にして後ろで束ねているものだ。その髪型は、今浪士の間で流行っているものだ。 また、着流しではなく、袴を穿き、腰には刀を大小二本差している。 だから、それだけ見れば、どこから見ても武士の姿だ。たとえ、胡乱な浪人の姿に見えようとも。 「武士の格好を真似ているだけだ」 しかし、やはり、武士の身なりをしただけの、偽武士だ。それは、自分自身が、一番わかっている。 「攘夷だなんだと言ったところで、俺たちはれっきとした武士になりたい、その一心で今度の将軍警護に参加する」 きっと、江戸での平穏さは、京にはない。なにせ天誅の嵐が吹き荒れている、その只中に行くのだ。 だからこその浪士募集であり、将軍警護とは名ばかりで、使い捨てされる危険も大いにある。 それでも、自分たちが行くのを決心したのは、試衛館という生暖かい居心地のいい場所で、費えることの怖さだった。 自分の手で、何事かを成し遂げたい、その欲求にしたがって、危険も顧みずに飛び込もうとしている。 だが、それに総司を巻き込むのは、間違いではないかと、歳三には思えてきていた。 「だが、お前は……」 「俺は、皆と京へ行く。そう、俺が決めたんですよ」 ほんの少し憮然とした声で、総司は歳三の言葉を遮った。 「前にも言ったでしょう? 俺は、貴方と共に、貴方の歩む道を、何処までも行くと。その背中を追い駆けて、追いついて、そして横に並び、生きていきたいんだって」 総司の真っ直ぐな眼が、歳三を射抜く。何の迷いもない澄み切った眼が。 「確かに、俺は微禄とはいえ、武士の出です。だから、武士になりたいとは思わないけど、貴方と共に夢は見たい」 逸らすことは許さないとばかりに凝視られて、歳三の躯が慄いた。 「貴方の夢の中に、俺はいませんか? 要りませんか?」 「いや……」 歳三は首を振った。 そんなことはない。歳三の夢の中には、必ず総司がいたのだ。 いつでも、歳三の傍らには総司がいる。それが当たり前で、当然の想いだった。 それを疑ったことは一度もない。そう、総司が子供の頃から、ただの一度も。 だが、京へ上るということは、江戸ではあり得ない危険に、身を晒すということで。 それを、考えたとき、ふと怖くなったのだ歳三は。 自分の身が危険に晒されるのはいい。それさえも、納得づくで京に上るのだから。 しかし、総司の身に危険が及ぶのは、嫌だった。総司の剣の腕は天才と呼ばれるのに相応しいものであり、歳三のそれが単なる杞憂であったとしても。 そして、総司が人を斬るということも、嫌だと思ったのだ。 歳三が武士になりたいと思ったのは、もともと我侭な憧れからだった。 けれど、ひとつには総司の存在の所為もあった。総司は下級とはいえ武士の出で、歳三はどう言っても百姓だ。 確かに家は豪農で、食うに困らず、総司より恵まれてはいたが。 だが、長じるにしたがって、厳然とした身分の差が、存在していることに気付かされた。 総司と関係を結ぶのを、長い間呻吟し、躊躇していたのも、その所為だった。 剣の腕は、総司の方が遥かに上。喧嘩では負けなくとも、一度剣を持てば、総司の足元にも及ばない。 総司は、田舎剣法、三流道場よと蔑まれていても、試衛館道場の塾頭で。歳三は目録止まりの居候にしか過ぎない。 それでも、総司は何かにつけ、歳三を立ててくれていたのだが。 しかし、武士になれば、総司と肩を並べても遜色はなく、堂々と共に歩めると思ってのことだ。 そんな歳三の邪な気持ちを、総司は知らない。 「総司。これを遣る」 そう言って、歳三が徐に懐から取り出したものは、綺麗に折り畳まれた和紙だった。 総司が、中に何か書かれた風なその紙を、その男にしては綺麗な歳三の手から受け取り、開いてみると、 『さしむかふ 心は清き 水かゝみ』 そこには書いた人を表すかのような繊細な筆遣いで、句がひとつ、認められていた。 「歳さん、これ?」 「今度の件で、詠んだ句だ」 上洛に際し、歳三が詠んだ句だという。決意の句であろうか。 「だが、お前を想って、詠んだ句でもある」 「おれ、を?」 思いがけない言葉に、総司の声が上擦った。 「ああ。さっきもお前が言っただろう? 俺の道を、共に行くと」 「はい」 「それを初めて聞いたとき、俺はお前にだけは、恥じぬ生き方をしたいと思った」 斬る斬られるということを、自分の身に起こる覚悟はしても、総司の身に覚悟を出来ていなかった歳三だったのだが、先程の総司の言葉に覚悟を決めた。 「お前が要れば、俺は何事があろうとも、きっと強く歩いていける」 何処までも総司を放さず、連れて行くと。 「だから……」 覚悟を決めた歳三は、すうっと、ひとつ息を吸った。 「だから、総司。俺の傍にいてくれ。俺が道を踏み外さぬように、道に迷わぬように、ずっと一緒にいてくれ」 「…………」 返答をせぬ総司に、歳三は恐る恐るといった風情で、俯いていた顔を上げてみた。 「総司……」 歳三の眼に入った総司の顔は、喜びと、戸惑いとが、綯い交ぜになったような表情で。 「歳さん、嬉しい」 そんな言葉を、ずっと待っていたのだと、総司は歳三を抱き締めた。 その総司の温もりが、暖かく歳三の躯も心も、すっぽりと包み込むようで、歳三を安堵させ、総司の広い背中に腕を回させた。 「歳さん」 総司低い囁きが聞こえ、口付けが降ってくるのを、うっとりと歳三は受け止めた。
それから、雪が小止みになり薄日が差してきた中を、二人日野まで黙々と歩いた。だが、この沈黙は暖かいものを含み、時折触れる手がそれを物語っていた。 やがて、稲荷の森が見えてきたところで、二人は右と左に別れたのだ。名残惜しげに眼を見交わしながら。 そして、総司は姉のみつに別れの挨拶を済ませ、心尽くしの食事をし、旅立ちの餞別を受け取って、歳三の待つ佐藤家の門を潜った。 みつの狭く、子供たちのいる家では、ゆっくりと寝むこともできないし、天然理心流の強力な後援者である佐藤彦五郎にも、挨拶をせねばならぬからと、断って。 案の定、歳三が上手く言ってくれてあったのだろう、総司が彦五郎に挨拶を終えると、ささやかな酒宴の場が設けられた。佐藤家の者だけでなく、天然理心流を学ぶ近在の者たちの顔も見える。 それらの皆に、総司は塾頭として、今まで世話になった礼と感謝を伝え、帰ってくるまでの不在を詫び、酌をして廻った。 夜もすっかりと更けた頃、ようやく場もお開きとなり、三々五々帰る人たちを見送って、総司と歳三は部屋へと引っ込んだ。 この部屋は、歳三が佐藤家に入り浸っていた頃の歳三の部屋で。綺麗に片付けられていたが、総司や歳三が佐藤家に泊まる際は、必ずここに泊まっていた。
いったい幾夜を、二人してこの部屋で過ごしたことだろう。 そうして、二人っきりになれば、おのずと行う行為は一つで。 今度こうやって、この部屋で過ごすのは、いつになることだろうか。 そう思いながらも、今夜も、誰憚ることなく睦みあい、満足して躯を離して。 総司は昼間に貰った歳三の句を取り出し、眺めていたというわけだった。 満面の笑顔の総司に、歳三は面映くなる。 「歳さんからの文なんて、初めてでしょう?」 総司は顎を手で支え、見せびらかすようにもう片手で持った紙を、歳三にひらひらと見せた。 「そりゃ、一緒にいれば、わざわざ文なんざ、書かないだろうが」 「それはそうですけど。でも、歳さんが試衛館に来る前だって、一度もなかったじゃないですか」 むくれたように、総司はそう言ったが、総司とて歳三に文を書いたことなど、ないのだ。お互い様と言うものではないだろうか。 そう反論しかけた歳三だったが、 「まるで、戀文みたいだ」 うっとりと夢見心地で、総司に言われて、 「ばっ……」 歳三の顔が、真っ赤になった。 「大事にします、これ。宝物ですよ」 心底、大事そうに扱う総司を見て、歳三の内に嫉妬の情が湧き上がる。 「どっちが、大事だ?」 そして、つい歳三は、拗ねるように呟いた。 「え? どっち?」 きょとんとした顔で、総司が見返した。 自分で遣った文に嫉妬していては、なんとも言えないが、その幼い風情の表情を見ながら、歳三は総司の口唇を啄ばみ、もう一度問う。 「どっち、だ?」 艶やかな笑みを浮かべて、問い掛ける歳三に、総司はくらくらと眩暈がしそうだ。 けれど、歳三の問いの意味に気づいた総司は、 「そんなの、決まってるじゃないですか」 「決まってる?」 望む答えを引き出そうとする、その麗しい丹華に、 「そう」 丹念に指を這わし差し入れて、しゃぶらせた。 「歳さんに、決まってる」 総司の指をしゃぶりながら、聞きたかった答えを引き出し、満足そうに歳三は微笑んだ。 その笑顔に溜まらず、総司は指を抜き、代わりに舌を差し入れ、千切れるほどに深く吸いあって。 歳三の唾液が絡んだ指は、その間にそっと下に降りてゆき、下肢の狭間に滑らせた。 「ちょっ、総司。よせっ」 満足して弛緩している躯を捩って、歳三は抵抗するが、 「イヤ、です。もう、止まらない」 一度融けた歳三の体は、力が入らず、総司の指の侵入を易々と許した。 「あっ……」 後には、歳三の声が甘く響くばかり。 |
||||
| やっぱり、最初はこの句から。そう思って書き上げました。今のところ、投票でも第一位だし。 でも、思い入れが一番ある分、難しいですね。 |