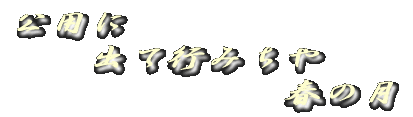 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 黒谷へと呼び出された歳三は、総司を伴って出掛けた。 黒谷などに新撰組の用で副長として出掛けるときは、必ず一人は供をつけるようにしている。 新撰組と知って、襲ってくる輩からの護衛のためである。 気心が知れていたし、一人だけの供のときは、総司や井上、斎藤などを供に連れて行くことが多かった。 特に総司は、歳三にとっても、もっとも気楽な相手だ。 だからついつい、総司に声を掛ける機会が多かった。 それに、総司は歳三と情を交わした相手であるから、その道行きは公のものではあっても、逢引に似たものになり、自然心が浮き立つのだ。 副長と一番隊隊長という間柄である、人目もあるからそうそう二人でいちゃつくことも出来ぬ、と歳三は思っていた。 だから、これぐらいは特権だろうと、副長としての権限を大いに利用している。 もっとも、二人の関係は試衛館の頃からの人間には、ばればれであったし、勘の良い人間などは気付きつつある。 それは、普段の歳三の総司に対する接し方を見ていれば、よくわかるのだ。
総司は歳三の半歩後ろを、歩いてゆく。 京へ来てからの総司の癖のようなものだ。 新撰組というだけで、売名行為の浪士たちに命を狙われる。 ましてや歳三は、副長であるという地位から、それほど顔を知られていないにも拘らず、血気に逸った輩に狙われることも度々で。 後ろからの敵に対処するために、横並びに歩くのではなく、斜め後ろを歩くようになったのだ。 もっとも、それはこういう公用の時のことであり、私用で一緒に出歩くときは、必ず並んで歩くようにしている。 総司が後ろを歩くことを、言葉には出さないが、歳三が淋しく思っていることを分かっての、総司の行動であった。 歳三が供を伴って出掛けるときは、巡察などの用が入っていない限りは、総司が付いて行く。 ただし、花街での宴会を含んでいるときは、大抵その供は井上のことが多かったが。 これは、妓といるところを、総司に見せまいという、歳三なりの気遣いらしかった。 けれど総司は、そこまでしなくても良いと思っていた。 歳三が、花街に行くのは公用であり、仕方がないと思っている。 それぐらいの分別は、つくようになっているつもりであった。
二人、夕闇の迫った道を特に急ぐでもなく、歩いてゆく。 黒谷へと呼び出されたものの、それほど急用という訳でもない用件に、少しでも共にある時間を長くしようと、二人の歩みは遅かった。 無言ではあったが、その沈黙は心地よいもので、何も語らずとも互いのことを想っているのが判り、それが居心地の良い空間を作っていた。 その後ろから、朧の月が二人の後を、追いかけて行った。 |
||||