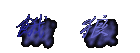 |
||||
| 歳三は時折り山を降り、人里へと出て行くことがある。 それは、一日の半分を人の姿で過ごすために、どうしても必要なことだった。 狼の姿ならば衣服なども要らずにすむが、人の姿では無理というもの。 手先が器用で何でもそつなくこなしてしまうとはいえ、布などの材料なくして衣服は作れず、それらを賄うために人里へと降りるのだ。 総司と暮らすようになって、歳三は総司を着飾りたいと思うようになっていた。 ごてごてと装飾をするのではなく、上等の着心地の良い物を与えたいと。 それらを手に入れるためには物々交換と言う手段もあるが、より良い品を得るためにはそれよりも金だ。 その金を得るために、歳三は己が狼の姿のときに狩った獲物を持っていく。 先日は総司の狩った獲物も持って行き、評判は上々だ。 山にいる時は、総司の行動を束縛したりは一切しない歳三だったが、己が里へ降りるときは一人残していく総司に気が気ではない。 「里へ降りるが、お前も一緒に行かないか?」 だから、里へ降りるときに再三総司を誘っていたのだが、総司はいっかな首を縦に振らない。 「え? ううん、私はいいよ。ここで留守番しているから――」 怖いのだ、総司は。 昼間に人の姿になることのない総司にとっては、空の上から垣間見ることはあっても、人と接したことは殆んどなく、その只中に行くことは怖かった。 歳三もそれを承知していたから無理強いはしなかったが、誘うことだけは止めなかった。 「総司。今日も駄目か?」 本当ならば、総司を目の届かぬところにおいておきたくないのだ。 「うん。行ってみても、いいよ」 そして、今日やっと総司も一緒に降りることを承知した。 人との交わりを殆んど知らぬ総司には勇気がいることだったが、少しでも一緒にいたいと思うのは歳三と同じ事。 最大限の勇気を振り絞ってみたのだ。 総司が肩に乗っても大丈夫なように、襟から肩部分に自分が狩った獲物の毛皮を縫いつけた衣服を着て、歳三は人里に出た。 手には売り物の兎や雉をぶら下げている。 この時期にこれだけの獲物を捕らえるなど、その腕の良さが分かろうと言うもの。 そんな羨むような妬ましいような猟師の男どもの視線を受け流しつつ、その肩には無造作に鷹を肩に止まらせ歳三は歩いていく。 その鷹の足には、何かの牙だろうか。 金泥を施した二つの牙が、鈴の代わりに取り付けられていた。 それが、揺れるたびにカチカチと音を奏でていた。 肩にある総司のその雄雄しくも優美な姿を手にしている歳三に対して、羨望の眼差しを向けられているのが歳三には快感だった。 その鷹のものと思しい尾羽を束ねた飾りを首に掛けた逞しくも見目麗しい歳三が、女たちの目に留まらぬはずはない。 獲物を沢山持っているのも、それを煽る材料だ。 女を養える力があるということに他ならないから。 |
||||
 |
||||
歳三が獲物を全て金に変え、帰途に着こうと言う頃。 秋波を送り続けていた女の中でもとびきりのが、歳三に声を掛けてきた。 「ねぇ、兄さん。ちょっと私と遊ばないかい?」 蓮っ葉な女の物言いだが、歳三の色男ぶりに本気になってもいいという色が見え隠れする。 そういうのは鬱陶しいが、上手いあしらい方も心得ている歳三だから、そういう誘いにその気にもなろうというもの。 歳三とて男である。それこそ精力の旺盛な、ある意味健全な男である。 女に言い寄られて悪い気はしなかった。 ましてや、それがとびきりの女ならば尚のこと。 たとえ、最愛の想い人がいようともだ。 特に何と言葉を交わす訳でもなく、しかし歳三と女の絡み合った視線には、意味深な意味が明らかに込められていて、それは総司にも伝わった。 敏感に察した総司は、二人を見ていることに耐えられず、ばさっと翼を広げて歳三の肩から飛び立った。 その急な動きに驚いた歳三だったが、飛び去っていく総司に一声も掛けずに苦笑った。 そして、そのまま目の前の女の肩を引き寄せるようにして、女の指し示す小屋へと入って行った。 総司がその歳三を悲しく見咎めていたのを知りもせず。 歳三が夕暮れ前に家へと戻ってきても、総司の姿はまだなかった。 しかし、もうじき日が暮れる。 鷹の時はともかく、人の姿では山は危険だから、総司の間もなく帰ってくるだろうと、気楽に考えながら歳三は里で買ってきた酒を一人飲み始めた。 しかし、待てど暮らせど総司は帰ってこない。 辺りは既に闇に包まれていて、歳三の姿は人から狼に変わっているし、当然のことながら太陽の落ちた今、総司の姿も鷹から人に変わっているはずだ。 ふと、今日最後に見た総司の姿を思い起こして、このまま帰ってこないのではとの思いに囚われた歳三は、身を起こして狼に変じたその姿を闇の中へと躍らせた。 |
||||