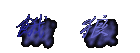 |
||||
| 歳三の下で脱力したままの躯を、総司はもぞっと動かした。 その拍子に、総司の鷹の時には足に、今は首に肌身離さずある歳三の牙で作られた飾りが、かちりと音を立て歳三の行ったことを非難するかのようだ。 歳三が月明かりを頼りに透かし見ると、疲労の色が濃いように見える。 それもその筈だと、冷静になった歳三は頭の片隅で思った。 と同時に、総司に対して申し訳ないという気が沸き起こってきた。 誇り高い歳三には謝るという芸当がなかなかできない。 それでも今度のことは、歳三に非があることは明らかで、 『すまなかった』 それだけを、ようよう言った。 総司は頭を廻らして、項垂れ気味の歳三を見遣った。 いつも昂然と頭を上げ、前を見ている歳三らしからぬ姿だ。 「なんで、こんなことをしたの?」 総司には歳三の行動の理由がさっぱり掴めていなかった。 鈍いばかりの総司に、呆れたほうがいいのやら笑ったほうがいいのやら判らずに、内心苦笑するに留めていた歳三だったが、黙っていては話にならぬと、総司に自分の心情を聞かせた。 歳三は総司より年長であり、また昼に人の姿になることも多いため、人との交わりを格段に知っていた。 もちろんこれには、女との躯の交わりも含まれている。 歳三は男盛りの若い男だ。 しかも、森の王とも言われる狼でもある。それ故、肉欲は強い。 周りに同族がいれば、それで発散もされるだろうが、生憎いないとなれば人間の女で間に合わせるしかない。 が、総司の躯を知ってからは、到底それでは収まらなくなっていた。 物足りないのだ。 もちろん女の中を穿ち、果てることはできる。 だが、充足感がない。 総司との時のように高揚感が全くないのだ。 ただ、己の欲望を吐き出しただけと言う感覚だけだ。 だが、総司と心行くまで交われるのはひと月に数日だけ。 昼に月が昇った時だけだ。 その時だけは、二人共に夜同じ人の姿になれるから。 しかし、それだけでは歳三の強い性欲が抑えられるはずもなく。 その想い人が今は鷹の姿で、二人が共に人の姿でいられる時間が短いとくれば、歳三が欲求をよそで満たそうと思うのも無理からぬことではある。 歳三の有り余る精力を満たすには、その時間は余りにも短すぎた。 そう、総司の想いを踏みにじることではあっても。 だから、昼間のようなことをしたといい、最後にこんな風にはもう抱かぬと言えば、 「歳さんが、女の匂いをつけている方が、ずっと嫌だ」 と総司は縋り付いて来た。 「それに、歳さんはどんな姿をしていても歳さんでしょう? 別に狼の姿であっても嫌じゃないよ。それとも歳さんは鷹の私は嫌い?」 『そんなことはない! どんな姿でもお前はお前だ。あの大空を優雅に舞う姿も綺麗だ』 「私も歳さんのあの天鵞絨のような毛並みや、力強く大地を走るしなやかな姿が好きだよ」 含羞んだような笑みを、総司は歳三に向ける。 「だから、狼の姿でも気にならない。さっきはびっくりしただけ……」 人の姿で狼の歳三と交わるのに、総司には嫌悪も禁忌もないようだった。 人でないのだから、当たり前かもしれないが。 『本当に良いのか?』 それでも歳三が確認するように聞くと、 「うん。いいよ。まだ、する?」 と、するりと肩から羽織っていたものを総司は滑り落とした。 煌々と月に照らされた総司の躯は、先ほどまでの情交の名残を色濃くとどめていて、歳三の理性を引きちぎることは容易かった。 歳三は鼻先を近づけ鼻を押し当てると、その冷たい感触にぴくんと総司の体が震えた。 それに嬉しさの笑いを噛み殺し、総司自身が胸から腹にかけて飛ばした蜜を、歳三はざらついた舌で丹念に舐め取っていく。 特に乳首には執拗に絡まり、総司を息も絶え絶えに喘がせる。 「あっ、ん……」 歳三の頭に掛かった総司の手は、歳三を押しのけようとしているのか、抱えようとしているのか総司自身にもわからないに違いない。 総司の間に割り込ませて、片方の前足で総司の片足を押さえ、 『足をもっと開け』 と、総司に命じるように言えば、総司は唯々諾々として自分の足を手で掬い上げ開いた。 開かれた総司の下肢の間では、総司のものがふるふると再び勃ちあがってきている。 その総司のものを、咥えれば牙で傷つけそうで、歳三はぺちゃぺちゃと舐めしゃぶっていく。 「……あぁ、んっ」 やがて歳三の舌の上に、総司の淡い蜜の味が広がってく。 『総司』 名を呼べば、総司は快感に煙る瞳を歳三に向けて、無言で問い掛ける。 『尻を開け』 歳三の狼の手では、尻を広げることはできず、総司にさせるしかない。 その意図を察した総司は、自分の両手で尻を広げて、菊口を歳三の目の前に晒した。 歳三の長い舌が、己が総司の中で放った精を啜るように差し込まれた。 |
||||
 |
||||
総司のものとは違って濃く苦い味がするが、それでも総司の中に留まっていたものだと思えば、甘露となるから不思議なものだ。 歳三の舌が総司の中を気侭に蹂躙する間、総司は身悶えながらも両手は押し広げたままで。 「いや。歳さん、いやっ」 首を打ち振るたびに豊かな黒髪が左右に広がる。 『嫌? どこが嫌だ? ここは嬉々としてるぞ?』 歳三の舌を受け入れ収縮する襞に、意地悪く歳三が聞き返せば、 「果て、ちゃう。だから……いやっ! 一緒でないと、いや」 息も絶え絶えに喘ぎながら、総司は訴えた。 確かに総司のものからは蜜が滴るように溢れ伝い、歳三が舐めている菊口へと流れてきて、歳三の精と交じり合っている。 一緒に果てたいと強請る総司が可愛く、歳三に否やはない。 歳三が身を一旦離すと、総司は自分から四つん這いになり、歳三が挿入しやすいように尻を高くあげ、再び菊口を押し広げた。 その背に歳三が前足を掛け圧し掛かって、先ほど犯したときとは比べ物にならぬ優しさで、押し開き埋め込んでいった。 先の情交と歳三の舌によって解れきった総司の菊口は緩み、中の襞は歳三を柔らかく包み奥へと誘っていく。 耳朶近くの汗で塩辛い首筋をぺろりと舐めると、びくりと総司の躯が震え締め付ける。 その動きに歳三も果てそうになった。 『総司』 優しい声音で歳三に呼ばれ、総司が首を廻らすと、歳三の舌が薄く開いた総司の口に差し込まれた。 「んんっ! ん、ぁっ――」 舌っ足らずな鼻に抜けた喘ぎが、総司の花のように色付いた唇から零れ落ちた。 月が沈み、太陽が昇るまで、この二度目の宴は艶やかな吐息を振りまきながら繰り広げられた。 |
||||
| ど、どの部分の話が挿絵になるのか、期待と不安が入り混じっていたんですが絵を拝見して、「どっか〜〜ん!」と吹っ飛びました。 いや〜ん、すっごいエロ!じゃないですか〜。 いや、まぁ。そういう話を書いたのは私なんですけど……。でも、それにしても、と。 皆様も、息遣い荒くご堪能くださいませ。 |
||||