■涼宮ハルヒのえっちな憂鬱■ |
||
|
教室で下敷きをうちわ代わりにしてつかっていたら、珍しく始業の鐘ぎりぎりにハルヒが入ってきた。 不機嫌そうに机につくと、どすりと鞄を投げ出し、 「キョン、あたしにもあおいでよ」 「自分でやれ」 ハルヒは二日前に駅前で別れたときとまったく変化のない仏頂面で唇をアヒルのように突き出していた。最近マシな顔になってきたと思っていたのに、また元に戻っちまった。もったいない。 「あのなぁ、涼宮。お前、『しあわせの青い鳥』って話、知ってるか?」 「それが何?」 「いや、まぁ、なんでもないんだけどな」 「じゃあ訊いてくんな」 ハルヒは斜め上を睨み、俺は前を向き、担任がやってきてホームルームがはじまった。 この日の授業中、不機嫌オーラを四方八方に放射するハルヒのダウナーな気配がずっと俺の背中にプレッシャーを与えていて、いや、今日ほど終業のチャイムが福音に聞こえた日はなかった。チャイムと同時に、俺は脱兎のごときスピードで部室へと退避した。 部室に入ると、パイプ椅子に座って長門が読書していた。 もはや部室で長門が読書する姿は今やデフォルトの風景であり、もはやこの部屋と切り離せない固定の置物のようでもあった。 だから俺は、長門には一瞥をくれただけで、一足先に部室に来ていた古泉一樹にこのようにいった。 「お前も俺に、涼宮のことで何か話があるんじゃないのか?」 今、この場には俺と古泉、そして長門の三人しかいない。ハルヒは今週が掃除当番だし、二年の朝比奈さんは終わりが遅く、まだ来ていないからだ。 「おや、お前も、というからには、すでに他のお二方からはなんらかのアプローチを受けているようですね」 古泉は昨日図書館から借り出した本に顔をうずめている長門を一瞥する。こいつのまるで全てを知っているかのような、訳知り口調が気に入らない。 「場所を変えましょう。涼宮さんに出くわすとマズイですから」 その意見には賛成だ。 古泉が俺を伴って訪れた先は食堂の屋外デーブルだった。途中で自販機のコーヒーを買って俺に手渡し、丸いテーブルに二人で座った。 「それで、あなたはいったいどこまでご存知なのですか?」 「涼宮が只者じゃないってことくらいか」 「それなら話は簡単です・・・その通りなのでね」  これは何かの冗談なのか?SOS団に揃った三人が三人とも、涼宮が人間じゃないみたいなことを言い出すとは。地球温暖化のせいで、熱気にあてられているんじゃないのか。 「まずはお前の正体から聞こうか」 スカトロ好きの宇宙人と、放尿好きの未来人には心当たりがあるから、 「まさか、実はアナルセックス好きの超能力者、などというんじゃないだろうな」 「先に言わないで欲しいなあ」 古泉は微笑むと、手にした紙コップをゆるゆると振った。 「そうです。実は僕はアナルセックス好きの超能力者なんですよ」 俺は黙ってコーヒーを飲んだ。減糖のコーヒーにするべきだった。甘ったるくて飲めたもんじゃない。 「本当はこんな急に転校してくるつもりはなかったんですが、状況が変わりましてね。よもや長門さんと朝比奈さんの二人が、こうも簡単に涼宮ハルヒと結託するとは想定の範囲外でした・・・それまでは外部から観察しているだけだったんですけどね」 ハルヒを珍しい昆虫か何かみたいにいうな。 なぜかいらついた俺の気配を感じ取ったのか、 「どうか気を悪くしないでください。我々も必死なんですよ。涼宮さんに被害を加えたりする気はさらさらありませんし、なにより、むしろ我々は彼女を危機から守ろうとしているのですから」 「我々、ってことは、お前のほかにもいっぱいいすのか?そのアナルセックス好きの超能力者ってやつは」 「みんながみんな、アナルセックス好きというわけではありませんがね・・・アナルセックスは、あくまで超能力発揮のための一手段に過ぎませんから・・・まぁ、嫌いではありませんが」 そういうと、古泉はいつもの笑顔になる。 「僕は末端なので正確には知りませんが、それでも地球全土で十人くらいでしょう。その全員が『機関』に所属しているはずです」 「機関?」 「実体は不明です。構成員が何人いるのかも。トップにいる人たちが全てを統括しているはずですが」 「それで、その機関とやらは何をする団体なんだ?」 「あなたの想像通りですよ」 古泉はぬるくなったコーヒーで唇を湿らせ、 「機関は三年前の発足以来、涼宮ハルヒの監視を最重要事項にして存在しています。きっぱり言い切ってしまえば、涼宮さんを監視するためだけに発生した組織です。ここまでいえばもうお分かりでしょうが、この学校にいる機関の手のものは僕だけではありません。すでに何人ものエージェントが潜入済みです。それで僕は追加要員としてここに来たわけです」 どうしてみんなそんなにハルヒが好きなんだ?エキセントリックで居丈高で、周囲の迷惑を顧みない自己中心女のどこにそんな大げさな組織から狙われるような要因があるというんだ? ふと、俺は教室のかたすみで、窓の外を眺めているハルヒの横顔を思い浮かべた。 ・・・まぁ、なんだ。見てくれがいいのは認めるがな。 「今から三年前に何があったのかは解りません。僕にわかるのは、三年前のあの日、突然僕の身に超能力が芽生えたということだけです。さすがに最初はパニックに陥りましたが、すぐに機関から迎えがきて救われました・・・もしもあのままだったら、僕はてっきり自分の頭がおかしくなったと思って自殺していたかもしれませんね」 「その時から今まで、ずっとお前の頭はおかしくなり続けなんじゃないか?」 「ええ。その可能性もなくはありませんね」 古泉は笑った。 「しかし我々は、もっと畏怖すべき可能性を危惧しているのですよ」 自嘲的な笑みと一緒にコーヒーを飲み込んだ古泉は、ふいに真顔になった。 「あなたは、世界がいつから存在していると思いますか?」 「さぁな。遥か昔に、ビックバンとかいう爆発が起きてからじゃないのか」 「たしかにそういうことになっていますね・・・ですが我々は、一つの可能性として、世界が三年前から始まったという仮説を持っているのですよ」 「はぁ?」 俺は古泉の顔を見返した。なにを言い出すんだ、こいつは?正気の沙汰とも思えん。 「そんなわけないだろ。俺は三年前より以前の記憶だってちゃんとあるし、親だって健在だ。ガキの頃に近所のガキ大将とキン消しの取り合いで負った三針縫った傷跡だってちゃんと残ってる。世界が三年前に始まったのなら、今日本史で必死こいて覚えている歴史はどうなるんだよ?」 「もし、あなたを含めた全人類が、それまでの記憶をもったまま、ある日突然世界に生まれてきたのではないということを、どうやって否定するのですか?三年前にこだわることもない。いまからたった五分前に全宇宙があるべき姿をあらかじめ用意されて世界が生まれ、そしてすべてがそこから始まったのではないと否定できる論拠などこの世のどこにもありません」 「・・・それはそれでいいことにしておこう。世界が三年前か五分前に始まったってのもまぁいい。しかしだな。そこからなにをどうひねったらハルヒの名前が出てくるんだ?」 「機関のお偉方は、この世界をある存在が見ている夢のようなものだと考えています。なにぶん夢ですから、その存在にとって我々が現実とよぶ世界を創造したり、改変したりすることなど児戯に等しいはずです。そして我々は、そんなことの出来る存在の名を知っています」 丁寧語で落ち着いたしゃべりのせいか、古泉の顔つきは腹立たしいほど大人びて見えた。 「世界を自らの意思で創ったり壊したりできる存在・・・それは、神です」 ・・・おい、ハルヒ。お前、ついに神様にされちまったぞ。 俺は体育の授業中、ぶっちぎりでゴールインしながらにこりとも笑わないハルヒの姿を思い浮かべた。変なところは多分にあるが、ハルヒは普通の人間、のはずだ。それが、神ねぇ。 「ですから、機関の者は戦々恐々としているのですよ。もしもこの世界が神の不興を買ってしまったら、神はあっさりと世界を破滅させてしまうかもしれません。まるで砂場につくった山の形が気に入らなかったから壊してしまう子供のようにね」 そして、古泉はまたいつもの笑顔を浮かべた。 「僕はこの世界にそれなりの愛着を抱いています。ですので、世界を守ろうとしている機関に協力しているわけです」 「なら、ハルヒに直接頼んでみたらどうなんだ?世界を壊すのはやめてくださいってな」 「たしかに、機関の中にもそのように主張している者もいます。けれど大部分の意見は、下手に神を刺激して予測不可能の事態に陥るよりも、現状を維持していくほうがリスクが少ないと思っているんですよ。彼女は神の力をもってはいますが、自分がその力を持っているとは気づいていません。できることなら、我々は彼女は生涯自分が持っている力に気づかないまま、平穏無事な人生をおくってもらいたいと思っているのです」 「はぁ」 「いうならば、彼女は未完成の神なのです。自在に世界を操るまでにはなっていない・・・ところが最近、彼女は未発達ながら、その力の片鱗をみせるようになってきてたのです」 「どういうことだ?」 「あなたはなぜ我々みたいなアナルセックス好きの超能力者や、あるいや朝比奈みくるや長門有希のような存在がこの世にいると思うんですか?偶然だと思いますか?そんな偶然があるはずがない。全ては、涼宮さんがそう願ったから、実現したのですよ」 スカトロ、放尿、アナルセックス、獣姦マニアがいたら、あたしのところに来なさい。 最初に出会った教室の自己紹介でハルヒがのべたセリフが蘇る。 「アナルセックス好きの超能力者とかいったな?」 「ええ」 「だったら、何か超能力を見せてくれよ。そうしたらお前のいうことを信用してやってもいい」 古泉は楽しそうに笑った。含み笑い以外の笑みを見るのはこれが最初かもしれない。 「すみません。無理です。普段の僕にはなんの力もないんです。超能力を使えるのは、とある限定された条件の下でだけなんです。いつかまた、あなたにお見せする機会もあるでしょう」 長々と話したりしてすみませんでしたといって、古泉はにこやかに笑った。そしてテーブルから離れ際に、 「実は一番不思議なのは、あなたたんですよ」 といった。「なにがだ?」と尋ねたところ、 「失礼ですが、あなたのことは調べさせていただきました。あなたが一番の謎なんです。あなたは僕や朝比奈さん、長門さんのように特別な存在ではありません。保証してもいい、あなたはごく普通の、特別の力をもたない一般人です」 言われなくても自覚しているよ。それがほっとしていいことなのか、悲しむべきことなのかは解らないがな。 「しかし、涼宮さんから一番最初に選ばれたのは、あなただ。あなたが涼宮さんの前に現れてから、彼女はあきらかに変化しつつあります。ひょっとしたら、あなたが世界の命運を握っているということも考えられます。これは我々からのお願いです。どうか涼宮さんがこの世界に絶望してしまわないように注意してあげてください」 俺の知ったこっちゃない、と答えると、「あなたらしいですね」と笑って、古泉は去っていった。 俺は古泉の背中が見えなくなるまで見送り、もう冷たくなったコーヒーを一口すすった。 「ハルヒが、神様ねぇ・・・」 俺にとっては、変ではあるが、普通の女にしか思えん。黙っていれば可愛いんだがな、黙ることはないからな。もったいない。 古泉がかえってしばらくして、俺は大きな背伸びをした。 実は俺は、古泉と話しながら、一つの懸案事項を抱えていたのだ。その懸案は朝、俺の下駄箱に入っていたノートの切れ端。 そこには、 『放課後、誰もいなくなったら、一年五組の教室に来て』 と、明らかな女の字で書いてあったのだ。 誰かのいたずらななのかもしれない。たとえば、あの谷口とかだったらやりかねない。いかにもアホの谷口がやりそうな頭の悪いギャグの匂いがプンプンする。 しかし、いたずらでなかったら? たとえば長門。 長門には前科があるからな。しかしこの紙切れの字は長門の字とは明らかに違う。あの自称宇宙人モドキのスカトロ好きの字は、機械のように綺麗だった。 では朝比奈さんは? 違うだろう。朝比奈さんだったら、こんな紙切れなんかでなく、ちゃんとした封筒と便箋で書いてくれるであろう。 ハルヒは? ありえん。あいつならこんなまどろっこしいことはせず、いつかのように強引に俺の首根っこを掴んで引っ張って話をつけるだろう。 古泉は? 却下。さっきまで話していたじゃないか。 というわけで脳内会議でも結論が出ず、結局、とりあえず行ってみることにした。誰かいるならそれでいいし、いなければいないで、帰ればいいだけだからな。 この時、ひそかに始まっていたのだが、神ならぬ俺は、その事実を知らなかった。ほとんど誰も知らないうちに始まって、また終わった事件。 俺の人生観をも、一変させてしまうような事件。 今から考えれば、この事件から、俺は戻れない道に足を踏み入れてしまったのかもしれない。 事件は、女の姿をしていた。 誰がそこにいようと驚くことはなかったろうが、実際そこにいた人物を目にして俺はかなり意表をつかれた。まるで予想だにしなかった奴が黒板の前に立っていたからだ。 「遅いよ」 朝倉涼子が俺に笑いかけていた。 清潔そうなまっすぐの髪を揺らして、朝倉は教壇から降りた。プリーツスカートから伸びた細い足と白いソックスがやけに目につく。 教室の中ほどに進んで歩みを止め、朝倉は笑顔をそのままに誘うように手を振った。 「入ったら?」 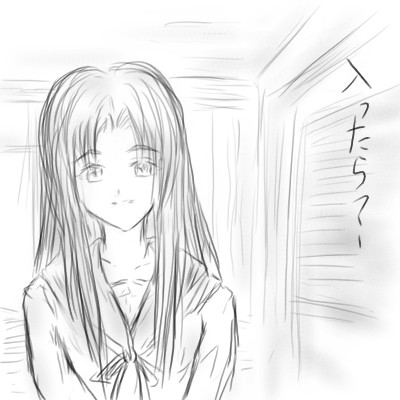 引き戸に手をかけた上代で止まっていた俺は、その動きに誘われるように朝倉に近づく。いったいぜんたい、どうしてクラス委員長の朝倉が、俺を呼び出すんだ? 「意外でしょ」 朝倉はくったくなく笑った。その右半身が夕日に紅く染まっている。 「何のようだ?」 わざと、ぶっきらぼうに訊いてみる。他の誰かならともかく、クラス委員長に呼び出しを受ける覚えはない。朝倉は笑った。 「用があることは確かなんだけどね。ちょっと訊きたいことがあるの」 俺の真正面に、朝倉の真っ白な顔があった。 「人間はさぁ、よく『やらなくて後悔するよりも、やって後悔したほうがいい』って言うよね。これ、どう思う?」 「よくかどうかは知らないが、言葉どおりの意味だろうよ」 「じゃぁさぁ、たとえ話なんだけど、現状を維持するままではジリ貧になることは解ってるんだけど、どうすれば良い方向に向かうことが出来るのか解らないとき。あなたならどうする?」 「なんだそりゃ?日本経済の話か?」 俺の質問返しを朝倉は変わらない笑顔で無視した。 「とりあえず何でもいいから変えてみようと思うんじゃない?どうせ今のままでは何も変わらないんだし」 「まぁ、そういうこともあるかもしれん」 「でしょう?」 手を後ろに組んで、朝倉は体をわずかに傾けた。 「でもね。上の方にいる人は頭が固くて、急な変化にはついていけないの。でも現場はそうもしてられない。手をつかねていたらどんどん良くないことになりそうだから。だったら現場の独断で、強行に変革を進めちゃってもいいわよね?」 何を言おうとしているんだ? 「何も変化しない観察対象に、あたしはもう飽き飽きしてるのね。だから・・・」 キョロキョロするのに気をとられて、俺はあやうく朝倉の言うことを聞き漏らすところだった。 「あなたを殺して、涼宮ハルヒの出方を見る」 ほうけているヒマはなかった。後ろ手に隠されていた朝倉の右手が一閃。さっきまで俺の首のあった空間をにぶい金属光が薙いだ。 猫を膝に抱いて背中を撫でているような笑顔で、朝倉は右手のナイフを振りかざした。軍隊に採用されてそうな恐ろしいナイフだ。 俺が最初の一撃をかわせたのはほとんど僥倖だ。その証拠に俺は無様にしりもちをついて、しかもアホ面で朝倉の姿を見上げている。マウントポジションを取られたら逃げようがない。慌ててバッタみたいに飛びずさる。 なぜか、朝倉は追って来ない。 ・・・いや待て。この状況はなんだ?なんで俺が朝倉にナイフを突きつけられねばならんのだ。待て待て。朝倉はなんといった?俺を殺す?ホワイ?なぜ? 「冗談はやめろ」 人間、こういう追い詰められたときは常套句しかいえないのだと、俺は思った。 「マジ危ないって!それが本物じゃなかったとしてもビビるって!だから、よせ!」 「冗談だと思う?」 思いたい。しかし、どうやら違うようだ。 朝倉はあくまで晴れやかに問いかけてくる。それを見ていると、まるで本気だとはみえない。笑顔でナイフを向けてくる女子高生がいたら、それはとても怖いと思わないか?答えはイエスだ。俺は今、めちゃくちゃ怖い。 「ふーん」 朝倉はナイフの背で肩をたたいた。 「死ぬのっていや?殺されたくない?わたしには有機生命体の死の概念がよく理解できないけど」 俺はそろそろと立ち上がる。この状況は冗談、シャレだよな。本気だったらシャレじゃすまされんが。だいたい信じられるわけがないだろ。別に泥沼化したあげくこっぴどく振った女でもなく、クラスでもロクに喋りゃしない真面目で美人の委員長に刃物で切りつけられるなんて、本気の出来事だと思えるわけがない。 だが、もしあのナイフが本物だったなら・・・とっさに避けなければ、俺は今頃血だまりのなかに死んでいたことは間違いないだろう。 「意味が解らないし、笑えない。朝倉、いいからその危ないのをどこかに置いてくれ」 「うん、それ無理」 無邪気そのもので、朝倉は教室で女子同士かたまっているときと同じ顔で微笑んだ。 「だって、あたしは本当にあなたに死んで欲しいのだもの」 そう言うと、ナイフを腰だめに構えた姿勢で突っ込んできた。 早い。 が、今度は俺にも多少の余裕はあった。朝倉が動き始める前に脱兎のごとく走り出し、教室から逃げ出すことにする。 ・・・逃げ出すはずであった。 「なんでだ?」 俺は勢いよく、壁に激突した。 ??? ドアがなくなっている。 窓も、なにもない。 廊下側に面した教室の壁は、まったくの塗り壁さながらにネズミ色一色で染められていた。 ありえない。 「無駄なの」 背後から近づいてくる声。 「この空間は、あたしの情報制御下にある。脱出路は封鎖した。簡単なこと。この惑星の建造物なんて、ちょっと分子の結合情報をいじってやればすぐに改変できる。今、この教室は密室。出ることも入ることもできない」 振り返る。夕日すら消えている。校庭側の窓も全てコンクリートの壁におきかわっていた。知らないうちに店頭していた蛍光灯が、寒々しく並んだ机の表面を照らしている。 嘘だろ。 薄い影を床に落としながら、朝倉がゆっくりと歩いてくる。 「ねぇ、諦めてよ。結果はどうせ同じことになるんだしさぁ」 「・・・何者なんだ、お前は?」 何回見ても、壁は壁でしかない。立て付けの悪かった引き戸もすりガラスの窓も何もない。それとも、どうかしちまったのは俺の頭の方なのか? 俺はじりじりと机の間をぬって朝倉から少しでも離れようとした。しかし朝倉は、一直線に向かってきた。 逃げ場はない。俺はたちまちのうちに教室の端に追いやられた。 こうなったら。 女に手をかけるのは主義に反するが、こういう状況ではそうも言ってられない。フェミニズムなんかくそくらえだ。 俺は近くにあった椅子を持ち上げると、思いっきり朝倉めがけて投げつけてやった。 かきん。 空中で、なにかにあたった音がする。椅子は朝倉の手前で方向転換すると、空中で曲がって横に飛んで落ちた。そんなアホな。 「無駄。言ったでしょう。今、この教室は全てあたしの意のままに動くって」 待て待て待て待て待て待て。 何だこれは?何なんだこれは?冗談でもシャレでも俺か朝倉の頭が変になったわけでもないとしたら、いったいこれは何だ? あなたを殺して、涼宮ハルヒの出方を見る。 またハルヒか。 人気者だな、ハルヒ。 「最初からこうしておけばよかった」 朝倉が何事かをつぶやいた。 とたんに、俺の体がぴくりとも動かなくなった。 足が床から生える木にでもなったみたいに、微動だにしない。手もパラフィンで固められたみたいに上がらない。それどころか、指一本動かせない。下を向いたままの状態で固定された俺の視線に、朝倉の上履きが入ってきた。 「理由は判らないけど、あなたが涼宮ハルヒにとっての大事な存在だということはわかる。だから」 かろやかな声だ。とても今から、俺を殺そうとしている冷酷な殺人者の声には聞こえない。 「あなたが死ねば、必ず涼宮ハルヒは何らかのアクションを起こす。多分、大きな情報爆発が観測できるはず。またとない機会だわ」 知らねぇよ。 毒づきたかったが、唇もまったく動かない。無理だ。 「じゃぁ、死んで」 朝倉がナイフを構える気配。どこを狙っているんだろう。頚動脈か、心臓か。解っていれば少しは心構えもできるんだが・・・せめて目を閉じ・・れない。なんということだ。 空気が動いた。 ナイフが俺に降ってくる。 その時。 天井をぶち破るような音とともに、瓦礫の山が振ってきた。 コンクリートの破片が俺の頭にぶつかってくる。 「痛いな、この野郎!」 俺は叫んだ・・・叫んだ? 体が動く。 俺は顔をあげ、見た。 俺の首筋に今にも触れようとしているナイフの切っ先とナイフの柄を逆手に握って、驚きの表情で静止する朝倉と、ナイフの刃を素手で握り締めている、長門有希の小柄な姿が、そこにあった。 「なぜ?」 「空間閉鎖、情報封鎖に気がついた」 長門は平素と変わらない無感動な声で答えた。 「邪魔する気?」 対する朝倉も平然たるものだった。 「この人間が殺されたら、間違いなく涼宮ハルヒは動く。これ以上の情報を得るにはそれしかないのよ」 「あなたはわたしのバックアップのはず」 長門は平坦な声で、 「独断専行は許可されていない。わたしに従うべき」 「いやだと言ったら?」 「情報結合を解除する」 「やってみる?通常空間ならともかく、ここではわたしのほうが有利よ。この教室はわたしの情報制御空間」 「情報結合の解除を申請する」 言うがはやいか、長門の握ったナイフの刃が煌きだした。熱い紅茶に入れた角砂糖のように、ナイフは微小な結晶となって、サラサラとこぼれ落ちていった。 「!」 ナイフを離すと、朝倉はいきなり5メートルくらい後ろにジャンプした。それを見て俺は、今更ながらに、あぁ、この二人、本当に人間じゃないみたいだな、と思った。 一気に距離をかせいだ朝倉は教室の後ろにふわりと着地すると、変わらぬ顔で微笑んだ。 空間がぐにゃりと曲がった。朝倉も机も天井も床もまとめて揺らぎ、液体金属のように変化していく様がみえた。 空間が、空間そのものが、槍のように凝縮した・・・と思った瞬間、長門のかざした手のひらの前で結晶が爆発した。 空間がこごめられた槍が目にもとまらぬスピードで長門を襲うのだが、その全てを長門が手で迎撃していた。長門が槍に触れるたび、槍は結晶となって舞い散っていく。その姿は、まるで雪につつまれているかのようだった。 長門は朝倉の攻撃をはじきながら片手で俺のネクタイをつかんで引き卸、俺はかがみこんだ長門の背中にのっかかるような体勢で膝をついた。 「うわぁ!」 その瞬間、先程まで俺の頭があった場所を槍が何本も通過していき、背後で黒板が粉々に叩き潰されたのがわかった。もしも長門が俺をひっぱってくれなかったら、黒板の代わりに俺が粉々に叩き潰されていたことだろう。危ない。助かった。 「この空間では、私の方が有利。あなたは勝てないわ」 まったくの余裕の表情で朝倉はたたずんでいる。数メートルの間を挟んで長門と対峙。俺はというと、情けないことに腰が抜けて、床にへばりついていた。 長門は俺の頭をまたいでたっていた。生真面目にも上履きの横に小さく自分の名前を書いているのが長門らしい。小説の朗読をするような口調で、長門は何かを呟いた。それはこう聞こえた。 「SELECTシリアルコードFROMデータベースWHEREコードデータORDER BY攻性情報戦闘HAVINGターミネートモード。パーソナルネーム朝倉涼子を敵性と判定。当該対象の有機情報連結を解除する」 教室の中はもうまともな空間ではなくなっていた。何もかもが幾何学模様と化して湾曲し、渦を巻いて踊っている。見ていると酔いそうだ。 「あなたの機能停止の方が早いわ」 極彩色の蜃気楼の影に隠れた朝倉の声が、いったいどこから聞こえてきているのか解らない。 ヒュン、と風きり音がなった。 同時に、長門のかかとが俺を思いっきりけとばした。 「なにす・・・」 言いかけた瞬間に、俺の鼻先を見えない槍が通過していった。床がめくれあがり、離れた場所で爆発音が聞こえてくる。 冷や汗をかく。もしも長門が蹴飛ばしてくれなかったら・・・いや、考えるのはよそう。 「そいつを守りながら、いつまで持つかしら?じゃぁ、こんなのはどう?」 朝倉の言葉と同時に、俺と長門の周りに無数の槍が出現した。1,2,3,4・・・とても数え切れない。360度、全ての方向に槍の鋭い切っ先が見える。 「さよなら」 無数の槍が俺たちめがけて飛んできた。 ものすごいスピードで長門が動き、無数の槍が白い結晶となって砕け散る。しかしいかんせん、槍の数の方がまさった。迎撃しきれなかった1ダース以上もの槍が俺の眼前にせまり・・・ 次の瞬間。 俺の前に立ちはだかった長門の身体が、1ダース以上の槍に貫かれていた。 長門の顔から眼鏡がおちて、床におちてレンズが割れた。 「長門!」 「あなたは動かないでいい」 胸から腹にかけてビッシリと突き刺さった槍を一瞥すると、長門は平然といった。 鮮血が長門の足元に小さな池をつくりはじめている。 「へいき」 そんなわけがない。 長門は眉ひとつ動かさずに、身体に生えた槍を引き抜いて床に落とした。乾いた音をたてて転がった血まみれの槍は、数瞬ののちに生徒机へと姿を変えた。 槍の正体は、それか。 「それだけダメージを負ったら、他の情報に干渉する余裕はもうないでしょ?じゃ、とどめね」 揺らぐ空間の向こうに、朝倉の姿が見え隠れする。笑っている。その両手が静かにあがり・・・指先から二の腕までがまばゆい光に包まれて二倍ほどに伸びた。 「死になさい」 朝倉の腕がさらに伸び、触手のようにのたくって突出した。左右からの同時攻撃。動けない長門の小柄な身体が揺れ・・・ 俺の顔に、紅くて暖かい液体が飛び散った。 右のわき腹に突き立った朝倉の左腕と、左胸を貫いた右腕が、背中を突き破って教室の壁をもぶち抜いてようやく止まっていた。 長門の身体から噴出した鮮血が、白い足をつたって床の血溜りの幅を拡大させていった。 「もう、動けないでしょう」 いつの間にか、朝倉の両手が元に戻っていた。 朝倉はゆっくりと歩いてきた。長門は立ったまま動かない。 「あなたがそいつを守ったのは、涼宮ハルヒのため?それとも」 朝倉が近づく。 「あなた自身が、そいつを守りたかったの?」 「あなたには関係がない」 ぼそりと、長門がつぶやいた。よかった。生きている。 「ふふ。そう」 朝倉は笑うと、長門に抱きついた。 「でも、残念だったわね。ここであなたはデリートされるし、あなたの守りたかったそいつも、あなたが消えた後に殺されるのよ」 朝倉は長門の頬に顔を近寄せると、舌を伸ばして長門の頬についていた鮮血をれろんと舐めとった。 「とても残念ね」 長門は答えない。 「消える前に、あなたに思い出をあげる」 朝倉は床に倒れたままの俺をみた。情けないことに、俺も身体が動かない。 「私はあなたのバックアップだった。だから、完全ではないけど、あなたの思いは私にフィードバックされてくる。あなたは、涼宮ハルヒの対象として以上に、そいつのことを思っている」 「それが、なに」 「あなたの三年ばかりの人生に、思い出なんてないでしょう?今から最後の数分間だけ、思い出をあげるわ」 そういうと、朝倉はすでにビリビリに破けている長門のスカートに手をやり、一気に引きおろした。長門は抵抗をしない。出来ないのかもしれない。 飾り気もなにもない、純白の下着が眼前に現れた。長門らしい下着だ。 「これも邪魔ね」 朝倉がよく聞き取れない声でなにかつぶやいた瞬間、長門の下着がさきほどの槍のように、白い結晶となって消えていった。 もはや隠すものは何もなかった。長門の女性器がみえる。まわりの陰毛は薄い。色は長門の髪の毛と同じ色だ。 「最後の思い出に、よく見てもらいなさい」 朝倉は長門の背中から覆いかぶさると、左手で長門の胸をつかみ、右手でそのあらわになった女性器をゆっくりと触り始めた。朝倉の手が動くたび、くちゅくちゅという音がする。 「あれれ、長門さん、濡れてるわよ」 楽しそうに、朝倉はいった。相変わらず長門は無表情だが、ほんのりと頬が上気しているのがわかった。 「広げちゃおうか。私たちには必要ない、子宮まで見えちゃうかもしれないわね」 人指し指中指を使って、朝倉は長門の女性器を大きく開いた。ぬらりとした液体が糸を引き、長門の下の口がぱっくりと開いた。奥の奥まではっきりと見える。その光景に、俺は吸い込まれそうになった。 「胸は小さいわね」 あいかわらず、左手は長門の胸をもみしだいていた。こぶりの胸の真ん中で、乳首が立っているのが解る。 朝倉は長門の頬をれろんとなめた。朝倉の唾液が長門の頬と舌の間で糸を引いた。 くっくっくと、楽しそうに朝倉は笑った。そして、長門をぺたんとその場に座らし、ちょうど俺の目の前に長門の股がくるように仕向けた。 朝倉は長門の後ろに座り込み、さきほどまで長門の乳首をもてあそんでいた左手で長門の左足を持ち、女性器をいじっていた右手で長門の右足を持った。 「さぁ、御開脚しましょう」 ゆっくりと、長門の足を開かせる。 ぬっりとした卑猥な長門の女性器が、俺の眼前に広がった。 「わたしとあなたはつながっていた・・・だから、わかるの」 そう言うと、朝倉は右手と左手を動かし・・・長門の身体の中の、一番、恥ずかしい部分・・・女性器よりも、恥ずかしい部分・・・肛門を、触った。 「あなたが・・・ううん。わたしたちが、一番感じるのは、胸でも、おへそでも、あそこでもなく、ここ・・・」 よく濡れた指で、長門の肛門の周りをもみしだいていたが、やがて、ゆっくりと、背後からまわした右手の人差指が長門の肛門に差し込まれていった。 「アナルが、一番感じるところなのよね」 「・・・あ」 初めて、長門があえぎ声をあげた。 そのあえぎ声にあわせて、再び朝倉の人差指が、長門の肛門奥深くにまで差し込まれていく。第一関節・・・第二関節・・・そして、人差指は全て、長門の肛門に吸い込まれていった。 「次は、こっちの指」 朝倉は、今度は左の人差指を長門の肛門にあてた。 「入れるわよ」 返事はなかった。ただ、 「・・・あ」 という、さきほどと同じような、長門のかぼそいあえぎ声だけが聞こえてきた。 また、指が奥深くまで挿入されていく。第一関節・・・第二関節・・・左の指も、全て長門の肛門に差し込まれていった。 「・・・はぁ」 「うふふ。長門さんの直腸の中、ぬるぬるしてるわよ」 いたずらそうに朝倉は笑った。 「じゃぁ、あなたの大事なひとに、見てもらいましょうか」 朝倉はそういうと、長門の肛門に差し込まれた指をつかって、ゆっくりと、しかし確実に、長門の肛門を開き始めた。 「・・・ふぅ」 なんともいえない声が、長門の口から漏れてきた。自らの肛門を開かれる瞬間を見たくないからであろうか、目はしっかりと閉じられている。 長門の女性器はすでにどろどろになっていた。あふれ出た愛液が、肛門に伝わり落ちていっている。その愛液がローション代わりになり、朝倉の指がより深く差し込まれる形となっている。 「奥まで見えるかしら?」 今では、長門の肛門は極大まで開かれ、拡張されていた。ちょうど俺の眼前に広がるその光景は、俺を興奮させるのに十分だった。 長門が、ゆっくりと目を開き、そして俺の姿をみた。俺が興奮しているのを見て、長門も興奮してきたようだった。 「長門さんの肛門の奥にあるもの、見えるかしら?」 朝倉が尋ねてくる。俺は答えなかった。答えるつもりはなかった。だが、朝倉の質問の意味はよく理解できた。拡張された長門の肛門の奥深くに、あるものが見えたのだ。それは、茶色い色をしていた。 「ふふふ。答えられないのね。恥ずかしいのかしら?なら、私が答えてあげる」 朝倉はいたずらっぽく笑うと、長門の頬にほおずりをした。息を吹きかけ、そして言う。 「私の指先にあたってるもの。この柔らかい塊。押したら奥まで引っ込んでいくわ。可愛い」 また、指に力をいれ、長門の肛門が開かれた。どんどん拡張されていく肛門の奥で、それが動いたのが見えた。満を持して、朝倉がいった。 「この暖かい柔らかい塊・・・長門さんの・・・う・ん・ち」 この言葉が、キーワードだったようだ。長門の息が激しくなってきているのが、目に見えて解った。 そういえば・・・自分で自分のこと、スカトロに興味があるって言っていたよな・・・ 俺はふと、そういった長門のことを思い出した。あのときは、長門は無表情のまま言っていた。しかし今は、目に見えて長門は興奮している。 「出しちゃおっか?」 肛門をひらきつつ、嬉しそうに朝倉がいった。朝倉も興奮しているようで、とめどなく汗を吹き出している。 「出しちゃお。ね、出しちゃおうよ!」 朝倉と長門の頬が触れ合った部分が、しっとりと濡れていた。朝倉の唾液や汗だけではない、興奮してきた長門も、ほんのりと汗をかきはじめているのだ。 「出しちゃおうよ。大事な人に、見てもらおうよ。ねっ、ねっ?」 無邪気な朝倉の声に・・・長門は・・・ついに・・・こくんとうなづいた。 「決まり!」 そういうと、朝倉は長門の肛門が俺にもっとよく見えるように、長門の身体を動かした。朝倉は長門の肛門から指を引き抜くつもりはないらしい。このままの体勢で、長門に排泄させるつもりなのだろう。 「今から長門さんが、一生懸命うんちを排泄するからね。人生最後の排泄だから、しっかりその目で見ていてね。見終わったら、死んでね」 屈託のない笑顔でそう言う。最後の言葉が気になったが、今の俺には、それにかまっているヒマはない。目が長門の肛門に釘付けになっていた。 しばらく、長門は動かなかった。じっと、俺の表情を見ていただけだった。しかしこの時、すでに長門は精一杯力んでいたのだ。流れる汗が増えていき、やがて長門は言った。 「・・・出る」 「来たわ!」 肛門が動いた。 奥にすぼまっていた茶色い塊が動き始めた。 「あ、私の爪の間に入りそう」 妙にリアルな感想を朝倉が述べた。肛門の奥深くに差し込まれた二本の指の間で、長門のうんちが少しずつ、ゆっくりと、しかし確実に、排出されていった。 茶色い塊が、長門の肛門から頭を出した。 「ちょっと待って!そこで止めて!」 朝倉がいう。長門は素直にそれに従った。 俺の眼前で、肛門から1センチほどうんちを出したままの状態で、長門は脂汗をいっぱいにかきながら、息を荒げている。 「まだよ・・・ここで出来るだけ我慢するのが、一番いいんだから・・・」 そういう朝倉も興奮している。 長門の肛門から、長門のうんちの匂いが俺の鼻腔を刺激した。思ったほど、匂いは強くない。やはり宇宙人は、少しからだのつくりが違うのだろうか? いや、目の前で排泄の途中中止で必死に我慢している長門の表情を見ていると、とても宇宙人であるとは思えなかった。 かなりの時間がたった。もはや長門の我慢も限界にきていた。それをみてとったのだろう、最高のタイミングで、朝倉が許可を出した。 「いいわよ!長門さん、思いっきりひり出しなさい!」 その言葉を合図として、長い長い排泄が始まった。 「出る」 長門のかぼそい声と同時に、見事な一本の長門のうんちが、形そのままで排出されていった。長門の肛門はめくりあがり、とめどなく出てくる一本のうんちは、長門の腸液にまみれてぬらぬらと濡れていた。 20センチ?30センチ?いや、40センチはあったかもしれない。 いつまでも続くかと思われた長門の排泄も、物理的に限界がある。出だしは硬かった長門のうんちも、出続けていくうちにだんだんと柔らかくなり、最後にはどろどろの軟便に近くなってきていた。 長門は肛門を動かし、できるだけ最後の最後まで排泄しようとしていたが、もはや直腸内にうんちは残っておらず、最後に一度肛門をすぼめてうんちを断ち切ると、長門の排泄は終わった。 後には、40センチ近い長門のうんちだけが残された。長門の体内でずっと温められていたそれは、白い湯気を出していた。  「終わった」 長門はポツリと言った。 「よく頑張ったわね。あなたの三年ばかりの人生で、一番頑張った瞬間じゃないの?すごく長いうんち・・・いい思い出になったでしょう?」 「違う」 排泄の間、あれほど恍惚の表情を浮かべていた長門が、突然表情を変えた。興奮に身をゆだねた表情ではない。ある種の決意を持った、凛とした顔だ。 「情報連結解除、開始」 いきなりだ。 教室の全てのものが輝いたかと思うと、その一秒後にはキラキラとした砂となって崩れ落ちていく。俺の横にあった机も細かい粒子に変じて崩壊する。 「そんな・・・」 天井から降る結晶の粒を浴びながら、今度こそ朝倉は驚愕の様子をみせた。 「あなたはとても優秀」 長門がそういうと、肛門につきたてられていた朝倉の両手が、キラキラと輝く結晶となって崩れ落ちていった。 「だからこの空間にプログラムを割り込ませるのに今までかかった。でも、もう終わり」 「・・・侵入する前に崩壊因子を仕込んでおいたのね。どうりで、あなたほどの人が弱すぎると思った。あらかじめ攻性情報を使い果たしていたわけね・・・」 どんどんと結晶化していく自らの身体を眺めながら、朝倉は観念したように言葉を吐いた。 「あーあ、残念。しょせんわたしはバックアップだったかぁ。膠着状態をどうにかするいいチャンスだと思ったのにな」 朝倉は俺を見てクラスメイトの顔に戻った。 「わたしの負け。よかったね、延命できて。でも気をつけてね。統合思念体は、この通り、一枚岩じゃない。相反する意識をいくつも持っているの。ま、これは人間も同じだけど。いつかまた、わたしみたいな急進派が来るかもしれない。それか、長門さんの操り主が意見を変えるかもしれない」 朝倉の胸から足はすでに光る結晶に覆われていた。 「それまで、涼宮さんとお幸せに。じゃあね」 音もなく、朝倉は小さな砂場になった。一粒一粒の結晶はさらに細かく分解、やがて目に見えなくなるまでになる。 さらさら流れ落ちる細かいガラスのような結晶が降る中、朝倉涼子という女子生徒はこの学校から存在ごと消滅した。 とすん、と軽い音がして、長門が後ろへと倒れこんだ。倒れこんだのが後ろでよかった。もしも前に倒れこんだなら、この40センチもある自ら排泄したうんちにあたまから突っ込んでいたところだった・・・そんなことが頭をよぎったが、それよりなにより、俺は慌てて立ち上がると長門を助け起こした。 「おい!長門!しっかりしろ!今、救急車を・・・」 「いい」 目を見開いて天井を見上げながら、長門は 「肉体の損傷はたいしたことない。正常化しないといけないのは、まずこの空間」 砂の崩落が止まっていた。 「不純物を取り除いて、教室を再構成する」 見る間に一年五組が見慣れた一年五組へと、元通りに、そうだな、まるでビデオの逆回しのように戻っていく。 白い砂から黒板が、教卓が、机が生まれて、放課後教室を出た時と同じ場所に並んでいく光景は、なんと言えばいいんだろうな。こうして生でみなければよくできたCGだと思っただろうな。 俺はまだ寝ている長門の脇にかがみこんだ。 「本当に大丈夫なのか?」 確かに、どこにも怪我があるように思えない。あれだけ槍に突き刺されれて穴が開いているはずの制服も完全に修復されており、朝倉に消滅させられたはずのスカートも無事にもどってきていた。 「処理能力を情報の操作と改変にまわしたから、このインターフェースの再生は後回し。今やっている」 「手を貸そうか」 俺の伸ばした手に、案外素直にすがりついた。上体を起こしたところで、 「あ」 わずかに唇を開いた。 「眼鏡の再構成を忘れた」 「・・・していないほうが可愛いと思うぞ。俺には眼鏡属性ないし」 「眼鏡属性って何?」 「何でもない。ただの妄言だ」 「そう」 こんな会話をしている場合ではなかったのである。後々俺は、とことん悔やむことになる。はやくこの場を立ち去るべきだったと。 「うぃーす」 ガサツに戸を開けて、誰かが入ってきた。 「WAWAWA忘れ物〜、忘れ物〜・・・うお!」 自作の歌を歌いながらやってきたそいつは、よりにもよって谷口だった。 まさか谷口もこんな時間に教室に誰かがいるとは夢にも思わなかっただろう。俺たちがいるのに気づいてギクリと立ち止まり、しかるのちに口をアホみたいにパカンと開けた。 この時、俺はまさに長門を抱き起こそうとするモーションに入ったばかりだった。その静止画を見たら、逆に押し倒そうとしているとも思えないもない体勢なわけで。 しかも運の悪いことに、床には、先程長門が頑張って排泄したばかりの、40センチはあろうかという長いうんちがまだ横たわっていたのだ。 クラスメイトに見られて、これ以上最悪な光景というものがあるのなら教えてくれ。 「すまん」 聞いたこともない真面目な声で谷口は言うと、ザリガニのように後ろにさがり、戸も閉めないで走り去った。追うヒマもなかった。 「面白い人」 長門がいった。 俺は盛大なため息をついた」 「どうすっかなー」 「まかせて」 俺の手にもたれかかったまま動くことなく、長門はいった。 「情報操作は得意。朝倉涼子は転校したことにする」 「そっちかよ!」 思わず突っ込んだ。 まぁ、後のことは後で考えよう。ただひとつはっきりしているのは、今まで長門がいっていた「私はスカトロマニアの宇宙人」というのは、掛け値なしの真実だったってことだ。いくら俺でも、こんな経験をした後にまで懐疑的になることはできない。 ということは、朝比奈さんの「放尿プレイ好きの未来人」も真実だし、古泉の「アナルセックスマニアの超能力者」も真実なのだろう。 そして、ハルヒがなにやら特別な存在なのだということも。 オレンジ色に染められた教室で、俺はしばし唖然としたまま硬化していた。長門の体重を感じさせない身体を支えたままで。 まぁ、とりあえず。 「これ、このままじゃまずいよな」 俺は教室の床に横たわってまだ白い湯気をあげている長門の排泄した40センチものうんちを見ながらそうつぶやいた。 そんな俺を、抱きかかえられていたままの長門がぱちくりと目を見開いていった。 「食べようか?」 「いや、いい」 なにをいうんだ、こいつは。 俺はやれやれとため息をつくと、 「さっきみたいに、結晶化させてなくしてくれ」 といった。 「そう」 長門はぼそりとそう呟いた。とたんに、床に横たわっていたうんちが白く輝き始め、結晶となって消えていった。 あんなに頑張って出してくれたのに少しもったいない気もするが、まさかこのまま教室に置いておくわけにもいかないし、ないより、頼めばこれからも、長門は出してくれるような気がする・・・いやいやいや、俺はいったい何を考えているんだ? 呆けていたおかげで俺は、とっくに全てを終わらせていた長門が無表情に見上げていることにも気づかなかった。 こうしていると、整った可愛い顔立ちをしているんだがな。長門は。 翌日、クラスに朝倉涼子の姿はなかった。 当たり前といえば当たり前のことなのだが、それを当たり前だと思っているのはどうやら俺だけであり、担任が、 「あー、朝倉くんだがー、お父さんの仕事の都合で、急なことだと先生も思う。転校することになった。いや、先生も今朝きいて驚いた。なんでも外国に行くらしく、昨日のうちに出立したそうだ・・・」 と、あまりにもうそ臭いことをホームルームでいったとき、クラスの連中がざわめき始めた。 まぁ、無理もない。 「キョン、これは事件だわ!」 もちろん、この女が黙っているわけがなかった。すっかり元気を取り戻した涼宮ハルヒが目を輝かせていた。 どうする?本当の事をいうか? 実は朝倉涼子は情報統合思念体なる正体不明の存在につくられた長門の仲間で、なんか知らんが仲間割れして、その理由が俺を殺すか殺さないかで、なぜ俺かと言うとハルヒの情報がどうのこうので、あげくのはてに長門によって砂に変えられてしまい・・・それだけならともかく、しかも長門も正体は宇宙人で、昨日俺の前でお前が心から望んでいるスカトロショーを披露してくれて・・・たぶん俺が頼めば、いつでもしてくれるだろうということを・・・ 言えるわけねぇ。 つーか、俺が言いたくない。 「謎の転校生が来たかと思ったら、今度は理由も告げずに転校していく女子までいたのよ。これは絶対、なにか裏があるはずよ」 ハルヒよ、当りだ。 「だから、親父さんの仕事の都合なんだろ」 「そんなベタな理由、認めらんない」 「といってもなぁ・・・」 「これは調査の必要ありね」 ハルヒはにっこりと笑った。思わず、俺も「可愛いな、こいつ」と思ってしまったほどの、最高の笑顔だ。 「SOS団として、これは座視するわけにはいかないわ。この先には必ず、この世の不思議なエッチが広がっているはずなんだから!」 勘がいいやら悪いやら。 とにかく、やめてくれ。 昨日の事件は、俺に決定的な変革を要求せしめた。なにしろ、マジモノの超常現象を目の当たりにしてしまったのだから。 後ろの席で、嬉しそうに俺の背中をツンツンつついてくるハルヒをうっとおしく感じつつも、同時に少しばかりの可愛らしさを感じてしまうのはなぜだろうか? こいつが世界の命運を握っているねぇ・・・ 少なくとも、俺の命運は握っていそうだがなぁ。 な、ハルヒ。 |
||
第六章に続く |