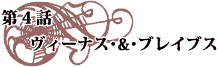
エクレスとマスターが人ごみを掻き分けてランプを吹き消していった。 店内が一段と暗くなる。客たちは中央に設けられた壇に視線を向けた。 高いピアノの音が一音。それに続いて低音の重厚な和音。 鈴の音がシャンッと響き、後方から壇に向けて光弾が走り破裂した。 眩しさに思わず目を閉じたが、再び壇上を見ると、そこには二人の人間が 立っていた。それぞれ両腕のバングルから薄布を垂らした男女だ。 女はバク宙で壇の奥へ跳び、いつの間にかそこにあった椅子へと着地した。 男は優雅に手を上げ、一礼してから一歩下がった。 再びピアノの和音が響くと、壇を観る観衆たちの後方から白と黒の鳥が 螺旋を描きながら飛んできた。 壇上でクルクルと周りながら互いが寄り添ったと思ったら、白煙と共に弾けた。 その煙の中から、艶やかな露出の多い衣装に身を包んだ、黒髪の小柄な女性が現れた。 回転しながら華麗にお辞儀をし、威勢良く顔を上げて叫んだ。 「はぁいっ!今日はこのホノカ・セキグチとその楽団『ヴィーナス・アンド・ ブレイブス』のライブに来てくれて、どうもありがト〜〜ぅッ!!」 爆発したように上がる歓声の中、ホノカがポーズを取って両手を挙げると、手のひらから 優しい光の玉が、いくつもいくつも現れ、楽団のメンバーたちを照らし出した。 ピアノは高音がキャナル・ウィンフィール、低音がヴァーグナル・カンタ。 光と共に椅子の周囲に円陣のように様々な打楽器が並べられたパーカションには イガーナ・シャロワ。その右方には、足元には金管楽器、手には弦楽器を構えた アディ・ナット。そして、壇の中央にはヴォーカル、ホノカ・セキグチ。 これががこの楽団の全メンバーだった。 「うおおおおぉぉぉ〜〜〜〜〜!!ホッノッカッ!ホッノッカッ! えるおぉぶぃいーーーーーーーアイラブ!ホノカァアアア"−−−−−ッッッ!!!」 ホノカの蜜のある歌声を掻き消す勢いで、ホールの中央からダミ声が上がった。 そちらを見ると、ボサボサの黒い長髪に鉢巻を巻いた体格のいい男を中心に、 そろいの鉢巻をした男たちが肩を組んで揺れあっていた。 「ちょっと!何さあのキモいやつら!あいつらが邪魔であたいのアディが見えないじゃないのさ!」 フェルフェッタが息を巻いて、お目当てのメンバーの姿を拝むために興奮の渦に 飛び込んでいってしまった。 「キャーーーーーッ!ヴァンーーーーッ!こっち向いてぇーーーんっ!!!!」 「ヴァーグナルーーーー!!愛してるーーー!」 「や〜ん!今、私を見てくれたわぁ!」「何よ!あたしを見たのよ!」「ヴァーーン!」 陶酔して頭を振り回しながら演奏するヴァーグナルへ黄色い声が降り注いだ。 手元に注目すると、和音を掻き鳴らしているだけなので、キャナルの冷静な旋律が 曲を支えていた。 「……想像以上に、騒々しい……」 ワイズがボソッと言い放った言葉を聞き、団長は目をしばたいた。 「……シーテ先生でも、ダジャレを言うんですね」 ワイズは顔を伏せた。心なしか、耳が赤いように見えた。 団長は気づかない振りをして、熱潮にある酒場のホールを見た。 思い思いに叫び、拳を振り上げ、時には踊り、足踏みをする観衆の中を エクレスはトレンチを片手に舞うようにすり抜け、注文の品を的確に運んでいた。 団長はホール全体を、ぐるっと見渡してみた。 どの人にもあれが見えた。個人を中心に回るように、ゆっくりと浮かんでいる。 これだけたくさんの人がいて、これだけ活気と熱が溢れているのに、 急に孤独を感じ、ビールの入った杯を一気に呷った。 空の杯を机に置いたが、手放せずにそのままズルズルと頬を机にぶつけた。 「……シーテ先生、私は気が狂ったのかもしれません」 「なんだ君、酒に弱いのかい?」 団長は迷った。しかし、もう、どうしても、誰かに言ってしまいたかった。 「先生は、女神の存在を信じますか?」 「宗教論かい?そういう意味だったら僕は信じない。信じる人にとっては存在するだろうけど 僕は信じてないから、僕にとっては存在しない」 「なるほど。実は、私も信じていません。でも、その私の元に女神が現れました。 これはどういうことでしょう?」 「……女神に会った?」 「はい。とびきり美人で、とびきり変な服でした。あんな服、恥ずかしくて普通の女には 着れませんよ、だから、あの人は女神です。立派な翼もありました」 「もしかして、その人は紅の長髪に、三叉翼のサークレットをしていた? 腰からは大きな時計を下げていなかったかい?」 「はい。それで、やたら脚を出していました。……お知り合いですか?」 「エレオノーレ・エヴァンス、これは極めて重要なことだ。本当に、今言った 容姿の人物に会ったんだね?そして……」 ワイズは声を落として言った。 「滅びの予言を聞いたんだね?」 エレオノーレは顔を机から剥がして、ワイズの目を真直ぐに見て頷いた。 「はい。20年後に最初の一撃が来る、と」 「なんてことだ……」 ワイズは天井を仰いで、手で顎を押さえた。 そこにエクレスが目ざとく空になった杯を見つけ、追加注文を取りに来た。 ワイズは冷えた水を二つ頼んだ。 「先生〜。これから盛り上がるって時に、おひやは無いんじゃないですか? ねぇ、エルツー?」 「先輩、おひやふたつ」 「あ〜はいはい。ミネラルウォーターふたつ、と。マリスベイとシーラ、どっちの銘が いいです?」 「シーラで。キンキンに冷やしてくれ」 ワイズの注文を背に、エクレスは再び渦巻く観衆の間へと消えていった。 それを見届けた後、ワイズは再び団長を見て、さらに声を落としていった。 「エヴァンス君……君はもしかして『クロニクル』を知っているんじゃないか?」 「?はい。知ってますが……手書きの小説ですよね。先生もご存知だったんですか」 「!どこで見つけた?!」 ワイズが身を乗り出して尋ねた。鼻がぶつかりそうだったので、団長は慌てて少し身を引いた。 「騎士団本部の記録室の書架です」 「記録室……?僕が前に調べた時は見つけられなかったが……見落としたか?いや、 そんなはずは無い……前の団長……いや、あいつはボンクラだ……となると…… どこかのアクラルが……いや……それだと……が……」 ワイズはブツブツと独り言を喋りながら、頭をゆらゆら動かした。 合わせて帽子の先端から下げている三日月型のメダルが揺れた。 団長はそんなワイズをじっと見ていた。当然、かつての師にもアレは見えていた。 「エヴァンス君、僕の言うことを冷静に聞いて欲しい」 ワイズは夢から覚めたように顔を上げ、わざとゆっくりと、言い聞かせるように団長に声をかけた。 「はい」 「君は気が狂ってなんかいない。無論、僕もだ。いいかい?君が会ったという女神は 本物の女神だ。したがって、滅びの予言も本物だ。このまま君が何も手を打たなければ このアクラルは20年を待たずに……」 ワイズは一呼吸置いた。 「滅亡する」 その言葉を受けて、団長はゆっくりとまばたきをした。女神に言われるよりも、 ワイズに断定されるほうが説得力があった。 「そして、君が読んだという『クロニクル』。あれは……史実だ。かつて、実際にあった ことなんだ」 「……?先生、失礼ですが、私はアクラル史の授業もきちんと単位を取りました。 有史以来、そのようなことがあったとは聞いていませんし、百年にも及ぶ あれだけの魔物の侵攻が、歴史の裏舞台に隠されていたとは到底思えませんが?」 団長の反論に、ワイズは頭を振った。 「わかる、わかるよ。そう。有史以来そんな事実は無い。あれはその前なんだ。 分かりやすく言うと、……この世界は一度滅んでいる。そして再建した。 歴史に残っているのは再建以降だ。再建前、つまり有史以前の記録、それが 『クロニクル』だ」 「……文化レベル的に、ありえないと思いますが……」 「話せば長い……。このアクラルは一度、いや、実際には一度ならず、数度滅んでいる。 これは学者の間では定説だ。『クロニクル』は一冊ではない。数冊、その存在が 確認されている。ウェロー中央図書館、サイラス寺院、キュリス陵墓、アクラリム遺跡、 王城付属アクラル・アイ……だから僕たちはそれらを『クロニクルズ』と呼んでいる。 その全てが、史実だ。実際にこのアクラルで起きた戦いの記録なんだ。そして その度に、アクラルは滅んでいる」 「……私が読んだものは、世界は予言より百年の後、滅びを回避していました」 「それはおそらく、後から最後の部分が改ざんされているんだろう。 他の『クロニクル』も百年で大団円を迎えているが、全ての本において、 結末近くの数ページの改ざんが見つけられている。紙やインクや筆跡を 巧妙に似せているが……人間の目をごまかせても、科学はごまかせない」 団長は記録室に置いてある本の最後のページを思い出した。 最後に載せられている言葉を彼女はとても気に入っていた。 小説だと思っていても、心に響く言葉だった。 だが、それが自分を欺いたような気がして、ひどくがっかりした。 「はい、お待たせしました!お・ひ・や、でございま〜す」 エクレスがこれまた絶妙なタイミングで冷えて汗のかいたグラスをふたつ 机の上に置いて去っていった。 ふたりとも黙ったまま、手にとろうとはしなかった。 ホノカ達の音楽と歓声の反響で、ホール全体の空気が熱く振動していたが、 ふたりの周りだけは凪いでいた。 「……私がこのまま何もしなければ、世界はすぐに滅びを迎える」 先に沈黙を破ったのは団長だった。 「……私が、団員を集め、世界を巡り魔物と戦えば、すぐには滅びない」 ワイズは大きく頷いた。帽子のメダルがキラリと光った。 「……それでも、百年の後、結局は世界は滅びるんですか? だったら、それまでの百年は何のためにあるんですか?! 私たちが戦うというのなら、それに何の意味があるんですか?! 結局は滅びるというのに!!」 エレオノーレは声を荒げて、机を叩いた。 グラスに波が立って、小さなしぶきが上がった。 ワイズはそれを袖で拭いてから、団長の前にグラスを置きなおした。 「本当に滅びるかは、百年後にしか分からない。……百年後。僕も君も 当然生きてはいない。だから、結末がどうなるかは分からない。 でも、種を蒔いておくことはできる。君にはその権利が与えられた。 今すぐ諦めるのは簡単だ。『クロニクル』のことは、世界でも一握りの 人間しか知らない。もし、数年後に世界が滅んでも、誰も君を責めたりはしないよ」 エレオノーレは、グラスに歪んで映り込む、ホールの熱狂を見つめていた。 「でも、百年もあるんだ。今までの『クロニクル』では見つけられなかった 何かを探して、滅びを回避できるかもしれない。……可能性だ。 君が動くことによって、世界に可能性の猶予期間を与えられるんだ。 とても重いことだと思う。辛くて大変なことだ。だが、女神は 君ならそれができると思って託したんだ。……泣かなくてもいい。 君の中に、滅びを回避したいという気持ちがあるなら、僕は全力で 協力するよ。僕は君の背中を押してあげることはできる。 でも、決めるのは君だ」 まだ少女の面影が残る頬を、涙が一粒、また一粒と伝っていった。 彼女はそれをぬぐうことも忘れたかのように答えた。 「……答えは、もう決まっています……」 ワイズは優しく団長の手の甲を叩いた。 「そうかい……。では、僕が団員立候補第一号だ」 差し出された手を緩く握り、団長は涙をそのままで口の端で微笑んだ。 「ありがとう、ございます」 涙で全てが滲んで見えた。ホノカ達の音楽が頭の上から爪先まで駆け抜けていく。 それを追って、酒場全体の喧騒が彼女を取り巻いた。 目を閉じれば、まるで世界の中心にいるような気分だった。 「……シーテ先生は、他の『クロニクル』の内容もご存知なんですか?」 「ああ、一応全てに目を通す機会があったよ。何か今後の参考になりそうなことを 思い出して但し書きを作っておこう」 団長はようやく目の淵を拭いてから、グラスの水に口をつけた。 氷点の冷たさが、咽から胃へと落ちていき、頭をもう一度冷やしてくれた。 尋ねておかなくてはいけないことがあった。 「目のことは、何か載っていませんでしたか?」 「目?」 団長は、改めてワイズの周りに浮かぶそれに焦点を合わせた。 「『女神の力によって何かが見えるようになった』ということはありませんでしたか?」 「記憶に無いな」 団長は女神の言った言葉を思い出した。 『私も長く人間を見てきました。あなたの言い分もわかります』 (……長く……) どれだけの時間を、あの女神は過ごしてきたのだろう。 団長はもう一口グラスに口をつけてから、女神と会った時のことを詳しく話し始めた。 前の話 次の話 |