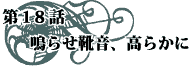
塔と塔をつなぐ渡り廊下は網の目のように張り巡らされていた。 その内のひとつの手すりに、少年はもたれ掛かって南西の方を見ていた。 北の薄い日差しが、彼の伸び放題の髪を日干しにする。 『……それでね、そいつらは流星騎士団って名乗っているの』 彼の耳元だけに、遠い地にいる女性の声が届いた。 「きしだんはどこにいったの?」 彼は宙に向かって言った。 『西よ。そうね。そろそろバルセールに着くころじゃないかしら?』 彼は頭の中の引出しから、完璧に叩き込まれた大陸の地図を取り出した。 バルセール。ウォルタランドからバルサ地方への入り口の役目を果す街だ。 北方のフェルミナとの境界でもある。 「歩いていったの?めんどうだね」 『でも、自由に外に行けるなんて羨ましいわ。わたしはヴァレイからそ』 急に声が途絶えた。 誰かに見つかりそうになったのだろうか。 大陸を股にかけた内緒話は終わりを迎えた。 彼はつまらなさそうに手すりに顎を乗せた。 (そとに行けることが、うらやましいこと) 覚えておいた方が良い気がして、頭の中で何度か反芻した。 そんな時、下の階層の渡り廊下を男子学生の集団が通った。 年のころは彼と変わらない。皆、黒いローブとタイ、そしてメダルの無い帽子を被っていた。 その内の一人が、何気に上を向いた。 目が合った。 逸らす必要もないので、彼らはしばらくそのまま視線を交わした。 他の者もそれに気づいて、全員が上を見上げた。 「あっ!あいつ、ヨーウィじゃん。相変わらず気持ち悪いな。こっち見るなよ」 「彼がヨーウィ?あの、最年少の伝書魔法使いの?」 最初に彼を発見した学生が尋ねた。 「へぇ……初めて会ったよ」 「そりゃそうだ。あいつは教授たちのお気に入りだから、授業に出なくてもいいんだからね。 僕たちとは会わないさ」 「いいよな〜、あのメダルがあれば一人前の証だもんな」 「あいつのどこが一人前なんだよ!ご飯の食べ方は汚いし、字も書けないし、風乗りすら できないんだよ?伝書以外取り得が無いグズだぜ?!」 「知ってるか?ヨーウィってのは本名じゃないんだって。伝書魔法使いたちは 本名を隠しておかないとだめなんだってさ」 「でもさ、すごいよね。大陸のどことでも話すことができるんだろ?……いいなぁ!」 「なんだリム。ヴァレイのお母さんとお話したいんだな?ははうえ様〜お元気で〜す〜か〜♪」 リムと呼ばれた少年は口を一の字に引いて、隣の少年の髪を引っ張った。 やったな! とじゃれ合いながら、集団は廊下を走り去った。 聴力のいいヨーウィには、そのやり取りは漏らさず聞こえていた。 顔を少し左に向け、遠くを見つめた。レヴァス高地の山々がうっすらと青く見える。 そのはるかはるか向こうにある大陸に向けて語りかけた。 「リム、いま、はなせそう?」 しばらく耳を済ませて待ったが、返事は返ってこなかった。 目を閉じて、手すりに頭を預けた。石の冷たい温度がひやりと伝わる。 『……ヨーウィか?構わんぞ』 しわがれた低い声が鼓膜に滑り込んできた。 ヨーウィは顔を上げて、平たい空を眺めた。 「ありがと。ねぇ、リムは字は書ける?」 『書ける。なんじゃ、お主は字を習ってないのか?ウェローの頭でっかちどもはお主に何を教えておる』 「読むのは習ったよ。ねぇ、字は書けたほうがいいの?」 『声と文字は違う。声はこうして一瞬で立ち消えてしまうもの。しかし、字は後に何千年も残すことが できる。そうして、後世に思いを伝えていくものだ』 「のこす……」 『そうじゃ。今のワシがあるのも、お主があるのも、先人が残してくれた様々な思いから。 そしてワシらがまた次の世代へ伝える。これこそが人の営みじゃ』 「たいせつな、ことなんだね」 でも、今まで教授はそんなことを教えてはくれなかった。 文字を学びたいと言ったら、彼らは教えてくれるだろうか? 「さっきまで、ヴァレイのロッシとはなしてたんだ」 『何か有益なことを言っていたか?』 「ほろびの予言のきしだんが、バルセールについたって」 『ああ、あの気の毒な生贄たちか。せめて無事を祈っておこう』 「ロッシはそいつらのことを、うらやましいって言ってたよ」 『あやつは、まだ若い娘じゃからな。外に憧れておるんじゃろう』 「リムは、どう?うらやましいって思う?ヴィムから出たいって思ったことはある?」 『ワシは比較的自由に動けるからな。若いころは騎兵隊に所属しておった。その時に アクラリンドの隅々まで行ったものだ。聞きたいか?』 「ききたい」 『よし。今から三十年ほど前にじゃな……』 ヨーウィは、姿を知らない年の離れた友人の武勇伝に耳を傾けた。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 「ああ、もう、ダメ……」 フェルフェッタはベッドに倒れ込んだ。隣にあるベッドにホノカがゆっくりと腰をかけた。 形のいい脚を組む。ハーフブーツの汚れを見るために、両足を左右に傾けて視認した。 「フェル、靴を脱ぎなさいよ。話はそれからでしょ?」 「ううう……怖くて脱げない……」 「ンフフ、脱がせてあげよっか?」 「……いい。自分でやるわさ」 フェルフェッタは生気の抜けた顔で、横たわったまま丸まる形で、足を手に近づけた。 そーっと足の裏と靴底を離す。 「〜〜〜〜〜!!!!」 痛みで涙がでてきた。歯を食いしばって一気に引き剥がした。これでまだ右足だけだ。 左足にも同じ苦痛を与えなくてはいけない。 「水を貰ってくるから、それまでに足を出しときなさいね」 ホノカはそう言い残して部屋を出て行ってしまった。 王都を経ってから約60日、流星騎士団はここバルセールの街までやって来た。 この街より西は旅人の森が大半を占めるバルサ地方。北は山岳都市フェルミナ領だ。 ここまでの道のりは、大きく言えば何事も無かった。 ヴァレイより出て宗教都市グラツィアを経由し、このバルセールまでは、主要な交易路である。 街道もしっかり整備されており、宿場町もきっちり点在していた。 生真面目な団長と魔術師、それにペースメーカーのお堅い騎士のおかげで、 寸分狂いの無い日程で旅は進んでいた。 フェルフェッタの足の傷のことも、なんでもお見通しな師匠の計算どおりだった。 最初に靴擦れを起こしたのは、グリムグラムであった。 「痛いよぅ。足の裏を鉄板で焼かれてるみたいだぁ!!」 大の男がお構いなしに涙を流しながら訴えた。 妙に甲高い彼の声と、雨季の高温多湿と相まって、団員たちはわざとその嘆きを 無視していた。もちろん、最初に靴擦れができかけた時は何かと気を使い、 治療や負担の軽減に努めたものだが、彼のために歩みを止めるわけにも行かず、 毎日毎日こうも嘆きつづけられると、さすがに何も言いたくなくなっていた。 「エル団長。東から雨が来ます」 アディがしんがりを歩く彼女の隣まで遅れて合わせた。 「とうとう前線に追いつかれたね。皆、止まって。雨の準備をして下さい」 「やれやれ。僕としては、この厚さだから雨が降ってくれた方がいいや」 「やーね!服も荷物も濡れちゃうじゃない!んも〜」 エルヴァールの意見にホノカが反対を出した。 それぞれが荷物を今一度確認し、着衣を直し雨に備えた。 「ほれ、あんちゃん。泣いてても治らんだろ?痛み止めやるから我慢しろよ」 座り込んだグリムグラムに、シュウガは懐から出した紙包みを手渡した。 ちゃっかり代金はいただいている。 再び歩き始めた彼らの頭上に、灰色の雲が東から手をかざした。 最初はゆっくりと、そして突然急激に太陽を隠し、代わりに鉄槌のような 雨が浴びせられた。 「キャー!何よこれーー!!」 誰かの悲鳴が上がった。団長は空を見上げた。そのすきに、首と服の隙間から 冷たい水が胸に浸入してきた。分厚い雲が東から押し寄せている。 西の方は辛うじてまだ明るい。その明るい方に向かっているだけ、気が楽だった。 髪に止まっていたフィニーを外套の下に避難させた。 前方に頭からすっぽりと外套を被った誰かが立ち止まっていた。 最後尾を努める団長はすぐにその人に追いつく。立ち止まり覗き込んだ。 「ん?ああ、ごめんごめん。靴を脱いでたんだ」 エクレスだった。黒のロングブーツを両足とも脱ぎ、背負った荷物の上に押し込んだ。 「いやさ、実は私も靴擦れができかけてたんだよ。あの子と違ってくるぶしだったから まだ何とかなってたんだけどね。雨で道が冷えてよかったよ。裸足の方が気持ちいい」 「破傷風に気をつけてくださいね」 「ああ、そうだね。……ねぇ、靴って難しいね。ちょっとの間に履いてるだけなら、 サイズが合えば歩いてられるんだよ。でも、本当にぴったり合ってないと、 長い時間付き合うと、こうして裏切られることもある。でも、選ぶ時なんて一瞬でしょ? 自分が気に入った形で選ぶ。でも、ずっと後にならないと、自分と合うか合わないかは 分からないんだよ」 「靴に限りませんよ。例えば剣だとか、弓でもそうです。馬もそうですよ。 見た目がどんなに良くても、どんなに優秀な血統でも、合う合わないは騎手と騎馬同士の 相性なんです」 「ハハッ!そこで馬を出すかね?さっすが騎士。そこは普通は男を出すもんでしょ?」 「はぁ」 「どうなの、エルツー。あんたはエルワンのことが好きなの?」 「……好きと嫌いで分けるなら、もちろん好きですが」 「あら模範解答。まっ、あんたは今はそれどころじゃないもんね」 「そうですよ」 雨の音で二人の会話は外には聞こえない。集団の先頭ではティモアが黙って 歩くペースを計っていた。イガーナが彼に並んだ。 「ティモアさん、ティモアさん。この雨は皆さんを分断してしまいます。 もう少しゆっくりの方が良いと思います」 「…………そうだな」 ティモアは後ろを振り返って呟いた。しんがりの団長が視界に入らない。 「大丈夫、まだ皆さんはぐれていません」 イガーナは耳を済ませて音を聞き分けた。 「……旅慣れているのだな」 「ハイ。アディと二人で二年間旅をしてきました。何度か隊商といっしょに旅したこともあります」 「出身はどこなのだ?」 「アクラリンドの西の端、オディサリクです。ウォルタ海の隣にあります。 雨はよく降っていました。だから、私は雨が好きです。ティモアさんは?」 ティモアは何を問い掛けられたのか分からなかった。仕方がないので、全てに答えることにした。 「……自分は、ジグー出身だ。……ヴァレイの北にある宗教都市だ。そこは一年の大半は雨が 降っているので、自分は……」 「大半ですか?それはすごいですね。オディサリクでは一日に一回降るのです。朝は晴れていて、 午後になると少し曇ってきます。鳥が低く飛んで巣に戻り、そうしたら雨が降り出します。 空は明るいんです。すぐに止みます。そうしたらウォルタ海に沈む夕日が見えます。 雨のおかげで、虹がかかります。とっても綺麗ですよ」 「……貴殿の故郷の雨は、美しいのだな。ジグーの雨は、人を神妙にさせる。毎日降るものだから、 街は軒下で発展した。商店街も神殿も学校も、すべて地下にある」 「地下?地面の下ですか?地面の下に人が住んでいるんですか……すごいですね!いつか、 行って見たいです」 「……騎士団にいれば、いつか行く機会があるだろう」 「そうですね!楽しみです」 「………………雨は」 「はい?」 「……自分も、雨は好きだ。心が落ち着く」 「……!そうですか!好きなのおんなじですね!」 二人の話し声は聞こえてこないが、会話が弾んでいることはイガーナの背から見て取れた。 上手いことやりやがって、とヴァーグナルは思っていた。 自分の隣を歩いているのは、シュウガ・ジンという下町の商人だった。 (……雨のベールの中、女性とひそひそ話をするという絶好のロマンティックな機会なのに、 なんで隣は男なんだ……) ヴァーグナルは顔に張り付いた前髪を剥がしてうなだれた。 シュウガは羽織を脱いで腰に巻いていた。上半身裸で雨に打たれて、気持ちよさそうだった。 結っていた髪に溜まった雨水をギュッと絞りながら、騎士に声をかけた。 「隣が男でご不満かい?カンタ卿」 「もちろんだ」 心を読まれた問いに、ヴァーグナルは即答した。 「おう、俺もだ。せっかくこの団には可愛い子がそろってるのに、なぁ?」 「ならば、前に行くか後ろに行くかでずれてくれないか?」 「そうしたいんだけどね。このペースを崩せないんだよ。俺の右足さんと左足さんが、 これ以上速くは歩けないし、遅く歩くともう止まる!ってワガママ言ってんだよ」 「……私の右足と左足も、同じことを言っている」 毎日歩きどおしで、両足に疲労が蓄積されていた。自分の最良のペースを維持しなければ、 歩みが止まってしまう。 「で、さ、カンタ卿。あんたは誰を狙ってるんだい?」 「私は全ての女性を等しく愛している」 「おぉ〜〜さっすが、リーベリッター・フォン・カンタ。恐れ入るぜ」 「ジン殿はどうなのだ?意中の女性がいるからついて来たのか?」 グリムグラムのことを思い浮かべながら問うた。 「いんや。俺は商売と取引でついて来たのさ。嫁探しじゃねぇ。でもま、嫁さんを貰うことを 考えてもいい頃合ではあるな」 「おいくつだ?」 「俺か?今年で十と九だ。そうだな〜ホノカは顔はいいけど、性格がキッツいなぁ。 ああいうつんけんしてるのが、泣いたりすると可愛いところもあるけどな。フェルフェッタは 知らないから未知数だな。知的な魔女ってのはいい。知らない振りをして色々教えてもらいてぇ」 「イガーナ嬢は異国の魅力がある。何よりあの話し方が愛らしいな。彼女はこちらから色々と 教えて差し上げたい。エクレスは……身体だな。見ているだけで目の保養になる。愛想もいいし 話しやすい。ただ、あれは営業用のスタイルであるし、大体彼女は」 「なんだかんだとお手つきだからな。人のものに手は出せん。で、我等がエレオノーレ団長だが…… あの子はなぁ……なんというか……こう……」 「なんだ。はっきり言えよ」 ヴァーグナルとシュウガは顔を付き合わせた。 「上司の騎士で年下。そういう女の子に命令されて動くのって、男として悪くないんじゃねぇ?」 シュウガは首をかしげてニヤリと笑った。ヴァーグナルの耳には、聞こえるはずの無い 鐘の音が聞こえた。 「……同士よ!ジン殿、仲良くしよう!!」 「おうよ!シュウでいいぜ、兄弟!」 二人はがっしりと肩を組んだ。そんなむさ苦しい二人を前方に見据えながら、 エルヴァールとフェルフェッタは並んで歩いていた。 「……ね、エル先輩。先輩はエルの眼のことを知っているって聞いたわさ」 「……君も知っているのかい。……女神のことは?」 フェルフェッタは黙って頷いた。エルヴァールはそうかい、と短く呟いた。 「それを、他の皆にあの子が言わないのが気になって。すごく大事なことだし、 隠すと返って言い出しづらいんじゃないかと思うんだわさ」 「気持ちは分かるよ。でも、エルの気持ちも分かる。多分、話して拒絶されるのが 怖いんだよ。簡単に信じて貰える話じゃないし、重たいものを相手に背負わせる ことになるから、気を遣ってるんだと思う」 「……損な子」 「だから、支えになってあげたい」 「そうね」 二人の斜め前を歩いていたワイズは、このやり取りを聞いて、過保護、と肩をすくめた。 最後尾のやや手前には、太っちょ戦士と冒険者、そして王都育ちの魔女が固まっていた。 ホノカの前ではさすがに愚痴は言わない。精一杯真面目な顔つきでグリムグラムは痛みに 耐えていた。そんな彼をホノカは横目で頭の上からつま先まで眺めていた。 旅に持ち出した帽子は撥水効果のあるレグール皮だ。長い髪の毛が水を吸うのだけが いただけなかったが、暑い季節が幸いして、ずぶ濡れになることはさほど苦痛ではなかった。 心優しいアディはグリムグラムの様子を心配して、彼の傍についていた。 ホノカは合わせてアディの全身も遠慮なくじろじろ眺めた。 アディはイガーナと同民族でアクラリンドのオディサリク出身だ。二人は髪の色も目の色も 似ていたし、褐色の肌も同じであった。身に付けている衣服の文様や織り、バングルも同じだ。 北出身の団長とは、世界地図で考えれば対角線の端と端の民族同士だ。 共に並んだ姿はコラージュのようで、いびつだけれど、不思議な調和を保っていた。 ホノカは混血のウォルタ人。彼らともまた違う色の肌と瞳を持っている。 (でもま、人間同士なんだからおんなじよね) 濡れぼそった髪をひとつにくくってから、二人の男に近づいた。 「トランタン君。あなた、がに股だからダメなのよ。いい?歩き方が美しいってことは、 正しい姿勢で歩いてるってことなの。正しい姿勢で歩けば疲れないし、靴擦れもしないわ。 アディも。トランタン君を気遣うのはいいけれど、それで猫背になるのはよくないわ」 「え……、俺、ガニ股なの?」 グリムグラムは間の抜けた声を出したが、ホノカから話し掛けてもらって笑顔を浮かべた。 「そうよ。つま先の向きが開いてる。もうちょっと足の内側に体重をかけて。そうそう。 どうせ靴擦れが出来たのってかかとの外側でしょ?」 「うわぁ、すごい!ホノカちゃん、当たりだよ!」 「……ホノカは、優しいね」 アディは背をまっすぐにしながら、ホノカに微笑みかけた。 ホノカは片眉を上げてから、彼にウィンクを返し、美しい姿勢の美しい歩行を保った。 それからほどなくして、雨のせいで皮がふやけた戦士の靴は、彼の大きな足に ミラクルフィットする型に馴染み、ホノカの歩行矯正もあり、靴擦れは驚くほど解消された。 それと入れ替わる形で、固くコーティングされた革靴のフェルフェッタに痛みが訪れた。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 「……はぁ。脱げた……」 破れた皮と靴の中底とを引き離す悲劇をどうにか乗り越えたが、気力の大半を奪われた。 雨季や湿地帯に備えた靴を選んだのが仇となった。この街で新しいものを手に入れたほうが いいのかもしれない。しかし、今はどんな靴にでも、足を入れるのが嫌だった。 ノックされたので、やる気のない返事をした。 ドアを開けてヴァーグナルが顔を覗かせた。手には桶と布を持っている。 「大丈夫か?フェル。ホノカに言われて薬湯と巻く布を持ってきたのだが」 「ありがと……」 そう言ったヴァーグナルは敷居の向こうに立ったままだった。 ああ、そうか。 「どうぞ、入りなさいな」 「失礼する」 ヴァーグナルは頭を下げてから敷居をまたいだ。金色の綺麗な髪がサラリと顔にかかった。 彼女が横たわる寝台の脇に桶を置き、跪いて布を浸した。 「脚を触る許可もいただけるかな?」 「やってくれるの?」 「自分ではやりにくいのだろう?」 「うん」 「早く治さないと、足の形が悪くなるぞ。そうなったら大いなる世界の損失だ」 「大げさ。でも、お願いするわさ」 「御意〜」 ヴァーグナルは最大限に気を配って、フェルフェッタの足を持ち上げて布で優しく拭き始めた。 なんとなく、ヴァーグナルが女性に受ける理由が分かった。 整った顔と過剰な誉め文句。それをなんとなく、笑いながら受け入れてしまえるような男なのだ。 前の話 次の話 |