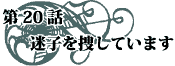
「まさか、はぐれるとはね……」 「こういう場合、どっちか迷子?リーダーはあっち。人数が多いのはこっち」 「どっちも迷子」 「やっぱり?参ったなぁ」 「人の通った残りを探しましょう。そうすれば、人に会うかもです」 イガーナの提案に、地図を団長に預けたままの一同は賛成した。 この広大な旅人の森で、彼らは確実に迷い人となった。 幸い、食糧は各自が己の分を携帯しており、予備はエルヴァールとグリムグラムが 分けて持っていた。 木々の天蓋がいまだに太陽を隠していた。正確な方角を読むことができなかった。 旅慣れている東の二人が、足元の草や苔を見分けながら、道を探っていった。 フェルフェッタは分離してしまった四人の面子を考えると気が気で無かった。 同じ気持ちではないだろうかと、エルヴァ―ルを盗み見た。 彼も神妙な面持ちで茂みを掻き分けていた。 「あの子たちが心配だね」 エクレスが彼の後ろを歩きながら話しかけた。声のトーンが重かった。 「ああ……。でも、あの子は騎士だ。他にもうひとり、騎士もついている。 なんとかしてるはずだ」 エクレスは意外な答えに驚いた。 「エル、あんた結構冷静なんだね。もっとこう、取り乱すかと思った」 「今すぐ大声で呼んで探したい。そんなことをしたら敵に見つかる。待つのは時間が惜しいし 確実な方法じゃない。なら、どうする?当初の目的地で合流するのが一番だ」 エルヴァールは苛立ちを隠せず早口に言った。 「そりゃまぁ、そうなんだけど……」 あんた、あの子のことが好きなんじゃないの?だからもっと心配じゃないの? とは、さすがにこんな状況で言えるわけも無かった。 エルヴァールの苛立ちの原因は他にもあった。 先ほどの戦闘で、エレオノーレが自分をかばって戦ったことだ。 鮮やかな剣さばきとその気迫が、彼女を際立たせていた。 戦う姿を目の当たりにして、改めて悟ったのだ。 彼女は騎士団の団長なのだと。 動きに合わせて舞う金の髪の束が美しかった。 それに比べて自分ときたら。 どん臭い動きで、ワイズの支持でようやく一鏑を放つのがやっとだった。 彼女を支え、守ってあげたいと入団したはずなのに、反対に守られてこの様だった。 そして、分裂してしまった一団に、自分ではなくティモアがいてくれたことに安堵する 自分がいた。 彼ならエレオノーレを守りきれるだろう。 そのことが、とにかく悔しかった。 アディとイガーナは注意深く人の通った痕跡と、獣道を探っていた。 ヴァーグナルは周囲に気を配りながら、獲物を追う肉食獣のような眼のアディに声をかけた。 「アディ。そんなに気を張り詰めるな。お前の気配が返って気取られる。 ……やつら、何者だろう。相当な手練だった。お前の戦い振りにも、正直驚かされたぞ」 後半は、他の者に聞かれないように小声だった。 アディはヴァーグナルの進言に、少し緊張を解いた。 「前にも、あんなやつらと会ったことがある。メゾン湿原。まったく音がなかった。 いきなり目の前にいた。逃げられなかった。戦った」 アディは頭の飾り布を目深く直した。瞳を覆う水分の膜が、木漏れ日を反射して光っていた。 「殺した。できなかったら、ボクもイガーナも、一緒のキャラバンも死んだ。 ふつうの盗賊じゃなかった。声は聞こえなかった」 アディから再び強い気配が漏れ出た。ヴァーグナルの右手は、本人も意識せずに 剣の柄にかかっていた。 「理由にならない。ボクは人を殺した。ひとりじゃない。殺した」 冒険者は騎士を見た。恐ろしいほどに無表情だった。 普段の彼を知っているからこそ、正視するのが辛かった。 「だから、ボクはもう歌は歌わない。歌えない。……イガーナは自分の歌と踊りを探している。 ボクは、できない。歌えない」 ヴィーナス・アンド・ブレイブスのどの場面でも、アディはハミングすら披露したことが無い。 旋律を伝えるのは、手持ちの楽器か口笛でだった。 「ならば、なぜ騎士団に入り、旅を続けるのだ」 しばらく沈黙が支配した。アディは無表情のまま、視線を足元に落とした。 「……ボクたちは旅をする民。旅が無くなったら、することが分からない。 ボクは冒険者。歌を歌えなかったら、することが分からない。 何も無い。でも、もし、また歌うことができるようになったら……」 彼は一度手でまぶたを撫でた。 「歌いたいことがたくさんある。歌に乗せたいことがたくさんある。イガーナのこと、 ヴァーグナルのこと、ホノカのこと、ヴァレイのこと、騎士団のこと。 ボクたちは歌で伝える民。だから、また歌えるようになりたい。 悪い理由。それでも、旅をしていたい」 ヴァーグナルは右手を固いものからそっと離した。拳を作って、アディの肩を軽く叩いた。 それから開いて、じっと手の平を見た。 彼は人を殺したことは無い。王都や周辺の集落に出た賊の討伐隊として、実戦に赴いたことは 何度かあった。相手の命を奪う真似はしなかった。 もし、自分がこの手で人間の命を奪う日が来たら (……ご婦人の手を取ることができなくなりそうだ) イガーナが発見した人の通り道らしきものを一同は辿り始めた。 ワイズは辛うじて差し込む陽光から、方角の一致を確認した。 ローブの左袖に隠し持っていた、小さなカラクリ虫をそっと顔の前に持ってきた。 どこも壊れてはいないようだ。逃亡劇の混乱の最中、彼の元に吹っ飛んできたのだ。 眼を覗き込むと、おぼろげな大陸全土の左下に、文字らしきものが瞬いていた。 キングリオンの位置だ。それよし少し上に、人型をしたものが蠢いていた。 (こっちが僕らの位置か。いや、彼女の位置か) 「おい、拡大はできないのか?」 小さな虫に囁きかけた。フィニーは息をするがごとく羽根を閉じたり開いたり するだけだった。 (だめか。正確な位置が分かれば、伝書を飛ばすことができるんだけど) もう一度フィニーの眼を確認してから、ポケットにそぅっとしまった。 (しかし、こいつはどういう仕組みなんだ?……分解したら、……ダメだろうな。 元に戻す自信がまったく無い) 日が森の陰に落ちてしまい、辺りは暗く静かになっていった。時折、蛍が行き交い、夜に開く キノコの燐光に蛾が誘惑されていた。 空はまだ薄明るいが、方角を完全に見失う恐れがあるので、一行はキャンプを張ることにした。 とは言ってもたったの四人なので、大きな倒木の陰に寝床を確保する程度の簡素なものだ。 雨季の後の深い森には乾いた木が少ない。火を起こせば煙が多く発生してしまい、 敵に見つかる可能性があるので、焚き火はしないことにした。 携帯していた干し肉のドライフルーツ挟みを頬張り、水筒から水を飲んだ。 一同はほとんど黙ったままだった。 気分がマイナスに落ちている生真面目団長、普段から無口な騎士、戦闘を目の当たりにして縮み上がった戦士。 ホノカはうんざりしていた。 せめてもと思い、苔の少ない地面を選んで杖の先で簡単な魔法陣を描いた。 短く指で印を切って、その中に熱の無い光の玉を出した。 魔法陣がホノカの代わりにそれを維持してくれる。 「ありがとうございます、セキグチ先輩」 光に照らされたせいか、少し明るい表情になった団長が礼を述べた。 「暗いとどんどん気持ちが暗くなるでしょ?あたし、辛気臭いの嫌いなの」 団長はなにも応えずに光をじっと見ているだけだった。 「あっちが心配?あたしはむしろ、こっちの方が心配だわ。人数少ないし」 「向こうにはシーテ先生とカンタ卿、それにエル……ヴァールさんがいます。 旅慣れたアクラリンドの二人もいます。おそらく、次の目的地であった集落を 目指しているでしょう。この人数では、有効な陣形を取ることができません。 賊に襲われるとひとたまりもありません。一刻も早く、私たちも同じくして合流します」 「……賛成」 ティモアの声が響いた。周囲の静寂のせいで、より低く聞こえた。 「……で、でもぉ、もし、また、あいつらに襲われたらぁ……?」 グリムグラムがか細い声を絞り出した。 団長は光を見たまま、対策を考え始めた。 グリムグラムは膝を抱えたまますがるように団長を見つめた。 (事態は悪い場合を想定しておいたほうがよい。この中で戦えるのは私とジェイナード卿。 トランタン殿は、悪いが戦力外。ホノカ先輩は……光の魔法が得意のようだから、 目くらましをしてもらう、か。その隙に私が二人、ジェイナード卿は……) 頭の中であの一団と自分たちを戦わせてみた。 脳内の戦場で、彼女は相手を一撃では屠れなかった。 人を殺すことをためらった。その隙に一撃を喰らい、尻餅をついた。 敵の三度目の攻撃で、エレオノーレはあっさりと命を落とした。 (……そして、あの、黒い者。あいつの力は計り知れない気がする。 ダメだ。どうやっても、敵に遭遇したら全滅する!!) 団長は眼を閉じた。本人は顔に出していないつもりだったが、眉間に皺がよっていた。 面倒くさい子。 こういう時こそ、前向きに行きましょ、とホノカは声をかけようとした。 「……エヴァンス団長」 ティモアに先を越された。団長は目を開け、彼を見た。 ホノカもグリムグラムも見た。角張った彼の顔を白い光が象っていた。 「合流する前に先刻の輩と遭遇したら、自分が囮になる……。その隙に、そこの 二人を連れて逃げられよ」 ティモアが視線で二人を指した。目が合ったそれぞれは身体が硬直した。 「それは、できません」 団長はティモアに強めに言った。 「……これが最も現実的な策だ……。お忘れか?自分の代わりは居ても、貴卿の代わりは いないのだ。御身のことを一番に考えられよ」 「それは、絶対に、しません!」 団長は両手を地面に打ちつけた。彼女の反応にホノカは驚いた。 「私は、私の命と皆の命を量りにかけるような真似は、絶対にいたしません!!」 「……自分の命とアクラリンド全土の命ならば、量りにかけるまでもない!」 「そもそも、量りにかけるものではありません!!!」 「では、どうするつもりなのだ?!目の前の現実を見ろ!!自分はメイホーク団長から 貴卿の安全を守るために遣わされたのだ!!そのためになら、この命を惜しむような 愚かな騎士ではない!!!」 「死による犠牲を前提とした入団だったのなら、……要りません!!そんな方は結構です!! 除名しますから、出て行ってください!!!」 「ちょっと……」「や、やめてよぅ……!」 二人に騎士は身を乗り出して激しい口論を交わしていた。 ホノカと半べそのグリムグラムは仲裁に入ろうとした。 しかし、普段が普段な彼らなので、この加熱ぶりにどう対処したらいいか分からなかった。 つかみ合いにならないのは、男女だからか、互いに騎士どうしだからか。 代わりにどんどん背筋がよくなる二人が、口論の激しさと相容れなくて、 見ている側は返って怖かった。 「そんな甘い考えでは、何も守れない!!」 「わかっています!それでも、貴卿やメイホーク団長の意向に賛同はできません!!」 「だから、それに代わる策を言えと先ほどから言っているのだ!!理想論では 何も進まない!!」 「……理想を抱いて、なにがいけないのですかっ?!!」 団長の左目から涙がひとつ、ポロリと落ちた。 それを見てティモアはハッと身を引いた。同時に団長も身を引いた。 これ以上零さないように目を見開き、口を一文字にひいて歯を食いしばった。 顎に力を入れすぎて頭が小刻みに震えるのを必死で隠した。 「お、俺が言ったことで、ごめんなさい。大丈夫だよぅ。あいつら、追ってこなかったって ティモアさんが言ってたし。お、俺の考えすぎだったんだよ。だから、 喧嘩はやめようよ……ね?」 グリムグラムは二人を交互に見ながら泣き声で嘆願した。 騎士二人は相手を食い入るように見ているだけだった。 肩で呼吸を整えてから、先に口を開いたのは団長だった。 「……策があっても無くても、道があっても無くても、先に進みます。進まなくてはいけません。 それが正しい筋ではなかったとしても、私は、私の信じたやり方で進みたいんです。 貴卿から見れば、勝手な言い分でしょう。でも、私のやり方を信じていただきたいのです」 「…………先ほどの暴言の数々を……お詫びする」 ティモアは姿勢をただし、肩膝をついて頭を垂れた。 「私こそ、非礼な発言の数々を、お許しください……。面を上げてください。そのように していただく謂れはありません」 「いえ、自分は団員。王都の門の誓いも忘れて、団長に反するなど騎士にあるまじきこと」 「貴卿が私に貴重な意見を述べてくださったことに感謝いたします。私が私を信じるように、 皆も皆、それぞれに信じるものがあるんですね。それを、恥ずかしながら失念していました」 団長も頭を下げた。二人とも地面に向かって喋っていた。 「それを気づかせてくださり、ありがとうございます。 私は、いつでも迷っています。自分の信じた道も、迷路のようで手探りです。 そんな時に、私とは違う誰かの、貴卿であったりセキグチ先輩であったりトランタン殿であったりの、 言動が支えてくれます。……除名などと軽く口にして、申し訳ありませんでした」 「……自分は、まだ、この騎士団に居ても……よろしいのか?」 「私からお願いします。共に歩み、迷い、戦ってください」 ティモアは顔を上げた。目の前に歪んだ笑顔の団長の顔があった。 視線を合わせることができなかったので、再び頭を一度下げてから、腰を上げて席を変えた。 喧嘩をしても仲直りをしても、やたらに姿勢のいい騎士二人を、ちょっと可笑しいな、 と思う余裕がグリムグラムに生まれた。彼自身もいつの間にかピンと伸びていた背を丸め、 握っていた拳を緩めた。暑さのせいだけではない汗でビッショリだった。 ホノカも息を大きく吐いて、背後の倒木にもたれかかった。 エレオノーレに対する見方が、ほんの少し変わった。 周りに適当におだてられて団長をやっているのかと勘ぐっていた。 くそ真面目で陰気という印象は変わらないが、思っていたより、マトモな子なのだ。 そして、ティモアの新たな側面を見て、なんだか胸が落ち着かなかった。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- (……眠れない……) (……不安で不安でたまらない……) (……だけど、そんなそぶりを見せられない……) (……しっかりしているように見せないと、不安がらせてしまうじゃないか……) ごろりと寝返りを打った。寝付けないのなら、自分が今の時間の見張りに立てばよかった。 いいや、皆で順番を決めたのだ。それに無理を通すことなんてできない。 ため息をついた。 低木の枝で作った傘で煙を薄めることができたので、一行は火を起こして簡単に温かい物を 摂ることができた。暑い夏場とはいえ、温かいものが胃に入るだけでほっとする。 アディの今までの旅の知恵と、エルヴァールの調理の機転の連携技だった。 アディはそのまま深夜の火の番を買って出た。獣を寄せ付けないためだ。 フェルフェッタが相棒となった。 寝静まった中で、枝がはぜる小さな音と二人のひそひそ声だけが響き渡る。 「だから、故郷を出たの?ふぅん……。面白いわさ」 「フェルはどうしてヴァレイに行った?故郷はウォルタランドだ聞いた」 「勉強したかったから。ほんとはね、ウェローに行きたかったの。魔法学園ね。 でもうち、お金があんまり無くて。だから、奨学金をゲットしてアカデミーに 通ったんのよさ」 「えらいな。魔法使いの学校は、アクラリンドにもあるよ。モルサガルサの右街。 あの街は変わってる。街がはんぶんこ。でも、けんかしてるわけじゃない。 大昔からの伝統」 「アディの話を聞いてるだけで、アクラリンドに行っているみたい!いつか、ウェローも モルサガルサにも行ってみせるわ!」 「フェルは、……ど?騎士団で旅するようになって、楽しい?」 「そうね、うん。さっきみたいな戦いは怖かったし、この旅は戦うための旅なんだから、 ああいうこともこれからも何度もあると思う。脚もひどい目に遭うし、今もはぐれちゃって 不安でだけれど、そうさね……楽しいわ。一日一日が毎日違う。それに気づいたらね、 なんだかすごく楽しいの」 不謹慎かもしれないけど!と小さく足した。 「旅をする、特に長い旅をするの必要なものはたくさんある。お金、体力、決める速さ、 色々。でも、一番大切なのは、旅を楽しむ気持ちだと思う。それがあれば、どこにだって 行ける。ボクはそう思う」 「アディが言うと説得力あるわさ。あたいも、旅を楽しいと思う気持ちがある限り、 ちょっとくらい辛いことや怖いことがあっても、まだまだ続けたいなって思うさ」 アディが嬉しそうに肩を揺らして、口笛を吹き始めた。 皆を起こさないように、外敵に見つからないように、器用に小さく小さく吹いた。 音色は煙と共に空へと上っていった。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- (……) (…………) (……………………) (………………………………メイホーク団長…… ……………………貴卿に盾を預けた自分は、最早騎士とは呼べないのでしょうか……) (…………) (自分は、エヴァンス卿の意思をまったく無視していたのだ………… ……そんな自分が、エヴァンス卿を守ろうとするのは、傲慢でしょうか) (…………) (……しかし、かの人を守りたいというこの意思は、どのように言われても) (揺るがないものだ……) (……この迷いも、自分が未熟ゆえ……) (まだまだ、目指す騎士の高みは遠いのだ) (…………) ティモアは警戒のために浅めに眠っていた。 頭が正しく働いていないので、同じ言葉がぐるぐる回る。まるで催眠術だ。 ヴァーグナル・カンタ卿がそうであったように、ティモア・ジェイナードも この流星騎士団に所属するまでは、エレオノーレ・エヴァンス卿の人となりは 知らなかった。己の実直な性格を買われ、メイホーク団長から示唆があった時に、 自らこの境遇を望んだ。 大いなる目的のために進む者を守る任務に就ければ、相手は誰でもよかった。 それが、エヴァンス卿であっても無くても。 『流星騎士団の団長』であれば。 しかし、今は。 エルヴァール・ネルドは己と違う。 エレオノーレがエレオノーレであるから入団した。 アカデミーで一通りは修めたとはいえ、戦いの素人である調理人が、だ。 他の団員たちも、あの二人が共にいることを当然のように認めていた。 あのように、心まで添いたいとまでは求めない。 彼女を守ることが、ひいてはアクラルを守ることにつながる、ただそれだけだ。 それだけだったはずなのに。 (…………この迷い、何ゆえだろうか…………) -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- ヴィムの筆頭伝書魔法使い、通称リムは、他の都市の伝書魔法使いとは違い、 自由に出歩くことができた。アクラリンドの大らかな気風が、彼の立場にも 影響しているのだろう。 若い頃は騎兵隊に所属し、各地を見て周り、引退後は過去に得た地理情報を活かし、 遠距離伝書魔法使いとなった。 彼には妻も子供もいなかった。 ひとりで気ままな余生を送っていたが、言葉を糧とする職業についているゆえ、 時々、意味などを考えなくても良い他愛の無い話をしたくなるときがあった。 今日もそんな気分だったので、東の工房攻防街にある旧友を訪ねた。 鍛冶を生業とするムジョス工房だ。 入り口の門の前で、ひとりの少女が看板をかけていた。 台の上に椅子を乗せ、さらに背伸びをして、ようやく一仕事を終えた。 注意深く降りる中、来訪者に気づいた。 「おはようございます、エナムリム様。お義父さんなら、今は裏手の井戸ですよ」 「おはよう、アミ。お邪魔するよ」 軽い巻き毛を後ろで高く結ったこの少女は旧友の養女だ。 彼も同様に妻も子もいない。代わりに、身寄りの無い子供を引き取っては、 親子とも師弟とも取れる関係で育てていた。 「久々に大物の仕事が入ったんです。アクラルの王様からの依頼なんですよ!」 そばかすの浮かんだ顔が輝くようにほころんだ。 「ほう……。あいつもいい歳じゃから、下手を打たないといいがな」 「お前よりは若いぞ」 当の本人が戸口からぬっと顔を出した。 「ひとつの差なぞ、関係ない。入れ歯の手入れは終わったか、総入れ歯」 エナムリムは虫歯ひとつ無い歯をわざと覗かせて言った。 「ふん、禄な物を食べてないから、お前さんの歯は虫歯菌にも哀れまれているんじゃ!」 唾を飛ばす勢いでムジョス・ビルダリクはまくし立てながら、炉の具合を点検し、ふいごに油を差し始めた。 少女は炉の上の鉄板に置いてあったポットを取り上げ、義父と来客のために 熱い紅茶を入れた。ムジョス博士は積まれている鉱石のひとつを手に取り、叩いては 音を確かめた。エナムリムは差し出されたカップを受け取り、舌を湿らせた。 「アクラル王からの依頼だと?また無駄にキラキラしい剣だの盾だのか? あの王は着飾った武具がお好きのようじゃからな。昔、おぬしが打ったフランベルグが ひどい有様のドレスを着せられたこともあったのう」 「あれは、私の子じゃ無い。刃は確かに私の子だが、外のお飾りを作ったやつの作品じゃ。 今度の依頼は、白銀のフルアーマー一式じゃと。それもとびっきりなものをとのご注文だ。 また意味の分からん飾りを彫られたらたまらんからな、飾りなぞ付け入る余地もないくらい、 美しいものを打ってやるつもりじゃわい」 腰を伸ばしてカッカッカと高笑いをした。 「そうですよ。お義父さんの武具は、飾りではなく本質です。道具とは用途の本質を 理解して使わなくては意味がありません」 少女が皮製の分厚いエプロンを着て、重い鉱物が詰まった袋を運んできた。 エナムリムは驚いて尋ねた。 「アミ、おぬしが手伝うのか?メルレーンはどうした?」 「あれ?エナムリム様はご存知無かったですか?メルレーン義姉さんは忙しくなった ウルザーク義兄さんの手伝いに住み込みで行ってしまったんですよ。 だから、今度からは私がお義父さんの手伝いをするんです」 「……おぬし、いくつだったかな?」 「九歳です。立派に鍛冶見習いになれる歳ですよ!」 少女は誇らしそうに笑ってから、己の仕事に戻ろうとした。 「もうひとつ、つまらぬことを聞くが……。アミは、読み書きはできるのか?」 少女は目をくりっと動かしてから、大げさに頬を膨らませた。 「もちろんですよぉ。ちゃ〜んと、書けますし、錬金術の本だって読めますよ!」 「そうか。失礼なことを聞いたな。立派な鍛冶になれるように、あのクソじじいの 最後の髪の毛まで毟り取る勢いで、業を盗みなさい」 誰がクソじじいだ、モーロクじじい!と主の声が工房の高い天井にこだました。 動かしている人間はたった二人だが、まるで全体が生き物のように活気付きだした 鍛冶場を眺めながら、遠い北の果てに住む少年のことを思った。 ウェローとの交信相手がヨーウィに代わってから三年が経とうとしていた。 都市間の伝書魔法使いたちはその担っている役割上、監視下に置かれていることが多い。 エナムリムは例外だ。自由に身近な人と接することのできない彼らは、 いつからか、顔の見えない彼ら同士で、こっそりと話をするという習慣ができていた。 これは、代々の遠距離伝書魔法使いだけしか知らない秘密だ。 異例な若さで就任したヨーウィは、初めて個人的に話をした時に、 あまりに何も知らなくて話にならなかった。 上から詰め込まれた正しい発音のアルセナ語と、病的に正確な地理情報しか 頭の中に無かった。自分の本名すら忘れていた。 話しかけても、彼自身が何を話し返せばよいのかを考えられなかったのだ。 彼とは反対に老成してから就任したエナムリムは、小さな同僚を不憫に思った。 我ながらお節介だと分かってはいたが、一方的に様々な事柄を話して聞かせた。 季節の移ろい、今日の食事内容、飢饉の情報、巷の流行ファッション、昔の甘酸っぱい思い出、 その日に遭遇した猫の数、読破した論文の批評、鍛冶屋を営む旧友の愚痴……。 三年間に重ねた言の葉は、深く深く積もり、ようやく土になれようとしていた。 ヨーウィは少しづつ変わった。自ら話しかけるようにもなり、自分の目に映るものを 自分の言葉で表現するようになった。 エナムリム・クーには子供も孫もいない。 このような感情を、顔すら知らない少年に抱いたことを、人は可笑しく思うのだろうか。 前の話 次の話 |