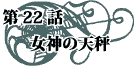
桟橋が遠ざかっていく。 潮騒に混じり、ウミネコの声がが縦横無尽にこだました。 マリスタを乗せた船は湾岸都市メゾネアから南へと出港した。 目的地は南アクラルのクロコ港。そこから内地の行程を踏み、水上都市スクーレまでの 護衛が、今回の任務だ。 マリスタとは初めて顔を合わせる傭兵ばかりだ。ウルバルドはいない。 己の武器を手に、甲板をゆっくりと歩いて周った。 速度を重視した細長い小型の帆船で、乗務員は船長を含めて23名、傭兵はマリスタを含めて7名。 二都市の友好関係にとって、非常に重要な役を担う積荷を運ぶと聞いて、 マリスタは志願した。 (しっかし、なぁんか、あんまり「友好」ってかんじのツラじゃないやつばっかりなんだよな) 海の男たちはいかつい顔をしている奴らばかりだが、一度海上に出れば、 海への愛と敬意に満ち、自然と陽気なオーラが出るものだ。 ましてや、今日のように雲ひとつ無い絶好の出航日和に恵まれたというのに、 どこか陰鬱なものが船に漂っていた。 後方に遠ざかる陸地に浮かぶメゾネアを見た。 三日前、メゾネア船長、つまり湾岸都市の長を勤めるヘンドリクセン・メイガンと 言葉を交わす機会があった。場末の酒場で安酒をちびりちびりとやっていたら、 かの人が共も連れずに一人で現れたのだ。 メゾネア船長は気さくな性格で、誰とでも対等に接し、話や訴えを聞いてくれるとは聞いていたが、 己もその恩恵をこうむる日が来るとは思ってもみなかった。 カウンター席に一人で座っていたマリスタの隣に、彼は自然な動作で座り、酒を注文した。 どうやら常連のようだ。 ここの酒場は言ってはなんだが「長」と名のつく職に就く者には全く相応しくない 安かろう悪かろうの品揃えだ。 船長はマリスタの飲んでいるものよりはほんの少しだけ値段の高い酒を、美味そうに飲んだ。 マリスタはそわそわと落ち着かなくなった。 他の客たちは船長には気づいていないのか、連れ同士で盛り上がっていた。 杯をテーブルと口に往復する速度が速くなった。 「君は、傭兵だね?……出身は、南アクラルだ。違うかな?」 彼から声を掛けてきた。マリスタはゆっくりと彼を見た。 強い意志を持つ薄い色の瞳と目が合った。 「……は。そうです。ウルカ峠にある村の出です。あ、あの、お目にかかれて光栄です、船長!」 「なんだ。私が誰かバレてたのか。それは、残念」 船長は頬杖をついて、杯をくゆらせた。マリスタは背筋を伸ばして向き直った。 「いいよいいよ、そんなにかしこまらないで。勤務時間が終われば、私はただのオッサンさ」 「そんな、ご謙遜を!」 「本当さ。私は勤務時間内に仕事を終わらせるのが好きなんだ。その他の時間は、 一メゾネア市民として過ごしている。今もそうだから、気にしないでくれ」 メゾネア船長はそう言ったもの、彼はいついかなる時にもメゾネアという街のことを 第一に考えて動いていることを、市民は知っている。 船長が市民をよく見ているように、市民も船長をよく見ている。 マリスタはしどもどと自己紹介をしながら、船長を尊敬していることを伝え、握手を求めた。 相手は快く応じてくれた。剣ダコとペンダコのある長い指の手だった。 「マリスタ君、今までどんなところへ行ったことがあるんだね?」 「は、最初はハーレイの村までの仕事でした。その次はアクラリンドのニモルドに行って来ました。 それで、明後日からスクーレまでの仕事に入ってます」 「ほぅ……。君が南アクラル出だからかい?」 船長は彼の分も酒を追加しながら尋ねた。 「それは……雇ってもらうのに考慮されたかもしれません。港からスクーレまでは 内地をしばらく旅しなくてはいけませんからね」 「そうだな。スクーレは色々と悪い噂が立ちやすいが、活気のある栄えた街だ。 君の旅路が無事であることを祈ろう。また、メゾネアに帰ってきてくれよ」 「あ、ありがとうございます!!」 その時のマリスタは、きっと頭の上まで真っ赤になっていただろう。 今回の仕事で行くついでに、ウルカ峠の実家に顔を出すつもりであったが、 自分の帰るべき場所はメゾネアだと思っている。 視界の中の湾岸都市は、白い死者の森と緑セントマリーの森が、緞帳のように 両脇から姿を緩やかに隠していった。 「しまった!一足遅かったか?!」 メゾネアの桟橋で市長の補佐官であるミギリ・メイガンが息を切らせながら悔しそうに沖を睨んだ。 懐に入れてある書類を、服の上から握り締めた。 「すまない……リクセン……!逃がしてしまった……!」 「ミギリ様、急ぎ後を追いましょう!船を手配いたします!」 「無理だ。あの小型船以上の速度が出る船は無い。陸地に着いてからも、地の利のある 奴らの脚に追いつくのは困難だ。……くっ」 ミギリは忌々しげに唇を噛んだ。 「しかし……!」 部下たちは不満の色を隠せなかった。ミギリの懐にある書類は、彼らが時間に追われながらも 必死に調べた情報なのだから。コートの下から取り出し、紙の皺を伸ばした。 「まだだ!諸君らが力を尽くして調べ上げたこの証拠。こいつを突きつけて、タルシュ海運の 事務所の捜索を行う!ついて参れ!」 「はっ!」「そうこなくっちゃ、ミギリ様!」 ミギリは先頭を大またで歩きながら、船長宛てに事の経過を伝書魔法で短く報告した。 兄であり補佐官であるミギリからの報告を、ヘンドリクセンは執務室で受けた。 目つきが険しく歪んだ。 スクーレの闇組織が不穏な動きをしていることは、以前から掴んでいた。 何かをこっそりと探しているようだった。 そして運悪く、メゾネア領で彼らの望む品が見つかったようだった。 確かにそれは、法律的には交易を行っても問題は無いものだった。 なぜなら、今までにそれを取引しようと考えた者がいなかったから、 取りしまる法律などそもそも存在しなかった。 しかし、メゾネア市長として、アクラル国民として、人道的に見逃すことができない代物だった。 何に使うかは知らないが、スクーレの手の内に落ちる前になんとかしてあれを消してしまわなければ。 船長は立ち上がって、執務室の入り口とは異なる扉をノックした。 「兄者、バルクウェイまでの遠距離伝書を頼みたい」 内側から鍵が開き、中からミギリと同じ顔をした彼のもう一人の兄が現れた。 「なんだ、みすみす逃がしてしまったのか。お前らしくも無い」 「面目ない」 「お前でもミスを犯すのだな。そのほうが人間らしくてよいと思うが」 「軽口で済む事態では無いのです」 「そうだったな。……ふふふ、では、我はこれより『リクセン』として、バルクウェイの 『アギ』と交信を行おう」 「お願いします」 船長の兄は魔法発動のための掌印を切り始めた。 切れ長の瞳は、船長と全く同じの薄い色をしている。 二人の瞳に、円弧を描いて発動する魔法陣が映りこんだ。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 踏みしめる森の絨毯の色もすっかり変わってしまった。 日も短くなり夜、営も肌寒く感じるようになった。 バルサの森での三つ目の集落を後にしたのが、七日前だ。 夏のあの日以来、不遜な輩に遭遇することは無かった。 合流して以来、朝の訓練にグリムグラムは果敢に参加していたが、 疲れのせいか、時々は寝坊してしまっていた。 迷ったせいもあり、予定よりもかなり北寄りの行路となっていた。 「これは、一旦バルサリオンの中継地に寄ったほうがいいね。疲れも溜まっているし、 冬支度の用意もいる」 「そうですね。どのみちこの調子なら、森を抜ければライカンウッドよりもそちらの方が 近いでしょう」 団長とワイズのやり取りを後方に聞いていたエルヴァールの帽子に、枯葉がくるりと当たった。 そのまま手で受け止めた。綺麗な黄金色をしていた。 「エル、それをいただいてもよいですか?」 イガーナが隣に並んで尋ねた。いいよ、と彼女に手渡した。 イガーナは裏と表を交互に見てから、鞄の中から布を取り出して、挟んでしまった。 「何かに使うのさ?」 それを見ていたフェルフェッタが尋ねた。 「ウフフ。もっと集まるまでの秘密です」 「ふ〜ん」 行く手に倒木があった。跨ぐ際に、エルヴァールはイガーナとフェルフェッタの手を引いてあげた。 さらに後ろの団長も手伝おう手を差し出したが、一手遅く、彼女は気づかずに自力でぴょんと 跳び越えてしまった。 「ん?ありがとう」 代わりにワイズが手を取った。 よっこいしょと言って、億劫そうに倒木を跨いだ。 エルヴァールはなんとなく、そのまま握る手に力を加えた。 「……?なんだい、手を繋いで欲しいのかい?」 フェルフェッタは思わず振り返った。 エルヴァールは冴えない顔をして、師と手を繋いだまま歩いていた。 数歩歩いてため息をついた。 「……シーテ先生。僕ってもしかして、お荷物ですか?」 「何をいきなり」 ワイズはじろりと隣の青年を見上げた。 フェルフェッタは目を丸くして、エルヴァールの隣まで後退した。 「どこをどう見たらそうなるんだわさ?エル先輩は調理に買い物に狩りにと大活躍してるじゃないのさ」 「それは……誰にでもできることで、当番だからやってるんだよ」 「与えられた仕事をきちんとこなす。結構なことじゃないか」 「……」 エルヴァールはまたため息をついた。 「君は、なにか勘違いをしているんじゃないか?」 ワイズが髪を払った。帽子の先端のメダルが揺れた。 「特別なことができることが大事ではなく、むしろ誰にでもできることをこなせることの方が、 こういう一団にとってはよっぽど重要だよ。それともなに、特別扱いでもされたかったのかい?」 「……そういうわけじゃありません。ただ、役に立ちたいんです」 「つまり、他人とは違う功績を挙げて認めてもらいたい、ということだろう?」 「……」 エルヴァールは再びため息をついた。 ワイズは口が悪いというより、言葉を濁さず真っ直ぐに喋る。 だから、時に正論すぎて胸に痛い。 たった今指摘されたことも、思い当たるからこそ反論できなかった。 数歩前を歩く金髪の少女を見た。 彼女の役に立ちたいという気持ちは最初から変わらないが、彼女の中で自分の存在を 特別な位置に確保して欲しいと願っていることに気づいてしまった。 十年近くも先輩後輩として過ごしていたのに、今更こんな感情を抱こうとは夢にも思っていなかった。 アカデミーの後輩としてのエレオノーレはもういなかった。 エルヴァール・ネルドは流星騎士団の団長に恋をしていた。 なまじ付き合いが長いだけあって、今までの関係を保つためによき先輩であろうと振舞うのが精一杯だ。 団長である彼女には思い悩むことがたくさんあることも承知している。 これ以上気持ちに余計な負担をかけたくもなかった。 「エル先輩、エルが部隊編成を決めた時に言ったことを、気にしてる? あれはエルなりに先輩のことを心配して決めたんだと思うわさ」 黙ってしまった彼を心配して、フェルフェッタが早口でフォローした。 「いいんだ。僕の行動がノロいことは自覚している。……治したいとは思っているけど、難しいな」 「素早さという意味なら、僕のほうがもっと鈍いさ。君はあれこれ考えすぎて、身体に伝達する前に 止まってしまうんだよ。僕みたいに考えながら動きなさい」 「そうそう、あたいなんて考え無しに動くから素早いけど空回りなわけよ」 「君はもうちょっと慎重に考えなさい」 「……」 エルヴァールは何度目かわからないため息をついた。 顔にまた枯葉が当たったので、振り払いつつ上を見上げた。 色づいた葉をスカスカと纏った木々がまっすぐに天を支えていた。 夏に比べて空の面積が大きくなった。白く輝く隙間に、渡り鳥が列をなして飛んでいるのが見えた。 横を見下ろして、師弟漫才を始めたワイズに向かって問い掛けた。 「先生って、どうやって奥さんと恋に落ちたんですか?」 「はぁ?……君って、何もかも唐突だね。いきなり藪から棒に」 「先生、秋ですよ秋。秋は人を詩人にし、悩める人にし、そして恋もするんだわさ」 ワイズがしんがりの集団となったので、団長は一人で歩いていた。 エルヴァールとは以前のように話すことができなくなっていた。 自分を見るエルヴァールの目が、よそよそしくなった気がして、どう対処してよいか分からなくなった。 頭の上には、ワイズから返却されたフィニーが静かに髪飾りの振りをしていた。 この虫は何も喋らない。そもそも生き物ではないのだろう。 それでもどこか親近感をが湧き、彼女はフィニーに一人で相談をすることが多かった。 「……エル兄は変わっていないと思う。なら、変わったのは私のほう?騎士になったから? 団長になったから?」 フィニーは羽根をゆっくりと動かした。 「……眼を持っているから?……そうだ、私は変わってしまった。それは、悪いことなのかな」 「なぜそう思うのです?」 「……以前のように、エル兄といられなくなったことが、寂しいと思うから……」 いつの間にか横を女神が歩いていた。 紅色の髪が炎のように輝いていた。 団長は女神が姿を現したことに驚きはしなかった。 それよりも、他の団員に見られてやしないかと心配し、前後を見回した。 木々の隙間から差し込む細長い光が幕のように遮り、他の誰も見えない。 歩く音すら聞こえなかった。先ほどまではあんなにカサコソと音がしていたというのに。 「エレオノーレ・エヴァンス。それは重要なことですか?世界を守るために必要なことですか?」 「……私個人の、問題です」 「自覚しているのなら、よいのです。何が大切かを、忘れてはいけません」 女神の脚が地に付いても、音は一切しなかった。 団長が枯葉を踏み壊す乾いた音が聞こえるばかりだ。 「あなたには、少々失望しました」 「……何か、ご不興を買うような真似をしましたか?」 「あなたに与えたこの駒」 女神は手の平を上に向けた。団長の髪からフィニーがふわりと飛び移った。 「もっとこれを活用しなさい」 女神は手をずいっと団長の顔の前に突き出した。 団長の眼がフィニーの眼を捉えた。視界が瞬き、眼の奥が痛む。 おぼろげな大陸の輪郭の左下、キングリオンの位置にモウリィマウスの文字。そのやや上部、旅人の森の位置に エレオノーレの名。その左上に…… 「ジャイアント……」 「二日も前に出現したと言うのに、あなたはまったく気づかなかった」 「……申し訳ありません」 「そして、モーンレックを逃がしましたね」 「モーンレック?」 「人に仇なす心の魔です。あなたには失望しました。……これ以上、失望させないで下さい」 「女神、待っ……」 存在が薄くなりつつある女神を掴もうと、団長は手を伸ばした。 「うぉっ、なんでぇ?」 代わりにシュウガの肩を掴んでいた。 「あ、すみません」 慌てて手を離すと、シュウガは首をかしげながら隣に並んだ。彼と話していたエクレスが 反対側に付いた。小首を傾げて尋ねた。 「どうしたの?顔色悪いよ?」 「……。……いえ」 「そう。ならいいけど」 「なぁ、エル団長?」 シュウガはわざとエクレスの真似をして女っぽく首を傾けた。 「あんた、何を隠してるんだ?」 団長は浅く息を吐いた。シュウガは初めから油断ならなかった。 ちょっとした仕草からでも人の心を読む男だった。 ワイズとは違う意味で、多くのことをお見通しなのだろう。 「……黒い霧のようなものです」 「?抽象的だね」 「団長。俺ぁあんたらアカデミー出とは違って学が無ぇからよ。そういう奴にも 分かるように言ってくれねぇか?あんたのしゃべる言葉は、標準語すぎて ヒジョーにナンカイなインショーでね。もうちょっと、くだけて喋っても いいんじゃね?そのほうが分かりやすいし、そっちも喋りやすいだろ?」 「……そう、ですか?」 エレオノーレは団長とは言え団内では最年少であったので、年上ばかりの団員たちに対して 丁寧な言葉遣いをすることは当然だと思っていたので、シュウガの指摘は想定外だった。 「エルツーの喋り言葉は綺麗な発音なんだけどね、儀式でもやってるみたいな なんていうかな、肩肘張った感じはするね。あんたは騎士だからしょうがないのかな。 昔みたいに、気軽に話してくれたほうが私としても嬉しいな」 「心がけます」 「おぅ、頼むぜ」 シュウガが左手で団長の頭をぐりぐりと撫でた。 その際に彼の手がフィニーという物体をこっそり探ったことには気づかなかった。 頭を拘束されながら視線を返した。 薄い色をした切れ長の眼に自分と峠が映っていた。 「私の隠し事、ひとつ言います」 シュウガとエクレスはゆるやかに身構えた。 団長は眼だけで素早く二人を交互に見た。 「私は、キノコが嫌いなんです」 「……知ってるし、隠してないでしょ……」 「バレてましたか」 「他にリンゴが嫌いなことも知ってるぜ」 「あ、それは知らなかった。そうなんだ?」 「はい。味が嫌いです」 「……」「……」「……」 生ぬるい沈黙が漂った。 もしかして、この子はジョークを言ったつもりなのだろうか、とエクレスは迷った。 「魔物を」 団長が言った。彼女の声は見た目に反して意外と低い。 「この眼で確認するまで、待ってください。本当に魔物が襲っていることを確認したら、 私の隠し事を全て話します」 「二言はねぇな?エヴァンス卿?」 「では、ソーヤソーシェの銘にかけて」 「うっし」 シュウガはバンと団長の背中を叩いて、前方へずかずかと歩いて行った。 女の子に何するのさ!とエクレスが後を追いかけた。 団長は再び一人になった。後続組みはワイズと奥方の馴れ初め話で盛り上がっていた。 フィニーをもう一度覗き込んだ。 港町イルグールの位置に、魔物の名が浮かんでいた。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 「うわぁ〜。エルがいっぱいいる」 「本当だ。鎧を着てなかったら混ざっちゃうんじゃない?」 「それはない、それはない」 「訛りが酷いな。……耳が慣れれば、なんとかなる。か?」 「イグラス訛りってんです。俺は分かるんで、ちょっと聞いてきますよ」 「私も行きます」 バルサリオンの中継地に辿り付いた一行は、ひとまず路傍に待機して、 団長とシュウガの二人が様子を伺いに向かった。 イルグール島を中心に、各イグラス諸島との定期船が発着する港を持つため、 イグラスの民やその血を引くものが多い。 通りすがる人々も旅人の森までとの容姿とは違い、北方特有の長い耳と薄い色の髪が目立った。 「とりあえずは宿を探しましょう」 「おう」 何人かに尋ね、地階が酒場となっているホテルで部屋を確保することができた。 宵の口と言うにはまだ早いが、外はすでに薄暗くなりつつある時間だったので、 気の早い連中がすでに酒場を占拠していた。 訛りの利いた早口でまくしてたているので、団長にはほとんど聞き取れない。 宿泊の手続きを案内してくれる女将の声を聞き分け、理解するのに精一杯だった。 宿帳にサインをし出口に向かった団長に、酒場の喧騒に耳を済ませていたシュウガが声をかけた。 「エル団長。イルグールに魔物が出てるらしいぜ」 「……はい」 「知ってたんだな」 「はい」 団長は振り向いて彼を見た。 批難の表情を覚悟していたが、シュウガはいつもと変わらずひょうひょうとしたままだった。 「そっか。知ってたんならあんたのことだ。遠征計画にはもう修正を入れてるんだろ?」 口調もまったく変わらなかった。 「はい。皆には一時の休養を取っていただいてから、話すつもりです」 「なら、いい」 シュウガは団長を追い越して酒場の両開きの扉を開けて出て行った。団長も後に続いた。 王都とは違う、やや甲高い鐘の音が五つ鳴った。 「団長。取引に必要なのは信頼だ」 シュウガが首を鳴らしながら呟いた。それからぐるんと首をまわして団長を見下ろした。 「意地悪な質問をしてやる。あんたから見て、俺はあんたを信用してるように見えるか?」 団長は一瞬だけ視線を合わせてから、彼とは反対側の軒並みを眺めた。 「見えます」 「なんで?」 「あなたは物の値段を量れるように、人の心を量れる方です。あなたが最初に提示した取引 だけを純粋に成立させたいと思ったのなら、イルグールのことは気にかけますまい」 「人を冷血みたいに言うなよ」 「そうじゃないと言ってるんです」 「ん?そうなのか?」 「ええ。それに、私がシュウを信用してます。これが理由です」 「……そうか。へっへっへ、ありがとよ」 シュウガは団長の頭に手を置き、下に押さえつけるように軽く力を加えた。 団長は迷惑そうに頭を振り子のように降った。 待機していたエルヴァールはその様子を目撃し、瞬きが異様に早くなった。 ティモアはまったく表情を変えなかった。 前の話 次の話 |