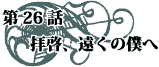
北東の魔法都市の冬は、緯度の割には過ごしやすい。 街をぐるりと取り囲む外堀が主軸となり、差し障りの無い程度に 自然の猛威を人間向きに和らげる魔法が施されている。 ここ数日はそれに上乗せする形で、魔物避けの魔法陣を張り巡らせる作業が 夜を徹して行われていた。照明を燈す魔女たちが列をなして蠢く様は、 精霊に捧げる群舞のようであった。 そろそろ夜が明けようとしていた。 ヨーウィは自室の寝台の上で掛け布団に包まって臥せっていた。 暖炉の薪がじりじりと黒く崩れていった。 新しいものをくべなくてはいけないが、ヨーウィは動けなかった。 あの日から、手紙を貰った日、白炎の村に魔物が現れた日から 彼は原因不明の頭痛に襲われ、この寝台の上に寝転がるだけの毎日となった。 頭痛が引き起こすのか、あるいは逆なのか、常にひどい耳鳴りがして、 ヨーウィは役目を果せなくなった。 それからは眠っているのか起きているのか、自分でもわからない状態が続いていた。 教授たちは対策会議や各地との外交問題で忙しく、助手達は論文の締め切りに追い討ちが かかるような忙しさで神経過敏になっており、他の伝書魔法使いたちは今までヨーウィが 大半を担っていた部分を担当する羽目になり、彼を遺して毎日が目まぐるしく過ぎていた。 抱えていた枕の破れ目に手を入れた。 中には柔らかい羽毛が詰まっている。 肌を滑るような感覚の向こうに、乾いた感触があるのを指で確かめると、安心したように息を吐き出した。 彼のただひとつの持ち物、手紙の隠し場所だ。 (…………どうして) 痛みが支配する頭を動かすのは大変な作業だった。 同じ道を何度も行ったり来たりしては迷っていた。 (ぼくに、この手紙をくれた子は……) 寝返りを打ち、布団から出した顔を天井に向けた。星図が描かれたモザイクタイル造りだ。 (ソースを自分でえらべるって、ぼくにおしえたんだ……) 先住の誰かの仕業だろうか、一直線にえぐれてタイルが傷ついてしまっている個所がある。 まるで天駆ける流星のようだった。 (きみはえらべる、……ぼくは、えらべない) 目の端がほんの少し熱くなり、一瞬にして冷えた。 再び布を頭のてっぺんまで引き上げ、枕を抱く腕に力を篭めた。 (手紙がこわい……それでも、もういちど、ほしい……) 寒さと頭痛のためか、肩が小刻みに震えた。 与えられた道を辿るだけだった彼に、初めて矛盾という事態が起きた。 今まで知らなかった感情に、彼は恐怖していた。 恐怖という感情すら初めてだった。 誰かに何かを言ってもらいたかったが、伝書魔法の使えない彼に、 遠くの友人達の声は届かない。 ヴァレイでは、ロッシが各地との中継処理に追われていた。 ヴィムでは、リムが魔物関連の過去の記録の洗いの直しに熱中していた。 メゾネアでは、リクセンが航行する公船の羅針盤の役を務めていた。 バルクウェイでは、アギが警備隊からの連絡を待っていた。 ゼレスでは、ジリーが南の荒野からの報告と北の斥候からの情報に考え込んでいた。 アクラル大陸に、新しい陽が昇る。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- ティモアは定刻どおりに目が覚めた。 テーブルから体を起こすと、周りには団員もそうでない者たちが死屍累々と横たわっていた。 その光景に、一瞬だけ脳裏を焼かれたが、すぐに思い出した。 ここはイルグール島の港町。流星騎士団の初戦にして初勝利を収めた翌朝だ。 暖炉の脇に立てかけてある大剣を手に取り、人を踏まないように注意しながら表へ出た。 昨日の戦場である灯台のふもとまで歩く。 朝の霧の中、見慣れた人物が見慣れた動きをしていた。 「……おはようございます、エヴァンス卿」 「おはようございます、ジェイナード卿」 団長も彼と同じく、武人としての体内時計が生活を支配しているようだ。 カンタ卿は、とうの昔に諦めていた。 筋肉をほぐしてから団長に並んで型の素振りに参加した。 今日ばかりは他の朝練メンバーも寝坊していた。 いつもどおりの運動をこなすと、体もほどよく温まってきた。 日が昇るにつれ霧も薄れていった。 お互い無言だった。 どうにも、この人と業務連絡以外で会話をすることができない。 一息入れたティモアは、思い切って団長に話しかけた。 「……エヴァンス卿、ご趣味は?」 「は?」 ティモアの声は低く聞き取りづらい。団長は今の時間を自分の中でもう一度再生してから、 何を問われたかを聞き取った。 「乗馬、です」 「なるほど」 またもや沈黙に陥った。ここから会話を繋げるためには、次は何を言えばいいのかと 考えていたら、 「ジェイナード卿は?」 「……?」 自分の思考回路で手一杯。相手方からの問いは予想してなかったので、答えを出すのに 時間がかかった。 「…………その、」 珍しく言いよどんだティモアに、団長は動きを止めて顔を見た。 「………………花……」 「花、ですか?ガーデニングですか?」 「……自分の出身地ジグーは、特殊な気候のため通常の草花が育たないのです。 それゆえ、ヴァレイ近辺で目にする植物が珍しく……………………。 ………………………………………………………………押花にして、保存している……」 「ならば、遠征の途中で目にする草花もされているのでしょうか。なるほど……。 今までそういう目で植物を見たことが無かったので、興味深いです。 素敵なご趣味ですね」 大の男にしてはずいぶんと少女趣味なことを自覚していたティモアは、 本物の少女と目を合わせることが出来なかった。 それでも、会話が続いたことには感謝した。 団長は陽にかざしながら刃を確認した後、鞘に収めた。 美しく装飾されていた柄の飾りは、昨日の衝撃により無残な姿になっていた。 宝飾もひとつ無くなっていた。確か真珠のはずだ。 どうせ無くすなら、売って資金にしておけばよかった。もったいない。 そんな思いで柄を眺めていたら、 「……貴卿の剣、拝見してもよろしいですか?」 ティモアの申し出に、団長は鞘ごと手渡した。 半分だけ抜いて、刃の根元をじっと見ていた。 「……これは、ヴィムのムジョス博士の刃だ」 「王から賜った物です。匠の名は伺いませんでしたが、銘はソーヤソーシェと言います。 イグラス語の銘ですが、ヴィムの業物でしたか……」 剣を受け取り、腰に挿した。フッケル政務官はただの宝飾剣だと言い放ったが、 名高いビルダリクの刃を与えてくれた王の厚意に、改めて感謝の念をいだいた。 「どういう意味の銘なのだ……?」 ティモアも大剣を背負い、振り返って尋ねた。 団長は自分の中の拙い言語辞典に照らし合わせた。 「正確に翻訳はできませんが。そうですね……『黄昏色の』といった意味です。 『曖昧な中間色』というか、具体的な色を指すわけではないのですが、色の名前です。 王は、私の瞳の色にちなんでと、下賜してくださいました」 ティモアは改めて団長の眼を見た。 団長も応えてティモアの瞳を覗いた。 それぞれの色の虹彩に、それぞれの顔が映りこんでいた。 横から差し込む陽光が、眩しい。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 「…………」 フェルフェッタは隣で黙り込む師匠からの圧迫感を適当に受け流していた。 気が付いたら太陽は頭のてっぺんよりも少し傾く頃合だった。 ワイズ・シーテの機嫌が悪い原因は複数思い当たる。 なにせ、昨日の彼の言動ときたら、百年に一度も拝めるものではなかっただろう! 思い返すだけで、自然と口に端が引きつりそうになった。 (見得っぱりの先生だもの。奥さんには絶対見せらんない姿だったろうに) 朝食をすっ飛ばして遅めの昼食を、全員で摂る為に男性団員用に押さえた大部屋に 集合していた。サイドボードに人数分、無理やり乗せられたカップをひとつ 取り上げて飲んだ。 「にがぁっ!」 果物のような匂いからは想像できなかった草の味に、思わず声を上げた。 その様子をホノカは少し目を見開いた後、自分の分に口をつけた。 「ふ〜ん……」 下唇を舌で拭い、再び口をつけた。ヴァーグナルもひとつ手に取り、 ホノカの隣に腰掛け小指を立てて飲んだ。 「んん。んー……これはウェリノールの茶葉を発酵させずに揉んだものだな」 「ヴァンタ、正解。腎臓と肝臓にいいのよ。まっずいけどね。酔い覚ましには持ってこい」 「ここらでは、漁の際にこれに唐辛子を入れて暖と滋養を取るって聞いたような……」 エルヴァールは昨日の曖昧な記憶を引っ張り出そうとしたが、頭がぐらついたのでやめた。 シュウガの早口だけが耳に残っていた。 「おーっす。待ったぁ?」 当のシュウガが両手いっぱいにバスケットを抱えて部屋に帰ってきた。 後ろにイガーナと団長が続く。バスケットの中身は固いバゲットのサンドウィッチだ。 魚のフライと野菜の漬物が挟み込まれているものと、エビのすり身とイモをふかしたものを 挟み込んであるものの二種類だ。空腹だった団員達は、我も我もと己の分を確保した後、 寝台や椅子に落ち着いた。 団長もそれぞれ一種類づつ膝の上に乗せた。エビのほうをかじってみた。 最初の一口は歯ごたえのある麦の固まりしか入ってこなかった。 パサついて喉が渇くが、噛んでいるうちにじわりと甘味を感じる生地だ。 お茶で潤してから二口目。 固ゆでのイモのしゃりっとした感触と、すり身の弾力のある歯ざわり。 この食感を知っている……。 よく、家で食べていたものと同じだ。 団長は動作が鈍ることなく、ふたつとも平らげた。 お茶のおかわりをと取り上げたポットは軽かった。 階下の台所にお湯を貰いに行こうとしたが、オレも欲しいから、とグリムグラムが 代わってくれた。食べるのが遅いホノカが間食するのを見届けたところで、 シュウガが指についたソースを舐め取りながら切り出した。 「さて、エヴァンス団長。オレらに話すことがあるんだろう?」 エクレスは長い脚を組んだ。ワイズは深いため息をついた。 アディは右手の包帯をさすった。 「はい。トランタン殿が戻られるのを待って、それからお話します」 「なに?なんか深刻な話?」 ホノカが枕にもたれながら尋ねた。 エルヴァールは扉と団長を見比べた。 団長は両手を軽く組んでみた。手の甲に指の冷たい温度が伝わった。 (……こういう時、指先も温かいと感じているのに、どうして冷たいということを 先に感じるんだろう……) グリムグラムが階段を登る音が薄い壁から伝わってきたので、ティモアは 壁から背を離して座りなおした。 団長は立ち上がって後ろを振り向いた。板が並んだ壁に向かって手を差し出した。 「女神、おいでください」 エルヴァールは肩を引き、フェルフェッタは下唇を噛んだ。 他の者は全員、目を見開いた。 上を向いていた団長の手の平の先に、見えない極薄の布があったかのように、 それを掻き分け、女性のしなやかな腕が現れた。 団長は頭を垂れて動かない。 布が後退するかのごとく、腕から肩が、胸が鼻が顔の輪郭が脚が、そして 一対の白い翼が現れた。 瞬きを一度もする間もなく、紅い髪に白い衣を纏った女性が立っていた。 「何用ですか?エレオノーレ・エヴァンス」 知らない凛とした声が部屋に響いたが、どこか遠い音楽のようだった。 ヴァーグナルの半開きの口から「美しい……」と一言だけ漏れた。 ティモアは膝に力が入り、寝台が小さく軋んだ。 (……エヴァンス卿と双子なのか?……いや、顔のつくりが似ているわけではない、?) (メゾネアで見た、精霊の像に、そっくり) イガーナはぱちぱちと瞬きを繰り返した。頬が熱い。 グリムグラムは目玉をせわしなく動かした。 (ホ、ホ、ホノカちゃんのほうが、可愛いじゃん!!) 「皆さん、この方は精霊です。この方の予言により、この魔物討伐の騎士団は結成されました」 「はぁ?」 ホノカは思わず声を挙げた。シュウガが結った髪を指で弾きながら尋ねた。 「募集の紙には魔物が増えるからそれに対抗してって書いてあったな。それは、 そこの美人の入れ知恵だったってわけか?」 「入れ知恵ではなく、予言です。この方は私に今後のアクラル大陸に強大な魔物が現れると 告げました。その魔物を討ち取らなくては、大陸は滅びに瀕するであろうと。 それに対抗する手段を得るべく、私は国王陛下とシーテ先生のご助力の元、団員を募集したのです」 「ホロビ……。その魔物ってのは、今キングリオンに出てるやつ?」 エクレスは脚を組みなおした。 「いいえ、エクレス・カーペン。あのモウリィマウスも昨日のジャイアントも、 取るに足らない小物です。真の脅威は二十年後にやってきます」 「にじゅーねん……。私、いくつだろ……」 呟くエクレス以外の団員も、二十年という時間について考えを巡らしているようだった。 団長はその空気を読んでほっとした。 自分やワイズが長々と説明するよりも、女神の一言の方が重みがある。 女神の存在により、滅びの予言も、それに立ち向かうことも皆にあっさりと受け入れてもらえた。 だが、今までずっと隠していたこと、女神をだしに使うためだけに呼び出したことの 後ろめたさに、指先はどんどん冷えていった。 アディが額の飾り布を外した。前髪を払いのけ、真っ直ぐに女神を背後に持つ団長を見た。 「じゃぁ、エル団長。アナタは二十年、戦うつもりか?」 「いいえ」 エルヴァールの視界の中で、団長は首を軽く振った。 「二十年より先まで、私はこの道を進むつもりです」 女神は美しかった。白い翼はまばゆいほど神々しかった。 それでも、その前に立つエレオノーレ・エヴァンスにしか意識が集中できなかった。 彼女の言葉に、急激に胃の辺りが痛くなった。 「ちょっと待った。……エレオノーレちゃん、なんでそんな大事なこと、隠してたのっ!」 ホノカが息巻いて立ち上がった。 一歩一歩に力を篭めて、団長に歩み寄った。 「つまりぃ、流星騎士団ががんばらないと、昨日のとは比べ物にもならないこわ〜い魔物が 大陸もヴァレイも滅ぼしちゃうってことなんでしょ?!」 「……そうです」 「昨日のあのでっかいやつも、倒すの大変だったでしょぉ?」 「灯台守の方々の機転に助けられました」 「この先まだまだ、危ないじゃない!!」 「……そうです。……今更言うことは卑怯だとは思いますが、この事実を踏まえた上で、 退団したい方は止めません。……言い出せなくて、」 「で・も!その修羅場をくぐり抜けたら、あたしって主役よね?!」 ホノカは団長の前でくるんと回ってからミニスカートの裾を摘んでウィンクした。 「いいじゃない!世界の危機に立ち向かう華麗な魔女、ホノカ・セキグチ。いい響きよね〜!」 グリムグラムは顔を輝かせて何度も首を縦に振った。 シュウガは左右非対称に眉をしかめて呟いた。 「主役はどうやっても、エレオノーレちゃんだろ……強いて言えば、俺ら全員だっつーの」 「そうだね。流星騎士団が主役だね」 エクレスが前に投げ出した脚がフェルフェッタのつま先に当たった。 フェルフェッタはエクレスと目を合わせて、ニカッと笑ってから団長を仰ぎ見た。 「エル。二十年ってとっても長いわさ。正直言うとね、あたいはそんなに長く旅をして 魔物と戦う自信は今は全然ない。それでも、あんたの、騎士団の力になれる限りは、 あたいは流星騎士団員でいたいの。それでもいいかな?」 「十分です。感謝します、フェル先輩」 「ああっ苦難の道に挑まれるエヴァンス卿に、ヴァーグナル、涙を禁じえません! 影となり光となり病めるときも健やかなる時も、卿を支えることをお許しください!」 大仰に悩めるポーズを取りながら、ヴァーグナルは団長の手を取って熱烈にキスをした。 「団長、ワタシたちも変わらず風が望むまま、キシ団と共に行きましょう。ね、アディ?」 「……そうだね」 ホノカは団長を中心としたこの仲良しごっこのハリケーンになんだかむずむずしたが、 思わぬ広大な舞台に自分が立っていることに陶酔していた。 隅で姿勢正しくことの成り行きを見守っていたティモアの元へ軽やかに歩いて行った。 「ね、ね?ティモアさん。ほら、アレやって欲しいな。ヴァレイ出る時にやったアレ」 「あれ?」 「アレよ〜。あの時のティモアさん、かっこよかったぁ!」 ホノカは唇をチュッと鳴らしてみせた。 視線を彷徨わせたティモアは、なんのことか思い当たり、眉根が少し動いた。 ホノカはティモアの背中を手でそそっと押した。 ティモアはそれから逃れるため仕方なく立ち上がった。思惑どおりだ。 (この人の、見た目に反したこういうところが、可愛いのよねぇ) ホノカは彼の広い背中を見上げた。 ティモアはかがんでエルヴァールに何やら話し掛けたが、彼に肘でつつかれて、 観念したようにうなだれた。 他の団員達の視線も彼に集まっていた。 「…………我ら、流星騎士団員は」 いつもの低い調子で彼はセリフを読み上げ始めた。 そんな浮き足立った空気の中、ワイズ・シーテだけは凍りついていた。 正確には、女神も同様だった。だが、女神は常にそうであった。 空気の流れも窓から入る光も、彼女にはなんの影響も及ぼしていない。 団長と団員達との心温まる茶番劇にも、なんの関心も持たなかった。 ワイズは女神が現れた瞬間から、それ以外をまったく見ていなかった。 周囲の音も耳には入ってきたが、聞いてはいなかった。 多くのクロニクルズを読んできたが、その中にだけ存在した予言の女神を 実際に見るのは初めてだったからだ。 (これが、女神?………………女神だって?!) 彼の目には女神と呼ばれるものは、白い美しい翼を持ちこそはすれ、 それは七対にも及び、生々しい肉色の肌をもった獣が、昆虫の蛹から 脱皮しようとして失敗したかのような、おぞましい姿に映っていた。 「ワイズ・シーテ」 名を呼ばれた。見た目とは裏腹に、優しく愛しい女性の声だった。 それが返って粟肌を立てた。 「数多のクロニクルに踏み込む愚者よ。恥を痴れ」 口調はあくまで穏やかだった。 「……僕は、お前の正体を知っているぞ……お前の目的も、知っている!!」 容赦なく浴びせられる威圧感の中、持てる限りの精神力で対抗した。 「しょうこともなし。私に到達する以前に、お前は精霊卿に下ることになる」 「承知の上だ!」 「ねぇ、でも、ワイズ?」 その声のまま、知っている口調に変化した。 「このアクラルでは、あなたは騎士団に出会うのが遅すぎた。でも、他のアクラルでは 違ったこともあったわ。最初から最後まで、ずぅっと騎士団員でいたこともあったわ」 硬直した腕に、そっと柔らかい手が触れた。眼球だけ下にやると、紺色の裾から 赤い刺青を持つ白い肌が見えた。 「でも、今回はダメ。あなたはすぐに死ぬわ。二十年を見届けることすらできないの。 それで終わりよ。けれど、このアクラルをリセットして、新しい世界を創めたら、 その時はあなたをずっと団員でいられるように、調整してもいいのよ? そうしたら、研究もずっと続けられるし、世界をもっとたくさん見て回れる。 それに、私ともう一度、恋ができるわ……」 おそるおそる、刺青の持ち主に顔を向けた。 初めて出会ったときと同じ、前髪を下ろした少女が笑っていた。 遠い夏の日に、グラツィアで強烈な張り手を食らわしてきた神官だ。 彼女の手に、自分の手の平を重ねた。 彼女の冷たさが伝わってくる。それでも、指先で触れた個所は温かいと感じた。 生身の人間の温度だ。 「……僕は、今でも君に恋をしているよ。口に出すのが気恥ずかしいだけで、 いつでも、どこでも、毎日君のことを想っている。君と結婚できて本当に嬉しいんだ。 そんなワイズ・シーテを、僕は悪くないと思っている」 両手で挟んだ彼女の手を優しく自分から引き離した。 「世界が自分の都合いいようにあるなんて、冗談じゃない。思い通りにならないからこそ、 思い通りに従える方が、楽しいじゃないか!」 女神に向かって視線を勢いよく投げた。 先ほどの醜悪な姿ではなかった。黒い外套を頭から被った姿は、影法師がそのまま 立ち上がったように錯覚した。 「ワイズ・シーテ。残念です。数多のクロニクルを理解した貴方なら、滅びを理解すると 思っていたのですが、見込み違いでした」 「お前に僕の何が分かる。自分のことも知らないくせに、名前すら持たないくせに、 ……シナリオ通りに動かしたいのなら、エヴァンス君に、その醜態を晒さないことだな!」 「お前は危険だ、ワイズ・シーテ。シロンの指輪にならないように、気をつけるがいい」 荒い息が止まらない。力の入れすぎで肩の付け根が収縮していた。 隣の彼女の気配はすでに消えていた。 急に視界が明るくなった。 「の名の元に、」 ティモアの低い声が耳に滑り込んできた。 「「「誓おう!!!!」」」 若者達の明るい唱和が狭い部屋にこだました。 ワイズは深く瞼を閉じた。 頭で整理がついていることだった。 しかし、暗い死の予言は彼の心にべったりと張り付いた。 緩やかに侵食してくるそれを拭い去れるほど、彼は強い人間ではなかった。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 「ヘクショィッ!!う〜〜〜〜小便してぇ」 「さっきあんなに飲み食いするからですよ」 「張り込みってのはさ、飲み食いしながらって相場が決まってるんだよ」 「なんですか、それ……」 「シッ!」 乾いた岩盤の中腹にぽっかりと空いた穴ぐらに緊張の色が漂った。 一番入り口に近い男が人差し指を手に当てて、反対の手の親指と人差し指で 作った輪を覗き込んだ。 「ふんふん。聞いてた特長どおりだな。あれがタルシュ海運のキャラバンだろう。 ひぃ、ふぅ……。人数が少ない。伏兵がいると見ていいかな」 「へっ。やっぱりただの運び屋じゃないぞ。胡散臭いな」 「エイレム、僕にも見せて」 レグレラムがしゃがみ込んで、冒険者の輪を通して馬車を見た。 「ずいぶんと厳重な魔封じの結界が施されている。……ヤバい匂いがするんだけど?」 「俺だってこんな仕事いやなんだよ!仕方ないだろ、市長の命令なんだから!」 「あ〜あ、どうせ俺たちゃしがない警備隊。上のご希望とあればエンヤコ〜ラ」 「その警備隊ってのは、今は無しだ。バルクウェイの者だということは伏せておくように というお達しだ」 「言われなくても、こんな山賊まがいのこと……母ちゃんが聞いたら泣いちゃうよぉ……」 「山賊山賊。そう。俺たちは今から仕事が終わるまで、警備隊じゃなく山賊団だ! 名前は……『ゴーレム山賊団』でいいや。俺のことは、『お頭』と呼べ。分かったな」 「ゴーレムってなんですか?隊長」 「お頭!」 「ハイハイ、ジャンジャールのお頭」 「ねぇ、漫才してるうちにあいつら行っちゃうよ」 「いかん、皆、隊列用意!」 背の低い騎士は首に巻きつけていた外套を鼻の上まで引っ張り上げた。 後の者もそれに習った。 彼が腕を振り上げると、彼らは音も鳴く垂直に近い崖面を駆け下りていった。 前の話 次の話 |