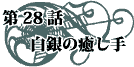
「ジョカミ殿、こちらです」 団長は後続に呼びかけた。 後ろを振り返ると、背の高い黒い革鎧の男が道端の花売りから花を一輪買っていた。 男は代金を売り子に握らせてから大またで団長と並び、持っていた花を彼女フードを 持ち上げて髪に挿した。 団長は驚いて見上げた。ティモアと同じくらいの角度だった。 「これはこの地方で一番ポピュラーな花なのです。お似合いですよ」 R・R・ジョカミは目尻を寄らせながら微笑んだ。 団長は指で花を触ってから、深呼吸をして再び先導を始めた。 「この街は花を売っている店が多いですね。しかもたくさんの種類があります」 R・Rはゆっくりと首を傾けて路地のそこかしこにある切花を扱う露店を見やった。 乾いた空気の中、植物特有の水っぽい匂いがかすかに鼻をくすぐる。 「花を見ると心が優しくなれます。しかし、荒野に囲まれたゼレスは土が貧弱で草木が 育ちにくいのです。目の前に無いとなると、手元に置きたくなるのが人情です。特に春は。 ですので、レイラントの街や近辺の農村から分けてもらっているのです」 「花で街が満たされるとは、とても素敵です」 団長は外から耳が見えないようにフードの位置を直しながら答えた。 R・Rが差し障り無く花の薀蓄を語っている間に、騎士団が泊まっている旅籠が見えてきた。 すると、入り口からホノカが早足で出てきて、団長たちとは反対側へと歩いていった。 動きから察するに機嫌が悪そうだった。 背中を見送りながら団長は扉を開け、R・Rに入るように促した。 この度の宿泊先は値段の割には豪華だった。今まで立ち寄った他に比べて街の規模が大きいからだろう。 一階にはちょっとした広さのラウンジがあり、フェルフェッタ・エクレス・イガーナに加えて ティモアが丸いテーブルを囲んでお茶を楽しんでいた。 団長が見える位置にいたフェルフェッタが片手を挙げ、指を開いたり閉じたりして彼女を呼んだ。 残りの三人も振り返り、二人のために場所を空けた。 ティモアが立ち上がってR・Rに席を譲ろうとしたが、彼は丁重に断った。 二人が並ぶとティモアのほうが若干低かった。 「おかえり、エル。そちらは?」 フェルフェッタが新しくお茶を注ぎながら尋ねた。 団長はフードを外しながら答えた。 「こちらの御仁はゼレス魔法管理課のR・R・ジョカミ殿です。これよりしばし、我が騎士団に 各員として籍を置いていただくことになりました」 「よろしくお願いいたします」 R・Rは腰からきっちりとお辞儀をした。 座ったままだった女性陣は慌てて立ちあがり、それぞれがピョコリとお辞儀をした。 「え、え〜っと、なんでですか?」 エクレスはどちらに尋ねていいもか判別つかず、二人のちょうど中間を見ながら問いかけた。 それを受けたのはR・Rだった。 「理由のひとつとしましては、ゼレス市の者としてヴァレイより派遣された皆様を キングリオンまでご案内するよう上から仰せつかったからです。リオン荒野は地元の民でも 移動するには辛い地域です。ましてや昨今は盗賊団が出没するという報告も受けております。 皆様の安全と旅の補助を努めさせていただきます」 ティモアは一歩下がってR・Rを見つめた。 名目上はなんであれ、ヴァレイからきた小隊につけた、ゼレスの監視役をいうことだ。 「もうひとつの理由としましては、シーテ博士の代わりとして、及ばずながら力を尽くすよう 上から仰せつかったからです。私は魔術には博士ほどは長けておりませんが、 各種補助魔法と回復魔法は心得ております。必要であれば、なんなりと命じてください」 「えっえっ……?代わりって……先生は??」 フェルフェッタが口をあけたまま団長を見た。 団長が省舎に出かけたのは、帰りの遅いワイズを迎えに行ってのことだったのだ。 団長は腰につけていたポーチから布で包んだ小さいものを取り出した。 それをフェルフェッタに渡しながら答えた。 「キングリオンに赴いてから再びゼレスに戻るまで、先生はゼレスに残っていただきます。 騎士団が王都より出発して以来、すべての戦闘に先生には出陣していただきました。 先生の補助の能力は強力でしたから、頼りすぎていたところがありました。 イルグールからバルサリオンに戻った辺りから、ずっと不調なご様子でしたが、 先日の祝福の日に、寝込まれたでしょう?……この往復の旅路の間だけでも、 休んでいただければと判断しました」 「シーテ博士はこの辺境の街までにも名のはせた高名な方です。ゼレス市としては 滞在を歓迎いたしますよ。ご教授に預かりたいという魔法使いも大勢いるでしょうし、 博士もこちらの図書館に興味を示しておられました。滞在中にご不便をかけるような ことがないと、お約束しましょう」 「あ、はぁ……」 長い説明に戸惑いながら、フェルフェッタは渡された包みをそっと開いた。 中には三日月型のメダルが入っていた。ワイズが帽子の先端にいつもつけていたものだ。 フェルフェッタはじっとそれを見つめてから、丁寧に布に包みなおした。 先ほど彼女が入れたお茶を差し出しながら、エクレスはため息をついた。 「先生って、そんなに有名な人だったんだ。しまったな、授業をちゃんと取っておけば よかった!」 「先生がいないととても寂しいです。よろしくお願いします、ジョカミさん」 イガーナが微笑みながら手を差し出した。髪には団長と同様に花が挿してあった。 赤の一輪を中心に小花を散らせた、ちょっとしたアレンジメントになっていた。 「こちらこそよろしくお願いいたします。よくお似合いです。その組み合わせは 『君に情熱を注ぐ』という意味があるんですよ。男女の告白に使うのです。 あなたにこの花を贈った方がうらやましいですね」 R・Rはイガーナの頭を自分に例えて指で花を指してみせた。 イガーナは彼の言葉に目を丸くして、ティモアを見た。フェルフェッタとエクレスも、 R・Rの言葉を聞いた瞬間から目を輝かせながら見ていた。 当のティモアは、凍りついたように下唇を軽く噛みながら、視線を誰もいない空間へ 退避させていた。 「そうだったんですか。でも、下さった方はきっとそんなことは知らなかったのだと 思います。純粋に花が好きな人なのです」 イガーナは早口に誰に宛てるでもなく弁明した。頬がほんの少し赤くなっていた。 それを見て団長は、なぜ先ほどホノカが怒って出て行ったのかが察しついた。 (ジェイナード卿のご真意は測りかねるが、なんだか、応援したい気持ちでいっぱいだ!) 団長から送られる視線も微妙に輝きを増したようで、ティモアはますます凍りついた。 単に、花に溢れたこの街で、初めて見る種類を購入したかっただけなのだ。 男一人で買う照れ隠しに、似た趣味を持つイガーナに同行してもらい、御礼にと適当に 見繕って贈っただけなのだが、まさかこれほど波乱を巻き起こそうとは思ってもみなかった。 (…………こういう時、カンタ卿ならばよい打開策を知っているのだろうか……) 「たっだいま〜!ヴァーグナル・カンタ、戻りましたっ!」 心の中で同僚騎士に助けを求めたところで、当の本人の能天気な声がラウンジに響いた。 -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 南アクラル、キーディス山脈の一角に祈りの山と呼ばれる岳がある。 東より太陽が登ると金色の光が岳より北に臨む内湾いっぱいに反射する清浄な光景を、 人々は正と死を司る光竜の精霊の縁の地であると言い伝えてきた。 そこより西にあるリーヴェ修道院が大陸の大多数を占めるリーヴェ派の本堂であることも 相成り、この二箇所を合わせて巡礼する者が多い。 ゴルドア平原と祈りの山頂の中継地として、ウルカ峠にある小さな村はこじんまりと栄えていた。 マリスタ・ティルウェリンは実家の裏手にある井戸にもたれ掛かって北東の空を眺めていた。 イヴァレス山の向こう、内湾のさらに向こうにある湾岸都市のある方角であった。 世話しなく人々が出入りする賑やかなかの街に思いをはせて、長いため息をついた。 限界まで息を吐き続けたので、今度は大きく息を吸い込んだ。 山麓の澄んだ空気が肺に流れ込む。 それと同時に、あざがようやく消えた肩の傷が痛んだ。 「うぇーっほ!ゲッホ、ゲホッ!」 咳き込むと腕も鈍く痛んだ。投げ出していた左腕には包帯が丁寧に巻きつけられていた。 「マリスタ、まだ冷える季節なんだから早く家に入んなさい!」 「はーい、はい……」 家の中から母が呼ぶ声に、ぶっきらぼうに答えた。 包帯の上から腕をさすりながら、怪我を負った戦闘のことを思い出した。 相手の一隊は真昼間に真正面から馬鹿正直に姿を現した。 外套や布で顔を隠してはいたが、統制の取れた動きと無駄の無い型、 教科書のような魔法の活用からして、とても山賊とは思えなかった。 冷静に思い返せる今ならば、あれは位置から考えてもバルクウェイの正規兵の可能性が極めて高かった。 しかし、タルシュ海運の傭兵隊は敵方を上回っていた。 各々が型崩れに動き、陣形という型枠に囚われた敵をかく乱した。 相手の長であろう若い騎士には、短髪のニンジャが沈黙のまま戦闘不能を言い渡した。 個人個人の力は互角であっただろう。しかし、多くの賊を相手にしてきた経験値が違った。 タルシュ海運は何事も無かったかのように、水上都市までの旅路を再開した。 荷の後衛についていたマリスタは後ろを振り返った。 倒れている者の中に、微かに震えている者がいた。 マリスタはそっと回復魔法の掌印を結んだ。 優しい光が敵方の何人かを包んだ。 その時、マリスタの左腕に強烈な痛みが走った。 「ぐぁっ!」 「誰が敵に情けをかけることを許可した?!」 隣の年かさの破戒僧が棍で打ち付けてきたのだ。 マリスタは反抗的な目で相手を見た。相手は奈落の底から闇を見下ろす目つきを返した。 「我らの雇用条件に機密保持が含まれていることを忘れたのか?奴らは我らの情報を得ている。 生かしておいては契約に反する。小僧、お前が責任を持って奴らの息の根を止めろ!」 僧侶は棍で再びマリスタの肩を突いた。勢いでマリスタは数歩、後方へよろめいた。 肩を抑えながら振り返った。地に伏せたまま上目でこちらを伺っていた若い騎士の長と目が合った。 そばかすだらけのまだ子供のような顔立ちの騎士の目が大きく見開かれ、腰につけられていたポーチから 何かを取り出し、天に掲げた。 (……!七又の尻尾だ!!) 道具を視認した瞬間に、七色の光が視界を覆った。思わず瞼を閉じたが、手で顔を庇いながら 薄目を開けた。そこには敵の姿は全て無くなっていた。 「馬鹿目が!!」 僧侶が再びマリスタの左腕を打ちつけた。嫌な音がして、左手の指が引きつった。 それでも、今回はマリスタは声を上げなかった。 唇をかんで耐えた。鉄くさい味がしんなりと広がった。 僧侶は大またで荷馬車の後衛へと着いた。 マリスタは限界まで息を吸い込み、2秒ほど息を止めた後、盛大に吐いた。 それから走って荷馬車に追いつき、黙って僧侶の隣に並んだ。 傭兵にとって、契約は絶対であった。 北東を眺めていたマリスタは、再び長いため息をついた後、ずるずると尻から寝転び、 仰向けに南西の空を仰いだ。時計塔が聳える水上都市のある方角だ。 (……あの荷、なんだったんだ?……運んでよかったものなのだろうか……?) 人の背の高さ程度の丸い荷物であった。布で分厚く包まれ、厳重に魔封じの結界が 施されていた。触れることは許されなかったが、魔法力がそこそこあるマリスタは 感づいていた。 (あれは、生き物を運んでいたんだ……) -----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*----- 堅牢な石造りの部屋に、天窓から光が帯状に差し込んでいた。 光の行路が見えるのは、空気中に漂う埃が輝いているからだ。 埃くさい部屋の中に、黒い長い髪の女性が立っていた。 彼女の前のテーブルには、様々の大きさのガラス瓶の中に様々の色をした液体が入っていた。 その脇には薬草やら乾燥した花や茸、蝙蝠の糞、鹿の角の粉末など、 妙薬珍薬が所狭しと犇いていた。 女性は置き天秤で分量を量っては手早く調合していく。 部屋のドアがノックされた。分厚いドアなので、廊下側に取り付けられた鉄の輪を打ち付けて 音を出さなくては、中にいる彼女には聞こえない。 「入れ」 彼女は扉の外に伝書魔法で答えた。 重量に反して、音も無くドアは音も無く開いた。 半端な長さの髪をヘアピンで留め、額を全開にした少年が入ってきた。 「メルレーン先生、今日の報告書を提出してください」 「そこにある。勝手に持って行け」 黒髪の女性はぶっきらぼうに指で一枚の紙を指した。長い爪も全て黒く染められていた。 少年は紙を手に取り、じっと見つめた。 「見てどうする。読めないのだろう?」 メルレーンは少年を目の端に捉えながら言った。 「読みたいとも思いません」 少年も抑揚の無い声で答えた。 メルレーンは顔を傾け、彼を見た。 少年の視線には明らかに己に対する負の感情が込められていた。 「ギィ、私を蔑んでいるのか?ならばお門違いだ。お前が勝手に私の人格を捏造し、 勝手に尊敬していただけだ。私は最初から私だ。お前の目つきは不愉快だ」 「別に。最初から尊敬なんかしてませんよ。ただ、白銀の癒し手とまで呼ばれた先生が 作る薬は、人を助けるものだと思ってましたから……」 「薬と毒は紙一重、使用者がどう使うか次第さ。お前がカビを売ることと、私が薬を 売ることは同じじゃないか。自分はきれいないい子で、私は汚い大人だと言いたいのか?」 メルレーンは鼻で笑った。 少年は唇を歪ませて目を逸らした。歳相応の子供らしい仕草だ。 メルレーンは顔にかかった前髪を掻き上げた。一見すると漆黒だが、先端のほうは金色に透けていた。 「明日までに、反論できるようになっておけ。そいつは飾りじゃないだろう?」 そう言いながら自分の頭を指して見せた。少年はますます険しい目つきになった。 メルレーンは彼に見えないからこそ、口元をほころばせた。 「邪魔だ、行け。それから、その紙は読むなら逆さまだ」 少年が早口で失礼します、と言い残して、再び部屋の中は彼女だけになった。 机の上にあった緑がかった液体の入った瓶を掴み、光にかざして見た。 目を細めて見ると、小さな気泡がふわふわ漂い、それと共にで小さな何かが無数に蠢いていた。 瓶を握る指の爪の黒は、むらがあった。よくよく見ると、化粧で染めているのでは無かった。 (私は、最初から私だ) 彼女には近頃、奈落から提供される情報でひとつ、楽しみなものがあった。 ヴァレイより西に向かい、現在はゼレスに駐留している一騎士団の情報だった。 団員の一人が彼女と同期でクロニクル研究機関に所属した者がいるのだ。 固くて融通が利かなくて顔もまったくよくなかった男だが、頭の回転だけは 恐ろしく早く、理論展開が素晴らしい男だった。 (ワイズ、まさかお前のような優等生が輪の外へ堕ちようとはな) 彼に子供が生まれたときに、冷静な彼にしては珍しく浮かれながら子供を 職場に連れて来て見せて回ったことがあった。 その時、メルレーンもその小さな命を優しい気持ちで触れた。 (馬鹿な奴だ。子供に因果を背負わせるつもりなのか?馬鹿な奴だ) 瓶をテーブルに置き、黒い爪を持つ指で再び調合作業を始めた。 『白銀の癒し手』の異名を持つメルレーン・ウシュ博士はクロニクル研究機関員として長く機関に 貢献していた。しかし、ある時忽然と姿を消し、公的には死者となっていた。 この大陸の語られない先史を遺すクロニクルズには、何が世界を滅ぼそうとしているかが 記されている。読み解いた研究員たちはもちろん、滅びの正体を知っていた。 知った時。 彼らの反応は様々だった。 ワイズは無表情のままクロニクルを置き、机を拳で叩きつけた。 メルレーンはその場で頭を抱え込んだまま、二晩以上を過ごした。 それからは、世界の全てが色あせて見え始めた。 この世界が愛されるに足るように、 自分が世界に愛されるに足るように。 清く正しく生きていけば、世界は輝くのではないのかと、 あの小さな命に触れた時に抱いた、あのかすかな祈りのような気持ちが、 彼女を色彩のある世界に繋ぎ止めていた。 しかし、疑問を抱いた心の中を反映するかのように、美しかった金髪は徐々に黒くなり、 足の爪に、指の爪にと黒い色素が現れるようになった。 やがて黒色が体の他の部分に現れ始めたときに、彼女はようやく気づいたのだ。 もう、自分は手遅れなのだと。 そうして彼女は死者となり闇の中で生きることを選んだ。 前の話 次の話 |