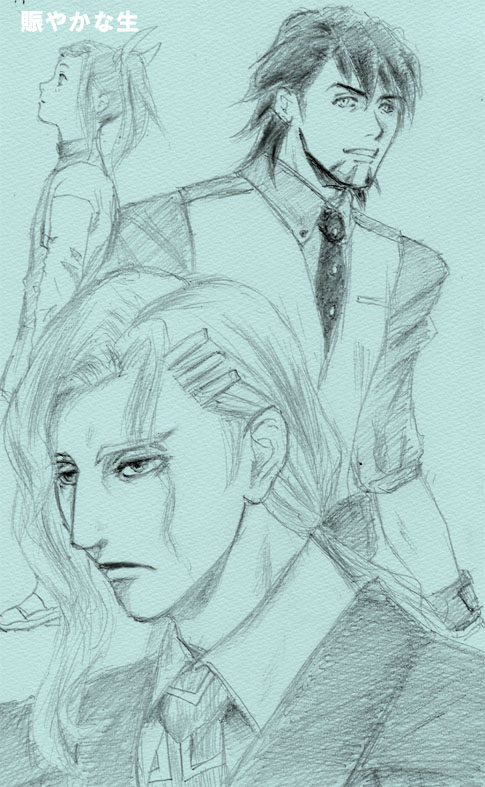
厳かな空気が、そこに存在する全ての者を畏怖させる場所。
司法権の象徴である司法局の法廷内、被告が座る場所に、いつもその男はけろりとした顔で足を組んでふんぞり返っていた。
トレードマークのように普段から被っているハンチング帽は流石に外して片手に握っているが、悪びれない表情は変わらない。
後方の傍聴席では大抵、彼とコンビを組んでいる青年が、どこか心配顔で彼の背中を見つめている。
「では、判決を」
裁判官ユーリ・ペトロフは、被告席に座る男、鏑木・T・虎徹に対して判決を下す。
罪を犯したNEXTと相対する存在……ヒーローは、実は居ながらにして法秩序を犯す存在でもある。
本来ならば、犯罪の取締りは司法警察権を行使する警察官しか出来ないことだ。
しかしNEXT出現後、その力をいわば利用する形で、司法局はNEXT能力者に「ヒーロー」という地位を与え、そして警察の秩序維持に協力をする権限を与えた。
だからこそ、ヒーローには、警察官ならば持っているはずの犯人の逮捕権は持たない。
持つのはただ、警察を補助する存在として、マスコミを使って「正義の使者」である事を宣伝し、その能力を使い人を助け、司法の許可が下りた時にのみ、犯人を確保する権限だ。
あるいはそれは、NEXT同士の秩序維持装置と言えるのかもしれない。
一方は「正義の力」としてその能力を使って一般市民から理解を得て喝采を浴び、一方は「人ではない存在」としてその力が社会から拒絶される差別的構造を孕んでいる。
ただその「正義の力」に対しての枷は、救助の際に器物を損壊した時、犯人に怪我を負わせた時に、厳しくヒーロー達を縛り付けるのだ。
事件発生後、即座に裁判が起こされ、その功と罪が秤にかけられた上で、彼らは「人智を超えた力を持つ能力者であるけれども、災害や犯罪者から一般市民を守るヒーローである」という理由で、犯罪者である事から免除される。
そして、一般警察官であれば免責されるであろう、多額の賠償金の支払い命令が下される。彼らとその雇い主は賠償責任から逃れることは出来ない。
能力を持たない一般の警察官が、ここまで厳密に業務遂行時の責任を取らされる事があるだろうか?
否。
例え犯人を射殺したところで、せいぜい降格人事や左遷で済む程度だ。
その太く頑健な不可視の枷は、ヒーロー達の手足に喰い込む様に嵌められて、彼らの自由な行動を縛り続けるのだ。
法廷の傍らでは、ジャスティスタワーの女神像を模した裁きの女神が、静かに佇んでいる。
それは公正な裁判の象徴。
女神よ。
あなたの前で決して公正とは言えない裁判が行われている事を、一体どう思われているのか。
判決を読み終えたユーリは、静かに女神を見やる。
勿論、ユーリの問いに、その女神は何一つ答えはしない。
「以上で終了します」
審判の終了を告げると、虎徹の溜息混じりの返事が、嫌に大きく法廷に響いた。
何度も何度も繰り返される、ユーリにとっては退屈な日常となっていた風景。
*
小春日和という言葉に相応しい穏やかな冬の日差しが、シュテルンビルト・ゴールドステージ、シュテルンメダイユ地区に柔らかく降り注いでいた。
12月を迎え、シュテルンビルトは煌びやかなクリスマスの飾りで溢れていた。街には定番のクリスマスソングと、年末を迎える人々の喧騒が満ちている。
ジェイク・マルチネスを巡る様々な事件の勃発。そしてジェイクの死による終結。
ユーリは市長を補佐するブレインの一人として行動し、ジェイクの事件にルナティックとして直接関与する事はなかった。そもそもショーアップされた茶番劇に付き合うつもりもなかったのだ。
しかし、ユーリにとっては喜劇でしかなかったその出来事も、ヒーロー達にとっては重い現実だ。
敗北により名声を失ったもの、そして英雄の称号を得たもの。
そして、怪我により暫くの間、メディアからのフレームアウトを余儀なくされたもの。
ジャスティスタワーを象徴する女神の足元にある小さな公園。
ユーリは一人で書類に目を通したい時に、そこを昼食を取る場所にしていた。
書類を一通り読んで顔を上げると、見慣れた人物が、小さな少女と共に公園に入ってくる所だった。
鏑木・T・虎徹。
ジェイクとの戦いで重傷を負い、暫くの間休養を強いられていた。
勿論HERO TVではその間、英雄バーナビーをサポートした理想の相棒として喧伝され、以前から言われていた「落ち目」という評判は賞賛の声に取って代わった。
アポロンメディアの株価は天井知らずの上昇を続けている。
その立役者の一人である虎徹が、今日は、いつもなら素顔を隠すためにつけているアイパッチもしていない。
素顔のまま、一人の小さな少女を宥めすかすようにして頭を下げていた。
「なぁ楓ぇ、いい加減、機嫌直してくれよぉ〜。パパが悪かったから!」
何度も何度も詫びる虎徹に対して、少女はふくれっ面でそっぽを向く。
「気持ち悪いからそのしゃべり方やめてって言ってるでしょ?! わたし、もう帰る!」
「ちょっと待ってって。せっかくクリスマス前なんだから、プレゼントも買ってやるし、な? それに、年末年始はちゃんと帰るし!」
「どーせまた『忙しくなったから帰れない』とか言い出すんでしょ! もう信じないもん、お父さんの言うことなんか!」
「楓ぇ……。とりあえず、落ち着いて話そう、な? どっかベンチにでも座って……あ」
キョロキョロと見回す虎徹と目が合った。丁度、ユーリが座っているベンチの隣が空いているのだ。
虎徹は気まずそうな顔をしつつも、少女の肩に手を置いて、ユーリの隣のベンチへと誘導する。
面差しが虎徹に似た少女が、怒りのせいか顔を紅潮させてそっぽを向いている。
不意に目があった。
鳶色の瞳が大きく見開かれて、自分の怒りの表情を見せまいとするように慌てて視線を逸らす。
「な、楓、せめて大会用の衣装、一緒に買いに行こう。ホントにゴメンな。20日は出張が入っちゃってるんだ……」
ベンチに座った少女の前に跪いて、虎徹が説得を始めた。
「なによ、次の大会は絶対見に来るとか言ってたのに。もういいかげんにして!」
少女はますますお冠だ。涙を浮かべながら虎徹を睨みつけている。
12月20日。確かヒーロー全員を集めた子供向けのチャリティーイベントを行うという報告書が上がってきていた事を思い出す。
ヒーローの行動を把握……そして監視しておくのも、管理官としてのユーリの仕事の一つだった。
どうやらそのイベントのせいで、おそらく娘らしきその少女が参加する大会を見に行けない事が原因なのだろう。
「ホントにホントにゴメン! パパが悪かったから! 行けない時はもっと早めに言うから……!」
「いっつもそれ。ごまかされないんだからね」
二人の会話は平行線を辿っている。
真昼とはいえシュテルンビルトの冬風はしんと冷たい。
ベンチに座る少女が身震いをするのがわかって、ユーリは何となく声をかけてみた。
何故そうしたのか、自分でもわからないまま。
「……鏑木さん、何か温かいものでも買ってきましょうか? 彼女は、寒いみたいですよ」
「え? ……あ、ペ、トロフ、さん? ……お気遣い、すみませんね」
虎徹は突然の申し出に戸惑っているようだった。視線が彷徨っている。
「あ、これは、俺の娘です。楓っていいます」
楓と呼ばれた少女は、再び鳶色の瞳をユーリに向けてきた。
澄んだ瞳が何かを見透かすように、ユーリを映している。
「楓、この方は、ペトロフさんといって、パパの仕事の『取引先』の人なんだよ」
楓は慌てて笑顔を浮かべ、ぺこりと頭を下げた。
「お父さんが、いつもお世話になってます!」
しっかりした口調はあまり父親には似ていないように思える。
「あ、じゃあ、パパちょっと暖かい飲み物買ってくるな。トイレにも行きたいし。楓、何が飲みたい?」
公園の隅にあるスタンドを指さしながら、虎徹が楓に問いかける。
「……ホットココア!」
ぶっきらぼうに楓は言って、虎徹から顔を逸らした。
「ペトロフさんは何がいいですか?」
不意の質問に、ユーリは思わず虎徹を見つめてしまった。
「私の事はお気になさらずとも」
笑顔で拒絶しようとするが、虎徹は大仰に頭を振る。
「あ、いやいや、楓の事を心配してくれたし、せめてこれくらい」
断った所で聞く感じではなさそうだ。
ユーリは苦笑して、虎徹の好意を受け入れる事にした。
「……ではお言葉に甘えて、ホットの紅茶を」
「紅茶! 俺、何となく、管理……じゃない、ペトロフさんはコーヒー派だと思ってましたよ。じゃ、楓、ちょっと待ってろな」
虎徹が離れると、楓は俯いて溜息をついた。
ぽつん、と沈黙が降りてくる。
正直なところ、ユーリには子供の扱い方がわからない。
物心ついた頃はまだ父親はまともだった。しかし、この少女位の年齢の時には、既に父親の能力減退とアルコール依存は始まりつつあった。
思春期にはもう、父親とは暴力と罵声を浴びせかける存在でしかなかった。
「ペトロフ、さん」
楓が、か細い声で名を呼んだ。
「……はい?」
「お父さん、そんなに忙しいんですか?」
ユーリをじっと見つめる目には何処か心細げな光が宿っている。
「フィギュアの大会、いっつも見に来てくれないし。せっかくシュテルンビルトまで来るのに」
ユーリは司法局で管理している虎徹のデータを思い出す。
妻とは死別。現在はオリエンタルタウンにいる母親に娘を預け、ブロンズステージのアパートで単身赴任中。
この様子では、虎徹はヒーローである事を娘には告げていないのだろう。
ユーリは楓に余計な情報を渡してしまわないように、必要最小限の事実だけ伝えた。
「私は君のお父さんと一緒に仕事をしている訳ではないから、詳しくはわからないけれど。
突然急ぎの仕事が入ったりして忙しいようだね」
司法局に見学に来た子供たちを相手にする時のような口調で。
ユーリは穏やかに楓に告げる。
「海外の会社と取引してるから、って、いっつも会えなくなって。この間なんて、長期出張だからなんて言って電話にも出ないし。お母さんは私が小さい時に死んでしまって、なのに、お父さんはいっつもこんな感じだし。……ペトロフさん。お父さん、ちゃんと、仕事してますか?」
ジェイクとの戦いの中で虎徹は重傷を負った。暫く入院していたから、おそらくその時は出張だと言って凌いだのだろう。
「私が知る限りでは、ちゃんと仕事をしていると思うよ」
あまり深く追求される前に躱そうとしたユーリの意図を悟ったのかどうか。楓はさらに言い募った。
「どんなふうにですか? ……お父さん、何度聞いても、最後はてきとうにごまかしちゃうんです。だから」
縋るような目で、楓がユーリを見ている。
酷く居心地が悪かった。
躊躇うことなく人を灼き尽くす炎を放てるはずの自分が。
どう誤魔化せばただの少女の、勇気を振り絞るようにして放たれた質問からどう逃れるか。
簡単な事の筈なのに、簡単な言葉すら返すことも出来ずに、ただ戸惑っている。
楓の言葉には、不信感と、その裏返しの、隠し切れない父親への愛情が存在していた。
ヒーローとその子供。
ユーリの脳裏に、遙か昔の、自分では忘れたと思い込んでいた筈の記憶が蘇る。
打擲(ちょうちゃく)の音。割れるガラス。絶え間ない悲鳴。
わるいひとはやっつけないといけないんだ。
みてみぬふりをしちゃだめなんだ。
おとうさん。
「ペトロフ、さん?」
恐る恐る問いかけてきた楓の声で、ユーリは我に返る。
「……ああ、すまないね、ぼんやりしてしまって。君のお父さんは、とても仕事に対して真面目なんだよ。だからずっと、一つの仕事を続けていられるんだと思うよ」
楓が、少しだけ安堵したような表情を見せる。その頬には、僅かに笑顔が浮かんだ。
「そう、なんですね。……ありがとうございます」
ユーリは気紛れに、楓に問うてみる。
「君は……お父さんが好きかい?」
楓は一気にふくれっ面になった。
「……大っきらい! うそつきだし、約束守らないし、いい加減だし!」
楓のあまりの勢いに苦笑してみせると、楓は僅かに顔を赤くして、小さい声で続けた。
「でも、……うちに帰ってくるときは、必ずおみやげを持って帰ってくれるし、いっつも色々プレゼントを送ってくれるから。多分、性格は悪くないと、思います。わたしが怒ると、ちゃんとあやまってくれるし」
「……そうか。その『大っきらい』は、好きの裏返しなのかな?」
からかうようにもう一度問うと、楓は唇を尖らせて、少しだけ頷いた。
「お父さんには、ナイショにしてて下さいね。多分、調子にのるから」
「君の言う通りにしよう」
ぺこりと頭を下げる楓の向こうに、虎徹の姿が見えた。
「……どうした楓?」
怪訝そうな顔で問いかけながら、虎徹は楓に、底を受け取りやすいようにカップの上部を持って差し出す。
ホットココアのカップを、楓はふくれっ面で、けれどもそっと掌に乗せた。
「お父さん、一応マジメに働いてるんだ」
「……なーんだよその言い方。ひでぇなあ。パパ、頑張ってんだぞ?」
虎徹がわざとらしく傷ついたような顔を見せると、楓は耐え切れなくなったのか吹き出してしまった。
「もういいよ。……クリスマスプレゼント、買ってくれるんでしょ」
「もちろん! 電車が出る前におっきなショッピングモールに行こうな。最近出来たんだ」
ほっとした表情の虎徹が、不意にユーリに視線を向けた。
「ありがとうございます、ペトロフさん。これ、熱いんで気をつけて下さいね。あと、ミルクとレモン、両方持ってきてるんで、好きな方を、どうぞ」
差し出されたカップには蓋がついていて、その上にレモンとミルク、シュガーがまとめて置いてあった。
「……ありがとうございます。では、遠慮なく」
「いやぁ、お気になさらず。うちの娘の相手をしてくれて、ありがとうございました」
ぺこりと頭を下げる仕草が、娘とそっくりだった。
顔を上げた虎徹が、じっとユーリの顔を見つめているような気がする。
「……どうかしましたか?」
「や、こんな事言うと失礼かもしれませんけど……ペトロフさんも、そんな風に笑ったりするんですねぇ」
「え?」
どこかからかうような風情で、虎徹がニヤリとした。
「子供の前だと、自然な笑顔って出るもんっすよね。いっつも生真面目な表情してるから、そんな穏やかな顔、初めて見ましたよ」
……穏やか?
ユーリは思わず虎徹をじっと見つめてしまった。
ただ、外向きの笑顔を作っていただけだ。何故穏やかなどと言われるのか、ユーリにはよくわからない。
「お父さん、お仕事の相手の人までからかうの、やめたら?」
楓がホットココアで両手を温めながら、父親をたしなめた。
「わかったわかった。……そういう時の言い方、ママに似てきたな、楓」
何処か寂しげな声音で虎徹はそう言い、自分用のカップに口をつけた。
「じゃあ、そろそろ行こう、楓。あんまり遅くなると、おばあちゃんが心配するからな」
「うん。……ペトロフさん、ありがとうございました」
楓は立ち上がると、ユーリに向かってもう一度頭を下げる。
「ありがとうございました。じゃあ」
人懐こい笑顔を浮かべて、虎徹は娘の肩に手を置いた。
「さ、行こうか楓」
「うん!」
賑やかに語らいながら、父子は公園を出ていった。
気がつくと、手元の紅茶はすっかり微温くなってしまっていて。
ユーリは一つ、深い溜息をついた。
*
なにかが、おいかけてくる。
ユーリの頭はようやく父親の膝を超える程度の高さで、まだ満足に、他人に意志を伝える事も出来ない。
こわい。
こわいよ。
訳もわからないまま恐怖が襲ってきて、ユーリはわんわん泣いた。
「どうしたの、ユーリ。怖い夢でも見たのかしら?」
母親に抱き上げられ、ユーリはその胸に縋り付いて泣き続けた。
母は背中をさすりながら、もう大丈夫よ、怖くないわよ、と耳元で囁く。
「どうしたんだ、オリガ?」
父親の声。母が「いきなり泣き出したの」と言うと、ユーリは父親に抱きかかえられた。
「どうした、ユーリ。お父さんがいるから、もう怖くないぞ」
ユーリの身体を支える大きな掌。母のものよりずっと高い体温が伝わって、ユーリは少しずつ落ち着いてくる。
「よーしよし。もう大丈夫だ。お父さんとお母さんがいるからな」
笑っている。やがて母も、安心したように微笑んだ。
「ユーリは、お父さんが大好きなのねぇ」
「そうだな、お前は私にそっくりだからな。……お前に能力が目覚めたら、私と同じように、ヒーローになるんだぞ」
母が苦笑する。
「あなた、誰もがNEXTになる訳ではないでしょう? 今はまだ小さいわ。もっと大きくなって、ユーリは自分で自分の道を決めるかもしれないですし、ね」
「そうだな。だが、ユーリ。強く育つんだぞ。お前は、このレジェンドの息子なのだから」
おとうさん。
ぼくはわるいことをしたやつを、やっつけるんだ。
おとうさんみたいに。
でんせつのヒーローになるんだよ。
やがて視界は、青と緑の斑になった炎で満たされた。
人の焼ける匂いが、これほど生臭く鼻につくものだなんて知らなかった。
自分の父親だった物体、その醜く弛(たる)んだ身体は少しずつ焦げ、人の形を喪ってゆく。
ユーリの顔に、もがき苦しむ掌の刻印を残して。
堕ちた英雄。
もう、悪人に対して、見て見ぬふりをしなくて済むんだ。
僕は。
この刻印と引換に、本当の正義を手に入れたんだ。
*
ユーリが息苦しさに飛び起きると、全身が冷汗で濡れていた。
父親を殺す夢は数えきれないくらい見ている。しかし、あんな小さな頃の思い出は、少なくともこれまで思い出すことはなかった。
幸せだったかもしれない日々との落差が、ユーリの心をさらに疲弊させる。
どうしてあのままでいられなかったんだ。
何故、能力減退の事実がわかった時に、さっさとヒーローを引退しなかったんだ。
恨めしさばかりがユーリの身を灼いた。
窓の外では下弦の月がか細い光を放っている。
そして廊下から、キイキイと車椅子の車輪が軋む音がする。
きっと母が目を覚まして、父の姿を探しているのだろう。
起きてガウンを羽織りながら、ユーリは昼間出会った鏑木父子の姿を思い出した。
虎徹は自分がヒーローである事を娘に告げていなかった。
ヒーローが家族を守るために、よくやる事ではある。
しかし、いずれ、少女が自分の父親がヒーローであるという事実を知る時が来るかもしれない。
眉間に皺を寄せ、ユーリは長い溜息をつく。
虎徹の愚直なまでに正義のヒーローであろうとする姿勢は、ジェイクとの戦いの時にも変わることがなかった。
結果として彼は大怪我を負い、暫く入院を余儀なくされたが。
だが、ユーリの中には、常にヒーローに対する不信感と嘲笑がある。
もしその力を喪っても、お前は変わらずにいられるのか、ワイルドタイガー?
「あなた、どこにいるの? 返事をしてちょうだい?」
夢の世界を漂う母を落ち着かせるために、ユーリは自分の部屋を出た。
*
「あ、ペトロフ……管理官」
司法局内の執務室で、書類仕事をしていると、不意にドアが開いた。顔を出したのは鏑木虎徹だった。
鏑木父子との偶然の遭遇から1週間程経過していた。
「どうしました?」
この部屋に呼び出しではなく、自分からヒーローがやってくる事は滅多にない。
「いやぁ、ちょっと、こないだの礼を、と思って。うちの娘がお世話になりました。なんでも俺の仕事の事を聞いてたとかで」
虎徹は人懐こい表情でユーリを見ている。普段、法廷で見せる顔とは違っていた。当然だろう。法廷には良い感情は一つもないだろうから。
ユーリは外向きの、人当たりの良さ気な笑顔を形作って、虎徹に返す。
「……娘さんにはヒーローの仕事の事は明かしていないんですね。差し出がましいようですが、その辺りはぼかしておきましたから。それに、紅茶をご馳走になったのは私の方ですよ? お気になさらず」
慇懃を装って暗に退室してくれと匂わせたのだが、虎徹はそれをわかっているのかいないのか、ツカツカと入り込んできて、机の前に立った。
「……っと、流石にここで帽子はちょっと、だな」
虎徹は被っていた帽子を片手に持って、ひどく曖昧な表情を見せる。
「先日、うちの娘がね、帰り際に言ってたんですけど」
「はい?」
「『ペトロフさん、お父さんの仕事のことを聞いたとき、一瞬だけ、すごく苦しそうな顔をしたの。何か悪いことを言ってしまったのだったら、ごめんなさい』って伝えてね、って」
息が詰まる。
脳裏に浮かんだ父親の記憶で一瞬思考が停止した時に、思わず顔に出してしまったらしい。
ユーリは自分の迂闊さに目眩がした。
弱みを悟られてしまうと、いずれ自分を追い詰める事になるかもしれない。
「ワイルドタイガー」が「ルナティック」とは全く反対の哲学を持っているのならばなおさら。
「楓が何か失礼な事を言いませんでしたか? だったら、本当に申し訳ない。親として、謝罪します」
虎徹は普段はまず見せないような深刻な表情で頭を下げた。
……虎徹が娘の事をどう思っているか、その謝罪は如実に伝えていた。
内心の焦りを笑顔で覆い隠して、ユーリは返す。
「彼女はただ、父親が何をしているかがよくわからなくて、不安だったようですよ。ただ、私が何処まで伝えて良いものか、判断に迷ってしまって。それで彼女が心配したのかもしれませんね。こちらこそ済みません。あなたが、彼女に何処までヒーローの事を教えているかわからなかったのもあって」
虎徹は表情を崩さないまま、ユーリに語りかけてきた。
「妻が……楓の母が5年前に亡くなって、俺はあいつをずっと俺の母親の所に預けてます。って、管理官は知っているかもしれませんけど。シュテルンビルトにいると、楓が事件に巻き込まれるかもしれないし、時間も不規則だからずっと面倒見てやる事も出来無いし。ヒーローの事について、今は全く話してません。でも、……あいつも成長してるんだなぁ」
ふと、虎徹の表情が和らぐ。その場にいない娘の面影を追うように、目が細められた。
それは父親としての、確かな愛情の証。
「……俺は妻と約束をしました。だから、出来れば長く、ヒーローを続けたい、と思ってます。いつか、楓がそれを知る時に、嫌がられるよりは喜んでもらいたいし。それに」
噛み締めるように、虎徹は一言一言を紡ぎ出す。
「俺は小さい頃、能力が暴走した所をレジェンドに助けられて、それがヒーローを目指すきっかけでした。……流石にレジェンドみたいな、とはいかないかもしれないですけど、娘が自慢出来るようなヒーローでありたいっすね」
「……レジェンド」
目眩がする。
贅肉を身に纏った悪と虚飾の象徴が、ワイルドタイガーをヒーローたらしめている。
「君のおかげで助かった、これで君もヒーローだって、言ってくれたんスよ。……あ、あれ、管理官、顔色が良くないですよ?」
椅子に座っていなければしゃがみ込んでいたかもしれない。ユーリからは血の気が引いていた。
そして今、ユーリは初めて自覚する。
虎徹もまた、「レジェンドの子供」なのだ。
英雄の虚像が虎徹を……ワイルドタイガーを生み出し、真実の姿がユーリを、そしてルナティックを生み出した。
「管理官?」
虎徹の声に、ユーリは辛うじて笑顔を作る。
「大丈夫です。お気になさらず」
まるで太陽と月だ。
賑やかな声に満たされ、眩しい生を送る者と、司法の力では裁く事の出来無い悪を、タナトスの名の下に静かな死の世界に追いやる者。
では、相反する子供達が持つ正義の形は、やはり相容れないものなのだろうか。
虎徹が不意に、俯くユーリの顔を覗き込んできた。
琥珀色の瞳が間近にある。
驚いて身を引こうとすると、虎徹は子供にするように、ユーリの額に手を当てた。
「……熱はないみたいっすね。管理官、もしかして低血糖だったりしますか? いや、妻がそうだったから」
虎徹の突然の行動にユーリが呆然としているうちに、虎徹は執務室の外に駆け出していった。
……何だ今のは。
状況を理解出来無いでいると、再び虎徹が駆け込んでくる。左手に紙のカップを持っていた。
チョコレートの甘い匂いが執務室に充満する。
「あ、ホットココアだと、すぐに血糖値上がるから、多分楽になると思いますよ。固形のチョコより手っ取り早いし」
「……」
何を言えば良いのかわからずユーリが黙り込んでいると、虎徹は人の良さそうな笑顔を見せた。
「しんどい時には、甘いものを取ると安心するって言うじゃないっスか。あ、これ、結構熱いから気をつけて下さいね」
ユーリの内心の動揺を知ってか知らずか、虎徹はデスクにココアのカップを置くと、再び帽子を被った。
「ありがとうございました、管理官。お大事に!」
背を向けて出て行こうとする虎徹を、ユーリは今出せる精一杯の声で呼び止める。
「鏑木さん」
「はい?」
虎徹は立ち止まって、ユーリの方へ向き直った。
「もし……あなたや、あなたの娘さんの身に何かがあったりしたら。あなたはヒーローを引退しますか?」
それはとても残酷な問い。
ユーリの心の片隅に浮かぶサディスティックな感情が、抑えきれずに吐き出された言葉にこもる。
虎徹にとっては予想外の問いだったのだろう。何処か苦しそうに、顔を歪めた。
「勿論です。……俺は、妻の死を看取れなかったから」
ユーリは無言で虎徹を見つめた。
虎徹の瞳に悲哀の色が浮かぶ。しかし投げかけられた言葉は迷いなく、力強かった。
「必ず、傍にいてやります。楓の父親は、他の誰でもない。俺だけだから。……では、失礼しました」
バタン、と荒々しくドアが閉められ、虎徹の足音が遠ざかっていく。
書類と公判資料だらけの執務室に、甘ったるいチョコレートの香りが広がってゆく。
「……私も子供扱いなのか」
知らず、ユーリの頬には苦笑が浮かぶ。
そして溜息をついて、ユーリは熱めのココアを一口啜った。
「甘いチョコレートは好きではないのだが……」
出来ればハチミツ入りの紅茶が欲しかったが、好意は有難く受け取る事にする。
ほろ苦さと、とろりとした甘さが舌に残る。まるで今のユーリの心情のようだ。
少しずつココアを口にするうちに、目眩は治まってきた。虎徹の言うように只の低血糖だったらしい。
「ヒーロー、か」
基本的にヒーローになるNEXT達は何処か一般の人間と違っている事が多い。
その中でも、虎徹は特別浮いているような気がしていたのだが、どうやらその感覚は間違ってはいなかったようだ。
「鏑木、虎徹」
父親が酒に溺れなければ。自分はもしかしたら、今の自分のような生き方を選ばなかったのだろうか。
悪を裁く事に躊躇はない。
死の神タナトスの如く振る舞う事に迷いはないが。
もう一人のレジェンドの息子は太陽の光で、ユーリの身を灼いた。
ユーリは静かに目を閉じる。全ての光を遮るように。
……全ての現実から視界を塞ぐように。
今は思考を遮断してしまいたかった。
心のうちから溢れ出す、憎しみに似た感情。その笑顔を引き裂きたいという衝動。
そして、その奥に小さく生まれた、怒りでも憎しみでもない光のような何かから、ユーリは必死で目を逸らすのだった。
2011.9.7アップ。静かな死と対になっています。
なぜか物凄く難産で、予定より1週間程仕上がりが遅くなりました。
前半中二病全開な文章になっていますので、めんどくさいと思われた方はすっ飛ばして下さい。
そして最初は簡単に、ユーリがデレるまでを書くつもりだったのですが、なんでこんな面倒な展開に!
…ということで、この続編もおそらく書きます。ええと、がっつり月虎になるかもしれませんので、掲載する時はコーナーを分けるかもしれません。
ただでさえカオスなサイトが更にカオスに(-_-;)